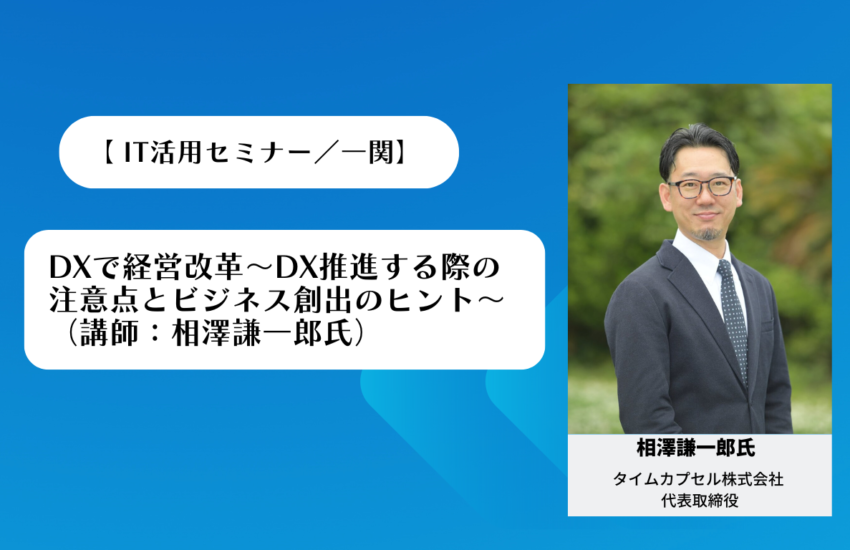人口減少や人材不足、原材料費・エネルギー費の高騰など、地域企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、「DXをどう経営改革や新たな価値創出につなげるか」は、多くの経営者や現場担当者にとって切実なテーマとなっています。
2025年12月17日、岩手県一関市で開催されたIT活用セミナー「DXで企業の未来を拓く」では、全国でDX推進を牽引する専門家3名が登壇し、地域に根ざした実践事例とともに、DXの本質について語られました。
本記事ではその中から、タイムカプセル株式会社代表取締役・相澤謙一郎氏による講演「DXで経営改革~DX推進する際の注意点とビジネス創出のヒント~」の模様を紹介します。人口1万人規模の町から始まったDXの挑戦や、金融・製造業・公共分野に広がる具体的な支援事例を通じて、相澤氏が一貫して伝えたのは、「DXはツールではなく、経営そのものを変える行為である」という明確なメッセージでした。
【講師プロフィール】
〇相澤謙一郎氏
タイムカプセル株式会社代表取締役/ヨコスカバレーボードメンバー横須賀生まれ、横須賀育ち。明治学院大学法学部卒業。19才で起業し、どぶ板通りでBARを開業。その後、株式会社ぱど、株式会社ユニメディアを経て、2010年Eagleを創業。2013年、岐阜県大垣市にてタイムカプセルを創業。
300本以上のスマホアプリの開発にたずさわり、累計のアプリダウンロード数は1,000万を超える。初期のヒット作『ちゃぶ台返し』のほか、『あべぴょん』、『横浜F・マリノスコレクションカード』などが好評を博す。県立岐阜商業高等学校、県立東濃実業高等学校にてアプリ開発の講師を担当。経営理念「熱意ある人が いつでもどこでも 挑戦できる社会を作る」ことを実現するため全国を駆け巡る。
共著「これからの自治体産業政策-都市が育む人材と仕事-」
- 人口1万人の町・高千穂町から始まったDXの挑戦
- 廃校をIT拠点に変える|気仙沼「ITベース こはらぎ荘」の取り組み
- スポーツ×デジタルによる地域連携の実践
- DX支援事例① 地銀DXの転換点──大垣共立銀行の挑戦
- DX支援事例② 100年企業・刃物メーカーの経営転換
- DX支援事例③ 地域交通×地域通貨を支えるDX──伊予鉄グループの挑戦
- DX支援事例④ 製造業の強みを新市場へ──ニフコのヘルスケアDX
- DX支援事例⑤ 公共施設DXが地域を変える──気仙沼市役所との挑戦
- DXを進める前に立ち止まって考えるべきこと
- DXを成功に導く「3C」の視点
- DXに不可欠な費用対効果(ROI)の考え方
- DXの成否を分けるパートナー選び
- DXのチャンスは、すでに地域に眠っている
- 情熱×DXで、地域の未来を切り拓く
人口1万人の町・高千穂町から始まったDXの挑戦

宮崎県の高千穂町は、人口1万人台の小さな町です。阿蘇山の南側、九州のほぼ中央に位置する山間部にあり、「日本の地方」を象徴するような地域だと言えるでしょう。
現在、この高千穂町では10人のスタッフが働いています。こうした取り組みを続ける中で、地元の高千穂高校を卒業した若者が新入社員として加わったり、かつて町を離れて別の地域で働いていた人が、再び故郷に戻ってくるといった動きが生まれてきました。高千穂では、確実に人の循環が起き始めています。
「タイムカプセルがなかった時代よりも、今この町にタイムカプセルがあってよかった」そう地域の方々に感じてもらえる存在でありたい――その思いを、私たちは強く持っています。
地域に愛され、地域から必要とされる。そんなソフトウェア開発会社であり続けることが、私たちの目標です。ただし、地域を元気にするために、一社だけでできることには限界があります。
だからこそ、地域で活動する企業や自治体、学校関係者の皆さまと連携し、それぞれの事業や取り組みをDXで支えていく。その積み重ねこそが、地域全体の活性化につながると考えています。
本日は、その中からいくつかの具体的な事例をご紹介します。
廃校をIT拠点に変える|気仙沼「ITベース こはらぎ荘」の取り組み
まずは、お隣の宮城県・気仙沼市での取り組みです。今日は気仙沼から車で移動してきましたが、所要時間はおよそ1時間ほどでした。
こちらが、私たちの気仙沼のオフィスです。一見すると、IT企業のオフィスには見えないかもしれません。この場所は、唐桑半島にある旧小原木中学校の校舎です。
気仙沼市では、小学校・中学校・高校の統廃合が進み、廃校となる学校が年々増えています。高校も数年前に気仙沼西高と気仙沼高校が統合されましたが、この小原木中学校も、十数年前に廃校となりました。
私たちは、この校舎の2階部分を活用し、IT企業が集まる拠点として「ITベース こはらぎ荘」を立ち上げました。廃校であっても、IT企業の集積地になれる――そのモデルづくりに挑戦しています。
もともと教室だった空間をリノベーションし、現在は地元スタッフが快適な環境で働いています。また、こはらぎ荘では、子ども向けのプログラミング教室や、シニア世代向けのスマートフォン講座なども定期的に開催しています。こうした取り組みを通じて、気仙沼市全体のITリテラシー向上にも貢献しています。
さらに、市民の皆さんと直接触れ合うことで、「気仙沼にアプリ開発会社がある」「ゲームを開発できる会社がある」という事実を知ってもらうきっかけにもなっています。地域の中にIT企業が存在し、身近に感じてもらうことも、私たちが大切にしている活動の一つです。
やはり、「知っているか、知らないか」で、その後の行動は大きく変わります。知っていれば、そこからアイデアが生まれ、「何かやってみよう」というモチベーションにつながる。一方で、まったく知らなければ、発想そのものが生まれにくい。だからこそ、私たちはこうした啓蒙的な取り組みを大切にしています。
スポーツ×デジタルによる地域連携の実践
宮城県・仙台市では、東北楽天ゴールデンイーグルスの公式スマートフォンアプリの開発・運営を、約3年間にわたって担当してきました。現在は別の体制で運営されていますが、アプリの新規機能の開発から運用フェーズまで一貫して関わった実績があります。
また、ベガルタ仙台とも連携し、スタジアム周辺に設置されたオリジナルデザインのマンホールをスマートフォンで撮影して楽しむ、参加型イベントを企画・実施しました。7年ほど前の取り組みではありますが、リアルな街の仕掛けとデジタルを組み合わせた先進的な事例です。
このように、私たちは気仙沼に限らず、東北各地でデジタルを活用した地域連携の取り組みを進めてきました。ITやDXは決して特別なものではなく、地域の文化やスポーツ、日常と結びつくことでこそ、多くの人に自然に届くものだと考えています。
DX支援事例① 地銀DXの転換点──大垣共立銀行の挑戦

ここからは、具体的なDX支援事例をご紹介します。
まず一つ目は、弊社のクライアントである岐阜県の地方銀行、大垣共立銀行様の取り組みです。
私たちは現在、大垣共立銀行様の公式スマートフォンアプリ「OKBアプリ」の開発支援を行っています。銀行のアプリ開発というと、「開発難易度が高く、中小企業には難しいのではないか」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。私たちは10年以上前から大手ネット銀行のアプリ開発に携わってきました。数百万人規模のユーザーを抱えるアプリの開発・運用実績もあり、技術的には中小企業でも十分に対応可能であることを実証してきました。
従来、銀行のアプリや基幹システムの開発は、大手ベンダーに委託するのが一般的でした。大垣共立銀行様も同様の体制を取っていましたが、その結果、コミュニケーションコストが高く、アプリの開発スピードが上がらないという課題を抱えていました。細かなUIの調整や使い勝手の改善をリモートで伝えることは難しく、アプリのアップデートは年に数回程度にとどまっていたといいます。
しかし現在、銀行にとってアプリは「もう一つの店舗」、あるいは「店舗そのもの」と言える存在です。実際、来店客数は最盛期と比べて大きく減少し、半減している店舗も少なくありません。その一方で、お客様との主な接点はスマートフォンアプリへと移行しています。
店舗であれば、売り場の配置を変えたり、チラシの置き方を工夫したり、季節ごとに装飾を変えたりと、日常的に改善を重ねていきます。それが当たり前の店舗運営です。にもかかわらず、「デジタル店舗」であるアプリの改善が年に数回しかできない状況では、ユーザーの不満が蓄積してしまいます。実際、その兆候はアプリストアのレビューにも表れていました。
そこで私たちは、地元で、対面で、当事者意識を持って開発する体制を提案しました。本店営業部に半常駐し、フェーストゥフェースで打ち合わせを行いながら、日常的にOKBのサービスを利用している地元エンジニアが開発を担う。この体制は、従来の外注型開発とはまったく次元の異なるものです。
その結果、現在では毎月のようにアプリのバージョンアップが行える体制が整いました。改善のスピードと精度は大きく向上しています。
さらに私たちが提案したのが、「内製化」という視点です。今後、銀行ビジネスの中心は、アプリをはじめとするITサービスへとますます移行していきます。店舗数を2倍、3倍に増やすことは現実的ではありませんが、ITサービスの品質を高めることで、顧客満足度を向上させることは可能です。
そのためには、すべてを外部に委託するのではなく、自らコントロールできる開発体制を持つことが重要になります。この考え方に大垣共立銀行様の経営陣も理解を示し、現在では銀行本体でのエンジニア採用・育成が本格的に進められています。弊社は、その採用支援や教育支援を担っています。
DXは単なるツール導入ではなく、経営改革そのものです。
大垣共立銀行様では、まさにその変化が「構想」ではなく「実行」の段階に入っています。
そして、この取り組みは銀行内部にとどまりません。大垣共立銀行様はDXの重要性を取引先企業や地域全体にも広げていくため、「デジタル統括部」を立ち上げました。現在、弊社はパートナーとして、銀行の顧客企業向けDX支援にも取り組んでいます。
具体的には、
- 学習塾の夏期・冬期講習などの申込フォームの開発
- 企業のコーポレートサイトリニューアル
- 自治体ホームページの改修
- 地域大学と連携した認知症予防アプリの開発
など、地域全体のDXを支える取り組みを共同で進めています。
DX支援事例② 100年企業・刃物メーカーの経営転換
二つ目の事例は、岐阜県に拠点を置く、創業100年を超える伝統的な刃物メーカー様です。包丁やカミソリを製造しており、私たちが日常的に使用している男性用・女性用カミソリの多くが、実はこのメーカーの製品です。
売上規模は数百億円にのぼり、国内と海外の売上比率はほぼ50%ずつ。しかし、国内市場において売上をさらに10%、20%と伸ばしていくのは容易ではありません。包丁もカミソリもすでに高い評価を得ておりますが、人口減少が進む中で「急激に売上が伸びる」ような市場ではないためです。
一方で、グローバル市場には大きな可能性があります。実際、同社の包丁は切れ味がまったく違います。私自身も釣りをしますが、この包丁を使うと、魚のさばき方そのものが変わるほど、体験価値に明確な違いがあります。こうした「日本の刃物が持つ世界観」を海外に伝えていくためには、ITの強化が不可欠だと提案しました。
こちらのメーカー様は100年以上の歴史の中で、一度もエンジニアを新卒採用したことがありませんでした。それでも取締役の方が決断し、「これからはエンジニアを自社で採用する」という方針へと大きく舵を切りました。弊社がエンジニアの採用支援と新人研修を担当させていただきました。
国内市場での大幅な成長が難しい状況であっても、グローバル市場に向けて日本のものづくりの価値を発信し、高付加価値の商品を届けていくことは可能です。そのための基盤となるのが、ITとDXです。
この事例が示しているのは、DXが単なる業務効率化の手段ではなく、新たな成長戦略を描くための経営判断そのものであるという点です。DXは、伝統ある企業においても、確実に大きな変化を生み始めています。
DX支援事例③ 地域交通×地域通貨を支えるDX──伊予鉄グループの挑戦
三つ目の事例は、愛媛県の公共交通事業者である伊予鉄グループの取り組みです。
愛媛県では現在、「みきゃんマネー」という地域通貨の運営が進められています。地域通貨を実際に使ってもらうためには、PayPayやSuicaのように、日常的に利用できる決済機能を備えたスマートフォンアプリの存在が不可欠です。
そこで愛媛県に足を運び、松山市内に開発拠点を設置しました。現地で印象的だったのは、「愛媛県内には本格的なアプリ開発会社がほとんど存在しない」という声です。ホームページ制作を行う企業はあっても、決済機能を含む高度なスマートフォンアプリを開発できる企業は地域に少なく、その結果、地元での開発体制が成立していませんでした。
伊予鉄グループ様は、鉄道やバスに加え、非常に特徴的な路面電車網を運営しています。観光用にたまに走る路線ではなく、山手線のように高頻度で街中を循環する、生活インフラとしての路面電車です。
こうした交通インフラ向けのアプリは、実際に電車に乗り、何度もテストを重ねなければ完成しません。数十回と乗車し、現場で使いながら改善を重ねていく必要があります。伊予鉄様の路面電車に一度も乗ったことがない開発者が、遠隔地から良いアプリを作るのは、現実的とは言えないでしょう。
そこで私たちは、松山に開発拠点を構え、伊予鉄グループ様と同じビル、同じフロアに入居しました。毎日フェーストゥフェースで議論を重ね、実際に路面電車に乗りながら、アプリを作り直しました。
その結果、ユーザーインターフェース(UI)やユーザー体験(UX)は大きく改善され、地域交通と地域通貨を実用的に支えるアプリへと生まれ変わりました。
この事例が示しているのは、DXは単なる外注ではなく、「現場に根ざした開発体制」そのものが価値になるということです。地域インフラを支えるDXだからこそ、地域に拠点を置き、地域の日常を深く理解した上で開発することが不可欠なのです。
DX支援事例④ 製造業の強みを新市場へ──ニフコのヘルスケアDX

次の事例も、製造業の企業です。
自動車部品メーカーのニフコ様は、プラスチック部品分野で世界トップクラスのシェアを誇るグローバル企業で、本社は神奈川県横須賀市にあります。東北にも工場を構え、業績は非常に好調です。
かつて自動車はボルトやナットで組み立てられていましたが、現在では「パチン」と留めるプラスチックファスナーが主流になっています。そのファスナーを製造しているのが、ニフコ様です。また、リュックサックのバックルをはじめとするスポーツ用品向けのプラスチック部品も、多くのメーカーに提供しています。
そんなニフコ様から、「新しい製品・新しい事業を立ち上げる」という相談を受けました。同社のライフソリューション事業部では、次の成長領域としてヘルスケア分野に挑戦したいという構想を描いていました。
そこで開発されたのが、足の指の握力(把持力)を計測する機器です。足の把持力は加齢とともに低下すると言われており、衰えることで転倒リスクが高まります。高齢者の転倒は、骨折や寝たきりにつながるケースも多く、国内でも社会課題となっています。
この把持力を「見える化」し、継続的にトレーニングすることで体幹を強化し、転びにくい身体をつくる。それを実現したいというのが、ニフコ様の狙いでした。
しかし、単に測定器を使って毎日足の指を鍛えるだけでは、なかなか続きません。そこで私たちは、「楽しく、自然に習慣化できる仕組みをつくろう」と提案しました。
そこで把持力測定器と連動するゲームアプリを開発しました。いわばリズムゲームですが、操作は足の指。タイミングよくコントローラーを足の指で握って操作する形式ですが、足の指で操作するゲームは、世界的にも非常に珍しい試みだと言えます。
これが、想像以上に面白い。
ゲーム性を持たせることで、「トレーニング」ではなく「遊び」として足の把持力を鍛える、新しい生活習慣を提案しています。
現在、年度内に3本のゲームを展開する予定で、すでにさまざまな企業に向けた提案も進んでいます。反響は大きく、新たなヘルスケア市場の可能性が見え始めています。
これまで、「自分の足の把持力が何キロか」を把握している人は、ほとんどいなかったのではないでしょうか。私自身も、この機器に出会うまで知りませんでした。しかし、把持力は体重と同じくらい、日常生活の質に深く関わる重要な指標です。
将来的には、体重計に乗るように、足の把持力を測ることが当たり前になる時代が来るかもしれません。私たちは、こうした新製品・新市場の創出を支えるソフトウェア開発やDX支援にも取り組んでいます。
DX支援事例⑤ 公共施設DXが地域を変える──気仙沼市役所との挑戦
五つ目の事例は、宮城県・気仙沼市役所様との取り組みです。コロナ禍をきっかけに、気仙沼市から「公共施設のキャッシュレス化を進めたい」という相談を受けました。
対象となったのは、市営テニスコートや運動場など、いわゆる公共施設の予約と支払いです。これらの施設は、1時間数百円と、非常に安価で利用でき、市民生活を支える重要なインフラです。
一方で、全国約1,700の自治体に共通する課題があります。それは、予約が基本的に「電話や受付窓口など有人対応」のままであることです。これは地方に限った話ではありません。私自身、東京都荒川区や神奈川県横須賀市でも同様の体験をしてきました。スポーツセンターでは、いまだに券売機でチケットを購入し、受付に渡す。こういったアナログな状態が全国的に続いています。
この課題に対し、気仙沼市様とともに実装したのが、「気仙沼市スポーツ施設予約システム」です。PCやスマートフォンから、空き状況の確認、予約、キャッシュレス決済までを、いつでもどこでも完結できる仕組みを整えました。
導入から3年目を迎えた現在、その成果は明確に表れています。市営テニスコートの予約件数は2倍以上に増加。電話や窓口対応が中心だった時代と比べ、施設の稼働率が向上し、結果として収益も増えました。
つまり、「予約と支払いをスマホでできるようにするだけで、公共施設は“稼げる”ようになる」ということです。これは、公共施設運営における大きな盲点でした。施設そのものは優れていても、「予約しやすくする」「支払いを簡単にする」「スマホで使いやすくする」といった視点は、これまでほとんど重視されてこなかったのです。SEOやUI/UXといった発想も、公共分野では十分に取り入れられてきませんでした。
しかし、「今、空いているかがすぐ分かる」「その場で予約し、支払いまで完了できる」という体験が提供されることで、利用は着実に増えます。実際、気仙沼市では市民の皆さんがテニスや運動施設の利用を習慣的に始めています。
テニスは一人ではできません。二人、三人、四人と人が集まり、定期的に体を動かすことで健康になり、自然とコミュニティも生まれます。この仕組みを導入した結果、
- 市民が運動を始める
- 健康になる
- 日常が少し楽しくなる
というポジティブな循環が生まれています。
首都圏でも多くの自治体では、予約はできても決済は不可、利用時間に制限がある、夜間は使えない、初回は必ず現地で会員登録が必要、といった不便な仕組みが、今も当たり前のように残っています。
私自身、最近利用した東京都内の公共施設でも、オンライン予約すらできず、現地で会員証を作りましたが、「予約時は次回もまた来てください」と案内されました。これは日本全国で、今も日常的に起きている現実です。
私は、この状況を「普通」だとは思っていません。むしろ、長年にわたって異常な状態が放置されてきたと感じています。この公共施設DXを日本全国に広げていくこと――それが、今の私自身のミッションです。
DXを進める前に立ち止まって考えるべきこと

ここまで、さまざまなDX支援事例をご紹介してきました。ただ、「では、みんなで一緒にDXを進めていきましょう」という話になるときには、いくつか注意すべき点があります。
その一つが、DXすること自体が目的化してしまうことです。
実際にあった事例として、ある自治体でLINE導入の支援を行ったことがあります。LINEを活用し、公共料金の一部を支払える仕組みまで、技術的にはきちんと整備しました。
ところが、蓋を開けてみると、どの部署も導入していませんでした。
システム自体は導入され、予算も確かに使われています。しかし、実際には活用されておらず、結果として利用実績はゼロです。これは、「ツールを導入すること」そのものが目的化してしまった典型的な失敗例といえるでしょう。
DXは本来、
- 行動が変わること
- 実際に利用されること
- そして、成果につながること
を目的とするはずです。
にもかかわらず、「予算化されたから導入する」「国の方針だからとりあえず入れる」といった理由で進めてしまうと、誰にも使われないDXが生まれてしまいます。それは、いわばゴールのないマラソン大会のようなものです。走ること自体が目的になり、どこに向かっているのか分からない状態です。
こうした「DXのためのDX」に陥らないためには、本当に誰の、何の課題を解決するのかを、プロジェクトの最初から最後まで問い続けることが何より重要だと感じています。
DXを成功に導く「3C」の視点
もう一つ、DXを進めるうえで大切だと感じているのが、マーケティングの「3C」の視点です。つまり、市場(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)という3つの観点から、DXを捉えることです。
DXそのものは、とても意義のある取り組みです。しかし、「流行っているから導入する」といった発想だけでは、成果にはつながりません。まず立ち返るべきなのは、「それは本当に必要なのか」という問いです。
仮にツールを導入できたとしても、
- その後の運用は本当に回るのか
- 現場で使いこなせるのか
- 継続的に有効活用できる体制があるのか
といった点を、冷静に見極める必要があります。
さらに重要なのが、「そのDXは、自社の強みを生かしているのか」という視点です。導入によって、どのような新しい提供価値や付加価値が生まれるのか。そして、その価値を本当にお客様が求めているのかを考えなければなりません。
同時に、競合の存在も忘れてはいけません。
- 同じ取り組みを、すでに他社が行っていないか
- 競合の方が、より優れた体験を提供していないか
- そのDXによって、本当に競争優位を築けるのか
もし競合が、さらに洗練されたサービスを提供してきた場合、そのDXは簡単に価値を失ってしまう可能性もあります。
だからこそ、DXは市場・競合・自社という3つの視点で、常に問い直されるべき戦略的な取り組みなのです。DXは目的ではありません。あくまで、価値を生み出し、選ばれ続けるための手段に過ぎないのです。
DXに不可欠な費用対効果(ROI)の考え方
もう一つ、どうしてもお伝えしておきたいのが、費用対効果(ROI)の視点です。
たとえば、先ほどご紹介した公共施設の予約・決済システム。これは日本全国で、毎年のようにプロポーザルが実施されており、年間では100件、200件規模にのぼると考えられます。
ところが、その予算額は自治体ごとに驚くほど大きく異なります。5,000万円以上という高額なケースがある一方で、400万円程度で実装されている例もあり、同じ「公共施設予約・決済システム」でありながら、価格差は極端です。ここに、IT業界の怖さがあります。
飲食店であれば、ある程度の相場感があります。1,000円で食べられる寿司屋もあれば、3万円の高級店もある。しかし、300万円の寿司は存在しません。ところがITの世界では、こうした感覚が簡単に崩れてしまいます。
記憶に新しい例としては、東京オリンピック関連のIT事業や、コロナ対策アプリなどがあります。正直に言えば、アプリ開発に73億円をかけるというのは、現実的な話ではありません。人間の手による開発はおろか、「神ですら難しい」レベルの金額です。それでも、こうした事業が平然と成立してしまう――そんな世界が、今のIT業界にはまだ残っています。
だからこそ、DXを進める際には、
- 何に、いくらかかるのか
- それによって、どんな成果が生まれるのか
- 投資に見合うリターンが本当にあるのか
この費用対効果を冷静に見極める視点が、極めて重要になります。
DXは「やればいいもの」ではありません。限られた予算の中で、最大の価値を生み出すための、経営や行政における重要な意思決定なのです。
DXの成否を分けるパートナー選び

最後にお伝えしたいのが、パートナー選びの重要性です。
DXは、新しいことへの挑戦です。だからこそ、ツールや技術以前に、人と体制が問われます。DXを推進する担当者は、社内で必ずしも歓迎される立場とは限りません。「DX担当になったものの、本当に成果を出せるのか」「予算ばかり使って、何も変わっていないのではないか」――そんな視線を向けられることも、現実には少なくありません。
そのため、DXを担う人には、強いリーダーシップやストレス耐性、そして最後までやりきる力が求められます。これは個人の資質というよりも、DXという挑戦そのものが持つ性質だと感じています。
一方で、選んだ外部パートナーの動きが悪い場合、状況は一気に厳しくなります。レスポンスが遅い、改善提案が出てこない、現場を理解しようとしない――そうなると、DXは文字通り「地獄絵図」になってしまいます。
だからこそ、パートナー選びは極めて重要です。先ほどご紹介した大垣共立銀行様の事例のように、内製化に挑戦し、自社でコントロールできる体制を築くという選択肢もあります。また、すべてを首都圏のベンダーに任せるのではなく、地元で開発できるパートナーを探すという視点も欠かせません。
地域を理解し、現場に足を運び、日常を共有できるパートナーでなければ、本当の意味でのDXは実現しません。
DXによるビジネスのヒントは、決して遠くにあるものではありません。地域の自治体、地元企業、金融機関――そうした身近な存在の中にこそ、DXの種は数多く眠っています。
DXのチャンスは、すでに地域に眠っている

DXによるビジネスの可能性は、実は私たちのすぐ身近なところに数多く存在しています。
たとえば水産業です。養殖や漁業は国内では右肩下がりと言われがちですが、グローバル市場に目を向ければ需要は確実に伸びています。ITやDXを活用して養殖を効率化し、海外市場を視野に入れれば、十分に勝負できる領域です。私たちは、こうした水産業のDXにも取り組んでいます。
アパレル・服飾分野でも、新たな動きが生まれています。私たちが関わったプロジェクトでは、顧客データを可視化し、全店舗で共有することで、どの店舗でも一貫した接客ができる仕組みが実現しつつあります。これまで属人的だった現場に、DXによる価値が生まれ始めています。
教育現場も、大きな可能性を秘めた分野です。私が講師を務めていた学校では、出席簿はいまだに紙で管理されており、その姿は昔からほとんど変わっていません。しかし裏を返せば、それは教育分野におけるDXの余地が非常に大きいことを意味します。そこには、まだ手つかずのチャンスが確かに存在しています。
さらに、私たちの生活に欠かせないごみ収集や産業廃棄物の業界でも、多くの現場ではいまだに手書きで数を数え、正の字で記録し、複数人がかりで毎日集計しているケースが見られます。これは日本全国で起きている現実であり、ここにもDXによる改善と新たなビジネスの可能性があります。
情熱×DXで、地域の未来を切り拓く
このように、ITがまだ十分に普及しておらず、DXが進んでいない領域は、実は無数に存在しています。社内で進めてきたDXの取り組みが、やがてソリューションとして、同じ業界や同じ地域へと広がっていく――そんな世界観を、いまは現実的に描ける時代になりました。
地域には、ビジネスチャンスが無限に広がっています。
あとは、やるか、やらないか。
行動に移すか、移さないか。
挑戦するか、しないか。
それだけの違いです。やれば、チャンスは必ず掴める。私は、そう信じています。
ぜひ皆さんと一緒に、地域に眠るチャンスを掘り起こしていきたい。情熱 × DX。地域を元気にするために、何よりもまず必要なのは、「情熱」です。
一関の皆さま、そして地域の皆さまとともに、地域を盛り上げるDXを、これから一緒に進めていければと思います。