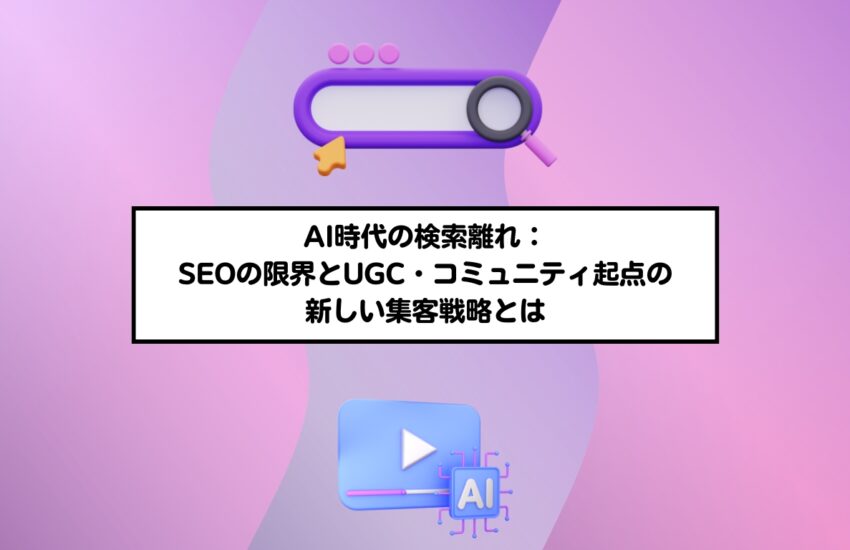生成AIの普及により、検索行動が大きく変わりつつあります。検索結果ページ内で答えが完結するケースが増え、SEOや検索流入に依存した集客モデルは転換点を迎えています。こうした中、ユーザーの体験を起点に広がるUGC(ユーザー生成コンテンツ)が、ブランド認知の新しい入口として存在感を高めています。本記事では、検索依存の弱まりとUGCの重要性を踏まえ、企業がこれから取るべき集客戦略を解説します。
検索エンジンの時代が変わりつつある

IT調査会社のGartnerは、AIチャットボットなどの普及により、2026年までに従来型の検索エンジンによる検索ボリュームが約25%減少すると予測しています。これは、ユーザーが「まず検索エンジンにキーワードを打ち込む」という行動そのものが、構造的に変化しつつあることを意味します。
実際に、生成AIの利用規模は急速に拡大しています。OpenAIのChatGPTは、2025年時点で1日あたり約25億件のプロンプト(質問)に応答しているとされ、週次アクティブユーザーは5億人規模に達しています。
-と-期間.png)
(出典:公開情報をもとに著者作成)
Googleの生成AI「Gemini」も同様に、2025年には3.5億人規模のアクティブユーザーを獲得し、アプリ単体としても数億ユーザーを抱える存在になっています。
-と-サービス.png)
(出典:公開情報をもとに著者作成)
.png)
検索プラットフォーム側の変化も加速しています。Googleは、生成AIによる検索体験「SGE(Search Generative Experience)」を経て、「AI Overviews」として正式サービス化し、検索結果ページの最上部にAIが生成した回答要約を表示する形へと舵を切りました。このAI Overviewsは、2025年第1四半期時点で月間15億人超のユーザーにリーチしていると報告されています。
さらに、米国では、従来の「青いリンク」がほとんど表示されないAI回答主体の検索モードもテストされています。こうした変化により、ユーザーは「リンクをクリックしてサイトを回遊する」のではなく、「検索結果ページ内のAI回答だけで完結する」ケースが増えています。
このように、「検索エンジン経由のアクセス」そのものが縮小しつつあるだけでなく、「検索結果ページの中で完結してしまう」という意味で、従来型のSEO・検索流入モデルは構造的な変化に直面しています。
検索依存からの転換:企業に迫られる集客戦略の再構築

検索経由のトラフィックが減少した場合、企業にとっては主に次の二つのリスクが生じます。
- 広告コストの上昇
オーガニック検索からの流入が減れば、その不足分を補うためにリスティング広告やディスプレイ広告への依存度が高まりやすくなります。競合企業も同様に広告出稿を強化すれば、クリック単価(CPC)の上昇圧力は避けられません。 - コンバージョン率(CVR)の低下
GoogleがAI ModeやAI Overviewsを通じて提供している「生成AIによる回答」は、検索結果ページ内でユーザーの疑問を解消してしまうため、リンクのクリック率が従来比で約3割低下したとする報道もあります。クリック自体が減少すれば、当然ながらサイト内でのコンバージョン機会も減少します。
従来は、「キーワード設計 × SEO最適化」によって検索順位を上げることが、比較的わかりやすい集客戦略でした。しかし、AIが検索結果の要約を提示するようになると、
- ユーザーがサイトに到達する前に情報ニーズが満たされる
- SEOで上位表示されていても、AI回答に埋もれてクリックされない
という構造的な課題が発生します。
このような環境下で企業に求められるのは、「検索エンジンに選ばれる」ことだけに依存しない集客戦略です。具体的には、AI検索の上位に表示されなくても、「あのブランド/あの会社を直接見に行こう」と想起してもらえる “人から選ばれる理由” を持つことが重要になります。
新しい集客の方向性①:コミュニティに人を集める
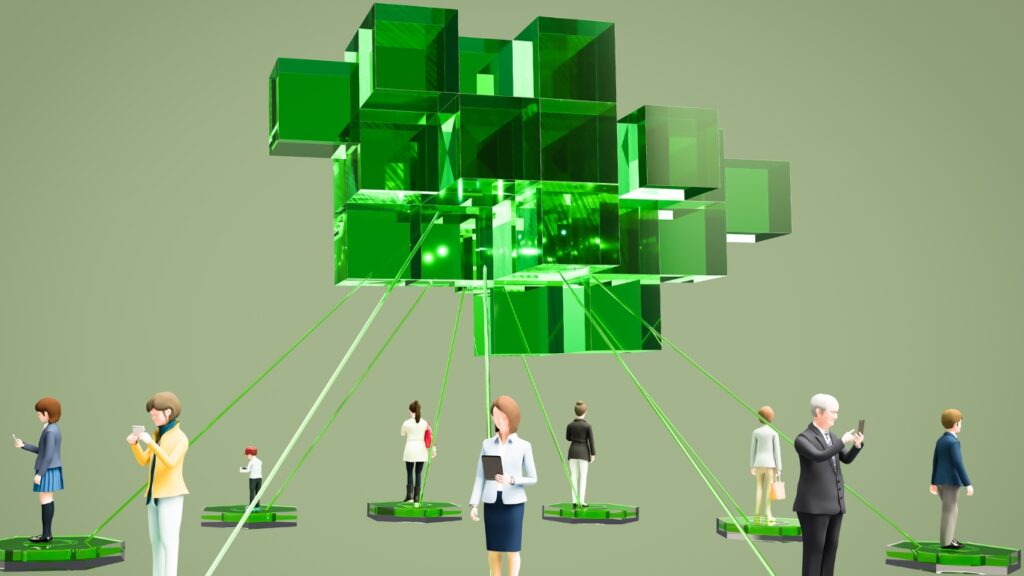
AIがテキストや画像、動画を生成できるようになったとしても、人間同士のつながりや共体験そのものを置き換えることは容易ではありません。
そこで注目されているのが、「コミュニティ」を軸にしたブランドづくり・集客です。
Patagonia:思想を共有するコミュニティ型ブランド
アウトドアブランドPatagoniaは、環境保護・気候変動などの社会課題に対し、一貫したアクティビズムを展開してきました。
製品の販売だけでなく、環境団体への寄付や、製品のリペア・再利用を促す「Worn Wear」プログラムを通じて、「環境保護という価値観を共有するコミュニティ」を形成しています。
顧客にとって、Patagoniaの製品を購入する行為は、「単にアウトドア用品を買う」のではなく、「同じ思想を持つコミュニティの一員になる」意味合いを帯びています。
Snow Peak:ユーザーイベントを通じた“キャンプ仲間”の場づくり
日本のSnow Peakも、コミュニティ型ブランドの代表例と言えます。同社が全国各地で開催しているユーザー向けキャンプイベント「Snow Peak Way」では、テント設営講習やキッズプログラム、アフターサービス、焚き火を囲んだ交流などを通じて、ユーザー同士とスタッフのつながりが生まれています。
Snow Peak Wayは、単なるイベントではなく、「Snow Peakの道具を使う人たちが実際に出会い、経験を共有する場」として機能しており、ブランドへのロイヤルティを高める中核施策になっています。
サバゲーフィールド:場に紐づくローカルコミュニティ
サバイバルゲームのフィールドもまた、コミュニティ型ビジネスの一例です。定例会や初心者向けイベントを通じて、常連プレイヤーと新規参加者が出会い、「特定のフィールドをホームとするコミュニティ」が形成されています。
ここでは、フィールド運営者は単なる施設提供者ではなく、「プレイヤー同士の関係性づくりを支援する役割」を担っています。その結果、参加者は「このフィールドに行けば、顔なじみがいる」「安心して参加できる」という心理的価値を感じ、リピートにつながっていきます。
新しい集客の方向性②:SNS×体験共有の連鎖

もう一つの重要な方向性が、SNS上でのUGC(ユーザー生成コンテンツ)を活かした成長戦略です。
生成AIは文章や画像、動画を生成できますが、実際の利用体験に基づく「リアルな感情」や「その人ならではのストーリー」は、現時点では人間のコンテンツに軍配が上がります。特に、キャンプやアウトドア、旅行といった「体験価値」が中心の領域では、その傾向が顕著です。
キャンプ・アウトドア企業 × インフルエンサーの事例
日本国内でも、アウトドア製品メーカーやキャンプ場が、InstagramやYouTubeを活用したインフルエンサーマーケティングに取り組む事例が増えています。
なかでもキャンプ・アウトドア領域では、キャンプ系YouTuberとメーカーが協業し、SNS上のUGCを起点に成長している事例が目立ちます。具体的な事例としては、次のような取り組みが挙げられます。
事例1: NATSU(女子ソロキャンパー) × tent‑Mark DESIGNS(キャンプギアブランド)
たとえば、女子ソロキャンパーのNATSU氏とテントブランド「tent-Mark DESIGNS」がコラボした「サーカスTC DX+ NATSUバージョン」は、本人監修のカラーリングや仕様を取り入れたモデルで、発売後には「#サーカスTC」などのハッシュタグとともに、購入報告や初張りの写真がSNS上に多数投稿されました。これらの写真は、企業側の公式アカウントからもリポストされ、「推しキャンパーと同じテントを使う」という体験が、ファン同士のUGCによって連鎖的に広がっていきました。
事例2:タナちゃんねる × TOKYO CRAFTS:YouTuber発D2CブランドとしてUGCが循環
キャンプ系YouTuber「タナちゃんねる」を運営するタナ氏は、自らキャンプギアブランド「TOKYO CRAFTS」を立ち上げ、焚き火台やテントなどを展開しています。
YouTube上では、新製品の紹介だけでなく、「なぜこの形状になったのか」「どのようなシーンで使うのか」といった開発ストーリーや実際の使用シーンを丁寧に発信しています。その結果、購入者が自分のサイトレイアウトや焚き火シーンをXやInstagramに投稿し、それをブランド側が紹介するという形で、UGCと商品開発が循環する仕組みが生まれています。
事例3:FUKU × WILDTECH/CAPTAIN STAG
実体験レビューから派生する“使いこなし”UGCキャンプ系YouTuberのFUKU氏は、アウトドアブランドWILDTECHと共同でギアケースやクーラーバッグを開発したり、総合アウトドアブランドのCAPTAIN STAGとコラボして、クッカーに収まるアルミケトルを企画したりしています。
YouTube上で実際の収納例や使用感を詳しくレビューすることで、視聴者は「自分ならこう使う」というイメージを持ちやすくなり、購入後に自分のギアの詰め方やコーヒータイムの写真をSNSに投稿する動機が生まれます。企業側はこうした投稿を公式アカウントで紹介し、レビューや写真を商品ページにも反映することで、UGCを信頼性の高い“第三者の推奨”として活用しています。
これらの取り組みは、企業側が制作した広告コンテンツとは異なり、「ユーザー視点のリアルな体験」としてUGCのように機能します。これらの投稿は、YouTubeやInstagramのおすすめ機能を通じて拡散され、「検索ではなくSNS経由でブランドを知る」きっかけを生み出しています。
共通しているのは、ユーザーが「検索して比較してから選ぶ」というよりも、「推しているキャンパーが使っているから」「フォロワーの投稿で何度も目にしたから」という理由でブランドを知り、興味を持っている点です。
起点になっているのはキーワード検索ではなく、「誰がどのような体験として紹介したか」というストーリーであり、そのストーリーがUGCとしてタイムライン上で再生産され続けることで、検索依存ではない認知と購買の導線が形成されています。
リファーラル(紹介)を起点とするグロース
SNSとUGCを前提にすると、成長の起点は従来の「キーワード検索」ではなく、「誰かの体験や紹介を見て興味を持つ」という流れになります。
企業側が取り得る施策としては、例えば次のようなものが考えられます。
- SNS投稿やレビュー投稿を促進するキャンペーン設計
- 体験イベントと連動したハッシュタグ企画
- コミュニティメンバーや既存顧客をアンバサダーとして位置づけるプログラム
- YouTuberやインフルエンサーとのタイアップにおいて、「1回きりの広告」ではなく、中長期的な共創企画とする
重要なのは、「ユーザーが自分ごととして語りたくなる体験」を設計することです。これにより、検索に依存しない「紹介の連鎖」を生み出すことができます。
まとめ:AI時代における“人間的接点”の再定義

生成AIの普及と検索プラットフォームの変化により、検索エンジンを前提とした集客モデルは確実に変わりつつあります。Gartnerによる検索ボリューム25%減少予測や、AI Overviewsに代表される「検索結果ページ内完結型」の体験は、その象徴的な動きと言えます。
こうした環境下で、企業の集客戦略は次のような方向にシフトしていくことが求められます。
- 検索順位や広告出稿に過度に依存せず、コミュニティやイベントを通じて人が集まる場を設計すること
- SNSやUGCを活用し、検索ではなく「共感」や「紹介」を起点とした発見の導線を作ること
- その結果として、「AI検索の上位に出るかどうか」に左右されにくい、指名検索や直接訪問されるブランドを目指すこと
AIが高度に発達する時代だからこそ、人間同士が交わる場・共体験・ストーリーといった「人間的接点」の価値は相対的に高まっています。
検索アルゴリズムの変化を追い続けるだけでなく、企業自らが「人が集まり、つながりが生まれる場」を設計できるかどうか――それが、AI時代の競争力を左右する重要なポイントになっていくと考えられます。