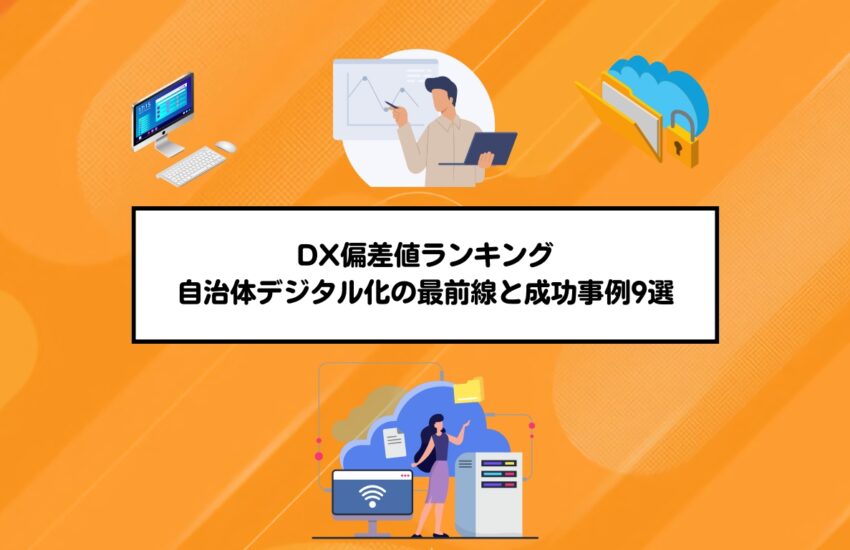自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、地域課題の解決や行政サービスの高度化に向けて、全国各地で加速しています。とはいえ、どの自治体がどの分野で成果を上げているのかを客観的に把握するのは容易ではありません。
そこで注目されているのが、自治体のDX推進度を可視化する民間指標です。今回、株式会社うるるが公表した「自治体ドックランキング2025」で上位に選ばれた自治体を対象に、その取り組み内容を調査しました。
上位自治体には、トップダウンによる推進体制、業務改革(BPR)、データ活用、人材育成、官民連携など、共通する成功要因が見られます。単なるデジタル導入ではなく、成果指標(KPI)で効果を可視化し、組織文化として定着させている点が特徴です。
では、具体的にどのような施策が行われているのでしょうか。本稿では、規模別に見た先進自治体のDX事例を紹介します。
DX偏差値とは?自治体デジタル化の“今”を可視化

自治体のDX推進には地域差があり、同じようにデジタル化を進めていても、体制や成果には大きな開きがあります。その“差”を客観的に示すために生まれたのが「DX偏差値」です。
「DX偏差値」は、自治体のデジタル化を単なる導入件数ではなく、組織体制・業務改革・人材育成・成果指標の運用といった複数の視点から総合的に評価する指標です。
全国でどの自治体がどの程度DXを進めているのかを「見える化」することで、取り組みの現状と課題を明確にする狙いがあります。
自治体ドックランキング2025とは?
株式会社うるるが実施する「自治体ドックランキング2025」は、全国1,741の市区町村を対象に、自治体のデジタル化状況を“DX偏差値”として数値化した調査です。 総務省が公開する各種データをもとに、自治体ごとのDX推進度を分析・算出しており、日本全国の「自治体デジタル化の今」を俯瞰できる仕組みとなっています。
評価は次の5つの分野で行われています。
1.DX推進体制:首長や専門部署のリーダーシップ、推進ガバナンスの整備度合い
2.フロントヤード改革:電子申請・オンライン手続きなど、住民サービスのデジタル化
3.情報セキュリティ:個人情報保護やサイバー対策などの安全管理体制
4.デジタルデバイド対策:高齢者や障がい者への支援、利用環境整備の取り組み
5.行政サービス高度化:AIやデータ分析による業務効率化、政策立案の高度化
これらの要素を総合的にスコア化し、自治体の“DX偏差値”として算出することで、自らの強みと課題を客観的に把握できるようになった点が、このランキングの大きな特徴です。
自治体DX成功の共通点3つ|上位自治体に学ぶ実践ポイント
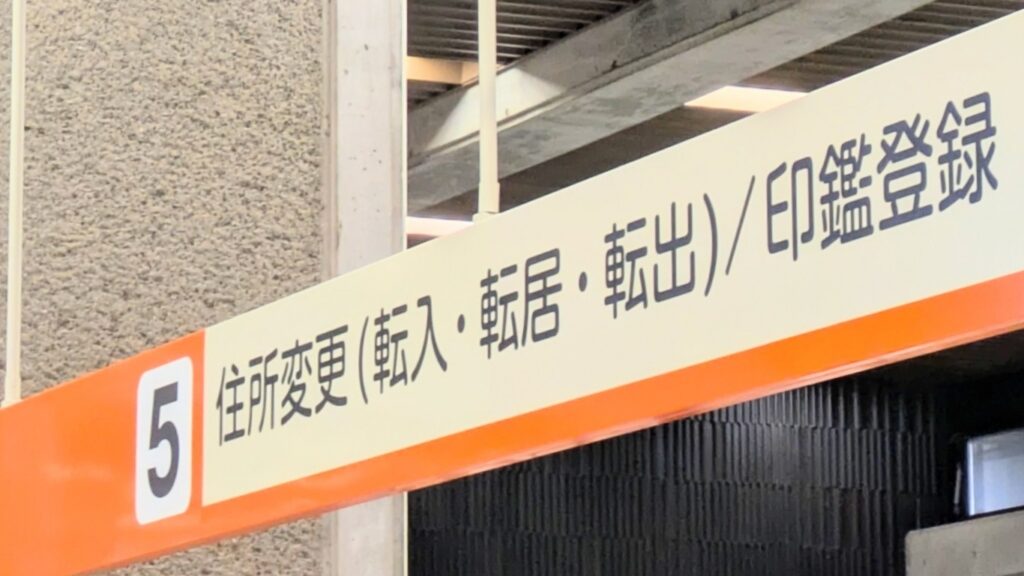
特に高い成果を上げている自治体には共通する成功パターンがあります。上位自治体に見られる3つの実践ポイントを紹介します。
トップダウン型の統治体制で迅速な意思決定を実現
首長が主導する推進本部やCIO/CDO体制を整備し、トップダウンによる迅速な意思決定を可能にしています。明確なリーダーシップのもとで全庁的な方針を共有し、部門横断的なDX推進を実現しています。
BPRとAI・RPAを融合した業務改革が鍵
業務プロセスを「デジタル前提」で再設計し、RPAやAI、クラウド、都市OSなどの技術を段階的に導入しています。これにより、定型業務の自動化と高度なデータ活用を両立させ、職員の付加価値業務へのシフトを促進しています。
KPI運用で成果を「見える化」し、改善を循環させる仕組み
オンライン化率、業務削減時間、住民満足度などのKPIを設定し、定量的に成果を把握しています。その結果を基にPDCAサイクルを回し、継続的な改善と施策の最適化を図っています。
次章では、規模別に先進的なDXの取り組みを紹介します。ガバナンス強化、業務改革、官民連携、人材育成など、偏差値を押し上げた具体的な施策を掘り下げていきます。
大規模自治体のDX実装事例(人口20万〜50万人未満)

大規模自治体は、職員数や業務の多様性ゆえにDX推進の難易度が高い一方、先進的な取り組みが進んでいます。ここでは、豊中市や町田市、一宮市などの実践例を見ていきます。
1.大阪府豊中市|RPAとAIで年間1万時間削減を実現した行政効率化DX
豊中市は、2020年に「とよなかデジタル・ガバメント宣言(Reとよなか)」を発表し、AI・RPA・AI-OCRなどを活用して庁内業務の自動化を推進しています。
教育、医療、予算管理など77業務にRPAを導入し、年間で約10,400時間の業務削減を実現。時間外勤務は令和元年度比で17.5%減少しました。
具体的には、就学援助申請、医療従事者免許の受付、学校給食の食数入力、請求や予算再配当の入力など、従来は紙や手入力に依存していた業務をデジタル化。これによりヒューマンエラーが減少し、住民対応の迅速化にもつながっています。
初期投資は約1,340万円、年間運用費は約1,410万円で、短期間での投資回収が可能な成果を上げました。
一方で、RPAシナリオの保守負荷やデジタル人材の確保が課題として残されています。今後は帳票デザインの最適化や基幹システムとの自動連携を進め、さらなる効率化を目指しています。
2.東京都町田市|生成AI活用で進化する行政サービス
東京都町田市は、「町田市デジタル化総合戦略2025」に基づき、行政手続きのフルデジタル化を推進しています。
市民対応には、3DアバターによるAIナビゲーターを導入し、利用満足度は85%に達しました。
職員向けには生成AIを活用し、議事録作成、要約、起案支援などで月8,000回以上利用されています。
オンライン化された手続き件数は、2022年度の275件から2024年度には553件へと倍増。クラウド移行率は100%を達成しました。さらに、オープンデータの年間ダウンロード数は100万件を超え、市民参加型のデータ活用が進展しています。
庁内では「デジラボ制度」を整備し、職員が主体的に業務改善に取り組む風土を醸成。
また、NTTデータやGovTech東京などの外部組織とも連携し、先端技術の導入を積極的に進めています。
3.愛知県一宮市|スマートガバメント構想で行政と地域を一体改革
一宮市は、「一宮市DX推進計画(2025)」に基づき、行政と地域が一体となって変革を進める「スマートガバメント」を目指しています。
「書かない窓口」「業務標準化とガバクラ移行」「公金収納の電子化」など、住民サービスの利便性向上に重点を置き、マイナンバーカードの普及率は81%に達しました。
都市OS「イチ・デジ」では、健康・防災・交通・福祉のデータを共通IDで統合。さらに、AI-OCRやRPA、ChatGPTなどの先端技術を積極的に導入し、職員の生産性向上を図っています。
また、あいちセキュリティクラウドを活用して24時間体制の監視を実現し、情報セキュリティ対策も強化しました。
今後は、電子契約や生成AIの全庁展開を進め、行政・地域・データが一体となった新たな都市経営モデルの構築を目指しています。
4.愛知県豊田市|人材育成とEBPMで支える“学ぶ行政経営”モデル
豊田市は、DXを「行政経営モデルの再設計」と位置づけ、人材育成と学習の循環を重視しています。
副市長をトップとするデジタル化推進本部が横断的に指揮を執り、各課に推進員を配置。若手職員を中心としたDXプロジェクトも立ち上げ、組織全体での推進体制を整えています。
さらに、4層構造のDX教育プログラムを整備し、ITパスポートやG検定などの資格取得を支援。庁内講師制度を設け、学んだ知識を全庁で共有する仕組みを構築しました。
こうした取り組みを通じて、データに基づく政策判断(EBPM)が着実に根づいています。
「意識 → スキル → 実装 → 成果 → 再投資」という学習循環により、DX投資の持続的な効果を高めています。
超大規模自治体(50万人以上)のDX成功モデル

市民数が多いほど、デジタルによる効率化や住民対応の最適化が求められます。千葉市の「知らせに行く行政」は、その象徴的な取り組みです。
5.千葉県千葉市|行政版CRM「CiRM」で“知らせに行く行政”を実現
千葉市は、2021年に「あなたが使える制度お知らせサービス(For You)」を導入しました。これは行政版CRM(CiRM)として、行政データベースから対象者を自動抽出し、LINEやメールで支援制度を通知する仕組みです。
対象制度は29種類、登録者数は約1.2万人(2023年末時点)。受給漏れの防止と問い合わせ件数の削減を同時に実現しています。初期費用は約1,596万円、年間運用費は約287万円と、費用対効果も高い水準を維持しています。
「申請を待つ行政」から「知らせに行く行政」への転換を象徴する取り組みであり、今後は福祉・教育・防災など、さらなる分野への展開が期待されています。
準大規模自治体(人口10万〜20万人未満)のDX戦略

中核都市クラスの自治体では、独自性とスピード感の両立が鍵となります。宮崎県都城市のように、経営視点でのDXを推進する事例が注目されています。
6.宮崎県都城市|CDO直轄のデジタル経営が生むDX成果
都城市では、市長がCDO(最高デジタル責任者)を務め、副市長が副CDOとして戦略と実行の両面を支える「二層構造」の体制を構築しています。さらに、外部アドバイザーを“翻訳人材”として活用し、現場へのDX浸透を促進してきました。
ここ数年で100件を超えるデジタル施策を実施するなど、自治体DXを先進的に推進しています。マイナンバーカードの普及率は90%台に達し、全国有数の水準を維持。これらの成果は、複数のアワード受賞にもつながっています。
成功の鍵は、KPIに直結した運用体制と、「成果が出ればすぐに水平展開する」というスピード感にあります。
中規模自治体(人口5万〜10万人未満)のDX成功事例

限られた人員でも大きな成果を上げているのが中規模自治体の特徴です。三条市や柏崎市のように、明確な目的とスリムな体制で成果を出しています。
7.新潟県三条市|全庁チャット導入で職員間レスポンス50%短縮
三条市は、全職員約1,000人を対象にビジネスチャットツール「LINE WORKS」を導入しました。わずか4か月という短期間で全庁展開を実現し、年間コストは約540万円と低コストを維持しています。
導入により、職員間のレスポンス時間を約50%短縮し、緊急連絡の漏れをゼロにするなど、業務効率化が大きく進みました。
また、KDDIから派遣された「地域活性化起業人」が庁内に常駐し、運用支援やガバナンス整備を担当。BYOD(私用端末利用)や権限管理などのルールを整え、安心して利用できる環境を構築しています。
三条市の取り組みは、短期間で高い効果を上げた再現性の高い自治体DXモデルとして注目されています。
8.新潟県柏崎市|「デジタル予算書」で行政情報を開放するDX改革
柏崎市は、予算・決算・行政評価を一体化した「デジタル予算書」プラットフォームを開発しました。市民がオンラインで行政情報を検索・グラフ化・地図化できる仕組みを整備し、行政運営の透明性を大きく高めています。
この取り組みにより、市への問い合わせ件数が減少し、市民による自発的な情報活用が進展しました。
開発期間は約1年9か月、初期費用は約3,000万円、運用費は年間約400万円。EBPM(エビデンスに基づく政策形成)を支える基盤としても高く評価されています。
小規模自治体(人口5,000〜2万人未満)のDX成功例

小規模自治体では、リソース制約の中でも持続可能なモデル構築が重視されます。羽咋市の共創型DXは、その好例です。
9.石川県羽咋市|共創人材とデータ活用による持続可能なDX
羽咋市は、市長をリーダー、副市長をCIO、外部専門家をCIO補佐官とする三層体制のもと、DXを推進しています。大学や金融機関と連携し、健康分野のデータを活用した政策実証(EBPM)にも取り組んでいます。
20業務にRPA・AI-OCRを導入し、電子申請件数は年間2,000件に到達。紙の使用量を年間100万枚以下に削減し、公共施設14か所へのWi-Fi整備も完了しました。
限られたリソースの中で、CIO制・共創・KPI管理を組み合わせ、持続可能なDXの実現を進めています。
行政DXの成熟期に向けて:標準化と運用設計の鍵

DXは行政運営そのものを再構築する動きへと発展しています。今後、自治体経営にはどのような変化が訪れるのでしょうか。
生成AI・都市OS・CiRMが行政の標準基盤へ進化
生成AI、都市OS、CiRM(Citizen Relationship Management)は、行政の新たな標準基盤として急速に定着しつつあります。これにより自治体は、「住民の要望を待つ行政」から「先を読んで動く行政」へと変化を遂げています。
また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)も単なる業務自動化のツールから、「人的・時間的リソースを最適に配分する戦略的手段」へと位置づけが進化しています。
BPRとKPI循環が持続的DXを生み出す鍵
DXを成功へ導く鍵は、まず業務改革(BPR:Business Process Re-engineering)を実施し、その上でKPI(重要業績評価指標)を活用した“学習循環”を設計することにあります。
DXの本質は、システムを導入することではなく、成果を継続的に生み出す“仕組み”を構築することです。これにより、自治体は変化する社会課題に柔軟に対応しながら、持続的な成長を実現していくことができます。
自治体DXを成功に導く5ステップ

最後に、成功事例に共通するステップを整理します。どの自治体でも再現可能な「持続的DX」の道筋を見ていきましょう。
1. 課題とKPIを明確化し、成果を定量的に可視化すること
DXの第一歩は、行政課題を明確に定義し、その解決に向けたKPI(重要業績評価指標)を設定することです。定量的な目標を明示することで、職員間の共通理解が形成され、成果の評価と改善が可能になります。
KPIの設定は、単なる評価指標ではなく、組織の「学習装置」として機能させることが重要です。
2. 業務をゼロベースで再設計し、効率性と価値創出を両立させること
既存の前提にとらわれず、業務を根本から見直す業務改革、BPRの視点が不可欠です。この再設計は、単なる効率化を目的とするのではなく、住民サービスの価値向上を同時に実現することを目指すべきです。
行政手続のデジタル化と業務プロセスの合理化を一体的に進めることが、持続的な改革につながります。
3. 小さく速く実装し、検証を通じて改善を重ねること
再設計した業務プロセスは、段階的な実装(PoC:概念実証)を通じて早期に効果を確認することが望ましいです。
小規模でも迅速に試行することで、課題を早期に特定し、改善を重ねながら完成度を高めることができます。
この「小さく始めて、早く回す」アプローチが、リスクを抑えながら実効性を確保する鍵となります。
4. 効果を測定し、成功モデルを横展開・標準化すること
実施後の効果は、設定したKPIに基づき定量的に評価し、成功事例を他部局や他自治体へ横展開することが重要です。
その過程で、再現性のある標準的業務モデルを構築し、組織全体の生産性向上につなげていくことが求められます。
標準化は、自治体間の共同開発や相互連携の基盤としても機能し得ます。
5. 人材の内製化と学習循環の定着を図ること
DXを持続的に推進するためには、外部委託に依存しない「内製化体制」と、人材育成の仕組みが不可欠です。
職員が自ら課題を発見し、デジタル技術を活用して改善を進める文化を醸成することで、組織としての自律的成長が実現します。
継続的な研修・評価・ナレッジ共有を通じて、学習が循環する体制を構築することが望まれます。
まとめ

地方自治体のDXは、もはや一過性のIT導入プロジェクトではなく、組織文化や人材育成を含む包括的な変革プロセスとなっています。
先進自治体の実践が示すように、これら5つのステップを着実に踏むことで、どの自治体においても再現可能な成功モデルを構築することができます。
今後は、国・広域自治体・地域企業との連携を通じて、標準化と人材育成の両輪でDXを深化させ、地域全体のDX成熟度を高めていくことが期待されます。