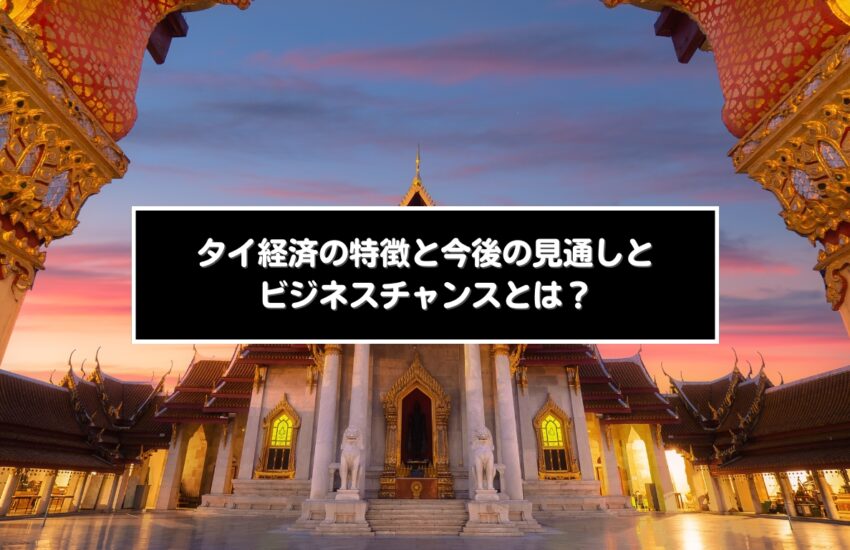東南アジアにおける戦略的ハブとしての地位を確立してきたタイ。観光大国、製造業の集積地、そしてデジタル新興国という多面的な顔を持ちながら、その経済は今、大きな転換期を迎えています。新型コロナウイルスの影響を乗り越え、回復軌道に入ったものの、成長率はASEAN主要国と比較して鈍化傾向にあり、さまざまなリスク要因が潜在しています。
本記事では、タイ経済の現状と構造を多角的に捉えながら、今後の成長シナリオや潜在的なビジネスチャンスについて考察します。
タイ経済の現状:主要指標と産業構造

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により、経済成長率がマイナス6.2%と大きく落ち込みましたが、その後2021年以降はプラス成長に転じ、徐々に回復基調に入りました。ただし、2023年は2.0%、2024年も2.5%にとどまっており、ASEAN主要国と比べると成長ペースはやや鈍く、控えめな状況が続いています。
2024年は、自動車などの耐久消費財の需要が振るわず、個人消費の伸びが抑えられましたが、サービス関連の消費は底堅く推移しました。結果として、民間消費全体では前年比4.4%のプラスを維持しています。加えて、公共投資や輸出の回復も、経済成長を支える要因となりました。
産業構造と部門別の動向
タイの産業構造をみると、GDPの約60%以上をサービス業が占めており、製造業は全体の約25%を構成しています。サービス業の中でも、卸売・小売業が最も規模が大きく、金融・保険、情報通信、運輸・物流なども堅調に成長しています。
一方、製造業は2022年以降、2年連続でマイナス成長となっており、2024年も前年比0.5%減と厳しい状況が続いています。農林水産業については、就業者の約3割が従事し、国土の4割以上が農地という農業大国である一方、GDPに占める割合は10%未満にとどまっています。そのため、生産性の向上や高付加価値化が課題となっています。
※参考として:日本の農林水産業は、就業者に占める割合は約3%、農地の国土比約12%、GDPに占める割合は約1%
雇用の状況
雇用面では、失業率が極めて低く、2025年初頭の時点で0.9%前後と前年よりもさらに低下しています。就業者数はおよそ3,940万人に達していますが、課題として準失業者(不完全就業者)の増加が挙げられます。週あたりの就労時間が短い人は430万人を超え、前年同期比で14.6%増と大きく伸びており、雇用の質の面で注意が必要です。
※「不完全就業者」とは、働く意思と能力がありながら、何らかの理由で十分に働けていない就業者を指します。
経済指標の動向:物価と金融政策
主要な経済指標を見ると、インフレ率は大きく落ち着きを見せています。2022年にはエネルギー価格の高騰などを背景に、消費者物価上昇率が平均6.1%まで上昇しましたが、2023年には1.2%に低下し、2024年通年ではわずか0.4%と、タイ中央銀行が掲げる目標レンジ(1~3%)を下回る水準にとどまりました。
こうした物価動向を受けて、タイ中央銀行は2023年9月以降、政策金利を2.5%で据え置いていましたが、景気の下支えを目的に、2024年10月に2.25%へ、さらに2025年4月には1.75%へと段階的な利下げを実施しています。
物価の安定と低金利環境のもと、国内消費は底堅く推移しているものの、家計債務の水準は依然として高く、GDP比で約88%に達しています。とりわけ、低・中所得層に対する借入規制の強化が、耐久消費財の需要を抑える要因となっています。
外需の回復:輸出と観光の動向
外需面では、2024年の財貨・サービス輸出が前年比7.8%の増加と、コロナ禍からの回復が鮮明になっています。なかでもサービス輸出は25.5%と高い伸びを記録しており、これは外国人観光客数の回復(前年比+ 25.5%、約3,500万人超)による影響が大きく、コロナ前の9割にまで回復しました。
財貨輸出も前年比4.3%と、3年ぶりにプラスに転じました。米国向け輸出が堅調に推移し、中国や日本向けの不調を補ったかたちです。2024年の輸出額(通関ベース)は3,005億ドル、輸入額は3,068億ドルと、いずれも過去最高を更新しています。この結果、貿易赤字は63億ドルと小幅ながら、3年連続で赤字となりました。
輸出の主要品目と動向
タイの主要な輸出品目には、自動車(完成車および部品)310億ドル(全体の10.3%)、コンピュータおよび関連部品246億ドル(8.2%)、宝石・宝飾品184億ドル(6.1%)が挙げられます。このほか、ゴム製品、各種機械、精製燃料なども上位を占めています。
2024年は特にコンピュータ関連が好調で、前年比38.1%の大幅増加となりました。米国向けのハードディスクや電子機器の輸出が牽引役となっています。一方、主力輸出品である自動車は、前年比で3.6%減とやや後退しました。
輸入の主要品目と構造的特徴
輸入面では、原油が最大で326億ドル(10.6%)にのぼり、これに続くのが電子部品(ICなど)244億ドル(8.0%)、機械類220億ドル(7.2%)、電子機器217億ドル(7.1%)、そして宝飾品の原材料である金地金などが194億ドル(6.3%)となっています。
タイの輸入構造は、エネルギー資源や生産財(半導体、機械、化学品など)に大きく依存している点が特徴的です。2024年は特に半導体(IC)の輸入が前年比24.7%増、宝飾品用の貴金属は62.9%増と、いずれも大きく伸びました。
このような貿易構造から、タイ経済は世界経済の動向や国際的な商品市況の変化に対して、比較的影響を受けやすい側面を持っているといえます。
タイ主要経済指標(2024年〜2025年)
◆ 実質GDP成長率:
+2.5%(2024年通年)
+3.1%(2025年第1四半期、前年同期比)
+2.3%(2025年通年予測、タイ中央銀行)
+1.8%(2025年通年予測、世界銀行)
◆ 消費者物価上昇率(CPI):
-0.25%(2025年6月、前年同月比)
+0.5%(2025年通年予測、タイ中央銀行)
◆ 失業率:
0.89%(2025年第1四半期)
◆ 名目GDP規模:
約5,460億ドル(2024年)
◆ 1人当たりのGDP:
約6,573ドル(2024年、名目)
◆ GDP構成比(農業:工業:サービス):
8.6%:34.2%:57.2%(2024年)
◆ 輸出額(財):
約3,007.6億ドル(2024年)
◆ 輸入額(財):
約3,139.7億ドル(2024年)
◆ 経常収支:
+23億ドル(2025年3月)
◆ 人口:
約7,032万人(2025年)
◆ 出生率:
1.08人(女性1人あたり、2023年)
◆ 平均年齢(中位年齢):
約40歳(2020年、推計)
補足:
輸出の見通し:2025年後半、米国の関税強化により輸出の大幅な減少が予想されています。
インフレ動向:2025年6月時点でCPIは前年同月比で-0.25%となり、3か月連続でマイナスを記録していますが、エネルギー価格の下落が主因であり、デフレとは見なされていません。
政治的影響:首相の職務停止などの政治的不安定要因が経済成長や投資に影響を及ぼす可能性があります。
今後の経済見通し:成長予測とリスク要因

2025年以降のタイ経済は、引き続き緩やかな成長にとどまる見通しです。国家経済社会開発委員会(NESDC)は、2025年の実質GDP成長率を1.3〜2.3%(中央値1.8%)へと下方修正。タイ中央銀行も1.3〜2.0%、主要な民間経済団体(JSCCIB)も2.0〜2.2%と、各方面で従来より慎重な見通しが示されています。
国際機関の見方も同様で、IMF(国際通貨基金)は2025年の成長率を1.8%、物価上昇率を0.7%と予測し、低成長・低インフレが続くとの見方を示しています。世界銀行も成長見通しを従来の2.9%から1.8%に引き下げており、ASEAN主要国の中でも相対的に見劣りする状況が指摘されています。一方で、アジア開発銀行(ADB)は2.7〜2.8%とやや高めの成長率を見込んでおり、見通しには一定の幅があります。
慎重な見通しの背景にあるリスク要因
複数の下振れリスクが、これらの慎重な見方の背景にあります。
1. 外部環境の不透明感
世界経済の減速や国際貿易の低迷、とくに中国経済の回復の鈍さや米欧の景気後退が、輸出依存度の高いタイの製造業に逆風となっています。2025年後半には各国の貿易保護主義の強まりが輸出に重しとなる可能性も指摘されており、世界銀行は「中国からの観光客の回復遅れや輸出不振が、成長の足かせになっている」と分析しています。
2. 観光業の回復ペース
2024年の訪タイ外国人観光客は約3,500万人に達し、回復が進みましたが、かつて最大の顧客だった中国からの戻りは鈍いままです。世界銀行によれば、観光客数がコロナ前(約4,000万人)水準に完全に戻るのは2026年第二四半期と見込まれています。GDPの1割超を担う観光業の動向は、成長率に直結します。
3. 政治・政策リスク
2023年の選挙後に発足した新政権では、2024年度予算の承認遅れや、一部大衆迎合的な政策により、公共投資の執行に課題が生じました。政局の不透明さは、2025年度の予算編成やインフラ投資に影響を及ぼす可能性があり、民間投資マインドへの悪影響も懸念されます。実際、2025年7月には首相の職務停止に関する憲法裁の判断が控えており、政情の先行きはなお不透明です。
加えて、米国がタイ産品への関税引き上げ(最大36%)を検討しており、今後の通商交渉次第では対米輸出が打撃を受ける可能性もあります。
4. 気候変動リスク
タイは長い海岸線と農業依存度の高さから、気候変動の影響を受けやすい国のひとつとされています。洪水や干ばつのリスクは農業収量に直接影響し、近年はコメなどの作物にも被害が出ています。将来的には極端な河川洪水により、2035〜2044年の間に影響を受ける人口が200万人以上増加するとの予測もあります。
さらに、バンコクを含む都市部では、豪雨や海面上昇による浸水、熱波による健康被害なども増加傾向にあり、観光業や都市生活にも影響を及ぼすと見られています。こうした環境リスクは、長期的な経済成長にとって看過できない要因です。
下支えとなる要因も
一方で、タイ経済を支える前向きな要素も複数存在しています。物価が安定し、金融環境が緩やかに推移していることは、個人消費の下支え要因となっています。最低賃金の引き上げなども一定の購買力強化につながっており、今後の消費を後押しする可能性があります。
また、政府が主導したデジタルマネー給付政策については、当初2024年に全面実施が予定されていたものの、財政面や政策効果への懸念などから段階的な実施となり、2025年中も一部対象層への支給にとどまっています。ただし、こうした政策は中低所得層の生活支援や地域経済への波及を通じて、一定の需要喚起効果をもたらしています。
雇用情勢は堅調で、失業率は引き続き低水準にあり、観光業の回復も家計の安定に貢献しています。財政政策の面でも、政府はインフラ投資の拡大に意欲を示しており、2024年度の補正予算では関連予算の増額が行われました。
さらに、米中対立を背景に進む「チャイナ・プラスワン」の動きにより、タイには製造業分野を中心とした海外企業からの直接投資が活発化しています。実際、2024年の対内直接投資認可額は前年比+ 31.6%の7,271億バーツと大幅に増加し、電気電子機器や自動車関連分野において新規進出の動きが見られました。こうした流れは、中長期的にみて設備投資や雇用創出を通じ、タイ経済の成長を下支えする要因となると期待されています。
注目される産業・分野の現状と成長性

本章では、観光、製造業、農業、IT・スタートアップ、エネルギーといった注目分野の現状と成長可能性に注目し、それぞれの分野が抱える課題と将来展望について多角的に分析します。ポストコロナ時代の経済回復、脱炭素化の進行、技術革新の加速といった時代の要請を背景に、タイがいかにして産業競争力の再構築を図ろうとしているのか、その全体像を明らかにしていきます。
観光産業
観光業は、タイ経済において最大級の外貨獲得源であると同時に、雇用創出にも大きく寄与している基幹産業のひとつです。新型コロナ以前の2019年には約4,000万人の外国人観光客を受け入れ、観光収入はGDPの2割近くに達していました。
パンデミックにより2020年から2021年にかけては観光客数が激減しましたが、2022年以降は入国制限の緩和を背景に急速な回復を見せています。2024年には外国人観光客が延べ3,504万人に達し、観光収入も1.8兆バーツ(約7兆円超)と、政府目標の3,500万人を上回る結果となりました。タイ政府観光庁(TAT)は、2025年には3,600〜3,900万人の外国人観光客、1.98〜2.23兆バーツの観光収入を見込んでいます。
回復の背景には、ビザ要件の緩和や航空路線の再開・拡充といった政府の施策が大きく寄与しています。2024年には、主要国からの直行便が続々と復活・新設され、航空座席の供給量は前年比26%増の4,700万席に拡大しました。また、音楽フェスティバルやスポーツイベントの開催、タイ国内のドラマ・映画のロケ地巡りといった新たな誘客コンテンツも奏功し、多様な市場から観光客を呼び込むことに成功しています。
とはいえ、いくつかの課題も残されています。国別では、中国からの観光客の戻りが依然として鈍く、2024年の訪タイ中国人は推計280万人にとどまり、コロナ前の約1,100万人にはまだ大きな開きがあります(中国政府による団体旅行解禁の遅れなどが要因とされています)。一方で、インドや中東諸国からの富裕層旅行者の増加が目立っており、市場の多角化が進展しています。
こうしたなか、タイ政府は「Amazing Thailand 2025」キャンペーンを掲げ、観光の質向上と持続可能性の確保に力を入れています。具体的には、長期滞在ビザの整備、高級志向のプロモーション強化、観光地の環境マネジメントの向上など、質の高い観光サービスの提供を目指す取り組みが進められています。
観光業は今後も、サービス産業全体の成長を牽引することが期待されていますが、一方で世界経済の動向や感染症リスク、地政学的要因など、外部環境の影響を受けやすいという脆弱性も抱えています。そのため今後は、富裕層誘致や観光地の分散化を通じたレジリエンスの強化が重要な課題となりそうです。
製造業の現状と展望(自動車・電子機器分野)
タイ経済において製造業は依然として中心的な役割を担っており、とりわけ自動車産業と電子・電機産業は輸出や雇用を支える重要な柱となっています。近年、これらの分野は急速な技術革新や国際的な需給構造の変化、さらには環境対応の要請といった外的要因に直面しており、大きな転換点を迎えています。本章では、EVシフトの波が押し寄せる自動車産業の動向と、米中摩擦やデジタル需要の高まりを追い風とする電子・電機産業の最新の展望について概観します。
自動車産業:EVシフトという転換期へ
タイは「東南アジアのデトロイト」とも称されるほど、自動車産業が発展しており、2019年にはアセアン地域で最多となる約216万台の自動車を生産しました。日系の主要メーカーをはじめ、欧米や中国の完成車メーカー、そして数百社にのぼる部品サプライヤーが進出しており、自動車および関連部品は現在でもタイの最大の輸出品目となっています。
しかし、世界的な脱炭素の流れのなか、タイの自動車産業も大きな変革期を迎えています。EV(電気自動車)やハイブリッド車(HEV)、バイオ燃料車など、次世代モビリティへの対応が喫緊の課題となっており、政府も「30@30政策」のもと、2030年までに国内生産車両のうち30%をZEV(ゼロエミッション車)とする目標を掲げています。
この方針に沿って、税制優遇や補助金、EV購入支援などの包括的な支援策が実施されており、タイ投資委員会(BOI)による法人税免除(最大8年間)なども活用されています。こうした支援策を背景に、中国のBYDや長城汽車などのメーカーがタイでのEV生産を決定しており、EV分野への投資が活発化しています。
国内市場でもEVの存在感は高まりつつあり、2023年には新車販売に占めるEV比率が約6%にまで上昇(前年比で数倍の増加)しました。ただし、ガソリン車に関連する投資の落ち込みが影響し、2024年の民間投資全体は前年比1.6%の減少となるなど、移行期ならではの影響も出ています。今後は、既存のサプライチェーンをEV仕様に転換する取り組みや、労働者の再訓練・人材育成が重要なテーマとなりそうです。
電子・電機産業:グローバル需給の追い風を受けて
自動車産業と並んで、電子・電機産業もタイ製造業の中核を担う分野です。とりわけハードディスクドライブ(HDD)の分野では世界有数の生産拠点であり、半導体の後工程(アセンブリ・テスト)や家電製品の製造拠点も多数立地しています。
2024年は米中摩擦の影響を受けて、タイから米国への電子製品の輸出が拡大し、コンピュータおよびその部品の輸出額は前年比38.1%増の246億ドルと大きく伸びました。電子集積回路(IC)は、重要な輸入中間財としても位置づけられており、タイ国内で組み立てて再輸出するモデルが成長しています。
タイ政府はこうした動きを踏まえ、電子産業の高度化を国家戦略の一つに据え、特に半導体分野の人材育成に注力しています。今後数年でエレクトロニクス分野のエンジニアを8万人育成する計画が進められており、日本の支援機関(AOTSやJTECSなど)との連携による研修プログラムも展開されています。
さらに、次世代半導体やデータセンターの誘致にも積極的で、AI時代に備えたデジタルインフラの強化にも力を入れています。これらの製造業の高度化には、電力供給やインフラ整備の充実も欠かせない要素であり、再生可能エネルギーの推進と密接に関わる分野でもあります。
農業分野
タイの農業は、就業人口の約3割を占める一方で、GDPに占める割合は1割に満たない水準にとどまっており、生産性の低さが長年の課題となっています。コメやサトウキビ、天然ゴム、タピオカといった伝統的な一次産品の主要生産・輸出国として知られていますが、農家一人当たりの収入は依然として伸び悩んでおり、農村部の所得向上が重要なテーマとなっています。
こうした状況を受け、タイ政府は農業の高付加価値化と技術革新に取り組んでいます。具体的には、スマート農業(精密農業)の導入や、農産品の加工・ブランド化を進めており、例えばコメの品種改良や果物(ドリアン、マンゴーなど)の高品質化、有機農業の推進といった取り組みが強化されています。
最近では、日本やイスラエルの先進的な農業技術を活用した実証プロジェクトも進んでおり、センサーやIoTを活用した温室栽培が注目されています。実際に、日本企業との連携でチェンマイにおいて高品質イチゴの栽培と低コスト物流に成功した例や、AIやドローンを使った精密農業を手がけるスタートアップの登場など、新たな展開が広がりを見せています。
バイオエコノミーへの展開とBCG戦略
加えて、タイは豊富なバイオマス資源を背景に、バイオエコノミー(Biotech)分野への展開も進んでいます。サトウキビやパーム油を原料としたバイオ燃料の生産はすでに活発であり、政府は「バイオ・サーキュラー・グリーン(BCG)経済」戦略のもと、農業副産物を活用したバイオ化学品の製造や、機能性食品などの高度食品加工産業の育成を目指しています。これらの取り組みは、農産物の付加価値を高めるとともに、農家の所得向上にもつながることが期待されています。
残る課題と今後の方向性
とはいえ、農業分野には依然として多くの課題も残っています。農家の高齢化や人手不足に加え、気候変動による不作リスクも深刻です。たとえば、2023〜2024年にはエルニーニョ現象の影響により干ばつが懸念され、主要ダムの貯水量低下を受けて作付け制限の必要性も議論されました。
さらに、焼畑による山火事・煙害、違法漁業といった環境・資源管理に関する問題も指摘されています。今後は、官民連携によるスマート農業の普及促進や、農協改革による流通効率化、気候変動に対応した作物転換や経営支援など、より実効性の高い施策が求められる局面に入っています。
IT・スタートアップ産業:デジタル成長のエンジンとして
タイは、東南アジアの中でも高いデジタル潜在力を持つ国として注目を集めています。約7,000万人の人口を抱える大市場で、スマートフォンの普及率も非常に高く、特に若年層を中心にSNS、EC(電子商取引)、デジタル決済といったサービスが日常生活に浸透しています。
こうした環境を背景に、近年ではタイ発のスタートアップ企業が東南アジア市場で台頭し始めており、物流テックやフィンテック分野では、ユニコーン企業(企業評価額10億ドル超)も誕生しています。
政府も「Thailand 4.0」政策のもと、スタートアップ支援を国家戦略の柱の一つに位置づけており、国家イノベーション庁(NIA)による資金支援やアクセラレーター・プログラム、デジタル経済振興機関(DEPA)による各種プロジェクトなど、公的支援策が充実しつつあります。民間セクターでも、CPグループ、シンハー、PTTといった財閥系企業がCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を通じてスタートアップ投資を拡大しており、エコシステム全体の基盤が強化されています。
分野の多様化と海外人材誘致
分野別に見ると、Eコマース、ライドシェア、フードデリバリーといったBtoC領域に加え、製造業向けIoTソリューション、スマート農業技術、観光プラットフォームといったBtoB系のスタートアップも登場しており、その多様性が広がっています。
外国人起業家や高度人材の受け入れ促進にも力を入れており、2022年にはスマートビザ制度を刷新してスタートアップ起業家を対象に優遇条件を整備。また、同年開始の長期居住(LTR)ビザ制度では、外国の富裕層やデジタル人材に対し、最大10年間の滞在資格と税制優遇を提供しています。さらに2023年には、法人税の軽減措置(中小スタートアップ対象で20%→10%)も導入されました。
こうした制度面での支援が後押しとなり、バンコクやチェンマイを中心にコワーキングスペースやインキュベーション施設が増加。国内外から起業家やクリエイターが集まる環境が着実に整いつつあります。
課題と今後の成長分野
一方で、課題もいくつか指摘されています。たとえば、シンガポールやインドネシアと比較すると、大規模な資金調達が難しい点や、英語によるビジネスコミュニケーション、政府調達や規制対応へのアクセスのしづらさなど、人材・制度面でのハードルが残っています。
それでも官民を挙げた取り組みが着実に成果を上げ始めており、タイは今後、東南アジアにおける「スタートアップの飛躍拠点」としての存在感を高めていく可能性があります。特に、AIやデータセンター分野では成長が期待されており、政府は「タイを地域のデータハブに」という目標のもと、全国各地で大規模データセンターへの投資誘致を推進しています。
5G通信インフラの整備も主要都市で進行中で、製造業や医療分野におけるIoT実証も始まっています。こうしたIT・スタートアップ分野の発展は、他産業の高度化を促すゼネラルパーパス技術(汎用技術)として、今後のタイ経済全体の競争力を左右する重要な鍵となっていくでしょう。
エネルギー分野の転換期:再生可能エネルギーを軸に
タイのエネルギー政策はこれまで長らく天然ガスに大きく依存しており、発電電力量の約6割をガス火力が占めてきました。これはタイ湾沖のガス田を含む国内産ガスを活用した構成で、石炭火力、水力(主にラオスからの輸入)などがこれに続く形となっています。
しかし近年、気候変動対策やエネルギー安全保障の観点から、再生可能エネルギー(再エネ)の導入が大きな政策課題として浮上しています。タイ政府は国家電源開発計画(PDP)の改定を通じて、2037年時点での再エネ発電比率目標を従来の36%から51%へと大幅に引き上げました。これは再エネが化石燃料を上回る水準となる意欲的な目標であり、特に太陽光発電の拡大(20GW規模への増強)が中心に据えられています。
タイは日照条件に恵まれており、今後20年で大規模な太陽光発電の導入余地が大きいとされています。また、既存のダム湖面を活用したフローティング型太陽光発電など、新技術との組み合わせによる発電効率の向上も進められています。電力供給の中核を担うタイ発電公社(EGAT)も、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、再エネ拡大、水素エネルギーの導入、小型原子炉の検討など、多方面での戦略を進めています。
再エネを後押しする産業ニーズと民間投資
再エネ導入を後押しする動きは、産業界からも広がっています。とくに輸出志向の製造業では、RE100(再生可能エネルギー100%利用)への対応が求められており、工場屋根への太陽光パネル設置や自家発電への投資が加速しています。日本の総合商社やエネルギー企業もタイ市場に進出しており、工業団地でのオンサイト発電事業などが展開されています。
こうした需要を背景に、エネルギー市場には新たなビジネス機会が生まれつつありますが、課題も少なくありません。たとえば、太陽光発電で生まれた余剰電力の売電が現時点では制約されていること、蓄電池のコストが依然高水準であること、また既存の地域電力会社と工業団地の電力利権の調整が新規参入の障壁となるケースもあります。
政府はこれらのボトルネックを解消すべく、規制緩和や電力系統インフラの整備にも着手しており、エネルギー政策全体の柔軟性が高まりつつあります。
次なるステップ:スマートインフラとエネルギー安全保障
再エネ以外の分野でも、タイはエネルギー転換の先導役を目指しています。東南アジアでいち早くEV用の急速充電インフラ整備に着手しており、今後の電力需要の増加を見据えたスマートグリッドの構築やピーク電力対策が急務となっています。
また、LNG(液化天然ガス)受入基地の拡張や、周辺国との電力融通協定など、エネルギー安全保障を強化するための取り組みも進行中です。
総じて、エネルギー分野は現在、脱炭素と技術革新を軸に大きな変革期を迎えています。再エネ導入目標の達成には多額の投資と制度整備が必要ですが、そのプロセスのなかで、太陽光・風力発電事業、蓄電池・水素関連技術、電力デジタル化サービスといった新たな成長分野が育まれることが期待されています。
外国企業・投資家にとってのビジネスチャンス

グローバル経済の変動が続くなかでも、タイは依然として外国企業・投資家にとって魅力的なビジネス拠点として注目を集めています。豊富な投資優遇策と堅実なインフラ、広範な通商ネットワークに加え、戦略産業への重点支援など、タイは多様なチャンスを提供する投資先として存在感を強めています。本章では、東部経済回廊(EEC)をはじめとする注目エリアの動向や、次世代自動車・再エネ・デジタル分野など将来性の高いセクターを中心に、外国企業にとっての事業機会を解説します。
投資先としてのタイの魅力
タイはこれまで一貫して外国直接投資(FDI)を積極的に受け入れており、日本をはじめとする海外企業にとって、東南アジアにおける有望な投資先として高い評価を得ています。
その背景には、タイ投資委員会(BOI)による法人税や関税の免除(例:先端産業に対する最長8年間の法人税免除)、外国企業による土地保有の容認、外資規制の緩和、投資関連ビザの発給支援といった投資優遇策の充実があります。
とくに注目されているのが、チョンブリ・ラヨーン・チャチュンサオの3県にまたがる東部経済回廊(EEC)です。ここでは先端産業の集積やインフラ整備が進められており、EEC法に基づく特別優遇措置が適用されています。EECに進出する投資案件には、通常よりも手厚い税制インセンティブやワンストップでの許認可手続きの支援が提供され、自動運転車、航空、バイオテクノロジー、スマートエレクトロニクスなど戦略分野への投資が促進されています。
また、スマートビザや長期居住(LTR)ビザの導入により、外国人起業家や高度人材の長期滞在を後押しする環境も整ってきています。これにより、IT・エンジニアリング・デジタル分野のグローバル人材の誘致が進み、産業競争力の強化につながっています。
通商ネットワークと地域連携の優位性
通商面では、タイはASEAN経済共同体(AEC)の一員として域内関税の撤廃メリットを享受しているほか、日タイ経済連携協定(JTEPA)、タイ・オーストラリアFTA、タイ・インドFTA、そしてRCEP(地域的包括的経済連携)など多国間・二国間の自由貿易協定(FTA)網を広く展開しています。
2025年内の妥結を目指し、EUとのFTA交渉も約10年ぶりに再開されるなど、対外経済戦略はさらに活発化しています。加えて、タイ政府はFTAのカバー率を全貿易の60%超に拡大する目標を掲げ、バングラデシュや湾岸諸国とのFTA締結にも前向きな姿勢を示しています。
こうしたFTAネットワークの広がりと、域内の物流ハブとしての地理的優位性は、タイを生産・輸出拠点とする外国企業にとって大きな魅力となっています。
インフラ・人材・コスト面の強み
インフラ整備の面でも、タイは比較的高水準の物流・交通網を有しています。バンコクにはレムチャバン港やスワンナプーム国際空港といった拠点が整備されており、EECでは高速鉄道による空港連結プロジェクトなどが進行中です。
また、ラオス経由で中国とつながる国際鉄道の整備や、東西経済回廊の道路網の強化などにより、メコン地域の陸上物流ハブとしての役割も高まりつつあります。
電力・通信インフラに関しても、電力供給の安定性は高く、停電の頻度も減少傾向にあります。通信では5Gの整備が主要都市で進んでおり、ビジネスに適した環境が整っています。人件費面でも製造業労働者の平均賃金は月500〜600ドル程度と比較的抑えられており、生産性とコストのバランスを踏まえて高い競争力を維持しています。
有望な投資分野と日本企業の機会
外国企業にとって特に有望とされる分野は以下のとおりです:
- 次世代自動車・EV産業:部品供給、充電インフラ、ソフトウェア開発など
- 電子・半導体分野:半導体製造装置、IoT対応部品、電源制御技術など
- 再生可能エネルギー:太陽光設備、蓄電システム、エネルギーマネジメント
- スマート農業:精密農業機器、高付加価値品種、ICT農業支援ツール
- 観光・サービス業:ヘルスケア、ホスピタリティ、マーケティング支援
実際、2024年の対内直接投資データを見ると、日本やシンガポールからの投資案件が上位を占めており、日本企業にとっても依然としてタイは戦略的な拠点となっています。とくにタイ政府が掲げる5つの戦略産業(次世代自動車、電子機器、デジタル、バイオ・循環型産業、医療)には、日本の強みと合致する分野が多く、官民連携による協力機会も広がっています。
留意点と今後の展望

一方で、留意すべき点もあります。たとえば近年はガバナンス指標(汚職認識指数など)の悪化が指摘され、法制度の透明性や知的財産権保護、契約執行の面で改善の余地があるとされています。
とはいえ、政府は行政手続きのオンライン化や商務省窓口のデジタル化、投資ワンストップサービスの拡充といった改善施策を講じており、ビジネス環境は着実に整備されつつあります。
タイは今後も「アジアの中心で質の高い成長を目指す市場」として発展が期待され、中長期的な視点で見れば、海外企業にとっての戦略的な投資先としての魅力は引き続き高いといえるでしょう。
まとめ:変革期にあるタイ経済と広がるビジネス機会

タイ経済は現在、ポストコロナの回復過程にありながらも、成長の鈍化や外部環境の不確実性といった課題に直面しています。観光や輸出の回復、安定した雇用と物価、そしてインフラ整備の進展など、経済を下支えするポジティブな要因も存在する一方で、地政学的リスク、気候変動、政治の不透明さなど複合的なリスクが重層的に存在しています。
こうした環境の中、タイは産業構造の再編を進め、観光業の高付加価値化、EV・半導体分野を軸とした製造業の高度化、再生可能エネルギーやデジタル経済へのシフトなど、新たな成長領域を着実に育てつつあります。特に「Thailand 4.0」やBCG経済といった国家戦略は、次世代の技術と持続可能性を融合させる重要な布石となっており、多様な分野でイノベーションの動きが加速しています。
外国企業・投資家にとっては、タイは東南アジア市場へのアクセス拠点として依然として大きな魅力を持っています。投資優遇制度や自由貿易協定(FTA)の広がり、高水準のインフラ、安定した人材供給などの基盤は整備されており、特に次世代自動車、スマート農業、デジタル、エネルギー分野には新たな商機が広がっています。
ただし、中長期的な視点での進出にあたっては、制度整備の進捗、政策リスク、持続可能な成長戦略の有無といった観点を丁寧に見極めることが重要です。
追記:アメリカの関税政策とタイ経済への影響

2025年7月8日、米国のトランプ大統領は、14か国を対象に新たな関税措置を発表しました。対象国が8月1日までに米国との貿易協定に合意しない場合、最大で40%の輸入関税を課すと警告しています。これは、4月に打ち出された「相互主義関税」政策の実施段階にあたり、当初示されていた90日間の猶予期間の終了に合わせて発動されたものです。
中でもタイに対しては、36%の関税を課す方針が通告されており、その影響は深刻です。関税対象となるのは、電子機器、ゴム製品、農産加工品など、タイの主要輸出品目に及びます。
2024年のタイの対米輸出額は約549.5億ドルで、全輸出額の18.3%を占めており、米国はタイ最大の輸出先です。したがって、今回の措置はタイ経済全体に広範な影響を及ぼすことが懸念されます。
こうした状況を踏まえ、アメリカの新たな関税方針がタイにもたらす影響について、最新の動向をもとに詳しく見ていきたいと思います。
タイ政府の対応と経済政策の転換
タイ政府は、米国との貿易不均衡を是正し、関税の引き下げを目指して積極的な交渉を進めています。具体的には、今後5年間で対米貿易黒字を70%削減し、7〜8年以内に貿易収支の均衡を達成する計画を提案しています。また、米国からのエネルギー、航空機、農産物の輸入拡大を通じて、米国の貿易赤字解消に貢献する姿勢を示しています。
さらに、タイ政府は米国からの投資誘致や、先端技術分野での協力強化を図るなど、経済政策の多角化を進めています。これには、AIやデータセンター、先進製造業などの分野での協力が含まれます。
経済への影響と今後の見通し
関税問題の影響で、タイ経済は減速傾向にあります。2025年のGDP成長率は、前年の2.5%から2.3%へと低下し、関税の影響が続けば1%台に落ち込む可能性も指摘されています。
また、タイの株式市場も影響を受けており、2025年前半には主要アジア市場が上昇する中、タイのSET指数は5年ぶりの低水準に落ち込みました。これは、政治的不安定や貿易摩擦への懸念が背景にあります。
結論
タイと米国の関税問題は、タイ経済にとって深刻な課題となっており、政府は経済政策の大幅な転換を余儀なくされています。現在、両国間での交渉が進められており、タイ政府は関税引き下げと経済協力の強化を目指しています。今後の交渉の行方が、タイ経済の安定と成長に大きく影響することが予想されます。