【2025/7/16 更新】
本記事では、生成AIの活用事例や導入のポイントについて、基礎から具体的な実践例まで幅広くご紹介します。ビジネスに役立つ活用ヒントや、思わず試してみたくなる面白い事例も多数取り上げていますので、自社での導入検討にお役立てください。
- ビジネスシーンにおける生成AIの主要活用分野とは?
- 注目すべき生成AIビジネス活用事例【最新版】
- 【事例1】博報堂DYグループ|広告業務の効率化と品質向上の実現
- 【事例2】パナソニック コネクト:ConnectAIによる業務改革
- 【事例3】ソフトバンク株式会社:生成AIで変わるコールセンター業務の現場
- 【事例4】ベネッセグループ~生成AIは「使いこなす時代」へ~
- 【事例5】トヨタ自動車における生成AI活用事例
- 【事例6】三菱UFJフィナンシャル・グループの生成AI活用事例
- 【事例7】日本テレビの生成AIチャットボット導入事例
- 【事例8】福島カラー印刷株式会社(印刷・デザイン業)
- 【事例9】山田製作所とSpark+の協働プロジェクト
- 【事例10】ベネッセの事例
- 【事例11】三井住友海上火災保険|事故対応業務の高度化
- 【事例12】大和証券 全社員9,000人にChatGPTを導入
- 新価値創造に繋がる面白い生成AI活用アイデア
- まとめ
ビジネスシーンにおける生成AIの主要活用分野とは?

生成AIは、ビジネスのさまざまな場面で実用化が進んでおり、すでに多くの企業で成果が報告されています。主な活用分野としては、以下のようなものが挙げられます。
定型業務の効率化・自動化
定型的な事務作業や資料作成、議事録やメールの作成といった業務を自動化することで、従業員がより創造的・戦略的な業務に集中できる環境づくりを支援します。
マーケティングの効率化、自動化
広告コピーやブログ記事、SNS投稿、製品説明文などのコンテンツを短時間で多数生成できるため、スピーディーなマーケティング施策が可能になります。また、顧客データをもとにパーソナライズされたメッセージの作成も行えます。
製品開発・研究開発の効率化、自動化
新たなデザイン案の自動生成や、シミュレーション、複雑なデータ分析などにより、開発のスピードアップとイノベーションの加速が期待されています。
顧客対応(カスタマーサポート)の効率化・自動化
チャットボットによる24時間対応の顧客サポート、FAQの自動生成、フィードバックの分析などにより、対応品質の向上と業務負荷の軽減の両立が図れます。
教育・研修の効率化、自動化
受講者一人ひとりの習熟度に応じた教材の自動生成や、研修プログラムの構築、さらにはロールプレイングの対話相手としての活用など、教育現場での利活用も広がりを見せています。
このように、生成AIのビジネス活用は非常に幅広く、今後もさまざまな分野で導入が進んでいくことが予想されます。
注目すべき生成AIビジネス活用事例【最新版】

多くの企業が最初に取り組むのは、生成AIを活用した業務効率化です。実際に企業が生成AIをどのように活用し、どのような成果を上げているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
【事例1】博報堂DYグループ|広告業務の効率化と品質向上の実現
従来の広告制作では、プロのコピーライターによる緻密な表現が求められる一方で、制作に多くの時間と工数がかかっていました。
特にWeb広告のように、大量かつターゲットごとに異なるコピーが必要となる場面では、対応しきれないケースや表現の画一化といった課題が顕在化していました。
解決策:広告に特化した生成AIの共同開発
こうした課題を解決するため、博報堂DYグループは「効率」と「質」の両立を目指し、以下の3社による共同プロジェクトを推進しました。
- 博報堂DYホールディングス:豊富なマーケティング知見と生活者インサイトの提供
- 博報堂テクノロジーズ:広告向けのテクノロジーおよびソリューション開発力
- 松尾研究所:東京大学発の最先端AI技術と産業実装ノウハウ
この3社の知見を結集し、広告制作に特化した大規模言語モデル(LLM)を開発。多様で説得力のある広告コピーを自動生成するAIの実現に成功しました。
効果:質を保ちながら“スピードとバリエーション”を両立
この広告特化型AIは、大手生成モデルであるGPT-4oと同等レベルの品質を維持しながら、より多様で独創的な表現を可能にします。従来対応が難しかったニッチな表現や多パターンのコピーも短時間で生成でき、生産性の大幅な向上が期待されます。
導入先と今後の展望
本技術は、博報堂DYグループが展開するマーケティングプラットフォーム「CREATIVITY ENGINE BLOOM」に搭載され、誰でも簡単に高品質な広告コピーを作成できる環境が整備されつつあります。今後は広告制作全体の最適化やクリエイティブ業務の省力化も視野に入れ、人員や予算が限られていても「プロ品質」の広告展開が実現可能となります。
ポイントまとめ
✅少人数でも効率的な広告制作が可能
短時間・少人数体制でも多くの広告文を生成できます。
✅訴求力のある広告を大量に展開
AIがペルソナや目的に合わせて最適なコピーを生成します。
✅属人化を防ぎ、安定した品質を確保
誰が使っても一定の品質が保たれ、表現のばらつきを抑えられます。
生成AIは、「コストを抑えつつ、売上につながる広告制作」を実現する強力なパートナーです。広告領域に留まらず、情報発信、商品紹介、営業資料の作成など、さまざまな業務への応用も期待されています。
【事例2】パナソニック コネクト:ConnectAIによる業務改革
パナソニック コネクトでは、2023年2月という早い段階から、生成AI「ConnectAI」を全社員に向けて展開し、業務の効率化やAIスキルの向上、シャドーAIリスクの低減といった明確な目的を掲げながら活用を進めてきました。1年間で、累計約140万回の利用実績があり、1回あたり平均20分の時間短縮を積み重ねた結果、合計で約18.6万時間もの労働時間削減につながる成果を上げています。
また、活用の範囲も着実に広がっており、日常的な質問対応に留まらず、戦略立案や品質管理、さらには製造現場での技術的な課題解決といった、専門性の高い業務にも応用されています。
特に注目すべき取り組みとして、自社の公開情報や社内の品質管理文書と連携した“自社特化型AI”の開発が進められており、社員が必要な情報を的確に引き出せるよう、プロンプト添削機能など、使いやすさに配慮した工夫も盛り込まれています。
今後は、人事やITサポートなど他部門への展開をさらに進めるとともに、AIが自律的に業務を遂行するオートノマスエンタープライズ(自律型企業)の実現に向けた構想も描かれており、生成AI活用における先進的な取り組みとして、ますます注目を集めています。
【事例3】ソフトバンク株式会社:生成AIで変わるコールセンター業務の現場
ソフトバンクでは、生成AIの活用を通じて、コールセンター業務をはじめとしたさまざまな業務領域での効率化と品質向上を推進しています。
まず、AIによる音声認識システムや応対支援ツールの導入により、オペレーターの業務負荷を軽減しながら、より安定した応対品質を実現。さらに、社内文書の検索や要約といった情報活用の面でも生成AIを導入し、日常業務のスピードと正確性を高めています。
とりわけ注目されるのが、日本マイクロソフトと共同で取り組む生成AIによるコールセンター業務の自動化です。このプロジェクトでは、お客様からのお問い合わせに対して、生成AIが適切な応答を行うことで、待ち時間の短縮や応対の均一化が可能になり、顧客満足度の向上が期待されています。2024年7月以降、自社のコールセンターへの段階的な導入が予定されています。
また、ボイスボットを活用した定型業務(たとえば本人確認など)の自動化も進められており、オペレーターはより複雑で判断が求められる業務に集中できる環境が整いつつあります。
このように、ソフトバンクでは生成AIの特性を業務の現場に的確に組み込むことで、業務効率の向上と人材活用の最適化を同時に実現する先進的な取り組みを進めています。
【事例4】ベネッセグループ~生成AIは「使いこなす時代」へ~
教育・生活領域を幅広く手がけるベネッセグループでは、社内業務の効率化から顧客対応の高度化、さらには子ども向け学習支援に至るまで、生成AIをさまざまな場面で実用化しています。
1.社内業務をよりスマートに──AIによる日常業務支援
ベネッセでは、社内専用の生成AIツール「Benesse Chat(ベネッセチャット)」を導入し、社員の業務を支援しています。具体的には以下のような活用が進んでいます。
- 会議の議事録を自動で要約し、共有作業の時間を短縮
- 新規企画や提案に向けたアイデア出しをAIと共に実施
- プログラムや文書のドラフト作成をAIが下書き支援
この取り組みのポイントは、AIを「人に代わる存在」とするのではなく、「人の思考を助ける補助役」として位置づけている点にあります。社員の創造性や判断力を活かしながら、業務の質とスピードを両立しています。
2.顧客対応にもAIを活用──高品質なサポートの実現
コンタクトセンター業務においても、生成AIが活躍しています。主な活用事例は以下の通りです。
- よくある質問(FAQ)の自動生成・提示によって、顧客自身での自己解決を支援
- オペレーターが迅速に対応できるよう、AIが適切な回答を提案
- 教育資料や研修コンテンツの作成・更新作業をAIが自動化
これにより、対応のスピードと精度が向上し、スタッフの負担軽減にもつながっています。
【事例5】トヨタ自動車における生成AI活用事例
トヨタ自動車株式会社では、車両設計から生産現場に至るまで、生成AIや関連技術の導入を進めることで、業務の効率化と生産性の向上を図っています。以下に、開発・製造の各フェーズでの具体的な活用事例を紹介します。
車両開発プロセスでのAI活用
トヨタシステムズは、30年以上にわたって蓄積されたCAE(Computer Aided Engineering)技術を基盤に、AIを組み合わせた「CAE×AIシミュレーション」を推進しています。この取り組みにより以下の効果が得られています。
- 設計精度の向上:AIがシミュレーション結果を学習・予測し、設計の最適解を導出。
- 開発スピードの向上:従来より短期間でシミュレーション検証が可能。
- コスト削減:設計変更の試行回数を削減し、試作・検証コストを低減。
生成AIによる設計支援
トヨタ・リサーチ・インスティテュート(Toyota Research Institute)では、空気抵抗や車高、キャビンの寸法などの工学的制約を考慮したAI設計支援ツールを開発しています。デザイナーは、自然言語によるプロンプトを入力するだけで、以下のような利点が得られます。
- スケッチの高速生成と修正
- エンジニアリング要件を満たす提案の自動生成
- 創造性と合理性の両立
生産ラインでのAI活用
自社開発AIプラットフォームによる異常検知と品質管理
トヨタは、製造現場自身がAIモデルを開発・活用できる「AIプラットフォーム」を構築しています。これにより現場では以下のような変革が起きています。
- 目視検査の自動化:画像認識による外観検査・仕様確認の効率化。
- 現場主導の改善活動:オペレーターが自らモデルを改善・運用可能。
- 生産性と品質の両立:AIが異常を迅速に検知し、不良品の流出を防止。
良品学習による高精度な異常検出
トヨタが開発したAIエンジンは、異常品のサンプルが乏しい状況でも、良品データを活用して異常を高精度に検出できます。このアプローチの特徴は以下の通りです。
- 大量の良品データの蓄積を活用
- 未知の異常にも柔軟に対応
- AI導入のハードルを低減
まとめ
トヨタ自動車は、AI技術と自社の現場知見を融合させながら、設計・開発・製造の各プロセスにおける効率化と高品質化を実現しています。今後も生成AIを含む先進技術を活用し、競争力のあるモノづくりを推進していくことが期待されます。
【事例6】三菱UFJフィナンシャル・グループの生成AI活用事例
三菱UFJフィナンシャル・グループでは、金融業務の高度化や業務効率化を目的に、AIおよび生成AI技術の活用を積極的に推進しています。ここでは、主要な活用分野について紹介します。
不正検知におけるAI活用
MUFG傘下の三菱UFJニコスでは、2023年4月よりクレジットカード取引に対するAIによる不正検知を本格導入。全てのオーソリ取引(与信照会)に対し、AIが不正リスクをスコアリングする仕組みを構築し、以下の成果を上げています:
- 不正トレンドへの迅速な対応:AIが日々変化する不正パターンを継続的に学習。
- 不正被害の大幅削減:件数・金額ともに導入前と比べて3割以上削減。
- 高精度な検知:業界最高水準の抑止率を実現。
市場予測と生成AI開発の連携
MUFGは、日本発の生成AIスタートアップ「Sakana AI」への出資を通じて、次世代金融×生成AIの可能性を追求しています。今後は以下の領域での活用が期待されています:
- 金融市場の動向予測
- 投資・資産管理アドバイスの最適化
- 顧客ごとのニーズに応じた情報提供の自動化
生成AIの特性を活かしながら、予測精度と提案のパーソナライズ度を高める取り組みが進んでいます。
パーソナライズド情報提供の強化
三菱UFJ銀行は、富裕層向けオウンドメディアにおいて、生成AIを活用したパーソナライズ動画やコンテンツ配信の拡充を検討しています。
- テキスト・動画・音声を組み合わせた情報提供
- 顧客ごとのライフスタイルや関心に基づいた提案
- エンゲージメントの強化とCX(顧客体験)向上
生成AIにより、これまで以上に「顧客に寄り添う」サービスが実現されつつあります。
行内業務の効率化とRPA連携による自動化
MUFGグループでは、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との連携を進め、バックオフィス業務の自動化を推進しています。
- 三菱UFJ銀行では、すでに約20業務で累計2万時間以上の作業時間を削減。
- 三菱UFJ信託銀行では、伝票入力などの手作業をRPAで自動化し、業務効率化とミス削減を実現。
こうした取り組みにより、単純作業から人を解放し、より高度な業務に人的リソースを集中できる環境が整いつつあります。
【事例7】日本テレビの生成AIチャットボット導入事例
日本テレビでは、社内DX推進の一環として、生成AIチャットボットを導入しました。主な目的は、社内ナレッジの検索効率向上と業務支援です。
💡特徴
- 社内マニュアル・ドキュメントの即時検索が可能。
- Google Cloud技術を活用し、セキュアで親しみやすいUIを実現。
- 画像・動画・音声データへの拡張も視野に入れた開発が進行中。
社内利用を前提とした生成AIツールの導入により、テレビ業界におけるホワイトカラー業務の効率化モデルとして注目されています。
まとめ
これらの企業に共通するのは、大規模データの活用力と、業務に密着したAI設計の姿勢です。業種特有のニーズを踏まえながらも、以下のような共通価値が生成AIにより生み出されています。
✅共通する生成AIの価値
・作業の自動化と省力化
・顧客体験の質的向上
・ビジネス判断や予測精度の強化
産業全体への示唆
これらの事例は、生成AIが「業務のデジタル基盤」として定着しつつある兆候を示しています。各社の取り組みから得られる示唆は次の通りです:
・生成AIは、専門性の高い業務領域でも効果を発揮する。
・組織内でのデータ利活用とAIモデル開発の内製化が鍵となる。
・顧客接点・バックオフィスの両面でAI活用が進んでいる。
今後は、他の業種・業界にもこれらの知見が波及し、AIが「企業の知能そのもの」として、あらゆる業務に組み込まれていく時代が到来することが期待されます。
【事例8】福島カラー印刷株式会社(印刷・デザイン業)
企業名・業種:福島カラー印刷株式会社–印刷・デザイン業(福島県福島市)
課題:チラシやカタログのデザイン制作において、顧客との打ち合わせ後の初期デザイン案作成に非常に時間がかかっていました。従来は会議の議事録作成からデザイン案の提案まで5日以上を要し、作業工程の無駄と担当者の負担が大きいことがボトルネックでした。
具体的な対策内容:顧客との打ち合わせを録音し、それをAIで文字起こししたテキストデータをChatGPTに入力。ChatGPTに「打ち合わせ内容を整理・構造化し、デザインコンセプトのラフ案を作成してほしい」と指示することで、チラシやカタログの初期デザイン案(たたき台)を自動生成する仕組みを構築しました。これにより、人間のデザイナーはゼロから案を考える手間が省け、AIが生成した骨子をもとにブラッシュアップ(微調整やクリエイティブな仕上げ)に専念できるようになりました。
導入後の成果:驚異的な時間短縮を実現しました。従来は5日以上かかっていた初期デザイン作成作業が、わずか半日で完了するようになりました。デザイナーからは「コンセプトがすっきり整理され、勢いが冷めないうちに本質的なデザイン作業に入れる」と好評で、業務効率化だけでなく制作品質やスタッフの満足度向上にもつながっています。また、この企業では他の業務にもChatGPTの活用範囲を拡大しており、社内の就業規則に関する問い合わせ自動応答、顧客対応メールの下書き生成、Webサイト更新用文章の作成、社内提案資料の構成案作りといった業務でもAIを導入しています。
【事例9】山田製作所とSpark+の協働プロジェクト
株式会社山田製作所(YAMADA)(本社:群馬県伊勢崎市/代表取締役社長:佐藤 賢)は、1946年創業の老舗メーカーです。自動車のオイルポンプやウォーターポンプ、トランスミッション・ステアリング部品など、クルマの「動き」に関わる機能部品を数多く手がけてきました。近年は、電動化に対応した電動オイルポンプや電動ウォーターポンプの開発にも取り組み、進化を続けています。
社内に埋もれていた「知恵」が見つからない
そんな山田製作所が抱えていたのは、蓄積された技術資料や図面が有効に活用されていないという課題でした。必要な情報を探すのに時間がかかり、ベテラン社員の知見が社内でうまく共有されないという声も。さらに、人手不足が進む中で、次の世代へのノウハウの伝承にも不安がありました。
東京大学発スタートアップとタッグ。AIで「社内の知恵袋」をつくる
そこで同社は、東京大学発のAIスタートアップ株式会社Spark+(スパークプラス)とタッグを組み、「社内文書検索チャットボット」を共同開発。ChatGPTなどの生成AIに、社内に蓄積された資料や図面を読み込ませることで、社員が自然な言葉で質問すると、該当する社内情報をAIが探し出して答えてくれる仕組みです。
このシステムのポイントは、図表や複雑な技術文書にも対応できること。Spark+が持つ最先端の「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」技術により、図面や仕様書の内容も正確に把握し、実務に即した回答を導き出します。
PoCから本格導入へ。「社員の知恵とAIをつなぐ」新しい仕組み
この取り組みは2024年にPoC(概念実証)を実施し、2024年7月に本格導入を開始。PoC段階でも、図表を含む複雑な文書からの回答精度の高さや、知見共有のしやすさなど、想定を超える成果が得られたことが導入の決め手となりました。
山田製作所では、このチャットボットを「社員の知恵とAIをつなぐ“ちえのわ”」と位置づけ、引き続きSpark+と協力しながら、社内の知識を誰でも活用できる環境づくりを進めています。
【事例10】ベネッセの事例
次世代の学びを支える──子ども向け生成AIサービス
ベネッセでは、生成AIを子ども向けの学習支援にも展開しています。たとえば、小学生向けサービス「自由研究お助けAI」は、子どもが答えをただ得るのではなく、「なぜ?」「どうして?」と考える力を引き出すよう設計されています。
このようなAIは、まさに“探究心を育てるナビゲーター”として機能しており、教育現場における生成AI活用の好事例といえるでしょう。
小さく始めて着実に広げる──段階的な導入アプローチ
ベネッセの取り組みのもう一つの特徴は、「小さく始めて効果を見極める」という段階的な導入手法です。
- まずは一部の部署で試験的に活用を開始
- 効果が見られた業務領域に対して、徐々に展開範囲を拡大
- 数値として成果が明確になったタイミングで、全社展開へ移行
また、現場の声を丁寧に吸い上げながら進めることで、現場ニーズに即した“使われるツール”として定着を図っています。
ベネッセの事例からは、生成AIを単なる最新技術としてではなく、「人の創造性」や「現場の知恵」を引き出す道具として活用する姿勢が、成功の鍵になっていることがわかります。
導入を検討する際は、まず現場の小さな課題に目を向け、「時間の節約」「知恵の補強」といった具体的な貢献を通じて、生成AIを組織の一員として活かす第一歩を踏み出すことが重要です。
【事例11】三井住友海上火災保険|事故対応業務の高度化
三井住友海上火災保険株式会社は、OpenAIのChatGPTを活用し、事故対応をはじめとする保険業務の高度化と効率化を推進する先進的な取り組みを展開しています。
背景:事故対応業務の課題と変革へのニーズ
損害保険業界において事故対応業務は、顧客との重要な接点です。迅速かつ正確な対応、そして丁寧な説明力が求められますが、以下のような課題が存在していました:
- 保険約款、法律、社内ルールなど膨大で複雑な知識の習得が必要
- 顧客や修理業者とのやり取りの履歴整理・要約に多くの時間を要する
- 担当者の経験差により、対応品質にばらつきが出やすい
これらの課題を解決するため、三井住友海上では生成AIによる業務支援ツールを導入し、対応品質の向上と業務の効率化を同時に実現する方針を打ち出しました。
仕組みと特徴:AIによる事故対応支援モデル
2023年5月の発表によると、三井住友海上は以下のような対話型AI支援モデルを導入しています。
主な機能と活用シーン
| 機能 | 内容 |
| AIによる文脈理解と情報抽出 | 保険約款・法令・社内マニュアルを学習し、事故の状況に応じて必要な情報を自動で抽出 |
| 対応案の自動提案 | 適切な対応方針をリアルタイムに提示し、説明の正確性と対応スピードを向上 |
| ベテラン社員の知見の再現 | 熟練社員のノウハウをAIに学習させ、仮想スーパーバイザーとして機能 |
| 会話の自動要約と記録 | 顧客や修理工場との会話内容をAIが自動で要約・記録し、入力作業を省力化 |
開発・導入体制
- NEC:AIモデルの開発・エンジニアリングを担当
- アクセンチュア:AI連携基盤「AI HUB」の提供とプロジェクト推進
- Microsoft(Azure OpenAI Service):セキュリティを確保したAI基盤を提供
この体制により、事故対応部門の全社員に仮想的なサポートを提供し、個人に依存しない一貫した対応が可能となりました。
成果と期待される効果
品質向上
- 対応内容の標準化により説明力や品質のばらつきを解消し、顧客満足度を向上
- ベテラン社員の知見が全体に共有され、組織全体のスキルレベル向上が期待される
業務効率化
- 問い合わせ対応や記録業務の自動化により、繰り返し作業を削減
- 担当者は「信頼構築」など、より付加価値の高い業務に集中可能
リスク対応力の強化
- 対応の一貫性とスピードを確保し、誤処理や情報漏えいリスクを軽減
今後の展開と進化
2023年7月には、社員全体が利用可能な生成AIチャットツール「MS-Assistant」の全社展開が始まりました。今後は以下のような展望が示されています:
- 事故対応に留まらず、全社的な業務プロセス改善へのAI活用拡大
- 保険代理店へのAI提供による顧客対応支援
- AIリテラシー向上を目指した「MS&ADデジタルアカデミー」による教育(プロンプトエンジニアリング等)
まとめ
三井住友海上では、従来の人手中心モデルから「人×AI」の協業モデルへと転換を図っています。これにより、事故対応のスピード・品質・説明力・記録性がすべて向上し、ナレッジ共有や人材育成にも貢献する、先進的な業務変革の事例となっています。
【事例12】大和証券 全社員9,000人にChatGPTを導入
大和証券は、生成AI「ChatGPT」が業務革新にもたらす可能性を高く評価しています。特に、以下の2つの観点から、積極的な導入姿勢を示しています。
・スピーディな適応を重視
世界的に活用方法が模索されている段階だからこそ、いち早く導入することで自社内でのユースケースを発見・開拓し、先行者としての優位性を築こうとしています。
・デジタル知見の活用
これまでに蓄積してきたAI・クラウド・デジタル技術に関する知見を活かし、生成AI活用の取り組みを加速させています。
ChatGPTの活用効果
ChatGPTによるアウトプットは、社員が最終確認を行うことを前提としつつ、以下のような効果が期待されています。
1.情報収集の支援
- 特に英語情報の要約・翻訳などにおいて活用
- 海外の金融レポートやニュースへのアクセス性が向上
2.資料作成の効率化
- 企画書、提案書、報告書などのドラフト作成を支援
- 外部委託にかかっていたコストや時間の削減が可能
3.プログラミング支援
- 社内システムや業務ツールの開発において、コードのたたき台(初期案)を作成
4.業務時間の最適化
- 文書作成などの定型業務を効率化することで、顧客対応や企画立案など本来注力すべき業務に時間を充てることが可能に
5.社内アイデアの活性化
- 幅広い社員による自由な活用を通じて、業務ごとのユニークな活用方法が生まれ、新たなユースケースの発見につながる
大和証券のスタンスと今後の展開
大和証券は、「金融・資本市場のパイオニア」として、常に技術革新を先取りする姿勢を掲げています。ChatGPTの導入も、単なる業務効率化ツールとしてではなく、新たな価値創造の基盤(プラットフォーム)として位置づけています。
今後は、導入効果や社員のフィードバックをもとに、他のグループ会社やより幅広い業務領域への活用を視野に入れた展開が進められる予定です。
総評
この導入事例は、日本の金融業界における生成AI活用の先駆的な取り組みとして注目を集めています。特に以下の点で、他企業にとっても模範となる事例です。
- 全社員を対象とした幅広い導入
- セキュアなクラウド環境を基盤とした運用
- 社員の創造性を引き出すための設計思想
今後の成果や応用範囲の広がりにも、業界内外から期待が高まっています。
新価値創造に繋がる面白い生成AI活用アイデア
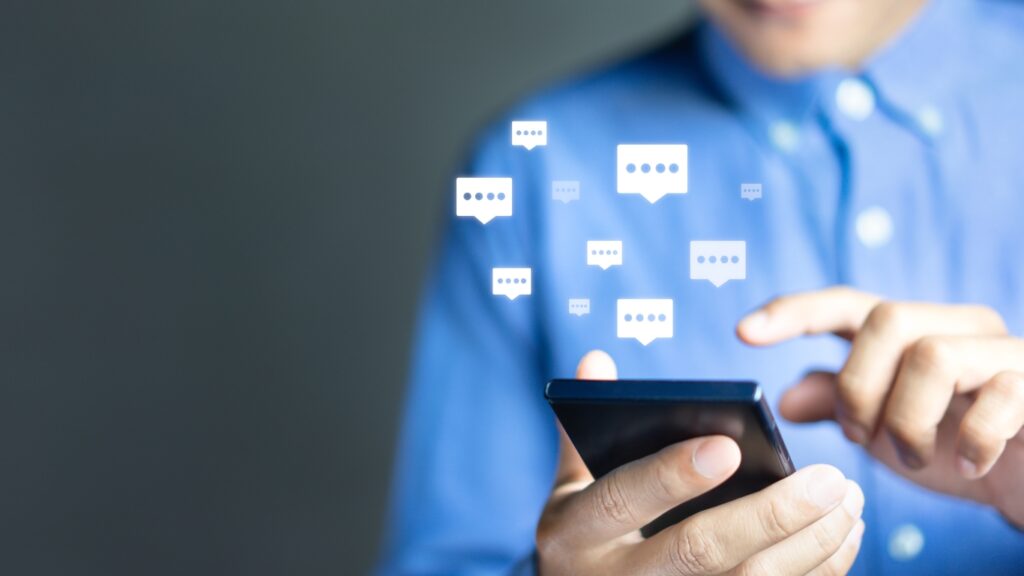
生成AIは、単なる効率化ツールに留まらず、これまでにない新しい価値やサービスを生み出す可能性を秘めています。ここでは、面白いAI活用事例や、アイデアをご紹介します。
パーソナライズされた商品提案
顧客の購買履歴や閲覧履歴、さらにはSNS上の発言などをAIが分析し、個々の嗜好に完全に合致する商品やサービスを生成AIが提案するといった活用が考えられます。
1.ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)
取り組み内容:顧客の購買履歴・店舗の行動データを分析し、アプリやオンラインストアでパーソナライズされた商品を提案。
技術活用:AIとビッグデータ分析を用いて、店舗ごとやユーザーごとに最適な商品・キャンペーンの提示を実現。
生成AI活用:2023年以降、チャットボットと連携した接客・提案機能に生成AI(ChatGPTなど)を導入し始めています。
2.ZOZO(ZOZOTOWN/ZOZOSUIT)
取り組み内容:ユーザーの体型計測データ(ZOZOSUIT)や購買傾向からAIがスタイルを提案。アプリ内でコーディネートを提案する機能も。
生成技術:「あなたのためだけのファッションレコメンド」に生成AIと画像認識技術を活用。近年は、商品画像をAIで生成する試みも進行中。
3.ワコールホールディングス
取り組み内容:女性下着の分野で、サイズと嗜好を反映したブラジャー選びのパーソナライズレコメンドをAIが実施。
チャネル:店頭とオンラインで顧客体験を統合し、マイページで個別提案。
4.資生堂
取り組み内容:顧客の肌質・過去の購入履歴・アンケートなどの情報をAIで解析し、スキンケア商品の最適提案を実施。
技術:「Optune(オプチューン)」というパーソナライズスキンケアブランドでは、IoTとAIを統合し、天候・肌状態に応じて最適処方のスキンケア製品を提供。
インタラクティブなエンターテイメントコンテンツ
ゲームのシナリオやキャラクターのセリフを、プレイヤーの行動に応じてリアルタイムに生成AIが生成することで、没入感の高い体験を提供できます。また、ユーザーが入力したキーワードに基づいてオリジナルの物語や音楽をAIが即興で作り上げる、といったエンターテイメントも可能です。
生成AIを活用して、プレイヤーの行動に応じてリアルタイムにシナリオやキャラクターのセリフを生成するインタラクティブなエンターテインメントコンテンツを提供している企業の事例をいくつかご紹介します。
1.株式会社Algomatic(アルゴマティック)
Algomaticは、ゲーム開発会社向けにAIを活用したシナリオ生成サービスを提供しています。このサービスでは、過去作のデータや設定資料、プロットなどを基に、キャラクターの個性や世界観に忠実なシナリオを最短1営業日で作成できます。また、約130言語に対応しており、日本語のプロットから直接、多言語のシナリオを制作することも可能です。これにより、シナリオライティングのコストと期間を大幅に削減し、品質向上に注力することができます。
2.株式会社レベルファイブ
『妖怪ウォッチ』や『イナズマイレブン』などの人気ゲームシリーズを開発するレベルファイブは、生成AIを積極的に活用しています。同社は、画像生成AI「Stable Diffusion」、大規模言語モデル「ChatGPT」、音声生成AI「VOICEVOX」などを用いて、背景美術の制作、ゲームタイトル画面のレイアウト案作成、3Dモデリング時のテイスト案作成、マップレイアウトのアイデア出し、キャラクター設定案の作成、クエスト・依頼の設定案作成、コーディング補助、イベントステージ演出のアイデア出し、さらには仮ボイスの生成にまでAIを活用しています。これにより、開発プロセスの効率化とクオリティの向上を実現しています。
3.カバー株式会社(ホロライブ)
大手VTuber事務所を運営するカバー株式会社は、所属タレント『博衣こより』のデジタルクローン「AIこより」を制作しました。このAIこよりは、音声入力をWhisperで認識し、GPT-3.5 Turboで回答を生成、CoeFontで本人の音声データに基づく回答を読み上げるなど、複数のAI技術を組み合わせています。これにより、ファンとの自然でインタラクティブなコミュニケーションを実現し、タレントの活動時間外でもファンとの接点を提供することが可能となっています。
4.TyranoBuilderを活用したノベルゲーム制作
ノベルゲーム制作ツール「TyranoBuilder」では、ChatGPTなどの生成AIを活用して、スクリプト(シナリオ・テキスト)の自動生成が可能です。これにより、ユーザーはAIが生成したテキストを組み込んだノベルゲームを簡単に作成できます。初心者向けのGUI操作が特徴で、AIを活用したゲーム制作の入門として適しています。
これらの事例は、生成AIがエンターテインメント業界において、リアルタイムのコンテンツ生成やインタラクティブな体験の提供に活用されていることを示しています。今後、生成AIの進化により、より没入感のあるパーソナルでダイナミックな体験が期待されます。
ユーザーの選択や行動に応じてリアルタイムに変化するシナリオ、キャラクターとの自然な対話、ファンとの継続的な接点など、これまで実現が難しかった体験が、いま現実のものとなりつつあります。
クリエイティブ分野での共創
デザイナーやアーティストが生成AIを「アイデアの壁打ち相手」や「共同制作者」として活用し、新しい表現や作品を生み出す事例が増えています。例えば、建築家が建物の基本コンセプトをAIに伝え、複数のデザイン案を瞬時に生成させ、そこからインスピレーションを得るといった使い方です。
【国内】株式会社大林組×AIによる建築デザイン支援
大手ゼネコンの大林組は、建築設計の初期段階で生成AI(主に画像生成AI)を活用した基本設計案のバリエーション出しを試みています。建物の用途や立地条件などのパラメータを入力することで、AIが複数の外観・レイアウト案を生成し、設計者の発想の起点にするという活用です。
共創ポイント:
・人間の制約を超えた大胆なフォルムや配置案が出てくる
・設計の「壁打ち」相手として、検討の幅を広げる
・デザインコンペなどの初期案として活用されている
【海外】建築:Zaha Hadid Architects(英国)
活用方法:Zaha Hadid Architectsは、建築設計の初期段階で、テキストから画像を生成するAIツール(例:DALL·E 2やMidjourney)を使用し、デザインのアイデアを広げています。
【海外】アート:Refik Anadol Studio(アメリカ)
活用方法:メディアアーティストのRefik Anadol氏は、AIを活用して膨大なデータセット(例:都市の写真や気象データ)を処理し、映像作品《Machine Hallucinations》を制作しました。
【海外】ファッション:H&MとIBMのコラボプロジェクト
活用方法:H&Mは、AIを活用して自社モデルのデジタルツインを作成し、広告キャンペーンに活用する取り組みを進めています。
【海外】映像制作:Runway(AIスタートアップ)と映画制作チーム
活用方法:Runwayは、テキストや画像から動画を生成するAIツール「Gen-2」を提供し、映像クリエイターがコンセプト段階での試作映像の生成に活用しています。
【海外】音楽:Grimes×Elf.tech(AI音楽制作)
活用方法:アーティストのGrimesは、自身の声をAIで再現できるプラットフォーム「Elf.Tech」を提供し、誰でも彼女の声を使った音楽制作が可能となっています。
まとめ
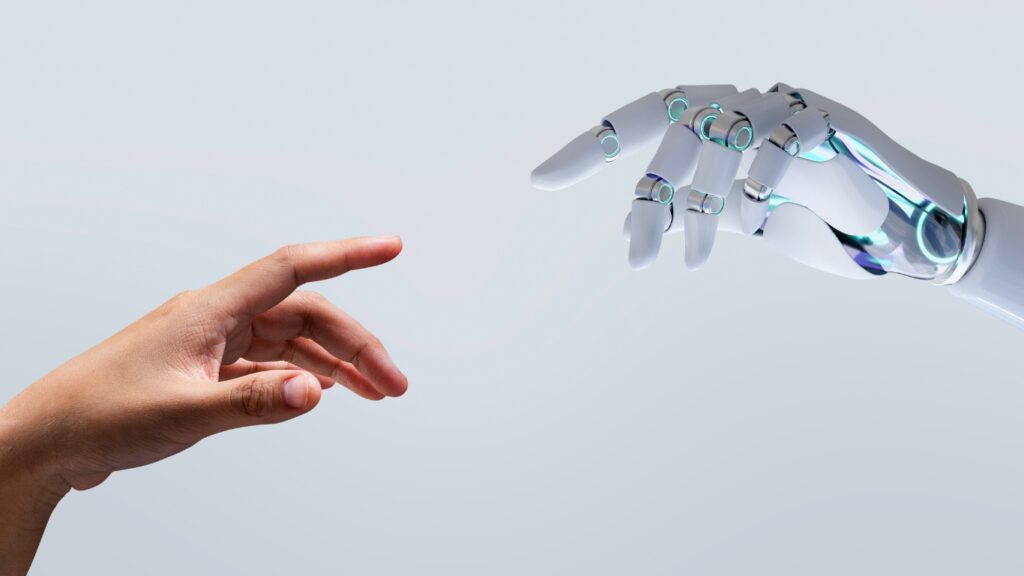
本記事では、生成AIの活用事例を中心に、その基礎知識から業界別・目的別の具体的なAI活用事例、さらには導入を成功させるためのステップや注意点について解説してきました。
生成AIは、ビジネスにおける業務効率化や生産性向上はもちろんのこと、面白いアイデアやこれまでにない新しい価値を生み出す大きな可能性を秘めています。企業が生成AIを導入し、その恩恵を最大限に享受するためには、自社の課題や目的に合った活用方法を見極め、計画的に導入を進めることが重要です。
今回ご紹介した多くの生成AIの事例や活用事例が、皆様のビジネスにおける生成AI導入や活用のヒントとなれば幸いです。ぜひ、生成AIという強力なツールを使いこなし、ビジネスの未来を切り拓いてください。

