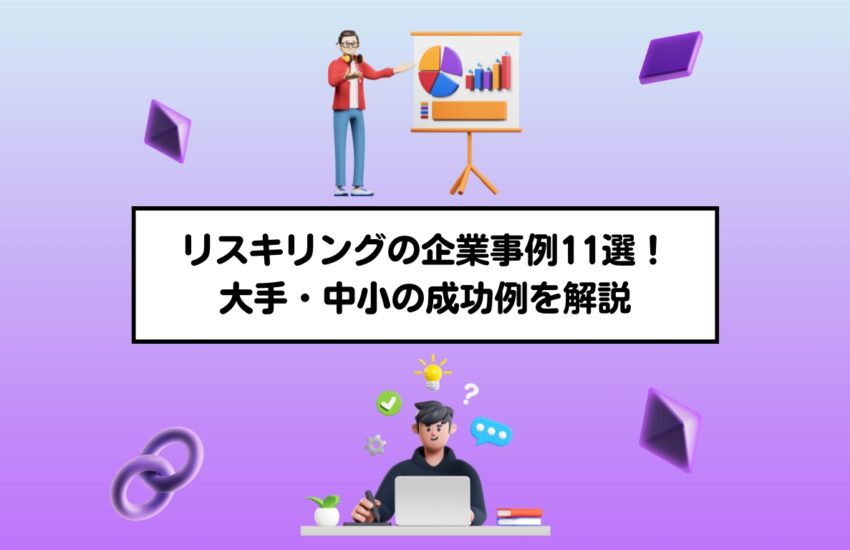「DX化を進めたいが、対応できる人材がいない」「事業構造の変化に合わせて、社員のスキルをどうアップデートすればいいのか」
このような課題を抱える企業の経営者や人事担当者の間で、リスキリングへの注目が急速に高まっています。
リスキリングとは、時代の変化によって新たに生まれた仕事に対応するため、社員が新しいスキルを習得することです。単なる研修とは異なり、企業の成長戦略と直結した重要な取り組みと言えます。
しかし、いざ自社で導入を検討しようにも、「何から手をつければいいのか」「他社はどんな取り組みをしているのか」と、具体的なイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、リスキリングの導入を検討している企業担当者様に向けて、以下の内容を分かりやすく解説します。
・大手・中小・目的別の企業事例11選
・リスキリングの基本的な定義と重要性
・導入を成功させるための具体的なステップとポイント
・活用できる国の補助金・助成金制度
この記事を読めば、リスキリングの全体像を理解し、自社に合った取り組みのヒントが見つかるはずです。ぜひ、貴社の未来を創る人材育成の第一歩としてお役立てください。
【大手企業編】リスキリングの成功事例5選

まずは、大規模な組織でリスキリングを成功させた大手企業の事例を見ていきましょう。経営戦略と連動させたダイナミックな取り組みが特徴です。
富士通株式会社
課題:
IT企業からDX企業への変革を進める中で、全社員約13万人を対象としたリスキリングが喫緊の課題となっていました。
取り組み:
2020年より、全社員を対象としたDX人材育成プログラムを開始。職種別にDX人材のスキルレベルを定義し、eラーニングや実践プロジェクトを通じたスキルアップを支援しています。また、データサイエンスやAIなどの高度専門分野については、社内大学「FUJITSU University」を設立し、より専門的な人材の育成にも注力しています。
成果:
社員全体のDXリテラシーが向上し、新たなDXビジネスの創出や顧客への提供価値の向上に繋がっています。
株式会社日立製作所
課題:
デジタル事業「Lumada」の拡大を戦略の柱とする中で、グループ全体約37万人の従業員を対象としたデジタル人財の育成が急務でした。特に、高度なAIスキルやデータ活用能力を持つ人材の早期育成が求められていました。
取り組み:
全社員を対象とした「デジタルリテラシー・トレーニング」を2020年度より導入。2022年度以降は、AIによる最適学習支援を行う「LXP(学習体験プラットフォーム)」を全社的に展開し、個々の成長目標に沿ったパーソナライズ学習を可能にしました。さらに、スキルレベルに応じた「デジタルスキル標準(3層構造)」を策定し、専門スキルや実践力を体系的に育成しています。
成果:
2022年度には約14万人が研修を受講。2024年度末までに9.8万人のデジタル人材育成を目標とし、特に高度なAI・データサイエンススキルを持つ人材は5万人規模での育成が進行中です。これにより、日立のDX事業「Lumada」の収益は急伸しており、2024年度には売上2.5兆円(189億ドル)超を目指すなど、事業成長に大きく寄与しています。
KDDI株式会社
課題:
通信事業を核としながら、ライフデザイン企業への変革を目指す中で、全社員のDXスキル向上が求められていました。
取り組み:
2020年に「KDDI DX University」を開校。全社員を対象にDXの基礎知識から、AI、IoTなどの専門スキルまでを学べるプログラムを提供。社員が自律的にキャリアを考え、必要なスキルを学ぶ文化の醸成を目指しています。
成果:
全社員のDXに対する意識が向上し、現場主導での業務改善や新規事業提案が活発化しています。
SOMPOホールディングス株式会社
課題:
保険事業に加え「安心・安全・健康プラットフォーム」の実現を目指し、DX・デジタルを軸にした新サービス創出には人材再教育が急務でした。
取り組み:
2017年に「Data Science Bootcamp(データサイエンティスト特別養成コース)」を開始。
その後、2020年以降約6万3000人を対象にDX基礎(AI・ビッグデータ・アジャイル・デザイン思考=ABCD)教育を全社展開。
社員が講師を担う形式に転換し、内製化を進めました。
成果:
新サービス開発や業務効率化に寄与するデジタル推進が定着。
DX企画人材やDX活用人材へのキャリアチェンジも活性化されています。
三菱商事株式会社
課題:
DX推進と既存事業の高度化、新規事業創出に向けて、全社的なデジタルリテラシー向上が不可欠な状況でした。
取り組み:
「MC DX Advancement Program」や全社員向けのデジタル人材育成講座(IT・デジタルリテラシー講座)を導入し、初級から管理職向け応用プログラムまで体系的に提供。応用プログラムまでを提供し、ビジネスとデジタルを結びつけられる人材の育成を進めています。
成果:
中間管理職研修では新規事業案・改善案が実用化検討フェーズへ至っており、営業含む複数部門でDX活用の成果が具体化しています。
【中小企業編】リスキリングの成功事例

リソースが限られる中小企業でも、工夫次第でリスキリングは成功できます。自社の状況に近い事例を参考にしてみてください。
有限会社ゑびや(飲食・サービス業)
課題:
伊勢神宮前のお土産物店として、来客予測の精度を上げ、食品ロス削減と売上最大化を目指していました。
取り組み:
IT業界出身の現経営者(元ソフトバンク勤務)が、POSデータや天候、周辺イベントなどの情報を基に、AIを活用した来客予測システムを自社開発しました。社員がデータ分析のスキルを習得。
成果:
来客予測の精度が大幅に向上し、食品ロスを約70%削減。データに基づいた商品開発や店舗運営が可能になりました。
製造業:石川樹脂工業株式会社 – ロボット導入とEC展開で生産性向上
企業概要:
石川樹脂工業は、プラスチック製の食器雑貨・工業部品・仏具やOEM商品の企画製造販売を行う中小メーカーです。コロナ禍以前から自社ブランド「ARAS」を展開するなど、新規事業にも挑戦しています。
リスキリングの背景:
2020年前後、新型コロナの影響で外国人技能実習生の契約更新が困難となり、人手不足が深刻化する懸念がありました。労働力不足への対策と新事業創出を目的に、経営者主導でデジタル技術の習得(リスキリング)に着手しました。
実施したリスキリングの内容・方法:
まず製造現場の自動化のため産業用ロボットを導入し、従業員がロボットを操作・プログラミングできるよう外部ベンダーの講習支援を受けながら研修を実施しました。併せて、自社ECサイトやAmazonでのオンライン販売に挑戦し、デジタルマーケティング分野のスキルを強化しました。
20代の若手社員を抜擢し外部コーチの指導のもとSNS活用や広告運用を学ばせた結果、わずか3ヶ月でオンライン売上を倍増させることに成功しています。
活用した支援制度・ツール:
リスキリング推進にあたっては、外部の専門家によるコーチングやベンダー企業の研修プログラムを積極的に活用しました。また国や自治体の補助金・支援策も適宜利用しながら、就業時間内に計画的な研修を行い社内DXを加速させました。
販売面では自社HP・Amazonといったデジタルプラットフォームを導入し、SNSマーケティングにも注力しています。
成果:
現在では自社でプログラミングした20台のロボットを稼働させ、生産工程の大幅な効率化を実現しました。オンライン販売強化の成果で自社EC売上は3ヶ月で倍増し、自社ブランド「ARAS」はInstagramフォロワー15万人超の人気商品に成長しています。
オンライン経由の売上比率は全体の3割以上を占めるまでになり、新たな収益の柱となりました。業績好調を背景に従業員の賃金引き上げも実現し、人材育成を通じた成長戦略が評価されて2024年には「日経リスキリングアワード」大賞を受賞しています。
IT・通信:西川コミュニケーションズ株式会社 – 印刷会社のDX人材育成と事業転換
企業概要:
西川コミュニケーションズ(本社:愛知県)は、電話帳など紙媒体の印刷業から出発し、現在はWebサイト制作やデータ分析等も手がける中堅規模の情報サービス企業です。社員数数百名規模ながら、積極的な人材教育による事業多角化に取り組んでいます。
リスキリングの背景:
1990年代後半以降、携帯電話・インターネットの普及により主力の電話帳印刷需要が激減し、従来型ビジネスの限界に直面しました。急激な市場変化に対応し生き残るため、デジタル分野中心への事業構造転換を決断し、社員の大規模なスキル転換に踏み切りました。
実施したリスキリングの内容・方法:
2013年に社内横断の「教育プロジェクトチーム」を発足させ、社員の計画的なスキル習得を支援する仕組みを整えました。具体的には、(1) 今後必要となるITリテラシー等のスキルを定義し、(2) 資格取得や研修受講にかかる費用は全額会社負担としました。さらに (3) 全社員に毎年課題図書を配布して読了後に感想共有させる施策、(4) 希望者を対象に3DCG制作の専門学校に3ヶ月通学させ新事業に備える研修、(5) 全社員にAI関連学習を促す社内キャンペーン等を実施し、社員の自主的な学びを促進しました。
活用した支援制度・ツール:
上記のように、社内制度として資格取得支援(受験料・書籍代の会社負担)や勤務時間内研修の機会提供を行いました。加えて、必要に応じ外部の専門学校・研修サービスとも連携し、最新技術習得を支援しています。経済産業省の事例集にも掲載されるなど、公的機関とも情報共有しながら社内教育体制を強化しました。
成果:
継続的な学びを重視する企業文化の醸成に成功し、実際に多くのデジタル人材の育成・確保が実現しました。例えば社員のITパスポート取得者は220名以上、AI基礎資格であるG検定合格者70名以上、上位資格E資格も3名輩出しています。
またリスキリングの成果として3DCGを用いた新サービス開発やAIマーケティング支援事業を立ち上げ、非印刷系の売上が全社の約50%を占めるまでに成長しました。印刷依存からデジタル事業へと収益構造を転換できた好例と評価されています。
サービス業(旅館業):株式会社陣屋 – 老舗旅館のDX化と人材マルチスキル化
企業概要:
陣屋(神奈川県秦野市)は、大正時代創業で将棋・囲碁のタイトル戦開催でも知られる老舗旅館「鶴巻温泉 元湯 陣屋」を運営する企業です。従業員数50名以下の小規模ながら、地域観光を牽引する革新的旅館経営に取り組んでいます。
リスキリングの背景:
2009年に現経営陣が事業承継した当時、売上高はバブル期の5億円から2.9億円に落ち込み、EBITDAはマイナス6000万円と廃業の危機に陥っていました。紙の台帳管理や属人的な顧客情報管理など昭和型のアナログ業務が非効率の一因で、人材も定着せず離職率が高い状況だったのです。この危機を打開するため、従来のやり方を抜本的に見直し経営のデジタル化と社員のスキル再教育に踏み出しました。
実施したリスキリングの内容・方法:
大型投資を避けるため汎用クラウドサービスを活用して自社で旅館管理システム「陣屋コネクト」を開発し、予約・売上・顧客情報の一元管理を可能にしました。併せて社内SNSを導入し、従業員全員がリアルタイムに情報共有できる環境を整備。
日常業務でデジタル機器に慣れるためのOJTとOFF-JTを組み合わせた研修や、従業員同士が教え合う勉強会を開催し、ITリテラシーの底上げを図りました。経営状況やKPIを全員にオープンにすることで危機感と当事者意識を醸成し、業務改善やマルチタスク化への主体的な参加を促しました。
活用した支援制度・ツール:
社内コミュニケーション基盤として社内SNS(陣屋コネクト内蔵)を活用し、従業員間のノウハウ共有や問い合わせを円滑化しました。またフロント・予約・調理といった職種の垣根を越えて誰でも情報にアクセスできるクラウド環境を整え、従業員が自主的に学べる時間と機会を確保しました。副業推奨や新規事業提案制度も導入し、個々のキャリア成長を支援しています
成果:
従業員と一丸となったデジタル化で生産性が飛躍的に向上し、旅館業界では異例となる週休3日制の導入や従業員給与のベースアップを実現しました。経営も黒字転換し、かつて高かった離職率は大幅に改善。現在では培ったノウハウを活かし他県の旅館運営受託や、自社開発した「陣屋コネクト」の他社提供事業(IT子会社の設立)にも進出しています。倒産危機にあった老舗旅館が地域の観光リーダーへと復活し、リスキリングが業績向上と人材定着・新規事業創出に直結した好例といえます。
まとめと考察
ここで紹介した事例はいずれも、中小企業が経営戦略の中核にリスキリングを据えて成果を上げたケースです。共通するポイントは、経営トップの強いコミットメントの下、社内外の支援策(補助金・助成金、外部研修、ツール導入等)を巧みに活用しながら社員の学び直しを促進したことです。
その結果、人手不足や市場変化という課題に対応しつつ、生産性向上・業績拡大・新事業創出・離職率低下など「三方良し」の効果を生み出しています。リスキリングは大企業だけでなく中小企業にとっても競争力強化と持続的成長の鍵であり、2025年現在、各地でその成功例が着実に増えていると言えるでしょう。
【目的別】DX・IT人材育成のリスキリング事例3選

特にニーズの高い「DX・IT人材育成」に焦点を当てた事例をご紹介します。
楽天グループ株式会社(EC・ITサービス)
目的:
全社的なデータ活用文化の醸成と、データドリブンな意思決定の徹底。
取り組み:
全社のテック職・ビジネス職を横断して参加可能な、3ヶ月間の集中型データ教育プログラム「Data Education」をはじめ、継続学習制度も整備されています。このプログラムでは、BIツール習得のための集中講座から、徒弟制度による知識継承まで、多様な形態での学習支援が運用されています。
ビジネス職からエンジニアまで、役職や職種に関わらず、データ分析の基礎から応用までを学べる環境が提供されています。
成果:
社員のデータリテラシーが向上し、データに基づいたサービス改善やマーケティング施策が日常的に行われるようになりました。
パーソルテクノロジースタッフ株式会社(人材サービス)
目的:
IT分野の未経験者を育成し、ITエンジニアとして正社員就職を支援することで、若年層のキャリア形成とIT人材不足の解消を図ることが目的です。
取り組み:
20〜29歳の若年層を対象にしたITエンジニア育成プログラム「U_29キャリアチェンジプログラム」を実施。プログラムでは、プログラミングやインフラの基礎、ビジネスマナー、就職活動支援(履歴書・面接対策、求人紹介など)を含む実践的な研修を、オンラインまたは集合型で無料提供。未経験からIT業界への正社員就職を目指す内容となっています。
成果:
これまでに多くの未経験者がプログラムを通じてITエンジニアとして正社員就職を実現。就職率は9割を超え、若年層のキャリア支援とIT業界の人材不足解消に貢献しており、同社の人材サービスの新たな柱となっています。
そもそもリスキリングとは?目的と重要性

ここまで具体的な事例を見てきましたが、改めてリスキリングの基本について確認しておきましょう。
リスキリングの定義
リスキリング(Re-skilling)とは、経済産業省によると「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること」と定義されています。(出典:経済産業省「リスキリングとは」)
重要なのは、単に知識を学ぶだけでなく、変化に対応し、新たな価値を創出できるスキルを身につけるという点です。特に、DXの進展により、多くの業務でデジタル技術の活用が不可欠となり、企業が主体となって社員のスキルを再開発する必要性が高まっています。
リカレント教育やOJTとの違い
リスキリングと混同されやすい言葉に「リカレント教育」や「OJT」があります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
* リカレント教育
主に個人が主体となり、一度仕事から離れて大学などの教育機関で学び直すことを指します。学びの期間が長く、体系的な知識を深めることを目的とします。
* OJT(On-the-Job Training)
企業が主体となる点はリスキリングと同じですが、OJTは既存の業務を遂行しながら、実務を通じてスキルを習得する手法です。主に今ある業務の効率化や習熟度向上を目的とします。
これに対し、リスキリングは企業が主体となり、将来的に必要となる新しいスキルを、戦略的に習得させる取り組みです。必ずしも既存の業務の延長線上にあるとは限らず、全く新しい分野のスキルを学ぶことも含まれます。
企業がリスキリングを導入する進め方と成功のポイント

自社でリスキリングを導入する際の具体的なステップと、成功させるための重要なポイントを解説します。
導入のための具体的な5ステップ
1. 経営戦略と必要な人材像の明確化
まず、自社が今後どのような事業を展開し、どのような価値を提供していきたいのかという経営戦略を明確にします。その上で、戦略実現のために「どのようなスキルを持つ人材が、何人必要なのか」という具体的な人材像を定義します。
2. 現状スキルの可視化とギャップ分析
次に、社員が現在持っているスキルを把握(可視化)します。スキルマップやアセスメントツールを活用すると効果的です。そして、ステップ1で定義した理想の人材像と現状との間に、どのようなスキルのギャップがあるのかを分析します。
3. 教育プログラムの設計と選定
ギャップを埋めるための具体的な教育プログラムを設計します。e-ラーニング、外部研修、社内勉強会、メンター制度など、様々な手法を組み合わせます。自社で開発するのか、外部のサービスを利用するのかも検討しましょう。
4. 対象者の選定と学習環境の整備
プログラムの内容に合わせて対象者を選定します。全社員を対象とするのか、特定の部署や階層から始めるのかを決定します。同時に、社員が学習に集中できる環境を整えることが重要です。業務時間内に学習時間を確保したり、学習をサポートする体制を整えたりします。
5. 効果測定と継続的な改善
プログラム実施後は、スキル習得度や行動の変化、業績への貢献度などを測定し、効果を検証します。アンケートや面談で受講者のフィードバックを集め、プログラムの内容を継続的に改善していくことが成功の鍵です。
成功に導く3つのポイント
1.経営層の強いコミットメント
リスキリングは短期的なコストがかかるため、現場任せにすると頓挫しがちです。経営層が「リスキリングは未来への投資である」という強いメッセージを発信し、全社的な取り組みとして推進することが不可欠です。
2.従業員の学習意欲を引き出す仕組み
「学んだスキルがどうキャリアに活かせるのか」を明確に提示することが重要です。スキル習得を人事評価や昇進・昇格と連動させたり、新たな挑戦の機会を与えたりすることで、社員の学習モチベーションを高めることができます。
3.「学び」を称賛し、挑戦を許容する文化の醸成
学習の成果だけでなく、学ぶ姿勢そのものを評価する文化を作りましょう。また、リスキリングで得たスキルを活かして新しいことに挑戦した結果、たとえ失敗したとしても、それを責めるのではなく、挑戦したことを称賛する風土が、社員の積極的な学びと実践を後押しします。
リスキリングで活用できる国の補助金・助成金制度

リスキリングの導入にはコストがかかりますが、国や自治体の支援制度を活用することで負担を軽減できます。代表的な制度をご紹介します。
1.人材開発支援助成金(厚生労働省)
企業が従業員の職業能力向上のために実施する研修・訓練にかかる費用や、その間の賃金を国が支援する制度です。
・対象となるのは「雇用保険に加入している労働者」です。
・OJT(職場内訓練)・OFF-JT(職場外研修)のどちらも対象になります。
🧩 主なコース(支援メニュー)
企業のニーズに応じて、下記のコースが用意されています:
| コース名 | 内容 |
| 人材育成支援コース | OFF-JTやOJTによるスキルアップ訓練を支援 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 従業員に教育訓練休暇や職業能力評価制度を導入した企業を支援 |
| 人への投資促進コース | リスキリングや資格取得など戦略的な学び直しを支援 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 新分野展開や業態転換のための訓練費用を支援 |
💰 助成額と助成率
| 項目 | 一般企業 | 中小企業 |
| 賃金助成 | 1人1時間あたり 800円 | 400円 |
| 経費助成率 | 訓練経費の45% | 30% |
| OJT助成 | 1人1コースあたり 20万円 | 11万円 |
📅 手続きの流れと期限
計画段階
- 訓練開始の1〜6か月前までに計画届を提出
- 申請企業は雇用保険適用事業所であることが必要
実施・報告段階
- 訓練終了の翌日から2か月以内に支給申請
- 給与や手当を3か月間支給した後、5か月以内に申請
🧑🏫 職業能力開発推進者の役割
企業には1名以上の「職業能力開発推進者」を選任する必要があります。
主な役割は:
- 訓練計画の立案・管理
- 従業員への相談や訓練の実施支援
🔍 訓練の種類と条件
| 訓練種別 | 要件 |
| OFF-JT(職場外) | 10時間以上の研修で、座学や外部講師などが実施 |
| OJT(職場内) | 上司や先輩の計画的な指導付き訓練 |
| 組み合わせ型 | 両方を組み合わせた内容も対象可 |
📄 経費助成の条件と対象
助成対象となる経費:
- 講師謝金
- 旅費(講師や受講者の移動費)
- 教材費
- 施設費(会場使用料)
助成対象外の経費:
- 食費
- 自動車代(ガソリン代など)
- 再利用可能な備品(PCなど)
📤 申請方法
- 郵送・窓口・電子申請(GビズID使用)のいずれか
- 2023年6月から電子申請(雇用関係助成金ポータル)に対応
- 社会保険労務士等による代理申請も可能
📌 まとめ
「人材開発支援助成金」は、企業が従業員のスキルアップや再教育を行う際に、経費と人件費を国がサポートする制度です。
特に以下のような場面で活用できます:
- 新人研修や管理職研修の実施
- 新規プロジェクトに向けたリスキリング
- 社内DX化に伴うIT研修
- キャリアアップを目的とした資格取得支援 など
2.リスキリング・キャリアデザイン応援事業(東京都)
この事業は、東京都が都内の中小企業を対象に、従業員のリスキリング(学び直し)やキャリアデザインの取り組みを支援するものです。企業が人材育成の制度を整えることで、生産性の向上と持続的な成長を目指します。
主な支援は以下の2つです。
👨💼 ① 専門家の派遣(無料)
- 対象:都内中小企業等
- 回数:1社につき 最大2回
- 時間:1回あたり 1〜2時間
- 内容:
- 社会保険労務士などの専門家が訪問
- 人材育成の方針
- リスキリング制度の整備
- 社内でスキルを活かす制度づくり
- 上記について、企業の実情に合わせたアドバイスを提供
💰 ② 奨励金の支給(最大40万円)
- 金額:1社あたり 最大40万円
- 条件:
- 初回の専門家派遣を受けた後に申請可能
- 申請時には必要書類の提出が必要
- 奨励金額は実施内容により 20万円 or 40万円
- 振込時期:請求書に不備がなければ、受領日から おおむね1か月以内に指定口座へ振込(東京しごと財団名義)
✅ 奨励金の支給要件(主な条件)
申請から事業終了報告まで、以下の条件を全期間満たしている必要があります。
- 都内で事業を営む中小企業等であること
- 本社または主たる事業所(支店・営業所)が都内にある
- 都内に勤務する常時雇用の労働者が 1人以上かつ6か月以上継続雇用
- 就業規則を作成し、労基署に届出済みであること
- 労働法規を遵守していること
- 都税に未納がないこと
- 同種の助成金を過去に受給していないこと
📅 エントリー期間(申込期間)
| 回 | 期間 |
| 第1回 | 令和7年7月7日(月)10:00 ~ 令和7年7月31日(木)17:00 |
| 第2回 | 令和7年10月7日(火)10:00 ~ 令和7年10月31日(金)17:00 |
📝 まとめ
東京都のこの制度は、人材育成に本腰を入れたい中小企業にとって、制度設計と費用支援の両面から活用できる貴重な支援策です。特に、従業員のスキルアップやキャリア形成を企業として支援したい場合には、専門家の知見と奨励金の活用が大きな後押しになります。
3.DXリスキリング助成金(東京都)
東京都の中小企業が、従業員のデジタルスキル(DX)を高めるための研修を実施した際に、その費用を一部補助する制度です。
*DXとは、業務の効率化や競争力強化のためにIT・デジタル技術を活用することを指します。
✅ 対象となる企業は?
次のような条件を満たす中小企業・小規模企業が対象です:
- 東京都内に本社または主たる事業所がある
- 中小企業の定義に当てはまる(資本金や従業員数に制限あり)
- みなし大企業は対象外
- 労働関係法令を守っている
- 過去5年以内に重大な法令違反がない
🎓 助成対象となる研修は?
以下のような研修が対象です:
- DXに関連するスキルアップを目的とした研修
- 研修形式は「レディメイド(既製)研修」または「オーダーメイド研修」
- 事前に金額が決まっている(見積り明細が明確なこと)
- 通常業務とは区別された「OFF-JT」(職場外研修)であること
❌ 対象外となる研修例
- 趣味や教養を目的とする研修
- 資格試験対策・法令義務研修
医業・医療行為に関連する研修
👥 対象となる従業員(受講者)は?
- 申請企業に所属する正社員・契約社員など
- 東京都内の事業所に常時勤務している
- 研修の8割以上を受講することが条件
💰 助成される内容と金額
- 対象経費の4分の3が助成
- 対象経費:受講料・教材費・登録料
- 対象外:交通費、設備費、消費税など
上限額
- 1人1研修あたり最大75,000円
- 1社あたり最大100万円まで
📝 申請スケジュールと流れ
| ステップ | 内容 |
| 1. 申請 | 研修開始の1か月前までに交付申請書を提出(紙または電子) |
| 2. 審査・決定 | 東京都から交付決定通知が届く |
| 3. 研修実施 | 対象のDX研修を実施 |
| 4. 実績報告 | 研修終了後2か月以内に報告書を提出 |
| 5. 助成金請求 | 額の確定通知後1か月以内に請求。不備があると支給取消の可能性あり |
📌 まとめ
この助成金は、DX人材を育成したい東京都内の中小企業にとって、研修費用の負担を大幅に軽減できる貴重な制度です。
特に、社内でDXを進める上で「社員にITリテラシーやデジタルスキルを習得させたい」といったニーズがある企業にとっては非常に有用です。
4.事業内スキルアップ助成金(東京都)
東京都内の中小企業や団体が、自社の従業員向けに社内で実施する短時間のスキルアップ研修に対して、東京都が費用を助成する制度です。
・社内で行う集合研修(OFF-JT)が対象。
・主に業務に直結する専門的スキル・知識を習得させることが目的です。
✅ どんな企業が申請できる?
助成金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります:
- 東京都内で事業を営む中小企業または団体
- 資本金・従業員数が中小企業基準に合致
- 重大な法令違反が過去5年間にない
- 労働関連法令を順守している
🎓 対象となる研修の条件
以下の条件を満たす研修のみが助成対象です:
- 社内で実施される集合型研修
- 目的が「職務に関連した専門的スキルや知識の習得」
- 研修時間は1回あたり3時間以上10時間未満
- 受講者の80%以上が出席すること
❌ 助成対象外となる研修の例:
- 通信教育
- 社会人としての一般知識(例:ビジネスマナーなど)
- 趣味・教養目的の講座
- 法令で義務づけられた教育(例:安全衛生教育)
👥 受講する従業員の条件
助成対象の受講者にも以下のような要件があります:
- 申請企業の正社員や契約社員などの従業員
- 常時勤務している事業所が東京都内
- 研修の80%以上に出席していること
💰 助成される金額と上限
助成額は以下の式で計算されます:
受講者数 × 研修時間数 × 760円
(例:5人が4時間の研修を受けた場合 → 5×4×760=15,200円)
1社あたりの助成上限は150万円までとなっています。
📅 申請スケジュールと手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
| ①申請 | 研修開始の1か月前までに「交付申請書」を提出(紙または電子) |
| ②交付決定通知 | 審査後に東京都から通知が届く |
| ③研修実施 | 指定の研修を実施(労働時間内・業務命令で行うこと) |
| ④実績報告 | 研修終了日から2か月以内に報告書を提出 |
| ⑤助成金支給 | 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる |
📌 注意点
- 研修中の出席簿や実施中の写真が必要になります(報告時に提出)
- 提出書類に不備があると再提出や助成取消の可能性あり
- 申請を取り消したい場合は、交付決定から14日以内に手続きが必要
- 研修内容や日時に変更がある場合は、研修開始前までに申請
📝 まとめ
この制度は、東京都内の中小企業が自社で行うスキルアップ研修にかかる費用の一部を助成するものです。対象は比較的短時間の集合研修で、実務に直結したスキル習得を目的とした内容が重視されます。
「DX」「接客スキル」「現場作業の高度化」「業務効率化」などのテーマでの研修にも活用しやすく、少額でも従業員教育に取り組みたい企業にとっては有効な支援策です。
5.事業外スキルアップ助成金(東京都)
東京都内の中小企業・小規模事業者が、従業員のスキルアップのために社外研修を受けさせる場合に、研修費用の一部を東京都が補助してくれる制度です。
・「事業外」という名前の通り、業務時間外や外部機関での研修が対象になります。
・従業員の専門知識や技能の向上を目的とした研修であれば、助成対象になります。
✅ どんな企業が対象?
・東京都内に事業所を持つ中小企業または小規模企業
(例:小売・飲食業の場合、資本金5,000万円以下かつ従業員50人以下)
・過去5年間に重大な法令違反がないこと
🎓 どんな研修が対象?
- 外部の教育機関が実施する公開研修
- 形式は集合研修またはeラーニング
- 業務に必要なスキルや専門知識の習得が目的
✖ 対象外の研修:
- 通信講座や国・自治体主催の研修
- 趣味や一般教養、法令で義務付けられた研修
👨🏫 対象になる従業員は?
- 申請企業の従業員
- 都内の事業所に常時勤務している人
- 研修時間の8割以上を受講した人
💰 どのくらい助成されるの?
- 小規模企業:研修費の2/3、上限25,000円/人
- 中小企業:研修費の1/2、上限25,000円/人
- 企業全体での助成上限は150万円まで
助成対象となる費用:
- 受講料
- 教材代
- 登録料
(※交通費や設備費、消費税などは対象外)
🗓️ 申請期間と流れ
申請期間:令和7年3月1日~令和8年2月28日
研修開始の1か月前までに申請が必要。研修後、実績報告書を提出 → 審査後、助成金が振り込まれます。
📝 必要書類
- 交付申請書
- 助成対象額計算書
- 研修計画書など
提出書類は控えを残しておく必要があります。不備があった場合、再提出も必要になることがあります。
📌 まとめ
この助成金は、従業員のスキルアップを外部研修で行いたい東京都の中小企業にとって、研修費用の負担を軽減できる制度です。うまく活用すれば、社員教育にかかるコストを抑えつつ、組織力の底上げが図れます。
6.育業中スキルアップ助成(東京都)
育児休業(=育業)中の従業員がスキルアップのために受講する研修費用を、東京都が企業に助成する制度です。
・育児休業中でもキャリアの断絶を防ぎ、復帰後に即戦力として働けるようにすることが目的です。
・助成金は、企業が負担する研修の受講料や教材費、託児サービス費用などが対象になります。
✅ 対象となる企業は?
次の条件を満たす企業であれば、中小企業・大企業ともに対象です:
- 東京都内で事業を営んでいる
- 過去5年間に重大な法令違反がない
- 労働関係法令を遵守している
🎓 対象となる研修とは?
以下のような研修が助成対象です:
- 教育機関が実施する公開研修
- 集合研修またはeラーニング
- 育児休業中に受講するもの
❌ 助成対象外の研修
- 趣味や教養を目的とした内容
- 法令で義務付けられた研修(例:安全講習)
申請企業と資本関係がある教育機関が提供する研修
👶 助成対象の従業員(受講者)は?
以下の条件を満たす従業員が対象になります:
- 申請企業に所属する正社員・契約社員など
- 育児休業(育業)を4週間以上取得していること
- 育業期間中に研修を受講
- 育業前に勤務していた事業所が東京都内
💰 助成対象となる費用と金額
対象となる費用:
- 受講料
- 教材費
- 登録料
- 託児サービス費用
✖ 助成対象外:
- 交通費や設備購入費など
助成金額:
- 中小企業:対象経費の3分の2
- 大企業:対象経費の2分の1
- 1社あたりの上限:100万円
📅 申請スケジュールと手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
| ①申請 | 研修開始の1か月前までに「交付申請書」を提出 |
| ②交付決定通知 | 審査後、東京都から交付決定が通知される |
| ③研修実施 | 育児休業中に研修を受講(eラーニングもOK) |
| ④実績報告 | 研修終了後に実績報告書を提出し助成金請求 |
| ⑤助成金の受領 | 審査後、助成金が支給される |
📄 必要な提出書類
- 交付申請書
- 助成対象額計算書
- 研修計画書
- 育児休業の期間がわかる書類
- 提出書類の控えは保管が推奨されています
📌 まとめ
この助成金は、育児休業中の従業員のキャリア維持と復帰支援を目的とした制度です。
企業側にとっては、育業中の従業員がブランクなく職場復帰できるよう支援できるメリットがあります。特に、復職後にDXスキルやマネジメント力が必要な職場にとっては非常に有効です。
8.リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(経産省)
これは、働きながら新たなスキルを学んで転職・キャリアアップを目指す人を、国(経済産業省)が金銭面と学習・就職支援の両面でサポートする制度です。個人向け支援事業になります。
📌 支援の対象者は?
現在働いている人(在職者)で、新しいスキルを学び直して、より良い仕事に転職したいと考えている人。
💡 どんな支援が受けられるの?
支援は大きく分けて 3つ あります:
- キャリア相談
- 自分に合ったスキルや職業をプロが一緒に考えてくれます。
- 専門のキャリアカウンセラーがサポート。
- リスキリング(学び直し)講座の受講
- IT・デジタルスキル、ビジネススキルなどの講座を受講可能。
- 費用の最大70%が補助されます。
- 補助の詳細:
| 内容 | 金額または割合 |
| 講座修了 | 受講費用の1/2(上限40万円) |
| 転職後1年継続して働いた場合 | 追加で1/5(上限16万円) |
- 転職支援
- 履歴書の添削、面接対策、企業紹介など。
- 実際の転職までサポートしてもらえます。
🏫 どうやって利用するの?
- 公式サイトから補助事業者を選ぶ
→ 各事業者が提供する講座・支援メニューが違うので、自分に合ったところを選びます。 - 事業者と相談し、講座を受講・転職活動を行う
- 条件を満たすと補助金が支給される
📝 まとめ
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 現在働いている人(在職者) |
| 支援内容 | キャリア相談、講座受講、転職支援 |
| 補助金 | 最大56万円(講座費用の1/2+就職後1/5) |
| 手続き | 公式サイトから補助事業者を選んで相談・受講 |
補助金・助成金利用のポイント・注意点
- 事前申請が必要な制度が多い(後払い方式)
- 認定研修機関・指定講座のみが対象となることがある
- 受講後の修了証提出や実績報告が必要な場合も多い
- 自治体制度は年度単位で更新されるため、定期的な確認が重要
まとめ
本記事では、企業のリスキリング事例を中心に、その定義や導入の進め方、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
✅リスキリングは大手から中小まで、多くの企業で成功事例が生まれている
✅成功の鍵は、経営戦略と連動させ、社員の意欲を引き出す仕組みを作ること
✅導入ステップを明確にし、補助金なども活用しながら計画的に進めることが重要
リスキリングは、単なる社員教育ではありません。変化の激しい時代を乗り越え、企業が持続的に成長していくための経営戦略そのものです。
まずはこの記事で紹介した事例を参考に、自社であればどのような取り組みができそうか、小さな一歩から検討を始めてみてはいかがでしょうか。それが、未来の貴社を支える大きな力になるはずです。