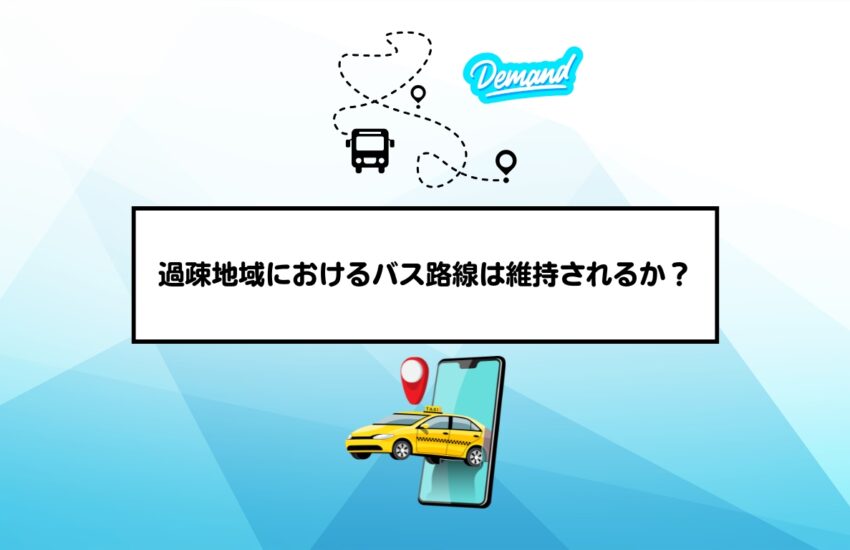少子高齢化と人口減少の波は、都市と地方のあらゆるバランスを変えつつあります。中でも大きな影響を受けているのが、過疎地域の公共交通網です。日々の通院、買い物、通学、そして社会参加——こうした日常の営みを支える「路線バス」は、生活インフラとして欠かせない存在である一方で、その多くが採算割れに陥り、財政依存型の維持が続いています。
実際に、過疎地で運行されている路線バスのおよそ7割が赤字という現実があり、自治体にとっても持続可能性に限界が見え始めているのが現状です。では、この交通危機をどのように打開すればよいのでしょうか?
本記事では、「補助金依存からの脱却」をキーワードに、デマンド交通、貨客混載、MaaS導入など、全国で進む多様な取り組みとその成果を具体的な事例をもとに紹介し、持続可能な地域モビリティの未来を考察します。まずは、利用者の予約や需要に応じて運行される、柔軟な交通サービスであるデマンド交通について述べたいと思います。
デマンド交通とは?

デマンド交通(Demand-Responsive Transport:DRT)は、予約に応じ小型車両が経路・時刻を変えるオンデマンド型の乗合公共交通です。これは従来の定時・定路線制のバスや鉄道とは異なり、必要なときに必要な場所へ運行される点が特徴です。タクシーとバスの中間的な存在とも言え、特に地方自治体や過疎地域での公共交通手段として注目されています。
例えば、点在する集落を効率的に結ぶために、「予約制・随時運行型」のバスや乗合タクシーを導入することで、回送距離や空車走行(空走)を削減できます。
これにより、従来の固定路線方式では運行が困難だった利用者の少ない地域でも、効率的にサービスを提供でき、運行コストの抑制が実現されています。実証実験などでも、このような成果が報告されています。
デマンド交通の特徴
デマンド交通の最大の特徴は、基本的に予約制となっており、利用者は事前に電話や専用アプリを通じて乗車を申し込みます。
運行ルートや乗降場所は固定されておらず、利用者の希望に応じて柔軟に変動します。これにより、交通アクセスの不便な地域でも利便性の高い移動が可能になります。
また、運行形態にも多様性があり、大きく分けて次の2種類があります:
1.ドア・ツー・ドア型:自宅から目的地までを直接結ぶ個別対応型
2.バス停・ポイント集約型:集落や拠点間を効率的に結ぶ乗合型
このようなデマンド交通は、特に高齢化や過疎化が進行している地域、あるいは既存の公共交通が存在しない「交通空白地帯」での導入が進んでいます。
予約制の乗合タクシーなどのデマンド交通のメリット
1.公共交通の維持・強化
デマンド交通は、従来の路線バスでは採算が取れない地域でも、効率的に運行できる手段として有効です。特に利用者が少ない時間帯や曜日であっても、需要に応じた柔軟な運行が可能なため、交通空白地帯における公共交通の維持・強化に貢献します。
2.利便性の向上
高齢者や自家用車を持たない住民にとって、デマンド交通は日常の移動を支える重要な手段です。乗降場所の柔軟さや予約制による運行は、個々の生活スタイルに合わせた利用を可能にし、「いつ来るかわからない」といった不安を軽減しながら、移動の見通しを立てやすくします。
3.環境・経済面での効果
需要に応じた最適な運行により、無駄な空車走行や回送が削減され、CO₂排出量の抑制につながります。同時に、燃料コストの削減や、自治体による交通費用の圧縮も期待できます。環境負荷の軽減と持続可能な地域交通の実現に向けて、大きな効果が見込まれています。
デメリットと課題
1.運行効率には限界がある
デマンド交通は柔軟な運行が可能である一方で、利用者の居住地が広範囲に分散している場合、配車の調整やルート設定が複雑になり、効率が低下することがあります。また、朝夕の通勤・通学など、利用が集中する時間帯には対応が追いつかず、待ち時間が長くなるなどの課題が発生することもあります。
2.利用者のITリテラシーに依存する面がある
多くのデマンド交通サービスは、スマートフォンのアプリやWebサイトを通じて予約を受け付けていますが、こうした仕組みはIT機器の操作に不慣れな高齢者にとっては利用のハードルとなる場合があります。誰もが安心して利用できるよう、電話による予約受付を補完手段として整備することが重要です。
3.コスト面でのハードルも存在
一見効率的に見えるデマンド交通ですが、システム構築や専用車両の導入など、初期投資にかかる費用は小さくありません。さらに、運行管理や人件費などのランニングコストも継続的に発生します。利用者数が一定の水準に満たない場合には、採算が合わず、継続的な運用が困難になるリスクも伴います。
今後の展望
今後は、AIやIoTなどの先端技術を活用し、利用者の予約状況や交通需要に応じて最適なルートを自動生成できる仕組みの構築が目指されています。これにより、より効率的かつ柔軟な運行が可能となり、サービス全体の質の向上が期待されます。
また、MaaS(Mobility as a Service)との連携を強化することで、鉄道・バス・タクシーなど複数の交通手段を一体化させた、シームレスで快適な移動体験の提供を実現していきます。
加えて、これらの取り組みを支えるために、関連法制度の整備や助成制度の充実といった政策的な支援が進められることも期待されており、今後のサービス普及と持続的な展開に向けた環境整備が重要な鍵となります。
乗合タクシーなどのデマンド交通|国内成功事例
ここでは、各地で導入が進むデマンド交通の具体的な事例をご紹介します。
導入例1:滋賀県米原市「まいちゃん号」予約制の乗合タクシーサービス
米原市全域をカバーする、予約制の乗合タクシーサービス
滋賀県米原市では、市民の移動支援および地域公共交通の充実を目的として、予約制乗合タクシー「まいちゃん号」を市内全域で運行しています。坂の多い地域や高齢化が進む中山間地など、既存の公共交通が行き届きにくいエリアを含め、多くの市民の日常的な移動手段として活用されています。
■ 基本情報
・運行方式:区域運行方式(完全予約制)
・運行エリア:米原市全域
・運行時間:毎日 6:00〜19:30(毎時00分・30分に発車 ※一部地域除く)
・運休日:年中無休
・車両タイプ:小型タクシー(定員4名)
・予約方法:インターネット、電話、FAXに対応
- ICTの活用:
・2021年10月:インターネット予約システムを導入
・2022年4月:キャッシュレス決済(PayPay)対応開始
■ 主な特長
・利便性:30分間隔の運行で、米原駅や近江長岡駅、公共施設・医療機関など広範囲をカバー。
・柔軟性:2人以上の乗合利用で「のりあい料金」が適用され、割安に利用可能。
・広域対応:市外の医療機関等にも、追加料金で直接アクセス可能(要事前申告)。
■ 今後の展望
・利便性のさらなる向上を目指し、利用者の声をもとに停留所や運行体制の見直しを継続
・予約締切時間の短縮により、直前でも利用しやすい体制へ移行
・地域密着型MaaSの先進事例として、他自治体との連携やモデル展開も期待されています
事例2: 滋賀県東近江市の移動を支える「ちょこっとバス・ちょこっとタクシー」
滋賀県東近江市では、市民一人ひとりの移動をより便利に、そして身近にするために、2つの公共交通サービス「ちょこっとバス」と「ちょこっとタクシー」を展開しています。いずれも市の委託によって運行されており、地域の実情に合わせた公共交通として、日常生活に密着した運用がなされています。
■ 「ちょこっとバス」:定時・定路線のコミュニティバス
「ちょこっとバス」は、通学・通院・買い物など、日常の移動に対応する定時・定路線型のコミュニティバスです。市内10路線を網羅し、利便性の高い移動手段として幅広い年代に利用されています。
主な目的地の例:
・医療機関:東近江総合医療センター、湖東記念病院 など
・観光地:永源寺、百済寺、マーガレットステーション など
・その他:市内の生活施設、公園、行政施設など
■ 「ちょこっとタクシー」:完全予約制の乗合型デマンド交通
「ちょこっとタクシー」は、必要なときだけ運行する完全予約制の乗合型交通です。バスではなくタクシー車両を使用しており、小回りが利く点が特長です。
主な概要:
・運行方式:予約があった便のみ運行(予約のない便は運休)
・予約方法:出発の30分前までに電話予約(早朝便は前日まで)
・運行エリア:市内各地(愛東・湖東、五個荘、蒲生、小脇・建部など)に路線を展開
🔄 柔軟な組み合わせで移動をより便利に
「ちょこっとバス」と「ちょこっとタクシー」は、乗り継ぎ制度により相互利用が可能です。たとえば、幹線部分をバスで移動し、タクシーで自宅や目的地付近までアクセスするといった使い方も可能です。
また、路線図や時刻表は市のウェブサイトで簡単に確認でき、利便性向上に向けた取り組みが継続されています。
✨ まとめ
「ちょこっとバス・ちょこっとタクシー」は、東近江市が直面する高齢化や地域間の交通格差といった課題に対し、きめ細やかに対応する公共交通モデルです。定時運行のバスと、柔軟に対応できるオンデマンド型タクシーを組み合わせることで、市民の誰もが「ちょっと便利」に移動できる環境を実現しています。
事例3:【福井県越前市】オンデマンドバス × 定額タクシーのハイブリッド運行
福井県越前市では、地域内の交通拠点の接続不足や高齢者の移動課題、観光地へのアクセスの弱さなど、複合的な交通問題に対応するため、オンデマンドバスと定額タクシーを組み合わせたハイブリッド型の地域交通サービスを導入しています。
🧩 課題背景
1.公共交通拠点間の接続不足
北陸新幹線延伸により、新駅「南越駅(仮称)」が開設予定となる一方、既存の中心駅であるJR武生駅との間に直接的な交通手段がなく、連携の確保が課題に。
2.観光地へのアクセスの不十分さ
新駅・JR駅から寺院、温泉、体験施設などの観光地への二次交通が整備されておらず、観光客の回遊性が低い状況にありました。
3.高齢者や非自動車保有者の交通手段不足
高齢者や公共交通に依存する住民にとって、日常生活や通院・買い物の移動が不便であり、地域内の移動支援が求められていました。
💡 主な施策
1.ハブ&スポーク方式の導入
・西エリアのハブ:JR武生駅
・東エリアのハブ:ショッピングセンター「武生楽市」
それぞれを中心に据え、周辺地域(スポーク)との接続には定額タクシーを活用。観光地や住宅地への柔軟なアクセスを確保しています。
2.オンデマンドバスの運行(MONET Technologiesとの連携)
・MONET社の配車システムを活用し、アプリまたは電話で予約可能
・空席がある場合は、予約なしでも乗車可能
・小型バス(定員12名/22人乗り仕様)を無料で運行
・高齢者やスマートフォン非利用者にも配慮した受付体制を整備
3.定額タクシーの導入
・各エリアに10カ所以上の乗降ポイントを設置
・1区間300円のチケット制(事前購入)を採用
・タクシー事業者の事務負担軽減にも配慮した設計
4.利用者アンケートと将来展望
・乗務員による対面ヒアリング形式のアンケートで、利用者の声を丁寧に収集
・今後は「1日乗車券」や「予約システムとの連携強化」など、新たな施策を検討中
🎯 これまでの成果
1.利便性の向上
オンデマンドバスの導入により、市内移動が柔軟かつ便利になり、高齢者や観光客など自家用車を持たない層から高い評価を獲得しています。
2.運行の効率化
混雑時間帯・人気ルートでの乗合促進によって、運行コストと車両稼働の効率化を実現。実証を通じて、将来的な持続可能な運行体制に向けた貴重なデータが蓄積されています。
3.地域交通と観光施策の連動
地域交通の課題を解決しながら、観光地へのアクセス改善による誘客促進も見込まれます。本事業は、交通と観光を融合させたMaaSモデルの先進事例として高い注目を集めています。
📝 今後の展望
実証結果を踏まえた本格運用の可否判断が進められており、あわせて以下のようなサービス拡充も検討されています:
・バスとタクシーのシームレスな予約連携
・観光客・市民共通の1日乗車パスの導入
・他自治体への展開も視野に入れた地域MaaSのモデル化
こうした取り組みにより、越前市は地域に密着した持続可能な公共交通の構築に向け、大きな一歩を踏み出しています。
貨客混載・マルチユース車両の活用

貨物輸送と旅客輸送を同時に行うことで、車両稼働率を向上。定期便の空きスペースに地元産品や宅配物を積載し、新たな収益源を確保できます。国土交通省の支援制度でも貨客混載の導入を推進しており、車両購入補助や運行支援が受けられます。貨客混載・マルチユース車両は特に、過疎地・山間部などで路線バスや物流便の維持が難しい地域において、交通・物流の効率化と持続可能性を両立する手段として注目されています。
貨客混載とは?
定義:1台の車両に「人」と「荷物」を一緒に載せて運ぶ運用方式。
例:午前は高齢者を病院に送迎し、午後はスーパーの商品を地域に届ける。
タイプの例:
・路線バスで宅配荷物を一緒に運ぶ
・郵便車両に地域住民を同乗させる
・デマンド交通で買い物代行や配送も同時に担う
マルチユース車両とは?
定義:用途を限定せず、複数の目的に応じて使える車両(旅客・貨物・行政サービスなど)
例:午前は通学バス、午後は買い物代行、夜は巡回診療などに使う。
メリットとデメリット
| ✅ メリット | 説明 |
| 1. 運行コストの削減 | – 複数用途を一台でまかなうことで、車両・人件費の削減が可能- 補助金に依存しない、自立可能な運行モデルに近づける |
| 2. 過疎地域での持続可能な交通手段 | – 住民の「移動の権利」を確保しつつ、生活インフラ(物流)を維持できる- 高齢化による免許返納者の支援手段としても有効 |
| 3. 地域の事業者との連携による相乗効果 | – 地元スーパー・薬局・診療所と連携し、地域全体の生活利便性を向上- 配送会社や郵便局との提携により、物流網を維持 |
| ⚠️ デメリット・課題 | 説明 |
| 1. 法制度の制約 | – 道路運送法・貨物自動車運送事業法など、用途ごとの許認可が必要- 特区指定が必要な場合もあり、一部地域では制度上のハードルが高い(例:国交省) |
| 2. 実務面での運用調整が難しい | – 時間帯・積載量・ルート設計など、旅客と貨物の両立に工夫が必要- 荷物の取り扱い・管理には人員や技術が求められる |
| 3. 利用者の理解と協力が不可欠 | – 「人と物が一緒に乗る」ことへの心理的抵抗感があるケースも- 地域住民や関係機関との合意形成が必須 |
貨客混載・マルチユース車両|成功事例(日本国内)
◆ 宮崎交通 × ヤマト運輸「客貨混載」事業(宮崎県)
宮崎交通とヤマト運輸は、宮崎県北部の延岡市-高千穂町、諸塚村-日向市を結ぶ2路線で、「客貨混載」事業を開始しました。これは、地域の路線バスで人と宅急便の荷物を同時に運ぶ取り組みで、過疎化や高齢化によって課題となっていたバス路線の維持と物流の効率化を同時に解決することを目的としています。
具体的には、バスの一部座席を荷物スペースに改造した専用車両を導入し、ヤマト運輸の荷物を乗客とともに運ぶ体制を整えました。これにより、高千穂町では県内全域への当日配送が可能となり、諸塚村・美郷町では集荷締切時間が15時から17時に延長されるなど、地域住民にとって宅急便サービスの利便性が向上しています。
また、宮崎交通にとってはバスの空きスペースを活用することで新たな収益源となり、ヤマト運輸にとってはトラックの走行距離が短縮されることでCO₂排出削減にもつながっています。この取り組みは、公共交通と物流を連携させた地域密着型の新しいモデルとして注目されており、持続可能な社会インフラの構築に貢献しています。
貨客混載・マルチユース車両|今後の展望
今後の取り組みとしては、「貨客混載」や「マルチユース車両」のさらなる活用が検討されています。これらの仕組みは、物流や移動の効率化を図るうえで、地域における移動サービスの柔軟性を高める鍵になると考えられています。
また、これらの取り組みを支えるためには、法制度の柔軟化や特区制度の活用が重要な要素とされています。地域の実情に応じたルール整備が進むことで、よりスムーズなサービスの展開が期待されています。
さらに、自動運転技術との連携も視野に入れられており、無人配送や移動支援などを通じて、地域住民の利便性を向上させる新たな手段としての自動運転車両の導入が現実味を帯びてきています。
加えて、MaaS(Mobility as a Service)との組み合わせによる「地域生活支援サービス」の展開も構想されています。この構想では、単なる交通手段の提供にとどまらず、買い物や通院といった日常生活全般を包括的に支援する仕組みの構築が目指されています。
MaaS・デジタル予約システムの導入

「MaaS(Mobility as a Service)」や「デジタル予約システムの導入」は、近年進展する交通・移動サービスのデジタル化を象徴する重要な取り組みです。スマートフォンアプリや電話予約など複数の手段を通じて利用者のデータを収集・可視化することで、AIによる需要予測や効率的な配車計画が可能となります。これにより、運行の無駄を抑えつつ、利用者の利便性を高めることができます。
特に地方部や過疎地域では、交通手段の確保が深刻な課題となっており、高齢者や観光客など多様なニーズに応える移動支援としても、こうしたデジタル技術は現実的かつ有効なソリューションとして期待されています。
MaaS(Mobility as a Service)とは?
MaaS(Mobility as a Service)とは、直訳すると「サービスとしての移動手段」を意味します。これまでバラバラに使っていた電車・バス・タクシー・シェアサイクルといった交通手段を、アプリやWebサービス上でひとつにまとめ、検索・予約・決済をスムーズに行えるようにする新しい移動のしくみです。
たとえば、「今から空港に行きたい」と思ったとき、従来であれば電車の乗換検索アプリ、バスの時刻表、タクシーアプリなどを個別に使っていました。MaaSを使えば、目的地を入力するだけで、最適な移動ルートの提案からチケットの購入、乗車までがスマホひとつで完結します。つまり、移動のすべてを“サービス”としてワンストップで提供する考え方です。
この仕組みにより、利用者にとっては「より便利に、快適に」移動できるようになります。自治体や地域にとっては、移動の選択肢が広がることで、高齢者や観光客の移動支援、公共交通の活性化にもつながります。また、交通事業者にとっては、利用データの活用やサービス改善、新たな収益機会の創出も期待されています。
すでに国内外の観光地や都市部では、観光施設の入場券付きフリーパスや、病院・スーパーへの送迎サービス、マイナンバーカードと連携した市民向け優待施策など、MaaSを活用した多様な取組が始まっています。
一言で言えば、MaaSは「移動の煩わしさをなくし、サービスとして体験できるようにする」新たなモビリティのあり方です。これからの交通を変えていく、大きな潮流のひとつとして注目されています。
デジタル予約システムとは?
デジタル予約システムとは、スマートフォンやパソコンを使って、インターネット上でサービスの予約ができる仕組みです。電話や窓口でのやりとりが不要になり、利用者は24時間いつでも、どこからでも簡単に予約を行うことができます。
このシステムは、今やさまざまな分野で活用されています。例えば、飲食店や美容室の来店予約、病院の診察予約、公共施設の利用申込み、さらにはバスやタクシーといった交通サービスまで、日常の多くの場面で導入が進んでいます。
デジタル予約システムの魅力は、利用者・事業者の双方にとってメリットがある点です。利用者にとっては、リアルタイムで空き状況を確認できたり、予定変更の際も簡単にキャンセル・再予約ができたりと、利便性が大きく向上します。一方、事業者にとっては、予約の管理業務が効率化されるだけでなく、データを活用した需要予測や人員配置の最適化にもつながります。
特に近年は、MaaSやAIオンデマンド交通のような分野でこのシステムが重要な役割を果たしています。たとえば、利用者が行きたい場所と時間を入力すると、自動的に最適なルートや配車を決めてくれるサービスがありますが、その「入り口」となるのがまさにこのデジタル予約システムです。
一言でいえば、デジタル予約システムは「予約をもっと簡単に、便利に、効率よく」してくれる現代のインフラともいえる存在です。今後も、私たちの暮らしや働き方を支える重要なツールとして、さらに広がっていくことが期待されています。
MaaSのメリット・デメリット
| 分類 | 項目 | 内容 |
| メリット | 1. 利便性の向上(利用者側) | ・スマホ1つで交通手段の検索・予約・決済が可能・乗り換え案内や運行状況をリアルタイムで把握できる |
| 2. 効率的な運行管理(事業者側) | ・データを活用した需要に応じた運行計画が可能・予約データからピーク時間帯や利用傾向の可視化が可能 | |
| 3. インバウンド・観光振興 | ・多言語対応や観光地との連携による観光客の利便性向上・交通と観光施設を一体化し、回遊性を高める | |
| デメリットと課題 | 1. ITリテラシー・通信環境の課題 | ・高齢者にとっての利用ハードルが高い・スマホやネット環境が未整備な地域では導入が難しい |
| 2. 導入・維持コスト | ・MaaSプラットフォーム構築に数百万円〜数千万円の初期費用が必要・運用・保守のための人材や業務体制の整備が必要 | |
| 3. 交通事業者・自治体間の連携課題 | ・経路検索や運賃連携のためのデータ統合が煩雑・利害の異なる複数事業者間での調整・協議が必要 |
成功事例(日本国内)
近年、日本国内では、MaaSの導入が各地で進んでいます。本章では、国内で展開されているMaaSの最新の事例をいくつかご紹介します。
地域交通の課題解決を目指すMaaS
◆京都府南山城村の取り組み
京都府南山城村では、高齢化の進行や交通事業者の撤退により、「車がなければ生活が成り立たない」という深刻な移動課題を抱えていました。こうした状況を打開するため、地域特性に応じた新たな交通手段として、AIオンデマンド交通を含む地域交通MaaS(Mobility as a Service)の導入が進められています。
■ 主な取り組み内容
- 公共交通の再編:村営バスやコミュニティバスの有償化とルート見直しによる再編
- 地域連携型の輸送支援:NPO等と連携した自家用車による有償運送の仕組みを整備
- 新たなモビリティの導入:JR駅や道の駅など、拠点施設と結ぶAIオンデマンド交通を導入
- 外出促進策の実施:買い物支援、イベント開催などを通じて地域住民の外出機会を創出
📱 MaaSアプリの活用
住民や観光客が地域の移動手段をより便利に活用できるよう、専用のMaaSアプリを導入しています。このアプリでは、次のような多機能が提供され、移動に関する一連の操作をスマートフォン一つで完結できます。
- 経路・時刻表の検索、乗車予約、キャッシュレス決済
- QRコードによるチケット提示機能
- 地域の観光・イベント・特売情報の閲覧
- 利用者ごとのプロフィール登録と管理
これにより、鉄道・バス・タクシーなど複数の交通手段を一元的に利用でき、地域内の移動が格段にスムーズになっています。
✨ まとめ
南山城村におけるAIオンデマンド交通の導入は、移動の自由度を高め、「行きたいときに行ける」地域社会の実現を後押しするものです。過疎化や高齢化が進む地域において、新たな公共交通のモデルとして注目されており、今後のさらなる普及と他地域への展開が期待されています。
◆群馬県前橋市:「GunMaaS(グンマース)」
前橋市では、バス、タクシー、シェアサイクル、デマンド交通といった多様な交通手段を統合し、リアルタイムでの経路検索や予約、決済を可能にするWebサービス「GunMaaS」を展開しています。 このサービスは、JR東日本が提供するプラットフォームを活用し、国土交通省の支援事業の一環として進められています。 マイナンバーカードと連携した市民割引などを導入することで、特に免許を持たない高齢者の外出を促し、公共交通の利用向上を目指しています。
◆北海道室蘭市:「いってきマース」
高齢化が進む室蘭市では、パナソニックITSがタクシー会社や地元の店舗、市の施設などと連携した「いってきマース」というサービスを提供しています。 専用アプリやLINEからタクシーを配車でき、利用すると割引クーポンや市のポイントが付与される仕組みです。 相乗り機能も導入し、より安価な移動を実現することで、高齢者の外出機会を創出し、まちの活性化に貢献しています。
◆ 北海道芽室町:「芽室MaaS事業」
農村地区の過疎化や公共交通の空白化という課題を抱える芽室町では、サブスクリプション型の乗合デマンドタクシーを導入しました。 WEBや電話で予約すると、自宅から目的地までドアツードアで送迎してくれます。 さらに、買い物代行や病院の予約代行といったサービスも提供し、地域住民の生活を支えています。
観光振興に貢献する観光型MaaS
観光地における交通渋滞の緩和や、二次交通の利便性向上は、多くの地域にとって重要な課題です。観光型MaaSは、これらの課題解決と観光客の満足度向上に貢献しています。
◆ 栃木県日光市:「NIKKO MaaS」
東武鉄道が提供する「NIKKO MaaS」は、東武線のフリーパスや特急券、日光地域でのバス、EVカーシェア、シェアサイクルなどをスマートフォンで一括して検索・購入・利用できるサービスです。 環境に配慮した移動手段を提供している点が特徴で、NTTドコモなどがプロモーションを支援し、サービスの利用拡大に貢献しています。
◆九州地方:「九州MaaS」
JR九州と宮崎交通は、鉄道とバスのスムーズな連携を目指し、統合型のデジタルサイネージを導入するなど、MaaSの取り組みを進めています。 アプリ上での共同チケット発売なども行っており、利用者への分かりやすい情報提供と利便性向上を図っています。
◆ 沖縄県宮古島市:「あいのりタクシー」
観光客と地域住民の双方を対象とした相乗りタクシーサービスが提供されています。 専用アプリで予約やチケット購入が可能で、住民向けの割引や観光客向けのクーポン配布なども行われています。
ユニバーサル社会の実現に向けたMaaS
◆熊本県山都町医療MaaS事業の取り組み
熊本県山都町では、2025年1月29日より「山都町医療MaaS事業」を開始しています。本事業は、MONET Technologies株式会社(以下、MONET)との連携により、医療アクセスが困難な地域におけるオンライン診療の支援を目的としています。
この取り組みでは、診療予約情報と連動して最適な運行ルートを確認できる運行管理システム、車両の稼働状況を把握できる管理者向けシステム、そして多様な用途に対応可能なマルチタスク車両を提供しています。
山都町は熊本県内で3番目に広い面積を持ち、地域によっては診療所や病院が近隣に存在しない場所が多くあります。また、公共交通機関が乏しいため、医療機関へのアクセスが難しくなっている住民も少なくありません。さらに、医師の高齢化や診療所の閉鎖が進んだ結果、熊本県内に存在する26カ所の無医地区のうち8カ所が山都町に集中しています。
こうした課題を受けて、山都町では遠隔地の医師によるオンライン診療を可能にするための環境整備が行われました。具体的には、電子血圧計、遠隔聴診器、ポータブル超音波診断装置(エコー)などの医療機器を搭載したマルチタスク車両に看護師が同乗し、蘇陽地区の公民館などを訪問します。現地では、山都町包括医療センターそよう病院の医師とオンラインで接続し、診療を行います。通信環境が整っていない地域においては、ソフトバンク株式会社が提供する衛星ブロードバンドサービス「Starlink Business(スターリンクビジネス)」を活用し、オンライン診療を実現しています。
今後は、薬剤師によるオンラインでの服薬指導の導入も検討されており、さらに「動く保健室」として健康教育や移動救護室など、より幅広い保健医療サービスの提供が計画されています。このように、MONETと山都町は、地域の実情に即した持続可能な医療提供体制の構築に取り組んでいます。
これらの事例は、MaaSが単なる移動手段の提供に留まらず、地域の活性化や社会課題の解決に貢献するポテンシャルを秘めていることを示しています。 今後、データの連携や活用がさらに進むことで、よりパーソナライズされた、シームレスな移動体験が実現していくことが期待されます。
MaaSの今後の課題と展望
今後のMaaSは、以下の3つの方向性に向けて進化が期待されています:
1.AIとの連携による進化:「AI × MaaS」
AI技術とMaaSを組み合わせることで、交通手段の最適経路の提案や需要予測が可能になります。これにより、ユーザーの移動体験がより快適で効率的なものとなるほか、交通混雑の緩和や運行コストの最適化にもつながります。
2.生活サービスとの統合:「生活MaaS」
医療・買い物・教育などの日常生活に密接したサービスとMaaSを統合する「生活MaaS」の実現が期待されています。高齢者や子育て世帯など、移動に制約がある人々の利便性向上を図る取り組みです。
3.行政サービスとの連携:マイナンバー・地域通貨との統合
マイナンバーカードや地域通貨と連携することで、公共交通の利用に対する割引施策やポイント付与などのインセンティブが提供可能になります。これにより、地域住民の移動促進や地元経済の活性化も期待されます。
公共と民間の連携によるスマート交通実証

公共と民間の連携(PPP: Public-Private Partnership)によるスマート交通実証は、国や地方自治体(官)と民間企業(民)が協力し、AIやIoTなどの先端技術を活用して交通に関する様々な社会課題の解決を目指す取り組みです。
スマート交通実証の主な目的は、交通渋滞の緩和、公共交通の利便性向上、交通事故の削減、環境負荷の軽減、そして高齢者をはじめとする交通弱者の移動手段の確保などです。 これを実現するために、以下の実証実験が行われています。
◆ MaaS(Mobility as a Service):電車、バス、タクシー、シェアサイクルなど、様々な交通手段を一つのサービスとして統合し、ルート検索から予約、決済までをスマートフォンアプリなどで一括して行えるようにする仕組みです。
◆自動運転: 特に公共交通が手薄な地域などで、自動運転バスなどを導入し、持続可能な移動サービスを提供します。
◆AIオンデマンド交通: AIを活用して利用者の予約に応じてリアルタイムに最適な運行ルートや配車を行うデマンド型の交通サービスです。
◆スマート信号機: 交通量に応じて信号のタイミングを最適化し、渋滞を緩和します。
これらの実証実験は、スマートシティの実現に向けた重要な要素としても位置づけられています。
官民連携スマート交通実証|メリットと課題
官民が連携してスマート交通実証に取り組むことには、双方にメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。
メリット
| 区分 | 解説 |
| 公共(自治体など) | ・民間の持つ先進的な技術力、ノウハウ、資金を活用できる
・行政だけでは難しい、迅速で柔軟なサービス開発・導入が可能になる ・財政負担を軽減しつつ、住民の利便性向上や地域活性化につなげられる |
| 民間(企業) | ・公共のインフラやデータを活用して、新しい技術やサービスの社会実装に向けた実証の場を得られる
・行政との連携により、事業の信頼性が向上する ・新たなビジネスチャンスの創出につながる |
課題
| 課題 | 内容 |
| 調整の複雑さ | 目的や文化、意思決定のプロセスが異なる官と民が合意形成を図るのに時間がかかる場合があります。 |
| データ連携の課題 | 個人情報保護やセキュリティの観点から、官民での円滑なデータ連携が難しい場合があります。 |
| 事業の継続性 | 実証実験で終わってしまい、本格的な事業化や持続可能なビジネスモデルの構築に至らないケースがあります。 |
| 法整備の遅れ | 自動運転など、新しい技術やサービスに対応した法律や制度の整備が追いついていない場合があります。 |
スマート交通の実証実験|国内事例
日本国内では、各地で官民連携によるスマート交通の実証実験が進められています。
【自動運転】茨城県境町:生活路線バスとしての自動運転サービス
概要: 鉄道駅がなく公共交通が脆弱な課題を解決するため、町が主体となり、BOLDLY株式会社(旧SBドライブ)と連携して自動運転バスを公道で定常運行しています。 これは、自治体による公道での自動運転バスの定常運行としては国内初の取り組みです。
連携: 境町が事業主体となり、民間企業が運行システムや車両を提供しています。 停留所の設置には私有地が提供されるなど、地域住民の協力も得ています。
成果: 高齢者や子育て世代の重要な移動手段として定着し、町外からの観光客誘致にも繋がり、地域内外の交流が活発化しています。 防災や健康増進サービスとの連携も進められています。
【MaaS】福岡県福岡市など:「my route」によるマルチモーダルサービス
概要: トヨタ自動車が開発したMaaSアプリ「my route」を活用し、西日本鉄道などと連携して展開されています。
連携: 自動車メーカー、鉄道会社、タクシー配車アプリ、シェアサイクル事業者などが連携しています。
成果: バス、電車、タクシー、シェアサイクルなど多様な交通手段を組み合わせたルート検索から予約・決済までをワンストップで提供。 利用者は複数のアプリを使い分ける手間なく、快適な移動が可能になっています。
これらの事例は、地域の特性や課題に応じて、官民がそれぞれの強みを活かしながら連携することで、スマート交通が地域住民や訪問者の生活の質を向上させる可能性を示しています。
タクシー補助制度へのシフト

バス路線の維持に対する新たな解決策として注目されているのが、従来のバス路線への補助金に代わり、住民のタクシー利用料金を支援する「タクシー補助制度への転換」です。
この施策は、利用者の多様なニーズに柔軟に対応しながら、自治体の財政負担を軽減する可能性を秘めています。
本章は、その施策の概要やメリット・デメリットに加え、国内における最新の成功事例についても解説します。
バスからタクシーへ、補助の形を変える
タクシー補助制度は、自治体がバス会社に支払っていた路線維持のための補助金を、住民がタクシーを利用する際の料金補助に振り替えるものです。多くの場合、高齢者や交通弱者を対象に、タクシー券を配布したり、運賃の一部を助成したりする形で実施されます。
この制度は、利用者が予約に応じて好きな時に好きな場所へ移動できる「デマンド交通」の一種と位置づけられます。 定時定路線で運行し、利用者がいなくてもバスを走らせる必要があった従来の方式に比べ、より効率的で利用者の利便性に即した交通サービスの提供を目指します。
タクシー補助制度へのシフト|メリット・デメリット
タクシー補助制度へのシフトには、利用者、自治体、交通事業者のそれぞれにメリットとデメリットが存在します。
メリット
| 主体 | 効果・利点 | 内容 |
| 利用者側 | 利便性の向上 | 「ドアツードア」の移動が可能となり、バス停までの徒歩の負担が不要になる・予約制により、自分の都合に合わせて移動時間を設定できる |
| 柔軟な対応 | 病院、買い物など多様なニーズに応じた柔軟な対応が可能 | |
| 自治体側 | 財政負担の軽減 | 利用者がいない便の運行が不要となり、路線バス維持のための補助金支出が削減される可能性・タクシー助成制度で乗客1人当たりの支出が適正化 |
| 持続可能な交通網の構築 | 地域タクシー事業者を活用することで、地域交通インフラの維持と経済活性化が期待できる | |
| 交通事業者側 | 経営の安定化 | 新たな需要の創出により、タクシー事業者の収益安定化に貢献 |
デメリット
| 主体 | 課題・懸念点 | 内容 |
| 利用者側 | 予約の手間 | 事前に電話やウェブでの予約が必要・高齢者などにとっては心理的ハードルとなることがある |
| 利用の制約 | 乗り合いになる可能性がある
利用できる時間帯やエリアに制限がある場合がある |
|
| 自治体側 | 財源の確保 | 制度導入や運用継続に必要な予算を確保することが課題となる |
| 制度設計の複雑さ | 地域実情に合わせた補助額・利用条件などの設計が必要で、設計作業が複雑 | |
| 交通事業者側 | 運転手不足 | 地域内のタクシー供給が不足している場合、需要に応じられないリスクがある |
| 収益性の低いエリアへの対応 | 人口の少ない地域では採算が合わず、運行が難しい可能性がある |
最新の国内成功事例
近年、多くの自治体がタクシー補助制度やデマンド交通の導入を進めており、成功事例も報告されています。
◆愛知県みよし市の「おでかけタクシー運行事業」
愛知県みよし市は2025年4月から、高齢者や障害者など公共交通機関の利用が困難な人々を対象に、1回300円でタクシーを無制限に利用できる「おでかけタクシー運行事業」を開始しています。この事業は、既存のコミュニティーバスの無料化に加え、さらに外出機会の少ない人々の移動手段を確保し、健康維持や医療費抑制を図ることを目的としています。
対象者は、65歳以上の高齢者、障害者、要介護・要支援者、妊娠中および出産後1年以内の人で、利用範囲は市内全域と隣接する豊田市の豊田厚生病院まで。運行は土日祝を含む毎日、午前10時から午後5時までで、タクシーの空車状況に応じて対応します。
本事業は2024年度に試験的に半年間実施され、延べ2,500件の利用がありました。この結果を踏まえて本格実施に踏み切るもので、小山祐市長は「コロナ禍で外出が制限されたことで認知症の進行や要介護度の悪化が見られた。外出を促進することは医療費の抑制にもつながる」と述べています。
この取り組みは、定額で無制限にタクシーを利用できる点で全国的にも珍しく、外出支援を通じて地域福祉の充実を目指す先進的なモデルといえます。
◆青森県平内町
2024年1月から、町内全域を対象としたデマンド交通の実証運行を開始しました。 住民だけでなく誰でも利用可能で、運賃は一律500円(乗り合い割引あり)と、利便性の高いサービスを提供しています。
◆ 新潟県加茂市
市民バスの非効率な運行が課題となる中、2021年からデマンド型タクシー「のりあいタクシー」の実証実験を開始しました。 自宅前から病院や駅などへ移動でき、市民の生活の足として持続可能な公共交通のあり方を検証しています。
◆ 富山県南砺市
2024年4月から、交通サービスが不足している地域で住民の移動を支援する「南砺市版自治体ライドシェア」の実証運行を開始しました。 市営バスの運行エリア内で、観光客を含む誰もが1回500円で利用できる手軽さが特徴です。
これらの事例は、地域の実情に合わせて制度を設計し、住民のニーズに応えることで、タクシー補助制度が過疎地の交通問題解決に有効な手段となり得ることを示しています。 今後、免許返納後の高齢者の移動手段としても、その重要性はさらに高まっていくと考えられます。
地域資源・人材の活用

地域にすでにある資源や人材を有効活用し、行政コストを抑制しつつ住民の生活を支え、コミュニティを活性化させる取り組みは、日本全国で数多くの成功事例を生み出しています。特に廃校の活用や地域住民が主体となる交通・福祉サービスは、持続可能な地域づくりのモデルとして注目されています。
地域資源の活用:廃校などを交通の拠点に
過疎化や少子化で増加する廃校や空き施設は、見方を変えれば低コストで活用できる貴重な地域資源です。これらをデマンド交通の車両基地や事務所、住民の待合所として再利用することで、初期投資や維持コストを大幅に抑制できます。
【事例】埼玉県小川町「東小川住宅団地地域住宅団地再生事業」
廃校跡地を活用し、デマンドタクシーの運行事業を含む、多世代共生・持続可能なまちづくりを目指す計画が進行中です。 このように、交通拠点の整備をまちづくり全体の計画に組み込むことで、相乗効果が期待できます。
廃校などを単なる車両置き場としてではなく、予約受付や住民交流の拠点とすることで、新たなコミュニティの核として再生させています。
自家用有償旅客運送の多様な展開
市町村やNPO法人が、自家用車を使って有償で住民を送迎する制度です。
定年退職者や地域のNPOボランティアなどが運転手として活躍する「自家用有償旅客運送」は、人件費を抑えつつ、利用者にとっては「顔の見える」安心な交通手段となります。 この仕組みは、貨客混載と組み合わせることで、さらなる収益源の確保と事業の持続可能性向上につながっています。
◆京都府京丹後市「ささえ合い交通」
京都府京丹後市の「ささえ合い交通」はNPO法人が主体となり、地域の住民がドライバーを務めるデマンド型の交通サービスです。 高齢者の通院や買い物といった生活の足を確保するだけでなく、ドライバーにとっては生きがいとなり、利用者との交流が地域コミュニティの活性化に貢献しています。
◆青森県佐井村
住民ボランティアが自身の車を活用して、高齢者などの移動を支援しています。
◆北海道占冠村
民間バス事業者の撤退に伴い、村が主体となってバスを運行し、通院や通学、さらには観光客の足としても機能しています。
マイクロモビリティの導入

利用者の減少による赤字路線の増加、運転手不足などが原因で、地域の重要な移動手段であるバスの減便や廃止が相次いでいます。 このような状況を打開する施策として、マイクロモビリティの導入が注目されています。
マイクロモビリティとは、電動キックボードや超小型EV(電気自動車)、電動アシスト自転車など、1〜2人乗りの小型で電動の移動手段を指します。 これらを活用し、既存の公共交通を補完したり、交通空白地帯の移動を支援したりする取り組みが全国で始まっています。
どのような施策か?
過疎地域におけるマイクロモビリティの導入は、主に以下の形で進められています。
◆デマンド交通としての活用: 利用者の予約に応じて運行する「オンデマンド交通」にマイクロモビリティを活用する施策です。 決まったルートを走る路線バスとは異なり、利用したい時に自宅や指定の乗降場所(ミーティングポイント)から目的地まで移動できるため、利用者の利便性が大幅に向上します。AIを活用して最適な運行ルートを瞬時に計算するシステムも導入されています。
◆ラストワンマイルの移動手段: 自宅から最寄りのバス停や駅までの「ラストワンマイル」の移動を補完する役割も期待されています。 特に、坂道が多い地域やバス停まで距離がある高齢者にとって、手軽な移動手段となります。
◆グリーンスローモビリティ(グリスロ): 時速20km未満で公道を走行できる電動カートなどを活用した移動サービスです。 速度が遅いため安全性が高く、開放的な車両は、乗客同士や地域住民とのコミュニケーションを生み出す効果も期待されています。 観光客の周遊や地域住民の足として導入されています。
メリット・デメリット
マイクロモビリティの導入には、多くのメリットがある一方で、デメリットや課題も存在します。
メリット
| カテゴリ | 内容 |
| 利用者・地域への利便性 | ドアtoドアに近い移動が可能・バスや鉄道がカバーできないエリアの補完・地域コミュニティの活性化・観光客の誘致と周遊促進 |
| 事業者・自治体の効率化 | 運行コスト(燃料費、人件費)の削減・AI活用による効率的な配車 |
| 環境への配慮 | CO₂排出量が少なく環境負荷が低い |
デメリット
| カテゴリ | 内容 |
| 天候への影響 | 雨や雪、強風など天候に左右されやすい |
| 利用者の制約 | 高齢者や運転に不慣れな人には訓練・サポートが必要・車両の定員が少ない |
| 事業性・コスト | 単独での収益化が難しい・導入・維持管理にコストがかかる |
| 安全性・制度的課題 | 事故リスクへの対応や保険制度の整備が必要・法整備および地域のルール作りが必要 |
マイクロモビリティ|最新の国内事例
各地で、マイクロモビリティを活用して地域交通の課題解決に取り組む動きが進んでいます。以下に、そうした取り組みの一部をご紹介します。
事例1:和歌山県すさみ町、トゥクトゥクEVのレンタルサービスを開始
~地域交通の新たな選択肢と観光活性化を目指して~
和歌山県すさみ町とJR西日本レンタカー&リース(本社:兵庫県尼崎市)は、2025年7月1日より、JR周参見駅において電動三輪自動車「トゥクトゥク」のレンタルサービスを開始しました。この取り組みは、地域内の二次交通手段を拡充し、周参見駅周辺のにぎわい創出を図ることを目的としています。町としては、さらなる観光誘客に繋げたいという思いを込めています。
トゥクトゥクとは、主に東南アジアでタクシーとして使われている三輪自動車で、今回導入された車両は、地方創生臨時交付金を活用して町が2台購入し、JR西日本レンタカー&リースに貸与され運用されています。車体は長さ約2メートル、幅約1メートル、高さ約1.6メートル、重さ195キロとコンパクトで、最高速度は時速40キロ、1回の充電で約80キロの走行が可能です。3人乗りで、普通自動車免許があれば運転できます。長距離走行に対応できるよう、希望者には予備バッテリーの貸出も行われています。
町の担当者は「すさみ町はかつて浪速・江戸航路の中継地として栄えた歴史を持ち、今もなお古き良き街並みや美しい自然、地元の料理など多くの観光資源が残されています。環境にもやさしく、風を感じながら走れる開放的なトゥクトゥクに乗って、カメラ片手にのんびりと散策を楽しんでもらいたい」と話しています。
このように、地域資源を活用しながら持続可能な観光を目指す取り組みは、地方創生の一環としても注目される存在となりそうです。
グリーンスローモビリティ(グリスロ)の活用
時速20km未満で公道を走行できる電動カートを活用した移動サービスです。
◆ 島根県大田市(石見銀山)ぎんざんカート
世界遺産エリアでの観光客の移動と、地域住民の足の確保を両立させています。 観光客の増加による交通問題を解決しつつ、免許を返納した高齢者の移動手段にもなっています。
◆ 北海道登別市(登別温泉)「オニスロ」
温泉街の回遊性を高めるモビリティとして導入され、環境にやさしい観光地としてのブランドイメージ向上にも貢献しています。
◆ 岡山県備前市(グリーンスローモビリティ)
交通空白地帯の解消を目指し、オンデマンド方式のグリーンスローモビリティを導入しました。 NPO法人が運行主体となり、地域住民の足としてだけでなく、高齢者の見守りや地域内の交流促進にも貢献しています。
◆東京都町田市 鶴川団地(グリーンスローモビリティ)
大規模な住宅団地内で、外出が困難な高齢者を対象とした送迎サービスにグリーンスローモビリティを導入しました。 年会費制の登録をすれば電話で予約でき、全国で初めて自家用有償旅客運送として事業化された事例です。
電動キックボードの活用
◆ 沖縄県那覇市(電動キックボード・シートボード)
深刻な交通渋滞や公共交通の利用者減少、オーバーツーリズムといった課題解決のため、電動キックボードと座って乗れる電動シートボードのシェアリングサービスが開始されました。 住民の通勤手段だけでなく、観光客の新たな移動体験を提供し、地域経済の活性化を目指しています。
これらの事例は、マイクロモビリティが単なる移動手段にとどまらず、地域の活性化や住民の生活の質向上に貢献する可能性を示しています。今後、持続可能な事業モデルの構築や、MaaS(Mobility as a Service)として他の交通手段とシームレスに連携していくことが、さらなる普及の鍵となるでしょう。
まとめ

過疎地における交通課題は、「インフラの老朽化」や「人手不足」などの物理的な問題だけでなく、住民の孤立を防ぐ“人の流れ”をどう確保するかという、より深い社会的課題でもあります。
本記事で紹介したように、デマンド交通や貨客混載、MaaSの活用、さらには地域人材の活用といったアプローチは、単なる「交通手段の再設計」にとどまらず、地域の自立と再生を支える仕組みとして注目されています。すでに実証実験や制度改革が全国各地で進んでおり、成功事例も増えつつあります。
今後求められるのは、地域ごとの特性に応じた柔軟な制度設計と、それを持続可能にするための行政・民間・住民の連携体制の構築です。移動の自由が制限されれば、教育・医療・経済といった他分野にも影響が及びます。
だからこそ、私たちはいま、「誰もが行きたいときに、行きたい場所へ行ける」社会の実現に向けて、交通を「コスト」ではなく「地域の投資」として捉える視点が求められているのです。