近年、東南アジアの中でもとりわけ目覚ましい成長を遂げている国のひとつがベトナムです。1億人を超える人口と若くて活力ある労働力、地政学的に有利な立地、そして政府による積極的な経済改革-これらを背景に、ベトナムは世界中の企業にとって魅力的な市場・投資先として存在感を高めています。本記事では、ベトナム経済の最新動向を踏まえながら、その構造的特徴、今後の見通し、そして日本企業にとっての具体的なビジネスチャンスを多角的に分析します。
ベトナム経済の特徴と概況

ベトナム経済は、かつては繊維や衣料といった労働集約型の製造業が主軸を担っていましたが、近年では電子・電機関連産業の輸出をけん引する存在となり、産業全体が高付加価値分野へとシフトしています。
また、サービス業も着実に拡大しており、2025年第1四半期にはサービス部門がGDPの約53.7%を占めるまでに成長しました。内需の堅調な推移や観光業の回復がこの成長を後押ししています。一方で、農林水産業に関しては、コメ、コーヒー、海産物を輸出することで経済を下支えしています。
地域別に見ると、北部は中国との国境に近いという地理的優位性を背景に、電子・機械産業の集積地として発展しています。中部では、ダナンをはじめとする都市でIT関連産業や観光業が活況を呈しており、メコンデルタ地域は肥沃な土壌を活かして農業や食品加工分野での可能性が広がっています。
南部はホーチミン市を中心に、多様な産業が広がるとともに、ベトナム最大の経済圏としての機能を担っています。
ベトナム主要経済指標(2024年〜2025年)
◆実質GDP成長率:
+7.09%(2024年通年)
+6.93%(2025年第1四半期、前年同期比)◆消費者物価上昇率(CPI):
+3.24%(2025年5月、前年同月比)◆失業率:
2.20%(2025年第1四半期)◆名目GDP規模:
約4,763億ドル(2024年)
約5,000億ドル(2025年見通し、世界33位)◆1人当たりのGDP:
4,282ドル(2023年)
4,700ドル(2024年推定)◆GDP構成比(農業:工業:サービス):
11.8%:35.7%:43.5%(2024年第1四半期)◆輸出額(財):
4,055億ドル(2024年)◆輸入額(財):
3,808億ドル(2024年)◆経常収支:
+247.7億ドル(2024年、貿易黒字)◆人口:
約1億352万人(2023年)◆出生率:
1.91人(女性1人あたり、2024年)◆平均年齢(中位年齢):
32.5歳(2020年、推計)
最新のマクロ経済動向

世界的な経済不確実性が続く中でも、ベトナムは力強い回復と安定した成長を両立させています。GDPの堅調な伸び、制御されたインフレ、活発な貿易・投資動向といったマクロ経済の最新データからは、同国の経済基盤が着実に強化されている様子がうかがえます。本章では、ベトナム経済の最新動向を多角的に捉え、今後の展望とリスクについて解説したいと思います。
高成長の持続とGDP動向
ベトナム経済は、2020年に新型コロナウイルスの影響で一時的に減速を余儀なくされましたが、その後は着実かつ力強い回復を見せています。2023年の実質GDP成長率は5.1%と堅調に推移し、2024年には7.1%と再び高い成長を記録しました。
この2024年の成長加速は、個人消費の持ち直し、輸出の回復、さらには投資の拡大が寄与した結果です。特に輸出は、2023年に一時減少を経験したものの、2024年には前年比15.5%増と大きく反転。なかでも米国向け輸出は23.2%の増加となるなど、外需の好調さが目立ちました。
2025年に入ってもその成長の勢いは継続しており、第1四半期のGDP成長率は前年同期比6.93%と、この5年間で最も高い第1四半期の伸びを記録しています。中でも工業・建設部門は7.32%の成長で、全体の成長率に2.44ポイント貢献しました。サービス部門も、観光客数の増加や内需拡大を背景に好調を維持しています。
政府は2025年通年で8%の成長目標を掲げていますが、国際的な見通しではやや慎重な見方も見られます。たとえば世界銀行は、2025年の成長率を4月時点で5.8%と下方修正しており、世界経済の減速や米中景気の先行き、貿易環境の不透明さが下押し要因とされています。
とはいえ、中期的な視点ではベトナム経済には依然として高い成長のポテンシャルがあると見られており、公的投資の拡大や不動産市場の回復による内需の下支えなど、明るい材料も多く指摘されています。
インフレと金融政策
ベトナムのマクロ経済は、全体として安定を維持しています。インフレについても比較的落ち着いた動きを見せており、2022年から2023年にかけては、世界的な物価高の中でも抑制的な水準を保ちました。
2024年5月には一時的に4.4%まで上昇したものの、その後は沈静化し、2024年通年の消費者物価指数(CPI)の上昇率は3.63%にとどまりました。2025年4月時点でも、ヘッドラインインフレ率は3.1%と、中央銀行が掲げる管理目標の範囲内に収まっています。
このような物価の安定を背景に、中央銀行であるベトナム国家銀行(SBV)は景気下支えのための金融緩和策を取りやすい環境にあります。実際、2023年にはアジア諸国の中でも比較的早い段階で利下げを実施し、中小企業向けの融資支援などにも積極的に取り組みました。
金融システム全体としては健全性をおおむね維持しているものの、不良債権の動向や不動産向け融資のリスクなど、引き続き注視が必要な分野もあります。こうした点を踏まえ、政府は銀行の資本基盤強化や、不良債権の早期是正を促す仕組みの整備など、金融システムの安定性を高める取り組みを進めています。
※ヘッドラインインフレ率とは、総合的な物価上昇率のことをいいます。
貿易・投資動向
外需主導型の経済構造を持つベトナムにとって、貿易の動向は極めて重要な意味を持っています。2024年には輸出の大幅な伸びが全体の成長をけん引し、通年の貿易総額は7,862億ドルと、前年から15.4%の拡大を記録しました。また、貿易黒字も過去最大となる247.7億ドルに達するなど、外需の好調さが際立つ一年となりました。
輸出額は4,055億ドル(前年比+14.3%)、輸入額は3,807億ドル(+16.7%)と、いずれも力強く増加。輸出品目では、携帯電話、電子機器、コンピュータといったハイテク製品が主力で、これに加えて繊維・衣料品、靴類、木製品、さらにはコーヒーや水産物(エビ、イカ、カニ)などの農水産品も国際市場で高い競争力を誇っています。特に携帯電話や電子部品の分野では、サムスンをはじめとする多国籍企業の製造拠点として、ベトナムは重要なポジションを占めています。
輸出先としては、米国が単一最大の市場(輸出全体の約30%)となっており、次いで中国、EU、日本、韓国などが主要な取引相手です。一方、輸入面では生産用資材の需要拡大に伴い、中国、韓国、日本などからの原材料・部品調達が活発化しています。
外国直接投資(FDI)についても好調が続いており、ベトナムはASEAN域内でも引き続き有力な投資先として存在感を示しています。2024年の実行ベースのFDIは約253.5億ドルと過去最高を更新し、前年比で10%以上の増加となりました。特に2024年後半以降は新規認可額が急増しており、2025年1月には前年同月比+48.6%の43億ドルに達するなど、堅調な投資流入が続いています。
投資分野としては、電子・電機、自動車部品、機械加工といった製造業が依然として最大の比重を占めていますが、不動産開発や発電所、再生可能エネルギーといったインフラ・エネルギー分野への関心も近年高まりを見せています。
投資国別では、シンガポール、韓国、中国本土および香港が新規投資額で上位を占めており、日本も累計投資額で第3位に位置づけられており、引き続き重要な投資国と見なされています。2024年11月時点の統計によれば、日本企業は累計5,473件、776億ドル超の投資を行っており、件数・金額の両面で確固たるプレゼンスを維持しています。
もっとも、近年は他国からの積極的な投資活動が目立ち、日本のシェアは2024年時点で約7.6%にとどまるとの指摘もあります。このような状況下、対内直接投資(FDI)をめぐる国際的な獲得競争は一層激しさを増しているといえるでしょう。
投資環境と規制の現状

持続的な経済成長を背景に、ベトナムは外国企業にとってますます魅力的な投資先として注目を集めています。その背景には、制度改革の進展やインフラ整備の加速といった政府の積極的な取り組みがあります。本章では、ビジネス環境の整備状況や各種規制改革の動向を整理し、日本企業にとっての機会と課題を明らかにします。
ビジネス環境とインフラ
ベトナム政府は、1986年の「ドイモイ(刷新)」政策を契機に、市場経済化と国際経済統合を一貫して推し進めてきました。こうした取り組みを背景に、ビジネス環境は着実に整備が進み、年々改善の傾向を見せています。WTO加盟をはじめ、さまざまな自由貿易協定(FTA)の締結により貿易・投資制度が制度的に整えられ、CPTPP(包括的・進歩的環太平洋パートナーシップ協定)やEU・ベトナムFTAといった高い水準の協定にもすでに参加済みです。
これらの協定は単なる関税の引き下げにとどまらず、投資保護やサービス市場の開放といった幅広い分野をカバーしており、日本企業にとってもビジネス展開に有利な制度環境が広がっています。また、政治的な安定性と比較的良好な治安の維持は、企業活動にとって安心できる基盤として大きな魅力です。
インフラ分野
インフラ整備の面でも、近年ベトナム各地で大型プロジェクトが進行しています。主要都市圏では、日本の円借款支援による都市鉄道建設が進むほか、高速道路の整備、港湾や空港の拡張といった物流インフラ強化にも取り組んでいます。工業団地内のインフラは比較的整っている一方で、国全体では依然として物流や電力供給などに課題が残っており、さらなる投資が求められる状況です。
政府もこうした課題を認識し、都市交通、物流、エネルギーといった分野を成長の鍵と位置づけ、インフラ関連の公共投資を積極的に推進しています。実際、2024年の国家予算執行においては、インフラ分野への支出が過去最高水準に達し、経済全体の投資拡大にもつながっています。
電力需給分野
電力需給の分野では、増加する需要への対応として「第8次国家電力開発計画(PDP8)」が策定され、再生可能エネルギーの導入拡大やガス火力の整備が進められています。一方で、洋上風力発電の開発計画の見直しや、原子力発電の再導入に向けた検討の動きなども見られ、エネルギー政策においては、技術的・経済的条件の変化や社会的受容性を踏まえた電源構成や導入計画の調整といった、状況に応じた柔軟な政策判断が求められています。
なお、電力分野には海外からの資本参加の余地も大きく、日本の官民も「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の枠組みを通じて、ベトナムのグリーン成長を後押しする姿勢を示しています。
規制改革の動向
ベトナムでは、外国からの投資環境をより整備すべく、関連する法制度のアップデートが継続的に進められています。たとえば、2021年には新しい投資法および企業法が施行され、外国投資家に対するビジネス許認可の手続きが簡素化されるとともに、各種優遇措置の拡充が図られました。
さらに2024年11月には、「計画法・投資法・PPP法・入札法の改正法(2024年法第57号)」が国会で可決され、投資プロジェクトの承認プロセスの迅速化や、官民連携(PPP)事業に関する手続きの簡略化、入札制度の透明性向上といった内容が盛り込まれています。この改正法は2024年から2025年にかけて段階的に施行される予定で、投資円滑化への寄与が期待されています。
不動産分野
また、不動産分野においても、2023年から2024年にかけて土地法・住宅法・不動産業法の改正が行われ、外国人や外資系企業の土地利用に関する制度面での改革が進められました。具体的には、土地の利用期間の延長や賃借権の強化など、長年の懸案であった土地使用権の不透明さを改善する措置が盛り込まれています。これにより、不動産を含む各種事業への中長期的な投資判断がよりしやすくなると見込まれています。
金融セクター
ベトナムの金融セクターでは、2024年以降、政府による資本規制の見直しが進められており、その一環として、一定の条件を満たす地場銀行に対しては外国銀行の出資上限を従来の30%から最大49%へと引き上げる措置が講じられました。この対象には、経営再建を目的として他行を引き受けた銀行などが含まれています。
この新たな枠組みにより、日本のメガバンクを含む外国金融機関にとって、現地銀行への出資や業務提携の可能性が広がり、ベトナム国内の金融市場の活性化や、サービスの高度化が期待されています。
税制面・ハイテク分野
税制面では、景気を下支えする施策として、2023年に期間限定の付加価値税(VAT)引下げが導入され、2024年もこの措置が延長されました。こうした機動的な財政対応は、企業活動へのコスト負担軽減や、個人消費の促進に寄与しています。
また、ハイテク分野における外資誘致を後押しするため、政府は「ハイテク企業向け投資支援基金」(政令第182号)を設立しました。この基金は、先端技術を担う企業に対して低利融資や補助金を提供するもので、日本企業にとっても活用が見込まれるインセンティブ制度となっています。
総評
総じて、ベトナム政府は外資系企業の誘致やビジネス環境の整備に前向きな姿勢を示しており、関連法制度のアップデート、行政手続の電子化、人材育成といった多角的な取り組みを進めています。
もっとも実務面では、許認可の取得に時間を要する手続きや、地域によって異なる行政の運用解釈など、現場レベルでの課題も残っています。また、知的財産権の保護や契約の執行といった法的インフラについても、いまだ発展途上の側面があるため、進出企業には現地の法制度に精通した専門家の助言を得ながら、慎重かつ計画的な対応が求められます。
日本企業にとって有望なビジネスチャンス

日本企業にとって、ベトナム市場および現地拠点には多様な事業機会が広がっています。ここでは、業界別・地域別・進出形態別の3つの観点から、主なビジネスチャンスを整理します。
業界別の有望分野
まずは、業界別に注目すべき分野を見ていきましょう。
製造業(電子・機械・自動車部品など)
ベトナムの製造業は、グローバルなサプライチェーンの一翼を担っており、特に電子・電機分野ではその存在感を着実に高めています。人件費の優位性や輸出インフラの整備に加え、地政学的リスクを分散する「チャイナ+1」戦略の流れも追い風となり、多国籍企業による生産拠点の移転が進んでいます。
日本企業にとっては、部品製造の拠点構築や、日系完成品メーカー向けの現地調達拡大に取り組む好機といえるでしょう。例えば、自動車分野では、二輪車で先行するホンダやヤマハによるサプライチェーン強化に加え、四輪車においても新興EVメーカー(ビンファストなど)への部品供給といった新たな可能性が広がっています。
また、産業の高度化に伴い、工作機械や産業用ロボットといった設備投資の需要も今後さらに高まることが見込まれています。
インフラ・建設・プラント
経済成長にともない、インフラ分野に対する需要は非常に大きく、交通・物流ネットワークから都市開発、エネルギーに至るまで、さまざまな分野で豊富なプロジェクトが進行・計画されています。日本企業はこれまで、政府開発援助(ODA)や官民連携の枠組みを活用し、都市鉄道(メトロ)の建設や高速道路の整備、港湾の拡張、空港インフラの開発などで、着実に存在感を示してきました。
今後も政府による公共投資拡大の方針のもと、都市鉄道や高速道路網の拡充、発電所の新設といったインフラ案件が継続的に打ち出される見通しです。中でも、慢性的な電力不足の解消に向けた発電所(LNG火力や再生可能エネルギー)の建設や、送配電インフラの整備は喫緊の課題であり、日系の重電メーカーや総合商社、電力会社などにとって大きなビジネス機会となっています。
さらに、都市化の進展に伴って、上水道や下水処理、廃棄物発電などの環境インフラ分野でもニーズが高まっており、日本の高度な技術への期待は今後ますます大きくなると考えられます。
デジタル・IT産業
ベトナムは、豊富なIT人材と政府による育成支援を背景に、ASEAN地域における有力なテクノロジーハブとして存在感を高めています。ソフトウェアやサービス開発の分野において、高いスキルを持つエンジニアを比較的低コストで確保できる点は、日本企業にとってオフショア開発拠点として大きな魅力となっています。
実際、多くの日本企業が現地に開発拠点を構え、AI、ビッグデータ、クラウドなどの先端領域でベトナムの高度IT人材を積極的に活用しています。IT業界そのものも急成長を続けており、ハノイやホーチミン市ではスタートアップの動きも活発化。日本企業との連携によるオープンイノベーションのチャンスも広がっています。
さらに、電子政府やフィンテック、Eコマース、DX支援といったデジタル化に対する国内需要も急速に高まっており、こうしたサービスを提供する事業への参入にも可能性があります。
一方で、優秀な人材をめぐる競争は年々激化しており、人材の定着率向上や情報セキュリティ対策といったマネジメント面での課題にも、適切に向き合っていくことが求められます。
消費財・小売サービス
経済成長と所得水準の向上を背景に、ベトナムでは中間所得層を中心とした消費市場が拡大しています。人口構成も若く、都市化が進行していることから、小売市場の規模は年々拡大傾向にあります。2025年にかけては国内消費の回復が着実に進み、小売売上高も前年を上回る水準で推移しています。
こうした環境のもと、日本企業にとっては、食品・飲料、化粧品、日用品といった消費財分野に加え、外食や小売サービス領域においてもビジネスチャンスが広がっています。実際、イオンをはじめとする日系大手小売企業が積極的に出店を進めており、ユニクロなどの専門店も着実に市場開拓を進めています。
ベトナム市場では、日本ブランドに対する信頼感が高く、中・高所得層を中心に「高品質志向」や「安全・安心」を訴求することで競争力を発揮しやすい状況です。
もっとも、近年は欧米、韓国、さらには地場資本のブランドとの競争も激化しており、現地の消費者ニーズを的確に捉えた商品開発や、現地に即したマーケティング戦略の構築が、今後ますます重要になると考えられます。
医療・ヘルスケア
経済の発展にともない、医療水準の向上や人々の健康意識の高まりが進んでおり、病院インフラの整備や医薬品・医療機器に対する需要が増加しています。公的医療に加えて民間医療機関の市場も拡大傾向にあり、先進的な医療機器や医薬品に対するニーズには大きな潜在力があります。
すでに日本の製薬企業による現地企業の買収(たとえば、大正製薬による現地大手製薬会社の買収)や、医療機器メーカーの進出といった動きも見られています。今後も引き続き、質の高い医療サービスや製品に対する関心は高まることが期待されます。
また、ベトナムでは高齢化はまだ初期段階にありますが、今後徐々に進行していくと見込まれており、介護サービスや高齢者向けのヘルスケア関連ビジネスも、中長期的に有望な分野となる可能性があります。
ただし、医療分野は規制の影響が大きい産業でもあるため、認可取得や市場参入にあたっては、現地パートナーとの連携や適切な制度対応が重要な鍵となります。
エネルギー・環境ビジネス
ベトナム政府は2050年のカーボンニュートラル実現を目指しており、それに伴い再生可能エネルギーや省エネ分野におけるビジネスの成長が期待されています。すでに太陽光発電の導入容量は東南アジアでもトップクラスとなっており、今後は陸上風力、蓄電設備、スマートグリッドなどの分野でも技術ニーズが高まる見通しです。
日本企業もすでに、太陽光パネルの屋根貸しスキームや風力発電所の開発、水力発電設備のリハビリ事業などを通じて、現地市場への参画を進めています。
さらに、排水・排煙処理やごみ焼却発電といった環境汚染対策、省エネ改修などの取り組みは、政府の重点支援分野として公的資金の投入も見込まれており、日本の高い環境技術を活かした事業展開にとって大きな商機となっています。
地域別の展開ポイント
地域によって経済特性や産業構造が異なるベトナムでは、進出先の選定がビジネスの成否を左右します。ここでは、主要4地域-北部・南部・中部・メコンデルタ-それぞれの特徴とビジネス展開のポイントを紹介します。
北部地域(ハノイ首都圏・紅河デルタ)
政治の中心地であるハノイと、工業港湾都市ハイフォンを有するベトナム北部は、電子・電機などのハイテク製造業が集積する地域として発展しています。たとえば、サムスン電子が大規模な生産拠点を構えるタイグエン省や、電子部品産業が盛んなバクニン省などがあり、これらの地域では関連するサプライチェーンへの参入機会も期待されます。
また、北部は中国国境に近接しており、サプライヤー調達や陸路を活用した物流の利便性にも優れていることから、「チャイナ+1」戦略の生産移転先として工業団地の人気が高まっています。
一方で、冬季における電力需要の増加による供給逼迫など、インフラ面での制約が一部地域で指摘されている点には留意が必要です。
ハノイは人口約800万人を擁する大都市であり、官公庁や大学が集積していることから人材確保の面で優位性がある反面、生活コストや用地費用が上昇傾向にある点も、進出・拠点設立を検討する際の重要な判断材料となります。
南部地域(ホーチミン市・周辺省)
ベトナム南部経済圏は、商業の中心地ホーチミン市(HCMC)を核として、同国のGDPにおいて大きな割合を占める経済のエンジンとなっています。周辺のビンズオン省、ドンナイ省、ロンアン省などには多数の工業団地が集積しており、自動車、機械、食品、繊維など幅広い分野で日系製造業の進出が進んでいます。
また、南部にはベトナム最大規模の港湾であるカトライ港をはじめとする主要港が位置しており、輸出入の拠点としても重要な役割を果たしています。加えて、消費市場としても最大規模を誇り、小売業やサービス業が進出するうえで非常に有利なエリアといえます。
一方で、都市化の進展にともない、交通渋滞や大気汚染といった都市課題も顕在化しており、物流コストの上昇や従業員の通勤環境といった面での配慮も求められます。
こうしたなか、ホーチミン市近郊では都市鉄道の整備や、新たな玄関口となるロンタイン国際空港の建設が進められており、インフラ面での改善とともに、今後さらなる地域発展が期待されています。
中部地域(ダナン・中南部沿岸)
ベトナム中部の中心都市ダナンは、リゾート地として広く知られる一方で、近年ではITサービス拠点やハイテク産業の誘致にも注力しています。良好な生活環境が評価されており、外資系IT企業のオフィス誘致が進む中、オフショア開発の新たな候補地として注目を集めています。
また、中部沿岸地域では、縫製や水産加工といった労働集約型産業も盛んで、地域経済を支える重要な産業基盤となっています。交通面では、ハノイとホーチミン市を結ぶ北南回廊の中間に位置することから、物流コスト面でやや不利な面もありますが、ダナン港の整備やチュライ経済区の開発が進み、インフラ環境は着実に改善されています。
さらに、中部には石油精製施設や大型製鉄所といった国家プロジェクトも展開されており、重工業分野における進出事例も一部で見られます。
もっとも、同地域の市場規模は北部や南部と比べるとやや小さいため、進出を検討する際には輸出志向型の事業モデルや、特定エリアを対象としたニッチなサービス展開など、戦略的な絞り込みが重要になるでしょう。
メコンデルタ地域
ホーチミン市のさらに南西に広がるメコン川流域のデルタ地帯は、ベトナム有数の穀倉地帯・水産養殖の拠点として知られています。コメやエビなどの農水産品は、同国の主要な輸出品目であり、日本企業にとっては物流、加工、品質管理といった分野で関与できる可能性が広がっています。
たとえば、コメの高付加価値化や果物の輸出前処理、エビ養殖における高度な管理技術の導入など、農業・水産業をめぐるビジネスチャンスは多岐にわたります。
加えて、近年ではデルタ地域の主要都市であるカントーなどにおいて工業団地の整備が進み、一部では製造業の誘致も始まっています。
ただし、同地域は輸出港からの距離がある内陸部も多く、インフラ整備や人材確保といった面での課題も残されています。そうした環境下では、現地の有力企業や農協、行政機関などとの連携が、事業の成功に向けた重要なポイントとなります。
進出形態別のポイントと留意事項
ベトナムへの進出には複数の方法があり、それぞれにメリットとリスクがあります。ここでは、代表的な進出形態ごとに特徴や留意すべき点を整理します。
現地法人の設立(100%外資の子会社)
多くの製造業やIT企業は、ベトナムにおいて100%外資出資による現地法人(子会社)を設立し、独自に事業を展開しています。現在、同国では大半の業種において外資100%での法人設立が認められており、通信・報道・銀行など一部の特殊業種を除いて、出資比率の制限はすでに撤廃されています。
単独出資による進出は、経営の自由度が高く、品質管理や企業秘密の保護といった面でも有利に働きます。一方で、現地市場の事情や行政手続きに不慣れなまま全てを自社で対応することには一定のリスクも伴います。そのため、現地に詳しい人材の採用や、経験豊富な専門コンサルタントの活用が重要となります。
また、ライセンス取得や用地確保といった進出初期には、煩雑な手続きが数多く発生するため、スムーズな立ち上げに向けては、スケジュールに十分な余裕を持った計画策定が不可欠です。
合弁事業(ジョイントベンチャー)
小売・飲食・サービス業など、現地市場の知見やネットワークが成功のカギを握る分野においては、有力なローカル企業との合弁による参入が有効な手段となります。ベトナム人の消費嗜好や商習慣に詳しい現地パートナーと連携することで、よりスムーズな市場展開が期待できます。
たとえば、コンビニエンスストア業態では、地場の大手流通企業との合弁(JV)を通じて店舗網を拡大したケースがあります。また、インフラのPPP(官民連携)事業においても、現地の国営企業との共同出資でプロジェクトに参画する事例が見られます。
合弁を組む際には、契約条件を明確に定めるとともに、信頼関係の構築が極めて重要です。出資比率や経営権の配分、技術提供の範囲などについては、慎重な調整と合意形成が求められます。
なお、過去には経営方針の相違などから合弁解消に至った例もあるため、パートナーの選定は事前の見極めを含め、十分な検討が不可欠です。
M&Aによる進出
近年では、既存のベトナム企業を買収または出資するかたちで市場に参入する動きも増えています。たとえば、製薬業界における日系企業による現地製薬会社の買収、金融分野での日系銀行による地場銀行株式の取得、あるいは消費財メーカーによる現地ブランドの買収などが代表的な事例です。
M&Aを通じた進出は、既存の流通ネットワークや顧客基盤、営業許認可などを一括で引き継げる点が大きなメリットです。一方で、企業文化の違いや買収後の統合作業において課題が生じるリスクも伴います。
また、一定規模を超える買収については、ベトナム当局の事前承認が必要となるケースもあるため、法的・制度的な手続きにも十分な注意が求められます。
成功に向けては、デューデリジェンスを丁寧に実施し、対象企業の価値を的確に評価するとともに、買収後の経営方針や体制について相互理解を深めておくことが重要です。
駐在員事務所・技術提携など
まずは市場調査や情報収集を目的として、駐在員事務所(連絡事務所)を設置するケースも一般的に見られます。駐在員事務所は、ベトナム国内での収益活動は行えないものの、設立手続きが比較的簡便であり、現地の情報を収集する拠点として有用です。
また、製造業においては、初期段階では日本から製品を輸出し、現地代理店を通じて販売を行い、その後市場の成長に応じて現地生産へと切り替えるといった、段階的な参入モデルも採用されています。
さらに、現地企業との技術提携や人材交流を通じて信頼関係を築き、その延長線上でジョイントベンチャー(合弁事業)へと発展させるアプローチも有効です。現地との接点を持ちながら柔軟に展開を進めることで、リスクを抑えつつ着実な市場浸透を図ることが可能になります。
総評
以上のように、ベトナムは日本企業にとって多面的なビジネスチャンスを提供する魅力的な市場である一方で、リスク管理の重要性も高まっています。
たとえば、人件費の上昇は中長期的なコスト増要因のひとつです。毎年5〜6%程度の最低賃金引き上げが行われており、特に優秀な人材ほど離職率が高い傾向にあるため、人材の確保と定着に向けた取り組みが求められます。
また、競争環境の激化も見逃せない要素です。近年では、中国・台湾・韓国をはじめ、欧米企業の参入も加速しており、市場には非日系企業の製品やサービスが多く流通しています。このような中、日本企業にとっては、品質、技術力、アフターサービスといった自社の強みを明確に打ち出し、差別化を図る戦略がますます重要になっています。
さらに、法令順守とガバナンス体制の構築も不可欠です。贈賄防止やコンプライアンスの徹底はもちろん、税務・労務などに関する法規制の変更にも柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。ベトナムではこうした制度改定が頻繁に行われる傾向があるため、常に最新情報を把握・反映する姿勢が求められます。
日本企業が知っておくべきポイントとリスク
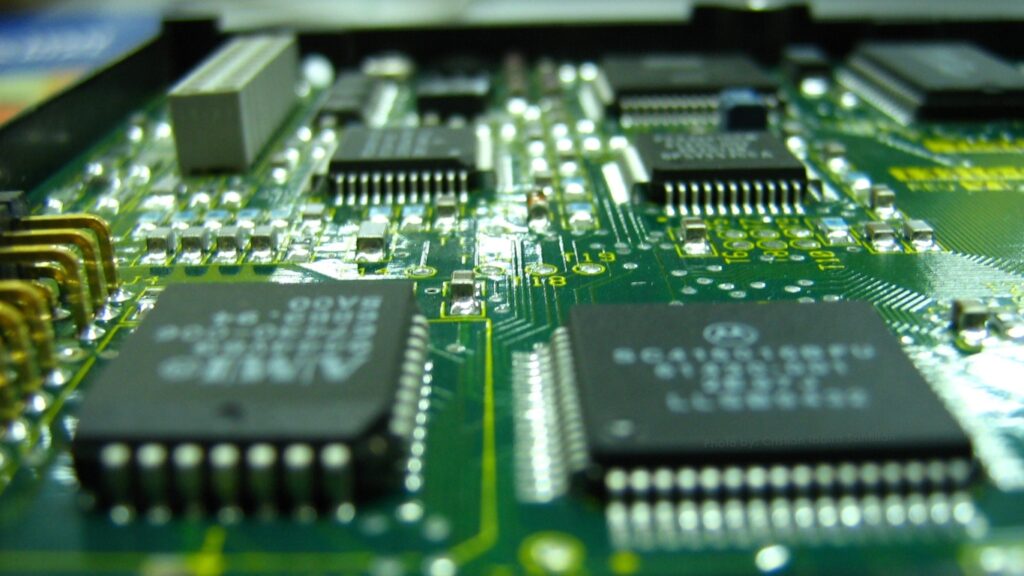
最後に、ベトナムへの進出や事業拡大を検討するうえで、日本企業が事前に把握しておくべき重要なポイントとリスクについて整理します。
労務・人材リスク
人件費については、依然として国際的には競争力があるものの、沿岸部の主要都市では上昇傾向が続いており、人材の確保競争も一段と激しくなっています。特に優秀な人材の早期離職や、マネジメント層・幹部クラスの人材不足といった課題に備え、現地での給与水準の見直しに加え、人材の育成や定着を図るための取り組みが重要となります。
加えて、労働法規の遵守にも十分な配慮が必要です。労働契約の締結、残業時間の管理、社会保険の加入義務など、企業が果たすべき義務は多岐にわたります。適切な労務管理体制を整えることで、法的リスクの低減と従業員との信頼関係の構築が図られます。
競争激化への対応
前述のとおり、ベトナム市場では日本企業のみならず、世界中の企業が商機を求めて積極的に進出しています。中国や韓国の企業は、コスト競争力や意思決定のスピードといった面で優位に立つ場面もあり、欧米企業はブランド力やマーケティングの巧みさで存在感を発揮しています。
こうした環境の中で、日本企業が持続的に収益を上げていくためには、製品・サービスの差別化に加え、現地ニーズへの柔軟な対応が不可欠です。
JETROの調査によれば、2024年にはベトナムに進出する日系企業の約64%が黒字を見込んでおり、過去5年間で最も良好な採算状況となりました。これは、輸出および内需の拡大を的確に捉えた各社の地道な取り組みの成果といえるでしょう。
今後も、品質やブランド力といった日本企業の強みを活かしながら、価格競争力やサービス対応の面でも他国企業に引けを取らないよう、戦略的な改善と対応を継続していくことが求められます。
法制度・ガバナンス
ベトナムでは近年、法制度の整備が進んでいるものの、法律の解釈に幅があったり、運用・執行にばらつきが見られたりする場面も依然として存在します。特に、投資許可や各種ライセンスの取得には時間を要することが多く、行政手続きの遅延がビジネスの進行に影響を与えるリスクについては、あらかじめ考慮しておく必要があります。
また、契約の強制執行や知的財産権の侵害への対応など、司法手続における不透明さが課題として指摘されるケースもあります。
こうした環境の中、日系企業の間では、不正防止や情報管理を含むガバナンス強化の重要性が広く認識されるようになっています。現地子会社における内部統制の整備、贈収賄リスクへの対策、行政機関との適切な関係構築など、コンプライアンス面での備えを徹底することが、安定的な事業運営のための重要な土台となります。
インフラ・供給網リスク
インフラ整備は着実に進んでいるものの、依然として道路の渋滞や港湾の混雑、電力供給の不安定さといった課題は残されています。特に製造業においては、突発的な停電や輸送の遅延がサプライチェーンに及ぼす影響を念頭に置き、リスクマネジメントの観点から、在庫の余力を持たせたり、自家発電設備の導入を検討したりといった対応が求められます。
また、近年のパンデミックや国際的な物流の混乱が示したように、単一の調達先や物流ルートに依存することのリスクが顕在化しています。今後は、複数の調達先を確保し、サプライチェーンを多元化することで、柔軟で持続可能な事業体制を構築していくことが重要です。
為替・経済変動リスク
ベトナムドン(VND)は管理変動相場制のもとで推移しており、対米ドルでは緩やかな下落傾向が続いています。急激な変動は比較的限定的とされていますが、中長期的には年数%規模での通貨安が生じる可能性もあるため、現地で得られた収益を円に換算する際の為替影響を見込んだ経営計画の策定が重要です。
また、世界経済の景気変動によって輸出が一時的に落ち込む局面では、ベトナム経済全体の成長にもブレーキがかかる可能性がある点にも留意が必要です。
とりわけ、米国・中国・欧州といった主要貿易相手国の需要動向や、関税措置などの通商政策の変化には常にアンテナを張っておくことが求められます。外部環境の変化に柔軟に対応できる体制を整えておくことで、戦略の迅速な見直しやリスク軽減につながります。
まとめ

現在、ベトナム経済は高い成長性と一定の安定性を兼ね備えており、投資環境の整備も着実に進展しています。日本企業にとってベトナムは、製造拠点としての優位性に加え、中長期的には有望な消費市場・技術開発拠点としての魅力も高まりつつあります。
実際、JETROの最新調査では、日系企業の過半数が今後1〜2年以内の事業拡大を計画しており、ASEAN域内でも最も積極的な姿勢が示されています。
一方で、競争環境は年々厳しさを増しており、現地市場での持続的な成長を実現するためには、日本企業ならではの強み――たとえば品質、信頼性、技術力――を活かしながら、ローカル市場への適応と着実なリスク管理が欠かせません。
あわせて、ベトナム政府との良好な関係づくりや、現地社会への貢献といった「共に成長する」姿勢も今後ますます重要になるでしょう。「攻め」と「守り」のバランスを意識しながら、ベトナム市場におけるビジネスチャンスを最大限に引き出していくことが期待されます。
おまけ:ホーチミンの実情は?
タクシー事情
ホーチミン市のタンソンニャット空港に到着すると、まず注意すべきはタクシーです。Grabが利用できないエリアのため、タクシースタンドから車を手配せざるを得ません。しかし、ここでぼったくりタクシーを紹介されるケースがあります。通常であれば15万ドン程度で済むところ、実際には63万ドンを請求されることもありました。到着直後から油断できないポイントです。
24時間の街
セブンイレブンが24時間営業で安心できる存在でした。夜のバックパッカー通りは圧倒的な熱気で、歌舞伎町を超えるほどの派手さに驚かされました。

バイクツアーと学生たちの案内
地元の大学生によるバイクツアーでは、街の隠れた魅力を案内してもらいました。さらにミッドナイトバイクツアーにも参加し、活気あふれるホーチミンを体感できました。

トイレ事情
ベトナムではトイレットペーパーを流せないのが一般的です。代わりに備え付けのシャワーを利用し、紙はゴミ箱に捨てます。旅行者にとっては最初のうちは戸惑いますが、現地のスタンダードに慣れることが必要です。
Web3の可能性、日本人起業家の可能性について
Web3の未来は東南アジアにあるとのことです。日本は規制が厳しい一方で、東南アジアは国家レベルで推進しており、ベトナムだけでもブロックチェーンユーザーは約3,000万人にのぼります。現地のWeb3イベントは1万人規模で、若者は英語力も高く、最近は日本の若者も多く訪れているそうです。さらに、元サイバーエージェント出身者が始めたピザチェーン(「Pizza 4P’s (ピザ フォーピース)」は、ベトナム発祥のピザレストランで、現在ではアジアを中心に32店舗を展開)も成功しており、起業のチャンスに満ちている様子が伺えます。

