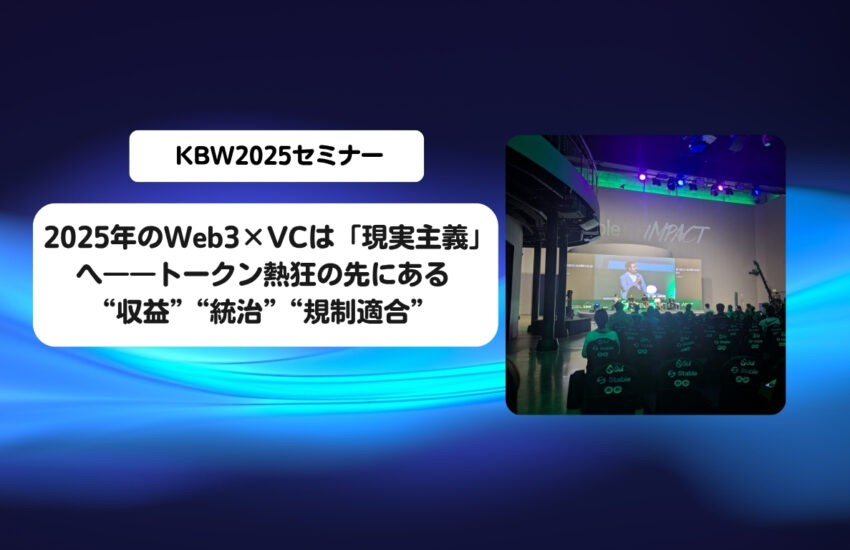〇登壇者プロフィール
Christopher Heymann(クリストファー・ハイマン)
1kx パートナー。技術的バックグラウンドを持ち、複数のスタートアップでCTOを歴任。過去8年間、暗号経済設計やガバナンス、分散型システムのスケーリングを支援。現在は1kxにて、成長を加速させる戦略的助言・技術支援・資金提供を通じて、革新的な暗号プロジェクトを支援している。
Danish Chaudhry(ダニッシュ・チョードリー)
Paper Ventures ジェネラルパートナー兼共同創業者。保険、Web3/ブロックチェーン、フィンテック分野に投資。以前はBlackRockで株式・マルチアセット運用を担当、またBitcoin.com Exchangeを創設・運営した経験を持つ。
Jordi Alexander(ジョルディ・アレクサンダー)
Selini Capital 創業者兼CEO。暗号資産ネイティブの投資会社を率いるほか、ポッドキャスト「Steady Lads」のホストも務める。
Ryan Kim(ライアン・キム)
Hashed 共同創業者・パートナー。シンガポールを拠点に、インフラ、DeFi、ゲーム、エンタメ分野への投資をリード。グローバルネットワークを活用し、起業家支援を行う。KAIST電子工学学士。過去にはSME向けモバイルソリューションLOOKETを起業し、Recobell社に売却した実績を持つ。
Zack Guzman(ザック・グズマン)〈モデレーター〉
Trustless Media 創業者、Coinage ホスト。NFT保有者によるコミュニティ主導型メディアを展開し、Netflix共同創業者からの支援も獲得。元Yahoo Finance・CNBC記者であり、ウォールストリートジャーナルなど多数メディアで執筆。2023年にはTerra崩壊に関するドキュメンタリーでSABEW賞を受賞。
- パネル:2025年、VCはどう価値を創出するか(Panel:How VCs Add Value in 2025)
- 2025年の地合い:循環の「戻り局面」でも、見られるのは“中身”
- VCの価値提供は「小切手」から「伴走」へ
- Web2型とWeb3型VCの「統治」と「開示」は収斂する
- 「Revenue First」——トークンの前に、まず現金売上
- インセンティブの罠を見抜く評価指標
- トークン設計の成熟:ベスティング、TGE、情報非対称の緩和
- “突然の成功”への対処——創業チームの規律と文化
- Debtとトークナイズド国債:資金循環の“土台”を厚くする
- ステーブルコインと規制の潮流:国家・銀行・企業の参画
- 「アプリケーションの時代」:交換所の次に来るもの
- 「36の法域での同時展開」は罠――集中と選択を
- 創業者のための実務チェックリスト(保存版)
- VC(投資家)のための実務チェックリスト
- 2025〜2027年の見取り図:規制は“壁”ではなく“滑走路”
- 結び:熱狂の時代を超え、作法の時代へ
パネル:2025年、VCはどう価値を創出するか(Panel:How VCs Add Value in 2025)

創業者と投資家が押さえるべき実務原則と、次の勝ち筋
2021〜2022年の熱狂期、2023〜2024年の淘汰期を経て、2025年のWeb3は「現実主義」へと舵を切っています。
本記事は、複数の登壇者によるパネル発言をもとに、以下の8つの論点を整理した実務レポートです。
1.VCの“価値提供”の変化
2.Web2型とWeb3型VCの統治・情報開示の違いと収斂
3.トークン依存から収益重視(Revenue First)への資本政策の回帰
4.インセンティブ依存を見抜く「真のPMF」の測り方
5.ベスティング設計とガバナンスの成熟
6.債務(Debt)やトークナイズド国債がもたらす資金循環
7.各地域の規制とステーブルコイン潮流
8.創業者・投資家が今日から使えるチェックリスト
結論はシンプルです。
「測れる収益」「持続可能なユースケース」「規制を味方にする統治」
――これこそが、次の勝ち筋を決定づけます。
2025年の地合い:循環の「戻り局面」でも、見られるのは“中身”
直近の市況は改善基調にあり、資金調達や上場環境も持ち直しています。
しかし登壇者が繰り返し強調したのは、「循環(サイクル)が戻っても、投資家の“見る目”は戻らない」という現実でした。
投資家は、短期的な価格上昇やインセンティブ拡大に踊らされるのではなく、
・実需
・継続的な収益
・規制適合
・情報開示
といった要素を冷静に点検する姿勢へと回帰しています。
その結果、「派手さ」よりも、“実務の手触り”が評価される局面に入っているのです。
VCの価値提供は「小切手」から「伴走」へ
1. 価値提供の中身
VCのコア価値は、資金提供だけにとどまりません。登壇者は次の3点を強調しました。
1.創業支援の同伴者(Co-builder)
採用・技術・Go-to-Market・法務/会計・IR・次ラウンド設計まで、日々の論点を共に解決していく存在。
2.市場アクセスの仲介
CEX/DEX上場、マーケットメイク、PR/メディア、アドバイザー選定、さらには“水面下の政治学”を読み解く力。
3.トラディショナル連携
銀行・証券・決済事業者・大企業・公的機関との接続。とくに韓国などでは、ローカル大手との組成が成否を左右する。
2. 地域横断の「翻訳者」
各国の規制や商慣習は均一ではありません。アジア、欧州、北米で「通る手続」と「通らない手続」は異なり、税制・KYC/AML・有価証券性の解釈にも大きな差があります。
こうした環境下において、“地域間の変換器(トランスレーター)”としてのVCの役割は、これまで以上に価値を増しています。
Web2型とWeb3型VCの「統治」と「開示」は収斂する
Web2の投資契約では、情報権の付与、ガバナンスへの関与、月次・四半期の定期レポーティングが標準です。
一方、Web3ではトークン上場(TGE)が最初の大イベントになりやすく、上場までの透明性が課題とされてきました。しかし2025年には、両者の仕組みが収斂しつつあります。
Web3においても、以下が必須となっています。
・月次のKPI/PL/BSの共有
・資金使途・残高・リスクの定点開示
・ガバナンス提案や投票の透明化
・ベスティング/ロック解除(Unlock)スケジュールの明確化
これにより、不正や“ガバナンスの空洞化”を防ぎ、投資家と起業家の間の信頼コストを低減することにつながっています。
「Revenue First」——トークンの前に、まず現金売上
登壇者は一貫して「トークンは目的ではなく結果である」と指摘しました。
PMF(プロダクト・マーケット・フィット)を測る際に重視されるのは次の点です。
・トークン報酬やエアドロップが途切れてもユーザーが使い続けるか
・売上が安定的に増加し、CAC/LTVが健全化しているか
・解約率(Churn)や有料化転換(Conversion)が改善しているか
インセンティブに支えられた“見かけ上の成長”は、イベント終了後に9割以上が失われる事例も少なくありません。そのため、持続的な収益源を先に確立し、トークン発行は後置するという原則が定着しつつあります。
インセンティブの罠を見抜く評価指標
「トークン・ポイント・エアドロップ」をばらまけば、短期的なアクティビティは上がります。
しかし投資家は、その“実質”を次の指標で見抜きます。
・補助金オフ後の残存率
インセンティブ停止後のDAU/MAU/セッション継続を確認。
・コホート曲線
獲得月別ユーザーの収益・継続率の推移を分析。
・プロダクト由来の粘着性
トークン無関係の利用理由(業務効率、決済コスト削減、UX優位など)。
・ボット/ファーミング検知
ウォレットの共通性や挙動パターンから、合成需要を切り分ける。
最終的に、“素の需要”を立証するダッシュボードこそが、華やかなプレゼン資料以上の価値を持ちます。
トークン設計の成熟:ベスティング、TGE、情報非対称の緩和
初期のブーム期とは異なり、現在ではTGE(Token Generation Event)で即日100%を付与するケースはほぼなくなりました。
一般的には以下の仕組みが導入されています。
・1〜3年のベスティング
・クリフ(据置)期間
・ロック解除の段階設計
これにより、創業チームの短期離脱や市場の撹乱を防止することができます。
加えて、月次での透明なIRを通じて、価格形成の根拠を丁寧に開示することが求められています。
教訓:
「TGE=ゴール」ではなく、「ガバナンスと開示のスタート」である。
“突然の成功”への対処——創業チームの規律と文化
トークン急騰により、エンジニアや初期メンバーが“紙の資産”で七桁規模を手にすることは珍しくありません。しかし登壇者は、それが組織の集中力を損ない、退職や内紛を招くリスクを強調しました。
このリスクに対処するには、次のような仕組みが有効です。
・長期モチベーションを保つ報酬設計
現金報酬に加え、長期インセンティブを組み合わせる。
・売却ルールの整備
ブラックアウト期間やインサイダー規制を明確に設定する。
・“成功ののれん”に依存しない評価制度
実績と成果に基づいた評価を徹底する。
また、創業者へのコーチングもVCが提供できる重要な付加価値のひとつです。
Debtとトークナイズド国債:資金循環の“土台”を厚くする
2025年の注目トピックの一つが、デット(負債)とトークナイズド国債/トレジャリーです。
従来、スタートアップは早期の超成長を狙うためにエクイティを中心に資金を調達してきました。しかし、運転資金や在庫・債権に連動する安定的なニーズは、デットで賄う方が合理的です。
さらに、オンチェーン国債やマネーマーケットの整備が進めば、エコシステム内での安全利回りが確保され、トークン経済の基礎金利として機能します。
ただし、その実現には税務・会計・担保権設定などの実務整備が不可欠です。教育(リテラシー)の普及と、専門チームの組成が鍵を握ります。
要するに、
・成長のガソリン=エクイティ
・走行の潤滑油=デット
を適材適所で組み合わせることが、資本効率を押し上げる決め手となります。
ステーブルコインと規制の潮流:国家・銀行・企業の参画
各国・各地域では、ステーブルコインの制度化が進み、公的機関や大手金融プレイヤーの参画が相次いでいます。その結果、銀行・大手決済事業者・公共機関が、Web3の“正面入口”に立ち始めています。
具体的には、次のような動きが見られます。
・国家・中央機関主導の安定通貨構想
・銀行によるトークン化預金やカストディ提供
・企業発行の“社内通貨/サプライチェーン通貨”
これらの仕組みは、個人投資家頼みのボラティリティを抑え、アプリケーション層の実装を後押しします。
登壇者は一貫して、規制の明確化は“リスク”ではなく“機会”であり、政府や大手企業と正面から組むことが不可欠だと強調しました。
「アプリケーションの時代」:交換所の次に来るもの
これまで最も成功したWeb3プロダクトは取引所(Exchange)でした。その次に求められるのは、アプリケーション層です。
注目分野は多岐にわたります。
・決済・送金・給与・サプライチェーン・ロイヤルティ
・データ/ID・証跡・権利流通・実世界資産(RWA)
・ゲーム/メディア/ファンエコノミー
規制が整いつつある今こそ、“誰もが毎日使う”実用品をつくる好機です。抽象化されたUI/UXと法規制適合を前提に、Web2の便利さを超える体験を提供できるかが次の勝負どころになります。
「36の法域での同時展開」は罠――集中と選択を
グローバルを狙う創業者ほど、“同時多発”に走りがちです。しかし登壇者は、規制が明確で、協業パートナーが存在する法域に集中することを強く推奨しました。
具体的には次のアプローチが効果的です。
・2〜3法域で深く実装し、その後に横展開
・ローカル・エコシステム(銀行・通信・決済・監督当局)との早期ハンズオン連携
・準拠法・管轄・データ移転の先回り設計
こうした集中と選択により、失敗コストを決定的に下げることができます。
創業者のための実務チェックリスト(保存版)
〔戦略・PMF〕
☐ トークン抜きでも使われる理由(時間短縮・コスト低減・規制対応・UX優位)が説明できる
☐ 売上/KPIの計測計画(DAU/MAU、リテンション、ARPU、Churn、CAC/LTV)を月次で回す
☐ インセンティブ停止時の残存率を検証するA/B設計を組み込む
〔ガバナンス・開示〕
☐ 月次レポート(BS/PL/キャッシュ、KPI、リスク、採用状況)を投資家・コミュニティに定期開示
☐ ベスティングとクリフ、ロック解除カレンダーを公開
☐ 意思決定プロセス(理事会/DAO/委員会の権限)を文書化
〔規制・法務・会計〕
☐ トークンの有価証券性に関する外部意見書/論点整理を取得
☐ KYC/AML・データ保護・越境移転のポリシーを明文化
☐ 監査人・法律顧問のアサインと費用計画を策定
〔資本政策〕
☐ エクイティ×デットの比率と使途を明確化
☐ トークナイズド国債や安定運用枠の検討(トレジャリー運用)
☐ 資本効率KPI(NRR、キャッシュコンバージョンサイクル等)の設定
〔人・文化〕
☐ 売却ルール・情報管理(ブラックアウト期間・インサイダー規制)を明示
☐ 現金/長期報酬のバランス設計で“突然の成功”による揺らぎに備える
☐ 価値観・倫理規定を明文化し、採用・評価制度に組み込む
VC(投資家)のための実務チェックリスト
〔デューディリジェンス〕
☐ 素の需要の証跡:インセンティブに依存しない利用の有無
☐ 規制地図:主要法域での適法性・許認可・リスクの整理
☐ 人材の粒度:創業陣の補完性、キーパー人材のリテンション設計
〔伴走計画〕
☐ 採用・営業・法務まで踏み込む伴走設計
☐ ローカル・パートナー網(銀行・CEX/DEX・監査・PR)
☐ 次ラウンドの可視化:里程標(マイルストーン)/KPIとタイムラインの明確化
〔ガバナンス〕
☐ 情報権・保護条項をWeb3においても明確化
☐ TGE後の開示・投票ルールを事前に設定
☐ 利益相反管理:マーケットメイク/上場/マーケティングに潜む“見えない力学”を透明化
2025〜2027年の見取り図:規制は“壁”ではなく“滑走路”
規制の明確化は、大手企業や公共機関との正面からの連携を可能にし、アプリケーション層の需要を押し上げます。
・Debt/国債トークナイズはエコシステムに金利の基盤をもたらし、資本効率を高める。
・統治と開示はWeb2標準に収斂し、“正しく地味”な運営が最終的に評価される。
・トークンは目的ではなく結果となり、Revenue Firstの考え方が定着する。
合言葉は 「測る・開示する・守る」。
すなわち、測れる収益で事業を築き、開示によって信頼を積み重ね、規制を守ることで市場を広げる。これこそが、循環がどう変わろうとも勝ち筋から外れない最短距離です。
結び:熱狂の時代を超え、作法の時代へ
Web3は、もはや“賭け”ではなく、作法(オペレーティング・システム)の勝負へと移行しました。
収益で語り、統治で支え、規制で広げる。VCは「小切手を書く人」から「現場をともに走る人」へ。創業者は「トークンの夢」から「顧客の現実」へ。
2025年、私たちはようやく持続可能な成長曲線の起点に立っています。
プロダクトの当たり前を積み上げ、ガバナンスの当たり前を守り、規制の当たり前を味方につける。
――その先にこそ、循環に左右されない“本物の価値”が残ります。