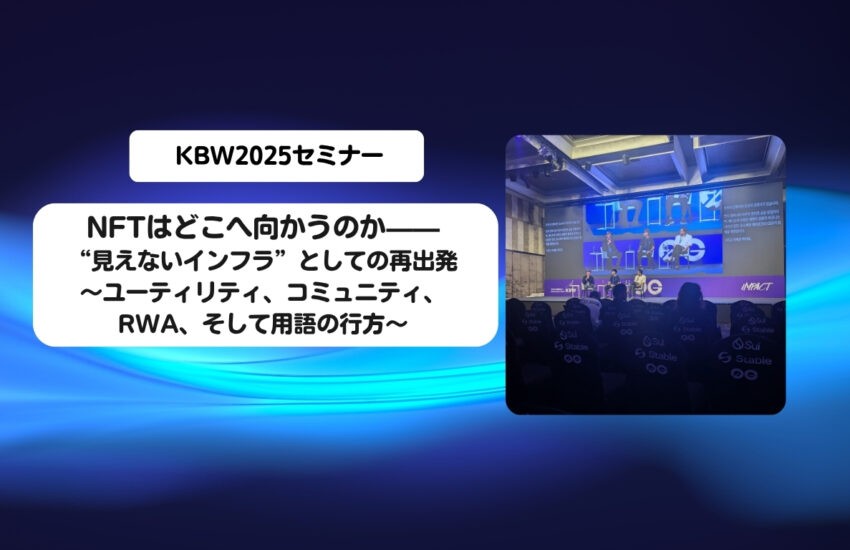〇登壇者プロフィール
Cameron Kates
ApeCo CEO。ApeCoinの財務運営を統括し、ApeChainや開発者主導のエコシステム拡大をリード。元Latham & Watkins弁護士で、2016年から暗号資産分野に従事。Yuga Labsでは最高法務責任者・最高事業責任者として「Made By Apes」を立ち上げ、ApeChainの展開を推進。
Yusuke Jindo
Animoca Brands Japan CFO兼バリデータ事業責任者。明治大学在学中に公認会計士試験で首席合格。Deloitteを経て、Mercoinでビットコイン取引サービスや暗号資産交換業ライセンス取得を担当。2024年よりAnimoca Brands Japanに参画し、財務・投資・戦略を統括。日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)の税制部会でも活動。
Joshua Kriger(Moderator)
The Edge of Company / Outer Edge 共同創業者。ロサンゼルスを拠点に、Web3・AI・ブロックチェーンに関する番組「Edge of NFT」「Edge of AI」を共同ホストし、25万以上の視聴者にリーチ。Outer Edge LAやRiyadhなどの国際イベントを共催し、教育・エンターテインメント・戦略支援を融合した活動を展開。元ビッグ5コンサル出身で、フードテックやeコマースの起業経験も持つ。
- パネル:デジタルアートは死んだのか?NFTとWeb3時代の知的財産の未来(Is Digital Art Dead? NFTs and the Future of Web3 IP)
- 市場の現況:ボラティリティの“次”にある地盤沈下と地盤固め
- ブルーチップの底打ち観:価格ではなく“持続性”に注目
- ユーティリティへの回帰:NFT=体験のハブ、金融のハブ、データのハブ
- “見えないNFT”:ユーザーにブロックチェーンを意識させない設計
- RWAとの関係:言葉は変われど、本質は“権利のデジタル表現”
- 規制サンドボックスと“ローカル・パートナー”戦略
- コミュニティの現実:多層化の把握と“能動運営”への回帰
- 日本・韓国・アジア発のIPはどう活きるか
- “NFTという言葉”の未来:2030年には背景化するのか
- 来年(1年後)への大胆予測:ヘルスケア×NFT、RWAの“入口”としてのNFT
- 実装の勘所:プロジェクトが明日から点検すべき7項目
- 「NFTはインフラへ」——再定義の構図
- “用語の外側”で勝つ:言葉よりも価値、価値よりも習慣
パネル:デジタルアートは死んだのか?NFTとWeb3時代の知的財産の未来(Is Digital Art Dead? NFTs and the Future of Web3 IP)

NFTは終わったのか——。
2021〜2022年の熱狂と、その後の冷却期を経て、2025年のソウルに集った登壇者たちが語ったのは、落胆ではなく「次のフェーズ」への確かな手応えでした。彼らは「市場規模は縮小した」と断じつつも、「本来の役割に回帰している」との見方が広がりつつあります。
今回のパネルでは、NFTの“文化”と“実装”の再定義、RWA(実世界資産)との接点、規制対応の現状、コミュニティ運営の再設計、さらには用語そのものの未来まで、多彩な具体例を交えて掘り下げられました。
本稿では、そこで交わされた示唆を整理し、「NFTは“見えないインフラ”になる」というキーメッセージを中心に、来年から2030年にかけての見取り図を描き出します。
市場の現況:ボラティリティの“次”にある地盤沈下と地盤固め
登壇者は冒頭、最新のマクロ指標を共有しました。2025年のグローバルNFT市場規模は約490億ドルに達する一方、「NFTにとっては最も厳しい年」との評価も示されました。セクター別ではゲーム関連NFTが全取引の約38%を占め、韓国は世界投資の約8%を担い、日本でもデジタルNFTの流通が年初来で約60%増加したといいます。もっとも、総取引量(ボリューム)は数十億ドル規模から約7億ドル前後へ縮小しており、「熱狂」から「実需」への“移行期”にあることは疑いありません。
この“縮小”を否定的に捉える向きもありますが、登壇者のトーンは総じて前向きでした。供給過多と短期売買の出口戦略偏重が一巡し、「価値を創らず価値を回収するだけのプロジェクト」が自然淘汰された点をむしろ歓迎する声が目立ちました。残ったプレイヤーが“次の5年”を設計するフェーズに入っているというのが、現場の共通認識です。
ブルーチップの底打ち観:価格ではなく“持続性”に注目
議論はブルーチップ・コレクションの現況にも及びました。主要コレクションの一つでは、最悪期に約3万ドルまで下落した個体価格が、現在は4万ドル程度に回復したと共有されました。登壇者は「底打ちを示す指標が複数出ている」と指摘しました。具体的には、
・市場全体の購入者数と出来高が減る局面でもコア層が維持されたこと、
・オフチェーンを含むコラボレーションやIP展開が継続している点、
・“保有の意味”を再設計する取り組みが芽生え始めたこと、
などが挙げられました。
強調されたのは「価格の回復=健全化」ではないという視点でした。むしろユーティリティの着実な積み上げ、IPの持続的運用、コミュニティの分化と深化といった“インフラ的な積層”が、長期の安定性を生むと語られました。
ユーティリティへの回帰:NFT=体験のハブ、金融のハブ、データのハブ
2021年の主役だったPFP(プロフィール画像)は、今も文化的存在感を保ちつつ、「NFT=ユーティリティ」への転換が加速しています。登壇者は次の領域を重視していました。
・ゲーム:アイテムやスキン、進行度、ライセンスの権利を表すNFT。
・チケッティング:真正性と二次流通の透明化、転売ルールのスマートコントラクト化。
・メンバーシップ/ロイヤルティ:「航空マイル的な仕組み」をNFTで再設計。
・財務ユーティリティ:UniswapのLPポジションがNFTで表現されるように、所有権の単位としてNFTを使い、担保・ステーキング・二次利用の選択肢を拡張。
・データハブ:ウォレット=IDという発想で、行動・嗜好・所属などの「参加の軌跡」をNFTで受け止める。
ここで繰り返し出たキーワードは、「NFTは“見せ物”ではなく“ハブ”である」という考え方です。見せるためのNFTから、接続するためのNFTへ。体験(イベント・ファンクラブ)、金融(担保・分配)、データ(参加履歴)の結節点として機能することで、毎日の生活や事業運営の基盤に静かに溶け込むのだといいます。
“見えないNFT”:ユーザーにブロックチェーンを意識させない設計
パネルでは、有名アーティストのファンクラブ基盤をNFTで裏打ちする最新事例も共有されました。特徴は、ユーザーがNFTを意識せずに利用できる点にありました。会員証・ポイント・限定アクセスは従来どおりのUIで提供され、その裏側で真正性・譲渡・履歴・分配をNFTが支えます。
このアプローチは大手ブランドの再挑戦にもつながります。過去には「NFTである」と過度に強調しすぎた結果、期待値と実益のギャップを生み、期待はずれに終わるケースもありました。今後は、
・「NFTであること」を前面に出さない
・既存コミュニティ(顧客基盤)の深化に活用する
という原則に沿った堅実な適用が主流になるだろうと語られました。
RWAとの関係:言葉は変われど、本質は“権利のデジタル表現”
数年前、分割所有(フラクショナル化)は規制上の論点から拡大が止まりました。しかし今、それに近い思想がRWA(実世界資産)として再浮上しています。登壇者は「5年前ならRWAは“NFT”と呼ばれていたかもしれない」と振り返りました。
ただし、法制度の未整備が依然として最大の障壁です。たとえば不動産。NFTの所有権が法的所有権の移転とその効力にどこまで直結するのか。日本ではブロックチェーン上の移転記録だけでは権利移転が成立しない場面がなお多く、紙の登記や補完的な手続きが必要です。
米国でも商法体系の改正(UCC)など議論は続くものの、“法の言語”と“ブロックチェーンの言語”を接続する橋の構築には、もうしばらく時間がかかりそうです。
結論として、RWA×NFTは技術と制度という両輪が噛み合ったときにこそ真価を発揮します。低リスクの分野(高額アートの持分記録、設備や在庫のトークン化、イベント収益の分配設計など)から適用が広がるとの見立てが示されました。
規制サンドボックスと“ローカル・パートナー”戦略
米国では暗号資産事業者の試行を認める「サンドボックス」構想が発表され、安全な実験環境が整いつつあると指摘されました。ただし、国ごとに制度設計や運用が異なるため、現地のパートナーと組んでビジネス慣習と規制の特性を活かすことが、失敗コストの最小化につながります。
セッションでは、韓国進出に際しローカルVCやスタジオと密接に連携し、落とし穴を回避している具体例が共有されました。
要するに、「グローバル×ローカル」の二層設計が鍵だということです。技術・IP・運用のグローバル標準を持ちながら、制度・商習慣・UXはローカルに最適化する——この両立こそ、NFTの再加速に不可欠だといいます。
コミュニティの現実:多層化の把握と“能動運営”への回帰
NFTの初期成長は、コロナ禍という特殊な環境が追い風でした。在宅時間の増加で多くのDiscordに参加することができた一方で、日常が戻った今は“25コミュニティ同時参加”が現実的ではない——これが冷静な自己認識です。
登壇者は、“コミュニティ=単数”という幻想を捨てるべきだと提案しました。参加動機は多様で、
・人とのつながりを求める人、
・ステータスを重視する人、
・限定的な体験(オフラインイベントなど)に価値を置く人、
・金融的リターンを期待する人、
といったサブグループに分かれているのが実態です。誰に何を届けるのかを明確にしなければ、総花的な企画は響かないといいます。
また、「NFTを発行すればコミュニティが自然に生まれる」という考え方は誤りです。
運営自体を“プロダクト”と捉え、更新・企画・対話を継続的に回す能動的な運営こそが、リピート率やロイヤルティを高める王道だと強調されました。
日本・韓国・アジア発のIPはどう活きるか
日本のマンガ/アニメIPは世界的に強い資産です。ただし権利者側の慎重姿勢から、ブロックチェーンやNFTの文言を前面に出さずに「デジタルコレクティブルの新体験」として先に提示する工夫が奏功した事例が紹介されました。テレビCMを使い大衆へ広げる際には、技術語ではなく体験ベースの言葉で伝えるのが有効だといいます。
韓国ではゲームと音楽がNFTの実装と相性が良く、ファンコミュニティの熱量をアクセス権・投票権・限定特典に変換する仕組みづくりが進んでいます。「NFTを見せずに使う」という発想は、アジア発の大衆展開において特に重要だと指摘されました。
“NFTという言葉”の未来:2030年には背景化するのか
「2030年に“NFT”という言葉は残っているか」。この問いに対し、「背景化しているだろう」という見方が優勢でした。TCP/IPを誰も意識せずインターネットを使うように、ERC-721/1155といったプロトコルは基盤として静かに動き、ユーザーはコレクションや会員証、チケット、ポイントといった「体験のラベル」だけを目にする世界になるといいます。
技術が成熟すればするほど、その名前は前面から消えていく——テクノロジーの歴史に繰り返されてきた現象が、NFTにも訪れるだろうという見立てです。
来年(1年後)への大胆予測:ヘルスケア×NFT、RWAの“入口”としてのNFT
パネルの締めくくりでは、1年後(2026年)にNFTはどう動くかが問われました。登壇者からは、
・ヘルスケア/バイオテック/サイエンス/宇宙/量子など、高い信頼性の根拠提示が求められる領域において、出自証明(Proof of Origin)や真正性担保の仕組みとしてNFTが活用される、
・RWA・ステーブルコイン・決済など本丸インフラに向かう入口として、NFTが権利表現・会員認証・担保記録を担い、“地味だが欠かせない”役割を広げていく、
といった予測が示されました。「派手な打ち上げ花火よりも基礎工事」。この堅実なトーンこそが、現場の空気を端的に示していました。
実装の勘所:プロジェクトが明日から点検すべき7項目
登壇者の示唆を、プロジェクト運営のチェックリストに落とし込みます。
1.「見せない設計」
NFT・ブロックチェーンの技術語はUIから排除し、会員証・チケット・ポイント・限定アクセスといった体験ベースの言葉で伝えます。
2.ユーティリティの明文化
「何ができるのか」を5W1Hで仕様化します(誰に、いつ、どこで、何を、どのくらい、どうやって)。更新周期とKPI(利用率・再訪率・直帰率・NPS)を明確に設定します。
3.コミュニティの分節化
参加動機別にサブグループを設計し、それぞれに適した「呼び水」(限定体験/情報先出し/貢献称号/高頻度交流)を用意します。
4.データ・IDの設計
ウォレット=IDを前提に、参加・貢献・購入・来場などの参加履歴をNFTでハブ化。プライバシー配慮と開示範囲のルールを明文化します。
5.RWA・金融ユースの初動
まずは法務リスクの低い領域での権利表現(限定特典の譲渡ルール、LPポジションの可視化、分配ログの自動化)から着手。司法書士・弁護士との連携を早期に組み込みます。
6.規制マップと現地連携
進出国の規制・税制・商慣習をまとめた1枚図を作成し、現地パートナー(スタジオ、VC、代理店、監査法人)と運用設計を調整します。
7.運営=プロダクト
発表→反応→改善の小さなサイクルを毎週〜隔週で回します。「運営ログ」を公開し、検証可能性を高めます。
「NFTはインフラへ」——再定義の構図
セッション全体を俯瞰すると、NFTは次の3つの軸で「見えないインフラ」として再定義されていました。
① 文化のハブ
ファンコミュニティ、IP、イベント、クリエイターエコノミーの「接続の繊維」として機能します。会員権・入場権・投票権・称号など、文化的インセンティブの共通フォーマットです。
② 金融のハブ
所有権の単位として、担保・分配・ポジション移転の記録を担います。LPポジションNFTのように、可視化から二次利用への道を開きます。
③ データのハブ
IDとしてのウォレットに、参加・購買・貢献の履歴を集約。ロイヤルティ設計やパーソナライズの基盤を築きます。
この三位一体が回り始めると、NFTは「持つこと」が目的ではなく、「何を動かすか」が目的になります。「保有」から「運用」へ。これが2025年の現場が見ている光景です。
“用語の外側”で勝つ:言葉よりも価値、価値よりも習慣
「NFTという言葉は消えるか」。登壇者の答えは「消えても構わない」というものでした。ここに、プロダクト思考と実務主義への明確な転換を見ることができます。
大切なのは、名称ではなく「価値」です。さらにいえば、価値よりも「習慣」です。ユーザーが意識せず繰り返し使い、「使わないと不便」と感じる段階まで浸透するかどうか。その閾値を超えた技術だけが、本当の意味で社会のインフラになります。NFTは今、まさにそこに向かっています。