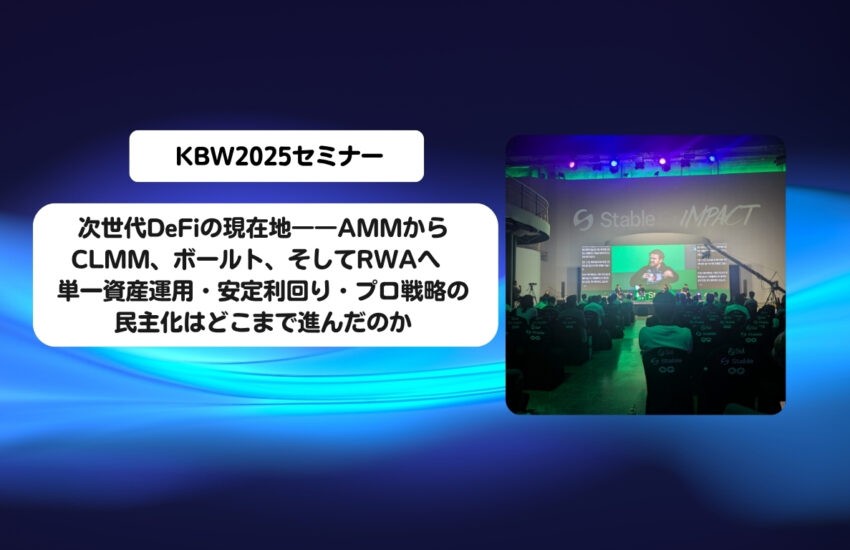Adrian Brink
Anoma 共同創業者。分散型プライバシー技術を開発するプロトコルAnomaを率いる。以前は Tendermint(Cosmos)でコア開発者兼パートナーシップ責任者、Web3 Foundationではテクノロジストとして勤務。Proof-of-StakeバリデータCryptium Labsや研究開発チームMetastateの共同創業者でもあり、ZK暗号やプロトコル設計に精通。
David Sneider
Lit Protocol共同創業者。分散型アカウント・アクセス制御ネットワークを構築し、AIエージェントウォレットやクロスチェーン通信を支える基盤を提供。前職のスタートアップはLinkedInに買収された実績を持つ。
Carter Feldman
Psy Protocol創業者兼CEO。ティーンエイジャー時代からハッカーとして活動し、Web3の原点である「スケーラブルで信頼不要なインターネット」の実現を掲げる。ユーザー主権を重視した分散型技術の開発をリードしている。
David Gan(Moderator)
Inception Capital創業者兼ゼネラルパートナー。2016年以降、Arbitrum、Lido、Circleなど主要プロジェクトに投資。Forbes「30 Under 30 Asia」選出。東西の橋渡し役として、ブロックチェーン領域の起業家やファンドマネージャーを支援している。
パネルディスカッション:DeFiの未来を定義するもの(This Is What Defines DeFi’s Future)

AMMの「次の一手」を探る
DeFiはAMM(自動マーケットメイカー)の登場で一気に大衆化しましたが、その後はボラティリティや無常損失(インパーマネントロス)、ガス代、MEVなどの現実的制約と向き合うフェーズに入っています。
こうした課題に対して、単一資産で参加できるプールや、プロトレーダーの運用戦略をパッケージ化するボールト、さらにはRWA(実世界資産)による安定的な利回り源など、次の選択肢が現れています。
本稿では、登壇者の発言をもとに、
(1)AMMの次世代像
(2)単一資産プールの台頭
(3)CLMMとプロ向け流動性提供
(4)ボールトによる戦略の民主化
(5)高速チェーンの実務論点
(6)RWA・プライベートクレジットの役割
の6点を整理し、個人投資家と事業者が“どこで・どう参加するか”をわかりやすく解説します。
AMMの次世代像:単一資産・モデル駆動・安定志向へ
従来のx*y=k型AMMは「二資産を常に50:50」で預けるシンプルさが魅力でした。一方で価格変動が大きいと無常損失が顕在化し、手数料収入で相殺しきれない局面も増えます。こうした背景から、次のような「より安定的で、モデル駆動」の設計が注目されています。
・単一資産(Single-Asset)型の流動性提供
預け入れは1銘柄のみ。プール側でデルタ中立(価格変動中立)を目指すヘッジや再均衡を行い、LPは価格リスクを抑えつつ手数料やインセンティブを狙います。
・モデル駆動(Quant)・ボールト戦略ボラティリティ・流動性・スプレッドを見ながら、動的レンジ配分やヘッジを自動化。
人手の裁量を極力排し、一貫したルールで期待収益を積み上げるアプローチです。
・“安定だが100%固定ではない”利回り
マーケット状況に応じて変動しますが、従来型より利回りのブレを抑える設計が志向されています。
事例:単一資産ボールト「OmniVolt」と複数プール運用
登壇者は、こうした潮流を体現する具体例としてOmniVoltに言及しました。要点は以下です。
【OmniVoltの仕様(概要)】
・約2,000万ドル規模、30以上のチェーンでアクセス可能
・実績EPR(利回り)28%前後(発言時点)
・トータル手数料は約20bp(0.2%程度)で抑制
・6カ月のドローダウン耐性を確認済み
・Chronos Researchが連携し、戦略のCEFI連携・ヘッジを組み合わせている点が特徴
また、別のプロジェクトからは次のようなプール群が紹介されました。
・ステーブルコイン単一資産プール(約20%)
単一のステーブル資産で参加し、価格変動リスクを抑制。LPは「ステーキング報酬+手数料」を享受します。
・ネイティブトークン偏重プール(最大90%の比重)
プロジェクト支持者向けにネイティブトークンの配分を高めたLPを提供。エミッション調整で利回りと需要のバランスを取ります。
・ETC(Ethereum Classic)プール(約3%)
他チェーン・他銘柄の安定運用も並行して増やし、発行体やCEXのステーブル発行主体とも連携。手数料・金利の動的調整で利回りの安定性を高めています。
・デルタニュートラル/ノート戦略の導入検討
裁定・先物ヘッジ・オプションデルタ調整などを組み合わせ、金利・手数料をベースに横ばいで積む“ボラ抑制型”の収益源を拡充しつつあります。
ポイント:いずれの事例も、「単一資産で参加できること」「利回りの安定性」「戦略の見える化」を重視し、LPの心理的ハードルを下げています。
CLMM(集中流動性AMM)とプロ向け流動性提供
Uniswap v3以降で普及したCLMM(Concentrated Liquidity Market Maker)は、価格帯を指定して流動性を集中配分できるため、資本効率が高い一方、運用の難易度が上がるというトレードオフがあります。登壇者は次の論点を挙げました。
・表現力と柔軟性は高いが、運用は高度
レンジ設定や再配分のタイミング、ガス・手数料、ボラティリティ対応など、プロのマーケットメイカー(MM)に向く設計です。
・プロの純オンチェーン運用はコストが重い
優先手数料(Priority Fee)やMEV対策、注文競争など、常に競り合いになります。利益の安定確保が難しい局面もあります。
・ボールトで「プロ戦略の民主化」
こうした高度な運用をボールト(Vault)として戦略パッケージ化し、個人がシェアクラスのように乗れる形へ。“プロの裏側”を間接的に活用できるようになります。
要するに:CLMM自体は難しくても、ボールトが“使いやすさの皮”を被せることで、個人でも使えるフェーズに入りつつあります。
高速チェーンでも油断は禁物:レイテンシ、手数料、約定の現実
登壇者はSolanaを例に、「速いチェーン=すべて解決」ではない現実を率直に共有しました。
・ブロックタイムは速いが、優先手数料が重くなると競争が激化
実効的には200〜400ms級のレイテンシでも、超高速の順張り・逆張りが密集し、オンチェーンで常時勝ち続けるのは容易ではありません。
・CEXのFIFO(先入れ先出し)文化との差
伝統的なマーケットでは約定ルールや順序が明確で、高頻度取引の作法が確立しています。オンチェーンはブロック生成と手数料の駆け引きが重なり、別種の最適化が必要です。
結論:利益を安定化するには「設計」が肝心
レンジ管理・ヘッジ・ルーティング・ボラティリティ対応・手数料設計など、技術×市場の総合設計で戦う必要があります。ここでもボールト化が有効です。
「コストの絶対主義」:DeFiが勝つための最重要KPI
複数の登壇者が強調したのは、コスト(原価)こそがDeFiの“勝ち筋”だという点です。
・過去:LLM推論の原価が代替モデルの200倍に達した時期も
その差はユーザー体験では埋まりません。無料や薄利で勝負するには、徹底した単価引き下げが不可欠です。
・安価GPUのプール化で「分散=高い」を覆す
中古30xx世代などの分散GPUを市場化し、需要に応じた動的アロケーションを行うと、CEXやクラウドに対しても推論原価を大幅圧縮できます。
・DeFiの価値は“公開市場で叩ける単価”
価格シグナルが明確に働くため、誰でも最安・最良を選べるようになります。アルファよりまず原価、という実務姿勢が鍵です。
RWA(実世界資産)とプライベートクレジット:安定利回りの“土台”
暗号資産だけに依存した利回りは、相場やエミッションの影響を受けやすい課題があります。そこでRWA、とくにプライベートクレジット(事業者向けの貸付)が注目されています。
・オンチェーン化で効率化
審査・貸付・回収・証票管理をオンチェーンに載せることで、コストと不正リスクの低減を図ります。
・eFiat・ステーブルとの親和性
法定通貨連動資産やオンチェーンの現金同等物と組み合わせれば、為替・価格変動の影響を極小化し、“利回り=信用スプレッド”というシンプルな世界観で設計できます。
・PMF(プロダクト・マーケット・フィット)が明快
事業者側は資金を必要とし、投資家側は安定収益を求める。両者をスマートコントラクトでつなぐことで、手数料の透明化・配分の自動化が進みます。
留意点:RWAは法規制・KYC/AML・情報開示と不可分です。ここをおろそかにすると事後コストが爆発します。規制適合の設計とパートナー選びが肝要です。
投資家・発行体が押さえるべき実務チェックリスト
1. 投資家(LP)向け
1.商品設計:単一資産か、二資産か。デルタ中立やヘッジの仕組みは明示されているか。
2.利回りの質:手数料収入/インセンティブ/裁定益の内訳と持続性。ドローダウンの過去実績はあるか。
3.手数料の透明性:管理手数料・パフォーマンスフィー・取引コストの合算を年率換算で把握する。
4.リスク管理:無常損失、スマコン脆弱性、カストディ、流動性枯渇、デペグ、清算連鎖の想定シナリオを確認。
5.開示と監査:戦略レポート、オンチェーン指標、第三者監査、保険の有無。異常時の連絡手順。
2. 発行体・運営者向け
1.戦略のボールト化:高度なCLMM運用やヘッジをプロダクト化し、UI/UXで難易度を下げる。
2.コストKPI:1ドル当たりのスループット、1取引当たりの原価、スリッページ損益を定点観測。
3.チェーン選定:レイテンシ×手数料×ツールチェーンの総合点で最適化。ブリッジとリスク分散の設計を。
4.RWA連携:法務・会計・KYC/AMLの枠組みを早期に固め、“規制優等生”としての信用を積み上げる。
5.コラボレーション:CEX、マーケットメイカー、ステーブル発行体、監査法人、保険などエコシステム連携を強化。
よくある疑問にまとめて回答
Q1.単一産プールは本当に“安全”ですか?
A. 価格変動リスクは低減しやすい一方、スマートコントラクト・相手先・デペグなど別種のリスクは残ります。「何のリスクが、どこまで減るのか」を把握し、分散投資で備えることが大切です。
Q2.CLMMは個人でも使えますか?
A. 直接の運用は難度が高いです。ボールト経由で戦略に乗るか、学習用の少額運用→実運用へ段階を踏むことをおすすめします。
Q3.高速チェーンならMMで勝ちやすいですか?
A. 競争はむしろ熾烈です。優先手数料やMEV、設計の巧拙が結果を左右します。“速さ”だけでは勝てません。
Q4.RWAは何から始めるべきですか?
A. 信頼できる発行体・KYC基盤・監査体制が整った案件から。利回りの源泉(信用スプレッド)と回収メカニズムが明確なものを選ぶべきです。
まとめ:DeFiは「プロの設計」をプロダクトに埋め込む段階へ
・AMMの次世代は、単一資産・モデル駆動・安定志向に向かい、ボールトが“プロの戦略”を民主化しています。
・CLMMは資本効率が高い反面、運用の難度と競争コストが上がります。個人はボールトを活用し、運営側はボールト化でUXを磨くのが現実解です。
・高速チェーンでも設計が命。レイテンシや手数料の最適化、ルーティング、ヘッジを含めた総合設計が必要です。
・RWA・プライベートクレジットは、安定利回りの“土台”として機能します。規制適合と開示で信頼を積み上げ、オンチェーンの資金循環を太くします。
そして何より、“コストの絶対主義”。原価を測り、叩き、可視化することが、DeFiが長期的に選ばれる最大の理由になります。
最後に、投資家の方には「利回りの質(持続性)」「手数料の総額」「開示と監査」の三点を、運営者の方には「ボールト化」「コストKPIの定点観測」「規制適合の先回り」の三点を強くおすすめします。
DeFiは、もはや“実験”ではありません。プロの設計をプロダクトに埋め込み、誰もが使える形にする。この地に足のついた進化こそ、次の強気相場でも弱気相場でも、選ばれ続けるプロトコルの条件になるはずです。