地方創生の文脈で「工場誘致」は古典的施策と見なされがちですが、半導体・電子部材・化学素材といった先端製造の波を取り込み、いま再び強い成長ドライバーとして機能しています。
実際、熊本県菊陽町のTSMC、岩手県北上市のキオクシア、北海道千歳市のRapidus、茨城県茨城町の着実な集積など、各地で雇用・投資・地価上昇といった成果が可視化される一方、交通や住宅、教育・医療など“暮らしの器”の整備遅れという副作用も浮き彫りになりました。
本稿では、主要事例を俯瞰しながら、効果の実相と課題、成功の要点(インフラ前倒し・人材育成・地元調達の多層化・環境配慮)を整理します。結論を先に言えば、工場誘致は「いまも有効」。ただし、単発の立地獲得ではなく、受け皿の設計と関連産業を束ねる“複線型”の都市・産業戦略こそが、持続的な地域価値を生む決定要因です。
地方活性化における工場誘致の成功事例
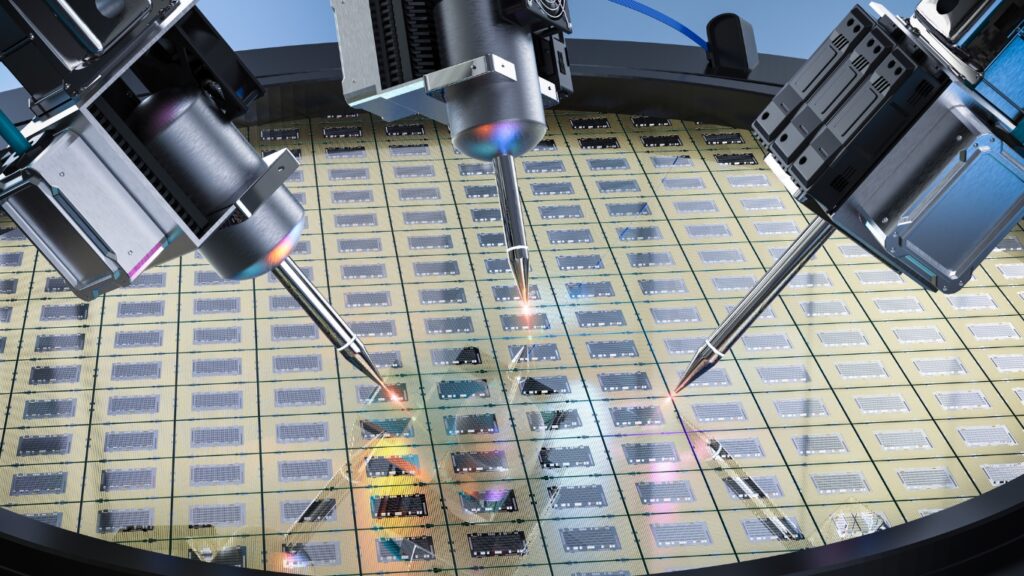
近年、全国各地で半導体や電子部材、化学素材などの先端製造業による工場誘致が活発になっており、地域の雇用や投資、地価の上昇といった効果が広がっています。以下では、その主な事例をご紹介いたします。
1.熊本県・菊陽町におけるTSMC効果

台湾の半導体大手TSMCは、熊本県菊陽町において、日本法人JASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)による第1工場を建設し、2024年12月に本格稼働、2025年1月には量産開始を予定しています。このプロジェクトをきっかけに、地域の経済やまちの景観は大きく変化を遂げています。
地場シンクタンクの試算では、今後10年間で少なくとも20兆円の経済波及効果が見込まれており、TSMCの進出がもたらすインパクトの大きさが注目されています。
実際の効果:雇用・投資・地価の上昇
菊陽町周辺では、企業進出にともなって雇用が創出され、関連企業の投資も活発化しています。これに加えて、不動産市場にも変化が表れ、2025年時点で工業用地の基準地価が前年比+12%の上昇を記録しました。
1.新たな雇用機会の創出(JASM直接雇用に加え、協力企業の人材需要も拡大)
2.周辺不動産の開発促進(賃貸・分譲の需要急増)
3.飲食・小売・医療など生活関連産業の成長
これらの波及効果により、地域全体の経済活動が活性化しています。
課題:インフラ遅れと渋滞の深刻化
一方で、急激な人流・物流の増加により、交通渋滞などの副作用も顕在化しています。特に、工場関係者や建設業者の車両が集中することで、朝夕の通勤時間帯を中心に深刻な渋滞が発生しており、地域住民の日常生活にも影響を与えています。
このような背景から、JASM第2工場(フェーズ2)については、周辺インフラの整備が間に合っていないことが要因となり、着工時期の見直しが報じられました。これを受けて、町や県では道路整備や公共交通の再編を急ピッチで進めています。
成功のポイントと教訓
熊本・菊陽町の事例は、工場誘致が地域経済に大きな成長の可能性をもたらす一方で、「暮らしの器」の整備が追いつかないと副作用も大きくなることを教えてくれます。
・誘致前からのインフラ整備の工程化
・交通・住宅・教育・医療の受け皿整備
・第1フェーズだけでなく、その先の展開を見据えた“複線型”の都市設計
これらを意識した“先読みのまちづくり”が、今後の成功を左右する鍵となるでしょう。
2.岩手県・北上市におけるキオクシアほか製造業の集積
岩手県北上市では、半導体大手キオクシアの北上工場(K2棟)を中心に、多様な製造業の集積が進み、市の経済活性と雇用創出が加速しています。特にAI・データセンター需要の高まりを背景に、同工場では最先端のフラッシュメモリを量産する体制が構築され、2025年9月に第2製造棟が稼働開始しました。
地域経済への波及効果と成長性
キオクシアの新工場(北上工場第2製造棟)では、第8世代(218層)3D NAND(BiCS FLASH 第8世代)を念頭に置いた量産体制を整備しており、2026年前半には本格的な出荷を開始する見込み です。
AI需要を見据えた増産投資を背景に、北上工場を含む工場群の記憶容量ベースの生産能力は、将来的に 2 倍にまで拡大する計画が打ち出されています。
現在、キオクシアの北上工場には「2,100人余り」が勤務しているとの報道があり、K2稼働にあたっては追加で約1,000人規模の雇用拡大も見込まれています。
北上市のように、地場に根ざした製造基盤に加えて、次世代技術を担う先端企業の進出が重なることで、産業集積の層が厚くなり、地域の持続的な発展につながっています。
北上市の工場誘致の特徴と構造的な強み
北上市の工場誘致は、単発の成功ではなく、市制(1954年)以来の「工業による地域振興」の一貫した政策方針に基づいています。県主導が多いなか、市主体での戦略的な取り組みが長年にわたり続けられてきた点が特徴です。
北上市の工場誘致の強みとして以下が挙げられます。
・東北新幹線・東北自動車道・北上金ヶ崎ICなどの交通インフラが整い、東北圏内で随一のアクセス性を誇る。
・全10ヵ所の工業団地・流通基地・産業業務団地が整備され、用途地域とセットで企業に提示可能。
・県内最大の工業都市として、240社以上の企業が進出済み(2025年時点、市資料より)。
他の主な企業進出事例(多層型の成功)
キオクシアの進出で注目を集める北上市には、ほかにも多彩なものづくり企業が集積しています。地域内には自動車、半導体、精密機器、素材加工など、分野の異なる企業が共存し、多層的な産業ポートフォリオを形成しています。
たとえば、トヨタ紡織東北は本社と工場を構え、自動車の内装部品を中心にウレタンフォームやドアトリムなどを製造。東北地域の自動車産業を支える中核的な存在です。
ジャパンセミコンダクター岩手事業所は、北上駅や東北自動車道ICに近い利便性の高い場所に立地。半導体製造を担う主要拠点として地域経済を支えるとともに、工場見学などを通じた地域との交流も積極的に行っています。
3Mジャパン 岩手事業所では、粘着テープや工業用ファスナーなど多様な製品を生産。北上北工業団地内の主要拠点として、素材技術分野での地域連携も進んでいます。
さらに、アイ・テック北上DMCは2024年に竣工した鉄鋼加工・物流拠点で、団地への新規進出を象徴するプロジェクトです。東北最大級の加工設備を備え、今後の地域産業の広がりを期待させます。
シチズン時計マニュファクチャリング東北北上工場は、1963年から操業を続ける老舗の生産拠点。時計部品や金型などを手がけ、環境に配慮した生産体制を整えるとともに、地域住民との交流にも力を入れています。
こうした企業群の存在が、北上市を単なる「製造拠点」から、多様な技術と人材が共存する産業都市へと押し上げています。
これらの事例は、北上市が単一産業に依存せず、関連する複数業種を戦略的に誘致している証左です。
成功を支える実務的な施策・仕組み
北上市の工場誘致成功には、以下のような制度・支援・インフラ整備の連携が大きく貢献しています。
✅ 交通優位性と土地供給
・新幹線・高速道路・IC至近の立地
・用途地域・団地整備が一体で提示されるパッケージ戦略
✅ 企業立地インセンティブ
・設備投資額の最大10%(上限3億円)を補助する立地促進補助金制度
・雇用・投資条件を明確化し、企業側の予見性を担保
✅ ワンストップ対応と情報基盤
・市役所内の企業立地課が一元対応し、団地管理・手続きを簡素化
・「北上市企業データベース」を通じて地場企業の情報を公開し、調達・雇用・連携を支援
✅ 産学官の連携基盤
・「北上オフィスプラザ」「オフィスアルカディア北上」等による知的ネットワーク形成
・大学・高専と連携した技術研修・人材育成支援
継続的な企業進出が「ブランド」となる
北上市では近年も新規進出のニュースが途切れることなく続いており、「進出が著しいエリア」としてのブランド力が高まっています。これは単なる一時的なブームではなく、政策・インフラ・誘致手法の積み重ねによる成果といえるでしょう。
まとめ:北上市の事例が示す、持続可能な工業都市モデル
岩手県北上市は、交通・用地・政策・人材の“すべてを整えた受け皿”を持つ工業都市として、全国の自治体にとって大きな参考となる事例です。
単に企業を「呼ぶ」のではなく、進出後の定着・拡大・共生までを設計に組み込むこと。この視点こそが、これからの工場誘致に求められる“成熟した地方活性戦略”といえます。
3.北海道・千歳市におけるRapidusの進出と地域の変化
北海道千歳市では、先端ロジック半導体の量産を目指すRapidus(ラピダス)の進出により、道内でも類を見ない大規模な経済波及とまちづくりの変革が進行しています。工場の建設とともに、地価・人口・消費・税収・関連産業など、多方面にわたる活性化の兆しが可視化されています。
千歳市の変化を牽引するRapidusの進出効果
Rapidusは、次世代ロジック半導体の製造拠点「IIM-1工場」を北海道千歳市「美々ワールド」工業団地で建設中であり、2025年末に設備搬入、2027年から量産開始を目指しています。
国や北海道・千歳市内部の報告書・将来構想案では、このプロジェクトが地域経済や人口動態に与える影響を重視しており、下記のような期待・指摘が出されています。
地価上昇
千歳市内の商業地・住宅地で地価上昇率が全国トップクラスとなっており、国の報告書でも「ラピダス進出の押上げ効果が含まれているとみられる」と指摘されています。
経済波及効果
報道ベースでは2036年までに最大18.8兆円の経済波及効果や約3,600人規模の雇用創出という試算も示されており、北海道経済の構造転換への寄与が期待されています。
千歳市における人口・消費の増加と新たな“まちづくり”ビジョン
千歳市は2025年2月7日、「千歳市将来ビジョン」を公開し、Rapidus進出を見据えた人口・消費・定住政策を具体化しました。
▶ 消費経済への影響(2023〜2040年)
・累計消費効果:約1,423億円(出張者・転入者による飲食、宿泊、家賃等)
・年平均:およそ80億円の消費拡大
▶ 人口への影響
・出張者数:常時約2,000人が市内滞在と推計
・転入者数:2025〜2040年の累計で約7,800人
・人口ピーク試算:2036年に10万2,200人強(24年10月現在は約9万7,545人)
このように、Rapidus進出は単なる工場建設にとどまらず、まち全体の将来像を描き直す転機となっています。
クラスター効果による関連産業・裾野産業への波及
千歳市における工場誘致の本質は、ラピダス1社の効果だけではなく、装置・電池・材料・物流といった“関連産業の同時集積”が生まれている点にあります。
・最先端の半導体だけでなく、装置メーカー・部材供給企業・クリーンルーム対応物流業者の立地が進行中
・地場の中小企業にも調達機会・雇用機会・設備更新のニーズが波及しており、裾野産業の活性化が進んでいます
この構造は、熊本や北上と同様に、「単独立地 → 関連立地 →地域全体の底上げ」という成功パターンをなぞるものです
今後の課題と千歳市の対応方針
千歳市では、Rapidus進出に伴う急速な人口流入や出張・滞在者の増加を見据え、都市機能・住宅供給・教育・交通インフラの整備を本格化しています。市の目標人口10万人の達成は、従来見込みどおり2030年頃に実現する見通しです。
「千歳市将来ビジョン」と「人口ビジョン(改訂)」では、住宅供給・子育て支援・公共サービスの拡充を重点に掲げており、長期滞在型出張者や家族帯同転入者に対応する住宅・生活支援策の検討も進行中です。
これにより、「人が来る」→「住む」→「地域に定着する」という三段階の構造が地域の持続性を支える土台となっていきます。
まとめ:Rapidusによる千歳モデルは“まち全体で未来をつくる”先進事例
北海道・千歳市におけるRapidusの誘致は、単なる一企業の進出にとどまりません。これは、地域の都市構造・人口構成・経済基盤を中長期的に塗り替える可能性を持つ、国家規模のプロジェクトといえます。
まず注目すべきは、高度人材の集積です。半導体製造という先端産業の特性上、国内外から高い専門性を持つ技術者や研究者が集まり、地域の人材構成そのものが質的に変化します。それに伴い、教育機関や研修施設といった知的インフラの整備も加速するでしょう。
次に、裾野産業との共進化が期待されています。製造装置、素材、物流、サービスなど多岐にわたる関連企業が集積し、地域経済に新しい産業生態系が形成されます。単なる「工場誘致」ではなく、技術と産業が連鎖的に成長していく仕組みが構築されている点が大きな特徴です。
さらに、住宅・交通・教育・消費圏の整備といった生活基盤の刷新も進められています。人口流入を支える住環境整備、交通インフラの拡充、次世代教育の強化が一体的に進められ、地域の持続可能性を高めています。
そして何より重要なのは、将来を見据えた“まちの設計”です。Rapidus誘致を核としながら、産業・都市・人材の三位一体で再構築を進める「千歳モデル」は、単なる地域振興策を超え、次世代の地方創生を象徴する先進的な事例として位置づけられるでしょう。
4.茨城県・茨城町における着実な工業集積と誘致戦略
茨城県茨城町は、首都圏近郊という物流・地価・産業バランスに優れた立地を活かし、着実に企業誘致を進めてきた成功事例です。町内には「茨城工業団地」「茨城中央工業団地」という2つの主要団地が整備されており、県外企業を含む多様な業種の企業が進出・操業しています。
全国1位の実績に貢献する立地戦略
経済産業省の「工場立地動向調査」によると、茨城県は2017年から2024年まで8年連続で、県外企業による工場立地件数が全国1位となっています。この背景には、茨城町を含む県内自治体の戦略的な企業誘致の取り組みがあります。
・地価の安さ:地価水準が全国平均よりも低く、企業にとって初期投資リスクが小さい
・首都圏へのアクセス性:東京都心部から1〜2時間圏内に位置し、首都圏市場や港湾・空港との接続性が高い
・多様な産業の集積:茨城県内には電気機械器具製造、化学、鉄鋼などの基幹産業が集積しており、関連企業の立地が促進されやすい土壌があります
これらの条件が揃った茨城町は、「立地のしやすさ」と「成長性のある集積」の両方を備えた誘致拠点といえます。
茨城町の工業団地と立地企業の状況
■ 茨城工業団地
・立地企業数:11社
・主な業種:製造業、運輸業、物品賃貸業
■ 茨城中央工業団地
・立地企業数:18社(うち16社が操業中)
・主な業種:製造業、卸売業、物流関連事業
■ 代表的な進出企業
UDトラックスジャパン株式会社、あけぼの印刷社、その他、多様な業種の中小・中堅企業が操業し、地場雇用や周辺経済への波及効果を生み出しています。
企業誘致を後押しする制度:茨城町の「工場等立地奨励金制度」
茨城町では、町内に工場などを新設・増設する企業を対象に、独自の奨励金制度を設けています。これにより、初期投資の負担軽減や地元雇用の創出を後押ししています。
【奨励制度の主な内容】
■ 固定資産税の減免
・土地:取得後3年間
・家屋・償却資産:新設・増設後3年間
・一定条件のもと、課税された固定資産税の一部を交付
■ 新規雇用助成金
茨城町に居住する従業員を新たに雇用した場合、人数に応じて奨励金を交付
■ 対象となる投資
土地取得、建物建設、設備導入などが対象範囲に含まれ、中小企業の立地拡張も支援対象になります。
成功要因の整理:茨城町が評価される理由
| 要素 | 内容 |
| コスト優位性 | 地価の安さと固定資産税の優遇で初期投資を抑制 |
| アクセスの良さ | 首都圏・港湾・高速道路圏への接続性 |
| 多様な産業基盤 | 電機・化学・鉄鋼など、周囲に関連産業が集積 |
| 団地の整備状況 | 茨城工業団地/茨城中央工業団地における着実な立地と稼働実績 |
| 誘致制度の整備 | 明文化された支援制度と、雇用を伴うインセンティブ設計 |
これらの複合的要素が、県外企業にとっての「立地先としての魅力」を構成し、8年連続全国1位という実績につながっています。
まとめ:茨城町は「堅実で安定感のある誘致モデル」
茨城県茨城町の企業誘致は、派手さではなく着実さと制度設計の丁寧さが光る事例です。地価や交通といった基本条件を活かしながら、団地整備・支援制度・集積環境といった“受け皿の総合力”で勝負している点に特色があります。
今後も、首都圏の製造業や物流業の分散ニーズを取り込むことで、地元雇用と町財政への好影響が継続的に期待される好事例といえるでしょう。
地方で工場を誘致する主なメリット

地方自治体にとって、工場誘致は雇用創出や税収増加をはじめとする、多くの経済的・社会的メリットをもたらす有力な地域活性化手段です。近年では、産業クラスターの形成や人口定着の促進など、より広範な波及効果も期待されています。
以下では、地方で工場を誘致することによって得られる主なメリットを整理いたします。
1.雇用・所得が増える
工場を地方に誘致することにより、地域住民にとって新たな雇用機会が創出され、所得の向上が期待できます。工場は単に製造職だけではなく、設備の保守を担う保全職、製品の品質を確認する品質管理職、物資の搬出入や輸送を担う物流部門、さらに購買、総務、経理といった事務系の職種まで、幅広い職種を抱えるのが一般的です。
また、工場は常用雇用(正社員・契約社員)に加えて、季節雇用やパートタイム、派遣など多様な雇用形態を導入することが多く、幅広い層の就業ニーズに対応できます。これにより、地域における家計所得の底上げが実現され、商業やサービス業など他産業への経済波及効果も期待されます。
成果指標(KPI)
効果を定量的に把握するためには、以下の指標が活用されます。
・常用雇用者数(うち地元居住者の割合)
・地域住民の平均賃金や可処分所得の増加率
・地域内の求人倍率や雇用改善状況
これらを継続的にモニタリングすることで、地域経済への実質的な効果を把握できます。
留意点
ただし、誘致の過程で「スキルのミスマッチ」や「勤務時間帯の不一致」などが発生する可能性があります。たとえば、工場側が深夜勤務を必要とする一方で、求職者は日中の勤務を希望するなど、労働条件が一致しない場合もあります。
そのため、以下のような対策が重要となります。
・地域の職業訓練機関と連携したスキル研修の実施
・柔軟なシフト設計(短時間勤務・昼夜交替など)の導入
・通勤手段としてシャトルバスや送迎車の運行など
これらを通じて、地域住民と雇用側双方にとって無理のない就業環境が整備され、工場誘致の効果が最大限に発揮されます。
2.税収・財政が安定する
地方自治体が工場を誘致することにより、自治体の税収が増加し、財政運営の安定につながります。工場が操業を開始すると、用地や建物、機械設備などに対して固定資産税や償却資産税が課税されるほか、企業が利益を上げれば法人市民税の増収も見込まれます。
さらに、工場で雇用された人々が地域に定住することで、個人住民税の増加や、地域での消費活動の活性化による間接的な税収効果も期待できます。このように、直接・間接の両面から税収の底上げが可能となり、地域の財政基盤がより強固になります。
具体例
・精密機械、医薬品、半導体関連など、初期の設備投資額が大きい業種では、操業初年度から償却資産税の税収が大きく貢献します。
・また、工場が一定年数ごとに設備の増築・更新を行うことで、税収が単発で終わることなく、継続的な財政効果が見込まれます。
こうした特徴により、人口減少などで税収が減少傾向にある地方にとって、工場の存在は安定した財源確保の有力な手段となります。
成果指標(KPI)
税収面での効果を測るには、以下の指標が有効です。
・固定資産税・償却資産税の増収額(年次推移での変化)
・法人市民税における税源の偏在度(特定企業への依存割合)
これらのKPIをもとに、税収の持続性やリスク分散の状況を把握し、財政運営の見通しを立てることが可能になります。
留意点
ただし、企業誘致に際して税優遇措置を設ける場合には注意が必要です。過度な減免を行うと、かえって自治体の財政を圧迫するリスクがあります。
そのため、税優遇制度は以下のように設計することが望ましいです。
・投資金額、雇用創出数、地元企業からの資材・サービス調達率など、実績に連動したインセンティブ型にする
・一律減免ではなく、段階的・期間限定の優遇措置にとどめ、持続可能な財政運営を担保する
こうした工夫により、企業側と自治体側の双方にとって公平で健全な関係を構築しながら、地域経済と財政の安定を実現することができます。
3.関連産業の集積(サプライチェーン効果)
工場を誘致することで、その周辺地域に関連する企業やサービスが集積しやすくなり、地域全体の生産性と経済活力が高まります。特に製造業の場合、部品や資材の調達、製品の納品、設備の保守といった業務は、距離が近いほど効率が良くなり、コスト削減やリードタイム短縮に直結します。
企業同士の取引が活発になると、共同輸送・共同購買・共同受注といった取り組みも実現しやすくなります。これは特に中小企業にとって、コスト圧縮や販路拡大の大きなチャンスとなります。
具体例
・工場に伴って広がる裾野産業には、部品・資材の供給業者、治具製作業者、設備点検・メンテナンス企業、フォークリフトや搬送機器の保守業者、包装資材業者、産業廃棄物処理業者、地域密着型の物流会社(ローカル3PL)などが挙げられます。
・産業団地などに複数の工場が立地している場合、工場間で協力して「ミルクラン(巡回集荷)」を行うことで、トラックの運行台数を減らし、CO₂排出削減や物流費削減に寄与する事例も増えています。
このような地域内ネットワークの充実は、地域経済の自立性や強靱性を高めるうえでも重要です。
成果指標(KPI)
関連産業の集積とその効果を測定するには、以下の指標が有効です。
・地元企業への発注総額および地元サプライヤーの数
・調達リードタイム(注文から納品までの時間)、在庫回転日数(在庫が売れるまでの平均日数)
これらの指標が改善されれば、地域の産業基盤が強化されていることを示すといえます。
留意点
サプライチェーンの地元化を促進するためには、地元企業にとって「どうすれば取引できるかが明確であること」が重要です。以下のような取り組みが不可欠となります。
・発注予定や必要とされる製品・サービスについての情報の可視化
・地元企業が参加しやすい商談会・展示会の開催
・発注先との取引における品質や納期などの標準要件の共有
こうした情報開示とコミュニケーションを通じて、地域内のサプライチェーンを構築・強化していくことが、持続的な経済活性化につながります。
4.人口定着・U/Iターン促進
地方における工場誘致は、安定した雇用の場を創出することによって、人口の定着やUターン・Iターンを促進する効果が期待されます。特に若年層にとって、「この地域で将来設計が描ける」と感じられる環境が整えば、進学や就職を機に都市部へ流出することを抑制し、さらには地域外からの転入も生まれます。
また、単身ではなく家族を伴った転入が増加することで、学校や保育所、地域の商業施設、医療機関などの社会インフラの維持・発展にもつながり、まち全体の持続可能性が高まります。
具体例
・工場が新卒採用とあわせて社宅提供や家賃補助、保育支援制度などを整えることで、20代〜30代の若年層を中心とした移住・転入が促進されます。
・また、工場の操業にあたっては管理職や専門職の転入も見込まれ、これにより地域における可処分所得の水準が改善され、消費活動の活性化や住民サービスの充実に波及します。
成果指標(KPI)
人口定着や移住効果を測るには、以下のような指標が活用されます。
・社会増減(転入者数 − 転出者数)および20〜39歳の人口比率の推移
・合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)
・地域の学級数や保育所の利用者数など、子育て関連施設の持続状況
これらの指標により、地域が若年層や子育て世代にとって魅力ある生活圏となっているかを把握することができます。
留意点
一方で、雇用があっても定住に結びつかないケースも少なくありません。その背景には、以下のような生活基盤におけるボトルネックが存在します。
・住まいの確保が困難(賃貸物件や社宅不足)
・保育施設が不足している、または待機児童が多い
・公共交通の便が悪く、通勤が負担
こうした課題を放置したままでは、せっかく雇用が創出されても一時的な就業にとどまり、地域への定着が進みません。したがって、工場誘致と並行して、住宅施策・保育サービス・交通インフラの整備を総合的に進めることが、人口減少対策として極めて重要です。
5.インフラ・生活環境の底上げ
工場の立地に伴って、地域のインフラ整備が進むことは、企業にとっての生産性向上だけでなく、地域住民にとっても生活の質の向上につながる大きなメリットです。交通、上下水道、通信、防災といった公共インフラが近代化されることで、安心・快適な暮らしが実現されます。
これにより、地域全体の魅力度や定住意欲の向上にもつながり、長期的には人口の流出防止や地域活性化に貢献します。
仕組み
企業が地域に進出すると、その周辺において以下のような公共インフラの整備が必要となります。
・工場へのアクセス向上のための道路改良や交差点の整備
・水使用量の増加に対応するための上下水道の容量拡大・更新
・データ通信やリモート管理を前提とした高速通信回線や電力網の整備
・地震や水害に備えた防災設備の強化(排水設備、非常電源など)
これらの投資は企業活動に必要なものであると同時に、住民側の利便性向上にも直結するものです。
具体例
・工業団地へのアクセス道路を拡幅することで、通勤時の渋滞が緩和され、地域の道路利用者全体にとって快適な交通環境が実現します。併せて、路線バスの増便が行われれば、交通弱者の移動手段確保にもつながります。
・上水道や工業用水、下水道の老朽化設備を更新することで、漏水の減少や、大雨時の浸水リスクの軽減など、安全・安心な生活環境の整備が図られます。
成果指標(KPI)
インフラや生活環境の改善効果を把握するためには、以下のような定量的な指標が活用されます。
・交差点ごとの平均旅行時間の短縮状況
・公共交通の運行本数や乗降人数の増加
・水道の漏水率の改善
・停電件数や通信障害発生回数の減少
これらの数値を定期的に測定することで、住民目線での改善効果を見える化することが可能です。
留意点
インフラ整備には多額の初期投資が必要となるため、その費用対効果を明確に評価することが重要です。また、住民にとっても工場誘致による生活上の便益が実感できるよう、以下のような工夫が求められます。
・インフラ整備の内容とその目的、想定される住民への恩恵をわかりやすく可視化・説明する
・地域住民の声を反映したインフラ整備計画の策定
・投資後の改善効果を広報や報告書で共有することによる透明性の確保
こうした姿勢により、住民の理解と支持を得ながら、持続可能な地域基盤を築いていくことが可能になります。
6.技術移転・人材育成
工場の誘致は、地域に先進的な技術や経営ノウハウをもたらす大きなチャンスとなります。企業が導入している先端設備や品質管理手法、安全衛生管理体制、生産工程のマネジメント技術などが地域に流入することで、これまでにない高度な知見が共有され、地域全体のスキルレベルが底上げされます。
さらに、高等専門学校や大学と連携し、インターンシップや共同研究、カリキュラム連携などが進むことで、地元の若者が「地元で学び、地元で働く」人材循環の仕組みが形成されていきます。
仕組み
誘致された工場が持つ実践的な知識や運用ノウハウを活かして、以下のような人材育成のサイクルが生まれます。
・教育機関と企業との産学連携によるPBL(課題解決型学習)や現場実習
・工場の人材育成プログラムへの地元企業の参加
・地域全体への技術・管理ノウハウの波及
このような取組みは、単なる雇用の創出にとどまらず、地域の「知的資産の蓄積」に直結する重要な効果です。
具体例
・高専・大学と連携した「課題解決型インターン(PBL)」の導入や、地元での技能検定(例:QC検定、電気主任技術者など)の共同開催により、若年層の技術力向上が進みます。
・また、誘致企業の支援によって、地元中小企業にも5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動やTPM(全員参加の生産保全)、ISO取得などの品質管理・改善活動が普及し、地域産業全体の底力が高まります。
成果指標(KPI)
技術移転や人材育成の進展状況を測るためには、以下のようなKPIが活用されます。
・産学連携の実施件数、およびインターン受け入れ人数
・地元における資格取得者数(QC検定、電気主任技術者、衛生管理者など)
・地域内企業の製品不良率や労災発生率の改善
これらの数値は、技術と人材が地域に根づいているかを示す客観的な指標となります。
留意点
技術やノウハウの多くは暗黙知(マニュアルにしづらい経験的な知識)であることが多いため、単なる資料提供や座学研修だけでは浸透しにくいのが実情です。そのため、以下のような「現場密着型」の取り組みが効果的です。
・OJT(On the Job Training)や現場見学の受け入れ
・標準作業手順書やチェックリストなどの共同整備
・他企業との改善事例共有会や現場ラウンドテーブルの開催
これらの手法を通じて、企業のノウハウが地域全体へと広がりやすくなります。
7.地域ブランド・PR効果
工場の立地は、単なる経済的効果にとどまらず、その地域に独自のブランド価値を付加する力を持っています。特定の企業や製品が「○○(地名)でつくられている」という事実は、地域の名前を広く世の中に知らしめるきっかけとなり、移住希望者・観光客・企業投資家など、幅広い層への関心を高める効果があります。
特に、環境配慮型の「グリーン工場」や再生可能エネルギーを活用する事業所であれば、“環境先進地域”としてのイメージ発信にもつながり、今後の脱炭素社会に向けた地域戦略の柱としても活用できます。
仕組み
企業が地域に立地し、そこで製造された製品やサービスが高評価を得ることで、その地域名が「産地ブランド」「技術の拠点」として自然にタグ付けされていきます。これにより、以下のような波及効果が生まれます。
・地域に対する移住・定住意欲の向上
・観光や企業視察の増加
・他業種からの新たな投資誘致の呼び水となる
これらが複合的に作用し、地域のポジティブなイメージ形成とプレゼンス向上に貢献します。
具体例
・地元の名前を冠した製品(例:「○○産クラフトビール」や「○○ファクトリー印の電子部品」など)の展開により、製品と地域が一体で認知されます。
・見学可能なショールーム型工場を設置し、観光・教育目的の来訪を促すことで、地元の産業や環境への取り組みを直接伝える場として活用できます。
・再生可能エネルギー100%の電力利用や、ゼロエミッション車両の導入により、地域全体で「脱炭素に積極的なまち」として情報発信が可能になります。
成果指標(KPI)
地域ブランドやPR効果の可視化には、以下のような指標が用いられます。
・新聞・テレビ・Webなどでのメディア露出件数
・企業・投資家・行政関係者の視察・来訪件数
・観光客数の推移、移住相談件数の増加
・SNS(X、Instagram等)での言及件数やポジティブ評価の割合
これらのデータは、地域の発信力やブランド価値がどの程度社会に浸透しているかを測る指標となります。
留意点
地域のPR効果を高める上で、もっとも重要なのは「実態とメッセージの一致」です。環境・労働・地域貢献への取り組みが伴っていない中で無理にPRを進めると、かえってレピュテーションリスク(評判の悪化)を招く可能性があります。
そのため、PRは事実を誠実に伝えることを基本とし、企業活動の裏側にある社会的配慮や倫理的責任も丁寧に発信することが、地域として信頼されるブランドづくりの鍵となります。
8.空き地・遊休資産の活用
工場誘致は、地域内に存在する未利用地や遊休資産の再活用を促す有効な手段となります。かつて稼働していた工業団地や旧工場跡地、港湾の背後地、鉄道の貨物ヤードなど、現在は機能を失った土地・施設であっても、適切な整備・用途転換を行うことで、再び経済価値を持つ資産へと生まれ変わらせることが可能です。
これにより、地域の土地利用効率や税収効率が向上し、景観の改善や治安向上といった副次的効果も期待されます。
仕組み
遊休化した工業用地は、以下のような取り組みを通じて、工場や物流施設の誘致対象地として再生されます。
・土壌汚染の浄化や地盤改良などの環境整備
・小規模事業者にも対応できるようなスモールロットでの区画再編
・港湾や鉄道などのインフラとの連携を活かした用途転換(例:物流施設、研究拠点、食品加工団地など)
これらを組み合わせることで、元の土地の特性を活かしながら新たな価値を創出することができます。
成果指標(KPI)
遊休資産の再活用効果を把握するには、以下の指標が有効です。
・遊休地の面積の減少率、および再稼働エリアの稼働率(操業企業数)
・土地の鑑定評価額や固定資産税評価額の上昇
・稼働地周辺のインフラ整備率や利便性指標の向上
これらの定量的指標を通じて、土地資産の活用度や税収インパクトを明確にすることができます。
留意点
一方で、遊休地を活用する際には、地権者が多数に分散しており、合意形成が困難になるケースも多く見受けられます。そのため、次のような調整手法が重要です。
・土地区画整理事業を通じて、用途変更と資産再配置を同時に進める
・PFI(民間資金活用型の公共事業)やPPP(官民連携スキーム)の導入により、利害関係者の合意形成と事業推進を効率化する
こうした仕組みを活用することで、遊休資産が地域全体の成長エンジンとして機能するようになります。
9.危機対応力(BCP)の強化
工場の誘致は、地域と企業の双方における危機対応力(BCP:事業継続計画)の向上にもつながります。特に自然災害や感染症、国際的な物流混乱など供給網が脆弱化しやすい時代においては、分散型の生産・物流体制を構築することが極めて重要です。
工場や倉庫が特定地域に集中せず、複数の場所に適切に配置されていることで、一部の拠点が被災した場合でも、他拠点が機能を補完し、製品供給や物流が維持できる体制が整います。
仕組み
工場の立地とあわせて、地域や企業が以下のような冗長化・分散化の仕組みを構築することにより、災害や突発事象へのレジリエンスが高まります。
・電力・通信・道路インフラの多重系化(冗長化)
・高台・内陸部への倉庫設置や災害想定に基づいた立地選定
・代替工場やサテライト拠点との相互補完契約(相互受託生産など)
このような仕組みにより、工場誘致は単なる経済振興だけでなく、「危機に強い地域社会の構築」にも直結します。
具体例
・高台に設けられた倉庫や、非常用発電設備・二重受電体制、耐震強化されたラックの導入などにより、停電・浸水リスクを最小化。
・地域内または他地域の工場間で相互に代替生産を行う協定(相互受託生産)を結ぶことで、生産の停止を防ぎ、顧客への供給責任を果たす体制を確保。
・非常時に備えた優先輸送ルートの事前合意(警察・自治体・運輸会社との連携)によって、物資の移動を確保。
これらの対策が、企業・地域の双方にとって危機対応力の実効性を高める鍵となります。
成果指標(KPI)
BCP強化の効果を定量的に把握するためには、次のような指標が用いられます。
・非常時からの復旧時間(MTTR=平均修復時間)
・安全在庫日数の確保状況(最短◯日間供給可能か)
・防災設備の稼働試験回数、BCP訓練への参加人数(実施頻度と範囲)
これらは、机上の計画だけでなく、実働としてどれだけ機能するかを評価するために欠かせない指標です。
留意点
BCPは策定するだけで満足してしまいがちなテーマですが、「絵に描いた餅」にしないための実践と訓練の継続が不可欠です。
・年1回以上の実動訓練(ロジスティクスの再現含む)を行い、ルート確保や積載条件などを実際に体験する
・実際の車両・実荷物を使って搬送テストを行うことで、輸送手段や作業時間の見直しポイントを可視化
・自治体・消防・警察・近隣企業との合同訓練により、地域全体の連携体制も強化する
このように、計画→実践→検証→改善のサイクルを地域ぐるみで回していくことで、災害に強いまちづくりが実現されます。
住民・企業・自治体がWin-Winになる実装ポイント

工場誘致を真に地域の活性化につなげるためには、単に企業を呼び込むだけでなく、住民・企業・自治体の三者がそれぞれ利益を実感できる仕組みづくりが重要です。その実現には、雇用や人材育成、生活インフラ、環境対応など、多角的な視点での準備と支援が求められます。以下では、三者にとってWin-Winとなる実装のための主要ポイントを整理いたします。
1. ターゲット業種を選ぶ
工場誘致を成功させるには、地域資源との親和性が高い業種を見極めることが重要です。たとえば、以下の観点から誘致対象を絞り込むと、長期的な定着と地域との共生が期待できます。
・水資源や電力の安定供給が必要かどうか(例:食品・化学・半導体)
・高速道路・港湾・鉄道との物流連携が重要か
・地域に存在する人材の技能と合っているか(例:溶接・電気・品質管理の有資格者が多い など)
業種選定を誤ると、「雇用が生まれても地元から採用できない」「インフラが過剰負担になる」といったミスマッチが生じますので、最初の選定が肝心です。
2. 人材育成を同時に実装する
工場誘致と同時に、地域での人材育成支援を並行して行うことで、地元雇用の定着率とキャリアの質が高まります。具体的には次のような取り組みが有効です。
・高専・高校・大学とのカリキュラム連携(企業ニーズを授業に反映)
・リスキリング支援や職業訓練給付金の導入(失業者や転職希望者の再就職を促進)
・技能検定や資格取得支援の提供(例:QC検定、フォークリフト、電気工事士)
地域の人材が育ち、企業にとっても外部に頼らず人材確保できる好循環が生まれます。
3. 地元調達の可視化
企業活動による経済波及効果を最大化するには、地元企業との取引がどれだけ行われているかを「見える化」することが重要です。
・ローカル発注率を最低〇%と明示する立地協定の締結
・定期的な商談会の開催(新規参入しやすい機会づくり)
・共通の品質・納期・安全基準の共有(中小企業も対応しやすく)
これにより、企業側も調達先の安定性を得られ、地元企業は販路拡大が見込めます。
4. 生活インフラをパッケージで整備
雇用が生まれても「生活環境」が整っていなければ、転入や定着にはつながりません。企業誘致とセットで以下の要素をパッケージ化して提供することが大切です。
・社宅・家賃補助制度の整備
・託児所・保育支援施設の併設
・地域医療機関へのアクセス性の改善
・通勤バス・公共交通路線の拡充
企業にとっても「生活支援が整っている地域」は、人材確保がしやすくなる魅力的な立地となります。
5. グリーン要件の明記
環境への配慮は、企業のブランド価値と地域の信頼性を左右する要素です。以下のようなグリーン要件を立地協定に明記することで、将来の競争力と共感を得ることができます。
・再生可能エネルギー(PPA契約)による電力調達
・廃水・廃熱のリサイクル設備導入
・低炭素輸送(EVトラック、モーダルシフトなど)
・地域と連携した脱炭素のまちづくりへの参画
単なる「エコ推進」ではなく、実効性のある環境配慮を条件にすることが大切です。
6. 単一依存の回避(ミニクラスター化)
1社依存の誘致では、万一その企業が撤退・縮小した際に地域への打撃が大きくなります。そのため、特定分野の関連企業を複数誘致し、「ミニクラスター」を形成することでリスクを分散させます。
・たとえば、電子部品製造業+検査機器+物流+メンテナンス業など、補完関係にある企業群を構成
・業種横断の連携会議や共同受注体制の構築
これにより、地域全体が一体となった「産業圏」として発展できる土台が整います。
まとめ
これらの実装ポイントを戦略的に組み合わせることで、工場誘致は単なる「施設誘致」ではなく、地域に根差した持続可能な成長戦略となります。住民は生活環境の向上を、企業は人材とインフラの安定を、自治体は税収とブランド強化を享受できる、まさにWin-Win-Winの構図が実現します。
地方活性化において工場誘致の「課題・リスク・デメリット」

工場誘致には大きなメリットがある一方で、地域によっては副作用や思わぬ課題に直面するケースもあります。持続可能な地域活性化を実現するためには、こうしたリスクを事前に把握し、適切に備えることが重要です。以下に、主なリスクと留意点をまとめます。
1. 雇用の“地元外”流出
地域に雇用が生まれても、実際に働く人が地元住民でないケースが多くあります。特に専門スキルが必要な工場では、都市部からの出張社員や転勤者が中心となり、地域の雇用創出に直結しない恐れがあります。
・地域住民のスキルや勤務希望条件と合わない
・人材育成が間に合わず、外部採用に依存
➡ 対策として、誘致前に地元人材の職業訓練やリスキリング施策を実施し、採用マッチングを高めることが重要です。
2. 公共インフラへの負荷と財政圧迫
工場の立地に合わせて道路、水道、電力、下水、通信インフラなどの整備が求められますが、その初期投資・維持費用が自治体財政を圧迫する可能性があります。特に、企業に対する税優遇制度を設けている場合、投資回収までに時間がかかる点にも注意が必要です。
・稼働前後で期待した税収効果が見込めないリスク
・企業撤退後にインフラだけが残る「空洞化」問題
➡ 費用対効果を精査したうえで、段階的整備や企業負担の併用も検討すべきです。
3. 1社依存による地域経済の不安定化
誘致先の企業に過度に依存してしまうと、景気の変動や経営判断による撤退・縮小の影響が地域全体に波及します。特に、1社が自治体の法人税収や雇用の大半を占める場合、「企業都合で揺らぐまちづくり」になりかねません。
・規模の大きい単独工場誘致の副作用
・雇用・地元調達・税収が一気に消滅するリスク
➡ 「ミニクラスター誘致」や業種分散によって、リスクの分散が必要です。
4. 環境負荷・地域住民の反発
工場の種類によっては、騒音・排水・臭気・振動・交通渋滞などが発生し、住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。立地に関する情報開示や説明が不足すると、地元住民からの反対運動に発展することもあります。
・夜間操業やトラック交通による生活環境の変化
・地元合意形成の不足による軋轢
➡ 立地初期段階から住民説明会を行い、環境配慮や生活利便性の向上策を丁寧に説明することが不可欠です。
5. 地元中小企業との競合・人材奪い合い
大手企業の高待遇・福利厚生が地域に進出することで、地元中小企業の人材流出が加速するリスクもあります。また、調達力に差があるため、地域の購買が大企業中心に偏り、中小の取引機会が減少する懸念もあります。
・中小企業の人件費上昇圧力や人材確保難
・技術・取引の格差拡大による地域経済の二極化
➡ 中小企業との連携・育成支援も並行して実施し、「共生型の産業構造」を形成することが望まれます。
6. BCP対策・撤退対応が不十分なケース
誘致契約にBCP対応や撤退時の取り決めが明記されていない場合、災害や経済状況の変化による急な工場閉鎖に対応しきれないことがあります。土地の再活用や住民・従業員へのケアが宙に浮くリスクも存在します。
・撤退後の遊休地化・固定資産税収の減少
・雇用喪失による人口減少の連鎖
➡ 立地協定に「BCP対策」「撤退時の責任分担」「再利用計画」などを盛り込むことが大切です。
まとめ
工場誘致は多くのメリットをもたらしますが、事前の制度設計や関係者との合意形成が不十分である場合、地域にとって負担やリスクにもなり得ます。成功のカギは、こうした課題を冷静に把握し、“持続可能で地域主導型”の誘致モデルを構築することにあります。
工場誘致は「いまも有効」──ただし、“受け皿”と“多層化”が成功の鍵

工場誘致は、現在においても地方活性化の有効な戦略であることに変わりはありません。実際に、熊本県菊陽町、岩手県北上市、茨城県茨城町、北海道千歳市などでは、工場誘致を契機に、雇用の創出、民間投資の拡大、地価の上昇、商業施設の整備といった波及効果が確認されています
ただし、これらの成功事例には共通する前提条件が存在します。それは、工場そのものだけでなく、受け皿となる生活インフラと地域産業の多層的な支援体制が整っていることです。
具体的には以下のような要素が重要です。
・住宅・道路・公共交通・教育・医療などの生活基盤が、工場の稼働前に整備されていること
・人材を受け入れる教育・訓練体制や、保育・通勤環境など、暮らしを支える仕組みがあること
・地元中小企業が、サプライチェーンの一員として参画できる構造が用意されていること
こうした条件が揃えば、企業と地域の関係が一時的なものにとどまらず、“定着する活性化”へと発展します。
一方で、住環境の未整備や交通渋滞、1社依存による産業構造の脆弱化などの課題が放置された場合には、投資拡大や事業の次フェーズ(第2工場・研究開発拠点など)が遅延・停滞するリスクも伴います。
たとえば、TSMCの熊本第2工場の計画について報道された遅延の背景には、インフラや生活環境の対応力がボトルネックになっているとの指摘もあります。
成功のための視点
つまり、工場誘致を「地域に根ざした成長戦略」とするためには、単なる施設の誘致にとどまらず、
・受け皿(暮らし・教育・移動)の整備
・多層化(複数業種・地元中小との連携)
・持続可能な地域ビジョンとの一体化
といった、包括的なまちづくりの視点が不可欠です。
今後の工場誘致は、「企業に来てもらう」だけでなく、「企業とともに地域をつくる」という発想が求められます。これが、地方創生の本質的な成功に向けた大きな一歩となるでしょう。
これから工場誘致を目指す自治体のための実務チェックリスト

工場誘致を計画・検討している自治体においては、誘致活動そのものよりも「受け入れ体制の整備」が勝負を分ける要因となっています。以下に、誘致を本格化させる前に確認すべき実務的な要点を整理いたします。
【交通インフラ】計画段階から工程表に組み込む
工場誘致による交通量の増加は避けられません。交差点改良、バイパス整備、鉄道・バスの増便計画を、誘致前から工程表化しておくことが重要です。住民と企業の両方が利便性を感じられるインフラ整備が求められます。
【住宅供給】多様なライフスタイルに応じた段階的整備
単身者、家族連れ、外国人従業員など、多様な居住ニーズに対応した住宅供給計画を立てる必要があります。以下のように段階的に整えることが理想です。
・企業寮・社宅(短期)
・賃貸住宅(中期)
・分譲住宅・定住支援(長期)
短期滞在型の宿泊施設やサービスアパートメント(外国人・プロジェクト要員向け)
【人材育成・生活支援】地域と連携した仕組みづくり
工場の操業に必要な人材を地元から確保するためには、高専・大学・職業訓練校と連携した即応型のカリキュラム整備が有効です。さらに、外国人従業員に対応するための語学支援・生活相談・行政手続きの伴走支援も整えておくと定着につながります。
【中小企業支援】調達・品質対応の支援窓口を一本化
大手企業が進出した際に、地元中小企業が調達先として選ばれるかどうかは、支援体制に左右されます。認証取得や品質改善、納期対応など、複数の相談先が分散していては機会損失となります。
そのため、「品質・認証・調達支援窓口」の一元化(ワンストップ化)が効果的です。大手企業の条件に対応できる地元企業を増やす仕組みが不可欠です。
【多層ポートフォリオ】中核企業+関連企業をまとめて誘致
現代の工場誘致は、単体の企業にアプローチするだけでなく、装置メーカー、素材サプライヤー、部品加工業者、電池メーカーなどを一体で誘致する「多層ポートフォリオ戦略」が成功の鍵です。
例:半導体関連では、製造企業だけでなく、洗浄装置や検査装置、化学材料、物流事業者を含めた同時誘致が行われています。
まとめ

工場誘致は、いまなお強力な地域活性の起爆剤となり得ます。しかしその成否は、企業1社を“呼ぶ”ことではなく、暮らしと産業の“両方を受け止める器”を用意できるかどうかにかかっています。
さらに、関連企業や地元企業も含めた「束ねて誘致する発想」を持つことが、これからの“勝ち筋”の地域戦略となるでしょう。
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略

