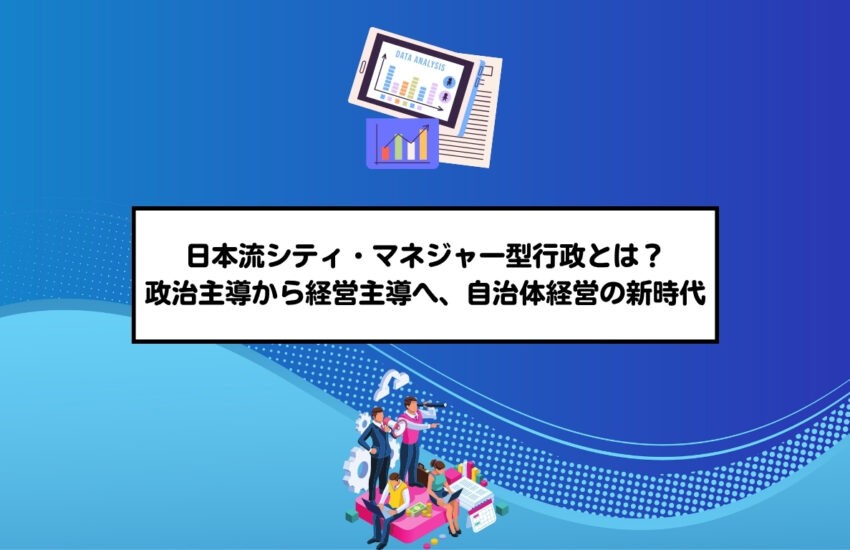人口減少・財政制約・人材難という“三重苦”の中で、自治体には「運営」ではなく「経営」への発想転換が迫られています。
鍵となるのが、政治(方向性の決定)と行政(実務の遂行)を分離し、専門職が行政をマネジメントする発想――日本流シティ・マネジャー型です。憲法・地方自治法の枠組みを踏まえつつも、副首長の外部登用、首長の“行政CEO化”、EBPM*×DX、そして長期ビジョン運用が、実務面から自治体を“プロ経営”へと押し上げています。
本稿は、米国モデルの要点、日本における制度的制約と文化的ギャップ、現場で進むハイブリッド実装、そして2025–2030の展望を体系的に解説します。
※EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)とは、「証拠に基づく政策立案」と訳され、政策を経験や勘だけに頼るのではなく、客観的なデータや統計(エビデンス)に基づいて行う考え方です。
アメリカ発「シティ・マネジャー制度」とは?――政治と行政を分ける合理的モデル

アメリカでは、首長を住民の直接選挙で選ばない自治体もあります。
このような自治体では、市民が選挙で選ぶのは「市議会議員」であり、市議会がその中から名誉職的な市長を選出します。
一方、実際の行政運営は、市議会が任命するシティ・マネージャー(City Manager)が担当します。これは、「シティ・マネジャー制度」と呼ばれる行政の仕組みであり、この制度は、アメリカの中規模から小規模の都市で広く採用されており、代表的な例として、アリゾナ州フェニックス、テキサス州ダラス、ノースカロライナ州シャーロットなどが挙げられます。
シティ・マネジャーは、行政の実務・人事・予算編成などを専門的に担い、政治的な思惑に左右されずに仕事を進めることができます。
この仕組みの魅力は、効率性と専門性、そして透明性の高さにあります。政治家は方向性を示す「意思決定」、マネジャーは実際の「運営・実行」を担当するため、責任の所在が明確になります。また、専門知識を持つマネジャーが行政を担うことで、財政の健全化や住民サービスの質向上につながるケースも多く報告されています。
実際に、人口2万5千人以下の市町村を除くと、アメリカではシティ・マネジャー型の制度を採用する自治体が6割以上にのぼるとされています。政治の安定性と行政のプロフェッショナル運営を両立できる点が、多くの自治体から支持されている理由です。
日本に導入できない理由:憲法と地方自治法の“制度の壁”
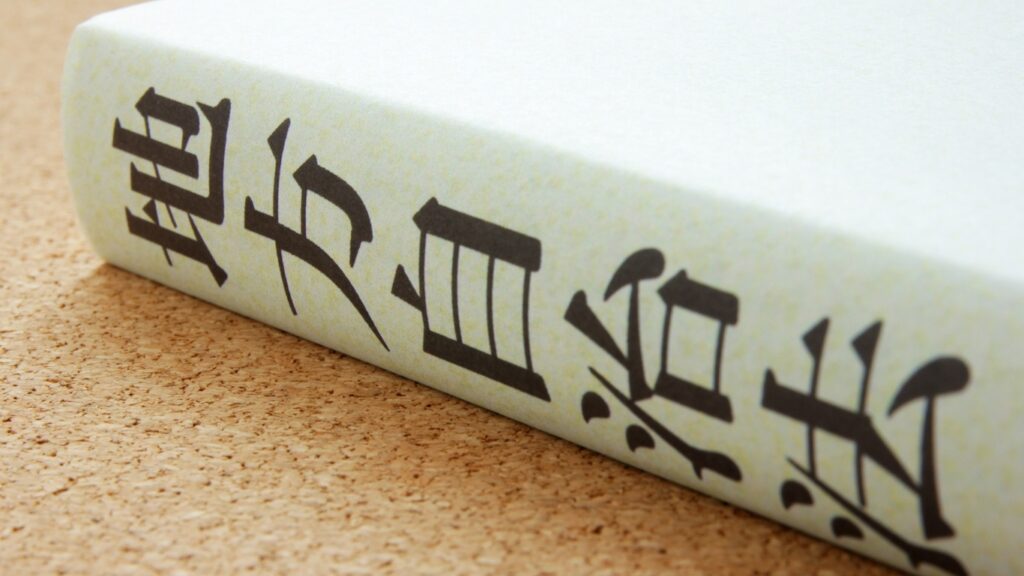
米国で確立されたシティ・マネジャー制度は、政治と行政を明確に分ける効率的なモデルとして注目されています。しかし、日本では同じ仕組みをそのまま導入することはできません。
背景には、憲法や地方自治法が定める首長の直接公選制という「制度の壁」があります。ここでは、その法的な制約と制度的不整合の実態を見ていきます。
1. 憲法93条が定める「首長の直接公選」の原則
日本では、憲法第93条2項が「地方公共団体の長は、住民が直接これを選挙する」と明記しています。この「住民による直接選挙」は、地方自治の民主的基盤とされ、戦後一貫して維持されてきました。
一方、米国のシティ・マネジャー制度では、議会(カウンシル)が行政トップであるマネジャーを任命します。つまり、行政の最高責任者が「住民ではなく議会によって選ばれる」構造になっています。この点が、日本の憲法の規定と根本的に異なるため、現行制度のままでは導入ができないのです。
憲法改正を伴わない限り、「首長を議会が任命する」モデルをそのまま採用することは不可能と解されています。
2. 二元代表制という構造的制約──議会と首長の独立関係
さらに、地方自治法でも、首長(知事・市町村長)は「執行機関の長」と位置づけられ、議会とは独立した存在とされています。首長と議会の二元代表制――つまり「住民が両方を選び、互いにチェックし合う」仕組みが、現行の地方自治の根幹です。
これに対してシティ・マネジャー制度は、議会が行政の実務トップを任命し、首長の役割を形式的に限定するという「単元的」な構造です。したがって、日本でシティ・マネージャー制度を導入する場合は。地方自治法の改正だけでなく、制度の基本理念を大きく見直す必要があります。
3. 政治文化の違い──「人望型リーダーシップ」と制度設計のギャップ
米国では、議会制と専門職行政の分業が進み、政治と行政の距離を保つ文化が根付いています。しかし日本では、首長のリーダーシップや人望が行政運営の中心にある文化が強く、「政治主導で行政を動かす」モデルが一般的です。
仮にシティ・マネジャー制を導入したとしても、
・マネジャーの任命をめぐる議会内の政治的対立
・住民から見えにくくなる責任の所在
など、制度的な摩擦や混乱が生じる可能性があります。
4. 過去の導入議論が停滞した背景
2000年代には、研究機関(例:日本総合研究所〈JRI〉など)や一部の学者が、「シティ・マネジャー的要素を取り入れた行政改革」を提案しました。しかし、実際に導入するためには憲法や地方自治法の改正を要するため、法制度の壁が依然として高いままです。
一部の自治体では、副市長や政策参与を「マネジャー的役割」として活用する試みもありますが、あくまで部分的な応用にとどまっています。
“日本流マネジャー型行政”とは何か?――制度を変えずに進化する自治体経営
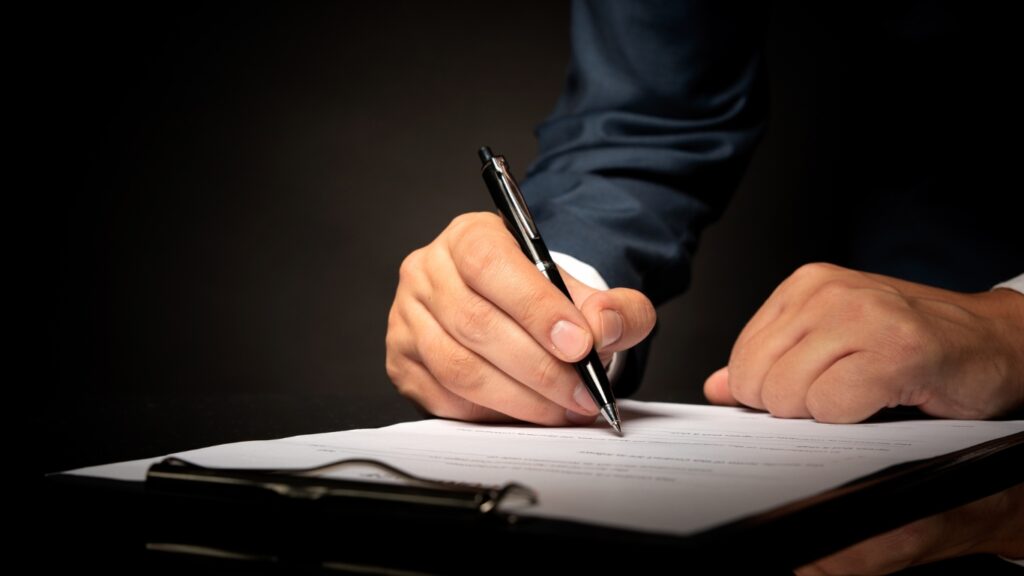
日本では憲法上、首長を住民が直接選ぶ仕組みが定められているため、米国型のシティ・マネジャー制度をそのまま導入することはできません。
しかし、法改正を伴わずに「行政運営のプロフェッショナル」を中核に据える取り組みは、すでに各地で進み始めています。ここでは、その代表的な3つの潮流を紹介します。
1. 外部登用の副市長・副町長が担う“COO的役割”
従来、地方自治体の副市長・副町長は内部昇任が中心でした。しかし近年、外部から経営感覚を持つ人材を登用し、組織横断的な改革を推進する動きが広がっています。
生駒市などでは副市長を全国公募で選び、民間での経営経験を持つ人材を採用しました。行政内部のしがらみにとらわれない意思決定を促し、官民連携やDX推進の牽引役(COO)として機能させています。
この発想は、米国の「任命型プロ経営者」を副首長ポストで疑似的に実装するものです。人事マネジメントや財政改革を通じて、組織の実行力を高める狙いがあります。
2. 首長自身の“行政CEO化”──専門職リーダーの出現
神奈川県真鶴町の小林伸行町長は、就任時にMPA(公共経営修士)を有する専門職としての経歴を明示し、町政改革に着手しました。当初は、議会の議長を“名誉職(Mayor)”、町長を“実務責任者(Town Manager)”と位置づけ、業務の立て直しを図りました。
現在は制度的分業を解消しましたが「政治家であり、同時に行政CEOである」という考え方を体現した稀有な例といえます。首長自身が経営感覚と行政専門性を兼ね備えることで、外部任命に頼らずとも、実務の高度化を実現しています。
真鶴町は1993年に「まちづくり条例(美の基準)」を制定し、約30年にわたり住民合意のもとで運用してきました。都市景観や土地利用の判断を明文化された価値基準に基づいて行うことで、政策の一貫性と説明責任を担保しています。
こうした“変えない価値”の存在は、行政マネジャー型運営と非常に相性が良い仕組みです。長期的な合意があることで、専門職による継続的な政策運用が可能となり、結果的に組織の安定性と効率性を高めます。
なぜ今、マネジャー型行政が広がるのか?――構造変化が生む必然

“日本流マネジャー型”の行政運営は、ここ数年で導入・検討事例が確実に増えています。その背景には、人材・課題・財政・制度の各側面からの構造的な圧力があり、制度そのものよりも「現実対応としての必然性」が拡大を後押ししています。
1. 人材難と課題複雑化──「総合経営」能力の必要性
地方自治体が直面する課題は、かつてないほど複雑化しています。人口減少や高齢化、インフラ老朽化、防災・減災対策、子育て支援、観光・関係人口創出まで政策ポートフォリオが急速に肥大化しています。
従来の「縦割り行政」では対応が難しく、今や行政は“経営”の視点を持つことが求められています。そのため、行政経営の専門性を備えた人材——財政・人事・戦略立案を一体で運用できる“マネジャー型人材”の必要性が高まっています。
特に、複数分野を横断する政策を統合的にマネジメントできる能力は、首長単独では担いきれず、組織としての専門経営力を確立することが急務となっています。
2. 財政・説明責任・成果重視の時代へ──EBPMがもたらす変化
米国ではすでに、シティ・マネジャー制度が行政効率の向上や財政健全性と関連していることが研究で示されています。
日本でも同様に、限られた予算で多様な政策を実現しなければならないという“効率化の圧力”が高まっています。
加えて、成果の可視化と説明責任(アカウンタビリティ)が強く求められる時代です。
EBPMやパフォーマンス管理といった考え方が行政運営に浸透しつつあり、民間的な分析・評価スキルを持つプロ人材が必要とされています。
今後、自治体における「政策効果の測定」や「投資対効果の説明」は、単なる報告業務ではなく、組織経営の根幹に位置づけられるテーマになっていくでしょう。その中心的役割を担えるのが、マネジャー型の専門人材です。
3. 外部登用と人材市場の成熟──自治体間の“学習効果”
副市長や副町長の公募・外部登用は、すでに複数の自治体で定着し始めています。民間出身の副市長が成功事例を重ねることで、採用側・応募側の双方に「成功パターン」が共有されつつあります。
各自治体がポジション要件・評価指標・契約条件などを具体的に設計するケースが増加しており、これにより、採用市場における“学習効果”が進み、以前よりもスムーズにマネジャー人材を受け入れられる環境が整いつつあります。
一度成功例が生まれると、同規模自治体や近隣地域がモデルとして模倣・改良を行うため、波及スピードが加速しやすいのも特徴です。
制度の壁よりも現場の必要性が勝つ時代
かつては「法制度が壁」とされたマネジャー型行政ですが、現場ではすでに人材難・課題複雑化・財政圧力・実務知見の蓄積という“拡大ドライバー”が働いています。
今後は、首長の政治判断とマネジャーの専門実務が共存する「ハイブリッド型自治経営」が主流になる可能性があります。言い換えれば、制度改正を待たずとも、自治体の実務はすでに“マネジャー型進化”を始めているのです。
それでも残る課題とリスク:制度・議会・人材の三重構造

上述したように、“日本流マネジャー型”の行政経営は、確実に広がりを見せています。しかし、その展開には依然として制度的・組織的な制約が存在します。法制度、議会機能、人材供給の三つの側面から見た課題は、いずれも導入・定着を左右する重要な要因です。
1. 憲法の壁と制度的不整合──「擬似マネジャー制」の限界
最大の制度的制約は、やはり憲法第93条第2項です。この条文は、「地方公共団体の長は住民が直接これを選挙する」と明記しており、米国型のように議会が行政トップ(マネジャー)を任命する仕組みは、憲法上採用できません。
そのため、日本で実現できるのはあくまで「擬似マネジャー型」の範囲にとどまります。具体的には、副市長や政策統括官に専門的なマネジメント機能を担わせるモデルです。
しかし、これらのポストは首長の任命・議会の同意を経る形で置かれる“補佐職”に過ぎず、独立した行政権限を持つわけではありません。
この構造的限界がある以上、完全な「シティ・マネジャー制」の移植は困難であり、あくまで「日本型ハイブリッド運営」として設計する必要があります。
2. 議会の監督力不足──評価と任命の機能が未成熟
もう一つの大きな課題は、議会側の監督機能です。
米国型マネジャー制度では、議会がマネジャーを任命し、その成果を評価・監督する構造が前提にあります。つまり、議会自身が政策形成力とパフォーマンス評価力を備えていなければ、制度が機能しません。
しかし、日本の地方議会では、政策提案・評価・監視を専門的に行う体制がまだ脆弱です。結果として、制度的に議会が監督主体であっても、実際には人事や成果評価が“人依存”になりがちです。
特定の首長や副首長の力量に結果が大きく左右される構造は、制度としての再現性を損なうリスクをはらんでいます。この点で、制度の受け皿としての「議会のプロ化」も今後の鍵となるでしょう。
3. 人材エコシステムの欠如──任期と地域適応の課題
もう一つの現実的な制約は、人材の層の薄さです。
行政経営の専門資格であるMPA(Master of Public Administration)やMBA(経営学修士)を持つ人材は増加傾向にあるものの、地方行政に適応できる人材は依然として限られています。
また、副市長などの任期は通常4年以内と短く、成果を出す前に異動・退任するケースも多いのが実情です。一方で、地方行政には地域特有の文脈理解や人間関係構築が不可欠であり、外部人材が地域文化に馴染むまでの時間コストも無視できません。
この「成果を出す前に任期が終わる」「現場が慣れる前に人が入れ替わる」というサイクルは、組織疲労や改革の形骸化を招くリスクがあります。したがって、制度を支えるには、長期的に専門人材を育成・循環させる“行政経営人材エコシステム”の構築が不可欠です。
「文化を育てる行政経営」への転換が必要
マネジャー型行政の理念は明快ですが、それを支える法制度・議会機能・人材文化は一朝一夕には整いません。現行制度下では、「部分導入」や「ハイブリッド運営」にとどまるケースが主流となるでしょう。
しかし、逆に言えば、これらの課題を一つずつ克服していく過程こそが、日本型行政経営の成熟プロセスともいえます。“制度を変える”のではなく、“文化と人材を育てる”ことで、持続可能なマネジャー型ガバナンスの基盤を築くことが求められています。
2025–2030年の展望:制度から“実務モデル”への転換期

ここでは、2025年から2030年にかけてどのようにこの動きが定着・拡大していくのか、その展望を整理します。
結論から言えば、米国のシティ・マネジャー制度をそのまま法制度として移植する可能性は、今後5年でも限定的です。憲法と地方自治法の枠組みが明確である以上、「議会任命型マネジャー」を正式制度として採用するハードルは依然として高いままです。
しかし一方で、現場レベルではすでに“日本流シティ・マネジャー型”とも言うべき実務モデルが広がり始めています。その特徴は、以下の3要素を核とした「事実上のプロ経営体制」の形成です。
1. 日本流マネジャー型行政の拡大──副市長・CIO/CMOのプロ化
まず注目すべきは、副市長・政策監・CIO/CMO(最高情報責任者・最高広報責任者)などの外部登用が急速に進んでいる点です。地方自治体の中で、民間出身や専門職人材を経営補佐層に迎え入れる動きが一般化し、特に中規模都市や県庁所在市クラスで制度化が進んでいます。
こうした人材は、行政マネジメントを横断的に統括する“COO的存在”として、政策立案から実行管理、官民連携、DX推進までを担います。公募プロセスや任用ルールの明文化が進むことで、外部登用が“例外的措置”から“制度運用の選択肢”へと位置づけられつつあります。
2. 任期・評価・成果を可視化する“成果マネジメント”の定着
次に、注目されるのが任期・目標・評価を明文化した執行体制の拡大です。
近年、副市長や特任ポストに対し、ミッション(任期内の成果目標)を明示した任用契約を結ぶ自治体が増えています。これにより、従来の「在任=形式的補佐」から、「成果創出を前提とした契約型マネジメント」へとシフトしています。
EBPMやKPI設定、PDCA管理といった民間経営の手法が行政マネジメントにも根づき、“行政経営の可視化”が進むでしょう。
これらの流れが定着すれば、政治主導と専門職マネジメントのバランスを取る実務的ガバナンスが確立されます。
3. 「理念×データ」で動く行政──EBPM+DXの融合
真鶴町の「美の基準」に象徴されるように、長期的なまちの理念やデザインコードを明文化して共有する動きは、全国的に再評価されています。こうした「変えない価値」があることで、行政マネジャーが中長期的視点で一貫した判断を行える基盤が整います。
さらに今後は、EBPMやDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用により、“理念に基づいた意思決定×データに基づく実行”という二層構造が主流化していくと見られます。これはまさに、「感性+科学」の融合型ガバナンスであり、地方自治体経営の成熟を象徴する変化です。
拡大の方向性──中規模自治体から広域マネジャー型へ
2025〜2030年にかけては、小規模自治体から中規模都市を中心に、「日本流シティ・マネジャー型」への移行が加速すると予測されます。特に、人口減少や職員数の制約が大きい自治体では、専門職登用+DXによる効率経営が必然的な選択肢となります。
また、複数自治体を束ねて広域連携を進める「広域マネジャー的人材」への需要も増加すると考えられます。地域間で課題を共有し、医療・観光・防災などを横断的にマネジメントできる人材が、今後の地方経営の鍵を握ります。
制度から文化へ、「経営する自治体」の新しい成熟軸
今後の地方行政は、法制度の限界を運用で補う時代から、人材の専門性で運用を支える時代を経て、文化と理念で運営を継続する時代へと移行していくでしょう。
米国型マネジャー制度の“形”を追うのではなく、「日本流シティ・マネジャー型」=制度×人材×文化の統合モデルとして成熟させることが、今後の自治体ガバナンスの本質的な課題です。
その未来を象徴しているのが、真鶴町のような小規模自治体です。そこには、法律でも条例でも縛れない、「地域をどう経営するか」という哲学的実践が息づいています。
この小さな自治体の実験こそ、日本全体の地方行政の未来を映す鏡といえるでしょう。
制度定着の4条件(議会・人材・運用・ビジョン)
制度が広がるためには、以下の4つの条件が整うことが重要です。
| 観点 | 必要な条件 | 解説 |
| 議会 | 任命・監督機能を担う政策形成・評価スキルの強化 | 議員研修や専門スタッフの配置を通じて、議会が「評価主体」として機能することが不可欠。 |
| 人材 | MPA/MBA等の公共経営人材のリージョナル・プール化 | 大学院・NPO・都道府県・霞が関間での交流を促進し、地域間で専門人材を循環させる。 |
| 制度運用 | 副市長公募の要件明確化・評価設計・再任基準の整備 | 採用後の評価指標を標準化し、任期制を前提とした継続的マネジメント体制を構築。 |
| ビジョン | 真鶴町「美の基準」に代表される長期的合意理念の明文化 | 合意済みの理念・デザインコードが、行政判断の“ぶれない軸”として機能。 |
まとめ:次のフェーズは「制度」ではなく「運用」で決まる

今後の地方行政の進化は、法制度改正ではなく運用設計の巧拙によって差がつくフェーズに入ります。「任命・評価・継続・共有」の4要素を制度的に整えることができれば、“実質的なマネジャー型行政”は確実に拡大していくでしょう。
2025〜2030年の5年間は、制度の模倣期から実装・洗練期への転換点です。政治家と専門職が共に「経営の言葉」で行政を語る時代が、いよいよ現実味を帯びてきています。