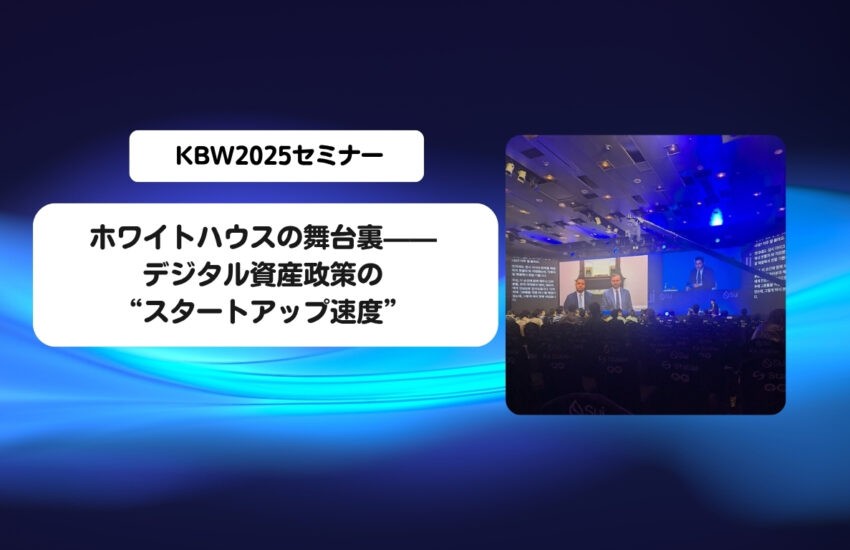〇登壇者プロフィール
Harry Jung
米ホワイトハウス「デジタル資産大統領諮問会議」副局長。CFTCにてCaroline Pham代行議長の首席補佐官を務め、暗号資産・DeFi・デジタル資産分野での政策対応を主導。以前はCitigroupで規制戦略や国際政策を担当し、Morgan StanleyやFINRAでも経験を積む。ミシガン州立大学ロースクール卒、ジョージタウン大学修士、ハミルトン大学学士。
Patrick Witt
米ホワイトハウス「デジタル資産大統領諮問会議」事務局長。国家のデジタル資産政策を統括するほか、国防総省で戦略資本局長を務め、約2,000億ドル規模の投資を指揮。前政権では米人事管理局副首席補佐官を歴任し、McKinseyで航空宇宙・防衛分野のコンサルティングにも従事。イェール大学卒、ハーバード・ロースクール修了。元アメリカンフットボール選手としてNFLに挑戦した経歴を持つ。
- DCの中心で、政策が走りはじめています
- 1|中枢の顔ぶれと意思決定:政策が“スタートアップ速度”で進む理由
- 2|Genius Actの実装へ:財務省ルールメイキングの“心臓部”
- 3|Market Structure Bill:資本市場の“配線図”を書き換える
- 4|“オープン・フォー・ビジネス” :米国回帰のカタリスト
- 5|ドル覇権の次段階:プログラマブル・ドルの国家戦略
- 6|“不可逆化”のシナリオ:レールが敷かれれば戻らない
- 7|DOJガイダンスと開発者の“心理的安全性”
- 8|議会攻略:ルールは「合意装置」である
- 9|産業界への具体的アドバイス:今すぐできる5つのこと
- 10|現場の肌感:スピードは“可視化”で作られる
- 11|タイムライン:2028年までに“形にする”
- 12|リスク管理:政権交代・逆風シナリオに備える
- 13|会場へのメッセージ:DCに来てください
DCの中心で、政策が走りはじめています

特別対談:ホワイトハウス デジタル資産評議会(The White House Council on Digital Assets)
ワシントンD.C.のホワイトハウスに設置されたデジタル資産アドバイザリーの中枢にいるキーパーソンを招いたカジュアルな形式の座談会でした。
登壇者は遠隔参加となりましたが、Genius Act(ステーブルコイン制度)の可決を受けた実装作業、審議が詰めの段階にあるMarket Structure Bill(市場構造法案)、そして省庁横断の実務オペレーションが、驚くべきスピードで動いている現状を具体的に語りました。
本稿では、その内容を「チームの意思決定」「立法・規則の進捗」「産業界との対話」「米国の覇権戦略」「タイムラインと不可逆化」の5つの軸で読み解いていきます。
1|中枢の顔ぶれと意思決定:政策が“スタートアップ速度”で進む理由
登壇者は、大統領の方針と担当トップのリーダーシップが、デジタル資産政策を「起業家のスピード感」で駆動していると説明しました。
・チーム構成は、国家安全保障や国防、財務といった他分野の実務経験者を含みます。初動で省庁間の“言語の違い”をブリッジできる人材を配し、合意形成の“移動コスト”を極小化しているのが特徴です。
・ワークスタイルは「早朝開始・深夜終了」が常態です。議会のスタッフや上院議員との協議、産業界ヒアリング、規則案へのフィードバック収集が毎日複数回走り、“優先課題の再スコアリング”を日々行います。
・意思決定の型は、“段階的だが同時多発”。すなわち、立法(議会)・規則(省庁)・ガイダンス(当局)を並走させ、ボトルネックの発生を最小化します。
このアプローチによって、「まずは現行法の解釈でできることを最大限進め、立法で追認・明文化する」という二段エンジンが機能しています。結果として、業界側の開発・実装の遅延を避けることに成功しつつあります。
2|Genius Actの実装へ:財務省ルールメイキングの“心臓部”
Genius Actは、米国におけるステーブルコインの制度枠組みを与える法律です。セッションでは、財務省(Treasury)が担う規則策定(ルールメイキング)が“野心的なタイムライン”で進んでいると説明されました。
・準備金の安全性・流動性・保管がコア論点です。米国内金融機関での保管といった要素が検討され、監査・開示・非常時償還の運用まで踏み込んだ“現場目線”の設計が求められています。
・既に市場反応も出ています。特定のステーブルコイン事業者の米国オペレーション発表や提携加速など、“オンショア回帰”の徴候が見え始めていると語られました。
・ルールメイキングはコメント収集→案の修正→最終化というプロセスを辿ります。登壇者は、産業界からの建設的フィードバックを歓迎しており、「現実に回る運用」を最優先すると繰り返しました。
重要なのは、“互換性”の設計です。米英をはじめとする主要法域との整合(コンパチビリティ)が高いほど、クロスボーダー事業の摩擦コストは下がります。米国は世界最大級の需要地であるがゆえに、「米国仕様」はそのまま国際標準の叩き台になり得ます。
3|Market Structure Bill:資本市場の“配線図”を書き換える
Market Structure Billは、トークン化資産の取扱い、取引所・ブローカーの責務、清算・カストディの境界など、市場インフラの配線を総点検する法案です。
・上院では複数案が併走し、条文は分厚く複雑です。登壇者は可決への感触を前向きに語る一方、実装リソースや監督の一貫性を担保するための工程管理が欠かせないと強調しました。
・成立後には、CFTC・SEC・財務省など複数当局で定義・手続・報告の詳細ルールを詰める必要があります。ここでも、“実務が回るか”が最優先指標となります。
・同法案はトークン化の位置づけを明確化するうえで決定打になり得ます。“証券性”と“コモディティ性”の線引き、流通・情報開示・投資家保護の要件が可視化されれば、長期資本が入りやすくなります。
登壇者の言葉を借りれば、「法案がゴールではなく、運用がゴール」です。制度の予見可能性が投資家の割引率を下げ、実装の平易さが発行体の法務コストを逓減させます。
4|“オープン・フォー・ビジネス” :米国回帰のカタリスト
セッションB全体を貫いたメッセージは、「米国はオープン・フォー・ビジネス」です。
・前政権期の厳格な執行ムーブで人材・資本がオフショアへ流出した反省から、現政権は回帰の受け皿づくりを最優先にしています。
・CFTC・SECは、可能な範囲のルールメイキングやスタッフガイダンスを先行し、立法で追認・明文化する“二段構え”で臨んでいます。
・産業界との対話は“電話一本、メール一本”の距離感です。登壇者は、製品の課題や規制上の障壁を率直に共有してほしいと繰り返しました。面会・意見交換の敷居は、かつてなく低くなっています。
この環境下では、規制アービトラージよりも、“米国準拠の設計”を早めに織り込むことが合理的になりつつあります。州規制差を含む“米国内の地図”を描きながらも、中核仕様は連邦準拠に寄せるのが先々のコスト最小化につながります。
5|ドル覇権の次段階:プログラマブル・ドルの国家戦略
米国の最大の強みは、深く厚い資本市場と成熟した法秩序です。セッションでは、これをデジタル時代に合致させる「次の一手」として、ステーブルコインや市場構造の標準化を位置づける見解が示されました。
・ステーブルコインの制度化は、ドルのネットワーク外延を広げ、“プログラマブル・ドル”の国際普及に直結します。
・ルールの国際互換性が高まるほど、ドル建てのデジタル決済・資本調達が滑らかになります。これは米国の金融覇権の新段階を支える施策です。
・政策はまだ任期1年目(セッション時点の文脈)で、2028年までの実装完遂を目標にした“時間との勝負”が続きます。
要するに、「制度=経済安全保障」という視点です。半導体での教訓を踏まえ、デジタル資産(とりわけステーブルコイン)を国家競争力の中核と捉え直す——それが現在の政策アジェンダの大筋です。
6|“不可逆化”のシナリオ:レールが敷かれれば戻らない
登壇者は、制度の不可逆化を明確に意識しています。これは、立法が通り、規則が整備され、監督実務が安定すると、産業・雇用・投資が国内に“根”を張り、政権交代でも時計の針が戻りにくくなるという意味です。
1.Genius Actの実装(財務省ルール)
2.Market Structure Billの成立→各当局の詳細ルール
3.省庁横断ワーキングの恒常運用(定例化・議事の可視化)
この三点が揃えば、政策の再現性が高まり、規制による恣意的ブレーキがかかりにくくなります。登壇者は、「今こそ臨界点」だと繰り返し強調しました。
7|DOJガイダンスと開発者の“心理的安全性”
実務面で象徴的なのが、司法省(DOJ)による開発者保護のメッセージです。登壇者は、ソフトウェア開発そのものを犯罪視しないという基本姿勢を示すメモやガイダンスの整備に触れ、安全・セキュアな設計を推奨しつつ、イノベーションの“心理的安全性”を担保する方針を説明しました。
・目的は、「米国内で安心して作れる」環境の確立です。
・開発者が刑事リスクの不確実性に怯える状況では、優秀な人材が国外へ流出し、国家競争力を損ないます。
・逆に、線引きの明確化はセキュリティ・バイ・デザインへの投資を促し、市場全体の耐障害性を高めます。
“作ってはいけない”ではなく、“この線を守って作るなら大丈夫”という示し方が、スタートアップ速度を引き出す鍵になっています。
8|議会攻略:ルールは「合意装置」である
登壇者は、連日上院議員・スタッフ・ロビイング団体と会合を重ね、条文の文言・適用範囲・合意形成の落とし所を探っています。ここで示唆的だったのは、「議会は最終的に合意装置である」という認識です。
・業界側は、理想案だけでなく、現実に通る代替案(プランB/C)を用意し、“合意可能領域(ZOPA)”を広げる必要があります。
・その際、比較法(海外制度)や既存の金融規制での先例を示すと、政治的コストを下げやすくなります。
・条文化に耐える用語定義、監督の測定指標(KPI)、移行期間の安全網など、実装設計の粒度が高いほど、合意は前に進みます。
要は、「規制は交渉」であり、「交渉はデータと代替案」だということです。
9|産業界への具体的アドバイス:今すぐできる5つのこと
セッションBのメッセージを踏まえ、事業者・投資家・開発者がすぐに着手できる実務アクションを抽出します。
1.規制地図の整備
・連邦法+州規制(マネー・トランスミッター等)の差分表を作り、許認可・登録の優先順位を引きます。
・越境を視野に、主要法域(米・英・EU・アジア)の最小公倍数要件を特定します。
2.開示テンプレートの標準化
販売形態(公募/私募/適格投資家限定)ごとにディスクロージャー・パッケージを標準化し、更新フローと監査証跡を定着させます。
3.ステーブルコイン対応の運用設計
・準備金の保管・破綻隔離・償還ドリルを運用規程+プロセスマップで明文化します。
・米金融機関保管を前提に、監査・日次照合・開示頻度の設計を詰めます。
4.ロビー/コメント活動の継続
・ルールメイキングのRFI/RFCに定期的に提出し、現場データで実効性を裏づけます。
・業界団体や学術コミュニティと連携し、互換性を最大化する提案をまとめます。
5.セキュリティ・バイ・デザイン
・鍵管理・復旧フロー(アカウント抽象化等)、不正監視・アラート、インシデント・レスポンスを製品仕様に内蔵します。
・開発者の行為規範と法的セーフラインを社内規程として整備します。
10|現場の肌感:スピードは“可視化”で作られる
セッションで繰り返されたのは、「可視化がスピードを生む」ということです。
・プロジェクト管理では、論点ごとに“依存関係”を洗い出し、並行処理できる領域を広げます。
・議会・当局とのやり取りは、論点メモと論点別の決裁フローを見える化し、ボトルネックを特定します。
・産業界の声も、単発の面会ではなく、定点観測(四半期・半期)のダッシュボードで共有することで、政策の再現性が上がります。
この“可視化”の徹底が、ワシントンの“スタートアップ速度”を支えているといえます。
11|タイムライン:2028年までに“形にする”
登壇者は、現政権の任期中(〜2028年)に、主要法案の成立と実装を「できる限り早く」完了させたいと語りました。
・短期(〜1年):Genius Actの財務省ルールが具体化。準備金・監査・開示・償還の運用基準が固まります。
・中期(〜3年):Market Structure Billが成立→詳細規則へ。定義・手続・報告を当局横断で整えます。
・中長期(〜4〜5年):監督実務の安定化とエンフォースメントの一貫性が確立し、制度の不可逆化が進みます。
このロードマップは、産業側にとって投資計画の“物差し”になります。いつ、何が確定するのかが見えれば、資本配分と人材採用の意思決定が容易になります。
12|リスク管理:政権交代・逆風シナリオに備える
参加者からは、政権交代時の逆風(いわゆるOperation Chokepoint再来)への懸念も示されました。登壇者の答えは明快です。
・省庁横断ワーキングを高頻度・恒常運用することで、一体政府(Whole-of-Government)の合意を積み上げます。
・制度の実装(人・金・プロセス)が国内に根付くほど、“戻すコスト”が上がり、不可逆性が強まります。
・ガイダンスと判例を積み、現場運用の慣行を作ることも、制度安定の装置になります。
事業者としては、“法のグレー”に依存した戦術ではなく、“法の更新”にコミットする戦略へ舵を切ることが、長期的には最もリスクを下げます。
13|会場へのメッセージ:DCに来てください
登壇者は、DCに来て対話してほしいと繰り返しました。
・何を作っているのか/どこで詰まっているのかを、NDA下の実装メモや失敗例も含めて共有してほしい、と。
・政策側は、“どこを直せば現実に回るか”の手触りを求めています。机上の理屈より現場のログが、ルールの質を押し上げます。
・業界団体を介した提案でもよいですし、個社で来ても構いません。「電話一本・メール一本」の距離感で、窓口は開かれています。