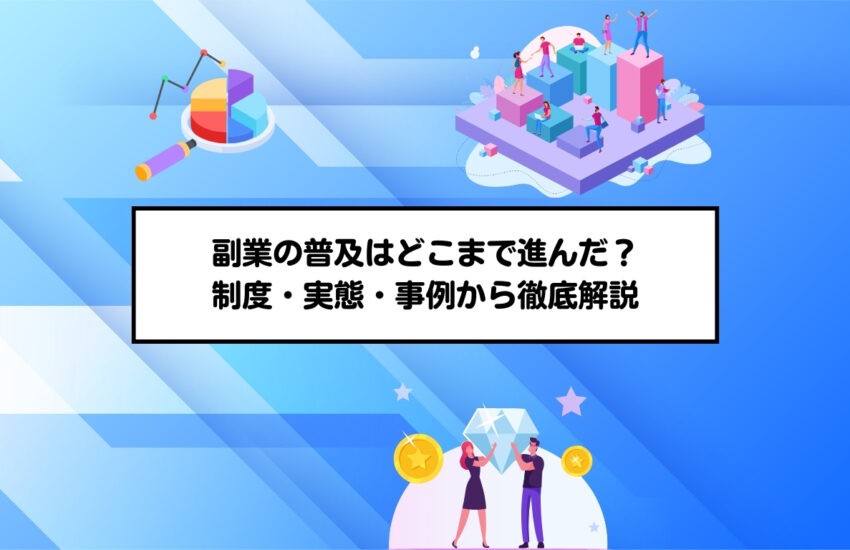「副業解禁」が叫ばれるようになってから、すでに数年が経ちました。しかし、現実はどうなのでしょうか。
制度は整備され、企業も容認の方向へと舵を切り始めました。柔軟な働き方も広がっています。それでもなお、副業が“普通の選択肢”として受け入れられるには、いくつかの壁が残されています。
実際に、どれほどの人が副業に踏み出しているのでしょうか。企業はそれをどのように受け止め、どのように運用しているのでしょうか。そして、制度は現場でどの程度機能しているのでしょうか。
2025年の現在、公的統計と信頼できる調査をもとに、「副業のリアル」について読み解いていきます。
副業の実態と課題:制度は整いつつも、普及は伸び悩み

副業はどの程度、実際に広がっているのでしょうか。総務省「就業構造基本調査」によると、2022年時点で副業を持つ人の割合は、女性5.3%、男性4.4%。企業側も約6割が副業を容認しており、ルール整備も進展。
しかしながら、実際に副業を行っている正社員は1ケタ台にとどまり、受け入れ体制とのミスマッチが大きな課題となっています。
また、コロナ禍で広がったテレワークは現在落ち着きを見せつつも、直近1年間での実施率は全国平均16.1%。柔軟な働き方は副業への後押し要因として引き続き注目されています。
加えて、厚生労働省はガイドラインやモデル就業規則、労働時間管理の運用モデルを整備しており、制度に則った運用でリスクを抑えることも可能です。
一方で、「簡単に稼げる」といった甘い誘いに乗った副業詐欺も増加傾向にあり、消費者庁や国民生活センターが注意を呼びかけています。
(なお、ここで言う「副業者比率」は、「就業構造基本調査」における定義に基づいたものであり、調査の枠組みに準拠した統計である点に留意が必要です。)
企業側の受け止め——“容認6割”でも実施は伸びず
企業による副業の容認は広がりを見せており、2023年の調査では60.9%の企業が副業を容認していると報告されています。
しかしその一方で、正社員の副業実施率はわずか7.0%にとどまり、企業側で実際に副業を受け入れた割合も24.4%と低水準。企業が制度として「認めている」ものの、実際の活用には大きなギャップが存在しています。
このギャップの背景には、個人側の副業意欲は依然として高く、副業を希望する人は全体の40.8%にのぼるものの、「本業が多忙で時間が取れない」「希望に合った副業の選択肢が少ない」など、マッチングの難しさや働き方の制約がボトルネックとなっている実情があります。
働き方の変化:テレワークは“定常化”
コロナ禍で急速に広がったテレワークは、現在ではやや落ち着きを見せながらも一定の水準で定着しています。国土交通省の年次調査によると、直近1年間におけるテレワークの実施率(雇用者ベース)は16.1%。
コロナ禍ピーク時に比べると低下していますが、出社とリモートを併用する“ハイブリッド型”の働き方が常態化してきていることがうかがえます。
こうした働き方の変化は、副業の実行可能性を高める重要な“環境要因”でもあります。テレワークや裁量労働制度の浸透は、時間や場所の制約を緩和し、より柔軟な働き方を可能にします。実際、これらの制度については利用者の継続意向も高く、副業への取り組みを後押しする土台になっていると考えられます。
ルール整備:何が“できて”、どこに気をつける?
副業の広がりに伴い、制度面でもルール整備が着実に進んでいます。厚生労働省は2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、2020年・2022年に内容を改定。
モデル就業規則の改定や、複数事業所における労働時間の通算・管理の方法についても具体的な解説資料が整備されており、企業・労働者の双方が実務上で感じやすい疑問への対応が強化されています。
さらに、「副業・兼業の事例集〜24社から学ぶ〜」といった公開資料では、実際の企業の導入例や受入れ体制、プロボノ型支援など、多様な副業の形が紹介されています。
どのような業種・地域の企業が、どんな目的で副業制度を取り入れているのか -その傾向を把握するうえでも有用な資料となっています。
副業を推進している企業の事例

「副業・兼業の事例集〜24社から学ぶ〜」の事例をもとに、業種や地域、導入目的ごとに整理した一覧表をご紹介します。それぞれの制度設計に見られる工夫や特徴も、見やすくまとめました。
副業企業事例(抜粋)
| No. | カテゴリー | 企業名 | 業種 | 本社所在地 | 副業制度の特徴・注目点 |
| 1 | 送り出し企業 | 青山商事株式会社 | 卸売業・小売業 | 広島県 | 接客スキル活用。人事部承認後すぐに働くことが可。採用競争力向上 |
| 2 | アルプスアルパイン株式会社 | 製造業 | 東京都 | 再雇用者も対象.、従業員のプロフェッショナル化が目的。二重就業制度を利用 | |
| 3 | オムロン株式会社 | 製造業 | 京都府 | 副業に従事した時間は勤怠管理の備考欄に記載、所属長が把握できる。コンサル業務、講師など | |
| 4 | カルビー株式会社 | 製造業 | 東京都 | キャリア支援、副業によるモチベーション向上 | |
| 5 | キリンホールディングス株式会社 | 製造業 | 東京都 | 副業ガイド・好事例共有。ITやマーケティング業務が多い | |
| 6 | シミックホールディングス | サービス業 | 東京都 | 入社直後から活用可能な制度で従業員が専門性を発揮。講演や執筆活動が中心 | |
| 7 | ゼネラルパートナーズ | サービス業 | 東京都 | 従業員が外部で得た経験を社内に活かすことが目的。福祉系の資格を活かしてカウンセリングを行う、コラム執筆など | |
| 8 | 第一化成株式会社 | 製造業 | 東京都 | 年齢・職種を問わず利用可能。簡潔な申請書と遵守事項を基に社長決裁まで行う厳格なフローと、労働時間管理による健康配慮が特徴。 | |
| 9 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 大阪府 | 会社主導の「公募型」と従業員主導の「申請型」。スキルや知識、人脈を強化 | |
| 10 | 髙島屋 | 卸売・小売業 | 大阪府 | 副業休暇あり。制度ガイド整備 | |
| 11 | 日本郵政 | サービス業 | 東京都 | 企業文化の変革を狙う「戦略的副業」。副業・兼業に関する企業間のコンソーシアムに参画 | |
| 12 | パーソルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 「ファースト副業」としての社内副業・兼業の活用。 | |
| 13 | パナソニック ホールディングス | 製造業 | 大阪府 | 従業員の自己実現の機会創出のための重要な施策として位置づけ。制度説明会等で周知、社内イントラを用いて好事例を周知 | |
| 14 | ピジョン | 製造業 | 東京都 | 社外副業として支援するのは就業後の時間及び休日のみ | |
| 15 | ユニ・チャーム | 製造業 | 東京都 | 細かくなりすぎないよう、一定のルールを守れば利用可能な制度としており、人事規程で禁止している副業先を設定 | |
| 16 | リーガルコーポレーション | 製造業 | 千葉県 | 従業員の副業がきっかけで新たなビジネスを創出 | |
| 17 | 受け入れ企業 | オムロン株式会社 | 製造業 | 京都府 | 業務委託契約により、社内にない知識や経験を取り入れ、新たな視点やアプローチを導入。 |
| 18 | 日本郵政株式会社 | サービス業 | 東京都 | 戦略的副業として多様な外部人材を受け入れ、人事・財務・分析等で活躍。 | |
| 19 | 鬼頭精器製作所 | 製造業 | 愛知県 | ITや技能検定の専門人材を副業・兼業で受け入れ、既存人材では補えない業務や新たな知見を得ています。 | |
| 20 | K.S.ロジャース | 情報通信業 | 兵庫県 | 採用難を背景に副業・兼業人材を受け入れ、全国から優秀な人材を確保しています。 | |
| 21 | 僕と私と株式会社 | サービス業 | 東京都 | 事業拡大とリモート普及を背景に副業人材を受け入れ、リファーラル採用と柔軟な働き方環境で専門スキルを活かしています。 | |
| 22 | プロボノ活動支援 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 製造業 | 大阪府 | 助成金・プロボノを通じてNPOの基盤強化と社会課題解決を支援し、従業員のスキル活用や成長にもつなげています。 |
| 23 | ピジョン株式会社 | 製造業 | 東京都 | AMCプログラムを通じ、ボランティア・プロボノ等の制度で従業員の挑戦とキャリア形成を支援しています。 |
(副業・兼業の事例集を参考に表を作成)
次に、実際にどう運用されているのか、特徴的な企業5社の取り組みを掘り下げてみます。
事例紹介①:青山商事株式会社の副業制度――“社員の成長”と“即戦力確保”を両立
青山商事株式会社では、2020年に副業・兼業制度を正式に導入しました。背景には、社員のスキル向上と視野の拡大を促し、それを本業にも活かしてもらうという明確な目的があります。
✅ 導入の背景と経緯
当初は2019年、グループ会社の人手不足対応として、グループ内での副業・兼業を制度化。その翌年には、コロナ禍を受けて副業ニーズが急増したことを受け、対象をグループ外にも拡大し、社内制度として整備されました。
⭐ 制度の特徴と仕組み
・対象とルール
全従業員が対象であり、雇用型・非雇用型の副業いずれも可能。ただし、同業他社での勤務や、公序良俗に反する職種は禁止とされています。
申請は社内システムを通じて行い、人事部門の承認が下りれば、即日での副業開始も可能です。
・勤務時間と労務管理
副業は基本的に本業の終業後や有給休暇中に実施。勤務時間は月末に報告し、翌月の予定も提出する運用。副業と本業の時間外労働の合計が月80時間未満になるよう制限を設け、健康面への配慮もなされています。
・社外からの副業人材の受入
もともとは退職者を対象に開始された社外副業人材の受け入れは、現在では一般にも開放され、繁忙期に即戦力を確保する手段として活用されています。
🎯 成果とメリット
【利用状況】
制度の利用者は約130名にのぼり、主に20〜30代の店舗勤務者が中心ですが、本社社員の活用例もあります。社内メールなどを通じて制度の周知が進んだ結果、認知度・利用率ともに上昇しています。
【企業側のメリット】
副業人材の受け入れを通じて、接客スキルを持つ即戦力の確保や採用力向上につながっており、「副業制度があるから志望した」という応募者の声も。離職者との関係維持にも貢献しています。
【従業員側のメリット】
給与補完だけでなく、異なる職場での経験を通じたスキルアップや自己成長の機会が提供されており、「助かっている」「前向きな刺激になっている」といった反応が寄せられています。
🔍 総括
青山商事の副業制度は、「社員の成長」「企業の柔軟な人材活用」「採用力の強化」という三方向での効果を発揮する、戦略的かつ実践的な制度です。特に、申請のしやすさや健康管理への配慮、制度運用の透明性が、継続的な活用を支える要因となっています。
事例紹介②:アルプスアルパイン株式会社の「二重就業」制度——プロフェッショナル人材の育成を支える柔軟な制度設計
アルプスアルパイン株式会社では、2016年3月に「二重就業」制度(副業・兼業制度)を導入しました。目的は、従業員のキャリア自律やスキルアップを支援するとともに、社外で得た知見を本業に還元すること。企業としての競争力強化と人材育成の両立を目指す制度です。
✅ 導入の背景と制度概要
導入の契機は、業界の変化と社内ビジネス環境の変動により、社員に柔軟性と専門性の両立が求められるようになったこと。加えて、同社ではテレワークやフレックス制度も整備されており、多様な働き方を許容する土壌がありました。
・個人視点の目的:キャリアの自律とスキル向上
・企業視点の目的:外部経験を社内に還元し、組織力の底上げを図る
⭐ 制度の特徴と運用
・制度の枠組み
全従業員(職種・年齢・雇用形態を問わず)が対象。再雇用者(60歳以上)も制度を利用可能で、雇用型・非雇用型どちらの副業も認められています。職種制限も緩やかで、公序良俗に反しない限り許容されています。
・申請・承認フロー
副業開始の1か月前までに申請し、直属上司 → 拠点人事 → 本社人事の3段階で確認・承認。申請内容には副業の目的や勤務形態が含まれ、本業への支障がないことが条件となっています。
・勤怠・健康管理
副業に従事した時間は勤怠システムの備考欄に自己申告し、労務・健康・安全管理を一体的に把握。過重労働の防止にも配慮されています。
🎯 利用状況と制度の成果
これまでに70件以上の申請実績があり、主に委託契約による副業(非雇用型)が中心です。具体的には、以下のような活動が行われています:
– 論文執筆やベンチャー企業での技術支援
– 飲食店勤務、水泳指導員など、個人の興味に基づく副業
– 再雇用者(64~65歳)の副業チャレンジも増加傾向
特に、時間に余裕のある再雇用層での活用が目立ちます。
【企業へのメリット】
社員のスキルアップやキャリア開発を後押しし、複数社で働く“個人事業主型キャリア”のロールモデル提示にも成功。企業としての柔軟な姿勢が、中長期の人材戦略の柱となっています。
【従業員へのメリット】
副業による視野の拡大や新たな経験の獲得は、本業にも好影響を及ぼしています。特に定年後を見据えたセカンドキャリア形成の一環として、副業が新たな働き方の足がかりとなっている点が注目されます。
🔍 総括
アルプスアルパインの「二重就業」制度は、副業を“キャリア支援の手段”として本格的に活用している先進事例です。再雇用者も含めた幅広い対象設定や柔軟な制度運用が特徴であり、単なる収入補填にとどまらない“成長の機会”として、副業を戦略的に位置づけています。
組織としても、こうした制度を通じてイノベーション創出や人材流動性の確保を図る動きが進んでおり、今後の人材活用モデルの参考となるでしょう。
事例紹介③:オムロン株式会社——副業を“社会課題解決×人材成長”の起点に
オムロン株式会社では、2022年3月21日に副業・兼業制度を導入。この取り組みは、同社の長期ビジョン「Shaping the Future 2030(SF2030)」に沿った、人材戦略の中核施策のひとつと位置づけられています。
✅ 制度導入の背景とビジョン
SF2030では、以下のような社会課題の解決を中長期的な目標としています:
・カーボンニュートラルの実現
・デジタル化社会の実現
・健康寿命の延伸
これらの実現には、社員一人ひとりが創造性を発揮し、主体的に成長することが不可欠——という考えのもと、副業・兼業制度が整備されました。
制度の目的は明確で、
・従業員の自律的な価値創造支援
・地域貢献・スキルアップ・人脈形成の促進
・副業経験の本業への知見還元による企業競争力の向上
を図るものです。
⭐ 制度の内容と仕組み
【適用範囲と副業の種類】
全従業員が利用可能で、雇用型・非雇用型(委託等)のいずれにも対応。個人活動も広く対象とされており、比較的自由度の高い設計です。
【申請・承認フロー】
従業員は所属長に申請し、所属長の許可後、人事部門が最終確認。
承認にあたっては、以下の観点で審査が行われます:
– 社のビジョンとの整合性
– 本業への影響
– 競合・利益相反・機密保持の観点
– 法令や社内規程、公序良俗の遵守
【勤怠・健康管理】
副業従事時間は勤怠システムで自己申告。
所属長が日次・月次で健康面や業務支障の有無をチェックします。
また、雇用型副業においては、副業先企業向けの注意喚起レターも配布し、割増賃金や法的留意点の説明も明記されています。
🎯 利用状況と活動傾向(2023年度実績)
【利用者数】
単体で120名、グループ全体では198名が制度を利用。前年度比で2倍増となり、社員ニーズの高まりがうかがえます。
【年齢層】
最多は40代(30%)、次いで50代・30代・20代と、働き盛り世代での活用が目立ちます。
【副業形態】
8〜9割が非雇用型(業務委託等)での活動。
【活動内容の傾向】
– 専門性活用型:コンサルティング、キャリアカウンセリングなど
– 自己実現型:語学講師、ヨガインストラクター、アウトドア製品の販売やキャンプ場運営 など
📈 制度がもたらす効果とメリット
【企業側のメリット】
– 副業で得た知見やネットワークを本業にフィードバックし、創造的な問題解決や新規事業の種に
– 異業種との接点からイノベーションを加速
– 社員エンゲージメント向上:自律的キャリア形成がモチベーション維持につながる
– 中長期的な人材育成戦略の一環として、企業成長への寄与
【従業員側のメリット】
– スキルや視野の拡大、キャリアの自由な設計が可能に
– 地域貢献や社会参加を通じた新しい挑戦
– セカンドキャリアの支援にもつながり、再雇用者にとっては専門性の社会還元の場にも
🔍 総括
オムロンの副業・兼業制度は、企業ビジョンと個人のキャリア形成を強く結び付けた戦略的施策です。
単なる「副収入の手段」にとどまらず、社員の創造性と社会的価値創出を促す土台となっており、自己実現・社会貢献・企業のイノベーションを同時に実現する、先進的なモデルといえるでしょう。
特に、専門性を活かした社外活動×本業還元という“ハイブリッドな人材育成”の仕組みは、他社にとっても導入検討の参考になるはずです。
事例紹介④:鬼頭精器製作所——制度化に頼らない“現場主導”の副業人材活用
愛知県に本社を置く中小製造業、株式会社鬼頭精器製作所では、現在2名の副業・兼業人材を受け入れています。制度として明文化された枠組みではないものの、現場課題に即した柔軟かつ戦略的な人材活用として注目される取り組みです。
✅ 副業受け入れの背景と人材プロフィール
この取り組みは、同社が新たな外部人材活用の選択肢として、副業・兼業人材を積極的に受け入れる姿勢を打ち出したことに始まります。
・IT分野の専門家:ホームページ制作に関する助言を担当
・技能検定保有者(国家資格):データベース管理に加え、社員向け技能検定対策指導を実施
いずれの人材も、本業では正社員または有期契約労働者として勤務しつつ、当社ではパート・アルバイトという形で副業しています。
⭐ 制度の特徴と取り組みの工夫
鬼頭精器製作所の副業活用は、形式的な制度ではなく、現場主導で“できることから着手”した実践型モデルです。
【雇用形態】
副業人材はすべて非正規(パート・アルバイト)として受け入れ
【勤務調整】
本業に支障が出ないよう、勤務時間や業務範囲は柔軟に設定
【活動内容】
– 社内にない専門スキル(IT/資格支援)の補完
– 社員育成の一環として社外人材が技能検定指導を実施
【導入推進体制】
代表自らが旗振り役となり、採用担当や関係者に丁寧な説明と理解促進を図ったことで、スムーズな受け入れが実現しました
副業人材の獲得には、中小企業支援センター(県主催)プロジェクトの活用や知人からの紹介といった、多様なチャネルが活用されています。
🎯 成果とメリット
【企業側のメリット】
– 専門性の高い業務の内製化が可能に
既存社員では担えない領域を副業人材が担い、高品質な成果物を短時間で実現
– 業務効率の向上
社内のリソースでは時間がかかる作業を効率化
– 新たな視点の導入
社内にない発想や手法に触れることで、組織に新しい風を取り入れる効果も
– 経営への好影響
実際に「経営環境が改善された」との実感もあり、今後さらに受け入れを拡大したいという意向が示されています
【労働者側のメリット(暗示的)】
– 自身の専門性を活かした副業機会の獲得
– 地域企業への貢献と社会的意義の実感
– 教育・指導によるやりがいと成長
– 柔軟な働き方が可能になる環境
🔍 総括
鬼頭精器製作所の副業・兼業人材活用は、制度先行ではなく、必要性・課題感に基づいて丁寧に構築された“現場起点”の成功事例です。とりわけ、社内に不足する専門性を外部から補完しつつ、社員育成や業務効率向上にもつながっている点が特筆されます。
こうした柔軟な取り組みは、制度が未整備な中小企業でも十分に実現可能であり、地域企業の人材戦略における実践的なヒントとして大きな示唆を与えてくれるものです。
事例紹介⑤:キリンホールディングス株式会社——副業を“挑戦と成長”の仕組みに
キリンホールディングス株式会社では、2020年にグループ全体で副業・兼業制度を正式に導入しました。それ以前から一部では個別対応により副業が認められていたものの、企業全体で制度として明文化されたことで、より多くの従業員が活用できるようになりました。
✅ 制度導入の背景と目的
この制度の導入は、キリングループが掲げる企業理念「挑戦と成長」の実現と、企業競争力の強化に向けた取り組みの一環として位置づけられています。
・従業員の多様性 → 組織の多様性 → 企業価値の向上
・副業・兼業を通じて、自己成長と他者・社会との接点創出を促進
また、制度導入を支える基盤として以下のような柔軟な働き方環境が整備されています:
・スーパーフレックス制度(コアタイムなし)
・テレワークの定着
・たとえば「午前中は在宅勤務、午後は副業先へ移動」といった自由度の高い勤務が可能
⭐ 制度の仕組みと運用
【運用ルール】
報酬の発生するすべての業務については会社への申請が必須。
社内には「副業ガイド」が整備されており、制度内容・申請方法・注意点などを明文化。従業員に周知されています。
【承認フロー】
従業員は所属部門の上司に届け出たうえで、以下の観点から申請内容がチェックされます:
– 長時間労働につながらないか
– 競業や利益相反に該当しないか
– 本業に支障が出ないか
問題がなければ上司の承認のもと正式に認可されます。
【労務管理】
本業と副業の時間外労働の合計が月60時間を超える場合は、人事部門が所属部門に是正を促します。改善が見られない場合、副業の制限を働きかけるケースもあります。
【情報共有とコミュニティ形成】
副業に関する好事例や体験談はMicrosoft Teams上で共有され、関心のある社員は自由にアクセス可能。
「副業=個人の挑戦」だけでなく、「副業=社内の学びの場」としての機能も果たしています。
🎯 成果とメリット
【企業にとってのメリット】
– 副業で得たスキルや価値観が本業に好影響をもたらす
– 組織全体の創造性・多様性・イノベーション力の向上
– 社外との接点が、企業変革を推進する原動力となっている
【従業員にとってのメリット】
– 柔軟な働き方により、自己成長や新たな挑戦が可能に
– 本業だけでは得られないスキルや視野を獲得
– 副業に関する情報が社内でオープンに共有されていることで、安心してトライできる環境が整っている
🔍 総括
キリンホールディングスの副業・兼業制度は、「企業価値の向上」と「社員の成長支援」を両立する戦略的な人事施策です。
特に、スーパーフレックス制度・テレワーク・情報共有コミュニティといった支援インフラが整っている点が大きな特徴であり、社員の自律的なキャリア形成と挑戦意欲を継続的に後押ししています。
副業経験がスキルアップだけにとどまらず、組織全体の活力や変革推進の源泉となっている点は、今後の大企業における人材戦略のロールモデルとも言えるでしょう。
中小企業の視点:活用はこれから本格化

副業・兼業制度の広がりは、大企業を中心に先行して進んできましたが、中小企業ではいまだ本格的な活用には至っていないのが実情です。
『中小企業白書2024』(中小企業庁)によれば、従業員による社外副業を「認めている・認める予定」と回答した企業は約3割にとどまっており、一方で他社人材の副業受け入れについては、約7割の企業が「未実施・検討外」と回答しています。
このことから、白書では「副業を“認める側”と“活用する側”の両輪が揃うことで、制度の本格的な定着と活用が進む余地が大きい」と指摘しています。
中小企業にとっては、社内制度の整備だけでなく、実務における受け入れノウハウや柔軟な体制づくりが今後の課題となりそうです。逆にいえば、これからの広がり次第で、人材確保・育成の新たな手段として大きなポテンシャルを持つともいえるでしょう。
リスクと対策:制度活用には“注意点の整理”が不可欠

副業・兼業制度を安全かつ効果的に活用するには、企業・個人の双方におけるリスクへの備えが欠かせません。以下に、主な注意点とその対策を整理します。
✅ 長時間労働の防止
副業により労働時間が増えすぎると、健康リスクや本業への支障が懸念されます。
厚生労働省は「労働時間通算の原則」や「管理モデル(簡便な時間管理方式)」を提示しており、就業規則や届出様式の整備、運用ルールの明確化によりリスクの抑制が可能とされています。
特に本業+副業で時間外労働の合計が一定時間を超える場合のチェック体制は重要です。
✅ 情報管理・競業リスクの回避
副業・兼業の活用において、最も注意すべきは情報漏洩や競業のリスクです。
秘密保持義務や競業禁止の線引きをあいまいにしたまま制度を運用すると、以下のような問題が発生する恐れがあります:
・社内情報の流出
・利益相反や企業ブランドの毀損
・労務管理上の混乱(指揮命令系統の不明確化など)
このため、副業の業務範囲や職種・時間帯などを制度設計段階で具体的に規定しておくことが、企業にとってのトラブル回避のカギとなります。
✅ 詐欺的副業への注意喚起
近年、SNSなどを通じて広がる「簡単に稼げる副業」をうたった詐欺が急増しています。
国民生活センターや消費者庁は以下のようなケースに対し、強い注意喚起を行っています:
・前払い金を要求される
・個人名義の口座に振り込みを促される
・副業に必要な“講座”や“初期投資”と称した高額請求
こうした案件は、実質的な労働が存在しない“情報商材型詐欺”である場合も多く、特に副業初心者は慎重な判断が求められます。
企業にとっては制度設計と管理体制の整備が、個人にとっては信頼できる情報の見極めと自衛意識が、健全な副業環境づくりの前提条件となります。
浸透を阻む“ギャップ”はどこにある?

副業・兼業制度の制度化や企業側の容認が進む一方で、現実として活用が伸び悩む背景には、いくつかの“ギャップ”が存在しています。各種民間調査でも、以下のような課題が繰り返し指摘されています。
✅ 1. 需要と供給のミスマッチ
副業希望者のスキルや関心と、企業側の副業求人における要件・期待値が一致しないケースが多く見られます。たとえば、「クリエイティブな経験を積みたい個人」と「即戦力を求める企業」の間で目的やスタンスが食い違うことが、受入れの難しさにつながっています。
✅ 2. 本業多忙と評価への不安
多くの労働者は副業に関心を持ちながらも、「本業が忙しくて時間が取れない」「副業が本業での評価に悪影響を及ぼすのでは」という懸念を抱えています。たとえテレワークやハイブリッド勤務が可能であっても、業務の再設計や負荷分散の仕組みが整っていなければ、副業は現実的に“できない選択肢”になりやすいのが現状です。
✅ 3. 受け入れ設計の未成熟
副業人材を受け入れる企業側でも、「オンボーディング体制が整っていない」「業務の切り出し方や成果の定義があいまい」といった課題が散見されます。とくに中小企業では、副業人材の活用経験が少なく、業務設計や評価制度が“本業中心の常識”にとどまっているケースも多く見られます。
こうした“制度はあるが現場で機能しない”ギャップを埋めるには、副業の受け皿となる業務の具体化や、評価・労務制度の再設計が突破口となります。
企業と個人が対等なパートナーとして協働できる仕組みが、副業制度の実効性を左右する鍵となるでしょう。
どう始める?個人・企業の実践チェックリスト

副業・兼業制度を活用するには、個人と企業の双方が事前に確認すべきポイントを把握しておくことが重要です。以下に、実践に向けたチェックリストを整理しました。
個人編:はじめる前に確認したいこと
1.就業規則の確認
自社で副業が「許可制」なのか「申告制」なのか、禁止業務や競業制限の規定があるかを必ずチェックしましょう。
厚生労働省のガイドラインでも、就業規則の明文化が重要とされています。
2.労働時間と健康管理の意識
副業は本業との合算で過重労働にならないよう管理が必要です。
簡易な記録方法(管理モデル)を活用しつつ、十分な睡眠・休息を確保することも大切です。
3.税・住民税の申告ルール
給与以外の所得が年20万円を超える場合は確定申告が必要(所得税)。
一方で、所得税では副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、多くの自治体では住民税の申告が必要です(例:さいたま市、北九州市など)。
4.詐欺的副業への警戒
「前払いを要求する」「高額な情報商材を売りつける」「SNSで“楽して稼げる”と勧誘される」といったケースには要注意。
消費者庁や国民生活センターが注意喚起を出しており、副業詐欺の手口は年々巧妙化しています。
企業編:制度づくり・受け入れ体制の整備
1.副業ポリシーと申請窓口の明確化
許可の要否、業務範囲、競業・情報管理の線引きなどを明文化し、従業員に共有。
申請・承認フローを明確にし、相談しやすい窓口を設けることが信頼につながります。
2.労働時間把握の仕組みづくり
副業時間を含めた労働管理のため、届出様式や簡易管理モデルの導入が有効です。
健康配慮も含めた“見える化”が求められます。
3.受け入れ側の制度設計(副業人材を受け入れる場合)
– 業務の切り出し方(役割定義)
– 成果の定義(何をもって完了とするか)
– オンボーディング手順(初期説明や業務導入の流れ)
といった設計が不十分だと、双方にとって不満足な結果につながりかねません。
4.先行事例からの学び
厚労省が公開する「副業・兼業の事例集〜24社から学ぶ〜」や『中小企業白書』などの資料を活用し、同規模・同業種での取り組みを参考にすることも有効です。
副業制度の活用は、個人にとっての「新たな挑戦の機会」、企業にとっての「人材戦略のアップデート」を意味します。その一歩を、ルールと実務の両面から丁寧に整えることが成功のカギとなります。
展望:副業は“オプション”から“インフラ”へ

副業・兼業をめぐる環境は、今や「例外的な働き方」から「選択可能な働き方」へ、そして将来的には“働き方のインフラ”としての位置づけへと進化しつつあります。
企業側の姿勢も変化しつつあり、副業を容認する企業はすでに主流派となりつつあります。また、働き手側の副業への意向も依然として高水準を維持しており、制度整備や受け入れ体制が進むことで、実施率の緩やかな上昇が見込まれる局面に入っています。
中小企業庁も、「副業人材の受け入れは、人手不足対応や外部知見の導入によるイノベーション促進の有効な手段になり得る」と評価。特に専門性の高い人材の一時的な登用や、プロボノ型でのスキル支援といった形で、柔軟かつ実用的な活用が拡大しつつあります。
さらに、行政側も副業促進に呼応するかたちで、「学び直し(リスキリング)」や「越境学習」の推進を打ち出しており、企業内外をまたいで得た経験を個人のキャリア資産として高めるための支援が広がっています。
今後は、副業が単なる「収入補完」ではなく、学び・成長・関係性の再構築を可能にする“社会的インフラ”としての役割を果たしていくことが期待されます。
企業と個人、そして行政が三位一体で仕組みを進化させていくことで、より多様で持続可能な働き方が実現される未来が見えてきています。
まとめ:副業・兼業の次なるステージへ

副業・兼業を取り巻く環境は、この数年で大きく様変わりしました。
制度の整備、企業の容認、テレワークなどの働き方の柔軟化、さらには多様な事例の蓄積により、「副業は特別なもの」という時代から、「自分らしい働き方の一環」として定着しつつある段階へと移行しています。
一方で、実際の活用にはなお多くの課題も残されています。
スキルと求人のミスマッチ、企業内での評価不安、受け入れ設計の未成熟など、“制度があっても活用されない”ギャップは根強く、本格的な普及には制度と現場の両面からの再設計が不可欠です。
中小企業においても、副業人材の受け入れは人手不足やスキル補完の有効な選択肢であり、戦略的に取り入れる動きが出始めています。
さらに、行政や支援機関も「学び直し」や「越境経験」の価値を後押しし、副業がキャリア開発・地域活性・イノベーション創出を支える“実践の場”として機能する土壌が整いつつあります。
これからの時代において、副業・兼業は単なる収入手段にとどまらず、「人と組織の可能性を広げる社会的インフラ」としてますます重要な位置を占めていくでしょう。