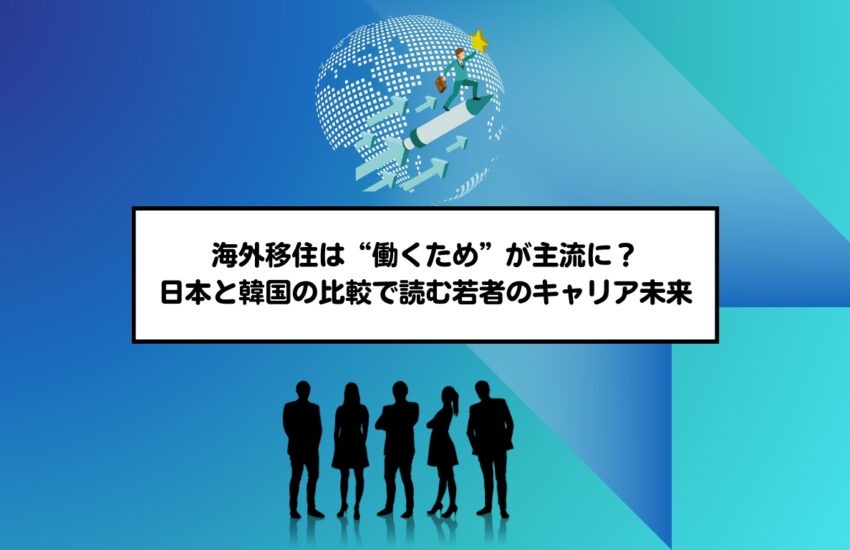日本ではこれまで、海外移住といえばリタイア後のロングステイが中心でした。
しかし今、若者の間で「働くための海外移住」が現実的な選択肢となりつつあります。
背景には、賃金停滞・円安・人口減少といった構造的な課題が横たわっています。
一方、韓国では超少子化や地域衰退を受け、若年層の海外志向が制度によって後押しされています。
本記事では、日本と韓国の制度・意識の違いに注目し、今後の移住トレンドをデータとともに読み解きます。
日本人はどこに移住している?

2024年10月1日時点で、海外に住む日本人(在外邦人)は約129.3万人にのぼります。
このうち、長期滞在者は約71.3万人(全体の55.1%)、永住者は約58.0万人です。
【地域別の分布(外務省データ)】
・北米:37.9%
・アジア:26.9%
・西ヨーロッパ:16.7%
【国別の上位(外務省データ)】
・アメリカ:32.0%
・オーストラリア:8.1%
・中国:7.5%
若年層の海外移住は本当に増えている?
「若者の海外移住が増えているのか?」という問いに対しては、現時点で在外邦人統計に年齢別の構成は含まれていません。そのため、直接的な数値で若年層の傾向を把握することは難しい状況ですが、若者の「海外志向」を示す近接指標として、海外留学のデータがあります。
【海外留学の回復(日本学生支援機構)】
2023年度に海外留学を開始した日本人:89,179人(前年比 +53.3%)
内訳:
・協定に基づく留学:56,560人
・協定外の留学:32,619人
コロナ禍を経て、留学は急回復しており、パンデミック前の水準を上回る勢いです。
若者の海外移住は今後どうなる?
公的な統計の設計上、「若者の海外就労や移住」をピンポイントで捉える時系列データは限られています。しかし、在外邦人の総数が高止まりしている一方で、留学を通じた“海外志向”の若年層が確実に増えている兆しが見えてきます。
これは将来的な「海外就業」や「移住」へのステップとして注目される動きであり、若者による越境行動の裾野が広がりつつあるといえるでしょう。
なぜ若者は海外を選ぶのか?

若者が「海外で働く・暮らす」ことを現実的な選択肢として捉えるようになった背景には、いくつかの社会経済的な要因があります。
賃金と購買力の差が移住を後押し
OECDが公表する「平均年間賃金(購買力平価換算・PPP)」によれば、日本の水準は2020年以降、韓国を下回る状態が続いています。名目賃金はここ数年でようやく上昇傾向にありますが、インフレを考慮した実質賃金の回復は限定的です。
そのため、「同じ仕事をするなら海外の方が稼げる」と感じる若者が増えても不思議ではありません。とくに購買力の観点では、その実感は強まっています。
人手不足と物価高がキャリア選択に影響
日本では深刻な人手不足が続いており、若年層にとっての就職の“選択肢”は広がっているといえます。しかし同時に、国内では賃金プレミアム(希少性による高賃金)の圧縮や、生活コストの上昇も進行中です。
OECDの最新レポートでも、2025年の日本は「失業率2.5%」と雇用は堅調ながら、物価高の影響で「実質賃金はまだ完全に回復していない」と評価されています。
このような状況下では、若者が報酬や成長機会をより多く得られる“グローバル市場”への関心を強めるのは自然な流れといえるでしょう。
リモート普及と円安で働き方は国境を超える
リモートワークの普及や、英語圏・アジア圏でのIT人材や専門職の需要の高さは依然として続いています。これにより、「日本にいながら海外の企業で働く」「海外移住してもキャリアを維持する」といった“可搬性のある働き方”が現実的な選択肢となりつつあります。
また、為替変動の影響も無視できません。円安傾向が続けば、「外貨で稼ぐ」ことの経済的メリットが大きくなります。
まとめ:移動を前提としたキャリア志向が広がる
かつては一部の限られた人に限られていた「海外移住」という選択が、いまや若い世代にとって経済合理性と可能性を備えた“現実的な選択肢”になりつつあります。
賃金、物価、働き方、そしてキャリアの見通し——。こうした複数の要因が交差し、日本の若年層の海外志向を後押ししているのです。
韓国の若者が海外に向かう理由

韓国では、少子化と地方の人口縮小という深刻な構造問題を背景に、「海外」を視野に入れたキャリア形成が現実的な選択肢として制度的に位置づけられつつあります。
韓国の出生率は世界最低水準に
韓国の合計特殊出生率は2023年時点で「0.72」と、世界最低水準を更新。同年の出生数は約23万人と、人口再生産に必要とされる水準からは大きく乖離しています。
このような少子化は、社会保障・労働市場・地域経済の持続性に影響を与えており、中長期的な人材戦略の見直しが急務となっています。
在外コリアン708万人が示す海外志向
2022年末時点で、在外コリアンは約708万人にのぼります。
その内訳は以下の通りです:
・韓国国籍の在外居住者:約246万人
・外国籍の同胞(移住者の子孫など):約461万人
この数は、日本の在外邦人(約129万人)と比較しても非常に多く、「海外とつながるキャリア設計」が社会に根付いていることが読み取れます。
KOTRAなど政府による海外就職支援
韓国では、若年層のグローバルなキャリア展開を支援する制度がすでに整っています。
たとえば、政府系のK-MOVEプログラムやKOTRA(大韓貿易投資振興公社)が代表例です。
・2023年、KOTRAは計1,263人の海外就職を支援
・そのうち、日本向けの就職者は208人(全体の16.4%)
こうした支援制度により、「海外で働くこと」が“選ばれうる進路”として制度的に整備されているのです。
地方人口の減少が若者の流出を加速
少子化と並行して、韓国の地方都市では急速な人口縮小が進行中です。
・2022年には155の市・郡・区で人口が対前年比減少
・地方自治体の将来推計でも、今後も減少トレンドが続く見通し
この傾向は、地方からの人材流出を加速させ、若者の都市集中や海外志向を後押しする要因となっています。
制度で後押しされる韓国の移住

韓国の若年層が「海外で働く」ことを現実的な選択肢として捉えている背景には、個人の意思だけでなく、制度的・構造的な後押しが存在します。
その要素を整理すると、次の3点が挙げられます。
地方縮小が「外に出る」動きを強める
少子化とともに、首都圏以外の地方都市で人口減少が急速に進んでおり、地域における雇用や生活の選択肢が限られてきています。 結果として、若者が「地元に残る」以外の選択肢を模索する動きが強まっているのです。
若者の挑戦志向とグローバル思考
韓国の若年層の間では、「より高い報酬」「成長できる環境」「国際的なキャリア」を求める志向が強まっています。
海外を視野に入れることは、単なる逃避ではなく、より良い機会を求める“積極的な選択”となっています。
国主導で進む海外就職支援の整備
K-MOVEなどに代表される政府主導の海外就職支援制度が確立されており、若者が海外に挑戦しやすい環境が制度的に整えられています。
これは、「海外で働くこと」を個人任せにしない国家戦略的な取り組みとも言えます。
このように、
・地方の縮小という構造的背景
・若者のグローバル志向という社会的潮流
・制度的な支援という政策的後押し
これら三つが重なり合うことで、韓国においては「海外で働く」という選択が、制度にも社会にも組み込まれた“標準的なキャリアルート”として可視化されているのです。
日本と韓国の違いはどこ?

日本と韓国は、社会構造の多くの側面で共通点を持っています。
しかし、「海外就労・移住」に対する制度設計や社会的なアプローチには、明確な違いが存在します。
共通する社会構造:少子化・格差・都市集中
両国に共通する構造的課題は、以下の3点に集約されます:
・少子高齢化の進行
・地方と都市の間にある機会の偏在
・購買力平価(PPP)ベースで見た賃金水準の相対的な弱さ
こうした背景のもと、若者が「海外での就労」や「移住」を意識する構図は、日本でも韓国でも大きく変わりません。
明暗を分ける政策のスピードと制度化
最大の違いは、その現象に対して政府がどう関与しているかという点です。
韓国では、
・KOTRA(大韓貿易投資振興公社)
・産業人力公団
といった政府系機関が、海外就職を希望する若者を制度的・面的に支援しています。
キャリア形成の中に「一時的な海外就労→スキルと経験の国内還流」といった“循環モデル”が政策として明示されているのが特徴です。
一方、日本では、
・官主導の越境就労支援はまだ限定的であり、
・海外留学、個別企業の採用、フリーランスとしての越境労働などが、主な選択肢となっています。
そのため、日本では「個人主導の挑戦」が主軸となり、制度的な支援や環境整備は韓国に比べて遅れているのが実情です。
制度が先か、個人が先か:日韓の違い
韓国は、「海外に出ること」を前提とした人材戦略が国全体で構築されており、社会全体でその選択を支える体制があります。対して日本は、個人が先に動き、制度がそれに追いつく構造となっており、「越境する人」はまだ限られた存在になりがちです。
この違いは、若者の移動性、経験の蓄積、将来の人材還流力において、今後の国家競争力にも影響を及ぼす可能性があります。
10年後、海外移住はどうなる?

「海外で働く」ことが若者にとって現実的なキャリア選択になりつつある現在、今後10年を見据えたとき、何が追い風となり、どこに課題が残るのか。データと構造的なトレンドをもとに、展望と論点を整理します。
海外移住を後押しする要因
1|グローバル人材需要の拡大
英語圏やアジア諸国を中心に、デジタル系や専門職(IT、医療、工学など)における人材不足は慢性的です。
グローバル市場では「質の高い人材をどこから確保するか」が課題となっており、日本人若年層の流動性が評価される余地は広がっています。
2|国内の賃金・物価・税のジレンマ
日本国内では、実質賃金の伸び悩みと生活コスト(物価・税)の上昇という二重苦が続いています。
OECDも指摘するように、高齢化による経済的負担の増大は構造的であり、短期的な改善は見込みにくい状況です。
3|海外経験がキャリアの標準に?
2023年度には89,179人が海外留学を開始。
これはコロナ禍以前を超える水準であり、若年層の「国境を越えること」への心理的・実務的ハードルが下がっていることを示しています。
今後は「まずは海外で経験を積む」ことがキャリアのスタンダード化していく可能性もあります。
課題として残る点
1|言語と専門性の両立が不可欠
海外での就業において、評価されるのは「英語(あるいは現地語)+職能スキルのセット」です。
言語力だけでも、専門スキルだけでも不十分であり、国際的な競争環境で“通用する力”を育てる教育設計が必要です。
2|社会保障制度と制度的な壁
医療、年金、税制といった社会保障制度の適用範囲や二国間協定の有無は、長期滞在や帰国後の生活に直結します。
また、滞在資格の維持・更新に関わるルールも複雑で、“制度の壁”が移動の障壁になることも少なくありません。
3|日本の国家戦略が不透明なまま
最大の論点は、「人材の海外流出を防ぐべき」なのか、それとも「一度外に出して、経験を持ち帰らせる循環型モデルを構築すべき」なのかという国家戦略の立ち位置です。
OECDは、高齢化社会で持続的成長を保つためには、「女性・高齢者・移民」の労働参加拡大が不可欠としています。この文脈で見れば、海外経験をもつ若者を“還流資産”とみなす発想も不可欠でしょう。
まとめ:「移動」が常識になる時代に備えて
10年後、「日本人が海外で働くこと」は一部の特別な人の選択肢ではなく、広く一般化したキャリアのひとつになっている可能性があります。
それに備えるには、制度の整備、教育の転換、そして国家としての長期ビジョンが求められます。
移住は特別から日常へ

かつて、海外移住は「老後にゆとりをもって暮らすための特別な選択」として語られることが多くありました。
しかし今、その風景は大きく変わりつつあります。
若者は“働くために”移住する時代へ
韓国ではすでに、若年層の海外就職が国家政策として可視化され、実績も伴っています。
たとえば、KOTRA(大韓貿易投資振興公社)は2023年に1,263人の海外就職を支援し、そのうち日本向けは208人にのぼります。
つまり、「海外で働くこと」が制度として“選べる選択肢”になっているのです。
日本も移住を合理的選択肢として考えるとき
日本も同様に、少子化・地域縮小・実質賃金の伸び悩みといった構造的な課題を抱えています。
この共通の課題を前にしたとき、若者が「越境キャリア」を選ぶことは、もはや特別なことではなく、合理的な判断だと言えるでしょう。
これからの時代に必要な3つの要素
この流れを一過性の現象に終わらせず、未来に向けた持続可能なキャリア戦略とするためには、以下の3つが重要です:
1.個人:世界で通用するスキルを磨くこと
― 言語力だけでなく、専門性や異文化適応力を含めた「越境可能な力」を育てる
2.企業:越境人材を受け入れる仕組みの整備
― 海外経験者を活かせる柔軟な制度・ポジション設計、ダイバーシティへの理解が求められる
3.国家:還流可能なエコシステムの構築
― 海外に出た人が「戻ってこられる」「関わり続けられる」仕組み(例:税・年金・社会保障の連携、越境型起業支援など)
移住は特別な挑戦から当たり前の選択へ
グローバルに働くという選択肢は、もはや“特別”ではありません。
これからの時代に必要なのは、それを支える制度と意識のアップデートです。
日本社会が「出ていくこと」と「戻ってくること」の両方を受け入れる準備ができるかどうか——それが問われています。