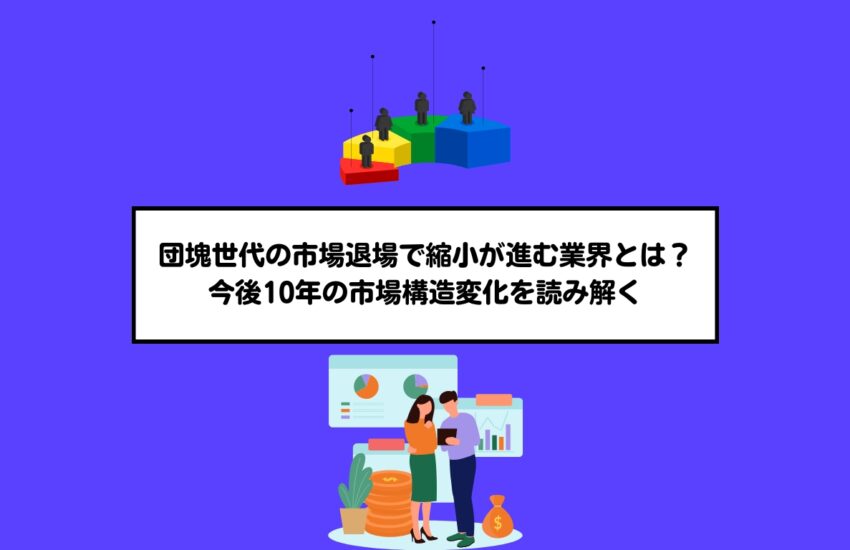団塊世代は、長らく日本の需要を牽引してきた最大級の消費コーホート(特定の共通項を持つ集団)でした。しかし、同世代が後期高齢期に入り、移動・購買・保有の各行動に変化が表れています。
本稿では、どの市場で縮小が先行しやすいのか、どの順序で進むのか、そして事業側の実務的な対応策を整理します。
団塊世代の市場影響とは?——“可処分時間×所得×健康余命”がもたらした黄金期

団塊世代(主に1947〜49年生まれ)は、戦後の復興と高度経済成長期を生き抜いた“経済の主役世代”でした。彼らは安定した職業に就き、長年の勤続や年功序列制度に支えられて比較的高い所得を得ていました。さらに退職後も年金や貯蓄が十分にあり、「お金」と「時間」の両方に余裕を持つことができたのです。この経済的・時間的ゆとりが、アクティブシニア市場を大きく育てました。
旅行・レジャー市場のけん引役
団塊世代は、仕事一筋の現役時代を終えると「第二の人生」を謳歌しようと、旅行や趣味に積極的にお金を使いました。夫婦での温泉旅行、友人同士の海外ツアー、ゴルフやカラオケといった娯楽は、まさにこの世代が牽引したブームです。
特に「団体旅行」が定着したのは、同世代同士で価値観や嗜好が似通っていたから。皆が同じテレビ番組を見て育ち、似たような生活体験を共有していたため、「みんなで一緒に楽しむ」スタイルが自然に広まりました。
消費行動の特徴:量×単価で市場を押し上げ
この世代は人口規模が大きく、しかも1人あたりの消費額も高かったため、企業にとっては“理想的な顧客層”でした。旅行、外食、高級家電、ブランド品、さらには雑誌や新聞などの紙媒体まで、あらゆる業界で「団塊世代向け商品」が花盛りとなりました。
特に1990年代から2000年代初頭にかけては、「シニア向け高品質ツアー」「プレミアム家電」「健康志向食品」など、単価の高い商品が次々にヒットしました。彼らの消費は“量”と“質”の両面で市場を支え、企業の売上を押し上げていたのです。
同質的な文化と社交性
団塊世代は、戦後教育の中で「みんなと同じ」が重視された時代に育ちました。そのため、流行やトレンドに対して「みんなが買うなら自分も」という同調性が強く、集団消費を促進しました。
また、地域のサークル活動や同窓会、OB会など、社交的なつながりを大切にする傾向がありました。これが、団体旅行や趣味サークル、カラオケ大会などの市場を後押しする結果につながったのです。
団塊世代の退場で縮小が進む主要市場7分野

① 旅行・レジャー業界 —— 地方観光地と団体旅行の危機
かつて日本の観光業を支えた「平日旅行」や「団体旅行」は、団塊世代のアクティブシニア層によって成り立っていました。
彼らは時間と資金の両方に余裕があり、平日にゆっくり温泉地や観光地を巡る長期滞在型の旅行スタイルを好みました。ところが、彼らが後期高齢期を迎えるにつれて、こうした旅行形態が急速に減少しています。
平日旅行・長期滞在の減少が直撃
観光地にとって“平日の宿泊客”は、稼働率を安定させる重要な存在です。しかし、団塊世代の高齢化により、長距離移動や階段の多い観光地への旅行を避ける人が増加し、結果として、平日発のツアーや3泊以上の長期逗留プランが激減しています。
特に影響を受けているのは、大型温泉旅館、観光バス会社、土産物店など「団体旅行前提」のビジネスモデルを持つ事業者です。これまで安定的に稼働していた観光バスや宴会場が、稼働率の低下に直面しています。
個人旅行への移行は限定的
一方で、「団体旅行が減っても個人旅行が伸びているのでは?」と見る向きもあります。確かに、若年層や現役世代による短期・近距離旅行は一定の伸びを見せています。しかし、その多くは日帰りや1泊2日といった“ライト層”の動きであり、団体旅行が生み出していた宿泊日数や消費額の“量”には及びません。
たとえば、団体旅行では一人当たり数万円規模の出費があり、地域全体に経済効果が波及していましたが、個人旅行ではその波及が限定的です。
地方経済への波及と構造変化
地方の観光地では、平日の人通りが減る「平日空洞化」と、週末だけ人が集中する「週末偏在」が進んでいます。これにより、飲食店や土産店は平日の営業維持が難しくなり、地元雇用にも影響が出ています。
また、旅行会社も従来の“団体中心モデル”を見直し、地域体験型の小規模ツアーや、交通・宿泊を個別に組み合わせる「モジュール型旅行商品」への転換を模索しています。
② モビリティ・カー用品市場 —— 免許返納が連鎖的影響
かつて自動車は「自由と自立の象徴」でした。特に団塊世代にとって車は、仕事でも家庭でも欠かせない存在であり、レジャーや買い物、家族旅行の中心にありました。
しかし、近年は高齢化に伴い「免許返納」が進み、車を所有するシニア層が減少しています。この変化が、カー用品市場から地域交通まで、幅広い分野に連鎖的な影響を及ぼしています。
高齢ドライバー減少で市場が縮小
団塊世代が運転の第一線から退くにつれ、カー用品、車検整備、自動車保険など、車を取り巻く周辺市場が縮小しています。特に高齢ドライバーは安全装備やナビなど高機能製品の購入意欲が高く、保険加入期間も長期にわたることから、これまで業界を支える“安定顧客層”でした。
しかし、免許返納が進むとこの高齢セグメントがごっそり抜け落ち、販売店や保険会社は新たな需要開拓を迫られています。例えば、ドライブレコーダーやメンテナンス用品の販売数は近年、地方都市を中心に減少傾向にあります。
地方では緩やかなペースも、構造変化は不可避
一方、地方では公共交通の選択肢が限られているため、「まだ車が手放せない」という声も多く、返納のペースは都市部に比べて緩やかです。買い物や通院など生活に直結する移動手段が少ない地域では、軽自動車の保有率が高く、共助型の「乗り合い送迎」や自治体運営の「デマンド交通(予約型バス)」が少しずつ整備され始めています。
それでも全体的なトレンドとしては、車の所有から「必要なときだけ乗る」方向へとシフトしています。
貸切バス・送迎市場の再構築が鍵
団体旅行の減少により、観光バス業界は稼働率の低下に直面しています。しかし、この流れを悲観的に見るだけではなく、新しい需要を取り込む動きも始まっています。
たとえば、スクールバス、企業の通勤送迎、病院や介護施設との連携輸送など、地域生活を支える“社会インフラ型モビリティ”への転換です。これにより、観光中心から地域密着型の運行へと再定義されつつあります。
特に自治体では、「高齢者の移動支援」と「地域交通の維持」を両立するため、AIを活用した最適ルート運行や、予約アプリを使った小型シャトルサービスの導入が進み始めています。
③ 富裕嗜好・百貨店外商市場 —— “買い”から“整理・処分”の時代へ
かつては「人生のごほうび」として、高級腕時計や宝飾品、絵画、オーディオ機器を買い揃えることが、団塊世代の成功の象徴でした。百貨店の外商部門は、こうした顧客を中心に繁盛し、バブル期には数百万円単位の買い物が珍しくありませんでした。
しかし、いまやこの富裕層の消費スタイルは大きく変わりつつあります。“買う時代”から“手放す時代”へ意識の転換が進んでいます。
高級消費は残るが、買い替えサイクルは長期化
現在も一定数の富裕層市場は存続していますが、従来のような頻繁な買い替えや新製品志向は薄れています。たとえば、宝飾品や骨董、高級オーディオなどは、一度購入すれば長く使い続ける傾向が強まり、買い替えサイクルが10年単位に延びています。
団塊世代が70代後半に差し掛かる今、「もうこれ以上は増やさない」「良いものを長く使う」という価値観が主流になりつつあり、消費の“量”よりも“維持・管理”に重点が移っています。
「手放す」「整理する」ことに価値が生まれる
この世代が直面するのが、相続や生前整理の問題です。高価なコレクションや貴金属、美術品は、次の世代にとっては必ずしも“欲しいもの”ではなくなっています。結果として、購入よりも「どう処分するか」「どこに預けるか」といったニーズが増加。
百貨店やブランドショップも、従来の販売中心モデルから「買取」「委託販売」「修理・リユース」などのアフター市場に力を入れるようになりました。近年では、百貨店がリユース専門業者と提携して“外商顧客専用の買取サービス”を展開するケースも増えています。
百貨店外商の役割が変化する
百貨店の外商部門は、かつては「高額商品を売るプロ」でしたが、今後は「顧客の資産と人生に寄り添うパートナー」へと役割が変化しています。
例えば、宝飾品や絵画を資産としてどう管理するか、子どもや孫にどう引き継ぐか、保険や信託とどう組み合わせるか——といった“ライフマネジメント型の提案”が求められています。
また、外商担当が顧客の思い出の品を査定し、次の持ち主へとつなぐ「ストーリー型リユース」など、モノの売買を超えた新たな付加価値が生まれています。
④ メディア・小売市場 —— 紙媒体と地上波広告の脆弱化
かつて新聞や雑誌、テレビは「世代を超えて共通の話題を提供する場」でした。特に団塊世代にとって、朝の新聞、週刊誌の特集、夜のニュース番組は、社会とのつながりを感じる日常習慣の一部でした。
しかし、団塊世代の購読・視聴離脱が進む今、紙媒体や地上波広告を中心とした旧来型メディアの基盤が揺らいでいます。
デジタル移行では埋まらない“読者共同体”の喪失
新聞や雑誌の購読者が減ると単に部数が落ちるだけでなく、「同じものを読む仲間意識」——つまり“読者共同体”が失われます。
紙の媒体には、デジタルにはない“共通の時間と空間”がありました。たとえば、旅行雑誌を片手に次の旅先を語り合う、趣味誌を通じてクラブ活動が広がる、新聞の地域欄をきっかけに町内イベントが活性化する——そうした小さな連帯の場が存在していました。
デジタル版のニュースサイトやアプリでは、記事が個々の関心ごとに分散し、読者間の“共有体験”が生まれにくい傾向があります。そのため、たとえデジタル閲覧数(PV)が増えても、紙媒体が持っていた「定期購読による安定的な収益」と「長期的な読者関係」を再現することは容易ではありません。
結果として、広告主から見た媒体価値も「一時的なアクセス」中心となり、広告単価(CPM)は低下圧力を受けやすくなっています。
広告構造の変化:地上波テレビのKPIミスマッチ
地上波テレビも依然として高齢層の視聴時間を維持していますが、広告主の求める成果指標(KPI)とのズレが問題になっています。
従来のテレビ広告は「視聴率」で価値が判断されていましたが、現在の広告市場では「来店」「予約」「購入」など、デジタルと連動した“行動データ”で成果を測る傾向が強まっています。
このため、視聴時間が長くても購買行動に結びつきにくい層が中心となると、広告主がテレビに投じる予算は減り、結果的にCPM(インプレッションあたりのコスト)の見直しが進みます。
さらに、YouTubeやSNS動画広告のようにターゲットを細かく設定できる媒体と比較すると、テレビは「広く浅い」訴求になりがちです。特に若年層や都市部の視聴者が減る中で、地上波は“ブランドの認知拡大”という上流効果に特化せざるを得なくなっています。
小売への波及:雑誌販路と広告モデルの変容
紙媒体の販売減少は、書店やコンビニなど小売の現場にも影響しています。雑誌ラックの縮小、新聞の宅配網の統合など、かつての“情報の流通インフラ”が収益を維持できなくなりつつあります。
一方で、出版社や広告会社の中には、紙から「コミュニティ型メディア」への転換を模索する動きも見られます。限定イベントや会員制ニュースレターなど、再び“読者共同体”を取り戻そうとする試みが広がっています。
⑤ 金融・保険業界 —— 取り崩し期に入る資産構造
団塊世代が築いてきた莫大な金融資産が、いま「積み上げ」から「取り崩し」へと転じています。現役期には“貯める・増やす”が中心だった家計行動が、退職後は“使う・守る”へと変わり、金融機関の収益構造にも大きな影響を与えています。
店頭投信・保険の成長余地が頭打ちに
銀行や証券会社にとって、これまで団塊世代は安定した収益源でした。特に投資信託(投信)や一時払い生命保険といった金融商品は、退職金の運用先として人気を集め、2000年代以降の店頭販売を支えてきました。しかし、70代後半を迎えた現在は、投資によって資産を「増やす」よりも「減らさない」「安全に保つ」志向が強まり、積極的な購入が減少しています。
資産を取り崩す局面では、投信の“回転売買”や積立残高の増加が難しくなり、金融機関にとっては販売手数料や信託報酬といったフィー収入の逓減が避けられません。
また、一時払い型の生命保険も、相続・贈与ニーズを中心に一定の需要はあるものの、新規の契約件数は伸び悩んでいます。
「資産を守る」から「資産をどう引き継ぐか」へ
今後のキーワードは“運用”よりも“承継(しょうけい)”です。団塊世代の金融資産は、退職金・預貯金・不動産を含めると数千兆円規模にのぼるとされ、今後20年でその大部分が次世代に移る「大相続時代」が訪れます。
この流れの中で、金融機関の関心も「投資商品販売」から「相続設計・資産管理・信託サービス」へとシフトしています。
例えば、遺言信託、家族信託、資産凍結リスクへの備えなど、“人生の終盤に備える金融商品”が拡充しています。また、デジタル化が進む中でも、高齢顧客は「対面相談」への信頼が厚く、店舗や外訪担当者の役割は依然として重要です。
金融業界の課題:次世代との接点づくり
一方で、団塊世代の資産を継ぐ子世代・孫世代は、金融に対する価値観が大きく異なります。ネット証券やスマホ投資、少額分散型の運用など、非対面でのスピード感を重視する傾向が強く、従来型の「店舗中心ビジネス」では関係を維持しにくいのが現実です。金融業界にとっては、資産の移転に合わせて“顧客も世代交代する”構造的リスクが課題になります。
したがって今後は、「親子二世代でのライフプラン設計」や「家族口座管理アプリ」など、世代横断的な金融サービスが重視されるでしょう。これまでの「資産運用提案型」から「人生サポート型」への転換が、業界再成長のカギを握ります。
⑥ 住宅・暮らし関連市場 —— “維持から縮小へ”の住宅行動
団塊世代が現役だった頃、マイホームは“人生最大の夢”であり、“家族の象徴”でした。住宅ローンを完済した後も、「家をきれいに保つ」「庭を手入れする」ことに喜びを見出す人は多く、リフォームやガーデニング市場を長く支えてきました。
しかし、70代を超えたいま、住宅への向き合い方は大きく変わりつつあります。キーワードは“維持”から“縮小”へ。暮らしの重心が「拡張」ではなく「身の丈に合わせた整理・安全・効率」へと移っています。
大型リフォームや高級ガーデニングが逓減傾向に
2000年代にかけて、団塊世代の住宅市場を牽引したのは「快適さ」と「趣味性」を追求する高付加価値リフォームでした。浴室のリノベーションや断熱工事、ウッドデッキや庭造りなど、住まいを楽しむための投資が活発でした。
しかし、70代前半をピークにこうした“拡張型リフォーム”は減少しています。理由はシンプルで、体力・管理負荷・維持コストの問題です。広い庭や大きな一軒家は、掃除・草刈り・修繕といった日常の手間が重くのしかかります。
そのため、「なるべく手をかけず、長持ちさせる」方向へと需要が変化しています。たとえば、外壁塗装や屋根補修など“安全・防災型リフォーム”、手すり設置や段差解消など“バリアフリー工事”、短期間で完了する“部分リフォーム”が主流になっています。
「手放す」「住み替える」選択肢が現実的に
住宅を“資産”として維持するより、“暮らしやすさ”を優先して身の丈に合った住まいへ移る動きも広がっています。
郊外の大型戸建てを手放し、利便性の高いマンションやサービス付き高齢者住宅(サ高住)へ移るケースが増加するに伴い、「空き家の買取」「荷物整理・処分サービス」「住み替え支援」といった新しい需要が拡大しています。特に、不動産会社やリフォーム事業者が協業して“ワンストップでの住み替え支援”を行う事例が増えています。
また、家財や庭の管理を請け負う“暮らしサポート業”や、“実家の片付け代行”といったサービスも中高年層を中心に市場を広げています。かつて「建てる」「直す」だった住宅ビジネスが、いまや「手放す」「小さくする」方向へと再編されつつあるのです。
暮らしの価値観の転換:量から質、所有から軽やかさへ
背景には、物理的な労力の問題だけでなく、心理的な変化もあります。「子どもが独立し、部屋が余っている」「自分たちの生活に本当に必要な空間はどれくらいか」——そんな問いが現実的になり、“減らすこと”がポジティブに捉えられるようになりました。
こうした潮流は、住宅関連市場全体に新しい機会も生んでいます。リフォーム業界では「コンパクトリノベーション」、不動産業界では「空き家の再活用」、家電・家具業界では「省スペース・省エネ型商品」が伸びています。団塊世代の“縮小志向”は、暮らしの最適化ビジネスを育てる新たな土壌になっています。
⑦ 公営競技・街娯楽 —— “現地マス”の時代の終焉
かつての日本には、「同じ場所に集まり、同じ体験を共有する」娯楽が数多くありました。競馬・競輪・競艇といった公営競技、カラオケスナック、社交ダンス、パチンコなど、いずれも“同世代の仲間と現地で盛り上がる”ことが魅力の中心でした。
団塊世代はその中心的な担い手であり、昭和から平成にかけて、こうした“現地マス(mass)型の娯楽文化”を支えてきた世代でもあります。しかし今、その時代が静かに終わりを迎えようとしています。
オンラインで一部補完、しかし「空気感」は戻らず
公営競技の売上自体は、オンライン投票やアプリ導入により一定程度持ち直しています。特にコロナ禍以降は、在宅での投票が普及し、デジタルで“買う”行動は定着しました。とはいえ、「現地で仲間と声を張り上げる」「レース場の熱気を共有する」といった“身体的な娯楽体験”は戻りにくくなっています。
同様に、カラオケや社交ダンスなど、複数人での参加が前提となる娯楽も、参加者の高齢化と感染リスクへの意識が重なり、利用頻度が減少しています。特に夜間外出や飲酒を伴う娯楽は、健康面・安全面から控える傾向が強まり、街のナイトカルチャーもかつての勢いを失いつつあります。
“同世代コミュニティ”の弱体化が直撃
団塊世代が現役を退いた後も、地域サークルや趣味団体を通じた交流の場が存在していました。しかし、世代交代が進むにつれてこうしたコミュニティの運営が難しくなり、“みんなで集う”文化そのものが縮小しています。
特に、公営競技やカラオケ、ダンスホールといった娯楽は「同年代が集まってこそ成立する空間」であり、人口構成の変化がそのまま市場縮小に直結します。
一方で、若年層や中年層はオンラインゲーム、動画配信、ライブ配信アプリなど“つながりはデジタルで完結する”娯楽に慣れています。そのため、リアル会場を主戦場とする娯楽業界は、顧客の世代交代が進まず、構造的な縮小局面にあります。
これからの方向性:“小さなリアル”と“デジタル連動型体験”
完全にオンラインに置き換えることはできないものの、「小規模・限定型」のリアル体験には依然として価値があります。たとえば、少人数のVIPルーム型カラオケ、地域のダンスサークル、限定観戦イベントなど、“安心して参加できるミニマルなリアル”が再評価されています。
また、公営競技でも、ライブ配信と現地観戦を組み合わせた“デジタル連動型観戦体験”が拡大しつつあります。
つまり、“マスで集う”時代は終わっても、“個人や小集団で深く楽しむ”時代が始まっているのです。団塊世代の退場は、その転換点を象徴しているといえるでしょう。
“縮む市場”を左右する3つの条件

① 代替可能性 —— 下の世代が同じ形で消費を継ぐか?
市場が「縮む」か「形を変えて残る」かを決める最初の条件は、次の世代が同じ消費行動を引き継ぐかどうかです。団塊世代が支えてきた多くの市場では、この“代替可能性”が低下しています。
世代交代は単純な継承ではない
団塊世代と次世代(主に団塊ジュニア・ミレニアル世代)では、価値観・情報の受け取り方・生活スタイルが大きく異なります。団塊世代が「モノを持つ」「集団で楽しむ」ことに価値を見いだしたのに対し、下の世代は「体験を共有する」「デジタルでつながる」方向へと重心を移しています。
そのため、たとえば「団体旅行」や「紙の趣味誌」など、昭和~平成型の“同じフォーマット”をそのまま引き継ぐことは難しくなっています。メディア接触の中心も、新聞・テレビからSNS・YouTube・サブスク配信へと完全に移行しており、企業が同じ販売構造を維持することは現実的ではありません。
「形を変えた継承」にこそチャンスがある
しかし、これはすべての市場が消えるという意味ではありません。フォーマットを変えることで命をつなぐ市場も少なくないのです。
たとえば、かつての「団体旅行」は減りましたが、代わりに「小規模グループでの体験型ツアー」「地域コミュニティ単位の交流イベント」などが台頭しています。また、「紙の雑誌」は縮小しても、そこから派生した「趣味人コミュニティ」「オンラインサロン」「リアルイベント」など、読者の“つながり”を核にした新しい形が生まれています。
つまり、下の世代が「同じ目的を、違う手段で実現する」場合、消費の継承は可能です。モノからコトへ、集団から個人へ、リアルからデジタルへ——その“橋渡しの形”を設計できるかどうかが、業界の持続を左右します。
市場存続の鍵は「価値の翻訳」
企業や自治体がすべきは、単に若い世代に“同じものを売る”ことではなく、世代ごとに異なる価値観へ翻訳することです。
たとえば、「旅行=休暇消費」ではなく「自己成長やリフレッシュの機会」として再定義する、「紙の情報」ではなく「信頼できるキュレーション」として届けるなど、価値の言い換えによって旧市場を次の形へとつなげることが可能です。
市場の“縮み”は、単なる終わりではなく、“形の更新”を迫られるタイミングでもあります。
② 移動負荷 —— 移動が価値の中核か?
市場の縮小を左右する2つ目の条件は、「移動そのものがどれほど価値の一部になっているか」です。高齢化が進むなかで、人が「移動を楽しめる範囲」は確実に狭まっています。移動の距離や回数、負担の大きさが市場の成長余地を左右するようになっています。
長距離・連続移動が前提の市場ほど縮小しやすい
たとえば、団体旅行・観光バス・大型イベント・百貨店など、“現地に行くこと”が前提のビジネスは、加齢による移動負荷の増大に直面しています。
若い頃には「移動そのものが楽しい体験」だったものが、年を重ねると「体力的・心理的なハードル」へと変わっていきます。特に高齢者にとっては、長距離移動や乗り換えの多い行程、階段・混雑・宿泊を伴う外出は大きな負担です。その結果、旅行、レジャー、イベント参加など“遠くに行く型の消費”は縮小しやすくなります。
また、都市部では交通インフラが整っていても、「外出そのものが億劫になる」傾向が強まり、いわゆる“近場消費化”が進行。地方では公共交通の減少が移動制約をさらに強めており、地域によっては「行きたくても行けない」潜在需要が増えています。
価値の再設計:体験を“近づける”・“分ける”
この移動制約を乗り越えるには、体験の「近接化」と「分散化」が鍵になります。つまり、遠くへ行かなくても同じ満足を得られる仕組みをつくることです。
たとえば、
・観光業では「地元再発見ツアー」や「駅前マルシェ」など、“近場での非日常”を企画。
・小売業では「出張販売会」「移動スーパー」など、顧客のほうへ行く販売形態を強化。
・娯楽では「オンライン観戦」「ライブ配信」「メタバース体験」など移動を省略した体験代替が進んでいます。
こうした“移動しない楽しみ方”が普及するほど、従来の「遠出が前提の市場」も形を変えて生き残ることができます。
「移動=価値」から「アクセス=価値」へ
かつては、「遠くへ行く」ことが価値そのものでした。旅行やイベントにおける“移動の手間”は、むしろ特別感や努力の象徴でもあったのです。しかし、これからの時代は、“移動しなくても価値にアクセスできる”設計が求められます。
デジタル技術の発展により、オンラインでの鑑賞・体験・購入が当たり前になった今、「距離の制約をどう超えるか」が企業の競争力を決めるポイントになっています。高齢者市場においては、「近くで」「楽に」「安心して」楽しめる設計こそが、縮小を防ぐ最大の処方箋です。
③ 共同体性 —— 同世代マスが価値源泉か?
市場の縮小を左右する3つ目の条件は、「その市場がどれほど“同世代の一体感”によって支えられていたか」です。つまり、消費の源泉が「個人の好み」ではなく「同世代の共通体験」にあった場合、その世代が退場すると価値そのものが薄れやすくなります。
団塊世代が築いた“同世代マス市場”
団塊世代は、日本史上もっとも大きな人口コホートでした。彼らが社会に出てから半世紀以上、「数の力」がそのまま市場の原動力となってきました。
たとえば、
・同じ雑誌やテレビ番組を見て育ち、
・同じ音楽やブランドを共有し、
・同じ旅行スタイルや趣味を楽しむ。
こうした“横並びの文化”が形成され、企業はその同質的な嗜好に合わせて商品やサービスを設計しました。まさに「みんなが持っている」「みんなが行く」こと自体が価値だったのです。
しかし、こうした“同世代マスの力”が弱まるとき、共同体としての市場も同時に縮小します。
コホートの崩壊=価値の分散
同世代の人数が減少し、行動が分散すると、「共通の話題」や「同じ行動パターン」が消えていきます。これは単なる人口減ではなく、価値共有の基盤そのものの消失を意味します。
かつての「団塊世代マーケット」は、量的規模だけでなく、彼らが同時に同じものを消費する“同期性”によって成り立っていました。
いまやその同期性は、加齢によるライフステージの差、デジタル習熟度の差、健康状態の差などによって細分化されています。結果として、“同世代マス”という市場単位が溶け始めているのです。
新たな共同体づくり:世代を超えた“テーマ型連帯”へ
ただし、共同体性が失われたままでは市場も文化も衰退します。そこで重要になるのが、「世代ではなく、テーマで人をつなぐ」という発想です。
たとえば、
・「健康」「地域活動」「ペット」「環境」「歴史」など、関心軸を共有するコミュニティ。
・オンラインとリアルをつなぐ“ゆるやかな共同体”(SNSグループ+地域イベント)。
・親子・三世代で共に楽しめる仕掛け(地域フェス、家族参加型プログラム)など。
こうした異世代混成・テーマ起点の再編こそが、縮小市場を再び“人が集まる場”へと再生させる鍵です。
つまり、「同世代の輪」ではなく、「関心で結ばれる縁」へ。昭和的な“横の連帯”が衰える一方で、令和的な“ゆるいつながり”が新たな価値源泉になろうとしています。
2035年までの市場縮小シナリオ——“縮小均衡”への時系列予測

2026〜2028年:旅行・媒体業界で「減量化」が顕在化
2026年以降、日本経済の中でまず目に見える形で“縮小の波”が現れるのが、旅行・観光業界と紙媒体を中心としたメディア業界です。これまで団塊世代の旺盛な可処分所得と時間に支えられてきたこれらの分野が、「減量化」と「構造転換」を迫られる時期に入ります。
平日団体旅行の減退と「曜日偏在」の拡大
平日発の団体旅行や長期滞在プランは、アクティブシニア層(70代前半)が支えてきた市場です。彼らが後期高齢期に移行することで、移動負荷・体調リスク・仲間集団の縮小といった要因が重なり、平日稼働率が急速に低下していきます。
旅行会社では「ツアー催行の最低人数を満たせない」「バスや旅館の固定費を回収できない」といった問題が顕在化し、週末や祝日に需要が集中する“曜日偏在”が進みます。
この結果、観光地では「週末は混雑、平日は閑散」という二極化が常態化し、温泉地や地方旅館では従業員の稼働シフトや収益管理が難しくなります。
2027年頃からは、こうした需要の変動を前提に、大型宿泊施設や観光バス会社が“平日休業・週末集中稼働”型の経営設計へとシフトする動きが本格化します。
紙媒体の構造的縮小と「広告単価の鈍化」
同時期に、新聞・雑誌などの紙媒体の購読離脱も加速します。読者の高齢化と購読習慣の自然減により、定期購読モデルの維持が難しくなります。
これに伴い、広告主の出稿判断も変化し、広告単価(CPM)の引き下げ圧力が強まります。出版社や新聞社はデジタル版への移行を進めつつも、「読者の共同体性」「信頼ブランドとしての文脈」をどう維持するかが課題になります。
2026〜2028年の間は、デジタルへの転換期というより、“紙とデジタルの共存が崩れる時期”と位置づけられます。広告主にとっては「効率はデジタル、信頼は紙」という二極化構造の中で、紙媒体が“信頼を支える補完メディア”として再定義される可能性もあります。
大型アセットへの圧力と「コスト最適化」への転換
旅行・メディアの両分野に共通するのは、固定コストの高さと需要変動の大きさです。観光バス、旅館、印刷設備、販売網など、これまで「規模の経済」で支えられてきた資産が、一転して重荷になっていきます。
このため、各業界では2027年ごろから、
・稼働率データに基づく柔軟な運営モデル(週単位・季節単位での稼働調整)
・地方拠点の統廃合や共同運用
・AIによる需要予測と在庫・稼働の自動最適化
といった「スリム化経営」が急速に広がります。
これらの対応は単なるリストラではなく、“縮小を前提に持続可能な均衡を目指す”試みの始まりです。いわば、「拡大再生産」から「縮小均衡」への最初の転換点が、2026〜2028年フェーズです。
2029〜2032年:富裕嗜好・金融で「頭打ち」が明確化
2029年以降、日本の消費市場では“静かな鈍化”が広がります。旅行・メディアといった「体験・外出型」市場に続き、富裕嗜好品・金融商品・車関連といった“資産消費型”分野にも、明確な頭打ち傾向が表れます。
この時期の特徴は、表面的には市場が「安定しているように見える」一方で、中身が「維持」から「整理・再配分」へと転じている点にあります。
高額消費の量的縮小と「再流通」への転換
百貨店外商や高級ブランド市場では、顧客層の中心である団塊世代が後期高齢期に入り、外出・購買頻度が減少します。高級腕時計、宝飾品、骨董、美術品といった嗜好性の高い商品は、「買い替え」よりも「整理・委託販売・資産管理」のフェーズへと移行。
同じ“富裕層市場”であっても、売る・増やすから手放す・つなぐへと軸が変わります。
これにより、百貨店やブランドショップでは「外商による販売」から、「リユース・査定・引継ぎ相談」へと業務の比重がシフトします。リユース企業やオークション、相続支援サービスとの提携が加速し、“アフター消費市場”が主軸産業として浮上します。
店頭型金融の回転難化と「資産再編支援」へのシフト
金融分野でも、団塊世代の資産構造が「取り崩し期」に入り、店頭販売による投資信託や保険商品の回転率が鈍化します。
新規購入や積立増額が減る一方で、解約・償還・現金化が増加。結果として、銀行・証券会社におけるフィー収益(販売手数料・信託報酬)が伸び悩み、店舗収益モデルの見直しが進みます。
この時期の成長余地は、“資産を増やす提案”ではなく、資産を組み替える・引き継ぐ提案にあります。
たとえば、
・老後の生活資金を考慮した資産の分割運用
・不動産と金融資産を組み合わせた「終活ポートフォリオ」
・親子二世代での資産承継設計(信託・贈与・税務連携)
など、「守る+引き継ぐ」型の金融支援が主流となります。銀行や証券会社も、“販売”より“伴走”を重視するコンサルティング型ビジネスへと軸足を移していくでしょう。
車・モビリティ市場の鈍化定着
同時期、車関連市場でも高齢ドライバー層の縮小が明確になります。免許返納や移動習慣の変化により、新車需要だけでなくカー用品、車検、保険といった周辺需要も安定的に減少します。
地方では一定のマイカー依存が続くものの、買い替え周期の長期化と「軽・小型車」への集中が進み、全体として鈍化基調が定着します。
一方で、再編の兆しもあります。カーシェア・送迎・自治体モビリティなど、所有から“支え合い型交通”への移行が進行します。特に高齢者送迎・医療連携・地域交通インフラとしての車利用が注目され、民間・行政連携の新市場が立ち上がる可能性があります。
拡大から「再循環」へ——成熟経済の新段階
この2029〜2032年フェーズは、「縮小」が一時的な衰退ではなく、“再循環型市場”への構造転換期として位置づけられます。
売上の総量が増えなくても、
・所有からリユースへ、
・投資から承継へ、
・消費から維持・管理へ、
という流れの中で、価値が再配置される経済が生まれます。
言い換えれば、「新たに買う人が減る」社会で、“持っている人の次の動き”を支える産業が主役へと入れ替わる時期。それが2029〜2032年の日本市場の姿です。
2033〜2035年:相続・生前整理のピークアウト後、定常化へ
2033年以降、日本社会は「縮むこと」を前提とした新たな安定期に入ります。団塊世代の高齢化が一巡し、相続・生前整理・資産移転といった一連の動きがピークを越えると、急激な変化は徐々に落ち着きを見せます。
市場の多くは、かつての“拡大再生産”を取り戻すことはできないものの、“小さくても持続する安定市場”=縮小均衡という段階へと移行していきます。
相続・整理需要のピークアウトと「再配分後の定常化」
2030年前後に集中していた相続・生前整理・リユース関連の需要は、2033年頃を境に落ち着きを見せます。団塊世代の主要層が80代後半を迎えることで、大規模な資産移転の波が一巡し、これ以降は、次世代(団塊ジュニア〜ミドル世代)による“再配分後の安定期”に入ります。
リユース・買取・不動産売却・家財整理といった市場は、一時的なブームを経て「常設インフラ」的な存在になります。
たとえば、
・相続対応型不動産サービス
・定額制の家財整理・保管サービス
・生活再設計を支援するコンサルティング業
などが地域に根付き、“終活”が特別な行為ではなく日常的なライフマネジメントの一部として定着します。
「無理に増やさない経営」への転換
この時期に多くの企業が直面するのが、「市場の総量が増えない時代」における経営設計です。
過去のように売上や店舗数を増やすことを目的とするのではなく、需要規模に合わせて柔軟に身の丈を整える“縮小均衡経営”が現実的な選択肢になります。
たとえば、
・地方観光では「週末限定」「季節限定」で収益を最適化。
・小売やサービス業では「定常顧客の深堀り」に重点を置き、会員制・地域密着型へ転換。
・住宅・生活サービスでは「維持・修繕・管理」を主軸に据え、長期安定収益を確保。
つまり、“成長を目指さない”のではなく、“成長の定義を変える”段階です。
ボリュームの拡大より、継続のしなやかさに価値を置く経営が、日本経済の新しい常識として定着していきます。
「大きな市場」から「小さな安定ニッチ」へ
市場構造の全体像も、“大市場の時代”から“安定ニッチの集合体”へと変化します。かつて数百万人単位で動いていた市場は、数十万人規模の小商圏に細分化されますが、地域・趣味・ライフスタイルに根差した濃い需要が残ります。
たとえば、
・地元密着の観光・交流事業
・趣味特化型のオンラインコミュニティ+リアルイベント
・高齢者・中年層が共に参加できる地域型スポーツ・文化教室
など、「少人数でも続けられる仕組み」を整えた事業が息の長い安定収益を実現します。このフェーズでは、市場規模よりも持続性・関係性・共感性が経済の軸となります。
縮小の先にある「静かな成熟社会」へ
2035年の日本は、成長を失った社会ではなく、“成長しすぎないことを受け入れた成熟社会”へと変わっています。
企業も自治体も、市場を“拡張する”ことより、“暮らしを保つ”ことを使命とする。その姿は、人口減少社会のネガティブシナリオではなく、「小さく安定する幸福」を探る新しい経済モデルの始まりといえるでしょう。
縮小市場でも“負けない”事業戦略とは?

旅行・観光業:平日需要の再定義とインバウンド置換
・平日用途の再設計
団体依存から、ワーケーション、教育旅行、部活動・合宿、リモート合宿などへ。
・プロダクトの粒度を小さく
大型から小規模・高体験価値(食・自然・学び)へ。
・動線の一気通貫
空港—二次交通—体験まで事前手配を標準化し、言語・決済・返金の摩擦を最小化。
・曜日ミックス平準化
料金・特典設計で平日化インセンティブを明確化。
モビリティ・保険:移動体験と安全支援の融合
・“運転する人”から“移動したい人”へ
ドライバー保険の発想を、移動サブスク/MaaS×見守りへ転換。
・移動不安の軽減
送迎同乗、乗降サポート、医療・観光連携のB2Bソリューションを整備。
百貨店・富裕市場:“所有”から“再流通”への転換
・下取り保証・委託販売を標準メニュー化し、資産化ストーリーで再流通を主導。
・外商の再定義
相続・住み替え・資産組み替えなどライフイベント同席型へ拡張。
メディア・小売:コミュニティ価値とKPI再設計
・紙→デジの単純移行ではなく、オフラインイベント×会員コミュニティで“会いに行く理由”を設計。
・広告KPIの更新
GRP中心から来店・予約・購入へ直結する指標設計と在庫のパフォーマンス運用。
金融:取り崩しDXと家族連携
・“売る”から“取り崩しを設計する”へ
自動売却ルール、税務最適化、家族同席ダッシュボードで可視化。
・遺産の移動先で関係維持
相続前からの次世代ID化(家族口座・教育基金・金融教育イベント)。
住宅・暮らし:メンテ最小化とダウンサイジング支援
・小口サブスクで庭木・雨樋・設備点検を平準化し、短工期バリアフリーを定番化。
・ワンストップ支援
住み替え・家財圧縮・不動産売却・遺品整理を一体で扱うサービス設計。
早期警戒KPI(現場で“縮み”を実感できる指標)

✅宿泊・観光バスの平日稼働率/ADR
✅団体予約の平均人数・直前キャンセル率
✅免許返納件数×地域モビリティ乗車回数の推移
✅店頭投信残高の純減ペース/分配金再投資率
✅百貨店外商の新規獲得数・平均単価
✅紙媒体の定期購読率(65歳以上→75歳以上の移行)
これらは、社内で定点観測しやすく、現場の体感と数値のズレを早期に矯正するのに有用です。
まとめ——団塊世代後の市場で企業が生き残るために

団塊世代の市場退場は、移動負荷が高い/同世代マスが価値源泉/後続が継ぎにくい領域から順に進みます。影響は旅行にとどまらず、モビリティ、富裕嗜好、紙メディア、店頭金融、郊外大型リフォームなど広範です。
重要なのは、縮小を悲観的に捉えるのではなく、平日需要の再定義、インバウンド置換、取り崩し期の金融設計、再流通主導といった“次フェーズ”に合わせた事業の組み替えです。
固定費の高い大型アセットは撤退の判断も視野に、同業連携による集約、外需の取り込みや二拠点運営による転地を適切な順序で検討することが、安定的な縮小均衡下でも持続的に価値を創出する最短経路となります。