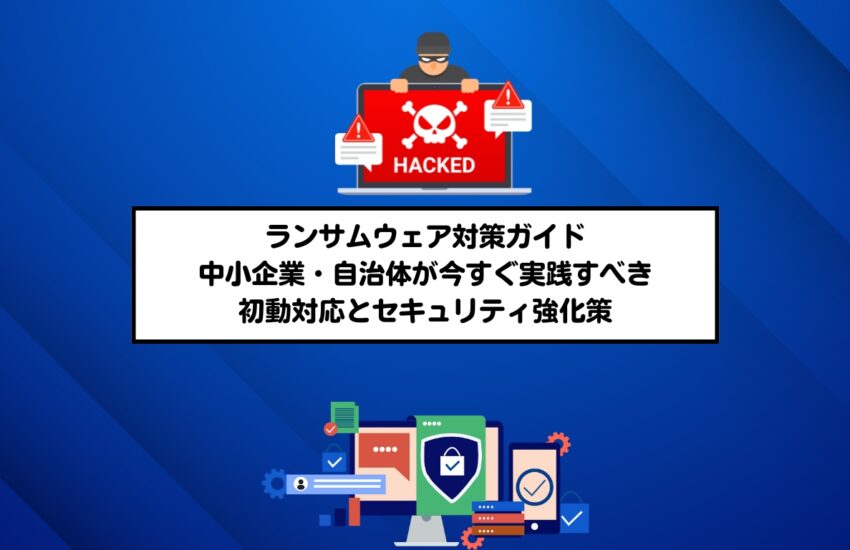ランサムウェア攻撃は、企業規模や業種を問わず発生する一般的な経営リスクとなりました。国内でも、大手企業や自治体が業務停止や情報漏えいなどの被害を受ける事例が報告されており、その影響は取引先や地域社会にも及んでいます。
こうした状況において、情報セキュリティはもはや専門部署だけの課題ではなく、経営層が主体的に取り組むべき経営課題と位置づけられます。中小企業や自治体でも、限られた人員や予算の中で現実的に実施できる対策を段階的に進めることが重要です。
本稿では、初動対応から体制整備まで、組織として「まず着手すべきこと」を整理します。目的は、恐怖をあおることではなく、平時から備えることで被害を最小化するための判断材料を提供することにあります。
ランサムウェア被害が「他人事」でなくなった理由

被害の拡大背景には、攻撃グループの組織化や金銭目的の犯罪ビジネス化があり、その影響は業種・規模を問わず広がっています。
国内で急増する被害と実際の攻撃事例
近年、日本国内でも大企業や社会インフラ級のサービスが相次いでランサムウェア攻撃を受け、受注・出荷の停止、ECサイトの閉鎖、業務の全面停止といった甚大な被害が発生しています。もはや「他人事」ではなく、あらゆる組織が被害対象となり得る状況です。
・ニコニコ(KADOKAWA/ドワンゴ):2024年6月、データセンター内の多数の仮想マシンが暗号化され、主要サービスおよび社内業務が広範囲に停止しました。復旧については「一から作り直す規模」と説明されています。
・アサヒグループホールディングス:2025年9月末、ランサムウェア攻撃により国内の受注・出荷・生産といった中核機能が麻痺。犯行グループ「Qilin(キリン)」による攻撃と報じられています。
・アスクル:2025年10月、攻撃を受けて物流およびECシステムが停止。無印良品やLOFTなど関連企業のオンライン販売にも影響が及び、サプライチェーン全体に波及した典型的な事例となりました。
ランサムウェアとは何か?攻撃の特徴と最新トレンド
ランサムウェアとは、コンピュータやサーバー内のデータを暗号化・窃取し、復旧のための「身代金(Ransom)」を要求するサイバー攻撃です。
近年では、単なる暗号化にとどまらず、情報漏えいの脅迫やDDoS攻撃を組み合わせた「二重・三重の恐喝」が主流になっています。
なぜ中小企業や自治体が狙われるのか
かつては大企業が主な攻撃対象とされていましたが、近年は中小企業や自治体にも被害が拡大しています。その背景には、以下のような要因があります。
・サプライチェーン攻撃の増加:大企業を直接狙うよりも、取引先や委託先である中小企業を踏み台に攻撃する方が容易であるためです。
・セキュリティ体制の脆弱性:VPN設定の不備、古いネットワーク機器の利用、認証の甘さなど、攻撃者にとって侵入しやすい環境が残っているケースが多く見られます。
「対策していなかった」こと自体が最大のリスク
現在のサイバーリスク環境においては、「特別な対策を講じていなかった」という事実そのものが最大の脅威となります。
被害を受けた場合、業務継続の停止、機密情報の流出、取引先との関係断絶といった影響が同時に発生し、損害は億単位に及ぶことも少なくありません。
さらに、信用失墜、行政報告、法的対応といった二次被害も避けられません。今や、「明日、自社が被害者になる」可能性を想定した対策が必須の時代です。
ランサムウェアの仕組みと被害の進行プロセスを理解する
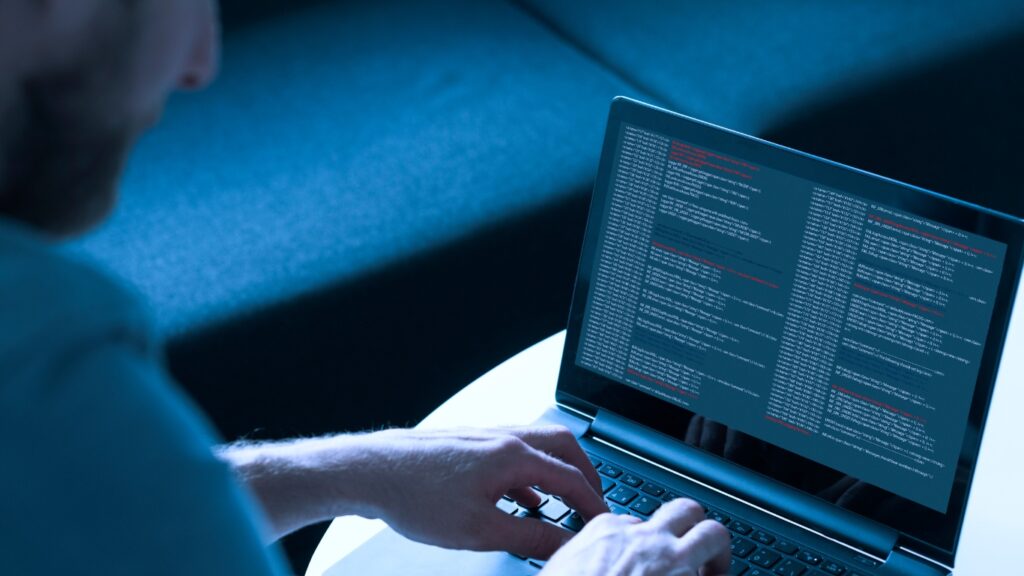
ランサムウェアは複数の経路を通じて侵入し、組織内で段階的に被害を拡大させます。以下では、その主な侵入手口と被害の進行構造を整理します。
主な侵入経路(メール・VPN・認証情報の盗難)
ランサムウェア攻撃は、企業の防御の隙を突く形で多様な経路から侵入します。代表的な手口は以下の通りです。
1.フィッシングメールや不正な添付ファイル、偽サイトによる感染誘導
2.VPNやリモート接続装置の脆弱性・設定不備を突いた侵入
3.盗まれたID・パスワードの悪用(特に多要素認証を導入していない場合に多発)
感染から暗号化・恐喝までの攻撃フロー
攻撃者は侵入後、社内ネットワークを巧妙に探索し、短期間で被害を拡大させます。一般的な攻撃の流れは次の通りです。
1.フィッシングメールやVPN経由で企業ネットワークに侵入
2.社内で横方向に感染を拡大し、管理者権限を奪取
3.機密データを窃取・暗号化
4.復旧と引き換えに身代金を要求
5.支払いに応じない場合は、情報を公開すると二重の脅迫を行う
このように、単なるシステム停止にとどまらず、情報漏えいと恐喝が一体化した攻撃が主流となっています。
バックアップがあっても被害を防げない理由と対策ポイント
「バックアップがあるから安心」とは限りません。近年のランサムウェアは、暗号化を行う前にデータを盗み出すため、バックアップが存在しても情報漏えいは防げないのが実情です。
さらに、オンライン接続されたバックアップシステム自体が暗号化されるケースも多く報告されています。
そのため、
・オフラインまたは書き換え不可能な形式でのバックアップを確保し、
・定期的な復旧テスト(リストアテスト)を実施することが不可欠です。
これにより、万が一の際にも業務を早期に再開できる体制を整えることができます。
初心者でもできる!ランサムウェア対策の5ステップ

サイバー攻撃の脅威が日常化する今、まず重要なのは「どこから手を付ければいいか」を明確にすることです。ここでは、特にこれまで十分な対策を講じてこなかった企業が、最初に取り組むべき5つのステップを整理します。
ステップ① 資産と脆弱性の棚卸し(現状把握)
最初の一歩は、自社のIT環境を正確に把握することです。
✅社内のPC・サーバー・SaaS・ネットワーク機器・境界装置をリスト化する。
✅各アカウントと権限を洗い出し、誰がどの権限を持っているのかを明確化する。
✅外部に公開されているシステム(VPN・Webサーバーなど)を特定し、脆弱性の有無を確認する。
まずは「自社の全体像」を可視化することが、すべての対策の出発点となります。
ステップ②:パスワード・認証の強化(MFA導入が鍵)
多くの侵入は「弱い認証設定」から始まります。パスワード運用の基本を徹底しましょう。
✅パスワードの使い回しを禁止し、長く複雑なパスフレーズを採用する。
✅管理者アカウントには必ず多要素認証(MFA)を導入する。
✅特権IDは最小限に絞り、日常業務での使用を禁止する。
✅退職者アカウントの無効化や共有IDの廃止を確実に行う。
これらはコストをかけずに始められる最も効果的な対策です。
ステップ③:信頼できるバックアップ体制の構築
「バックアップがある=安心」とは限りません。信頼性の高い体制を整備する必要があります。
✅3-2-1ルール(3つのコピー、2種類の媒体、1つはオフライン)を徹底する。
✅重要システムごとに復旧時間目標(RTO)と復旧ポイント目標(RPO)を定義する。
✅四半期に一度の復旧訓練(リストアテスト)を実施し、実際に復旧できるかを検証する。
バックアップは「取ること」よりも「戻せること」が重要です。
ステップ④:社員教育とフィッシング対策の徹底
どんなに堅牢なシステムでも、最終的な防波堤は「人」です。
✅「怪しいメールを開かない」だけでなく、AIで巧妙化した詐欺メールにも対応できるよう訓練する。
✅模擬攻撃メールの演習や通報ルールの明確化を定期的に行う。
✅「発見→隔離→報告」の行動を社員全員が自然に実践できるよう、継続的な教育を行う。
セキュリティ意識は一度の研修では定着しません。習慣化が鍵です。
ステップ⑤:外部専門家・公的支援の活用で“守れる体制”を作る
限られた社内リソースで全てを対応するのは現実的ではありません。外部の専門サービスを積極的に活用しましょう。
✅脆弱性診断、SOC(セキュリティ監視)、MSS(運用監視サービス)などを導入する。
✅国が支援する「サイバーセキュリティお助け隊」では、中小企業向けに24時間監視や緊急駆け付け対応を提供しています。
✅IT導入補助金(セキュリティ対策推進枠)や地方自治体の助成制度を活用し、費用負担を軽減する。
✅自社の取り組みを「SECURITY ACTION(二つ星)」として宣言し、継続的な改善への姿勢を内外に示す。
感染時にやってはいけない初動対応と正しい行動

ランサムウェア感染が疑われる状況では、一つの判断ミスが被害拡大につながる可能性があります。焦らず、冷静に対応することが何より重要です。まずは、次のような行動を絶対に避けてください。
感染時にNGな対応(再起動・放置・無料ツール使用など)
✖感染を隠す、または個人判断で再起動する
→システム復旧の手がかりとなる証拠を消してしまうおそれがあります。✖ネットワークを切断しないまま業務を続ける
→他の端末やサーバーへの感染拡大を招きます。✖インターネット上の“無料復号ツール”を安易に使用する
→偽ツールによる二次感染やデータ破損の危険があります。
これらの行動はいずれも被害を深刻化させる要因となります。まず取るべき行動は、「隔離 →証拠保全→関係者招集→通報」の4ステップです。
すぐに連絡すべき社内・外部機関一覧(JPCERT/CC・IPAなど)
【社内関係者】
・情報システム部門
・CSIRT(インシデント対応チーム)
・経営層
・広報・法務・個人情報管理部門
これらの関係部署を速やかに招集し、対応方針を統一します。
【外部機関】
・JPCERT/CC(一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター)
…インシデント対応支援や被害拡大防止に関する助言を受けられます。
・IPA「情報セキュリティ安心相談窓口」
…中小企業や自治体の相談窓口として、初動対応のアドバイスを提供しています。
・警察庁サイバー事案オンライン通報窓口
…犯罪被害としての正式な通報・相談を行います。
必要に応じて、所管官庁、主要取引先、保険会社への連絡も速やかに行いましょう。
これらの対応を「早く・正確に・組織的に」行うことが、被害の最小化と信頼の維持につながります。
中小企業でも実践できるセキュリティ体制の作り方

サイバー攻撃の高度化により、もはや「専門部署がないから対応できない」という言い訳は通用しません。限られた人員・予算の中でも、中小企業に適した現実的なセキュリティ体制を構築することは十分に可能です。以下では、その具体的なステップを示します。
専門部署がなくてもできる現実的な運用体制
・経営層のコミットメントとポリシー策定
まず経営者自らがセキュリティの重要性を明確に示し、基本方針を策定します。・「ミニCSIRT」(情報システム+総務+現場代表)の設置
専門部門がなくても、関係者で構成する小規模チームで十分に初動対応を組織化できます。・資産・脆弱性の可視化ダッシュボードの導入
社内の端末・アカウント・システム構成を一覧化し、リスク状況を見える化します。・多要素認証(MFA)の全社導入と特権権限の分離
認証の強化とアクセス管理の徹底は、最もコスト効率の高い防御策です。・バックアップ演習・業務停止訓練の定期実施
「もし止まったらどうするか」を全社員が理解し、復旧手順を確認することで、被害拡大を防ぎます。・SOC/MSSサービスの外部委託による常時監視
外部専門家による24時間監視体制を取り入れることで、自社に専門人材がいなくても継続的な防御が可能です。
「診断→是正→監視→演習」のサイクルで継続的に改善
一度対策を講じて終わりではなく、「診断 → 是正 → 監視 → 演習」のサイクルを四半期ごとに回す仕組みが理想です。 外部パートナーやクラウド型ツールを活用し、継続的に改善を重ねる“運用型セキュリティ”を目指します。
また、段階的にゼロトラストの考え方(すべてを信頼しない設計思想)を取り入れることで、社内外の境界を問わずリスクを最小化できます。
情報セキュリティ基本方針と“報告文化”の浸透方法
✅経営者名義での基本方針公開
自社サイト等で情報セキュリティ基本方針を公表することで、取引先や顧客への信頼性を高めます。
✅KPIによる改善の見える化
MFA導入率、訓練実施回数、報告件数などを指標化し、定期的に達成度を確認します。
✅「報告しても責められない」文化づくり
社員が「疑わしいメールを見つけたら即報告」できる心理的安全性を確保することが、結果的に最大の防御になります。
限られたリソースの中でも、「経営層のリーダーシップ」+「小さなチームの継続運用」+「外部支援の活用」によって、実効性のあるセキュリティ体制を実現できます。重要なのは“完璧”を目指すことではなく、継続的に改善し続ける姿勢です。
まとめ|今日から始める5つの基本行動

完璧を目指す必要はありません。重要なのは、「リスクを認識し、できることから着実に始めること」です。
サイバー攻撃の脅威は待ってくれませんが、対策の第一歩は今日から踏み出せます。以下の5つの行動を「今週中に着手する目標」として進めてみましょう。
資産棚卸し・多要素認証・バックアップ・社員教育・外部連携
1.資産と権限の棚卸し
自社のIT資産とアカウント構成を可視化し、どこにリスクがあるかを把握する。
2.多要素認証の導入と特権権限の最小化
認証強化とアクセス制御の徹底により、不正侵入のリスクを大幅に減らす。
3.オフラインを含むバックアップと復旧訓練の実施
バックアップは“保存”よりも“復元”を意識し、定期的にリストアテストを行う。
4.社員教育(フィッシング模擬訓練+報告体制の整備)
「気づいたら報告」が自然にできる文化を醸成する。
5.外部専門家との連携(SOC/MSS・お助け隊など)
専門家の支援を受けながら、継続的な監視・改善体制を整える。
中小企業でも、「何もしていない状態」から「守れる組織」へと確実に進化できます。一歩を踏み出すことが、最大のセキュリティ対策です。
無料で使える公的支援・ツール
中小企業がサイバーセキュリティ対策を始める際に、「どこから手をつければいいか分からない」「費用をかけずにできることはないか」と悩むケースは少なくありません。実は、国や公的機関が提供する無料または低負担で利用できる診断・支援ツールが多数用意されています。
たとえば、IPA(情報処理推進機構)が運営する「ランサムウェア対策情報」特設ページでは、最新の被害事例や対策ガイド、復号支援ツールへのリンクがまとめられています。また、国際的なプロジェクトである「No More Ransom」では、実際に暗号化されたデータを無料で復旧できるツールや教材を入手できます。
さらに、IPAの「SECURITY ACTION(二つ星)」自己宣言制度を活用すれば、自社のセキュリティ対策を可視化し、取引先や顧客への信頼を高めることが可能です。加えて、IT導入補助金〈セキュリティ対策推進枠〉やサイバーセキュリティお助け隊サービスを利用すれば、最大150万円の補助を受けながら、常時監視や緊急対応などの支援を受けることもできます。
これらの公的支援をうまく組み合わせることで、「低コストでも実効性のあるセキュリティ対策」を実現できます。