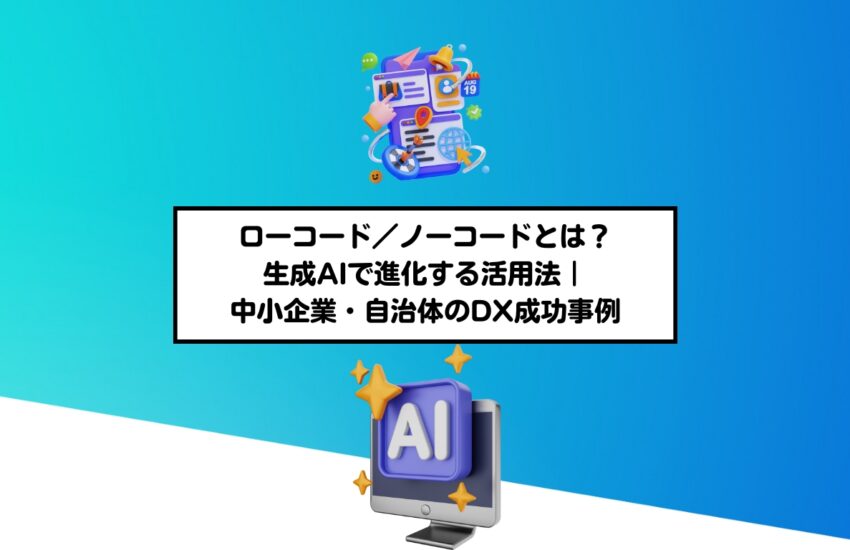「ローコード/ノーコードって本当に役立つの?」と思ったことはありませんか。
いま、生成AIと組み合わせることで、中小企業や自治体でも低コストで業務改善やDXを実現する成功事例が増えています。
この記事では、その仕組みと実際の活用事例をわかりやすく紹介します。
ローコード/ノーコードとは?基本の仕組みと特徴

ローコード/ノーコード開発とは、従来のように専門的なプログラミング言語を使わなくても、業務アプリやシステムを構築できる開発手法のことです。GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を使って、直感的に画面を操作しながらアプリを作れるため、エンジニアでなくても現場の課題に合わせたツールが作れるようになります。
ローコードとノーコードの違い
・ノーコード:完全にコード不要。ドラッグ&ドロップで操作可能。非エンジニア向け。
・ローコード:基本はGUI操作だが、一部コードを用いることで柔軟な拡張が可能。IT担当者や業務システムを高度化したい場面に適する。
中小企業や自治体で注目される理由
・IT人材の不足:開発を外部に丸投げせず、現場主導で改善できる。
・スピードとコストのバランス:短期間で開発でき、ベンダー費用も抑えられる。
・業務に即した開発が可能:現場の業務担当者が自分でアプリを作れるため、要件のズレが少ない。
特に「小さな業務改善を素早く行いたい」現場にとっては、非常に相性の良い手法といえます。
生成AIがローコード/ノーコードをどう進化させるか

近年注目されているのが、生成AIとの連携による開発体験の変化です。AIの力で、開発の補助や運用の最適化まで自動化されつつあります。
自然言語でアプリを開発できる仕組み
たとえば、ChatGPTのような生成AIに
「見積作成アプリを作りたい。顧客名・商品名・単価・数量を入力できるように」
と入力すれば、その内容に基づいたフォーム設計やワークフロー構築を自動生成してくれる段階に入っています。
自動テスト・改善提案で品質向上
生成AIはアプリのテストやUI改善にも活用できます。
「保存ボタンの位置を右下にした方が良い」「必須項目に未入力が多い」
といったフィードバックを自動で返してくれるため、継続的な改善にもつながります。
DXを加速させる生成AIの役割
・データから業務のボトルネックをAIが分析
・より改善インパクトの大きい部分をレコメンド
・日々の業務記録から業務フロー全体の最適化を提案
こうした活用によって、「気づけなかった改善機会」をAIが補完し、少人数でも持続的にDXを進められる組織体制が実現可能です。
自治体の成功事例|墨田区の学童クラブ申請オンライン化
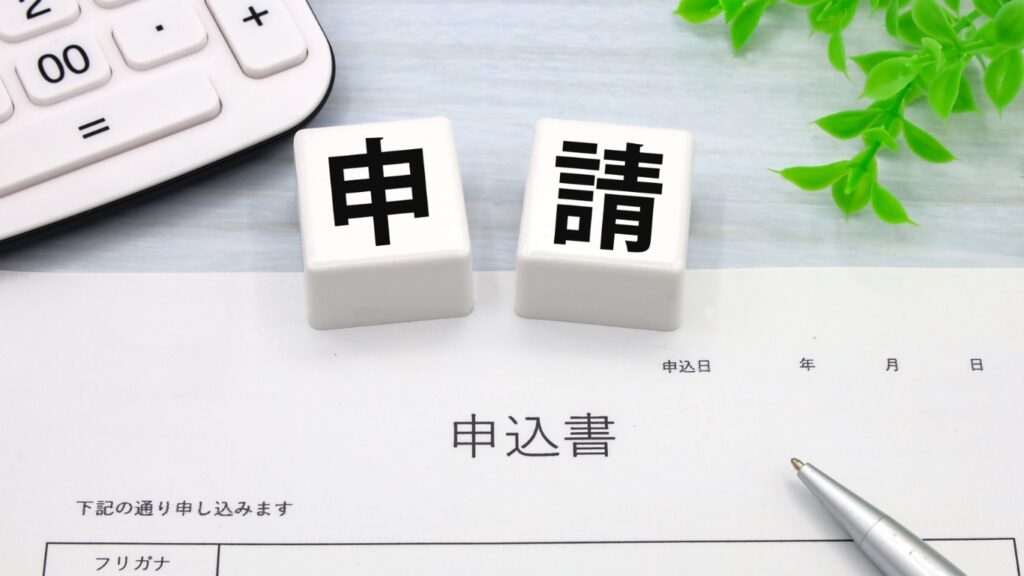
導入組織:東京都墨田区
使用ツール:LoGoフォーム、Kintone(検討中)など
紙ベース運用の課題
これまで、学童クラブ利用申請は紙で行われ、住民は区役所に出向き、職員は内容を一件ずつ入力・確認していました。
・手間・人件費・問い合わせ対応の負荷が非常に大きく
・「スマホで申請できないのか?」という声も多数寄せられていたといいます。
導入のステップ
1.紙運用の課題を整理・ヒアリング
2.LoGoフォームを使ってオンライン申請を構築
3.庁内システムと連携し、スマホからの申請にも対応
4.実運用後に効果測定と業務改善を実施
成果
・年間約3,000件の申請をオンライン化
・問い合わせ件数ゼロ
・利便性向上と職員の業務削減を両立
庁内の限られた人材でも、ノーコードを活用することで、行政サービスを現代化できた成功例です。
中小企業の活用例|生成AIとローコード/ノーコードで業務効率化

なぜ中小企業に向いているのか
・属人化していたExcel業務を置き換えられる
・ベンダー依存からの脱却
・日常業務の「ちょっと不便」を社員が自ら解決できるようになる
よく使われるツール(Power Apps、Zoho Creatorなど)
・Microsoft Power Apps:ExcelやSharePointとの統合が強み
・Zoho Creator:安価で始めやすく、画面も日本語化済み
・Bubble:スタートアップにも人気の自由度の高いプラットフォーム
・OutSystems:本格的な業務アプリ向け
活用例
・見積・請求書の自動作成
・日報・勤怠入力の簡素化
・商品データの一元管理
・受注〜出荷までのワークフロー自動化
効果測定のポイント
・手作業時間の削減
・入力ミスの件数
・社内満足度アンケートによる定性的評価
FileMaker活用事例|中堅企業の業務改善に学ぶ
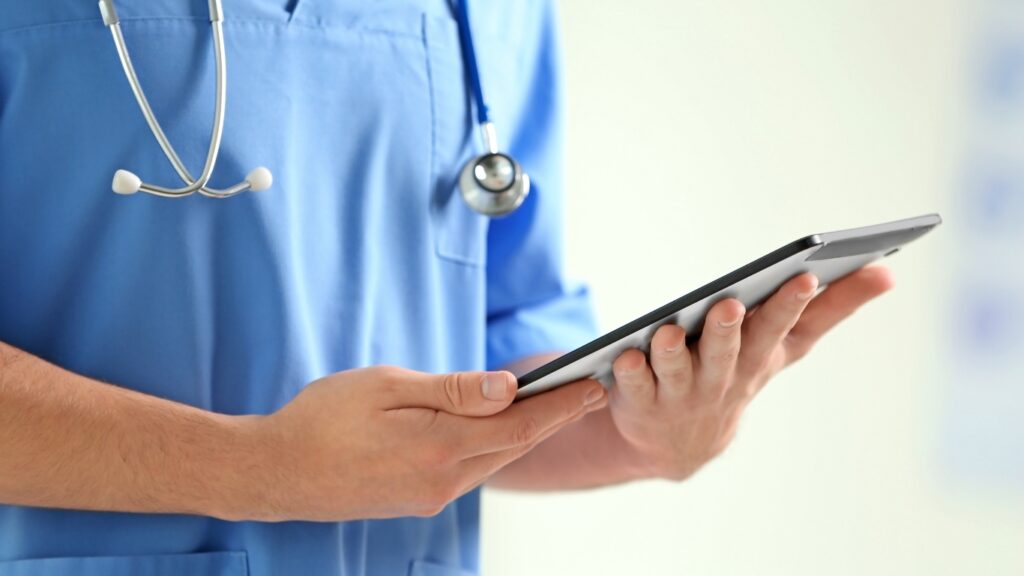
中堅規模以上では、Claris FileMakerによる内製事例が報告されています。
導入事例
・松波総合病院:iPhone連携で画像付き患者情報を即時共有
・信州ハム株式会社:旧式の生産管理をFileMakerで刷新。社員の現場改善意識が向上
・Osaka Metro:iPadで使える社内業務アプリをFileMakerで多数内製
・神戸製鋼グループ(コベルコ科研):AI画像解析と連携し、コストを1/10以下に削減
これらの事例は、FileMakerの柔軟性と拡張性を活かし、「既存業務に寄り添ったデジタル化」を実現した点で注目されています。
導入時の注意点|失敗しないために押さえるべきこと

ローコード/ノーコード導入は魅力的ですが、以下のような失敗例もあります。
よくある失敗
・目的が曖昧なままツールを選定してしまう
→ 実際の業務にフィットせず、形だけのツールが乱立
・教育不足で定着しない
→ 作ったアプリを誰も使わない状態に
・セキュリティや運用ルールを軽視
→ 社内データの取り扱いがバラバラに
解決のポイント
1.最初に「何を解決したいのか」を明確にする
2.小さな業務から始めて、社内の信頼と運用習慣をつくる
3.情報システム部門との連携・ガイドライン策定を忘れずに
まとめ|中小企業・自治体が生成AI×ローコード/ノーコード導入で成果を出すポイント
| 項目 | 内容 |
| ツール選定 | 現場のITスキル・予算・用途に応じて選ぶ |
| 導入ステップ | 課題定義 → ツール選定 → テスト導入 → 社内展開 |
| 成果測定 | 工数削減、エラー減少、満足度など定量・定性で評価 |
| 成功の鍵 | 小さく始めて、効果を見える化し、社内文化に浸透させること |
生成AIの進化とともに、ローコード/ノーコードは単なる「便利なツール」から、誰もが業務改善に参加できる仕組みへと進化しています。
中小企業や自治体にとって、今こそ「できるところから始める」ことが、継続的なDXへの第一歩になるはずです。