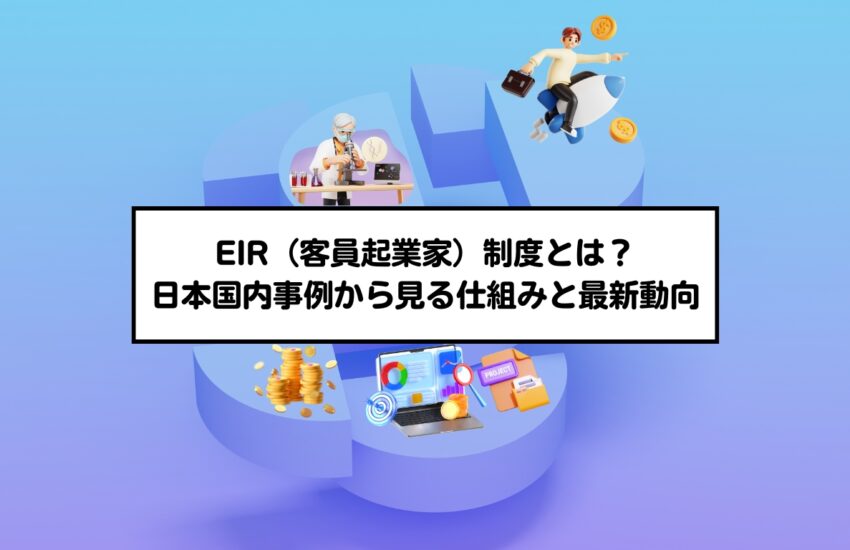イノベーション創出やスタートアップ支援の新たな手法として注目を集めるEIR(Entrepreneur in Residence、客員起業家)制度。アメリカ発のこの制度が日本でも広がり始め、スタートアップ創業者から大学・研究機関、事業会社、ベンチャーキャピタル(VC)まで幅広い関係者が関心を寄せています。この記事では、EIR制度の基本から日本における導入背景と発展経緯、大学・VC・企業での事例、成功例、そして制度導入のメリット・課題、今後の展望や支援策、活用促進のポイントまでを総合的に解説します。最新動向を踏まえつつ、読みやすい構成でEIR制度の全体像をお届けします。
EIR(客員起業家)制度とは?その仕組みと目的

EIR(Entrepreneur in Residence)とは、「住み込みの起業家」という名の通り、起業を志す人材がVCや企業、大学などの組織に一定期間所属し、その組織のリソースやネットワークを活用しながら新規事業の立ち上げを目指す制度です。日本語では「客員起業家」と訳され、企業が社内にない経験や知見を持つ人材を外部から招き入れることでイノベーション創出を図る取り組みを指します。通常、EIRとして招かれる人材は起業経験者や起業を目指す意欲ある人で、期間は半年~2年程度と限定される場合が多く、その間にビジネスアイデアの探索や事業化の検証を行います。受け入れ側の組織とは有期の雇用契約や業務委託契約を結び、一定の報酬や活動資金が提供されるため、起業家にとっては起業準備期間のセーフティネットになる点が特徴です。
EIR制度の目的は、起業家側と受け入れ組織側の双方にメリットがある形で新規事業やスタートアップ創出を加速することにあります。起業家にとっては給与を得ながら起業準備に専念できる安全な環境を得られ、メンターやネットワークの支援を受けられるため事業成功の確度を高められます。一方、受け入れる企業やVC側にとっては、社内にない外部の知見や人脈を取り込み、新規事業開発や投資機会の創出に繋げる狙いがあります。要するに、「起業家」と「社内起業家(イントレプレナー)」の良いとこ取りをする仕組みであり、起業家側はリスクを抑えつつ自由度を得て、企業側は外部人材の力でイノベーションを起こせるウィンウィンの関係を目指しています。
なお、EIRは海外では主にVC業界で一般化しており、有名スタートアップの創業にも関与しています。例えば、米国のモデルナ(Moderna)やSnowflake、Dollar Shave Clubといった企業はEIR制度を活用して設立された例として知られています。日本ではまだ馴染みが浅い制度でしたが、近年になって「第二の創業ブーム」を目指す国の方針もあり、その重要性が増しています。
日本におけるEIR制度の導入背景と発展経緯

開業率の低迷と起業人材不足の課題
日本でEIR制度に注目が集まる背景には、国内の起業率の低さや起業を支える人材の不足という課題があります。経済産業省の資料によれば、日本の開業率(新規企業の設立率)は欧米に比べ低水準で、2016年以降は4〜5%前後に留まっています。起業に対する意識面でも、自分に起業に必要な知識・スキルがあると答える人の割合が日本は他国より低いという調査もあり、こうした要因がイノベーション創出のボトルネックとなってきました。
特に大学や研究機関に目を向けると、近年ようやく大学発スタートアップが増えてはいるものの、研究者がビジネス面の経験不足から事業化に苦労するケースが少なくありません。せっかく世界に通用する技術シーズがあっても、それを事業に育てる経営人材の不足が各所で指摘されています。例えば京都大学や地方の大学では、有望な技術があってもそれを事業化できる起業家(CEO)候補が足りないことが長年の課題でした。
こうした中で、一般的な起業家と社内起業家の“いいとこ取り”をしたEIR制度は、日本の起業エコシステムの弱点を補う有力な手段と期待されています。外部の起業経験者を一定期間迎え入れて技術シーズの事業化を託すEIRの仕組みなら、起業家側はリスクと不安定さを軽減でき(※少なくとも期間中の収入と支援を得られる)、企業側は不足するノウハウを補完できます。この双方に利点があるモデルで、日本でも起業準備者の新たなキャリアパスとして注目度が高まっているのです。
政府によるスタートアップ支援策とEIR制度の推進
日本国内でEIR制度が発展し始めた背景には、政府の強力なスタートアップ支援策も大きく関与しています。2022年11月に策定された「スタートアップ育成5か年計画」では、戦後の創業ブームに次ぐ第二創業ブームの実現を掲げ、人材・ネットワークの構築を柱の一つに据えました。その一環として、起業人材の育成や支援組織の整備が推進されており、EIR制度も「スタートアップ創出に向けた人材・ネットワーク構築」の具体策の一つとして位置づけられています。
経済産業省は2022年からEIRの活用に関する実証事業をスタートし、一般社団法人JISSUI(社会実装推進センター)に委託してモデルケースづくりを進めました。2022年度には9社の企業・VCが採択され、各社でEIR制度の試行を支援する取組みが行われています。これらの成果はナレッジとして蓄積され、2023年6月には経産省より「EIR制度活用ガイダンス」が公開されました。ガイダンスではEIR制度の定義や運用ポイント、契約形態の工夫、そして国内先行事例がまとめられ、今後EIR導入を検討する組織向けの指針となっています。
政府の後押しは他にもあります。例えば内閣府や文部科学省も大学発ベンチャー支援のプログラムを拡充しており、その文脈で「研究開発型スタートアップに経験豊富な事業人材をマッチングさせる」動きが出ています。実際、HRサービス大手のビズリーチ社は慶應義塾大学、東京工業大学、東京理科大学などと連携し、同社の人材ネットワークを活かして大学内にEIR制度を構築する取り組みを始めています。これは、大学の眠れる技術シーズと外部の経営人材を結びつける産学連携の新しい形であり、国の支援策とも呼応した民間発の動きと言えるでしょう。
このように、国を挙げたスタートアップ支援の追い風の中でEIR制度は徐々に日本に定着しつつあります。2020年代前半から複数の先行事例が積み重なり、2024年〜2025年にかけては大学・VC・事業会社など様々な組織がEIR導入に乗り出している段階です。次章以降では、それぞれの現場での具体的な導入事例と成功例を見ていきましょう。
大学・研究機関におけるEIR制度の導入事例

大学や公的研究機関では、研究成果の事業化(社会実装)を加速する人材としてEIR制度を導入するケースが増えています。大学発スタートアップの創出には技術系研究者とビジネス系人材のタッグが不可欠ですが、日本ではその「ビジネスリーダー」人材が不足しがちなため、外部から客員の起業家を招く仕組みが求められているからです。
京都大学や東京大学の先行モデル
先駆的な例として京都大学があります。京大の100%子会社VCである京都大学イノベーションキャピタル(京都iCAP)は、2017年に自社で起業家候補のプール組織を立ち上げ、その中から選抜した人材をEIR(雇用契約 or 業務委託)として受け入れる制度を構築しました。EIRとなった人材は最初の半年間で大学内の技術シーズ探索や事業計画策定などを行い、その後も投資業務を経験しながら起業準備を進めます。京都iCAP側はEIRに対し特定の起業テーマや株式持分の事前指定はせず、自由度の高い環境で起業家の成長を促しました。この結果、京都発のディープテック起業がいくつか生まれており、例えば同VCのEIR出身者がライノフラックス株式会社(量子技術系スタートアップ)を創業したケースなどが報告されています。京都iCAPにとっても、自前で不足していた経営者人材を発掘・育成できるモデルとして手応えを感じているようです。
東京大学でも、大学発ベンチャー育成の文脈でEIR制度が導入されています。東京大学のVC機能を担うUTokyo IPC(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社)は、「Deep Tech Founders」というプログラム名でEIR候補者を公募し、有望な研究シーズと起業家人材をマッチングさせる取り組みを行っています。東大IPCのEIRは一定期間、東京大学や関連機関に籍を置きながら、世界市場を視野に入れたディープテック事業の立ち上げ準備を進める仕組みです。こうしたプログラムからは、東京大学発のスタートアップ創出に繋がる案件も徐々に増えてきており、大学側も新たな起業家輩出のエコシステムとして力を入れています。
地方・その他大学での広がり
EIR制度は地方大学や他の国立大学にも広がりを見せています。例えば東北大学では、大学のVCである東北大学ベンチャーパートナーズ(THVP)が2024年に初の客員起業家(EIR)を受け入れました。THVP第1号EIRとなった妹尾浩充氏は異業種からの挑戦者ですが、東北大学の技術シーズ事業化に取り組み、東北発ディープテック創業にチャレンジしています。東北地方では行政(仙台市など)のスタートアップ支援も活発化しており、それに呼応する形で地域からグローバルに飛躍する起業家を育成する一策としてEIRが注目されている状況です。
また、筑波大学は2025年7月に公式に客員起業家(EIR)の募集を開始しました。筑波大学ではこれまで起業チームの経営人材不足が課題となっており、将来のスタートアップCEO候補となりうる人材(EIR)を学外から招いて研究シーズの事業化を推進する方針を打ち出しています。実際に公募では、ウェアラブルバイオセンサーや新規抗菌ペプチド応用開発など5件の具体的研究プロジェクトごとにEIRを募る形を取っており、該当プロジェクトの社会実装リーダーになってくれる起業家人材を探しています。このように、筑波大学は大学発ベンチャーの継続創出を支えるエコシステム構築の一環としてEIR受け入れに踏み切った形です。
さらに千葉大学でも、2022年に「IMOスタートアップ・ラボ」という組織を立ち上げ、客員起業家(EIR)とURA(大学の事業化支援人材)を外部から招聘して大学発スタートアップ支援体制を強化しています。千葉大学は学生・教員数の規模の割に年間の起業社数が0~2件と少なく、起業機運の醸成が課題でした。そこで2024年よりメーカー出身の加藤優一氏をEIRに迎え、コンサル出身者をイノベーション・マネジメント研究員(URA)として加え、副業形式で大学の起業支援に参画してもらっています。このように兼業・副業型でEIR人材を受け入れる柔軟な形も出てきており、大学内に徐々に「起業してみよう」という空気を醸成する効果が期待されています。
以上のように、日本の大学や研究機関では東京・京都などの主要大学から地方の国立大学まで、EIR制度の導入が広がりつつあります。「研究シーズ×ビジネス人材」のマッチングによって大学発イノベーションを加速させるこの試みは、国の後押しも受けながら今後さらに定着していくでしょう。
インキュベーター・ベンチャーキャピタルにおけるEIR活用事例

インキュベーター(事業創出支援組織)やベンチャーキャピタル(VC)の分野でも、EIR制度の活用が進んでいます。VCや事業会社主導のインキュベーションでは、有望なスタートアップ案件を生み出すことや新規事業の種を育てることがミッションですが、そこに外部起業家を巻き込むことで成果を上げようという動きです。
ベンチャーキャピタルでの導入例
日本を代表するVCの一つジャフコグループは、国内スタートアップエコシステムの成長を目的にEIR制度を導入しています。ジャフコでは「First Leap」というEIRプログラムを運用し、起業前段階の優秀な人材を一定期間受け入れて事業構想を練らせています。VCにとってEIRを採用する直接のメリットは新たな投資案件の創出ですが、ジャフコは起業前の成功確度を測るのは難しいという課題に直面し、EIR制度の短期KPIを“起業家との新規接点数”など副次的効果に置きました。結果として、幅広い業界リサーチやイベント開催を通じ約400名の起業志望者との接点を獲得するなど、起業家コミュニティの拡大につながっています。このようにVCにとってEIRは、将来の投資候補とのネットワーク構築という側面でも効果を上げています。
独立系VCでは他にも、ANRIやBeyond Next Ventures(BNV)が積極的です。ANRIは2024年に客員起業家プログラム「Aurora」を開始し、ディープテック領域で起業したい人材を広く募集しています。BNVも「Peak Trial」という名称でEIRプログラムを展開し、自社リソースと大学の研究成果を掛け合わせて世界を変えるスタートアップ創出を狙っています。これらVCでは、自社のキャピタリストがEIRにメンタリングしたり、資金提供や研究者とのマッチングまで包括的に伴走する体制を敷いており、12か月程度での起業を目指す集中プログラムとして位置づけられています。
また、未来創造インベストメンツ(旧・みらい創造機構)は東京工業大学関連のVCで、技術シーズ活用型のEIR制度を導入しました。ここではEIR候補者とまず1年間の雇用契約を結び、投資業務に従事させながら経営者適性を見極めるというアプローチを取っています。契約形態も4種類の雛形を用意し、多様な人材を受け入れられるよう工夫するなど、柔軟な制度設計が特徴です。この結果、新たな起業人材への接触機会が増え、有望なキャピタリスト候補の発掘・育成にも手応えを感じているとのこと。
インキュベーター・事業会社での導入例
スタートアップスタジオ型のインキュベーターでもEIR制度が活用されています。たとえばデライト・ベンチャーズ(DeLight Ventures)は、起業家育成プログラムの一環としてEIRを導入し、連続的にスタートアップを創出する取り組みを行っています。スタートアップスタジオでは、スタジオ運営会社がアイデアや資金を提供し、客員起業家が具体的な事業立ち上げを担うケースが多く、EIRがスタジオ内のアイデアを形にしていく役割を果たします。海外ではこのモデルから数多くの企業が生まれており、日本でもDeLight社のようなプレイヤーが台頭し始めています。
事業会社によるコーポレート・イノベーションの文脈でもEIR導入例があります。三菱地所は不動産業の大手ですが、新規事業開発で地方展開を検討する中で九州に縁のある客員起業家2名を採用しました。5か月半の業務委託契約で協業パートナー関係を結び、具体的な指示に縛らない自由な活動環境を整えたところ、地方の新規プレーヤーとの関係構築や地域エコシステムの課題抽出に成功したといいます。これは事業会社が社内にない土地勘やネットワークをEIRで補完した好例と言えるでしょう。その他、南海電鉄でも新規事業創出を目的にEIR的な取り組みを行い、約1年間の事業検証を経て最終審査を通過した案件は子会社設立や社内事業化につなげるといった制度設計をしています。
これらの事例から分かるように、VCから大企業まで組織のタイプに応じた多様なEIR活用モデルが存在します。【投資案件組成型】【スタートアップスタジオ型】【技術シーズ活用型】【社内変革型】等、経産省ガイダンスでも類型化されている通り、自社の狙いに合った形でEIR制度を設計・運用することが肝要です。重要なのは、EIRとして迎える人材にどんな役割を期待するかを明確にし、適切な人選と契約・支援体制を整えることでしょう。次の章では、こうしたEIR制度導入によって得られるメリットと、運用上の課題について、企業側・EIR側双方の視点から整理します。
EIR制度導入によるメリットと課題

EIR制度は関わる双方(受け入れ組織とEIR本人)に利点をもたらしますが、同時に留意すべき課題もあります。ここでは企業側(受け入れ側)とEIR側(起業家側)に分けて、主なメリットと課題を見ていきます。
受け入れ企業・組織側のメリット
🟣外部の知見による新事業創出
社内にはない新たな視点や経験を取り入れることで、既存ビジネスにとらわれない発想が生まれやすくなります。停滞しがちな組織にイノベーションの刺激を与え、新規事業の種を発見・育成できる可能性が高まります。実際、EIRが入ったことで眠っていた技術シーズが事業化に繋がった大学事例も増えています。
🟣ネットワーク拡大と投資機会
EIRが持つ人的ネットワークや業界知識を活用できるため、新たな協業先や顧客、投資先との接点が生まれます。VCにとっては、EIRを通じて優秀な起業家候補と出会い将来的な投資案件を創出する効果が期待できます。ジャフコの例ではEIR経由で400名近い起業志望者と接触できたように、社外ネットワークの拡大は大きなメリットです。
🟣組織への良い刺激・変革
客員起業家のマインドやノウハウが社内に浸透し、社内の新規事業担当者や研究者にとって刺激となります。EIR制度を通じてイノベーション文化が醸成され、社員の起業マインドやオープンイノベーション志向が高まる効果も報告されています。外部人材と一緒にプロジェクトを進めることで、組織全体の活性化に繋がったという声もあります。
🟣新規事業の成功率向上
起業経験者や専門性の高い人材を迎えることで、事業検証や市場調査が専門的に行われ、失敗リスクを低減できます。例えば技術シーズ事業化の場合、EIRがビジネスモデル構築や資金調達支援まで担えば、プロジェクトの推進力が増し成功率が上がります。社内リソースを有効活用しながら外部の力を借りるため、スピーディーに事業立ち上げを進められるのも利点です。
受け入れ企業・組織側の課題
🟣成果の不確実性と評価
EIR制度は中長期的な投資でもあり、短期では成果が見えにくい場合があります。起業準備の支援がそのまま事業成功に結びつくとは限らず、ROI(投資対効果)の判断が難しい点は課題です。ジャフコのようにKPI設定を工夫する例もありますが、経営陣の理解と腰を据えた支援がないと途中で期待外れと判断されかねません。
🟣制度運用のノウハウ不足
日本ではまだEIR導入経験が浅い組織も多く、社内でのEIRの立ち位置や役割が不明確になりがちです。受け入れ部署がEIRをどう扱うか決めきれていないと、意思決定プロセスで混乱が生じたり、EIRが実力を発揮できない恐れがあります。このため、事前に役割・期待値を明確化し、受け入れ体制を整えることが重要です。
🟣契約・知財の取り扱い
EIR期間中に生まれたアイデアや技術の知的財産の扱い、EIR離任後の関係性など検討事項も多岐にわたります。契約ひな形の整備や合意事項の明確化が必要ですが、ひとつ間違えば起業家のモチベーションを下げる契約になりかねません。企業側は過去の副業制度等のノウハウも活かしつつ、公平で納得感のある条件設定を行う必要があります。
🟣コスト負担と継続性
優秀なEIR人材を招くには相応のコスト(給与・活動資金)がかかります。また、EIRが起業して独立した後に、その成果(例えば新会社への出資など)を企業側がどう位置づけるかも検討事項です。EIRを送り出した後も協業関係を維持できるのが理想ですが、場合によっては人材が流出するだけと捉える向きもあるでしょう。こうした懸念に対しては、経営陣がEIR制度の戦略的意義を共有し、長期視点で投資と捉えることが求められます。
EIR本人(起業家側)のメリット
🟣収入の安定とリスク軽減
通常の起業家と異なり、一定の給与や資金サポートを受けながら準備に専念できるため、生活面の不安を軽減できます。「全くのゼロからの起業」に比べて経済的リスクを抑えられる点は、特に家計を抱える社会人起業志望者にとって大きな魅力です。また、組織に属していることで各種バックオフィス支援も受けられる場合があり、本業(事業構想)に集中しやすくなります。
🟣リソースや設備の活用
受け入れ先組織のオフィス設備や研究施設、データベースなど、豊富なリソースを自由に使える環境が得られます。例えば大学や企業の研究機関に所属するEIRであれば、最先端の技術やアイデアに常に触れられる恵まれた環境で事業検討ができます。VCのEIRであれば、VCが持つ業界知見や専門スタッフのサポートを受けつつ、オフィススペースやツールを使える利点もあります。
🟣ハンズオンのメンタリング
EIR期間中、受け入れ組織のプロ人材から密なメンタリングを受けられるのも大きなメリットです。VCの客員起業家であればキャピタリストに事業設計の相談が気軽にできたり、デモデイ等で投資家との接点が提供されることもあります。事業会社の場合も、社内の専門家から市場や技術のアドバイスが得られるでしょう。一人で起業準備しては得られない知見が集まることで、事業計画のブラッシュアップが飛躍的に進む可能性があります。
🟣人的ネットワークの獲得
EIRとして活動する中で、起業家コミュニティや投資家ネットワークにアクセスできます。VC主催プログラムなら同期のEIR仲間ができ切磋琢磨できるほか、紹介を通じて将来のチームメンバーや協業パートナーと出会えるかもしれません。受け入れ企業内で実績を積めば信頼性や評判が高まり、その後の資金調達や事業提携を進めやすくなるという指摘もあります。
🟣最新トレンドへのアクセス
EIR活動では最先端の技術・市場トレンドに先んじて触れられるため、個人としての視座も上がります。普段なら出会えないような研究テーマや技術情報にアクセスできるのはEIRならではの経験であり、将来どんな事業領域に進むにせよ大きな学びと実績になるでしょう。
EIR本人(起業家側)の課題・注意点
🟣ポジションの期限と不安定さ
EIRの身分は基本的に一時的・有期であり、期間終了後にそのまま職が保証されるわけではありません。あくまで起業に向けた助走期間という位置づけのため、起業に至らなかった場合は次のキャリアを自分で切り拓く必要があります。つまり、雇用されつつも将来の不確実性は残る点に留意が必要です。「安定した会社員」と「独立起業家」の中間ではありますが、理想的な安定とは言えない面もあります。
🟣自由に選べる領域の制約
本来起業家は自由に事業領域を選べますが、EIRでは受け入れ先の方針やテーマに影響される場合があります。組織によっては「この技術分野での起業を検討してほしい」といった限定があるケースもあり、自分の興味と合致しないとミスマッチが起こりえます。経験としてプラスになる可能性もありますが、キャリアの選択肢が狭まるリスクは認識しておくべきでしょう。
🟣組織内での立場の難しさ
日本ではEIR制度がまだ浸透していないため、受け入れ組織内での扱いが曖昧になりがちです。肩書きは客員ですが社員ではない微妙な立場ゆえに、意思決定権限や責任範囲が不明確なケースもあります。その結果、動きづらさを感じたり、社内調整に時間を取られてしまうリスクも否めません。受け入れ先の文化や規模に適応できるかも重要で、スタートアップ経験者が急に大企業文化に飛び込むと戸惑う、といった指摘もあります。EIRを目指す側は事前に組織風土やサポート体制を確認し、自分に合った環境か見極めることが大切です。
🟣コントロール不能な要素
EIR期間中、自身の努力だけではどうにもならない組織側の制約もあります。例えば組織の戦略変更や予算都合でプロジェクトが中止になったり、社内合意形成に時間がかかって自分のペースで進められないこともありえます。完全に自分の裁量で進められるわけではない点は、独立起業との大きな違いです。柔軟性がある反面、組織に依存するリスクも覚悟しておく必要があります。
以上のように、EIR制度には多くの利点がある一方で、現実的な課題も存在します。ただ、適切なマッチングと運用によって課題は十分克服可能です。受け入れ側は制度設計やサポート体制の整備に努め、EIR側も自身の目的に合った受け入れ先選びを行うことで、双方にとって有意義な制度となるでしょう。
今後の展望と政府・自治体の支援動向

今後の展望:さらなる普及とエコシステム形成
2025年現在、EIR制度は日本においてまだ始まったばかりですが、スタートアップ支援策の強化や先行事例の成功を受けて今後さらに普及が加速する見通しです。政府がスタートアップ育成を国家戦略として掲げている今、EIRのような起業促進策は国としても後押しすると見られます。経産省の実証事業はガイダンス策定という形でひとまず成果を上げましたが、引き続き先端事例の横展開や未導入企業への啓蒙が図られるでしょう。また、官民ファンドや大学ファンドによる資金面での後押しもEIRプログラム拡充には欠かせません。
考えられる展開の一つは、大企業や地方企業へのEIR導入拡大です。現在はVCや大学発の事例が目立ちますが、オープンイノベーションを模索する事業会社が新規事業創出型EIRを採用するケースが増える可能性があります。実際、三菱地所や南海電鉄のような先例がありますし、他の業種でも「社内に眠る技術シーズ × 外部起業家」の組み合わせで事業開発を試みる動きが出てくるでしょう。地方企業にとっても、首都圏の起業家人材を招いて新事業を起こすEIRモデルは、地方創生やDX推進の観点から有効かもしれません。
また、大学間・VC間の連携によるEIR活用のネットワーク化も期待されます。ANRIが他VCや大学と合同でEIRイベントを開催したり、ビズリーチが複数大学と協働する例に見られるように、一つの組織内に留まらずクロスオーバーした人材交流が進む可能性があります。将来的には、起業家人材データベースを活用して全国の技術シーズにマッチングできるような、オープンプラットフォーム型EIRの仕組みが生まれるかもしれません。
政府・自治体の支援動向
政府レベルでは既述のように経産省が中心となりEIR普及を促していますが、他省庁や自治体でも関連する施策が見られます。例えば、内閣府は地方の社会課題解決型スタートアップを支援する文脈で「転職なき移住」など地方と都市部人材を繋ぐ政策を打ち出しており、これは都市部の起業家が地方企業や自治体プロジェクトに関与する道を開くものです(EIRと直接銘打ってはいませんが、類似の考え方)。自治体によっては、地域の中核企業や大学と連携してEIR的な制度を設ける動きも出てきています。東北の例では仙台市がスタートアップ支援を公約に掲げ、結果的に東北大VCでEIR採用が実現するなど、行政支援が間接的にEIR創出を後押ししたケースもあります。
今後は、地方自治体が公募するスタートアップ支援事業にEIRの活用が組み込まれる可能性もあります。たとえば「地域の技術課題を解決する起業家誘致プログラム」といった名目で、自治体が外部起業家を一定期間受け入れて事業化を図るような施策も考えられるでしょう。国の交付金事業などでモデルケースが生まれれば、各地に広がるかもしれません。
一方で、法制度や規制面の整備も今後の課題です。EIRそのものは契約次第で柔軟に運用できますが、例えば大学に外部人材を受け入れる際の規程づくりや、公的資金の取扱いルールなど細部の調整は必要でしょう。政府は現状ガイドライン提供に留めていますが、場合によっては税制上の優遇(EIRに支払う報酬の一部補助など)や認定制度を検討することも考えられます。いずれにせよ、国・自治体がEIRをイノベーション政策のメニューに明確に位置付けることで、企業側も安心して取り組める環境が整っていくと考えられます。
日本でのEIR活用を促進するためのポイントと提言

最後に、EIR制度を日本でさらに活用・定着させるための重要ポイントや提言をまとめます。これから導入を検討する企業・大学関係者、あるいはEIRに挑戦したい個人は、以下の点に留意すると良いでしょう。
🔵組織側:明確な目的設定と人選
なぜEIRを導入するのか(新規事業創出、人材育成、投資案件発掘など)、その目的を明確化した上で適切な人材を選ぶことが第一歩です。期待する役割や成果を事前に言語化し、募集・選考プロセスで共有しましょう。例えば「〇〇分野の事業アイデア創出がミッション」等と伝えることで、EIR候補もミスマッチを避けやすくなります。
🔵組織側:環境整備とサポート体制
EIRが活動しやすい環境を用意することも成功の鍵です。具体的には、受け入れ部署内のメンターや協力メンバーの選定、必要な情報・設備へのアクセス権付与、定期的な進捗フォローアップなどを計画しましょう。組織トップがEIRを特命プロジェクトのリーダーとして位置付け、社内各所に協力を促すような体制づくりも有効です。
🔵組織側:成果の共有とフィードバック
EIRの活動が組織全体に与える影響を定期的に評価・共有し、得られた知見を組織学習につなげましょう。EIRが提案した新規事業の種がうまくいかなかった場合も、なぜ駄目だったのかを分析し次に活かすことが大切です。成功事例が出た際には社内外に広報し、EIR制度の価値を社内に浸透させるとともに、自社ブランド向上や今後の人材募集にも役立てましょう。
🟢個人側:自分に合った受け入れ先選び
これからEIRに挑戦したい方は、自身の経験やスキルが活きる領域を持つ組織を選ぶことが重要です。受け入れ先の規模(スタートアップか大企業か)、文化(スピード感や意思決定スタイル)、提供リソース(資金・設備・ネットワーク)などを事前によく調べ、自分の起業プランにマッチする環境か見極めましょう。募集説明会やOBの話を聞く場があれば積極的に参加し、疑問点はクリアにすることをお勧めします。
🟢個人側:契約条件と将来プランの確認
EIR期間中の支援内容や報酬体系、知財や成果の取り扱い、期間終了後の選択肢(起業した場合の出資有無など)については事前に確認しましょう。不明点は遠慮なく質問し、将来のキャリアパスも視野に入れて計画を立てることが大切です。EIR終了後に自分が独立起業するのか、受け入れ元と新会社を共同で作るのかなど、いくつかシナリオを想定しておくと不安が和らぎます。
🟣エコシステム全体での協力
EIR制度は一社・一校だけで完結するものではなく、エコシステム全体で成功事例を増やすことが大事です。情報発信やイベントを通じて横のつながりを強め、EIR経験者同士のコミュニティを育てることも有益でしょう。ANRIや京都iCAP、みらい創造インベストメンツが合同でEIRパネルディスカッションを開催したように、互いに知見を共有し合う場が増えれば、日本全体でEIRの質が上がり認知度も高まります。
日本におけるEIR制度は、まだ発展途上とはいえ確実に芽吹き始めた新潮流です。スタートアップ創出の新たな選択肢として、企業・大学等の受け入れ側と起業家予備軍の個人側の双方が理解を深め、協力して磨き上げていくことで、より多くの成功ストーリーが生まれるでしょう。本記事で紹介したポイントが、皆様の参考になれば幸いです。ぜひ客員起業家(EIR)制度を上手に活用し、日本発イノベーションのさらなる飛躍につなげていきましょう。