企業のグローバル競争が激化する一方、教育機関における競争力強化に向けた取り組みも、優秀な人材を確保する上では見逃せません。特に近年、大学ファンドの形成により、研究力の強化に取り組む大学が次々と登場し、従来の「東大一強」の壁を破るかもしれないと注目されています。
この記事では、そんな大学における競争力の源泉として注目される大学ファンドについて紹介しつつ、大学ファンド形成を促す国際卓越研究大学制度を詳しく解説します。
大学ファンドとは

最近耳にするようになった大学ファンドとは、そもそもどういったものを指すのでしょうか。
大学ファンドの概要
大学ファンドは、日本政府が新たに創設した大学向けの巨大ファンドです。文部科学省が定める「国際卓越研究大学」に指定されれば、数十億円から数百億円にものぼる支援額を毎年受け取ることができます。大学ファンドは10兆円規模の運用額になるとされており、過去に例を見ない、研究機関向けの最大規模のファンドです。
大学ファンドは、指定された大学が生み出した運用益をもとに運営することを想定しており、運用益の目標は今のところ年間で3,000億円を想定しています。従来、大学に供与されてきた運営交付金よりもはるかに巨大な金額の支援を受けられることから、多くの大学がファンドの対象となることを望んでいます。
各大学で異なる強みを創出
大学ファンドの対象となるためには、国内はもちろん、世界でも通用するレベルの研究開発を大学が推進する必要があります。国際卓越研究大学の申請を届け出た大学は、いずれも他の学校にはない、独自の強みを武器に、巨額の支援を求めているのが現状です。
例えば東京大学は、大学ファンドの対象となるにあたって、脱炭素やバイオ分野における卓越した研究力の高さをアピールしています。2021年度、同大学の収入は国からの運営費交付金や授業料などを合わせ、2,887億円を計上していますが、認定校に指定されれば、事務スタッフの拡充やスタートアップ支援などを推進できるとして、大いに期待を寄せているとのことです。
また東北大は、次世代放射光施設「ナノテラス」を拠点としながら、半導体や量子、そして材料科学分野での活躍をアピールしています。今後成長が期待される量子技術を強みとしている同大学は、認定校の有力候補と言えるでしょう。
※以下のように日本の大学は2005年度と比べて伸びが少ない。一方で欧米の大学は伸びている。そのため日本の大学は競争劣位にある。

国際卓越研究大学制度とは

大学ファンドを成立させる上で重要な役割を果たすのが、文部科学省の制定した国際卓越研究大学制度です。
国際卓越研究大学制度の目的や役割
国際卓越研究大学制度は、2022年12月より募集を開始し、2023年3月末まで公募していた、大学ファンドの認定を教育機関が受けるための制度です。審査を経て正式に「国際卓越研究大学」と指定されることで、日本政府から通常の運営費交付金とは別に、数十億から数百億円にものぼる運用資金を受け取ることができます。
端的に言えば、大学ファンドは国際卓越研究大学に指定された大学にのみ有効な制度です。認定を受けることができた大学は、教育機関としての資金力を増強し、磐石な大学運営や先進的な研究への投資を進めることができます。
認定を受けることができなかった大学と比べ、突如として単純計算で数十億から数百億の経済的ギャップが生まれることは、認定校にとって大きなアドバンテージとなるでしょう。
このような巨額の大学ファンド運用を推進する背景にあるのが、日本の研究力の相対的な低下です。世界各国のトップレベルの研究大学が、豊富な資金を背景に高い研究力を獲得している一方、国内の大学では人材不足や予算不足を背景に、質・量ともに世界に通用する成果を出すことができていません。
そんな問題に対処すべく登場したのが、国際卓越研究大学制度、ひいては大学ファンドです。公的な財政支援やスタートアップとの連携により、豊富な財源を大学が獲得することで、トップクラスの研究力を再び獲得できるようにと制度が始まりました。
早大をはじめとする国内大学が応募
大学ファンドや国際卓越研究大学制度のような仕組みの登場は、これまでに類を見ないほど巨大なプロジェクトであることから、各大学からの注目度も非常に高いと言えます。同制度への申請は、国内の大学であれば国公立、私立を問わないため、どこの大学でも応募が可能です。
2023年3月に募集を終了した今回の公募枠では、全体で10の大学が申請を届け出ており、そのうち8校は国公立大学でした。私立大学で申請したのは早稲田大学と東京理科大学で、早稲田大学についてはアジアトップクラスの教育機関となることを志した、熱意ある意気込みを語っています。
同大学が東大や京大を2050年までに追い抜き、アジアの名だたる大学を凌駕する上で力を入れているのが、文理の区別なき教育の提供です。数学やデータサイエンスの力を学生に求め、エビデンスに基づいた思考ができる人物となれるよう変えていきたいと語っています。
文系・理系が隔てられた現在の教育体制から文理融合型に移行するためには、多くの時間と予算を必要とします。大学ファンドからそのための資金を調達し、組織にかかる負担を最小限に抑え、教育をアップデートしていくというのが同大学の狙いです。
※早稲田大学、東京科学大学(東京工業大学+東京医科歯科大学)、名古屋大学、京都大学、東京大学、東京理科大学、筑波大学、九州大学、東北大学、大阪大学が申請しています。
大学ファンド形成がもたらす大学間競争
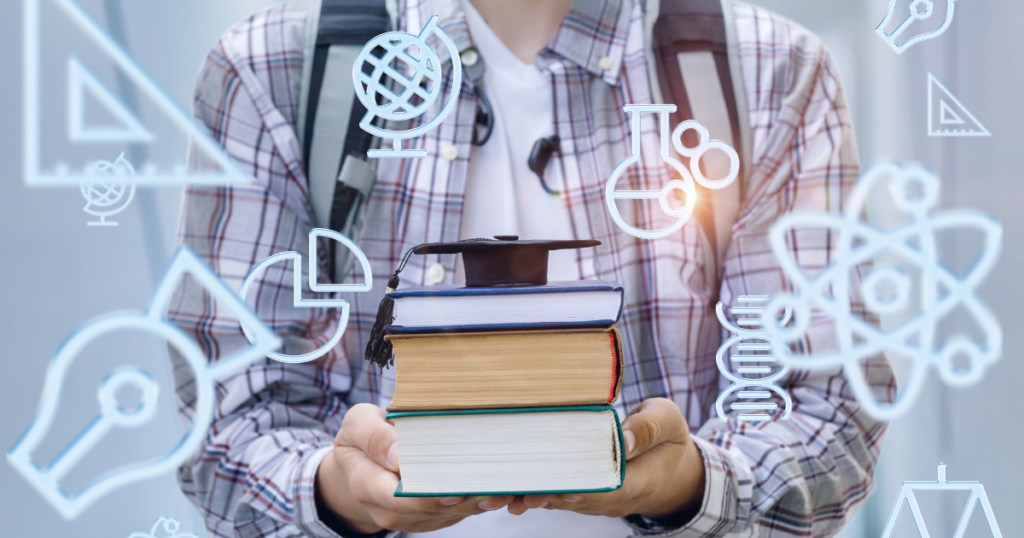
大学ファンドの登場は、これまで資金獲得力に悩んでいた日本の大学にとって、魅力的な制度であり、どんどんその規模を大きくしてもらうに越したことはありません。ただ、大学向けの研究ファンドを運用していくにあたっては、注意しておくべきポイントもあります。
大学間格差の増大がもたらすリスクとは
大学ファンドの形成に伴う最大の懸念点は、日本の大学間で大きな経済格差が生まれてしまう点です。数十億から数百億にものぼる多額の資金が、わずか数校にのみ分配されるというのは、政府主導の選択と集中であり、平等な施策であるとは言えません。
もちろん、予算の都合上、多額の資金を投入できる学校は成果を出している、あるいはこれから成果が期待できる学校に絞るべきというのはもっともですし、少額の資金を多数の大学に分配しても、多額の資金を必要としている学校にとって、雀の涙にしかなりません。
ただ、事実として大学ファンドの登場は大学やに経済的格差をもたらし、研究の多様性や研究者の獲得・育成、そして学生の多様性確保や育成に、支障をきたす可能性があることは覚えておく必要があります。
現在、日本は少子高齢化の影響もあり、大学に進学する子供や大人の数は減少傾向です。大学は学を志す全ての人に向けて開かれている教育機関であることが理想ですが、子供の数が減れば大学の数も減り、全国に大学を開校し続けることが極めて困難になります。
ましてや大学ファンドの形成により、大学間の経済格差が広がり、国民の学力維持に貢献している地方大学や中堅大学の数が減ることとなれば、大卒人口の低下や学力格差、就活格差などをもたらすことにもなるでしょう。
大学ファンドそのものが持つリスク
大学ファンドを運用する上で、もう一つ考えなければならないのが、事業の失敗や不景気の到来により、資金運用に失敗してしまう可能性があることです。大学ファンドは無償の給付金ではなく将来的にリターンが得られることを見越した政府直轄の投資プロジェクトです。せっかく多額の資金を獲得したにもかかわらず、資金の運用に苦慮してしまい、成果を出すことができなかった場合、大きな損失をその大学や、ファンドを提供した日本が被ってしまうこととなります。
間接的に税金を投下して運用しているファンドである以上、認定を受けた大学には正しい資金運用が求められます。ファンド運用になれていない大学が下手に資金を使ってしまうと、思わぬ墓穴を掘ってしまうこともあるでしょう。
こういったファンド運用のリスクを、どう乗り越えるべきかも考えながら、大学ファンドは運用される必要があります。
GAPファンドとの関係
大学ファンドに関連してGAPファンドも最近注目されています。GAPファンドとは、研究機関に属する研究成果を事業化する場合において、事業化するまでのギャップを埋めるための仮説検証やPoC、試作品製作、ビジネスモデルのブラッシュアップ等をするための資金を指します。研究成果がそのまま事業として成り立つことは少なく多くの場合は、更に事業化として成立させるためのステップが必要です。
文部科学省は、起業前段階から公的資金と民間の事業化ノウハウ等を組み合わせる新規性と社会的インパクトを有する大学等発スタートアップを創出し、世界に伍するスタートアップの創出に取り組むエコシステムを構築することを目的として、大学発新産業創出プログラム(START)を発足しています。具体的には、ギャップファンドプログラムの充実等、スタートアップ・エコシステム拠点都市におけるスタートアップ創出機能強化として、年間約100億円近くの予算をかけています。
ギャップファンドを充実させるための基盤づくりを行うことで、大学発のベンチャーの創出の質と量の増加を図っています。
まとめ

この記事では、大学ファンドや国際卓越研究大学制度について、詳しい制度の内容などを解説しました。大学ファンドは日本ではこれまでに類を見ない、大学向けの資金調達手段として注目を集め、すでに複数の大学が認定を受けるべく申請手続きを済ませています。
数十億から数百億にものぼる資金調達を受けられる魅力的な制度ですが、運用に当たってはあらかじめそのリスクも懸念しなければなりません。運用益を出すことができなかった大学は、途端に資金の提供が中止となり、当初想定していた通りの大学運営が成立しなくなる可能性もあるでしょう。
また、大学ファンドという制度そのものが、日本の大学間の経済格差を助長し、大学間競争をより熾烈なものとする懸念もあります。ファンドという性質上仕方のないものではありますが、今後大学間の生存競争は少子化に伴いさらに激化することが想定されており、各大学は何らかの対策を考え、実行に移さなければなりません。

