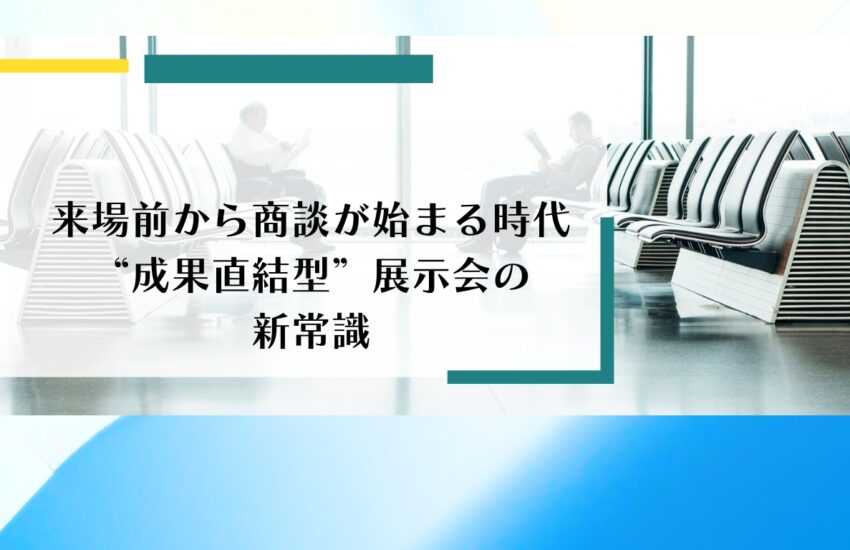数ある展示会の中で、どのような展示会が本当に価値ある場といえるのか。名刺交換だけで終わらせない、高品質なリードを獲得する仕組み、そして決裁層の来場率が際立つ集客戦略に定評のある展示会があります。
オンラインとオフラインを融合させたユニークなアプローチで出展企業・来場者の双方から高い支持を集める「Bizcrew EXPO」。本記事では、Bizcrew EXPO主催企業であるエバーリッジ株式会社の萩原氏に、その成功の舞台裏を詳しく伺いました。
ーー御社の展示会では、出展企業にとってどのようなメリットがあるとお考えですか?
萩原氏(以下敬称略):多くの出展企業様は、展示会をマーケティング施策の一環として積極的に活用されています。中でも大きなメリットとして挙げられるのが、新規顧客や見込み顧客、いわゆる「リード」の獲得です。展示会では名刺交換を通じて多くの顧客情報を収集できるため、それ自体が出展の大きな価値となっています。
さらに、私たちが提供する仕組みでは、リアルな展示会の開催前にオンライン上で来場予定者との接点を持つことが可能です。これにより、当日はすでに一定の関係性が築かれた状態で対話を始められ、単なる名刺交換にとどまらず、商談や成約につながる可能性が高まります。このように、事前のオンライン接点とリアル展示会を組み合わせたアプローチが好循環を生み、多くの出展企業様から高い評価をいただいています。
ーー一方で、来場される方々にとっては、どのような利点があるとお考えですか?
萩原:来場者の皆さまにとってはさまざまなメリットがありますが、最も本質的な価値は「情報収集」にあると考えています。
たとえば、日々の業務のなかで何らかの課題を感じていたり、紙やExcelで行っている業務をそろそろデジタル化したいとお考えの方は多いのではないでしょうか。そうしたニーズや課題に対して、「今どのような選択肢があるのか」を知る場として、展示会は非常に有効な情報源として活用されています。
また、展示会に併設される形でカンファレンスやセミナーを同時開催しているケースも多く、こうしたプログラムを通じて得られる「学び」も、来場者にとって大きな魅力のひとつとなっています。
ーーちなみに、今回の出展者数はどのくらいになりそうでしょうか?
萩原:今回はおよそ380社の出展を予定しています。
ーーそれはかなり多いですね。過去最多の規模ということになりますか?
萩原:そうですね、過去にはもう少し規模の大きい開催もありましたが、今回はそれに匹敵する過去最大級の展示会になる見込みです。
ーーありがとうございます。「リード獲得満足度ナンバーワン」との評価を耳にしましたが、その理由についてはどのようにお考えでしょうか?
萩原:はい、結論から申し上げますと、当社が他社と異なる「独自の集客施策」を実施していることが、質の高いリード獲得につながっている大きな要因だと考えています。
ーーなるほど。御社の取り組みによって、関心や課題意識の高い来場者が集まり、その結果として出展者が得られるリードの質にも良い影響が出ているのですね。
萩原:当社の集客施策の特徴として特に大きいのが、いわゆるデジタルマーケティングだけに頼らない点です。現在、多くの展示会では、メール配信やWeb広告などのデジタル施策が主流となっていますが、当社ではあえて「紙の招待状(DM)」の活用に力を入れています。
具体的には、全国の対象顧客に対して、実物の招待券を一件一件お送りしています。このアナログなアプローチが非常に高い成果を上げており、来場率の向上に大きく貢献しているのです。
さらに重要なのが、「送付先データの鮮度」です。同じ顧客リストを使い回すのではなく、毎回最新の情報を収集し、たとえば新たに就任された人事部長や経理部長といった意思決定者を的確にターゲティングしています。
こうした取り組みにより、「今まさに課題を抱えている方」「導入意欲の高い方」に対してタイムリーにアプローチすることができ、結果として来場者数が多いだけでなく、“質の高い”リードをご提供できています。これこそが、出展企業様から「満足度ナンバーワン」とご評価いただいている理由だと考えています。
ーーありがとうございます。では、次の質問です。来場者のうち約49%が課長職以上というデータがあります。つまり、ほぼ半数が何らかの決裁権限を持つ層で構成されていることになりますが、そうした高い役職の方々を多く集められている背景には、どのような戦略や工夫があるのでしょうか?
萩原:はい、この点については、当社の集客方針に明確な特徴があります。
私たちは、「決裁権を持つ方々を優先的に集客する」という戦略を掲げており、その実現に向けて重点的に取り組んでいます。
もちろん、出展企業にとってリードの「数」も重要な指標ですが、最終的な目的は製品やサービスの導入、つまり“受注”です。そのためには、意思決定に関わる責任者層に来場いただくことが、展示会の成果を大きく左右します。
そこで当社では、紙のダイレクトメール(DM)を活用しているのですが、特に役職の高い方々には、一般の来場者とは異なる「特別仕様の招待状」をお送りしています。
デザインや文面も専用に設計し、役員や部長クラスなどの決裁層にしっかりと響く内容に仕上げている点が特徴です。
実際に、そのような招待状が企業の役員のもとに届き、そこから「ぜひ現場の責任者に行ってもらいたい」と、部長クラスへ参加が指示されるケースも多くあります。
その結果として、決裁権を持つ来場者の割合が自然と高まり、出展者にとっても“質の高いリード”の獲得につながっていると実感しています。
ーーなるほど。そうしますと、紙の招待状に対して非常にきめ細やかに対応されている点が、他の主催者との差別化要素になっている、という理解でよろしいでしょうか?
萩原:はい、おっしゃる通りです。数年前までは、紙の招待状を活用していた主催者も一部ありましたが、コロナ禍をきっかけに状況が大きく変わりました。
パンデミックによる売上の減少やコスト削減の必要性から、多くの主催者が紙のDM送付を真っ先に見直し、現在ではその施策自体がほとんど行われていないのが実情です。
そのような中で、当社では今なお紙のダイレクトメールに注力しており、招待状の企画・制作・発送においても、コスト・人的リソースの両面で重点的な投資を続けています。その理由は明確で、他の手法と比べても、紙DMによる集客効果が最も高いと実感しているためです。
こうした取り組みを継続していることで、当社の展示会では単に来場者数が多いだけでなく、来場者の質の面でも高い水準を維持できており、出展企業様からも高い評価をいただいています。
ーー続いての質問です。オンラインでも多数のリードを獲得されているとのことですが、これは「出展製品まるわかりウェビナー」など、来場前に用意された仕組みの効果と捉えてよろしいでしょうか?
萩原:はい、その通りです。当社の展示会の大きな特徴のひとつが、来場者数や来場者の質の高さに加え、「開催前から来場予定者とのタッチポイントを多数設けていること」にあります。これにより、出展企業様にとってのリード獲得機会が飛躍的に広がっているのです。
具体的には、現在4つの主なチャネル(流入経路)から来場者情報を取得できる仕組みを整えています。
ご指摘の「出展製品まるわかりウェビナー」はそのひとつで、オンラインセミナー形式で開催され、参加者の情報をそのまま出展企業様にリードとしてご提供しています。実際、この施策からも多くの成果が生まれています。
さらに、出展製品やサービスを事前に検索できる「製品検索ページ」も用意しています。来場者はここで各社の製品資料やPR動画を閲覧でき、資料のダウンロードや動画の視聴・クリックなどのアクションが、そのままリード情報として出展企業様に連携される仕組みです。
加えて、4つ目のチャネルとして「ブース訪問予約(アポイントメント予約)」のシステムも導入しています。これは来場前に出展企業との面談予約ができるもので、非常に高い成果をあげています。実際に、ある展示会では3日間で2,400件以上の商談予約が成立し、出展者1社あたり平均で50〜60件の予約につながっています。商談化への非常に有効な導線となっています。
このように、展示会当日を迎える前から多角的に来場者との接点を築くことで、質の高いリードの創出につながっていると考えています。
ーーまた、実際に管理画面も拝見しましたが、非常に分かりやすく設計されていると感じました。こうした使いやすさにも、やはり強くこだわっていらっしゃるのでしょうか?
萩原:はい、まさにその通りです。オンラインセミナーの視聴者数を増やしたり、アポイントの件数を最大化したりするためには、Web上の導線設計や画面構成が非常に重要だと考えており、そこに力を入れています。
具体的には、各展示会ごとにPDCAをしっかりと回し、ユーザーの行動データや反応を分析しながら、画面構成やUIを改善し続けています。たとえば、ABテストを活用して「どちらの導線がより成果につながるか」を検証し、常に最適な設計に近づけていくという取り組みを継続しています。
ーー確かに、展示会関連のサービスでは、Webまわりの仕組みが十分に整っていないケースも見受けられます。その中で、御社のシステムは非常に完成度が高いと感じました。
萩原:ありがとうございます。実はこの背景には、業界全体の構造的な事情があります。多くの展示会主催者は、「リアル開催の3日間にどう来場者を集めるか」に主眼を置いており、それがWeb施策の優先度を下げている要因になっているんです。
加えて、展示会業界には“カニバリゼーション”の懸念もあります。事前にオンラインで情報を出しすぎてしまうと、「現地に行かなくても情報は得られる」と来場を控える人が出てしまう可能性があるため、どこまで事前に公開するかは非常に悩ましいポイントです。
資料や動画を充実させればさせるほど、「オンラインだけで完結できる」と思われるリスクが高まり、リアル来場の妨げになる恐れがある──それが、多くの主催者がオンライン施策に慎重な理由でもあります。
ーーなるほど。従来型のリアル中心の主催者にとっては、そうした判断が難しいのですね。一方、御社の場合は、当初から「オンラインとオフラインの融合」を前提に展示会を設計されている点が、大きな差別化要因になっているように感じます。
萩原:はい、まさにその通りです。これは当社の企業ミッションとも深く関わっていますが、私たちは「デジタルの力」と「リアルの力」を組み合わせることで、出展者と来場者の双方にとって最大限の成果を生み出すことを目指しています。
展示会という場を、「単なるイベント」ではなく「情報提供とリード獲得のためのプラットフォーム」として捉え、立ち上げ当初からオンラインとオフラインの両面を統合するかたちで設計・運営を行ってきました。
従来のようなリアル集客に偏った構造に縛られることなく、ゼロベースで設計できたからこそ、柔軟かつ効果的な仕組みを構築できたのだと考えています。
ーーつまり御社のオンライン展示会は、単に「オンライン会場を用意する」にとどまらず、オンラインを戦略的な集客チャネルとして位置づけているということですね。リアルとオンライン、どちらの形式にも柔軟に対応できる体制が整っていると理解してよろしいでしょうか?
萩原:はい、その通りです。 私たちは、展示会がたとえオンライン上で完結したとしても、それによって出展者様にしっかりと成果が生まれるのであれば、十分に価値があると考えています。
もちろん、リアル会場に実際に足を運んでいただけるのは非常にありがたいことです。ですが、来場予定の方がオンライン上で必要な情報を得て、出展者との接点が生まれ、それが商談や導入といった成果につながるのであれば、「リアルかオンラインか」という手段にはこだわらない──それが当社の基本的なスタンスです。
ーーなるほど。手段に関わらず、出展者の成果が上がれば上がるほど、展示会そのものの価値も高まるということですね。それがまさに本質的なポイントというわけですね。
萩原:はい、まさにその通りです。そしてもう一つ重要なのは、来場者の視点です。
リアルな展示会に参加するとなると、どうしても移動時間や拘束時間が発生し、交通費や宿泊費といったコストもかかってきます。そうした負担を感じる方にとっては、オンラインで効率的に情報収集や比較検討ができる手段があることが、大きなメリットになります。
だからこそ、当社では出展者だけでなく来場者にとっても価値のある体験を提供できるよう、オンラインとリアルの両方で有益な情報を届けることを重視しています。
ーーありがとうございます。それでは、次の質問に移らせていただきます。次回以降も幕張メッセや東京ビッグサイトでの開催を予定されていると伺っていますが、今後、地方での開催をさらに拡大していくご予定はありますか?
萩原:はい、地方展開については明確に方針を掲げており、今後の重要な取り組みのひとつと位置づけています。これまでも大阪では開催実績がありますが、来年は新たに3月に福岡、4月に名古屋での開催を予定しており、地方での展開をさらに広げていくフェーズに入ります。
当社としても、事業戦略の中で地方開催は大きな柱と捉えておりますが、一方で東京圏に比べると、地方での集客は難易度が高いのも事実です。商圏の規模や来場者の行動特性が異なるため、慎重な判断が必要になります。
私たちは集客に強みを持っていますが、それでも「確実に成果が見込める」と判断できるタイミングでの開催を重視しています。そのため、丁寧な市場調査と分析を重ねたうえで準備を進め、ようやく来年、福岡・名古屋での開催に踏み出せる見通しが立ったという状況です。
ーーありがとうございます。ちなみに、今回の展示会ではどの程度の来場者数が見込まれているのでしょうか?
萩原:今回7月に東京で開催される展示会では、約2万人の来場を見込んでいます。
ーー東京開催で約2万人とのことですが、地方開催の場合の想定来場者数はいかがでしょうか?
萩原:大阪開催では、これまでの実績として7,000〜8,000名規模の来場者数を記録しています。
一方で、来年初めて開催する福岡・名古屋については、各会場ともに4,000〜5,000名程度の来場を想定しています。これは初開催であることに加えて、地方では集客の難易度が相対的に高く、また会場の収容規模にも制約があるためです。
たとえばインテックス大阪は大規模な会場ですが、ポートメッセ名古屋やマリンメッセ福岡は比較的小規模な施設ですので、それぞれの会場に見合った集客目標を設定しています。
とはいえ、私たちとしては出展企業様にご満足いただける来場規模を確保することが最優先です。福岡・名古屋の両会場についても、5,000名規模が適切だと判断し、計画を進めています。
ーーありがとうございます。「DX 総合EXPO」と「バックオフィス World」は、それぞれ異なるブランドとして展開されているように見受けられますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか? また、ブランドを分けている理由についても教えてください。
萩原:はい。まず、私たちエバーリッジが主催する展示会は、すべて「Bizcrew EXPO(ビズクルエキスポ)」という統一ブランドのもとで展開しています。「DX 総合EXPO」や「バックオフィス World」もその中にあるテーマ別の展示会シリーズです。
それぞれの展示会は、扱う領域と対象が明確に分かれています。「DX 総合EXPO」は、ITツールやデジタルソリューションなど、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する商材に特化しており、出展対象も基本的にその領域に限られます。
一方で、「バックオフィス World」では、人事・総務・経理などのバックオフィス部門を支援するBPOやコンサルティングサービスなど、ITに限らない幅広いソリューションが出展可能です。
このようにテーマを明確に分けて設計することで、それぞれに合った来場者層を呼び込めるようになっており、出展者とのマッチング精度も高くなっています。
ーー実際、御社の展示会では来場者の職種や部署が非常に多様だと感じました。こうした幅広い層の来場にも、テーマごとの設計が関係しているのでしょうか?
萩原:はい、おっしゃる通りです。展示会ごとに明確なテーマ設定をしていることで、それぞれの業務課題や関心に合った来場者が集まり、結果的に複数部門からの来場が自然に生まれています。たとえば「DX 総合EXPO」ではIT部門や情報システム部門が中心ですが、「バックオフィス World」では人事・総務・経理などの来場が多く、データ上でもその傾向が明確に出ています。
ーー来場者インタビューでは、「他の展示会とは違う」という声も多く見られました。その背景には、来場者の目的意識の高さもあるのではないでしょうか?
萩原:はい、まさにそこが大きな特長です。当社の展示会では、情報収集だけでなく、実際に課題解決や導入を見据えて来場される方が非常に多くなっています。
これは、開催前から行っているオンライン施策の効果によるものです。事前にセミナーや製品紹介コンテンツをご覧いただいたうえで来場される方が多く、すでに比較検討フェーズに入った状態で、出展者との具体的な対話に臨まれているケースが増えています。
その結果、来場者と出展者のマッチングの質が高まり、展示会自体が「リードナーチャリングの場」として機能していると感じています。
ーーありがとうございます。ちなみに、展示会を通じて実際に商談や成約に至った件数などは、御社でも把握されているのでしょうか?
萩原:はい、最終的な「受注」状況については、さすがにすべてを網羅的に把握するのは難しいのが現実です。とはいえ、名刺交換を通じたリードの獲得数については、ほぼすべての出展企業様からご報告をいただいており、全体の傾向はしっかりと把握できています。
また、受注に関する情報についても、一部ではありますが、一定のデータは得られています。というのも、当社では出展企業様向けに「出展コンサルティング」という無料のサポートサービスを提供しており、これが非常に好評をいただいています。
このサービスでは、展示会前の目的設定やKPI設計の支援に加え、会期終了後には「振り返りミーティング」を実施しています。そこで出展企業様と一緒に成果を分析し、次回に向けた改善提案などを行うのですが、その中で「実際に受注につながった」といった情報をご共有いただけるケースも多いんです。
そのため、他の展示会主催者と比べても、成約に関する実態をある程度まで把握できている点は、当社ならではの強みだと考えています。
ーーなるほど、ありがとうございます。続いての質問ですが、御社の展示会ではさまざまな部署の方々が来場されている印象を受けました。これはやはり、「マーケティング・セールス World」や「バックオフィス World」など、複数のテーマ別展示会を同時開催していることによるシナジーの効果と理解してよろしいでしょうか?
萩原:はい、そのご理解で間違いありません。背景には、大きく2つの要因があります。
まず1つ目は、展示会全体のコンセプトとして、特定の職種に限定せず、オフィスのさまざまな部門の方々にご来場いただけるよう設計している点です。 たとえば「DX 総合EXPO」では、「人事DX」「経理DX」「マーケティングDX」など、業務領域ごとのデジタル化をテーマにしており、それぞれの部門ごとに課題解決のヒントを提供できる構成になっています。
また、同時開催している「人材育成EXPO」や「SDGs関連展示会」なども、それぞれ異なる関心層に向けて設計されているため、結果として来場者の職種・業務領域が非常に多様になります。
2つ目の要因が、まさにご指摘いただいた「シナジー効果」です。たとえば「人事DX」の展示を目的に来場された方が、会場内で「マーケティング・セールス World」や「AI World」など別のエリアにも立ち寄るケースが非常に多く見受けられます。
これは、自部門だけでなく他部門のトレンドやソリューションにも興味を持ち、横断的に情報収集をされている来場者が増えていることの表れです。展示会というリアルな場ならではの“偶発的な気づき”を求めて、多角的にブースを巡っていただいているのだと思います。
こうした動きが結果として、来場者層の幅をさらに広げ、出展企業にとってもより多くのリード獲得や商談機会につながっています。まさにこの「テーマ連携によるシナジー効果」こそが、展示会全体の成果を底上げする大きな原動力になっていると実感しています。
ーー御社の展示会では、リードの納品が非常にスピーディだと伺いましたが、それはどのような仕組みで実現されているのでしょうか?
萩原:はい。結論から申し上げますと、「デジタル名刺交換システム」を導入していることが大きな要因です。
来場者の方には入場時に個別のQRコード付きバッジをお渡ししており、出展者側はそのQRコードを、来場者ご自身のスマートフォンなどで読み取っていただく形になっています。
読み取りと同時に名刺情報が即時にデジタル化され、システムに登録される仕組みになっているため、展示会終了後すぐにリード情報を納品することが可能になります。
この仕組みによって、従来の紙の名刺を回収して手入力する手間が不要となり、出展者様は展示会終了直後からスムーズにフォローアップを開始していただける体制を整えています。
ーー実際の現場では、来場者のQRコードを使ったデジタル名刺交換に加えて、従来の紙の名刺交換も引き続き併用されているのでしょうか?
萩原:はい、以前は紙の名刺交換とデジタルスキャンを併用されるケースが多く見られました。特にデジタルに不慣れな方や、紙でのやり取りを好まれる方も一定数いらっしゃいましたので、両方を使い分けるという形が一般的でした。
ただ、ここ数年で状況が大きく変わってきています。現在では、多くの出展企業様が「利便性」や「データの即時性」を重視されるようになり、デジタル名刺交換をメインで活用する傾向が強まっています。情報がその場で自動的に蓄積され、すぐに営業活動に移れるという点が大きなメリットとして受け入れられているのだと思います。
ーーなるほど。来場時に事前登録でプロフィールを入力しておけば、それがそのまま名刺情報として使えるというのは、大きな利便性ですね。
萩原:はい、おっしゃる通りです。加えて、当社では「利便性」だけでなく、データの正確性や情報の深さにもこだわった仕組みを導入しています。
たとえば、来場者が企業名(法人名)を入力すると、それに紐づいて所在地や業種、売上高、資本金、従業員数などの企業属性情報が自動的に補完されるようになっています。そのため、出展者の皆様は、紙の名刺以上にリッチで実用的な情報を得ることが可能です。
このように、単なる名刺交換にとどまらず、営業やマーケティングに活用できる質の高いデータが得られるという点が、多くの企業様に評価されています。実際、紙の名刺に頼らず、デジタル名刺交換を積極的に活用する企業は年々増えており、今では主流になりつつあります。
ーーさらに、取得したデータをCSV形式で出力できるので、CRMなどの営業支援システムにそのまま取り込める点も、大きなメリットですね。
萩原:はい、まさにその通りです。CSVでのデータ出力ができることで、CRMやSFAとの連携が非常にスムーズになり、展示会後の営業活動にもすぐにつなげていただける点が高く評価されています。
また、当社の展示会では、かつて紙のアンケートで行っていたような内容──たとえばブースごとの星評価や、自由記述のメモなども、すべてデジタル上で完結できるような仕組みを整えています。これにより、出展者側にも来場者側にも、非常に高い利便性を提供できていると考えています。
ーー来場者にとっても、記録や振り返りがしやすくなるのは嬉しいですね。
萩原:そうですね。デジタル名刺交換を通じて得た情報は、来場者それぞれのマイページに自動的に蓄積されます。そのため、「どのブースを訪れたのか」「どんな印象を持ったのか」といった内容を、自分用に記録・整理することが可能です。
展示会後に訪問履歴を一覧で確認したり、各ブースの感想を振り返ったりといった使い方ができるため、たとえば社内での報告資料や検討用レポートの作成にも活用いただけます。
つまり、展示会を“その場限り”の体験で終わらせず、その後の比較検討や意思決定につながる情報基盤として活用していただける──これが、私たちの展示会の大きな特長のひとつだと考えています。
ーーなるほど、よく分かりました。ちなみに、今後開催される展示会についても、来場者の情報は同じプラットフォーム上で一元的に管理されるという理解でよろしいでしょうか?
萩原:はい、そのご認識で間違いありません。当社が主催するすべての展示会は、同一のプラットフォーム上で情報を管理・提供しており、来場者の方々にも統一された操作感でご利用いただけるように設計されています。
初めての方にもわかりやすく、リピーターの方にも使いやすい──そうしたユーザー体験の一貫性を重視しています。
ーー最後に、御社として読者の方々にお伝えしておきたいことがありましたら、お願いします。
萩原:ありがとうございます。最後に一つお伝えしたいのは、出展企業様から当社の展示会が高く評価されている理由についてです。
なかでも特にご評価いただいているのが、「短期間で非常に多くのリードを獲得できること」、そして「そのリードの質が非常に高いこと」です。これは毎回、出展者の皆様から明確な成果として実感いただいており、大きな価値と受け止めていただいています。
加えて、当社ではリードの獲得だけにとどまらず、出展者様の成果を最大化するためのさまざまな支援サービスを、すべて追加料金なしでご提供しています。たとえば、
・事前に参加できるオンラインセミナー
・リード獲得状況をリアルタイムで確認できるオンラインダッシュボード
・会期中に使えるデジタル名刺交換(QRコード)機能
これらはすべて「標準機能」として提供しており、他の展示会ではあまり見られない特長だと自負しています。
さらに、出展企業様をしっかりとサポートするための「出展コンサルティング」も無料でご提供しています。これは、出展目的やKPIの設計、ブースの装飾・動線の工夫、当日のオペレーション設計に至るまで、事前から一貫して伴走する支援サービスです。
そのため、展示会への出展が初めての企業様や、当社の展示会に初参加される企業様でも、初回からしっかりと成果を出していただけるケースが非常に多くなっています。
他の展示会では「出たとこ勝負」や「当日の運任せ」になってしまうこともあるかもしれませんが、当社は違います。成果を“再現可能な仕組み”として設計し、それをノウハウとして出展企業様にお渡しすることで、社内に知見として蓄積していただく──それが私たちの目指している支援のあり方です。
ーーありがとうございます。ちなみに、今回の展示会における各ブースの出展費用についてお伺いしてもよろしいでしょうか?
萩原:はい。標準的なサイズである「1小間」(間口3メートル×奥行き2.7メートル)のブースで、出展費用はおおよそ50万円となっています。この1小間あたり50万円を基準に、2小間であれば100万円、4小間であれば200万円というように、出展規模に応じて費用が加算される仕組みです。
ーーなるほど。そこに加えて、各社のブランドイメージやPR方針に合わせて、ブースの装飾などに追加コストが発生するというイメージですね。
萩原:おっしゃる通りです。ブースのデザインや装飾は企業の見せ方そのものであり、ブランド価値の訴求にも直結しますので、こだわる企業様にとっては非常に重要な投資項目となります。場合によっては、装飾だけで数百万円、あるいは1,000万円近くをかけるケースもあります。
ただし、当社の展示会の大きな特長は、大手企業様だけでなく、中小企業様やスタートアップ企業様の出展が多数を占めている点にあります。
「これから市場での認知を広げたい」「新しい製品やサービスを成長させたい」といった前向きな意欲を持つ企業様が多く出展されており、まさに“主役は中小企業”といえる展示会です。
これからDX分野での展開をお考えの企業様が多くいらっしゃるかと思います。ぜひ出展というかたちでご参加いただき、具体的な商談機会や業界の最新動向に触れていただければと思います。
また、来場者としてご参加いただいても、多くのヒントやソリューションとの出会いが得られる展示会です。ぜひ、多くの方に足を運んでいただければ幸いです。
ーー本日はご多用のところ、貴重なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。以上でインタビューを終了させていただきます。
Bizcrew EXPO 開催予定の展示会
・マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪
2025/8/27(水)-8/29(金)
インテックス大阪
・バックオフィス World 2025 夏 大阪
2025/8/27(水)-8/29(金)
インテックス大阪
・マーケティング・セールス World 2025 夏 東京
2025/9/8(月)-9/10(水)
東京ビッグサイト
・バックオフィス World 2025 夏 東京
2025/9/8(月)-9/10(水)
東京ビッグサイト
・AI World 2025 秋 東京
2025/10/29(水)-10/31(金)
幕張メッセ
・ビジネスイノベーション Japan 2025 秋 東京
2025/10/29(水)-10/31(金)
幕張メッセ
・DX 総合EXPO 2025 秋 東京
2025/10/29(水)-10/31(金)
幕張メッセ
・ビジネスイノベーション Japan 2025 冬 大阪
2025/12/17(水)-12/19(金)
インテックス大阪
・DX 総合EXPO 2025 冬 大阪
2025/12/17(水)-12/19(金)
インテックス大阪
・産業DX総合展 2026 夏 東京
2026/9/30(水)-10/2(金)
東京ビッグサイト