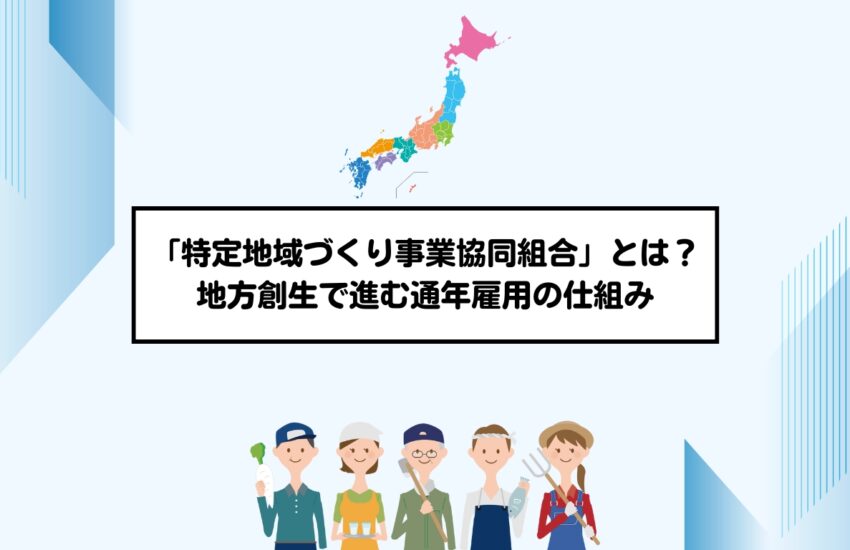地方の農村や離島、小さな町で暮らす人々にとって、「仕事があるかどうか」は生活を続けられるかどうかを左右する重大な問題です。特に農業や観光業のように、季節によって忙しさが大きく変わる産業では、通年での雇用を確保することが難しく、働き手は安定した収入や社会保険を得られないまま地域を離れてしまうケースも少なくありません。
こうした現実に対応するため、2020年に始まったのが「特定地域づくり事業協同組合制度」です。地域の事業者が力を合わせ、一年を通じて人材を雇用し、季節や業種をまたいで仕事を組み合わせる――そんな新しい雇用モデルが、人口減少に悩む地域の希望となりつつあります。
現在は農業・観光・製造など季節変動の大きい産業を中心に広がっていますが、今後は福祉や教育、ITなど通年需要がある分野にも活用の場が広がる見込みです。加えて、制度を支えるコーディネーター人材の育成や、効果検証のデータ整備も進み、地方創生の中核的な施策へと成長していく可能性があります。
本記事では、その背景や仕組み、メリット、全国各地の事例、そしてこれからの展望までを詳しく解説します。
特定地域づくり事業協同組合とは

特定地域づくり事業協同組合とは「複数の事業者が人材をシェアし、通年雇用を実現する」ための制度です。この制度は人口減少に直面する地域で、安定した雇用と産業の持続を両立させる新しい仕組みです。
制度の仕組み
ここでは、その基本構造や認定の流れ、運営方法を順に説明します。
1. 基本構造
特定地域づくり事業協同組合は、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合が、地域の人材を無期雇用(正社員)で採用し、複数の地元事業者に派遣する仕組みです。
・派遣の特例:無期雇用職員に限り、労働者派遣事業の「許可」ではなく「届出」で運営可能。
・公費支援:運営費の一部を国と市町村が1/2ずつ負担し、小規模自治体でも導入しやすい。
2. 法的根拠と対象地域
・根拠法:「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」
・施行:令和2年6月4日
・所管:総務省・厚生労働省(連携)
・対象:人口急減地域や、人材確保が特に必要とされる地域(過疎法区域に限らない)
3. 認定の流れ
1.地域事業者3社以上が出資し、協同組合を設立
2.都道府県知事に申請(事業計画・財務・運営体制を添付)
3.認定(10年更新制)
4.国・市町村と財政協定を締結
4. 運営のフロー
1.人材採用:地域内在住者やUIJターン希望者を対象に、社会保険完備で正社員採用
2.年間スケジュール作成:農繁期や観光繁忙期など、繁閑カレンダーを作り職務ローテーションを設計
3.派遣・出向の実施:届出制で運営し、派遣料金と公費支援で組合を運営
4.教育・スキル開発:業種別研修や資格取得支援で多能工化を促進
5. 関係主体の役割
・協同組合:人材採用・雇用管理・配員調整・研修
・派遣先事業者:業務提供・現場指揮・派遣料金支払い
・自治体:運営費負担・地域ニーズ調整・移住支援
・国:制度設計・交付金交付・事例共有
「特定地域づくり事業協同組合」制度の背景と広がりの理由
では、その背景にはどのような課題があり、なぜ全国で広がりつつあるのでしょうか。ここでは、制度誕生の経緯と位置づけを見ていきます。
人口減少が地域の存続を脅かす
全国の多くの地域で、人口が急激に減り続けています。若い世代が都市部へ移り住み、残された地域では高齢化が進行。「このままでは地域社会そのものが維持できない」という危機感が強まっています。こうした状況を受け、法律は地域経済を支える「地域づくり人材」が安心して働き続けられる環境整備を、最優先課題として位置づけました。
通年雇用の難しさと担い手不足
農業や観光業など、季節によって仕事量が大きく変わる産業が多い地域では、単独の事業者が年間を通じてフルタイム雇用を確保するのは難しいのが現実です。結果として、安定した雇用・賃金・社会保険を提供できず、UIJターンを希望する人が定住をためらう要因にもなっていました。
既存制度では解決できなかったミスマッチ
「仕事はあるけれど、時期がずれていてつなぎ合わせられない」――これが地方の現実でした。繁忙期と閑散期をまたいで仕事を組み合わせる“調整役”が不在で、一般的な労働者派遣制度も許可制や運用要件の高さから利用が難しい状況。地域に合った特例措置と財政支援の組み合わせが求められていたのです。
地方創生政策の中での位置づけ
この制度は総務省と厚生労働省が連携して設計し、特に農山漁村での活用を推進しています。さらに、2022年の「デジタル田園都市国家構想」など、地方創生の重要施策の一つとして位置づけられ、全国への普及が進められています。
この制度を使うと何が変わる?――メリットを解説
制度の仕組みを見てきましたが、このモデルが全国で注目を集める理由は、単に人手不足を埋めるだけでなく、働き手・事業者・地域の三者にとって“三方良し”となる点にあります。ここでは、その主なメリットを整理します。
1. 働き手にとって ― 安心して暮らせる通年雇用
地方で仕事を探すと、「繁忙期だけの短期雇用」「季節が終われば契約終了」というケースが珍しくありません。この制度では協同組合が正社員として無期雇用するため、年間を通じた安定収入と社会保険が保証されます。
たとえば、春は農業、夏は観光、冬はスキー場といった具合に職場が変わっても、給与や保険は継続されます。さらに、複数業種を経験することでスキルの幅も広がり、キャリア形成につながります。
2. 事業者にとって ― 人手不足の“谷間”を埋められる
繁閑差が大きい産業では、人手不足と余剰の波が交互に訪れます。単独の事業者では通年雇用が難しく、繁忙期の採用難や閑散期の人件費負担が課題でした。協同組合方式では、複数の事業者が人材をシェアすることで必要な時期に必要な人数を確保でき、採用コストの抑制にもつながります。
3. 自治体・地域にとって ― 移住・定住促進と産業維持
安定した働き口は、移住・定住を促す最大の要因の一つです。この制度は「1年を通じて働ける」地域モデルを提供し、UIJターン希望者にも大きな魅力となります。また、地域産業が持続することで学校や商店、交通などの生活インフラ維持にも直結します。
4. 雇用の質向上と地域ブランド化
短期雇用の連続では、長期的なキャリア形成が難しくなります。無期雇用とスキル習得の機会があれば、「地方でもキャリアを積める」という認識が広がります。地域全体で人材育成に取り組む姿勢は、外部からの評価や移住促進にもつながり、「働きやすい地域」というブランドを形成します。
5. 公費支援による導入ハードルの低減
国と市町村が運営費を折半し、市町村負担分の一部は特別交付税で補填されます。これにより、小規模自治体でも財政負担を抑えつつ制度を導入できる点が大きな後押しとなっています。
制度運用上の課題と留意点
メリットの多い制度ですが、実際に運用するとなると、いくつもの課題や注意点が浮かび上がります。ここでは、制度を円滑に機能させるために押さえておきたい主要なポイントをまとめます。
1. オペレーション設計の難易度
季節や曜日、時間帯ごとに複数の事業者の繁閑に合わせて配員するには、高度なコーディネート力が必要です。職務切替が頻繁になるほど、引き継ぎや安全衛生管理、教育の負担も増大します。
🔵対応策:年間の「繁閑カレンダー」作成、スキルマトリクスによる適材適所配置、二層スケジューリング(四半期で固定+週次調整)
2. 法令順守
届出制の特例はありますが、労働者派遣法や労働基準法の義務の多くは残ります。派遣可能業務の範囲や同一労働同一賃金の扱いなど、法令面の理解と対応が欠かせません。
🔵対応策:「就業条件明示」「待遇決定方式」などの文書化、労働時間通算や36協定の整理、個人情報管理規程の整備
3. 建設業務への対応
建設業への派遣は原則禁止ですが、在籍型出向なら可能です。ただし、契約や安全衛生教育など実務的なハードルがあります。
🔵対応策:出向契約書の雛形整備、現場ごとの資格要件の事前整理
4. “8割ルール”の順守
総労働時間の8割を一つの派遣先に偏らせないことが制度の趣旨。偏りすぎると雇用の安定性が損なわれます。
🔵対応策:派遣先別労働時間のモニタリング、最低2〜3社での勤務原則化
5. 賃金・就業ルール設計の複雑化
職場が変わることで賃金や手当、待機・移動時間の扱いが複雑になります。
🔵対応策:横断的な賃金テーブル作成、移動時間の取り扱いルール明確化、多面評価制度の導入
6. 財務の持続性
公費支援に依存しすぎると、補助が縮小した際に運営が行き詰まる恐れがあります。
🔵対応策:自立収支シナリオの策定、派遣料金改定ルールの整備、売掛金の回収管理
7. 採用・定着とキャリア形成
多能工化は魅力ですが、教育投資と離職リスクが表裏一体です。生活基盤の整備も定着率に直結します。
🔵対応策:ジョブローテの段階モデル、住宅・交通・保育支援、地域に根差すキャリアロードマップの提示
8. ステークホルダー間の合意と透明性
制度が一部事業者だけの利益になっていると見なされれば反発を招きます。
🔵対応策:料金やマージン率の開示、配員方針の事前合意、年次レポートで実績を公開
9. 安全衛生・BCP(事業継続計画)
複数現場・複数業種はリスクが多様化します。災害や需要急変にも備える必要があります。
🔵対応策:危険源と教育履歴のデジタル管理、代替就労メニューの事前設計、災害時の出勤判断基準明確化
10. 勤怠管理と情報システム
複数派遣先の勤怠・教育履歴を紙やメールで管理するのは限界があります。
🔵対応策:勤怠・配員・資格・評価を一元管理できるシステム導入、週次レポート共有
11. 地域間連携とインフラ整備
広域で人材を融通する場合、交通や住居、通信環境がボトルネックになります。
🔵対応策:短期住宅や社宅の確保、交通費規程化、オフライン勤怠のバックアップ運用
12. 効果検証とKPIの設定
制度効果を「雰囲気」で語るのではなく、数値で示すことが重要です。
🔵対応策:定着率や繁忙期充足率、移住定着件数などのKPI設定、四半期ごとのレビューと改善計画
特定地域づくり事業協同組合の活用事例集

前章で見たように、制度には多くのメリットがある一方、運営には課題や工夫が欠かせません。それでも全国各地では、この仕組みを地域の特性に合わせて活かし、成果を上げている事例が増えてきています。ここでは、その代表的な取り組みをいくつか紹介します。
海士町(島根県) ― 島の四季をつなぐ「複業の島」
人口約2,200人の離島・海士町は、長年「人手不足」と「仕事の季節変動」という二つの課題を抱えてきました。漁業は冬に水揚げが減り、観光は夏がピーク、農業は春と秋が繁忙期。
これらの波を逆手に取り、漁業・農業・観光・製造業など複数の仕事を一人の働き手が季節ごとにリレー形式で担う仕組みをつくったのが「海士町複業協同組合(AMU WORK)」です。
組合員は春にワカメ漁、夏は観光ガイド、秋は農作業、冬は食品加工といった具合に年中フル稼働。移住者からも「この仕組みがあったから島に住む決心ができた」という声が多く、人口流出の抑制に直結しています。
下川町(北海道) ― 森と町を循環する人材
人口約3,000人の下川町は、林業や木材加工を基幹産業としながら、小売や農業も盛んな町です。しかし冬季は林業も農業も減速します。
そこで「下川事業協同組合」が立ち上がり、林業・製材・農業・小売を横断するマルチワークを実現しました。夏は森林整備や製材所勤務、冬は除雪作業や店舗販売員として活動。「雇用の循環」により、働き手が町を離れず暮らし続けられる仕組みをつくっています。
佐渡市(新潟県) ― 離島の複合的な人手不足に挑む
2024年7月に認定を受け、8月に事業を開始した新しい事例です。観光、農業、福祉といった分野で人手不足が深刻化する中、「TOKI CONNECT」という組合が誕生しました。
離島特有の人材確保の難しさに挑み、移住希望者にも門戸を開くプロジェクトとして全国から注目されています。
東成瀬村(秋田県) ― 農業とスキー場の二刀流
農林畜産業が盛んな東成瀬村では、冬の農閑期が長く続きます。その間を支えるのが観光業、とくにスキー場運営です。
組合は夏に農業や畜産、冬はスキー場や宿泊業に就く複合雇用モデルを確立。農繁期と観光繁忙期がちょうど逆という特性を活かし、年間を通じた安定雇用に成功しました。
制度の進化と広がりに向けたこれからの展望

各地の事例からわかるように、特定地域づくり事業協同組合は、地域の産業や暮らしを支える実践的な仕組みとして成果を上げ始めています。では、この制度は今後どのように広がり、発展していくのでしょうか。
分野のさらなる拡大
これまでの活用は農業・観光・製造など季節変動の大きい産業が中心でしたが、今後は福祉・介護、教育支援、ITリモート業務といった、通年需要がありながら人材確保が難しい分野への広がりが見込まれます。特に福祉は高齢化が進む地域にとって不可欠であり、制度の新たな柱になり得ます。
建設業への対応
法律上、建設業への派遣は原則禁止ですが、在籍型出向を活用すれば対応可能です。インフラ整備や公共工事が多い地域では、このルートを使った人材確保の動きが今後増えると考えられます。
農林水産分野での重点活用
農林水産省は制度活用を積極的に推進しており、農山漁村における人材不足解消の切り札と位置づけています。特に漁業は繁閑差が大きく、マルチワーカーの導入効果が大きい分野と見られます。
効果検証とデータ整備
全国で126組合が稼働する中、今後は制度の成果をデータで可視化することが重要になります。派遣労働者数や就業分野、移住定着率などの指標を整備し、国や自治体が評価・改善に活用すれば、制度の信頼性がさらに高まります。
コーディネーター人材の育成
この制度の持続性を左右するのが、季節や業種の組み合わせをデザインできるコーディネーターの存在です。勤務シフト設計、スキルマッチング、労務管理、研修運営など幅広い役割を担う彼らは、地域のプロジェクトマネージャーとも言えます。各地の成功事例は、こうした人材育成の重要性を物語っています。
地域づくりに向けた第一歩としての制度活用まとめ

特定地域づくり事業協同組合は、人口減少や季節労働による雇用不安定といった地域固有の課題に対し、複数事業者で人材をシェアし、通年雇用を実現するという新しい解決策を提示しています。
その仕組みは、働き手に安定と成長の機会を、事業者に人材確保の柔軟性を、そして地域に持続可能な産業基盤をもたらします。
もちろん、運営の複雑さや法令順守、財務の持続性など、乗り越えるべき課題は少なくありません。しかし、各地の事例が示すように、地域の特性に合わせた創意工夫によって成果は着実に広がっています。
これからは、福祉や教育、ITなど新たな分野への展開や、コーディネーター人材の育成、効果検証の強化がカギとなります。
人口減少が避けられない時代にあって、この制度は「地域に暮らし、働き続ける」ための現実的かつ希望のある道筋を示す存在です。
地方の未来は、外から与えられるものではなく、そこに暮らす人々の手でつくるもの。特定地域づくり事業協同組合は、その力を引き出すための有効なツールであり続けるでしょう。
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略