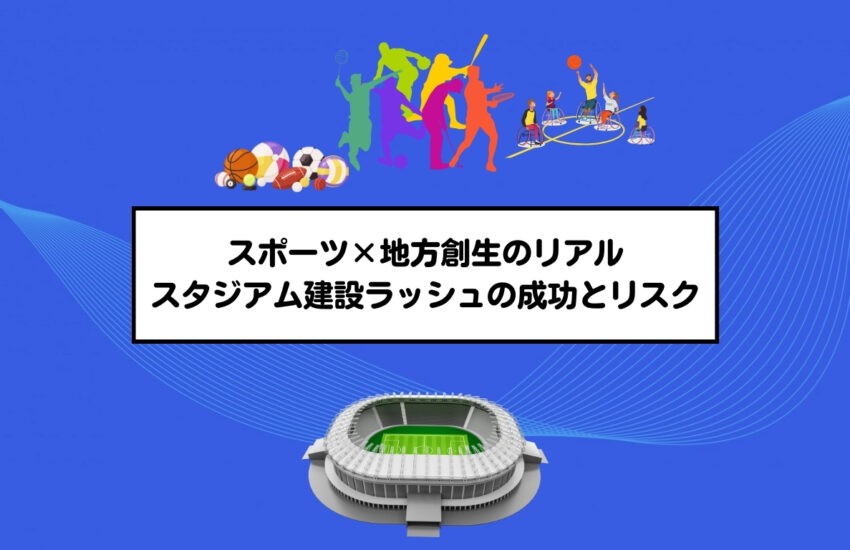スタジアム建設が止まらない。北海道、長崎、沖縄、横浜――。
ある街は人口の70倍を集客し、ある街は1,000億円を投じた「賭け」に出た。
巨額投資とリターン、成功とリスク。その数字を追うと、日本の地方創生の未来が見えてくる。あなたの街にスタジアムができたら、果たしてそれは希望になるだろうか?
全国で進むスタジアム建設、その先にある問い

2020年代に入り、日本各地でスタジアムやアリーナ建設が相次いでいます。東京の新国立競技場をはじめ、北海道北広島市の「エスコンフィールド北海道」、沖縄市の「沖縄アリーナ」、長崎市で進む「長崎スタジアムシティ」、さらには横浜の再開発など、スタジアムは今や「地方創生の切り札」として注目を集めています。
背景には二つの相反する視点があります。ひとつは経済波及効果への期待です。建設工事による雇用創出、観客動員による宿泊・飲食需要、国際イベントを呼び込むインバウンド効果、そして都市ブランドの強化。こうした効果は「地域経済を押し上げる装置」としてのスタジアム像を描かせます。
一方で、財政負担・持続性への懸念も常に存在します。建設費は数百億円から千億円規模に上り、維持管理コストも巨額です。利用率が低ければ「負の遺産」と化し、市民の税負担となるリスクも否めません。過去、札幌ドームやオリンピック施設の一部が示したように、「立派だが使いこなせない施設」が全国で繰り返されてきました。
まず北海道北広島市の「エスコンフィールド北海道」を題材に、スタジアムが地域に与えるインパクトを数字で読み解きます。人口わずか6万人の地方都市に、1年間で418万人が訪れるという事実は、スポーツ施設がもたらす可能性と課題を如実に示しています。
人口の70倍を集めた北海道 ― エスコンフィールド
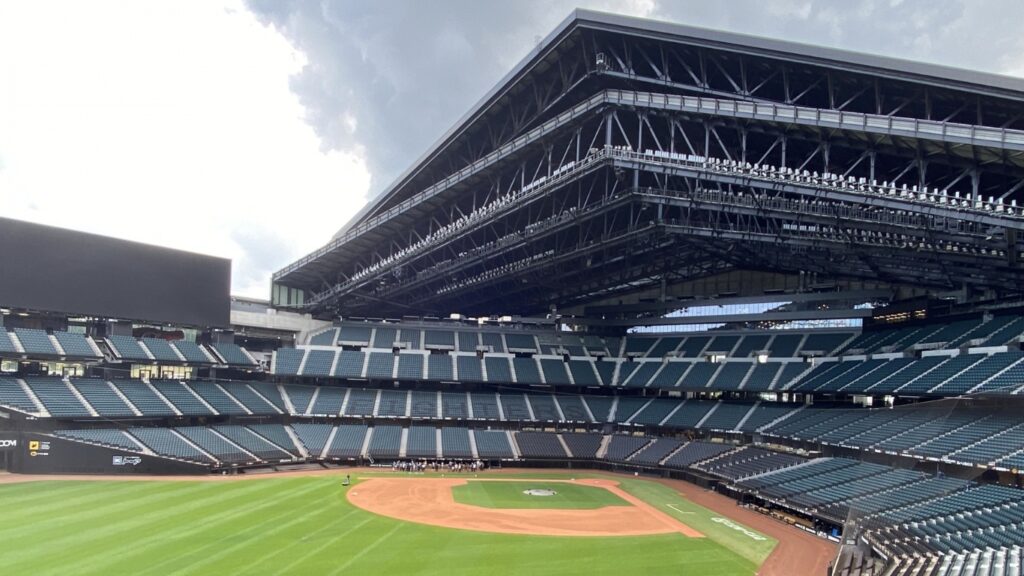
2023年3月に開業した「エスコンフィールド北海道」(以下、エスコン)は、北海道日本ハムファイターズの新本拠地であり、国内初の「ボールパーク構想」を掲げた球場として注目を集めました。開業初年度、エスコンを訪れた人々は418万7,046人でした。前年比で21%増という数字は、野球専用球場という枠を超えた集客力を証明しています。
内訳を見ると、公式戦観客数が207万5,734人、その他のイベントや観光利用で211万1,312人に達しています。つまり「野球を見に来た人」と「野球以外で訪れた人」がほぼ拮抗しているのです。一般的な球場はプロ野球シーズンに依存しますが、エスコンは野球の有無にかかわらず集客できる観光拠点となっています。
北広島市の人口は約6万人です。年間418万人という数字は、市の人口の70倍に相当します。地方都市にとって、これほどの人流を呼び込む施設は他にありません。
道外から102万人、海外客も倍増
来場者の地域分布を見ると、総数の約24%、およそ102万人が道外からの来場者でした。北海道の中心都市である札幌ではなく、郊外都市の北広島市にこれだけの道外客を集めたことは、スポーツツーリズムの新たな可能性を示しています。
さらに、海外からの来場者は前年の約2倍に増加しています。東京や大阪と比べればインバウンドの基盤は弱い地域ですが、スタジアムが国際的な観光拠点となり得ることを裏付ける数字です。
平均滞在時間3時間超、リピーター率の高さ
エスコンは「試合を見るだけの場所」ではありません。球場内には温泉、サウナ、クラフトビール醸造所、地元食材を使ったレストラン、さらには宿泊可能なホテルまで整備されています。
調査によれば、来場者の平均滞在時間は3時間超であり、通常のプロ野球観戦(平均2時間半程度)より長く滞在しています。また、再来場意向は5点満点中4.6点(前年比+ 6%)と非常に高い水準です。
経済波及効果:札幌から北広島へのシフト
北海道経済界は、エスコンフィールド北海道を中心とするFビレッジにより、年間数百億円規模の経済効果を期待しています。関西大学・宮本勝浩名誉教授の試算では、開業初年度だけで北海道全体に約1,600億円超、北広島市単体でも約500億円の波及効果があったとされます。来場者数は346万人を突破し、そのうち4割は野球観戦以外の目的で訪れるなど、観光や飲食を含め地域経済を大きく押し上げています。
札幌ドームを離れたことで札幌市内の一部経済はマイナス影響を受けましたが、北広島市は新しい観光資源を獲得しました。経済の重心が札幌から郊外都市にシフトしたことは、地方創生の観点から注目すべき動きです。
光と影 ― 数字から見える課題
とはいえ、本プロジェクトには課題も見逃せません。総事業費は約600億円にのぼり、その資金は借入と自己資本をおおむね2対1の割合で賄われました。これは民間主導による大規模投資である一方、インフラ整備や将来の回収リスクには公的関与も不可欠な構造です。観客動員の伸び悩みが続けば、巨額投資の収益回収は難しいのが現実的なリスクとして浮上します。
アクセス面でも依然として課題が残ります。2024年の来場者数は418万人超(前年比約21%増)と成功裏に推移した一方で、試合終了後にはシャトルバス乗り場で1時間半以上待つケースも発生するなど、混雑対策が追いついていない場面も見受けられます。JR北広島駅でもホームの停止位置変更や入場規制、臨時列車の増発など多様な対策が講じられてはいるものの、ターミナルとしての受け入れ能力には限界があるとの見方もあります。
エスコンが示す地方創生モデル
エスコンの数字を整理すると次の通りです。
・年間来場者数:418万人
・道外来場者:102万人
・海外来場者:前年比2倍
・平均滞在時間:3時間超
・再来場意向:4.6/5
・北広島市宿泊者数:前年比30%増
これらの数字は、スタジアムが「観戦施設」にとどまらず、観光・健康・交流を包含する都市機能の一部となり得ることを示しています。
地方創生において、スポーツ施設は単なるハコモノではなく、「人流を生むエンジン」であり「都市間競争の武器」と言えます。その典型例が、北広島市のエスコンフィールド北海道なのです。
1,000億円の賭け ― 長崎スタジアムシティ

長崎市で進む「長崎スタジアムシティ」構想は、地元企業ジャパネットホールディングスが主導する総事業費約1,000億円規模の巨大プロジェクトです。
この計画では、Jリーグ・V・ファーレン長崎の新本拠地スタジアムを核に、アリーナ、ホテル、オフィス、商業施設などを一体整備し、地域に新しい「都市拠点」を形成することが目指されています。単なるスポーツ施設の整備にとどまらず、「スポーツ×観光×商業×暮らし」を組み合わせた複合型開発が大きな特徴です。
想定される集客と経済効果
長崎スタジアムシティが注目されるのは、その集客規模と経済効果の大きさです。
・年間集客数:約850万人を想定
・開業後1年間での経済効果:約963億円
・雇用創出:約13,000人
長崎市の人口は約39万人です。これに対し、850万人という数字は人口の20倍を超える集客規模であり、全国的に見ても地方都市における前例はほとんどありません。
また、経済効果963億円という規模は、単なる地域イベントではなく、「都市全体の産業構造を押し上げる」レベルのインパクトです。
官民連携の新しい形
このプロジェクトの特徴は、自治体ではなく地元大手企業であるジャパネットが主導し、行政と連携して進めている点にあります。
従来、スタジアム建設といえば「自治体が主導し、税金で整備、赤字は市民負担」という構図が多く見られました。札幌ドームが典型例です。しかし長崎では、民間主導の官民連携(PPP)モデルが採用され、リスク分散と収益性確保が重視されています。
その意味で長崎スタジアムシティは、「ハコモノ行政」からの決別を示す全国的な先例となり得るのです。
地域文化との融合
長崎は歴史的に異文化が交差してきた港町として、豊かな観光資源に恵まれています。ジャパネットグループが手がけた「スタジアムシティ」構想では、スポーツ観戦に加えて、豪華なスタジアムビューのホテルやジップライン、屋上足湯、キッズパークなど、多彩な体験型施設を一体化しています。観戦を軸に、長崎ならではの観光とエンターテインメントが同時に楽しめる、まさに“体験型観光”の新たな拠点といえるでしょう。
課題:巨額投資の持続性
もちろん課題も存在します。総事業費1,000億円という数字は、地方都市にとって破格です。事業主体がジャパネットであるとはいえ、民間企業の投資には回収が不可欠であり、観客動員やテナント稼働率が計画通りに推移しなければ、収益性の確保は難しくなります。
地方都市としての構造的課題も無視できません。最新の人口推計によれば、長崎県全体の人口は2025年ごろに約125万人を記録した後、2030年には約117万〜119万人へとさらに減少し、地域の消費基盤は縮小が見込まれます。長崎市でも2025年の約38万人から2030年には約36万人台へ人口減少が進むとされています。この傾向を踏まえると、スタジアムシティのような大型プロジェクトでは、地域住民のみならず、インバウンド需要や広域からの集客をいかに取り込むかが成功の鍵となりそうです。
国際イベント誘致の可能性
長崎スタジアムシティは、国際大会の開催実績を持ち、大型イベントの誘致を後押しする補助制度も整備されており、国内外から幅広く活用される拠点として期待されています。さらに、国内外のサッカークラブと連携し、平和をテーマにした「PR (L)AY FOR PEACE」プロジェクトを展開するなど、国際的な視野を備えた施設でもあります。加えて、音楽や大道芸を楽しめる「エンターテイメントシティ長崎」も導入され、スタジアムの枠を超えた複合エンターテインメント拠点として注目を集めています。
長崎が描く「地方創生の未来像」
長崎スタジアムシティは、数字の面でも構造の面でも、日本の地方創生モデルの転換点を示しています。
・総事業費:1,000億円
・年間集客数:850万人
・経済効果:963億円
・雇用創出:13,000人
これらの数字は、地方都市であっても民間主導で世界水準の集客施設を整備できることを証明しています。
今後5年以内に、長崎スタジアムシティが「持続可能な成功モデル」となるか、それとも「過大投資のリスク」を露呈するかは、日本の地方創生にとって大きな試金石になるでしょう。
観光と黒字を両立 ― 沖縄アリーナ

沖縄市のコザ運動公園内にある「沖縄アリーナ」は、Bリーグ・琉球ゴールデンキングスの本拠地として利用される、沖縄県内最大規模の多目的アリーナです。2021年に開業し、バスケットボールの試合時には約8,000人、コンサートや大規模イベント時には最大約10,000人を収容できます。スポーツ観戦に加え、音楽ライブや展示会、国際会議など幅広いイベントに対応しており、従来の体育館型施設とは異なるエンターテインメント志向の設計が特徴です。大型ビジョンや演出設備を備え、NBAの試合やK-POPコンサートにも匹敵する迫力ある体験を提供できる空間として注目されています。
沖縄アリーナの収益構造と黒字運営
「沖縄アリーナ」の運営を担う沖縄アリーナ株式会社は、自治体からの指定管理料に依存しない独立採算経営を掲げ、第1期運営においては指定管理料を受け取らずに運営を行ったことが公表されています。
また、同社の決算公告によれば、
・第4期(2023年3月期):純利益 約1億1,734万円
・第5期(2024年3月期):純利益 約6,007万円
・第6期(2025年3月期):純利益 約6,468万円
と、いずれの期も黒字を確保しており、安定した収益性を示しています。
さらに、整備時に示された行政の試算では、事業収入と支出は年間およそ3.3億円で均衡し、年間約4,000万円の指定管理料で維持可能との見通しが示されていました。これらの数値は、公共アリーナの多くが赤字に苦しむ中で、沖縄アリーナが稀有な黒字運営モデルとなっていることを裏付けています。
観光との相乗効果
沖縄県は日本有数の観光地であり、観光需要はアリーナの集客とも密接に関わっています。令和5年(2023年)の入域観光客数は 約823万5,400人(前年比+ 44.5%) に達し、新型コロナ前の水準に近づきつつあります。
沖縄市では「スポーツツーリズム戦略」を策定し、琉球ゴールデンキングスをはじめとしたプロスポーツと観光を結びつける取り組みを進めています。試合観戦を目的に来沖した観光客が、滞在中に宿泊・飲食・交通・レジャーなどに波及的な消費を行うことが期待されており、アリーナ活用は地域観光振興の重要な柱のひとつと位置づけられています。
地域文化との融合
沖縄アリーナは単なるスポーツ施設にとどまらず、地域文化の発信拠点としての役割も果たしています。
■ 沖縄伝統芸能との融合
2025年6月、「エイサーナイト2025」がアリーナで初開催されました。地元青年会による迫力あるエイサーの演舞が間近に楽しめる舞台として、多世代が一堂に会する文化交流の場となりました。
■ 次世代育成の場としてのバスケクリニック
2024年7月、沖縄市スポーツ協会主催のクリニックには小学生55名、中学生75名が参加し、キングスのコーチや選手から直接指導を受けました。これに加えて、Jr.NBAプログラムに基づくクリニックも開催され、地域の子どもたちのスポーツ交流と技術向上に貢献しています。
こうした取り組みにより、沖縄アリーナはスポーツだけでなく、文化と世代をつなぐ交流拠点としての機能も担っています。
国際イベントとDX活用
沖縄アリーナは、2023年に開催された「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」において、日本国内の会場のひとつとして世界から注目を浴びました。
さらに、開業当初から売店やスイートルームなどにおいて、約80台の端末を用いた完全キャッシュレス決済(PayCAS)を実現。これにより、従来の現金取扱いに伴う運用リスクを低減しながら、利便性と業務効率を大きく向上させています。
課題:観光依存と持続性
沖縄アリーナの強みは、スポーツ施設の枠を超え、観光と連動した多目的活用にあります。しかし一方で、観光依存度の高さはリスク要因ともなり、パンデミックや航空便減便など外的要因で需要が大きく揺らぐ可能性は否定できません。
また、黒字運営を維持するためには、バスケットボールの試合だけでなく、コンサートや展示会、国際会議といった大型イベントを継続的に誘致することが不可欠です。沖縄市も「スポーツツーリズム」や「文化と観光の融合拠点」としてのアリーナ活用を掲げていますが、今後はどこまで戦略的に取り組めるかが持続性を左右する鍵となるでしょう。
まとめ
沖縄アリーナは、地方自治体の公共アリーナとしては珍しく黒字運営を続けています。バスケットボールの本拠地であると同時に、コンサートや国際大会の舞台としても活用され、観光と結びついた収益モデルを築いてきました。2023年には観光客が800万人を超え、スポーツと観光の相乗効果が地域経済を押し上げています。まさに「稼ぐインフラ」として、沖縄に新しい可能性を示している存在と言えます。
都市を巻き込む装置 ― 横浜スタジアム

横浜スタジアムは、プロ野球・横浜DeNAベイスターズの本拠地として長らく親しまれてきました。近年は観客席を約3万人から34,046席へ拡張するなど大規模なリニューアルを進め、関内地区の再開発とも連動しながら「都市型スタジアム」としての役割を拡大しています。
従来の球場が「試合を観て帰る」だけの施設だったのに対し、横浜では試合日を街全体のイベントに変える仕掛けを導入。スタジアムを核に周辺エリアまでにぎわいを広げ、都市全体を活性化させる装置として機能しています。
さらに2025年8月からは、メインスコアボードの大規模改修工事が始まり、2027年3月の完成を予定しています。改修後は横幅88メートル・高さ12メートルという、国内の屋外球場では最大規模のスコアボードが登場し、迫力ある演出やイベント対応が可能になります。
こうして横浜スタジアムは、単なる野球観戦の場を超えて、スポーツと都市文化をつなぐハブへと進化を続けています。
観客動員数の伸びと収益力
横浜DeNAベイスターズは球団経営改革とスタジアム改修により、観客動員数を飛躍的に伸ばしました。2012年の主催試合による観客数は約117万人でしたが、2019年には2,028,837人と、約74%の大幅増を記録しました。
コロナ禍による打撃を受けながらも、2023年には2,280,927人を動員し、1試合平均も32,126人と球団史上最高に。さらに2024年には2,358,312人を動員し、新たな動員記録を打ち立てています。
このような強い観客動員力は、安定的な収益基盤の確保にもつながっており、球団経営の好循環を支える重要な要素となっています。
街を巻き込む再開発と経済波及効果
横浜スタジアム周辺の関内・関外エリアでは、再開発プロジェクト「旧市庁舎街区活用事業」が進行中で、スタジアムと直結したホテル・商業・オフィス施設やライブビューイングアリーナなどが整備され、地域の回遊性を高める計画です。
DeNAは、チームの観客動線を街へ拡張する施策にも取り組んでおり、観戦後の送客を促進する飲食予約サービス「Neee」やイルミイベント「BALLPARK FANTASIA」など、街全体の賑わいを創出する試みを展開しています。
こうした活動は、スポーツを起点に街の活性化を目指す都市型スタジアムのあり方を体現しています。
都市型スタジアムの強み
横浜スタジアムの成功要因は、都市型スタジアムならではの強みにあります。
1.アクセス性:JR関内駅、みなとみらい線、日本大通り駅など、公共交通機関と密接に結びついている。
2.観光資源との近接:山下公園や中華街といった観光地が徒歩圏内にあり、観戦前後の観光回遊が可能。
3.街との一体感:スタジアムが「都市景観の一部」として存在し、観光ポスターや市民イベントの舞台にも活用されている。
横浜スタジアムは、試合観戦の場を超えて、横浜という都市そのものを象徴する存在となっているのです。
課題と展望
横浜の事例は都市型スタジアムの成功例とされますが、課題も残されています。
まず、都市中心部に立地するがゆえに、試合やイベント開催時には交通渋滞や混雑が発生し、周辺住民の生活環境への影響が懸念されています。
また、再開発の進展とともに地価や賃料が上昇し、個人経営の飲食店や小規模事業者の入れ替わりが激しくなっていることも報告されています。観客動員による消費拡大は地域経済に追い風となる一方で、家賃負担の増大は零細店舗にとって深刻な課題です。地元商店街では、大規模チェーンの進出に押されて撤退を余儀なくされる事例も見られ、地域文化の継承が揺らぎかねません。
さらに、横浜市としての直接的な投資負担は抑えられている一方で、1978年開場のスタジアムは今後ますます老朽化が進むと見込まれ、維持管理コストの増大は避けられません。こうしたコスト構造が、地域全体にどのような波及をもたらすかも注視が必要です。
それでも横浜スタジアムの事例は、「都市のど真ん中にあるスタジアムが、観光・経済を牽引し得る」というポジティブな側面を強く示しています。今後の課題は、にぎわい創出のメリットを活かしつつ、中小企業や商店街を含む地域コミュニティの持続性をどう守るかにあります。
今後の展望 ― 官民連携と地域文化の融合

今後の展望を読み解くキーワードは次の通りです。
官民連携(PPP)の広がり
長崎スタジアムシティの事例が示すように、民間主導による官民連携モデルは今後の全国的な潮流になると考えられます。自治体が単独で財政負担を背負う構図には限界が見えており、企業が投資リスクを引き受け、その見返りに収益機会を得る「PPP型」の仕組みこそ、スタジアム運営の持続性を高めるカギとなるでしょう。
地域文化との結びつき
スタジアムの魅力を経済効果だけにとどめず、地域文化と結びつける取り組みも広がっています。
・横浜では、商店街と連携したビアガーデンやクーポン企画が導入され、観客が街全体を回遊する仕組みが形成されています。
・沖縄では、泡盛や伝統芸能フェスなど地域固有の文化イベントとアリーナが融合し、観光振興と文化継承の両面で成果を上げています。
・北海道(Fビレッジ)では、地元農産物の直売や地域グルメを取り入れたイベントが展開され、食を通じて地域のブランド力を高めています。
これらは「観戦+食+祭り」を一体化した体験を生み出し、インバウンド観光にとっても強い訴求力を持っています。
デジタルと健康まちづくり
スタジアムは今や「地域DXの実験場」としても機能しています。
・エスコンフィールド北海道では、公式アプリを使ったチケットレス入場やモバイルオーダーが導入され、混雑緩和と快適な観戦体験を実現。
・沖縄アリーナでは、完全キャッシュレス決済が採用され、地域におけるキャッシュレス社会の先行モデルとなりました。
・その他、健康アプリと連動したウォーキングイベントなど、市民の健康増進とまちづくりを結びつける取り組みも始まりつつあります。
まとめ
官民連携による資金調達、地域文化との深い結びつき、そしてデジタル・健康施策の導入──これらの流れは、スタジアムを単なるスポーツ観戦施設から「都市の実験場」「地域アイデンティティの拠点」へと進化させています。スタジアムが地域に根差し、持続的に発展していくためには、これら三つの要素の融合が不可欠なのです。
5年後の未来像 ― 三つのシナリオ
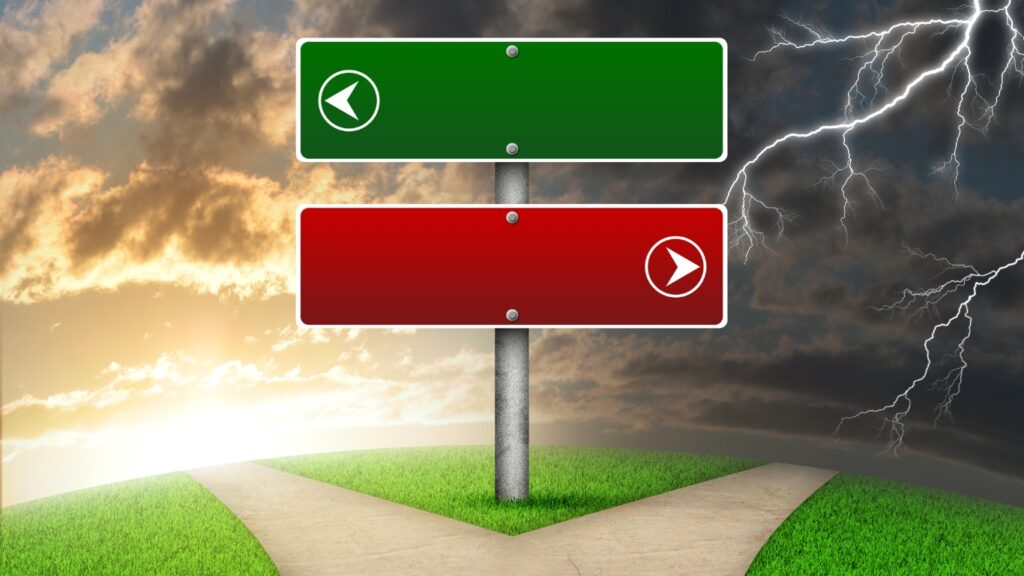
日本のスタジアムは、今後5年でどのような姿を描くのでしょうか。現状の実績と課題を踏まえると、次の三つのシナリオが考えられます。
| シナリオ | 内容 | 根拠・参考事例 |
| 楽観シナリオ | 各地のスタジアムが観光・生活を融合し、稼働率70%以上を維持。年間数百億円規模の経済効果を安定的に創出し、健康・交流の中核として機能する。 | 北海道(エスコンフィールド:来場418万人、稼働率高水準)、長崎スタジアムシティ(経済効果963億円試算) |
| 悲観シナリオ | 観客動員の鈍化や赤字運営が拡大。自治体が税金で補填し続け、「負の遺産」と批判される。 | 札幌ドームや地方アリーナの低稼働事例、赤字補填問題 |
| 現実的シナリオ | 成功と失敗が混在しつつ、官民連携や地域文化との融合によるノウハウが全国で蓄積される。 | 横浜(都市型・商店街連動)、沖縄(観光+伝統芸能)、北海道(農業・食文化)、長崎(PPPモデル) |
・楽観シナリオは、既存の成功例を全国に広げた場合に実現可能。
・悲観シナリオは、過去の「負の遺産」の再来。
・現実的シナリオは、成功と失敗を繰り返しながら「学習と進化」が進む姿。
つまり、日本のスタジアムは「光と影」を併せ持ちながら、地域と共に成長するか、それとも重荷となるかという分岐点に立っています。
結論 ― スタジアムは「建てる」から「活かす」へ
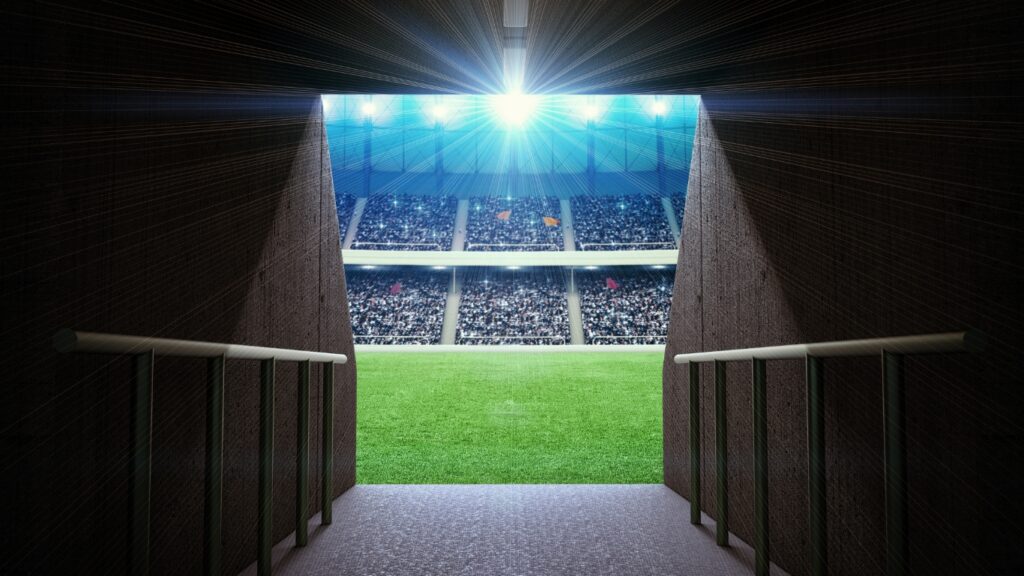
スポーツは地域に、経済の活性化と健康・交流の双方で寄与し得ます。しかし、その効果を左右するのは「建てること」そのものではなく、「どう活かすか」にあります。
北海道のエスコンフィールドは観光の核に、長崎スタジアムシティは都市再編の実験場に、沖縄アリーナは観光依存型の黒字モデルに、横浜スタジアムは都市全体を巻き込む装置に。それぞれが異なる形で、地方創生の未来像を示しています。
重要なのは、一過性の投資で終わらせず、市民に根づく仕組みをどう作るかです。スタジアムはスポーツの舞台であると同時に、都市と地域社会の「心臓部」ともなり得ます。それを「負の遺産」とするのか、「未来の資産」とするのかは、私たちの選択と運営の知恵にかかっています。
スタジアムは、地方創生の切り札にも、重荷にもなり得る。カギは「どう活かすか」。運営の工夫と市民の参加が未来を決めるのではないでしょうか。
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略