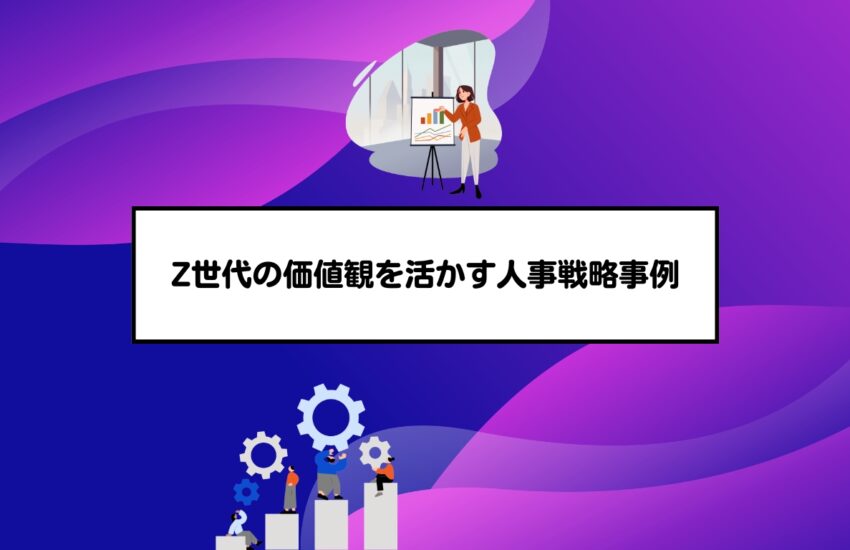経営環境の変化が加速する中、1990年代後半から2010年前半に生まれた「Z世代」が、職場の中心メンバーとして存在感を高めています。幼い頃からインターネットやスマートフォンに親しんできた彼らは、従来の世代とは異なる価値観や行動様式を持ち、企業に新たな期待と課題をもたらしています。
本記事では、まずZ世代の特徴や価値観を整理し、それを理解することで人事面にどのようなメリットがあるのかを概観します。そのうえで、日本国内の企業3社による最新の成功事例を紹介し、Z世代の強みを活かした採用・育成・定着のポイントを分析します。経営層の皆さまが自社の人材戦略をアップデートするための一助となれば幸いです。
Z世代の特長と価値観とは

デジタルネイティブであるZ世代は、生まれた時からスマートフォンやSNSが身近にありました。そのため、情報収集やコミュニケーションの方法が、それ以前の世代とは大きく異なります。
例えば、情報を探すときも「検索窓にキーワードを入力する」より、SNSで自分の感覚に合う情報を自然に受け取り、そこから必要な情報を見つける傾向があります。また、SNSでの「いいね」やコメントといった即時反応に慣れているため、職場で上司や同僚からこまめなフィードバックや承認が得られないと、不安を感じやすいとも言われます。
Z世代はさらに、多様性や共感、社会的意義を重視する価値観を持っています。インターネットを通じて世界中の情報や文化に触れてきたことで価値観が広がり、「なぜその仕事をするのか」「社会にどんな良い影響を与えるのか」といった理念やストーリーへの共感を大切にします。
企業選びでも、給与や安定性より「自分らしく働けるか」「成長できるか」といったやりがいや自己実現を優先する傾向があります。実際、ある調査ではZ世代の就活生が最も重視したのは「スキルアップ・成長機会」(56.0%)であり、給与や安定性は上位ではありませんでした。
また、ワークライフバランスへの意識も非常に高く、プライベートの時間を尊重しない職場には見切りをつけやすい傾向があります。日本のZ世代社員の96.7%がワークライフバランス重視を掲げており、業務都合の飲み会強制など旧来の慣習には強い拒否反応を示します。
こうした価値観から、Z世代は働き方や職場環境をシビアに見極めます。「上司に言われたから残業する」という従来型の働き方には馴染まず、「合わない環境ならすぐに離れる」ことにも抵抗がありません。事実、新卒入社者の3年以内離職率は約3割(34.9%)と高止まりしています。
「最近の若手はすぐ辞める」と嘆かれる背景には、価値観に合わない職場で無理に働き続けないという合理的な判断があります。裏を返せば、Z世代が満足できる職場環境を整えれば、高いエンゲージメントを発揮し、組織全体の活性化につながる可能性があるのです。
Z世代理解が企業の人事面にもたらす優位性

では、企業がZ世代の特徴や価値観を正しく理解し、適切に対応すると、人事面でどのようなメリットが得られるのでしょうか。鍵となるのは人材の確保・定着、そして能力発揮の最大化です。
まず採用面では、Z世代に響くメッセージやチャネルを活用することで、優秀な若手人材を効果的に惹きつけられます。彼らは企業が発信する情報に非常にシビアで、抽象的できれいごとばかりの採用広報には反応しません。
逆に、透明性が高く、共感できるリアルな情報発信は大きな武器となります。実際、多くの企業がSNSや動画で社員の本音や職場の実情を伝える採用マーケティングにシフトしており、成果を上げています。こうした発信ができる企業は、自社に合う人材を他社より先に獲得できるでしょう。
新人育成・定着の面では、Z世代の特性に合わせたアプローチが早期離職の防止と戦力化の加速につながります。たとえば「いつでも相談できる環境」があると、新入社員の不安は大きく軽減されます。
あるIT企業ではメンター制度導入後、新卒エンジニアの離職率が30%から10%に低下しました。これは、安心感の向上によってストレスが減り、企業へのエンゲージメントが高まったためです。また、別の企業では上司との1on1ミーティングを月1回以上実施した結果、若手社員が悩みを早期に相談できるようになり、離職率が大幅に下がりました。頻繁な対話やフィードバックは、離職防止だけでなく成長スピードの向上や職場定着にも効果的です。
さらに、Z世代はデジタルスキルや新しい感性において組織に大きな価値をもたらします。彼らが強みを発揮できる環境を整えることは、組織のイノベーション促進にもつながります。例えば、若手の声を経営に反映する仕組みを導入すれば、古い慣習にとらわれないアイデアや、IT活用による業務効率化など、次世代リーダーの芽を育てられます。Z世代を単なる指示待ちの部下ではなく、変革のパートナーとして位置づけることで、組織全体が新しい時代に適応しやすくなるのです。
このように、Z世代を理解し対応することは、採用力の強化・定着率の向上・組織革新力の向上といった多面的なメリットをもたらします。それでは具体的に、どのような企業がどのような施策で成果を上げているのか。次章では、日本企業3社の成功事例を詳しく見ていきます。
事例①: 富士通 – 「Gen Z Community」による若手主導の組織変革
富士通株式会社は、Z世代の力を社内変革に活かす先進的な取り組みを実施しました。
同社は2023年2月、若手社員が中心となり社内外に共感を広げるプロジェクト「Fujitsu Gen Z Community」を立ち上げました。目的は、デジタルネイティブで感性豊かなZ世代社員の視点とエネルギーを活用し、富士通のブランドイメージや企業文化を刷新することです。いわば、Z世代が主導する社内ベンチャー的チームによる文化改革の試みです。
主な取り組み事例
他企業との交流ワークショップ
富士通の全社DXプロジェクトと連携し、東京電力パワーグリッド社の若手社員と2日間の合同ワークショップを実施。自己紹介やブレインストーミング、社会課題の議論を通じて、企業の枠を越えたカジュアルな交流の場を創出しました。
学生エバンジェリストとの対談
学生ネットワーク団体が主催するアワードに協賛し、受賞大学生と富士通Z世代社員がパネルディスカッションを実施。柔軟で革新的な企業文化を語り合い、「若手が活躍できる富士通」というイメージを社外に発信しました。
大学とのコラボイベント
武蔵野大学アントレプレナーシップ学部と共同で「富士通を共感される企業にするには?」をテーマに学生と社員が議論。新たな施策案を次々と生み出しました。
成果と効果
このプロジェクトから学べるのは、Z世代に裁量と発信の場を与えることで、組織変革の起爆剤となるという点です。参加した若手社員は、自らのアイデアが経営に影響する手応えを得てエンゲージメントが高まり、社内に新しい風を吹き込みました。経営陣にとっても、Z世代ならではの発想や価値観を直に知る貴重な機会となり、トップダウンでは得られない洞察を得ることができました。
結果として富士通は、社内の風通しが改善され、若手人材の定着や採用ブランディングにも好影響をもたらしました。プロジェクト開始以降、学生から「革新的な社風」として注目される場面が増え、人材獲得競争での魅力も向上しています。
この事例は、特に年功序列が根強く若手の意見が通りにくい企業にとって、思い切った権限委譲が若手のモチベーションを飛躍的に高め、組織全体の活力源となり得る好例といえるでしょう。
事例②: メルカリ – 柔軟なオンボーディングと横のつながり支援で定着率向上
株式会社メルカリは、リモートワークが普及した環境下で、新人研修(オンボーディング)における柔軟性と一体感の両立を追求し、成果を上げています。
同社は「Your Choice」という制度により、日本全国どこでも働ける仕組みを導入しており、新入社員も勤務地を自由に選べます。このため新人研修は、国内外の参加者を想定したオンライン中心で実施。3ヶ月間の統一プログラムを提供し、研修内容はすべてドキュメント化して社内ポータルに集約。必要な情報にいつでもアクセスできる環境を整備しました。これは、デジタルネイティブなZ世代に適したオンデマンド型の情報共有であり、自ら調べて問題を解決できる仕組みになっています。
人とのつながりを補う工夫
メルカリは、単なるオンライン化ではコミュニケーション不足による不安が残ると考え、「メンターランチ制度」を導入しました。
新入社員(特にエンジニア職)には一人ずつシニアエンジニアがメンターとして付き、入社初週に業務上関係を築くべきメンバーを選び、メンター同伴でランチに招待します。
ランチ代は会社が負担し、部署を越えた横のつながりを促進。この制度は、他部署や他プロジェクトとの人脈が将来の問題解決に役立つため、エンジニア職を中心に特に好評を得ています。
対面での一体感醸成
2023年には、コロナ禍で中止していた入社時オリエンテーションの対面開催を復活。初日は東京本社で行い、経営陣による直接の歓迎メッセージやオフィス見学を実施しました。背景には、「同期の仲間意識を高めたい」「カルチャーを肌で感じてもらいたい」という狙いがあります。
成果と示唆
オンラインの効率性とオフラインの一体感を組み合わせたメルカリの取り組みは、Z世代が求める柔軟な働き方と帰属意識の両立に応えた好例です。
この事例が示しているのは、新人の不安を取り除き、自主性と人とのつながりを同時に支援することが、定着率向上の鍵であるという点です。
情報はオープンに共有し、質問しやすい雰囲気を整える。一方で、同期や先輩とのネットワークづくりを会社が積極的に後押しする──この包括的なアプローチによって、Z世代社員は組織に早く馴染み、「この会社で成長できそうだ」という安心感を得ます。その結果、早期離職が減少し、戦力化までの期間も短縮されるという好循環が生まれるのです。
事例③: 資生堂 – リバースメンタリングで世代間ギャップを突破
株式会社資生堂は、Z世代を含む若手社員の知見を経営層の学びに活かす「リバースメンタリング」を導入し、大きな成果を上げています。
リバースメンタリングとは、通常のメンター制度とは逆に若手社員が幹部や役員のメンター役を務める仕組みです。資生堂では、20〜30代の選抜若手社員が部長・役員クラスに対してITスキルや最新トレンド、若者の価値観を共有・指導する制度を導入しました。
制度導入の背景
資生堂がこの制度を始めたのは、
・社内デジタル化の加速
・世代間ギャップの解消
という経営課題を解決するためでした。市場変化に迅速に対応するには、経営層がデジタル技術や若年層の感性を理解する必要があります。しかし、従来のトップダウン文化では現場の新しい発想が経営に届きづらいという課題がありました。
具体的な取り組み
各部門長の推薦を受けた若手社員がメンターとなり、年間3〜6回の定期ミーティングを実施しました。そこで、
・SNSの効果的な活用方法のレクチャー
・他社の最新事例の紹介
・会社の課題に対する若手視点での提案
といった活動を行っています。
制度開始から数年で、このリバースメンタリングは部長級以上が必ず受講するプログラムへと発展。若手と経営層が定期的に対話することが、すっかり社内文化として根付いています。
効果と成果
若手側のメリット
幹部の意思決定プロセスに触れる貴重な機会となり、会社への信頼感や成長意欲が向上。提案が実際に採用される成功体験が、主体的な行動や将来のリーダー育成につながっています。
幹部側のメリット
新世代の発想や最新技術を学ぶことで固定観念が打破され、戦略立案に広い視野が生まれました。
結果として、資生堂全体でデジタル変革(DX)のスピードが加速し、市場の変化への適応力が強化されました。
事例の示唆
資生堂の事例は、経営トップ自らが「若手から学ぶ」姿勢を示した点で特筆に値します。世代や役職の垣根を越えてmentor/menteeの関係を築くことで、新たな連帯感が生まれ、「自分たちの会社を良くしていこう」という全世代共通の当事者意識が醸成されました。 Z世代だけでなく、全社員が主体的に動ける組織風土づくりのヒントが、このリバースメンタリングには詰まっています。
成功事例に見る共通点と今後の人事戦略への示唆

以上の3社の事例は、業種やアプローチこそ異なりますが、共通しているのは経営層がZ世代の特性を正しく理解し、それに応じた環境や仕組みを整えた結果、人と組織の双方で大きな成果を上げているという点です。
事例から読み取れる人事戦略上の示唆
1.Z世代の声を経営に活かす仕組みづくり
富士通のプロジェクトや資生堂のリバースメンタリングのように、若手が自由に意見を発信し、経営層と直接対話できる場は、Z世代のエンゲージメントを飛躍的に高めます。自分のアイデアが会社を動かす実感は、この世代にとって最大のモチベーションとなり、離職防止にも直結します。経営陣にとっても現場感覚を吸い上げられるため、意思決定の質が向上するwin-winの仕組みです。
2.フィードバックとサポートの徹底
メルカリのオンボーディングや各社のメンター制度に共通するのは、「放っておかない」こと。Z世代は、定期的な対話や相談相手の存在があってこそ安心して力を発揮できます。逆に、上司が忙しそうにして声をかけないだけで「迷惑かな」と遠慮し、孤立してしまうこともあります。成功企業は、1on1ミーティングやメンター制度を制度化し、些細な不安も早期に拾い上げて解消。その結果、早期戦力化と定着率向上を実現しています。
3.柔軟な働き方と一体感の両立
Z世代は時間や場所の自由を求めますが、孤立は望んでいません。メルカリのようにリモートワークを認めつつ、同期や先輩とのネットワーク形成を支援する、オンライン情報共有を充実させつつ節目には対面交流を設ける、といったハイブリッド戦略が効果的です。このバランスが、自律性と帰属意識を両立させ、企業文化へのエンゲージメントを高めます。
4.共感と価値観の発信
採用から定着まで一貫して重要なのは、企業が自社のビジョンや価値観を明確に示し、共感を得る努力を続けることです。Z世代は「何をするか」よりも「なぜそれをするのか」に心を動かされます。事例企業はいずれも、若手社員との対話やSNS発信などを通じて、ミッションやカルチャーを等身大の言葉で発信していました。
例えば、DMM.comは社内イベントや働き方をYouTubeで公開、ユニリーバ・ジャパンはInstagramで社員や社会課題への取り組みを発信し、透明性のあるブランドイメージを築いています。
Z世代対応は「特別扱い」ではなく普遍的な職場改善
経営層が意識すべきは、Z世代対応が全世代にとって働きやすい職場づくりにつながるという点です。柔軟な働き方や頻繁なフィードバックはミレニアル世代以上にも有益であり、心理的安全性の高い組織は全社員の能力発揮を促します。
結論

Z世代の強みや価値観を正しく理解し活かす企業は、人材獲得競争と組織力強化の両面で優位に立てます。今回の成功事例を参考に、人事施策をアップデートしてはいかがでしょうか。経営トップが次世代の声に耳を傾け、共に未来志向の組織づくりに取り組むことこそ、これからの持続的成長のカギです。