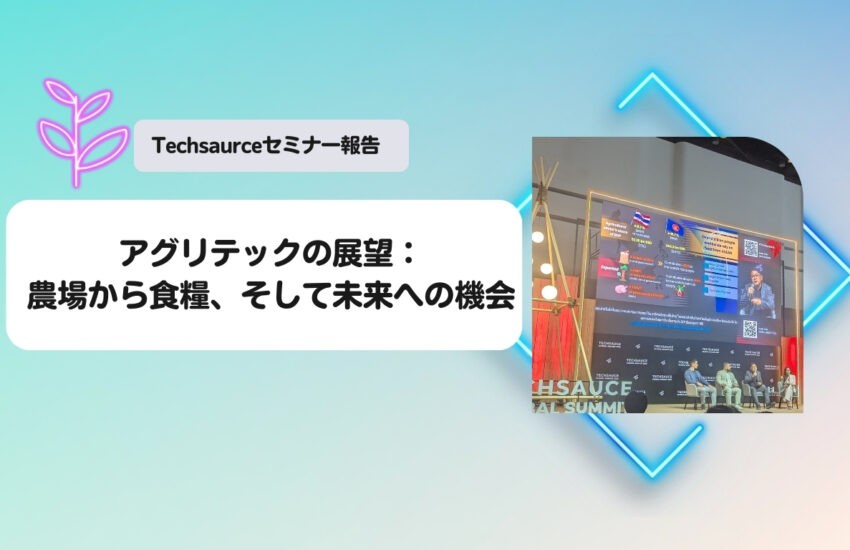2025年8月にバンコクで開催された「Techsauce Global Summit 2025」は、東南アジア最大級のテックカンファレンスとして20,000人を超える参加者を集めました。
今回のセッション「東南アジア農業とフードテック戦略」では、気候変動と食料安全保障に直面するこの地域において、技術革新と市場改革がどのように未来を切り拓くのかが議論されました。本記事では、その内容を整理し解説します。

登壇者プロフィール(セッション登壇者)
Serni Hakim(サーニ・ハキム)
Kök Ventures 共同創業者兼CEO。農業・フードテック分野で革新的なソリューションを推進し、持続可能な農業モデルの構築と技術導入による生産性向上を目指して活動。
Assoc. Prof. Sukhket Nakasathien(スケット・ナカサティエン准教授)
Bangkok Silicon Solutions 顧問、カセサート大学農学准教授。農学分野の専門家として、学術と産業界の橋渡し役を担い、タイ国内外での農業技術研究と実装に豊富な経験を持つ。
John Friedman(ジョン・フリードマン)
AgFunder アジアディレクター。アジア地域のアグリフード投資をリードし、スタートアップ支援や資本戦略の構築を通じて食の未来を支えるエコシステム形成に尽力。
Perada Supornpun(ペラダ・スーポンパン)
Taste Vision(Tasted Better)共同創業者兼CEO。消費者の嗜好や食文化に革新をもたらす製品開発を推進し、持続可能で美味しい食の提供をミッションとする。
はじめに
世界人口の増加と気候変動の影響が深刻化する中、安定的かつ持続可能な食料供給は国際的な重要課題となっています。
中でも、東南アジアは世界の食料供給量の約10%を担う「世界の食料庫」としての役割を果たしており、その動向はアフリカなど食料依存度の高い地域にも直結します。
本セミナー「Techsaurce」では、農業とフードテックを軸に、東南アジアの現状と課題、そして今後の成長戦略について、起業家、投資家、大学関係者などが議論を交わしました。
東南アジア農業の現状と課題
近年、農業のGDP寄与率はかつてより低下し、8〜9%程度にとどまっています。一方で、域内各国を合わせた食料供給力は世界全体の1割を超えており、その存在感は依然として大きい状況です。
しかし、高温化や異常気象、干ばつなど気候変動による生産不安定化が顕著になりつつあります。これらは国際的な食料安全保障にとって深刻な脅威であり、現状のままでは供給の継続性が危ぶまれます。特にアフリカ諸国など、東南アジアからの輸入依存度が高い地域にとっては死活問題となります。
官民連携(PPP)と大学の役割
こうした課題に対応するためには、官民および大学・研究機関の緊密な連携が欠かせません。
PPP(Public-Private Partnership)は単なるインフラ整備にとどまらず、農業技術や市場アクセス改善、農家の生活向上など多面的な協力を含む必要があります。
特に大学は、基礎研究と応用研究の橋渡し役として、最新の知見を現場に届ける役割を担うべきだという意見が多く聞かれました。
スタートアップ事例:タイ発女性起業家の挑戦
本セミナーでは、タイ発の女性起業家によるフードテック事例が紹介されました。
彼女のスタートアップは、低糖質・高たんぱく・高繊維の小麦粉製品や糖質・砂糖不使用のパンを開発しています。これらは健康志向と持続可能性を両立した商品として高く評価され、2020年には国際的な食品賞も受賞しています。
COVID-19期にはオンライン販売やデジタルマーケティングを強化し、ベトナム・香港・韓国など海外市場へ進出しました。
女性起業家によるアジア発の成功事例として注目を集めていますが、一方でフードテック業界全体に共通する課題として、「高価格による普及の壁」が指摘されました。
今後10年の有望分野
1. アグリ・バイオテクノロジー
気候変動下での農業生産を支える技術として、アグリ・バイオテクノロジーが有望視されています。
例えば、スウェーデン発のスタートアップは干ばつ耐性小麦の種子を開発し、インドをはじめとする南アジア市場に現地企業と連携して展開しています。
こうした事例は、地場の種子会社と海外の先端技術を組み合わせることで、新たな市場を切り開くモデルとなっています。
2. 農業マーケットプレイス
もう一つの成長分野は、サプライチェーン効率化を目的とした農業マーケットプレイス型プラットフォームです。
東南アジアでは、中間流通の非効率性が農家の収益性低下の要因となっており、これを解消することで市場全体の活性化が期待されます。
バイオテク企業とマーケットプレイスの連携により、改良種子や資材をより多くの農家へ届けることが可能になります。
投資環境と市場機会
世界的にベンチャーキャピタルの投資額は減少し、「冬の時代」とも呼ばれています。しかし、気候変動や食料インフレが進む中で、農業関連スタートアップへの需要はむしろ高まりつつあります。
市場機会を捉えるためには、既存のビジネスモデルに固執せず、環境変化に合わせて迅速に適応できる柔軟性が不可欠です。
化学から生物学への転換
農業技術の革新においては、化学肥料や化学農薬から脱却し、生物学的アプローチへと移行する動きが加速しています。これにより、環境負荷の軽減と人々の健康促進を両立できる可能性が高まります。
また、こうした技術はオーガニック市場の成長にも寄与し、プレミアム価格での販売を可能にするビジネス面での利点もあります。
技術融合型アプローチの必要性
単一の技術ではなく、バイオテクと農業オートメーションを統合し、相乗効果を発揮させる「技術融合型アプローチ」が注目されています。
既存の生産管理システムに耐性作物やバイオ資材を組み込み、効率化と品質向上を同時に達成する事例も出始めています。
生産施設のスマート化
高温や病害虫に強い品種が開発されても、それを安定的に生産できる施設がなければ意味がありません。温室や管理型農業施設など、生産インフラのスマート化は必須条件となります。
IoTやAIを活用した環境制御技術は、東南アジア各国でも導入が進みつつあり、気候変動下での安定供給を支える基盤となっています。
小規模農家への技術普及
東南アジアの食料生産の75%以上は小規模農家によって支えられています。しかし、先端技術は大規模農場向けに設計されることが多く、小規模農家への適用が進んでいません。
このギャップを埋めるためには、低コスト・スケーラブルなソリューションの設計と普及が必要であり、それが市場全体の底上げにつながります。
まとめ
Techsaurceセミナーでは、東南アジア農業の現状と課題、そして未来への戦略が多角的に提示されました。気候変動対応、バイオテクノロジーの活用、サプライチェーンの改革、小規模農家支援は、地域農業とフードテックの持続的成長を実現するための重要な柱です。
今後10年、この地域の農業は「持続可能性」と「競争力強化」の両立を目指し、技術革新と連携強化によって進化を続けていくと考えられます。