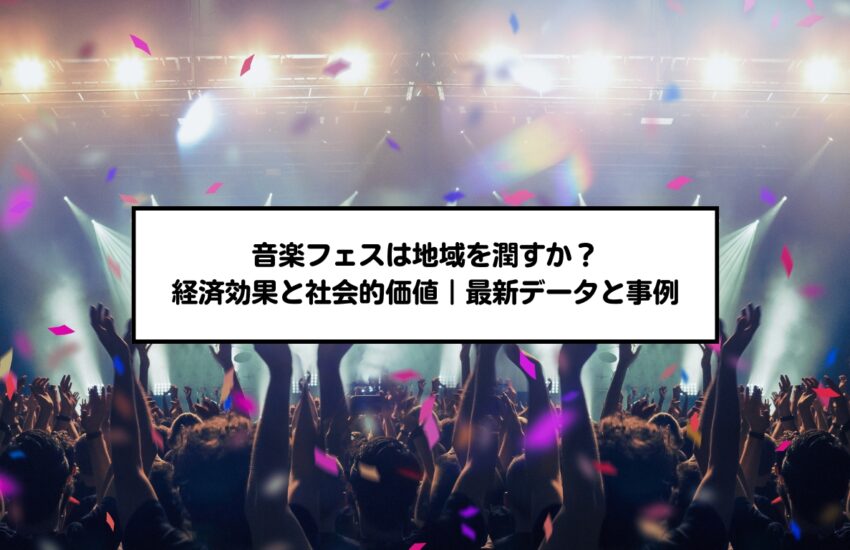2024年における音楽フェスティバル市場の規模は434億円と推計され、前年比で11.5%の成長を記録しました。動員数も前年から5.4%増加し、360万人に達するなど、2023年に続き市場は堅調に推移しています。新型コロナウイルスの影響から回復した2023年以降、音楽フェス市場は持続的な成長軌道に入ったと見られます。
音楽フェスは現在、音楽鑑賞の枠を超えた多機能イベントへと進化しています。地域経済への貢献、文化・観光資源との連携、さらには持続可能性への配慮など、社会的価値の高いプラットフォームとしての役割が拡大しています。
今後は、大規模フェスと地域密着型フェスという2つのモデルを軸に、経済効果と社会的インパクトの両面から、その戦略的意義を再評価することが求められるでしょう。
大規模と地域密着の“二つのモデル”が、これからの地方創生にどんな価値をもたらすのかを、経済効果と社会的インパクトの両面からひも解きます。
絶大な経済効果とブランド力:四大フェスの貢献

一般的に「三大フェス」と称されてきたフジロックフェスティバル(新潟県)、ライジングサンロックフェスティバル(北海道)、SUMMER SONIC(千葉県・大阪府)に加え、近年ではROCK IN JAPAN FESTIVAL(千葉県・茨城県)が加わり、「四大フェス」として位置づけられています。
これらの大規模フェスティバルはいずれも数万人から十数万人規模の集客力を誇り、開催地域に絶大な経済効果をもたらしています。
こうした大規模フェスは、地域のブランドイメージ向上にも寄与し、音楽をきっかけとした観光客の誘致、いわゆる「ミュージックツーリズム」の核となる存在です。
まずは、「フジロックフェスティバル」と「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」について、見ていきましょう。この2つのフェスは、日本の音楽フェス文化を牽引してきた両輪でありながら、そのアプローチと地域との関わり方は対照的です。
フジロックは「自然との共生」を軸に地域環境へも貢献する国際的なリゾート型フェスとして、ROCK IN JAPANは日本の音楽シーンの変遷を反映しながら開催地域と深く結びつき、時代に合わせて進化するフェスとして、それぞれが独自の方法で地域活性化に貢献しています。
1.フジロックフェスティバル (新潟県)
日本における野外ロックフェスティバルの草分け的存在であるフジロックフェスティバル(FRF)は、「自然と音楽の共生」という明確な理念を掲げ、新潟県湯沢町の苗場スキー場という広大な自然の中で開催されます。
スキーリゾート閑散期の救世主としての経済効果
フジロックが開催される7月下旬〜8月上旬は、スキーリゾート苗場・湯沢エリアにとって最大のオフシーズンです。この時期に国内外から10万人以上(2025年は、24日の前夜祭を含む4日間で、のべ12万2000人が来場)が訪れることで、地域の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿)、飲食店、小売店は年間で最も重要な書き入れ時を迎えます。
その経済波及効果は絶大で、過去の調査では200億円を超える規模と試算されたこともあり、地域経済のサイクルに不可欠なイベントとして完全に定着しています。
環境保全活動を通じた持続的な地域貢献
フジロックは「世界一クリーンなフェス」を目指し、参加者に徹底したゴミの分別やリサイクル活動を求めています。
さらに、地元NPOとの連携から始まった「フジロックの森プロジェクト」は、現在では湯沢町・新潟県・主催者である株式会社スマッシュが中心となり推進協議会を設立し、官民一体で展開されています。
会場周辺では、間伐・植樹・遊歩道整備といった森林保全活動を継続的に実施するとともに、森と親しめるエリアを整備し、一年を通じて人が集う交流・観光の拠点づくりを進めています。
また、地元の間伐材を活用した紙製品「フジロックペーパー」を製造し、売上の一部を森林整備に還元するなど、資源の循環利用を通じて地域経済と環境保全の両立を図っています。
こうした取り組みは、単なるイベント開催による一時的な消費促進にとどまらず、開催地の自然環境を維持・向上させるという、より持続可能で深みのある地域貢献の好例といえます。
「苗場」の国際的なブランド化
フジロックは海外からの評価も非常に高く、世界的な音楽メディアで「世界のベスト・フェスティバル」の一つに選出されることも少なくありません。
これにより、「苗場(Naeba)」の名は世界中の音楽ファンの知るところとなり、地域の国際的な知名度とブランドイメージを飛躍的に向上させました。音楽をきっかけに、日本の豊かな自然文化を世界に発信するショーケースの役割を担っています。
2.ROCK IN JAPAN FESTIVAL (千葉/茨城)
日本のアーティストがヘッドライナーを務めるフェスを」という想いから始まったROCK IN JAPAN FESTIVAL(RIJF)は、出演者をほぼ国内アーティストに絞りながら、日本最大級の動員数を誇るまでに成長しました。
2024年の記念開催では、千葉市と茨城県ひたちなか市の2会場で計10日間にわたり実施され、延べ20万人超の来場者を集めるなど、その規模は年々拡大を続けています。その歴史は、開催地との強い結びつきと、時代の変化への適応を象徴しています。
ひたちなか時代(〜2019)-「ロックの聖地」としての共存共栄
20年間にわたり開催された茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園では、RIJFは地域にとって夏の最大のイベントでした。
20万人以上が訪れることで、JR常磐線やひたちなか海浜鉄道、周辺の宿泊施設(特に水戸市)、飲食店に莫大な経済効果をもたらしました。
それ以上に重要だったのが、地元ボランティアの積極的な参加や、商店街を挙げての歓迎ムードなど、地域住民が「自分たちのフェス」として誇りを持ち、一体となってイベントを育ててきた点です。
RIJFはひたちなか市に「ロックの聖地」という強力なブランドイメージを与え、シビックプライドの醸成に大きく貢献しました。
蘇我時代(2022〜)- 都市型モデルへの進化
開催地を千葉市蘇我スポーツ公園に移してからは、都心から電車で1本というアクセスの良さを最大限に活かした「都市型フェス」へと進化しました。
これにより、首都圏からの日帰り参加者がさらに増加し、JR京葉線や会場周辺の商業施設に新たな経済効果を生み出しています。
ひたちなか時代のような宿泊を伴う広域的な効果とは質が異なりますが、より多くの人々が気軽に参加できるモデルを確立しました。
2拠点開催(2024)が示す地域との絆
2024年、ひたちなかでの開催が5年ぶりに復活し、蘇我との2拠点開催が実現しました。これは、開催地移転後も復活を望む地元の強い声に応えたものであり、RIJFとひたちなか市との間に築かれた20年間の深い絆を物語っています。
フェスティバルが単なる経済活動のツールではなく、地域にとっての文化的・精神的な資産であることを示す象徴的な出来事と言えるでしょう。
次にライジングサンロックフェスティバルとSUMMER SONICについて見ていきましょう。
3.ライジングサンロックフェスティバル (北海道)
北海道石狩市の特設会場で開催される「ライジングサンロックフェスティバル(RSR)」は、日本で初めて本格的に行われたオールナイト野外ロックフェスとして知られています。
同フェスの特徴は、北海道の広大な自然環境を会場設計や運営に取り入れている点にあります。2024年には2日間で延べ6万8,000人が来場し、全国から観客を集めました。
滞在型消費と広域観光への波及
RSRは、テントサイトを備えたキャンプイン型の音楽フェスとして開催されています。来場者の多くは通し券を利用して複数日にわたり滞在するため、飲食物やアウトドア用品の事前購入が促される傾向にあります。
また、道外からの参加者も一定数存在し、前後に道内を旅行する事例も確認されています。これにより、航空・鉄道・レンタカーの利用に加え、札幌市内を含む宿泊施設や飲食店など、石狩市を越えた地域にも経済効果が広がっています。
過去に実施された調査では、2018年開催時の経済波及効果が約102億円規模に達したと試算されています。内訳として、観光消費が約13億円、事前消費が約6億円に上り、会場内での飲食やグッズ購入などを含めた直接経済消費額は約48億円とされています。こうした数値からも、RSRが北海道全体の観光経済に一定の寄与を果たしていることが示されています。
北海道ブランドの発信拠点
RSRの飲食ブースでは、石狩や小樽の食材や地域料理を活用したメニューが多数提供されています。代表例として「石狩鮭醤油ラーメン」「石狩丼」「小樽横丁」の名物料理などが挙げられます。
こうした地元食文化の提供は、音楽体験とともにフェスの魅力を形成する要素となっており、北海道らしさを発信する手段として地域ブランドの向上にも寄与しています。
環境・社会活動との連携
RSRでは「ごみの13分別」に代表される環境対策が実施されています。特に「Earth Care」と呼ばれる活動では、分別案内やボランティアによる回収支援が行われ、参加者の協力を得ています。
この取り組みを契機に2001年に設立されたNPO法人ezorockは、その後、地域づくりや自然保護、関係人口創出などを目的とした活動を道内各地で展開しています。RSRは音楽イベントであると同時に、環境問題や地域課題に関する意識を高め、NPO活動の発展に寄与するプラットフォームとしての役割も果たしています。
4.SUMMER SONIC (千葉・大阪)
千葉のZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪の万博記念公園という二大都市圏で開催される「SUMMER SONIC(サマソニ)」は、海外のトップアーティストを多数招聘する国際的なラインナップと、都市部からのアクセスの良さを兼ね備えた「都市型フェス」の代表格です。
2024年8月17日(土)・18日(日)の2日間に開催された「SUMMER SONIC 2024」は、東京会場・大阪会場ともにソールドアウトとなり、ソニックマニアやミッドナイトを含めた総来場者数は25万8,000人に達しました。
都市機能への直接的な経済効果
郊外型フェスとは異なり、サマソニの参加者は会場周辺の既存の都市インフラをフル活用します。これにより、開催期間中は幕張エリア(千葉)や吹田・大阪市内のホテル、飲食店、商業施設に莫大な直接的経済効果をもたらします。
特に、会場である幕張メッセのような大規模コンベンション施設にとっては、施設の稼働率を高める重要なイベントとなっています。
国際的な都市ブランドの向上
世界的に著名なアーティストが出演することは、開催都市である千葉と大阪の国際的な知名度を大きく向上させます。
近年、文化庁が主導するプロジェクト“MUSIC LOVES ART(MICUSRAT)”では、音楽と現代アートの融合がサマーソニック会場およびその周辺で展開されています。これは、日本を文化芸術の国際的な発信拠点とするための取組の一つであり、都市の魅力を高め、インバウンド観光客を呼び込む可能性を持つ要素です。
アクセスの良さと幅広い参加者層
鉄道などの公共交通機関で容易にアクセスできるため、日帰りでの参加や、仕事帰りに立ち寄ることも可能です。これにより、キャンプや長距離移動が難しい層も気軽に参加でき、幅広い層の音楽ファンを取り込むことができます。
地域との共存共栄:多様化する地方発フェスの貢献
市場が拡大する中で、四大フェス以外にも、独自の魅力で地域活性化に貢献するフェスが全国で増加傾向にあります。これらのフェスは、経済効果だけでなく、地域の文化発信、コミュニティの醸成、そして地域への誇りを育むといった、多角的で持続可能な価値を創出しています。その代表例が、滋賀県で開催される「イナズマロックフェス」です。
5.イナズマロックフェス(滋賀県)
アーティストの西川貴教氏が発起人となり、「琵琶湖の環境保全と地域振興」をテーマに掲げるこのフェスは、当初から地域活性化を前面に打ち出しているのが特徴です。
地元の自治体や企業と連携し、滋賀県の観光や文化を広く発信する取り組みを継続してきました。
最新動向(2024〜2025年)
直近の2024年開催では、2日間で95,000人を動員し、出演アーティスト・パフォーマーは94組にのぼりました。また、フェスの収益の一部と合わせて約265万円が滋賀県に寄付され、琵琶湖の水質保全などの環境保全活動に充てられています。
そして2025年には、これまで行われてきた地域連携に加え、滋賀県と草津市のふるさと納税返礼品としてフェスチケットを導入する新しい仕組みがスタート。
来場者はチケット購入を通じて直接地域に貢献でき、自治体の財源確保や地域経済の活性化を後押しするモデルケースとなっています。
環境
イナズマロックフェスは、琵琶湖のカーボンクレジットを活用してCO₂排出量を相殺するなど、環境負荷を軽減する具体的な取り組みを続けています。自然環境を守りながら開催されるフェスとして、地域の象徴である琵琶湖との共存を大切にしています。
観光
フェス会場内の「おいで~な滋賀」体感フェアでは、観光パンフレットやPR動画の提供、陶芸や史跡巡りといった体験ブースを通じて、滋賀の観光資源を来場者に直接体感してもらう仕組みが整えられています。
さらに、西川氏自身が「イナズマをきっかけに滋賀を何度も訪れてほしい」と発信しており、フェスを契機に地域への再訪や周遊を促す意図が明確に示されています。
文化
地元食材を使ったフードブースや地域アーティストの出演など、音楽と並行して「滋賀ならではの文化」を発信する場にもなっています。
こうした取り組みにより、フェスは地域文化のショーケースとして機能し、土地固有の魅力を広める役割を果たしています。
コミュニティと経済
運営には地元住民がボランティアとして参加し、シビックプライドを高めるきっかけとなっています。
さらに前述しましたが、2025年からは、ふるさと納税返礼品としてチケットを提供する新しい取り組みが始まり、音楽イベントを通じて自治体の財源確保と経済活性化に直結する仕組みが導入されました。
結論
イナズマロックフェスは、環境・観光・文化・コミュニティ(経済)の4側面から地域と共生するフェスとして進化を続けています。2024年の動員実績や寄付活動、2025年からのふるさと納税活用など、単なる音楽イベントにとどまらず、地域と一体になって成長してきた「地域貢献型フェス」の好例と言えるでしょう。
6.京都大作戦 (京都府宇治市)
京都府出身のロックバンド10-FEETが主催する「京都大作戦」は、アーティストの地元愛が地域を動かす代表例です。
地域との一体感
毎年約2万人を動員するこのフェスは、宇治市の夏の風物詩として定着しています。地元商店街との連携も深く、ポスター掲示やコラボグッズの販売などを通じて、街全体でフェスを盛り上げています。
観光誘致への貢献
フェス参加者が「聖地巡礼」として宇治市の観光名所を訪れることも多く、新たな観光需要を創出しています。10-FEET自身も行政から「おこしやす大使」に任命されるなど、地域振興の重要な担い手となっています。
物語性の共有
2007年の第1回が台風で中止になった「幻の1回目」から始まり、アーティストとファン、そして地域が一体となってフェスを育ててきた物語性が、参加者に強い愛着を抱かせています。
舞台名に込められた地域文化
「源氏の舞台」「牛若の舞台」「鞍馬の間」といったステージ名は、京都の歴史や物語に由来します。観客は音楽を楽しみながら自然に京都文化に触れ、観光や学びのきっかけを得られます。
これは地域資産を“かっこよく”若者に伝える仕組みとしても価値があります。
環境と共生する仕組み
京都大作戦では「ゴミゼロフェス」を目指し、環境と共生するための仕組みづくりに力を入れています。リユースカップの導入やエコステーションでの資源回収を行うだけでなく、ファンや出演者が一体となって清掃活動に取り組む習慣も定着しています。こうした取り組みは、地域住民との共生を可能にし、会場の自然環境を守る大切な地域貢献活動となっています。
災害支援や社会貢献
2018年の豪雨で中止になった際には、チャリティー・レプリカ万能札を販売し、収益を被災地へ寄託。主催者自らが現地に赴き支援活動を行うなど、音楽フェスを超えて地域・社会への貢献を果たしています。
まとめ
京都大作戦は、
・文化発信(音楽×京都の歴史)
・観光・経済効果
・環境保全と地域共生
・災害復興支援
という多面的な地域貢献を実現するフェスです。単なる音楽イベントにとどまらず、「音楽を通じた地方創生モデル」として全国から注目される存在といえるでしょう。
7. ARABAKI ROCK FEST. (宮城県川崎町)
「ARABAKI ROCK FEST.」は、毎年4月下旬に宮城県川崎町のみちのく公園北地区「エコキャンプみちのく」で開催される、東北最大級の野外音楽フェスです。
2001年の初開催から、“東北の春の風物詩”として親しまれ、2025年には記念すべき25周年を迎えました。
名称の由来は、かつて東北地方に存在したとされる「荒吐族(あらはばきぞく)」であり、フェス全体に東北の尊厳と誇りを称える精神が息づいています。
ステージ名も「MICHINOKU」「TSUGARU」「HANAGASA」など、東北6県の文化や伝統にちなんで名付けられ、地域に根差した世界観が貫かれています。
2025年開催(25周年)のハイライト
◎ 来場者数と規模
・開催日程:2025年4月27日(土)・28日(日)
・来場者数:2日間合計で約47,000人
・出演アーティスト数:およそ120組(過去最多級)
節目の年にふさわしく、全国から多くの音楽ファンが来場し、春の東北が音楽一色に染まりました。
注目の出演アーティストと演出
2025年のARABAKI ROCK FEST.25は、世代やジャンルを超えた多彩なラインナップで話題を集めました。
東京スカパラダイスオーケストラといったベテラン勢が圧巻のステージを披露する一方、マカロニえんぴつや羊文学、NEEなど新世代の人気バンドが若年層を中心に熱狂を巻き起こしました。
さらに、出演者同士のセッション企画も行われ、世代やスタイルを超えたコラボレーションが実現。東北ゆかりのアーティストも加わり、地域とのつながりを感じさせる場面も見られました。
加えて、地元・宮城県川崎町からは川崎中学校吹奏楽部が「常連アーティスト」として登場。昨年の10-FEETとの共演でも話題を呼んだ彼らは、今年もフレッシュな演奏と地域に根ざした活動で、多くの来場者に感動を届けました。
地域連携と経済効果
◎ 地域とのつながり
ARABAKI ROCK FEST.は、地域経済や文化振興にも一定の役割を果たしています。
会場内には地元の飲食ブースが多数出店し、来場者と地域の食文化が触れ合う場となりました。さらに、仙台市内や近郊の宿泊施設を利用する観客も多く、公式シャトルバスによるアクセス手段とあわせて、地域全体がフェスを支える仕組みが整っています。
また、フェス運営を支えるボランティア活動には、地元の高校生を含む学生や若者も参加しており、環境対策や会場運営を通じて地域社会とのつながりを実感できる機会となっています。
総括:フェスの未来と東北の希望
災害やパンデミックを乗り越えた地域の誇りと、次世代への継承の場として、今後も大きな存在感を持ち続けるでしょう。
8. OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL (秋田県男鹿市)
秋田県男鹿市で毎年開催されている「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL」は、今や東北を代表する夏フェスのひとつとして知られています。
その始まりは2007年。「地元・男鹿を元気にしたい」という有志たちの想いから、文化会館ホールで開かれたプレイベントが原点でした。初開催の来場者数はおよそ400人という小さな規模でしたが、その情熱は確かに地元の心を動かし、年々規模を拡大していきました。
地域活性化の手段としての音楽フェス
このフェスは、地元に暮らす人々にとっての「誇り」や「話題の中心」となることを目指し、観光誘致や地域経済への貢献も視野に入れて企画されています。
実際、開催期間中には県内外から多くの観客が男鹿市を訪れ、宿泊・飲食・交通といった地域産業にも好影響を与えています。さらに、地元の若者がボランティアや出演を通じてイベントに関わることで、地域への関心と愛着が育まれていきます。
フェスの発展と来場者数の推移
2010年に本格的な屋外フェスとしてスタートした「VOL.1」以降、イベントは3日間開催へと拡張。2014年以降は運営の安定を考慮し2日間開催へと移行しましたが、動員数は着実に増え、現在では2日間で約15,000人が訪れる一大イベントに成長しています。
行政や地元企業とも連携を深め、男鹿市の観光・地域戦略とも親和性の高い取り組みとして定着しています。
継続する力と地元への定着
イベントの継続を支えているのは、何よりも地元の人々の存在です。ボランティアスタッフや地域住民の積極的な関わりが、フェスの安定した運営を可能にしています。
さらに、地元高校生のボランティア参加や秋田ゆかりのアーティストの出演によって、フェスは地域に根ざした催しとして発展してきました。これは全国からアーティストや観客を呼び込むだけではなく、地域内からも力を引き出す仕組みを持つ「地域参加型フェス」として注目されています。
男鹿の魅力発信と全国への波及効果
フェスは、男鹿半島の自然や食、そして伝統文化「ナマハゲ」とも連動しています。名前に“NAMAHAGE”を冠することで、地域固有の文化を全国へ強く印象づけ、都市部の来場者にとっては「秋田・男鹿」を知るきっかけにもなっています。
また、開催期間中は観光キャンペーンとの連動も行われ、男鹿の魅力が広く発信されています。
地域発フェスが示す「続ける力」
OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVALは、音楽と地域が融合しながら成長してきた好例です。
外部からの観客を迎えつつも、地元の人たちとともに「毎年の恒例行事」として築かれてきたこのフェスは、地域振興のモデルとして他の地方自治体や地域イベントにも示唆を与えています。
9.ジゴロック (大分県)
ジゴロック~大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL~は、大分県発の新たな大型野外フェスとして、地域経済に貢献しています。継続開催に向けて地域企業との連携を模索するなど、地方発フェスの挑戦を象徴する事例です。
発起人と成長の歩み
大分県出身のダイノジ・大谷ノブ彦氏が発起人となり始まったこのフェスは、初年度から成功を収め、2年目にはさらに動員を伸ばしました。地域に根付く新たな大型フェスとして、着実に成長を遂げていることがうかがえます。
大分の魅力を凝縮した「地獄極楽」という唯一無二のコンセプト
ジゴロックの最大の魅力は、その名の通り「地獄」と「極楽」という、大分県、特に別府温泉の観光資源から着想を得たユニークなコンセプトです。
地獄(ROCK): 激しいロックサウンドや熱狂的なライブパフォーマンスを、別府名物の「地獄めぐり」の熱気や荒々しさに例えています。これがフェスの核となる音楽体験です。
極楽(POP/FOOD/CULTURE): 一方で、心地よいポップミュージックや、豊かな自然、そして何よりも「おんせん県おおいた」が誇る美味しいグルメや温泉文化を「極楽」として表現しています。会場には地元の食材を使ったフードブースが多数出店し、音楽と共に大分の食文化を存分に楽しむことができます。
このように、ジゴロックは「音楽を通じて大分の魅力を丸ごと体験できる祝祭空間」となっています。
世代とジャンルを超える、ボーダーレスなラインナップ
発起人であるダイノジ・大谷ノブ彦氏の「面白いものは全部見せたい」という想いが反映された、非常に多彩でボーダーレスなアーティストラインナップも大きな魅力です。
多様なジャンル: ゴリゴリのロックバンドから、ポップス、アイドル、ヒップホップ、さらにはDJまで、特定のジャンルに偏らない多様なアーティストが出演します。
世代を超えたブッキング: 2025年には伝説的な歌姫・中森明菜さんが野外フェスに初参加するという歴史的な出来事が大きな話題となりました。このように、ベテランから今をときめく若手まで、世代を超えて楽しめるラインナップが組まれています。
新しい出会いの創出: この多様性により、普段は聴かないジャンルの音楽に触れる機会が生まれ、参加者にとって新たな音楽との出会いの場となっています。
海風が心地よい、開放的なロケーション
会場である大分スポーツ公園は海に面しており、非常に開放的で心地よいロケーションです。
快適なフェス体験: 都心から少し離れた広大な公園で、潮風を感じながら音楽を楽しむことができます。都市型フェスのような窮屈さが少なく、ゆったりとした雰囲気の中で過ごせるのも魅力です。
観光との連携: 大分市内からのアクセスも良く、フェス参加の前後に別府や湯布院といった県内有数の観光地に足を運びやすいのもポイントです。
「大分を盛り上げたい」という地元愛から生まれた熱気
ジゴロックは、大分県佐伯市出身のお笑いコンビ・ダイノジの大谷氏が「音楽で地元大分に恩返しをしたい」という強い想いから立ち上げたフェスです。
地域主導の熱量: この地元愛に共感したアーティストや地元企業、そして多くの観客が集まることで、会場全体が温かい一体感とポジティブなエネルギーに満ちています。
地域経済への貢献: 初開催から17,000人以上、2年目には約19,000人を動員し、大分県に新たな大規模イベントとして定着しつつあります。これは、宿泊、交通、飲食など、地域経済に大きなインパクトを与える存在です。
まとめ
「ジゴロック」は、大分ならではのユニークなコンセプトを軸に、世代やジャンルを超えた多様な音楽、開放的なロケーション、そして何よりも地元を愛する熱い想いが結集した、新しい時代の地域密着型フェスです。始まったばかりでありながら、そのポテンシャルは非常に高く、今後九州を代表するフェスへと成長していくことが大いに期待されています。
10.おぼろっく (福井県)
北陸新幹線敦賀開業を契機に、継続的なにぎわい創出を目指して官民連携で立ち上げられたのが音楽フェス「おぼろっく」です。名産の「おぼろ昆布」と「ロック」を掛け合わせた名称には、地域の魅力を発信する意図が込められています。
2024年初開催の来場者数
「おぼろっく2024」は、福井県敦賀市で初めて開催された大規模音楽フェスで、初日(2024年9月14日)には主催者発表で約5,000人の音楽ファンが来場しました。
主催と今後の展望
このイベントは、市内の官民団体で構成する実行委員会が主催したもので、地域をあげての取り組みとして位置づけられています。
実行委員長は「来年以降さらにパワーアップし、5年後には1日1万人規模を目指したい」と語っており、今後の成長が期待されるフェスです。
港町・敦賀の風情を感じる、開放的なロケーション
会場は、敦賀港に面した金ヶ崎緑地です。ここは、歴史的な赤レンガ倉庫や人道の港ミュージアムに隣接する、敦賀の歴史と港の風情を象徴する場所です。
・海風と音楽の融合: 潮風を感じながら、広々とした芝生の上で音楽を楽しめる開放的な空間は、都市型フェスや山間部のフェスとは全く異なる魅力があります。
・観光との親和性: 会場周辺には観光スポットが点在しており、フェスの前後に敦賀の街を散策する楽しみもあります。フェス体験と街歩きをシームレスに繋げられるロケーションです。
初開催とは思えない、多彩なアーティストラインナップ
初開催ながら、幅広い世代が楽しめる多彩なアーティストを招聘したことも大きな魅力です。ロックバンドだけでなく、ポップスやヒップホップなど、多様なジャンルのアーティストが出演し、多くの音楽ファンを惹きつけました。これにより、特定のファン層だけでなく、家族連れやカップルなど、様々な人々が楽しめるイベントとなっています。
地域グルメが集結する「食」の楽しみ
会場には、敦賀をはじめとする福井県内のグルメを楽しめるフードブースが多数出店しました。音楽と共に、その土地ならではの美味しいものを味わえるのは、地方開催フェスの醍醐味です。「おぼろ昆布」を使ったメニューなど、フェスのコンセプトに合わせた食の楽しみも提供されました。
まとめ
「おぼろっく」は、新幹線開業という大きな追い風を捉え、「おぼろ昆布」というユニークな地域資源を旗印に、官民一体となって敦賀の未来を創っていこうという熱い想いが詰まったフェスティバルです。
港町の心地よいロケーションで、多彩な音楽と地元の食を楽しむ。始まったばかりのこのフェスは、敦賀の新たな魅力となり、これから大きく成長していく可能性に満ちています。
音楽フェス比較一覧表
来場者数や特徴を比較し、来場者数順に表にまとめました。
注目の音楽フェス比較表(来場者数順)
| フェス名 | 主な開催地 | 最新来場者数 | 期間・開催形態 | モデル | 特徴(要点) |
| SUMMER SONIC(サマソニ) | 千葉(幕張)・大阪 | 258,000人(2024年/東京・大阪合計、ソニックマニア含む) | 都市型(スタジアム&展示場) | 都市型・国際フェス | 世界的アーティスト招聘/都市インフラ活用/インバウンド効果・文化庁連携 |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL(RIJF) | 千葉市・茨城県ひたちなか市 | 200,000人超(2024年/2会場10日間のべ) | 都市型+広域(2拠点) | 大規模・都市型 | 国内アーティスト中心/地域との強い絆/2025年から9月開催へ気候適応 |
| フジロックフェスティバル(FRF) | 新潟県湯沢町・苗場 | 122,000人(2025年/4日間のべ) | 夏・滞在型 | リゾート型・環境共生 | オフシーズン需要創出/森林保全・リサイクル活動/国際的評価で苗場ブランド化 |
| イナズマロックフェス | 滋賀県(琵琶湖岸) | 95,000人(2024年/2日間) | 地域密着・屋外 | 地域貢献型 | 収益の一部寄付(環境保全)/2025年からふるさと納税返礼チケット導入/CO₂削減・観光PR |
| RISING SUN ROCK FESTIVAL(RSR) | 北海道石狩市 | 68,000人(2024年/2日間) | オールナイト・キャンプイン型 | 滞在型・広域波及 | 北海道食・フェス飯の発信/「ごみ13分別」やNPO活動の拠点化/フェスツーリズムで広域観光へ波及 |
| ARABAKI ROCK FEST. | 宮城県川崎町 | 47,000人(2025年/2日間) | 春(4月下旬) | 地域文化型 | 東北文化を体現/地元ボランティア参画/地元食と宿泊需要に波及/25周年で最多級出演 |
| 京都大作戦 | 京都府宇治市 | 20,000人(毎年) | 夏・野外 | 地元アーティスト主催 | 京都文化由来のステージ名/「ゴミゼロ」運営/商店街・観光連携/災害チャリティ活動 |
| ジゴロック(大分“地獄極楽”) | 大分県(大分スポーツ公園) | 19,000人(2025年/2日間)/17,000人超(2024年) | 野外・海沿いロケーション | 新興・地域密着 | 「地獄×極楽」コンセプト/ジャンル横断ラインナップ/観光との連携/地元愛で継続発展 |
| OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL | 秋田県男鹿市 | 15,000人(直近/2日間) | 夏・野外 | 地域参加型 | 「ナマハゲ」ブランドで全国発信/観光キャンペーン連動/地元ボランティアが支える |
| おぼろっく | 福井県敦賀市(金ヶ崎緑地) | 5,000人(2024年初日/主催発) | 港町ロケーション・官民連携 | 新興・地域資源発信 | 北陸新幹線開業を契機/「おぼろ昆布×ロック」ネーミング/地域グルメと街歩き連動/将来拡大を目指す |
フェスがもたらす未来の潮流

音楽フェスは今や地域に人を集めるだけでなく、これからの社会課題や価値創出にどう向き合うかが問われています。今後5年を見据えると、「気候変動への適応」「新たな資金循環」「シビックプライドと関係人口」という三つの潮流が、フェスの姿を大きく変えていくでしょう。
まず、気候変動への適応です。真夏の猛暑はイベント運営における最大のリスクの一つになりつつあります。ROCK IN JAPAN FESTIVALが2025年から開催時期を9月に移行したのは、その象徴的な動きです。
今後はWBGT(暑さ指数)を基準にした安全対策や、ナイトフェス・秋開催へのシフトが広がると考えられます。熱中症対策は単なるオペレーション改善ではなく、フェスの持続可能性を左右する経営課題になっていくでしょう。
次に、新たな資金循環の仕組みです。滋賀県のイナズマロックフェスが2025年からふるさと納税返礼品としてチケットを導入したのは、自治体と音楽イベントを結びつける新しいモデルです。
これに続き、地域通貨や環境価値(CO₂オフセット)と連携する取り組みが各地で試される可能性があります。5年後には「フェス参加=地域投資」という意識が一般化し、イベントをきっかけに自治体財源や環境対策が支えられる仕組みが標準化しているかもしれません。
最後に、シビックプライドと関係人口の拡大です。ボランティアや学校参加などを通じて、地元の人々がフェスに関わる機会は年々増えています。中学生の吹奏楽部がステージに立つ、商店街が一丸となってフェスを盛り上げる──こうした光景は珍しくなくなりました。
今後は「フェスに参加したことが地域への愛着やUターンのきっかけになった」という事例も増えるでしょう。フェスは単なる娯楽ではなく、地域の誇りと未来を共有する“文化装置”として位置づけられていくはずです。
まとめ:音楽フェスは地域の共創装置へ

フェスはもはや一過性のイベントではなく、地域の産業・文化・観光・環境をつなぐ装置へと進化しています。大規模フェスは都市やリゾートのブランドを底上げし、地域密着型フェスは人と人、世代と地域を結び、持続可能な賑わいを生み出しています。
これからの地域づくりにおいて、音楽フェスという「場」をどう育て、活用していくか──その問いに、自治体も企業も、そして市民も関わる時代が来ているのかもしれません。本記事に関してのホワイトペーパーについては以下よりダウンロードができますので、併せてご覧ください。
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略