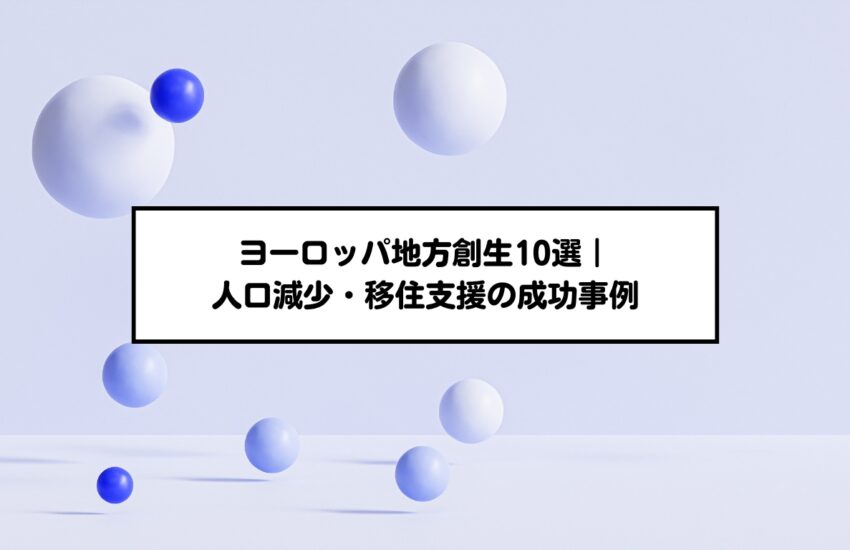少子高齢化と人口減少という構造的な課題は、日本だけでなく、ヨーロッパの多くの地域でも深刻な影響を及ぼしています。人口流出による空き家の増加、学校や病院の閉鎖、地域経済の縮小といった現象は、都市への一極集中と重なりながら、各地で“限界集落化”のリスクを高めています。
こうした中、地域の持続可能性を守り、新たな価値を創出するための「地方創生」への取り組みが、ヨーロッパでも積極的に展開されています。住民・自治体・民間企業が連携し、空き家活用、文化資源の再発見、テクノロジーの導入、そしてEUによる地域支援制度を柔軟に活かすなど、多様なチャレンジが芽を出し始めています。
本記事では、ヨーロッパ各地で実践されている10の地域再生モデルをご紹介します。これからの地方創生のヒントとして、日本の地域づくりにも応用可能な知見をお届けします。
地方創生成功事例【移住・人口対策モデル】

1. イタリア・ムッソメリ|「1ユーロ住宅」で空き家再生
イタリア・シチリア島の山あいに位置する人口約1万人の小さな町、ムッソメリ。長年、少子高齢化と空き家の急増という深刻な課題を抱えてきました。
転機となったのは、2017年に始まった「1ユーロ住宅」プログラムです。老朽化した空き家をわずか1ユーロで販売する一方で、購入者には一定期間内に改修を行う義務を課す仕組みを導入しました。
この取り組みにより、アメリカや北欧を中心に世界中から移住希望者が集まり、これまでに約300軒が売却されました。さらに、空き家を活用したカフェやゲストハウスが新たに生まれ、観光客の数は従来の10倍に急増。加えて、高速インターネットやコワーキングスペースも整備され、デジタルノマドの拠点としても注目を集めています。
こうしてムッソメリは、人口減少を食い止めるだけでなく、観光とデジタル経済を呼び込む新しい地域活性化モデルとして注目されるようになりました。
2. ギリシャ・フォルナ村|教育を守る移住支援モデル
ギリシャ中部の小村フォルナでは、かつて小学校に通う児童が2人まで減少し、閉校の危機に直面していました。もしこのまま学校がなくなれば、子育て世代は村に定住する理由を失い、さらに人口減少が加速しかねないという深刻な状況でした。
状況を変えたのは、教師パナギオタ・ディアマンティ氏と正教会のコンスタンティノス・ドゥシコス司祭。二人を中心に、地域外からの移住希望者に金銭的インセンティブを提供する仕組みを立ち上げました。
その結果、児童数は2人から8人へと増加。教育環境を維持できたことで、学校は存続の道を開きました。学校がなくなれば子育て世代の移住が途絶えるところでしたが、その連鎖を食い止めたのです。
さらに、この取り組みはメディアでも広く報じられ、全国的な関心を呼び、移住に関する問い合わせが相次ぎました。
「教育を守ることは、地域の未来を守ること」。フォルナの事例は、住民主体の持続可能な地方再生モデルとして示唆に富みます。
3. イタリア・サンタ・フィオラ|リモートワーカー向けスマートビレッジ
トスカーナ州の中世の村サンタ・フィオラは、人口減少対策として2020年に「スマートビレッジ」構想を始動。リモートワーカーを対象に家賃の50%(上限200ユーロ、最大6か月)を補助する制度を導入しました。
安心して働けるよう高速インターネットを整備し、最低2か月の滞在を条件に移住希望者を受け入れ。農業体験や伝統行事への参加も組み込み、地域との交流を重視しています。
都市の利便性と田舎の豊かさを掛け合わせた暮らし方は、コロナ禍以降の新しいライフスタイルとして注目を集め、サンタ・フィオラはその先進モデルとして高く評価されています。
4. スペイン「Holapueblo」|空白地帯の移住マッチングプロジェクト
スペインの農村地域は「La España vaciada(空白地帯)」と呼ばれるほど過疎化が深刻です。
この課題に挑むのが、2018年にスタートした「Holapueblo」プロジェクト。地方自治体、NPO、民間企業が連携し、都市に住む移住希望者と地方の空き家・仕事をマッチングしています。
これまでに85家族・200人以上が移住を実現し、ベーカリーや宿泊施設、クラフト工房などの小規模ビジネスが誕生。人口流入だけでなく、地域経済の再生につながっています。
地方創生成功事例【文化・アイデンティティ再生モデル】

5. ポーランド|EU支援を活用したテーマ村運動
ポーランド各地で広がる「テーマ村(Thematic Village)」は、村全体をひとつの物語として再構築する取り組みです。
例として、ヤニア・ゴラ『パンの村』、アダムコヴォ『鳥の村』、ヤイコヴォ『卵の村』などがあります。訪れる人は、農業や民話、手工芸を通じて、その地域ならではの文化を体験することができます。
背景には、EUのLEADERプログラムがあります。小規模自治体や住民団体が主導で活用できる資金が提供され、観光や教育、商品開発まで幅広く支援。行政主導ではなく、住民自身が戦略を立案・実行する仕組みが制度的に後押しされています。
6. ドイツ・ヴァイアン|住民参加型「村の更新」プロジェクト
バイエルン州の小村ヴァイアンは、1990年代から「村更新(Village Renewal)」に取り組んできました。
最大の特徴は、行政任せにせず住民が計画と意思決定に深く関与した点。修道院など歴史的建築を保存しつつ、住民協議会を通じて土地利用や公共空間のデザインを議論。
結果として、伝統と現代的な暮らしの両立に成功し、持続可能な地域発展を実現しました。住民主導型の計画づくりの好例として評価されています。
7. イタリア・マルケ州「Borgofuturo+」|フェスから始まる地域再生
マルケ州の小さな村で始まった「Borgofuturo」は、当初は音楽やアートのフェスティバルでした。
しかし2020年以降、「Borgofuturo+」として住民参加型のビジョン策定プロジェクトへ発展。ワークショップや討論を通じ、住民が「自分たちの村の未来像」を語り合う場を設けています。
この対話を起点に、観光・食文化・資源活用を軸にした新たな地域戦略が構築されつつあり、フェスを通じた対話が持続可能なまちづくりの方向性を示しています。
地方創生成功事例【ネットワーク・EU連携モデル】

8. ポーランド・農村開発財団|草の根からの地域自立支援
ポーランドの農村開発財団(Fundacja Wspomagania Wsi, Rural Development Foundation)は、政府機関ではなく民間の非営利財団(NGO)です。ただし、農村振興や地域開発の政策課題とも密接に関わるため、政府や地方自治体と連携しながら事業を進めています。
これまでに、マイクロローン、起業・金融教育、ICT普及などのプログラムを展開し、農村地域の小規模ビジネスや住民の生活向上に貢献してきました。
9. EUプロジェクト「RURITAGE」|文化・自然遺産を核にした再生
EUはHorizon 2020プログラムの一環として「RURITAGE」を推進。文化・自然遺産を地域再生の資源と捉え直し、観光・教育・環境保全を融合させています。
特徴は、先進地域(Role Models)と再現地域(Replicators)の知識移転の仕組み。巡礼路の再活用、伝統食の継承、景観保全などのテーマで、地域が独自の戦略を構築しています。
10. EU「Startup Villages」|農村をイノベーション拠点へ
EU委員会とJoint Research Centre (JRC) が主導する「Startup Villages Forum」は、農村地域をイノベーションの拠点とする欧州横断的な取り組みです。
自治体・大学・企業・NPOがネットワーク化され、農村部での起業を支えるエコシステムづくりを推進。具体的には:
1)「Startup Village」としての認定・マッピング
2)起業支援やメンターネットワークの構築
3)高速通信やワークスペース整備
4)住民と大学・企業の協働によるスキル育成
すでに複数地域で創業や新事業が始まりつつあり、「農村=衰退」ではなく「農村=イノベーション拠点」としての新たな価値が示されています。
地域再生の考察|小さな試みと横のつながりが鍵

今回紹介した10の事例からは、規模の大小を問わず共通点が見えてきます。
1)内発的発想と外部との接点の両立
地域固有の資源を再編集しつつ、都市や国外との接点を積極的に設計。
2)スモールスタートと持続性
小規模イベントやシンプルな制度から始まり、改善を重ねて持続可能な成果へ。
3)ネットワークと再現性の仕組み
EUの制度やプロジェクトが横の学び合いを制度的に後押し。
結論|地方創生の成功ポイントは“地域主体”

ヨーロッパの事例に共通するのは、「地域を変えるのはそこに暮らす人々の意思と行動」という考え方です。その背後には、行政やEUの柔軟な支援、そしてネットワークによる知の共有があります。
日本の地方においても、同様の課題と同時に大きな可能性が広がっています。ヨーロッパの実践は「地域の価値は再発見できる」「過疎は終わりではなく始まりになりうる」という力強いメッセージを投げかけています。
あわせて読みたい関連記事:
👉 地方創生は意味があるの?地方活性化は中央依存型からの脱出がカギ
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略