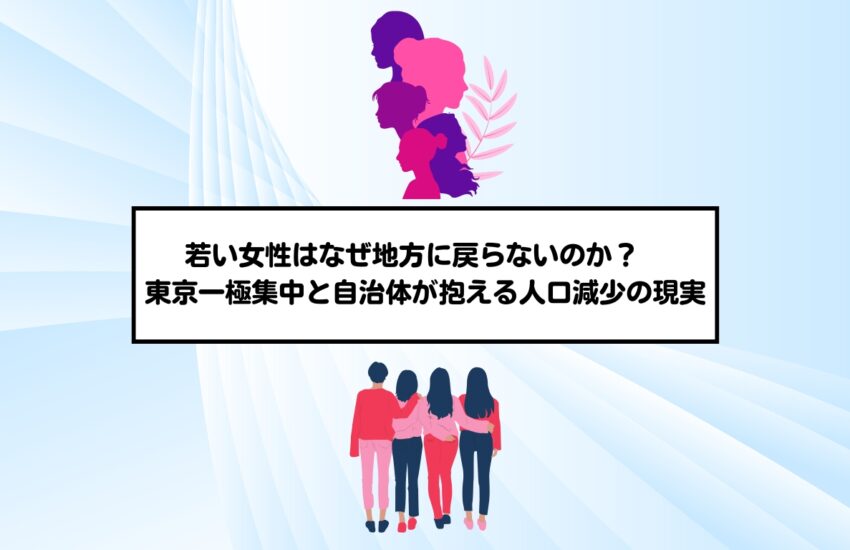若い女性は、なぜ都市に出て戻らないのでしょうか。進学・就職・結婚をきっかけに上京した女性たちは、そのまま都市にとどまり、地元に戻らない傾向が強まっています。
総務省の「住民基本台帳人口移動報告(2024年)」によれば、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)への転入超過は日本人に限ると29年連続で続いており、3大都市圏(東京圏を含む)への転入超過においては、 男性:約50,760人、女性:約68,906人と、女性が男性を大きく上回っています。
また、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)では、男女ともに若年層を中心に転入超過がみられますが、特に25〜29歳の女性では転入超過数が約9万人に達し、同年代の男性(約8.3万人)を8,000人以上上回っています。このことから、東京圏への人口流入は、若い世代の中でも25〜29歳女性において顕著に強いことが確認されており、地域社会の人口動態に深刻な影響を及ぼしています。
その背景には、教育や雇用の機会格差だけでなく、地方に残る「見えないルール」や「文化的な圧力」があります。これらが女性にとって“帰りにくさ”を強めているのです。女性が戻らない地域は、やがて若者全体が住みにくい地域になります。
では、自治体は何を変えるべきなのでしょうか――。
女性の東京流出が止まらない現実 ― データで見る人口動態の変化

内閣府『令和7年版(2025年版)男女共同参画白書』によれば、進学・就職・結婚などをきっかけに地方から都市へ移動した若者のうち、特に女性はその後も都市に留まり地方に戻らない傾向が顕著であると指摘されています。
白書の調査では、地方出身の女性が東京圏へ転出した理由として、『希望する進学先が少なかった』(女性42.1%、男性29.7%)や、『地元から離れたかった』(女性26.8%、男性15.0%)などが上位に挙げられています。また、女性は「親や周囲からの干渉から距離を置きたかった」とする回答も多く、このような地方の社会構造的な要因が、地方が『若い女性が戻らない地域』になりやすい状況につながっていると白書は考察しています。
これは単なる人口減少の問題ではありません。出産・子育て世代の減少による少子化、地域の労働力不足や消費力低下と直結し、地域活力を根本から揺るがす大きな要因となっています。
地方に若い女性が戻らない理由 ― 教育・雇用・文化の三重ハードル

地方から都市への人口移動は、個々の意思や性別による差だけでなく、社会の仕組みそのものが生み出す「構造的な要因」に大きく影響されています。とりわけ、教育と雇用という人生の基盤に直結する分野での機会格差は、若者を都市へと駆り立てる主要な背景となっています。以下では、その代表的な要素を整理していきます。
教育機会の格差が若者流出を加速させる
地方には大学の数や学部の選択肢が少なく、進学を希望する若者は都市部に移らざるを得ません。全国平均での大学進学率は約60%ですが、地方では進学希望者の多くが都市部へ流出しています。
地方の雇用構造が多様な働き方を阻む現実
地方の雇用は公務員や医療・介護、地場産業に偏りがちで、給与水準も都市部と差があります。一方、都市ではIT・金融・クリエイティブなど多様なキャリアパスが広がり、成長機会や収入面でも優位です。
👉 こうした教育・雇用の「機会格差」が、男女を問わず地方から都市への流出を促す大きな要因になっています。
女性が感じる“地元の居づらさ” ― 見えない圧力と多様性の欠如

都市流出の背景には、教育や雇用の格差といった男女に共通する要因があります。しかし、女性にとってはそれだけでは説明しきれない、より複雑で切実な事情が存在します。地方社会に根強く残る文化的な価値観や性別役割への期待が、女性にとって「地元に戻りにくい」「戻りたくない」と感じさせる大きな壁となっているのです。
地域社会に残る“無意識のジェンダーバイアス”
内閣府や地方自治体の意識調査では、女性から「親や地域からの干渉を避けたい」「地元にいると役割を押し付けられる」といった声が多く寄せられています。
具体的には――
・「母親は学校行事に必ず参加すべき」
・「家事や介護は女性が担うもの」
といった“見えないルール”が、今も地域には残っています。共働きが当たり前の時代に、平日昼間の学校行事を母親だけに求めるのは現実的ではありません。それでも「母親が来るもの」という暗黙の前提があることで、女性は大きな負担感を抱えます。
「地元に戻りたくない」と思わせる心理的ハードル
独身女性、子育て世代、キャリア志向の女性――それぞれが抱えるニーズは異なります。しかし地方では「結婚・出産して子育てする女性」という一つのモデルに当てはめられがちで、自己実現の選択肢が狭められてしまいます。
👉 こうした文化的圧力や多様性の欠如が、女性に「ここには戻りたくない」と思わせる大きな理由になっているのです。
女性が“戻りたい”と思う地域の条件とは?

では、女性はどのような条件が整っていれば「この地域に戻りたい」「ここで暮らし続けたい」と思えるのでしょうか。
都市への流出を食い止めるには、単に雇用の数を増やすだけでは不十分です。重要なのは、ライフステージや価値観の多様性を受け止めながら、女性が安心して自分らしく働き、生きられる地域の環境づくりです。では、具体的な条件を順に見ていきましょう。
1.キャリアの継続性
出産・子育て・介護といったライフイベントがあってもキャリアを途切れさせずに働ける仕組み。
(例:保育や介護の支援体制、柔軟な勤務制度)
2.多様な働き方
都市と同じようにリモートワーク、副業、起業など多様な選択肢が用意されていること。
3.自己実現の自由
性別にとらわれず、自分らしい生き方やキャリアを選べる環境。
4.居心地のよさ
「女性だから」という役割を押し付けられず、互いに尊重し合える地域文化。
👉 必要な条件が整っていなければ、雇用がどれほどあっても、女性が戻りたい、住み続けたいとは感じにくいのです。
自治体が取り組むべき地方創生の新戦略

女性にとって魅力ある地域を実現するためには、自治体が積極的に環境を整えることが欠かせません。これまで見てきたように、単なる雇用創出や人口誘致策だけでは限界があります。大切なのは、地域に根強く残る意識の壁を取り払い、制度を実効性あるものに整え、さらに挑戦できる土台を築くことです。そのために、自治体が優先して取り組むべき戦略は大きく三つに整理できます。
1.意識改革:地域全体の価値観をアップデート
これまで学校行事や地域活動においては「母親が担うのが当たり前」という暗黙の前提が根強く存在してきました。運動会の準備やPTAの役職、町内会行事の裏方などは、家庭の中で主に母親が引き受けるものとされ、その負担が偏ってきたのです。
しかし、こうした固定的な役割分担は、女性の社会進出や多様な働き方の広がりにそぐわないだけでなく、地域全体の活力を損なう要因にもなっています。
そこで必要となるのが、意識改革を通じた文化の転換です。まずは「誰が担うべきか」という前提を問い直し、男性や高齢者、さらには子どもや若者まで含めて役割を柔軟に分担する仕組みをつくることが重要です。
例えば、地域清掃をシフト制にして仕事のある人でも参加しやすくする、学校行事の準備をオンライン会議で分担する、体力を必要としない作業を高齢者が担い、若者は力仕事を担当するなど、適材適所の発想が求められます。
こうした取り組みは単に母親の負担を軽減するだけではありません。多様な人が地域活動に関わることで、世代を超えた交流や相互理解が深まり、孤立感の解消や地域の結束強化にもつながります。また、自治体にとっても「地域住民の参加率向上」「持続可能な地域運営」という形で大きな成果をもたらします。
意識を改めることは一朝一夕では実現できませんが、小さな変化の積み重ねがやがて「地域ぐるみで助け合う文化」へと発展していきます。その過程で自治体は、住民に役割分担の選択肢を提示したり、参加の柔軟性を確保する仕組みを整備したりする役割を担うべきでしょう。
2.制度整備:働きやすさと暮らしやすさの両立
日本の多くの自治体では人口減少が深刻化しており、若い世代の流出や子育て世帯の転出が地域の持続可能性に直結する課題となっています。
その要因の一つには「働きながら子育てや介護を両立しにくい制度・職場環境」があります。特に地方においては、大都市圏に比べ柔軟な働き方を選びにくいことが、移住希望者や地元に残る若者にとって大きな障壁となってきました。
この状況を打開するには、育休・時短勤務・テレワークといった制度を「特例的な待遇」ではなく「誰もが当たり前に利用できる標準の選択肢」とすることが不可欠です。
性別や年齢、雇用形態にかかわらず利用可能な仕組みを整えることで、男性の育児参加や高齢者の再就労も促進され、多様な人材が地域に根付いて働き続けられる環境が実現します。
具体的には、自治体が率先して柔軟な勤務制度を導入し、地元企業への導入支援や助成金制度を整備することが有効です。
また、テレワーク環境の整備は都市部からの移住希望者にとって大きな魅力となり、地方に住みながら都市圏の企業に勤務する「二地域就労」の形も可能になります。
さらに、移住促進のためには、保育施設や学童保育の拡充、地域コミュニティとの接続支援もあわせて行うことで「生活基盤の安心感」が確保され、長期的な定住につながります。
こうした制度整備は単なる「働き方改革」にとどまらず、人口減少対策と移住促進を同時に進める戦略的施策となります。
柔軟な働き方を可能にする環境が整えば、地域に魅力を感じて移り住む人が増え、子育て世帯や若い人材の流出も抑制できます。結果として、地域経済の活性化や持続可能な社会の形成へとつながっていくのです。
3.挑戦支援:女性の起業・再就職を後押しする環境づくり
女性が地域で活躍するためには、従来の「支える側」「担い手」としての役割にとどまらず、主体的に挑戦できる環境づくりが不可欠です。
特に、出産や子育てを機に一度は都市部へ出た女性が「また戻ってきたい」と思える地域にするためには、キャリアや自己実現の可能性を広げる仕組みが求められます。
その鍵となるのが「資金」「場所」「学び」の三点セットです。例えば、起業や副業に挑戦する女性に対し、自治体や金融機関が連携して小規模でも利用しやすい資金支援を提供する。
加えて、コワーキングスペースや地域コミュニティ施設を活用し、家庭や職場以外に安心して働ける場所を確保する。さらに、起業ノウハウやデジタルスキル、マーケティングなどを学べる研修やメンタープログラムを用意することで、挑戦のハードルを大幅に下げることができます。
また、地域で活躍する女性リーダーを可視化し、ロールモデルとして紹介することも大きな効果を生みます。身近な成功事例は「自分にもできるかもしれない」という共感を呼び、挑戦する女性を増やす原動力になります。
同時に、男性や地域全体の意識改革にもつながり、「女性が前に立つのは特別ではない」という文化が根付いていきます。
👉 意識・制度・挑戦 の三本柱をそろえて改革を進めることで、女性が安心して力を発揮できるだけでなく、地域全体に新しい事業や働き方が広がります。結果として、女性が「戻りたい」「住み続けたい」と思える地域づくりにつながり、人口減少に歯止めをかける持続可能な循環を生み出すのです。
成功事例に学ぶ ― 女性が活躍する地域の共通点

理念や戦略を示すだけでは、地域の変化はなかなか進みません。重要なのは、実際に現場で試みられている施策から学び、自分たちの地域に応用できるヒントを見つけることです。全国各地ではすでに、ジェンダー視点を取り入れたユニークな取り組みが進められています。以下に、注目すべき実践例を紹介します。
兵庫県豊岡市:企業認定制度でジェンダー平等を推進
まちの将来像に「ジェンダーギャップ解消」を掲げ、企業を対象に「あんしんカンパニー認定制度」を導入。認定企業では女性管理職比率が上昇し、柔軟な勤務制度も広がっています。
長野県塩尻市:「在宅ワーク支援」で子育て世代の就労を実現
自営型テレワーク推進事業「KADO」を展開。子育て世代や介護中の住民が在宅で仕事を得られる仕組みを整備し、参加者の継続就労率が高まっています。
滋賀県:託児付きコワーキングで女性の起業を支援
「女性の起業応援センター」を設置。託児付き・無料のコワーキングスペースや相談支援を提供し、創業数が着実に増加。女性の新規事業の定着にも成果を上げています。
👉 これらの取り組みに共通するのは、「制度」と同時に「文化」も変えようとする姿勢です。
結論 ― 女性が戻る地域は、人口減少を克服できる

若い女性が都市に出て戻らない現実は、「人口減少」「少子化」「地域活力の低下」に直結する深刻な課題です。だからこそ自治体は、男女一律の施策ではなく、女性特有の課題に正面から向き合わなければなりません。
女性が「帰りたい・残りたい」と思える地域は、同時に男性や高齢者、そして次世代にとっても暮らしやすい地域といえます。固定的な役割観にとらわれず、多様な人々が自分らしく生き、挑戦できる環境を整備することは、地域社会の持続可能性を高める上で不可欠な要件といえます。
コラム:自治体PR 実践チェックリスト
✅自治体公式SNSに「女性支援施策」の専用ハイライトを作る
✅移住検討層向けに「女性の声」を集めたインタビュー記事を公開
✅移住フェアや説明会をオンライン配信し、若い世代にもアプローチ
✅地元で起業・活躍する女性を積極的に取材し、ストーリーを発信
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略