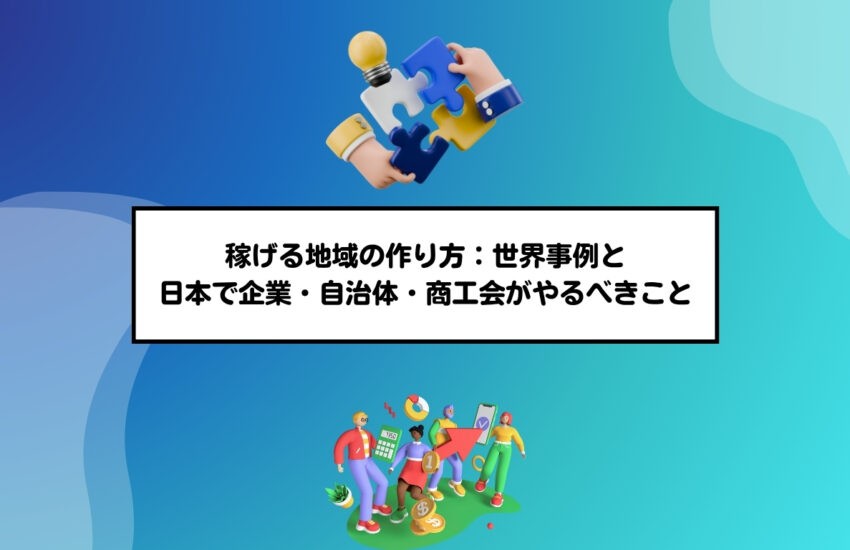日本の地域経済はいま、人口減少・税収減・若者流出という三重の課題に直面しています。これまでのように補助金や公共事業に頼るだけでは、地域は持続的に成長できません。求められているのは、地域自らが人・資金・情報を呼び込み、付加価値を生み出す力――すなわち「稼ぐ力」をつけることです。
では、どうすれば地域が自ら稼げるようになるのでしょうか。そのヒントは、すでに世界各地で実践されている「稼げる地域モデル」の中にあります。アメリカのシリコンバレー、ドイツのミュンヘン/バイエルン州、イスラエルのテルアビブ――それぞれの地域は、企業・自治体・商工会(あるいは産業団体)が連携し、人・資金・情報を循環させる仕組みを構築することで、持続的に成長を続けています。
本稿では、これらの事例をもとに、「稼げる地域」をつくるための条件を整理し、さらに日本において企業・自治体・商工会がそれぞれ何をすべきかを考察します。
シリコンバレー(アメリカ・カリフォルニア州 Santa Clara County)

【特徴】世界的テクノロジー集積地としての強固な経済基盤
シリコンバレーは、世界でもっとも高い経済的付加価値を生み出す地域のひとつです。中心となるSanta Clara County(サンタクララ郡)は、2025–26年度の推奨予算において歳入約126億ドル、歳出約130億ドルが見込まれています。この規模は、郡単位としては世界的にも極めて大きく、安定的な財政基盤を示しています。
歳入の構造を見ると、不動産税(Property Tax)が一般会計収入の約40%を占めており、景気変動に左右されにくい堅実な税源を確保しています。また、企業活動や固定資産に対する課税、そしてデータセンター・電力事業などの税外収入も加わり、多層的な財源構造を形成しています。
一方で、歳入規模の大きさに比して歳出も拡大しており、医療・福祉・インフラ・住宅支援など社会的コストが高止まりしている点は、今後の課題として指摘されています。
【企業の取り組み】イノベーションの連鎖が支える地域の収益力
シリコンバレーの経済的強さの背景には、企業群による継続的な技術革新と再投資のサイクルがあります。
【データセンターと電力事業の連携】
サンタクララ市では、公営電力事業「Silicon Valley Power」を通じ、データセンター関連収入が一般会計予算の約13%(約4,500万ドル)を占めるまでに成長しています。これは自治体が“テック産業の成長を財源化”する構造を持つことを意味します。
【スタートアップの創出と成長】
スタートアップエコシステムが成熟しており、AI、バイオテクノロジー、モビリティ、ソフトウェア分野で世界的企業が次々と誕生しています。また、ベンチャーキャピタル(VC)投資額は全米の中でも突出しており、資本と人材の循環が地域経済を支えています。
【研究・大学との連携】
スタンフォード大学を中心とした研究・起業支援ネットワークが強固で、学術知見と事業化の距離が極めて近い点も特徴です。大学・研究機関・スタートアップ・大企業が一体となってイノベーションを推進しています。
このように、企業活動と研究機関の結びつきが「知識と資本の循環」を生み出し、地域全体として持続的な成長を実現しています。
【自治体の取り組み】オープンデータと産業政策による支援
サンタクララ郡やその配下の市は、財政運営の透明化と産業支援の両立を重視しています。
【財政データの公開と可視化】
郡政府は歳入・歳出データをオンラインで公開し、政策・投資判断の透明性を確保しています。不動産税を基盤に、景気変動リスクを分散する構造的工夫が見られます。
【産業基盤・電力インフラの整備】
公営電力事業を活用してデータセンター誘致を進めるなど、自治体自らが新たな収益源を創出しています。税収だけに依存しない、いわば「自治体経営の多角化」が特徴です。
【観光・サービス税の再建】
パンデミック後の宿泊税減収に対しては、税率調整やイベント誘致による回復施策が進められています。経済の構造的偏りを是正する動きとして注目されています。
これらの政策は、地域の経済活動を支えると同時に、財政的な安定性を高める仕組みを意識的に作り上げている点で特徴的です。
【商工団体・地域組織の役割】官民連携の「データ駆動型ガバナンス」
シリコンバレーでは、官民・大学・市民団体が協働して地域経営を行う仕組みが確立しています。
【Silicon Valley Leadership Group(SVLG)】
企業横断的にインフラ、交通、気候、教育などの課題に取り組む団体。企業が行政政策に関与することで、地域全体の持続的発展を支えています。
【Joint Venture Silicon Valley(JVSV)】
毎年発表される「Silicon Valley Index」を通じ、地域経済・雇用・住宅などのデータを可視化。行政と企業の政策判断の基盤となっています。
→“エビデンスに基づく官民対話”を支える役割を果たしています。
このように、測る(データ化)→決める(合意形成)→実行する(政策実装)という循環が、地域の成長を制度的に支えています。
【成功要因】人材・資本・知識の高速循環
シリコンバレーが「稼げる地域」として成功している背景には、以下の三要素が挙げられます。
【安定した財政基盤と多様な収入源】
不動産税や企業活動に加え、データセンターや電力事業といった税外収入も確保。自治体の財政が成長産業に連動しています。
【人材と資本の流動性】
世界中から人材と資金が集まり、起業・投資・再投資のサイクルが継続。グローバル市場と直結した資金循環が特徴です。
【データを基盤とした政策形成】
JVSVやSVLGを通じて、地域の現状を可視化し、迅速に政策へ反映させる「Evidence-Based Governance」が定着しています。これらの仕組みが、地域としての「付加価値創出能力」を支える根幹となっています。
ミュンヘン/バイエルン州(ドイツ)

【特徴】高付加価値産業を軸とした堅実な経済構造
ミュンヘンおよびその所在するバイエルン州は、ヨーロッパの中でも経済基盤が非常に強い地域として知られています。2023年時点で同州の名目GDPは約7,684億ユーロに達し、ドイツの州の中でも最上位に位置します。
また、ミュンヘン都市圏は一人あたりGDPや可処分所得の水準が高く、2024年のデータでは購買力が全国平均を約35%上回るとされています。
このように、バイエルン州は製造業・サービス業・研究開発がバランスよく融合しており、安定的に付加価値を生み出す仕組みが形成されています。一方で、経済力の高さは同時に生活コストや人件費の上昇を招き、持続可能性の観点からはコスト圧力という課題も抱えています。
【企業の取り組み】製造と研究が融合する「知の経済圏」
ミュンヘンの強みは、製造業と研究開発の融合によって生まれる高付加価値の創出にあります。
【自動車・モビリティ産業】
BMWやAudiをはじめとする大手自動車メーカーが拠点を構え、電動化・自動運転など次世代モビリティの研究開発を主導しています。これに伴い、部品・電池・制御ソフトなど周辺産業も高度化が進んでいます。
【ICT・デジタル技術・スタートアップ】
Technical University of Munich(TUM)やLudwig-Maximilians-Universität München(LMU)を中心に、大学と企業が連携して新技術を社会実装する取り組みが進んでいます。2025年上半期のデータでは、バイエルン州のスタートアップ投資額はドイツ国内で最も高い水準にあり、AIやDeepTech分野を中心に起業が活発です。
【航空宇宙・防衛・エネルギー分野】
AirbusやMTU Aero Enginesなど、航空・防衛関連企業も集積しています。これらは「製造×研究×技術開発」の三位一体モデルを形成し、BtoB分野における安定した付加価値を生み出しています。
このような構造により、ミュンヘンは“モノをつくる地域”から“知識を生み出す地域”へと発展を遂げています。
【自治体・州政府の取り組み】戦略的な支援体制と政策設計
バイエルン州およびミュンヘン市は、経済・研究・起業支援を戦略的に推進する体制を整えています。
【企業誘致・投資促進】
州政府の機関「Invest in Bavaria」は、国内外の企業に対し立地選定から助成金、ネットワーク紹介までワンストップで支援を行っています。海外企業に対しても無料・機密対応のコンサルティングを提供し、グローバル企業の拠点誘致を進めています。
【イノベーション戦略と研究支援】
ミュンヘン市は「Innovation Agenda 2030」を掲げ、国際的なイノベーション拠点としての地位を確立することを目指しています。また、TUM傘下の「UnternehmerTUM」では大学発ベンチャー支援や資金調達支援を体系的に実施しており、研究成果の事業化を促進しています。
【先端技術への重点投資】
州レベルではAI、量子技術、グリーンエネルギーへの支援を強化しており、EU資金と連動した長期的な技術開発戦略を展開しています。
こうした政策は、単なる産業支援にとどまらず、「研究→企業→雇用→税収→再投資」という循環構造を制度として設計する点に特徴があります。
【商工会・団体・研究機関の役割】分散型エコシステムの形成
バイエルン州のもう一つの特徴は、官民・大学・団体が分散的に連携する「エコシステム型支援体制」にあります。
Munich Innovation Ecosystemでは、2,300を超えるスタートアップと680社以上の企業、約3.8万人の従業員が参加し、産学官連携による共同研究・実証を推進しています。
IHK Bayern(州商工会議所)は、中小企業の国際展開やデジタル化支援を担い、規制改革や税制改善に関する要望を政策側に伝える橋渡し役を果たしています。
大学・研究機関(TUM、LMU)は、研究成果をベンチャー創出に直結させる仕組みを提供し、起業家育成プログラムも整備しています。
このように、中央集権的な政策運営ではなく、各機関が自律的に連携する「水平協働モデル」が地域競争力の基盤となっています。
【成功要因】政策の一貫性と多層的な価値創出
バイエルン州が「稼げる地域」として機能している背景には、以下の3つの要素が挙げられます。
1.長期的かつ一貫した政策運営
州と自治体、大学、研究機関が共通の長期ビジョン(Innovation Agenda 2030)を共有し、安定した支援体制を維持している点。
2.産業の多様化と付加価値の高さ
自動車や機械、ICT、航空宇宙など、複数の産業軸を持ち、それぞれが高付加価値化を進めている点。
3.エコシステム連携による競争優位
大企業・中小企業・スタートアップ・大学・行政が相互補完的に連携し、研究成果や投資が地域内で循環している点。
この三層構造が、ミュンヘン/バイエルンをヨーロッパ有数の「持続的に稼げる地域」へと押し上げています。
テルアビブ(イスラエル)

【特徴】グローバル市場と直結する「知識創出型エコシステム」
イスラエルの経済中枢であるテルアビブは、スタートアップやハイテク産業の集積地として世界的に知られています。2025年版 Startup Genomeのレポートによれば、同地域のスタートアップ・エコシステムは世界第4位にランクされており、規模と成長ポテンシャルの両面で高く評価されています。
2022年7月〜2024年12月の期間には、スタートアップの新規創出および買収等を通じて約1,980億ドルの経済価値を生み出したとされ、単なる技術集積地を超えた「付加価値創出都市」となっています。
さらに、180社を超える多国籍企業がテルアビブ周辺に研究開発(R&D)拠点を設けており、人材・資金・情報が絶えず流入する国際的な知識経済圏を形成しています。
【企業の取り組み】先端技術分野での高付加価値化
テルアビブの産業構造は、特定分野に集中しながらも技術的深度と国際競争力の両立を実現しています。
【サイバーセキュリティ・AI・量子コンピューティング】
いわゆる「シリコン・ワディ(Silicon Wadi)」と呼ばれる地域では、サイバー防衛技術やAIアルゴリズム開発が主要産業となっており、世界的なスタートアップの拠点となっています。
【多国籍企業のR&D集積】
Google、Microsoft、Intelなどのグローバル企業が研究開発拠点を設け、現地スタートアップとの協業を進めています。技術と資本の双方が流れ込むことで、地域内で新たな知識と事業が連鎖的に生まれる仕組みが機能しています。
テルアビブでは、サイバーセキュリティやAIなどの先端分野に特化したスタートアップが集積し、技術革新の核となっています。
さらに、GoogleやMicrosoftなど多国籍企業のR&D拠点が進出し、現地企業との協業や買収を通じて新たな資金とノウハウが地域に循環しています。
こうした動きにより、「創出・成長・買収・再投資」が連鎖的に進む持続的なイノベーション・エコシステムが形成されています。
【政策・制度面の取り組み】国家戦略としてのイノベーション促進
イスラエルでは国家レベルでスタートアップ支援を明確に位置付けており、制度面の整備が進んでいます。
【Israel Innovation Authority(イスラエル・イノベーション庁)】
公的機関として、研究開発資金の助成、技術移転、スタートアップ支援を包括的に行っています。これにより、創業期から成長期までの企業に対して制度的な資金の流れが確保されています。
【ベンチャーキャピタルと投資環境】
イスラエル全体のスタートアップ投資額は2024年に約122億ドルに達し、テルアビブがその中心を担っています。企業設立後の初期段階から国際的VCの参入が活発で、成長資金が迅速に供給されています。
【法制度・研究支援の充実】
AI技術開発や倫理的課題への対応を目的とした法整備が進行中であり、規制と促進のバランスを取りながら産業の信頼性を高めています。
これらの政策は、単なる起業促進にとどまらず、国家としての産業競争力強化の枠組みとして設計されています。
【産業・研究エコシステム】大学・企業・投資の三位一体構造
テルアビブの経済的成功を支えるもう一つの要因は、研究機関・企業・投資家が緊密に連携するエコシステムです。
テルアビブ大学やワイツマン科学研究所など、世界水準の研究機関が集中し、研究成果がスタートアップやグローバル企業の新事業に直結しています。
インキュベーション施設やアクセラレーターが充実しており、研究→事業化→国際展開のプロセスが短期間で進みます。
投資家や起業家が「グローバル市場を前提」として行動する文化が根付き、国境を越えた資本・人材の循環を生み出しています。
こうしたネットワーク構造が、テルアビブの「稼ぐ力」の実質的な土台を形成しています。
【成功要因】スピードと柔軟性を備えたイノベーション文化
テルアビブが「稼げる地域」として機能している背景には、次の3つの要因が挙げられます。
1.外部資源の積極的な受け入れ
外国企業や投資家の参入を歓迎する政策と、オープンな技術交流の文化が相まって、国際的な資本・人材が集まる構造を形成しています。
2.高い起業率と短い事業サイクル
失敗を許容し再挑戦を促す文化が根付き、企業の新陳代謝が速いことが、結果的にイノベーションのスピードを押し上げています。
3.政策と市場の連動性
政府・企業・大学が政策設計段階から連携し、国家戦略として技術革新を推進している点で、他国の都市と比べても制度的整合性が高いといえます。
世界で「稼げている地域」に共通する5つの条件

いずれの地域も、単に経済規模が大きいだけではなく、「外部から人・資金・情報を呼び込み、持続的に付加価値を生み出す」という点で共通しています。次に、この3地域に共通する成功の構造を、5つの観点から整理します。
① 明確なビジョンと政策の一貫性
いずれの地域も、単年度施策ではなく、長期的な政策ビジョンと測定可能な目標(KPI)を設定し、政策の一貫性を維持しています。
シリコンバレーでは、郡・市が財政データや経済指標をオープン化し、エビデンスに基づく政策運営を徹底。産業振興と財政基盤強化を一体で捉える設計が特徴です。
ミュンヘン/バイエルン州は、「Innovation Agenda 2030」により、産業・研究・人材育成を横断的に支える仕組みを整備。政策の継続性と安定性が企業の投資を呼び込みます。
テルアビブは国家レベルでイノベーションを戦略化し、イノベーション庁が一元的に資金・制度を供給。都市と国の方針が明確に連動しています。
いずれも、「どこを目指し、何を測るのか」が明確で、長期ビジョンと短期成果を両立させている点が共通しています。
② 企業=価値創出、自治体=環境整備、商工会・団体=橋渡し
3地域の成功を支えるのは、官・民・学(商工会・団体を含む)による水平的な連携構造です。
企業は、技術開発・事業化・輸出によって直接的な価値創出を担い、
自治体・州政府は、インフラ整備や規制緩和、土地・実証環境の提供を通じて活動基盤を整備。
商工会・団体は、企業・行政・大学間のマッチングや政策提言、データ提供による合意形成を支援します。
このように、各主体が自律的でありながら補完的に機能することが、政策と市場を結びつける鍵となっています。
③ 人材・資金・情報の循環システム
3地域はいずれも、人材・資金・情報が絶えず循環するエコシステムを形成しています。
1.大学や研究機関が中心となり、アクセラレーターやベンチャー支援プログラムを通じて、研究成果を迅速に事業化するルートが整備されています。
2.ベンチャーキャピタルや公的支援によって、シードからレイターステージまで切れ目のない資金供給が行われ、Exit後には再投資が地域内に戻る「資本循環」が生まれています。
3.イベント、ピッチ、データベース、研究連携などを通じ、情報共有が制度化されている点も共通しています。
結果として、挑戦のハードルが低く、失敗しても再挑戦できる環境が持続的なイノベーションを支えています。
④ 外部との接続性――海外市場・グローバルネットワークとのつながりを意識
3地域の成長は、外部との開かれた接続性によって加速しています。
- シリコンバレーは世界中から企業・人材・資本が流入する国際的ハブ。
- ミュンヘン/バイエルン州はEU市場へのアクセス拠点として、製造業・研究・輸出が相互に結びついています。
- テルアビブは国内市場が小さいため、早期からグローバル展開を前提に設計されており、国際VCや多国籍企業のR&Dセンター誘致を積極的に行っています。
共通するのは、海外との往来を前提とした制度設計――ビザ、言語、税制、知財、研究提携、グローバル資金――が最初から意識されていることです。
⑤ 文化的背景――失敗を許容する風土と、オープンなコミュニケーション
最後に、これらの地域を支える根底には、文化としての「挑戦の許容度」があります。
- シリコンバレーでは、失敗は「学習」とみなされ、再挑戦が評価される文化が根付いています。
- ミュンヘン/バイエルン州では、長期的視点と品質・信頼を重んじる文化のもとで、協調と透明性が確保されています。
- テルアビブでは、俊敏で実用的な行動文化が根付き、起業・撤退・再挑戦が極めて短いサイクルで回っています。
また、情報共有や議論がオープンに行われ、意思決定のスピードと透明性を高めています。
この文化的基盤が、制度や政策の「柔軟性」と「持続性」を支える土台になっています。
稼げる地域は「システムとしての挑戦力」を持つ
3地域の共通点を貫く本質は、「システムとして挑戦を支える設計」にあります。明確なビジョン、役割分担、循環構造、国際接続、そして挑戦を肯定する文化。これらが一体となることで、「外部資源を呼び込み、内部で付加価値を生み出す」構造が成立しています。
日本の自治体や企業が参考にすべきは、単に産業を育てることではなく、挑戦が継続的に生まれる“仕組み”を制度としてつくることです。それが、地域が「稼ぐ力」を持続的に高めていくための、最も確実な道筋といえるでしょう。
日本への示唆:企業・自治体・商工会がすべきこと

世界の「稼げている地域」に共通しているのは、“挑戦を支える構造”が地域の仕組みとして存在していることです。それは単に補助金や規制緩和を行うことではなく、企業・自治体・商工会など、地域を構成するプレーヤーがそれぞれの役割を理解し、互いに補完し合う連携構造を築いているということです。
この章では、日本の地域経済が持続的に価値を生み出していくために、3つの主体が取るべき方向性を整理します。
【企業】地域課題をビジネスチャンスとして捉える
今後、日本企業が注目すべきは、地域固有の課題を“市場”として再定義する視点です。高齢化、人口減少、気候変動、インフラ老朽化――これらは課題であると同時に、新しいビジネス領域でもあります。
課題を解決する技術・サービスを地域発で展開することが、次の成長源になります。例として、エネルギーマネジメント、スマート農業、地域医療DX、防災テック、観光・文化資源の再編集などが挙げられます。
地域企業同士の協業・共創を促すことで、単独では難しい新規事業を生み出すことが可能です。 特に中小企業にとっては、「地域外の企業・大学・団体」とのネットワーク構築が事業機会の拡張に直結します。
シリコンバレーやテルアビブのように、“課題を見つけ、解決して、事業に変える”循環を日常的に行う文化を社内に根付かせることが重要です。
つまり、「地域にある問題を解決すること」が、そのまま「地域で稼ぐ仕組み」に変わる――これが日本企業に求められるビジネスモデル転換の方向です。
【自治体】「支援」よりも「挑戦を促す環境設計」へ
これまで多くの自治体は、「補助金」「規制緩和」「誘致支援」などの制度整備を中心に取り組んできました。しかし、世界の稼げる地域に共通するのは、“挑戦できる環境のデザイン”に重点を置いている点です。
たとえば、シリコンバレーでは自治体がデータ・インフラ・実証環境を開放し、民間が自由に試せる「フィールド」を提供しています。
ミュンヘンでは、大学・企業・行政が共に参加する“学びと実践の場”が整備され、アイデアから事業化までの距離が短いといえます。
テルアビブでは、市や国家が挑戦の失敗を受け止める仕組み(再チャレンジ制度・再投資文化)を構築しています。
日本の自治体に求められるのは、制度の量ではなく、「挑戦を誘発する設計」です。そのためには次の3つが鍵になります。
- 実証の場をつくる:安全・環境・交通・防災などの分野で、小規模でも企業が試行できる空間を整備する。
- データを開放する:地域課題を“見える化”し、企業・大学・市民がアクセスできる仕組みを整える。
- 挑戦者を守るルールを設計する:失敗時の救済・再挑戦を制度的に保障する(例:再チャレンジ補助、再雇用支援など)。
このように、「制度を増やす」よりも「挑戦しやすくする」ことこそ、次世代の地域政策の核心となります。
【商工会】「人材育成」と「企業間連携」のハブへ
商工会・商工会議所は、地域経済における中核的な存在です。しかし今後は、単なる補助金や税務相談の窓口にとどまらず、地域の産業共創を支える“知的ハブ”としての進化が求められます。
(1) 人材育成機能の強化
中小企業に不足しているのは、資金よりも「デジタル・経営・共創」の人材です。商工会が主導して、DX・マーケティング・事業承継・スタートアップ支援などの実務型研修や伴走支援を提供することが、地域経済の底上げにつながります。
(2) 企業間連携の促進
商工会は、地場産業と外部企業・大学をつなぐ“橋渡し役”としての役割を強化すべきです。異業種交流・共創プロジェクト・共同ブランドづくりなど、地域企業が単独では難しい領域をサポートする立場に立ちます。
(3) データ・ナレッジの蓄積・共有
地域企業の経営データや成功事例を体系的に分析し、次の挑戦者に還元することで、“地域知の継承”を可能にします。商工会が「学習する組織」へと変わることが、地域イノベーションを持続させる重要な条件です。
商工会が「企業支援機関」から「地域産業を育てる仕組みの設計者」へ――その変化が、地域経済の未来を左右します。
地域が“挑戦を仕組みに変える”とき、日本は強くなる
日本が今後、地域から持続的に価値を生み出すためには、「制度を整える」から「挑戦を仕組みにする」への発想転換が不可欠です。
- 企業は、地域課題を解決することを“利益の源泉”として捉え、ビジネスモデルを再構築する。
- 自治体は、規制や補助の整備よりも、挑戦しやすい社会的・心理的インフラを設計する。
- 商工会は、知の拠点として人材・情報・資本の循環を促すハブへ進化する。
こうした三者の連携が、「挑戦する地域」を生み出し、それがやがて、「稼げる地域」として世界と競い合う基盤となるのです。
まとめ:稼ぐ地域の共通項は「共創の場づくり」

世界で「稼げている地域」に共通して見えるもの――それは、優れた企業や人材の存在そのものではなく、彼らが互いに学び合い、挑戦し、価値を生み出す“共創の場”が制度として存在していることです。
地域の経済力を支えているのは、単発の成功事例や偶然の集積ではありません。それぞれの地域が、自らの強みを再定義し、企業・自治体・商工会などの主要プレーヤーが、自分の強みを他者の強みと結びつける仕組みを築いている点にあります。
「共創の場」は、地域の“再定義”から始まる
「共創」とは、単なる協力や連携ではありません。地域が抱える課題を起点に、“何を新しい価値として生み出すか”を共に考え、実装していくための仕組みを意味します。
- シリコンバレーでは、大学・企業・自治体がオープンデータと資本を共有しながら、新しい産業を創出しています。
- ミュンヘン/バイエルン州では、伝統産業と先端技術を掛け合わせることで、「製造」から「知の創造」へと発展しています。
- テルアビブでは、国家戦略のもと、スタートアップと大企業、研究機関が一体となって新技術を社会実装しています。
いずれの地域も、自らの資源・人材・制度を静的に守るのではなく、動的に再構築することによって「共創の場」を維持しているのです。
「個の力」ではなく、「仕組みの力」が地域を強くする
「稼げる地域」は、優秀な起業家や大企業の存在だけで成立しているわけではありません。
むしろ、仕組みとして“誰もが挑戦できる環境”を持つことこそが、本当の強さです。
- 企業は、自社の技術・ノウハウを地域全体の課題解決に応用し、地域から次の市場を創る。
- 自治体は、産業支援を“政策”ではなく“実験場の提供”と捉え、挑戦の土台を用意する。
- 商工会は、企業・大学・地域団体をつなぐ「共創ハブ」として、人材と知識の循環を支える。
この三者の相互補完関係が、地域を単なる「地理的単位」から「創造的な経済圏」へと転換させていきます。重要なのは、「誰が主導するか」ではなく、「どう仕組みを共に動かすか」です。
共創の仕組みづくりが、持続的な「稼ぐ力」を生む
共創の場は、単発のイベントや官民連携の掛け声だけでは機能しません。必要なのは、構造的・制度的な設計です。
- データを共有する仕組み(地域インデックス、オープンガバメント)
- 挑戦を可視化する仕組み(実証フィールド、成果指標の公開)
- 人材が集まり育つ仕組み(教育・研修・アクセラレーター)
- 資金が循環する仕組み(地域VC、共同出資ファンド)
これらを一体化した“共創エコシステム”を設計することが、地域が持続的に稼ぐための核心です。地域経済の未来を左右するのは、特定企業の成否ではなく、挑戦が繰り返される構造をいかにつくるかにあります。
稼ぐ地域は「仕組みで挑戦を支える地域」
最終的に、「稼げる地域」と「そうでない地域」を分けるのは、個人や企業の能力差ではなく、仕組みの差です。
「人が挑戦し続けられる環境」
「挑戦が次の挑戦を生む仕組み」
「異なる主体が共に価値をつくる場」
この三つを持つ地域こそ、長期的に稼ぎ続ける力を持ちます。それは単なる経済成長ではなく、社会としての創造力の持続を意味します。
また、地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。
- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略
こちらの記事「消滅可能性自治体からの脱却戦略:16事例から学ぶ」および「どうする!?湯河原
消滅可能性自治体脱却会議」も併せてお読みいただくことをお勧めします。また、以下のホワイトペーパーのダウンロードもお勧めします。
「消滅可能性自治体とは?
消滅可能性自治体の危機と対策は?」の
ホワイトペーパーをダウンロードする
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略