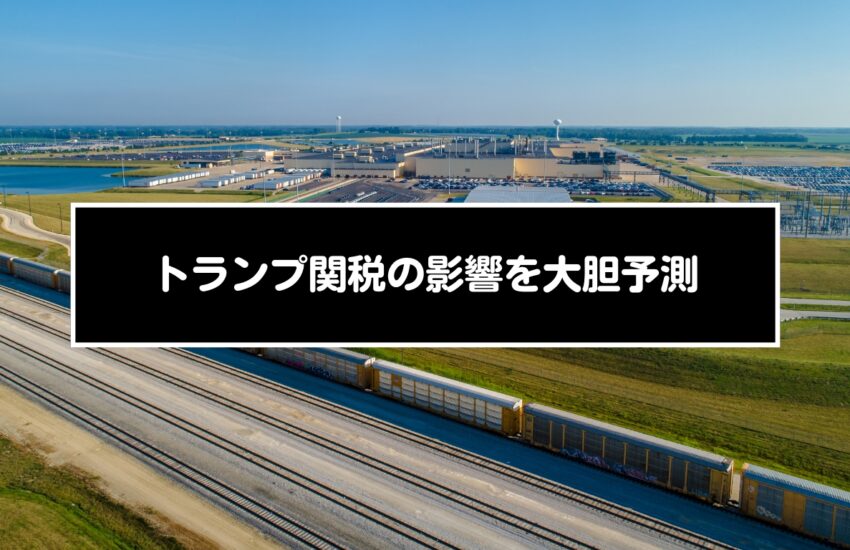トランプ政権の追加関税は、国内回帰と雇用創出を掲げています。しかし、過去の施策を見てもその実効性には疑問が残ります。企業の投資判断、労働力不足、コスト構造――さまざまな要因が絡む中、今回の関税は何をもたらすのか。本稿ではその現実と未来を読み解きます。
1. シナリオ背景と前提

1-1. 関税政策の歴史的教訓
過去に実施された鉄鋼・アルミへの追加関税(2018–2020年)では、期待された製造業の国内回帰は実現せず、むしろ関連部門での雇用が減少しました。最近のAMT協会(※1)の調査によれば、関税導入後に実際に米国内での生産再開を決断した企業はわずか7%にとどまり、残る93%は「在庫を積み増して関税負担の影響を緩和する」「第三国経由の輸入ルートを確保して関税を回避する」といった手段を選択しました。この背景には、米国内での生産コストの高さと、グローバルに分散したサプライチェーンを一時的にでも縮小できないという供給リスク回避の二律背反があり、関税だけでは企業の投資判断は動かせないことを示しています。
※1:AMT協会は「Association for Manufacturing Technology」という、米国の工作機械や製造技術企業を代表する業界団体
1-2. 米国のコスト構造――総人件費と労働力不足
米国製造業における労働コストは、基本賃金だけでなく、医療保険料、退職給付、労働訴訟リスクへの対応費用などを含めた総人件費として計算すると、平均時給42ドルに達し、OECD加盟34カ国中ワースト2位に位置しています。この膨大なコスト負担が、企業の国内投資をためらわせる最大要因です。
加えて、Deloitteの予測によれば、今後10年で190万人規模の技能労働者不足が生じるとされており、熟練工の採用・育成が追いつかない事態が顕在化しています。同時に、低賃金労働力の確保を期待された不法移民の活用も、近年各州で法執行が強化された結果、摘発リスクや労務トラブルの増加から採用後の定着率が低下し、雇用管理コストや法的リスク対応費用がさらに膨張しています。このような人材コストとリスクの増大により、企業は国内での生産拡大を一層困難に感じているのです。
国別の総人件費比較(時給換算)
| 国名 | 総人件費(時給換算) |
| メキシコ | 5.5ドル |
| インドネシア | 3.2ドル |
| 米国 | 42ドル |
2. 関税実施の初期インパクト

企業の対応行動と投資シフト
関税負担を理由に米国本土への全面的な生産回帰を選んだ企業は極めて限られ、ブルームバーグの分析によると、過去2年間で新規大型工場計画は8件にとどまり、そのうち民間主導の純投資はわずか2件でした。大半の企業はコスト圧迫を緩和するため、以下の手段を採用しました:
🔵ネアショアリングの加速
メキシコやカナダへ最終組立工程を移転し、米国本土での労働コストを回避。
🔵在庫積み増し
関税影響を吸収するため、主要部品・完成品の在庫を増加。
🔵自動化投資の強化
日本経済新聞が報じたところでは、企業は前年比約15%増の産業用ロボットを導入し、現地の人件費高騰を部分的に相殺しました。
これらの対応は短期的なコスト吸収策として一定の効果を上げたものの、米国内製造の本格回帰には至らず、サプライチェーンの抜本的再編は見送られる結果となりました。
3. 補助金・助成金政策——「赤い州」への利益誘導

3-1. Made in America Fundの偏在と背景
政権は関税効果の限界を補うため、2025年末に総額800億ドルの「Made in America Fund」を創設しました。ワシントンポストによれば、この資金は国内製造業再建を名目にしつつ、共和党支持率の高い州に約7割が集中配分されており、中西部や南部の「赤い州」での恩恵が顕著です。この配分は、地元有権者の支持固めと選挙戦略上の意図が背景にあり、必ずしも雇用創出効率を最優先したものではありませんでした。
3-2. 効果と課題
ブルームバーグの分析によると、Made in America Fundの支援を受けたプロジェクトでは、1億ドルあたりの平均雇用創出数が約8人にとどまり、補助金が期待されたほどの波及効果を発揮していませんでした。その主因は、短期的な設備投資や改修には資金が充てられたものの、長期的な操業拡大や労働者の技能研修といった根幹強化への資金配分が不十分であったためです。
また、半導体分野を対象としたCHIPS Actには、厳格な国内雇用要件や知財保護規定が盛り込まれており、フィナンシャル・タイムズによれば、これらが投資判断を遅延させ、予定していた2026年末までの生産開始スケジュールを大幅に後ろ倒しにする結果となりました。CHIPS Actは、国内でのチップ製造能力を強化するための包括的支援スキームとして注目されましたが、運用面の複雑さと高コスト要件が企業の参入障壁となり、地域的偏在をさらに拡大させる一因となっています。
4. 金融政策:パウエル退任から利下げ圧力へ

2026年5月のパウエルFRB議長退任後、後任としてハト派が指名される可能性が高いとされ、ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、連邦基金金利は2.5%から1.75%へ段階的に引き下げられる見通しです。
この利下げ圧力は、米国債利回りの低下を通じて住宅ローン金利と企業の借入コストを抑制し、株式市場や不動産市場を活性化させる一方で、ドルインデックス(DXY)が103から95へ下落しました。ドルインデックスは米ドルを主要6通貨(ユーロ、円、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン)に対して算出した指数であり、ブルームバーグによれば、ドル安は輸入品の価格を相対的に上昇させ、追加関税と相まって輸入インフレをさらに加速させる要因となっています。
5. 分配インパクト——富裕層と中低所得層の二極化

ブルームバーグによれば、2026年にかけて資産価格の高騰が進み、S&P500指数は4,500から5,300へ上昇すると予測されています。一方、同レポートでは、中央値世帯の実質可処分所得が▲2.1%悪化すると見込まれており、格差拡大の深刻さを浮き彫りにしています。
株式や不動産など資本市場アクセスを持つ富裕層は資産インフレの恩恵を受けたものの、食料や家賃といった生活必需品の価格上昇は中低所得層の購買力を直撃しています。政権は今後、大手小売チェーンを名指しで独禁調査に踏み切ることで物価高の責任転嫁を図る可能性が高いと見られています。
また、ニューヨーク・タイムズによれば、報復関税を仕掛けてくるEUや中国などの貿易相手国にも責任を転嫁し、『外部の圧力が物価高を引き起こしている』という論調で支持層の結束を図る戦略を採用すると予想されています。
6. 2026年中間選挙の帰趨

ニューヨーク・タイムズによれば、2026年の中間選挙では治安不安や経済ナショナリズム、移民問題が主要争点となり、共和党が下院で15議席、上院で3議席を増やすと予測されています。この結果、トランプ関税による具体的な効果が期待できなくとも、関税や補助金政策は少なくとも2028年まで継続する公算が大きいと見られています。
一方、民主党が再建を図るには以下の要因が大きな障壁となっています:
🔵資金調達力の低下
民主党系PACの資金流入が前回比で約20%減少しており、選挙キャンペーン資金に大きな制約が生じています。
🔵党内分裂とイデオロギー対立
進歩派と中道派の間で政策の優先順位が根本的に異なり、その対立は党の統一戦略に大きな混乱をもたらしています。進歩派は「グリーン・ニュー・ディール」「メディケア・フォー・オール」「富裕層への増税」など、急進的かつ包括的な改革を求める一方で、中道派は「財政健全性」「段階的な制度改革」「現実的な移民管理」の重要性を訴えています。この結果、気候変動対策や医療・社会保障の拡充、税制改革などをめぐる議論が党内で膠着し、キャンペーンのメッセージが有権者に対してぶれる状況です。Washington Postによれば、こうした内紛が有権者に「民主党は一枚岩ではない」という印象を与え、信頼感の低下につながっていると報じられています。
🔵地方組織の弱体化
2024年の州・地方選挙での敗北により、組織基盤が後退し、草の根運動やボランティア動員力が著しく低下しています。
これらの要因が重なり、民主党の巻き返しは容易ではなく、共和党優位の構図が当面続く見通しです。
7. マクロ指標ベースライン予測(2025Q4→2026Q4)

エコノミスト調査やFRBの公表資料を踏まえた予測モデルによれば、2025年第4四半期から2026年第4四半期にかけて主要マクロ経済指標は以下のように推移すると見込まれています。
🔵実質GDP成長率
2025Q4の+1.8%から、2026Q4には+0.6%へ減速する見通しです。これは高インフレと金融緩和の逆効果が同時に作用する環境が背景にあります。
🔵消費者物価指数(CPI)上昇率
2025Q4の+4.9%から、2026Q4には+5.3%へさらに加速すると予測されています。追加関税とドル安による輸入コスト上昇が主因です。
🔵失業率
2025Q4の4.2%から、2026Q4には5.5%へ上昇します。製造業の回帰失速とサービス業の雇用削減が影響しています。
🔵連邦基金金利(FF金利)
2025Q4の2.5%から、2026Q4には1.75%へ引き下げられる見通しです。金融緩和政策の継続が背景です。
🔵S&P500指数
2025Q4の4,500ポイントから、2026Q4には5,300ポイントへ上昇すると予測されます。資産インフレの影響です。
🔵住宅価格指数
2025Q4の145から、2026Q4には162へ上昇すると見込まれます。低金利環境が需要を支えます。
これらの予測は90%信頼区間の中央値であり、地政学リスクや政策変更によって変動する可能性があることに留意が必要です。
8. コスト構造の誤算

トランプ政権による追加関税を契機とした「米国製造業の国内回帰」は、政治的パフォーマンスとして掲げられる一方で、根本的なコスト構造の高さが作用し、実態としては限られた業種にしか恩恵が及んでいません。
まず、米国の総人件費は時給42ドルに達し、OECD加盟34カ国中ワースト2位という水準です(医療保険料、退職給付、訴訟リスク対応費用を含む)。これに加え、教育・訓練コストが高いため、技能労働者の育成に長期間と高額な投資を要します。結果として、高付加価値かつ自動化投資の効果が大きい半導体、自動車部品など一部の戦略的分野に限り補助金や関税による誘因が働くものの、一般的な製造業ではコスト競争力が大幅に後退しています。
ロイター通信によれば、原材料から部品調達まで海外依存度が高いサプライヤーネットワークの断裂が進み、最終組立のみを米国内で行う「外国部品の組立モデル」が定着。こうしたモデルは輸送コスト増や在庫圧縮ニーズを生み、価格競争力の低下を加速しています。
このコスト構造の硬直性は、米国企業の競争力を弱める結果を招き、長期的には国内雇用の縮小をもたらす見込みです。大手メーカーは名目上「国内回帰」を掲げて関係当局向けにアピールを行うものの、実際には人件費・教育コストの高さから回帰効果は限定的であり、雇用を維持するためにさらなる自動化や海外への生産移管を進めざるを得ない状況が続くでしょう。
以下は主な企業によるトランプ関税への対応についてみていきたいと思います。
TSMCアリゾナ
CIO誌によれば、TSMCはアリゾナ州に150億ドルを投資して先端2ナノメートル工場を建設しましたが、予想を上回る人材確保難と施設稼働率の低迷に直面しています。
🔵技能労働者の不足
現地で求められる半導体製造技術者が圧倒的に不足し、台湾本社から約200名のエンジニアを派遣して教育を支援したものの、現地雇用コストは30%高く、人件費負担が年間2億ドル超増加。
🔵供給網の断絶リスク
専門材料や蒸着装置部品の一部を海外調達する必要があり、コロナ以降の物流遅延で部品到着が最大6か月遅延。予備在庫の積み増しコストは5億ドルに膨張。
🔵運用コストの高止まり
工場の電力・水処理コストが予想比20%上振れ。地方自治体との税制優遇交渉も長期化し、ROI回収期間が当初想定の10年から12年に伸びる見込み。
これらを受け、今後TSMCは当局向けの“米国回帰”アピールを続けるものの、実際の生産シフトは限定的にとどまる見通しです。労働・教育コストの高さが恒常的に重荷となり、ポーズ的な建設に終始する可能性が高いと予想されます。
自動車ビッグ3(フォード、GM、ステランティス)
🔵フォード
・EV工場計画の見直し
元々2025年末までにミシガンで50GWhクラスのバッテリー工場を新設予定でしたが、賃金高騰により賃金ベースを同比20%削減する再交渉を実施。
・労働組合との衝突
UAW(全米自動車労組)との賃上げ協議が合意に至らず、一時ストライキ期間が3週間発生。損失推定5億ドル。
・メキシコ移転の加速
現地の労働コストが米国の1/6であることから、EVプラットフォーム組立工程をカリフォルニア計画からメキシコ工場に70%移転を決定。
🔵GM
・完全自動化ライン導入
ミシシッピ州の工場にロボット比率90%の製造ラインを新設。導入費用は20億ドル。
・教育投資の限定的効果
技能工研修に年間1,000万ドル投じたが、最新AR/VRトレーニングプログラムの定着率は30%未満。
・調達コストの増加
米国内サプライヤーからの部品調達価格が前年比15%上昇し、原価ベースに占める調達コストは50→58%へ増加。
🔵ステランティス
・補助金交渉戦略
イリノイ州とテネシー州で計12億ドルの州政府補助金を獲得する一方、2025年末に工場一時停止を通達し助成条件を優位に交渉。
・ハイブリッドモデル導入
米国工場における作業者は製造ラインとロボット監視を兼務するハイブリッドモデルを試行。結果、技能継承時間は従来比30%短縮。
・コスト比較分析
同一生産ユニットをメキシコで生産した場合のコストは米国比で40%低いとの社内調査を公表し、政治的アピールに利用。
これら自動車大手3社の動きも、政府へのパフォーマンスとして米国回帰計画を掲げつつ、実際にはコスト競争力の観点から生産移管の大半を海外に依存し続けるという傾向が鮮明です。高い労働・教育コストが継続的な製造回帰を阻むという構造的制約は変わらず、名目上は国内回帰を演出しても実態は限定的にとどまるでしょう。
ロイター通信によれば、EUや中国による報復関税が発動された場合、対象品目の輸出量が10〜15%減少し、2026年には米国企業の輸出関連収益が平均で5〜7%悪化すると予測されています。従来であればコスト削減のために即時的な国内レイオフが行われるところですが、ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、政権への“国内回帰”のアピールを維持するため、企業は当面国内でのレイオフを抑制し、代わりに海外拠点の人員削減や閉鎖を進める戦略を採用すると見られます。
この結果、海外でのリストラが先行し、国内の雇用は一時的に守られる一方で、グローバル競争力の低下が長期的な課題として残ることが懸念されます。
9. 金融市場と家計への影響

利下げ観測による金融緩和期待は短期的に資産インフレを助長しましたが、ブルームバーグによれば、この政策の本質は物価全体の上昇を加速させるものであり、特にトランプ政権の追加関税が引き起こした輸入インフレと相まって、2026年には消費財価格が前年比で6.5%上昇すると見込まれています。
中間層以下の家計は株式や債券といった資産運用の恩恵を受ける余裕がほとんどなく、食料、エネルギー、住宅といった生活必需品価格の高騰が家計を直撃しています。米国農務省のデータによれば、2026年には食料品の平均価格が前年比で7%上昇し、可処分所得の10%以上を食費が占める家庭が増加しました。また、住宅コスト指数も+8.2%と高止まりし、中間層以下は所得の大半を家計維持に費やす状況が常態化しています。
さらに、エネルギー価格の上昇は公共料金にも波及し、エネルギーコストが世帯支出の15%を超えるケースも増えつつあります。これらの価格圧力により、中間層以下の実質生活水準は2025年比で約3%悪化すると試算され、可処分所得の減少が消費支出の抑制と家計負債の増大を招いています。