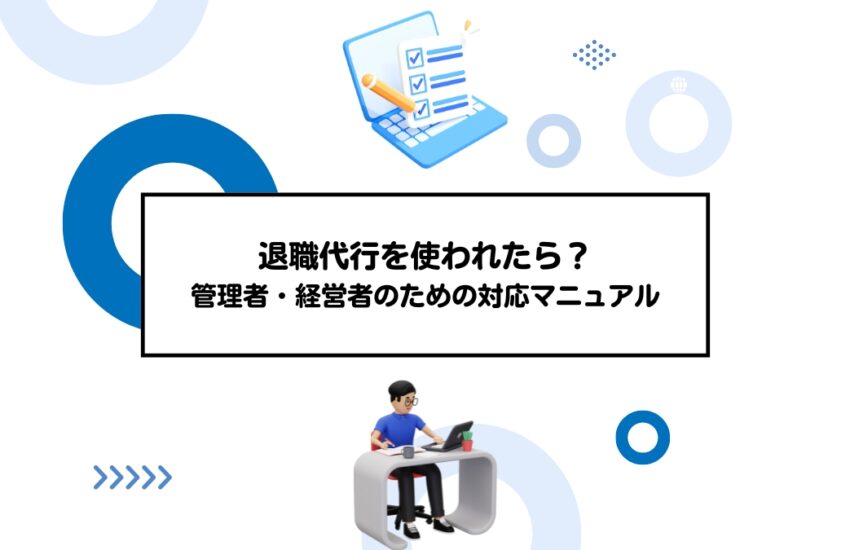最近、従業員が退職代行を利用するケースが増えています。突然の連絡で驚かれる管理者や経営者も少なくないでしょう。このような状況に直面した際、どのように対応するべきかを知ることは、企業としての円滑な業務運営や信頼性を保つために重要です。本記事では、退職代行の基本的な仕組みや利用される背景を整理し、対応時に考慮すべきポイントや具体的なステップを解説します。円滑な退職対応を実現するための参考としてご活用ください。
退職代行とは?

退職代行とは、従業員本人の代わりに退職手続きを代行してくれるサービスのことを指します。従来、退職はあくまで「従業員本人が会社に意向を伝え、手続きを進める」ものでした。しかし近年では、「職場に行きづらい」「上司に言い出しづらい」「退職意思を伝えると引き留められそうで面倒」といった理由から、第三者に退職の手続きを一括で依頼するケースが増えています。
退職代行サービスの主な特徴は次の通りです。
(1)退職連絡の代行
本来は従業員が直接会社に伝える退職意思を、退職代行業者が代行する。
(2)書類手続きサポート
退職届・離職票などのやり取りについて、メールや郵送でサポートしてくれることもある。
(3)心理的負担の軽減
直接対面や電話をしなくてもよいため、従業員の心理的負担が軽くなる。
従業員が退職代行を利用する背景

管理者や経営者からすると、「なぜ退職代行などを使って突然退職を言い渡してくるのか?」と疑問に思うこともあるかもしれません。退職代行を利用する主な背景には、4つの要因が考えられます。
(1)上司や経営者とのコミュニケーション不安
・対人関係が苦手で直接言い出しづらい
・パワハラまがいの環境で言い出しにくい
・退職の相談をしても真摯に取り合ってもらえなかった
(2)引き留めやトラブル回避のため
・会社からの引き留めが強く、退職がスムーズに進まない
・退職交渉が長引いたり、ネガティブな対応を受けるリスクを避けたい
(3)手続きに関する無知・不安
・必要書類の提出や、社会保険、年金手続きなどの詳細をよく知らない
・退職後に不利にならないように確実に対応したい
(4)ストレスの軽減
・大きなストレスを抱えており、そもそも出社できない
・メンタル的に追い詰められていて、関わりを避けたい
退職代行を使われた場合の基本的な対応方針

退職代行を通じて連絡があった場合、経営者や管理者はまず「従業員本人からの意思表示があった」という事実を受け止める必要があります。退職自体は労働者の自由な意思によって行使できる権利であり、原則として会社はこれを認めざるを得ません。
3.1 従業員本人の意思確認を最優先にする
退職代行があったということは、従業員本人が退職の意思を固めている可能性が高いです。実際に本人と直接話したいところですが、退職代行を使う方は「直接やりとりを避けたい」と考えていることが多いです。したがって、法的に問題のない範囲で、退職の意思を尊重する必要があります。
3.2 退職の流れの確認
退職の意思表示日をいつとするのか、退職日をどう設定するか、引き継ぎや貸与物の返却などの事務手続きをどう進めるかを、退職代行業者や本人(もし連絡可能であれば)と整理しましょう。
3.3 対応マニュアルの整備
企業として、退職代行を利用された場合のフローを事前に作成しておくとスムーズです。担当者、手続き、連絡方法などをマニュアル化しておくことで、慌てずに対処できます。
具体的な対応ステップ

ここでは、退職代行利用の連絡が来た際に、管理者や経営者が踏むべき具体的なステップを紹介します。
4.1 本人意思の確認・退職日程の調整
(1)書面またはメールで退職意思を確認する
退職代行業者はあくまでも「連絡を代行する存在」なので、できれば書面やメールなど正式な形で本人の意思を確認します。もっとも、本人と連絡がつかないケースも想定されるため、業者からの通知自体を本人の意思とみなす場合も少なくありません。
(2)就業規則の確認
就業規則に定められている「退職の手続き期間」や「退職届の提出期限」などを確認し、従業員の退職日をどのように設定するか判断します。法律上は民法で「2週間前通知で退職可」などの規定があり、就業規則や労働契約によってはさらに詳細が設定されていることがあります。
4.2 貸与物の回収や引き継ぎ
(1)貸与物(PC、制服、スマホ、社員証など)の返却方法
従業員が出社しない状態での返却方法を検討しましょう。郵送での返却や、指定日時にオフィスに置いていくなどの手段があります。
(2)引き継ぎ事項の整理
業務内容の洗い出しや顧客とのやり取りがある場合、引き継ぎが必要です。退職代行の利用者は往々にして出社しない場合が多いですが、可能であればメールや文書、クラウド上の共有ドキュメントなどで簡単な引き継ぎを依頼します。事業運営上必要な情報を漏れなく回収することが重要です。
4.3 給与や社会保険等の手続き
(1)未払い給与や立替金の精算
未払いの給与や出張費の立替金などがあれば速やかに精算します。法定の支払日を守りつつ、退職手続きに合わせて行います。
(2)社会保険、年金の手続き
健康保険、厚生年金、雇用保険などの資格喪失手続きを漏れなく行います。退職者には離職票の交付が必要です。退職代行業者に書類の送付先の確認をするなどの連携が必要になる場合があります。
4.4 コミュニケーション方針
(1)直接連絡をしてよいか確認
法的には、本人の意思を無視してしつこく連絡するのは避けるべきです。退職代行業者を通じて、「必要最小限の連絡で対応を進めたい」という希望があるかを確認します。
(2)無理な引き留めや説得はNG
退職の自由は労働者に保障されているため、無理な引き留めはトラブルやハラスメント問題へ発展しかねません。退職の理由を知りたい場合でも、あくまで希望があればヒアリングする程度に留めます。
企業側が注意すべきリスクと対策

退職代行を使われるケースが増えると、企業側のマイナスイメージにもつながりかねません。また、退職手続きや人手不足の対策、法的リスクへの対処なども重要になります。
(1)職場環境の問題点が表面化する可能性
退職代行を使われるということは、本人が直接伝えられないほど追い詰められている、もしくはコミュニケーションに問題がある可能性があります。
対策: 社内のハラスメント対策、相談窓口の整備、メンタルヘルスケアの充実などを図り、早期に問題を把握できる体制を作る。
(2)人手不足や業務への影響
突然の退職により、人手不足や業務の滞りが発生するリスクがあります。
対策: 業務のマニュアル化や、担当者が複数人で業務を把握する体制、適切な引き継ぎ手順の整備を日頃から行う。
(3)法的リスク
退職金や給与の未払い、社会保険の手続き遅延などによるトラブルが起こると、労働審判や訴訟に発展する可能性もあります。
対策: 人事担当や社会保険労務士などと連携し、法定手続きを確実かつ迅速に行う。就業規則の整備や適切な労務管理に留意する。
(4)企業のイメージダウン
従業員が退職代行を使うということは、「会社が辞めにくい環境だった」「適切に退職をサポートしてくれなかった」と外部から見られる可能性があります。
対策: 普段から円満退職の制度を整備し、退職しやすい環境・辞める際の相談ルートを整えることで、従業員が退職代行に頼るリスクを下げる。
「本人確認」や「なりすまし」への対応
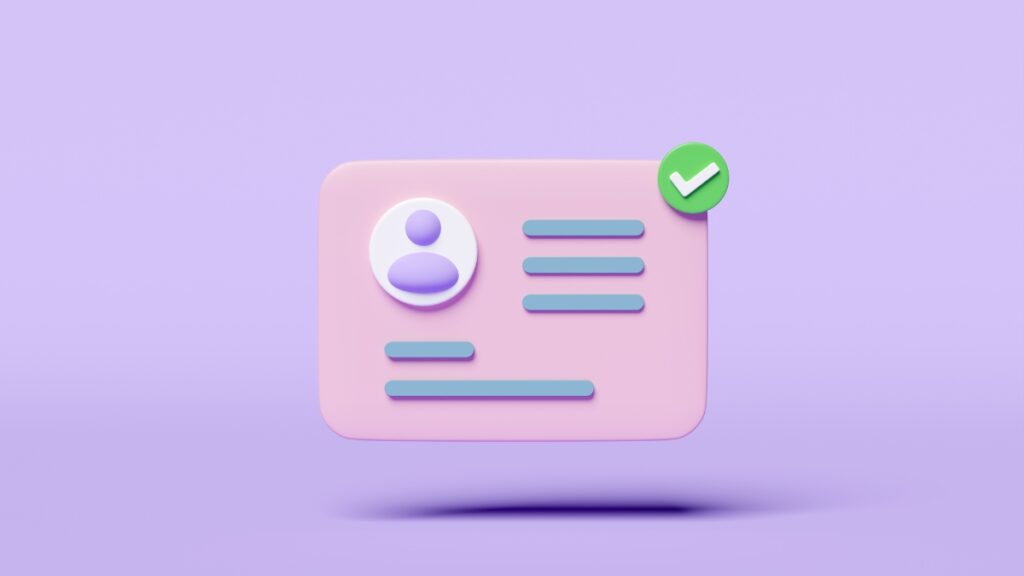
退職代行を利用する人が増え、代行業者からの連絡が一般的になりつつあります。しかし、「本当に本人の意思なのか」や「なりすましの可能性がないか」といった懸念がある場合もあります。こうした場合には、法的リスクを最小限に抑えつつ、公平でスムーズな退職手続きが進められるよう、次の対応を検討することが重要です。
1. 本人確認を徹底する
退職代行業者が本当に従業員本人から依頼を受けているか確認する手順を導入します。
(1)書面または電子的証拠の提出を求める
-
- 退職代行業者からの連絡時に、従業員本人からの委任状(署名入り)やメールのスクリーンショットを要求する。
- 委任状の例:
「私は○○(従業員の氏名)が、貴社に対して退職の意思表示を行うにあたり、退職代行サービス○○(業者名)を正式に代理人として委任します。」
※日付、署名を含むもの。
(2)本人確認のための書類提出
-
- 退職届または本人確認書類(運転免許証、社員証のコピーなど)の提出を求める。これにより、第三者によるなりすましのリスクを減らします。
- デジタルでの提出を許可する場合、PDFや画像形式で受け取ることも検討。
(3)本人へ確認する機会を作る(可能な範囲で)
-
- 業者を通じて「退職手続きのために最低限本人と連絡を取る必要がある」と伝え、本人と一度メールまたは郵便でのやり取りを行う。
- 「退職意向確認書」などの簡易書面に署名・返送を求める方法も有効です。
2. 業者の信頼性を確認する
退職代行業者が実際に信頼できるサービスかを判断するために、以下を検討します。
(1)代行業者の連絡先確認
-
- 業者の正式な連絡先(住所、電話番号、担当者名)を確認し、必要に応じて事業登録の有無や会社概要を調べます。
- 不明瞭な連絡手段や匿名性が高い業者の場合は、慎重に対応します。
(2)弁護士監修かどうか確認
-
- 一部の退職代行業者は弁護士監修で運営しているため、法的なトラブルが起きにくい場合があります。
- 「弁護士が関与しているかどうか」を確認し、不明確な場合は追加書類や確認プロセスを求めます。
3. なりすましを防止するための具体的対応
(1)手続きの進行条件を設定する
-
- 退職手続きを進める前に、本人確認を完了させることを条件とする。
- 例:
「退職届の原本提出を確認でき次第、退職手続きに進む」
「本人確認書類を受領しない限り、手続きを進めない」など。
(2)退職手続き開始前にフォローアップ
-
- 業者経由で本人に向けて、確認メールまたは郵送物を送付し、返答を得る形を取る。
- 「この退職の意思は貴殿自身のものですか?」という確認メッセージを送信し、返信を記録します。
(3)退職後のトラブルを防ぐ契約書の整備
-
- 従業員本人からの正式な退職届がない場合、「退職後にトラブルが発生した場合の責任所在について」明確に記した誓約書を用意し、業者を通じて提出してもらう。
- 「私○○は、退職手続きに関して○○業者を通じて全ての連絡を行ったことを確認し、手続き完了後の異議申し立てを行わないことを誓約します。」など。
4. 社内手続きやルールの見直し
(1)退職時の対応プロセスをマニュアル化
-
- 退職代行を利用した場合の標準手順を明文化し、担当者が一貫した対応を取れるようにします。
(2)本人確認のフローを規定する
-
- 委任状、退職届、本人確認書類の提出方法や確認基準を社内規定に盛り込む。
(3)相談窓口の設置
-
- 退職代行を利用せずとも気軽に退職相談ができるよう、ハラスメント対策やキャリア相談窓口を設置することで、退職代行利用の抑制を図ります。
本人確認やなりすまし防止のポイント
退職代行業者からの連絡を受け入れる風潮が広がる中でも、本人確認やなりすまし防止を徹底することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。重要なのは以下の点です:
(1)本人確認手続きの明確化:書類提出や連絡方法を統一する。
(2)業者との適切な連携:業者の信頼性や提供書類を確認する。
(3)柔軟な対応方針:法律に準拠しつつもトラブル防止のための対策を取る。
(4)内部体制の整備:マニュアルや相談窓口を充実させ、従業員の安心感を高める。
これらの対策により、退職代行を利用する従業員への対応を円滑に進めつつ、会社の信頼性を守ることができるでしょう。
退職代行対処のためのチェックリスト

退職代行サービスから「従業員が退職を希望している」との連絡を受けた際、企業(管理者・経営者、人事担当者など)が取るべき対応を整理したチェックリストです。状況に応じて優先順位を付けながら、適切に進めてください。
1. 初動対応
(1)退職代行からの連絡内容を確認・記録する
-
-
- 連絡があった日時、連絡手段(メール・電話・FAXなど)、対応した担当者を記録する。
- 退職希望日の申し出があれば、その日時も確認しておく。
-
(2)従業員本人に関する情報をすぐに把握する
-
-
- 氏名、所属部署、役職、雇用形態、入社日、契約期間(有期の場合)など、人事ファイルやデータベースから基本情報をチェック。
-
(3)社内の担当部署・担当者に共有する
-
-
- 直属の上司や人事担当者(労務担当、総務担当など)に、退職代行からの連絡があったことを周知し、連携体制を整える。
- 緊急時の連絡網やチャットツールなどで、円滑に情報を伝達する。
-
2. 退職意向の確認と対応方針の整理
(1)退職の意思表明の「受領窓口」を確認
-
-
- 退職届の提出先や、メールでの意思表示を正式に認めるかなど、就業規則の定めをチェック。
- 退職代行業者からの連絡でも、従業員本人の意思表示とみなす方針かどうかを検討・確認する。
-
(2)退職に関する就業規則・労働契約の内容を確認
-
-
- 退職に必要な手続き期間(例:退職希望日の14日前までに書面提出が必要 など)
- 有休消化や残業代の精算など、就業規則や労働契約上で定められた取り扱いを再確認する。
-
(3)退職の意思と希望条件(退職日・有休消化など)を整理する
-
-
- 退職代行を通じて連絡があった希望退職日と、就業規則上の退職予告期間を照合し、整合性を検討。
- 有給休暇を消化したい意向があるかどうかも確認する。
-
(4)本人との連絡可否・連絡方法の確認
-
-
- 必要最低限の連絡を本人へ直接してよいか、退職代行業者を通すか、方針を固める。
- しつこい引き留め等はトラブルの原因となるため、対応方針を事前に決めておく。
-
3. 手続き・書類対応
(1)必要書類(退職届・離職票など)の扱いを確認
-
-
- 退職届(所定フォーマット)が必要か、退職代行業者の連絡のみで本人意思を認めるのかを決める。
- 雇用保険や年金、健康保険関係の必要書類について、提出方法とスケジュールを整理する。
-
(2)貸与物の回収方法の案内
-
-
- PCやスマホ、社員証、制服、備品などの貸与物がある場合、どのように返却してもらうかを決定し、退職代行業者または本人に伝える。
- 返却方法(郵送・宅配便・代理人による持参など)や期限を明確にする。
-
(3)業務引き継ぎの有無・手続き
-
-
- 対顧客や同僚との業務がある場合、必要最低限の引き継ぎ事項を確認しておく。
- 代行利用者が出社しない場合も多いため、可能であればメール・チャット・文書などで対応可否を確認する。
- 業務情報(ファイル、パスワード、顧客リストなど)の共有・回収を整理する。
-
(4)給与・手当・立替金などの清算確認
-
-
- 未払給与、残業代、通勤費や出張費の立替金などを整理し、法定の支払日・期限を守って対応。
- 退職金制度がある場合は、支給条件や支給日について確認し、必要書類を準備する。
-
(5)社会保険・年金手続き
-
-
- 退職に伴う健康保険・厚生年金の資格喪失手続き、雇用保険の離職票などの発行対応を漏れなく行う。
- 退職後の手続きに必要な書類の送付先・方法を確認し、期日通りに手配する。
-
4. セキュリティ・システム対応
(1)社内システムアクセス停止の準備
-
-
- 社員用メールアドレス、社内システム、クラウドサービス、デバイスなどのアクセス権を退職日に合わせて停止できるよう準備する。
- 不正使用や情報漏洩リスクを防ぐため、退職者の権限をいつまで残すかを決定する。
-
(2)データやアカウント管理の確認
-
-
- 退職者が作成・管理していた業務データやアカウントの引き継ぎ先を決定。
- 個人情報や機密情報の取り扱いに注意しつつ、必要なデータは会社で保管できるようにする。
-
5. 社内対応・フォローアップ
(1)周囲のメンバーへの周知
-
-
- 関係部署やチームメンバーに、退職予定の概要(退職日、担当業務の引き継ぎ先など)を適切なタイミングで案内する。
- 業務混乱を最小限にするため、必要に応じて臨時対応やサポートを行う。
-
(2)ハラスメントやトラブル防止の確認
-
-
- 退職連絡後、しつこく引き留めたり、個人的な連絡をしてトラブルになることを避けるため、社内で方針を統一。
- 直属の上司や同僚が個人的に連絡をとる際の注意点を共有する。
-
(3)就業規則・マニュアルの見直し
-
-
- 退職代行を利用されるケースが発生したことで、社内の退職ルールやマニュアルに不備がないか再確認する。
- 「退職意向の伝達手段」「退職申出から退職日までの流れ」「引き継ぎ方法」などを整備・明文化しておく。
-
(4)職場環境改善の検討
-
-
- 退職代行を使われた理由として、ハラスメントやコミュニケーション不足の可能性がないか振り返る。
- 従業員が安心して退職の相談ができる社内体制(カウンセリングや人事面談、相談窓口の周知など)の整備を検討する。
-
6. 最終確認
(1)手続き完了・書類発送の最終確認
-
-
- 離職票や源泉徴収票など、退職後に必要な書類がきちんと手元に届くよう発送状況を確認する。
- 給与・退職金の最終支給日や受け取り口座が従業員と相違ないか確認。
-
(2)退職者からの問い合わせ対応体制
-
-
- 退職後に「離職票が届かない」「保険証の返却方法が分からない」などの問い合わせがあった場合に、迅速に対応できる窓口・担当者を明確にする。
-
まとめ

退職代行の連絡を受けた際には、「退職の自由を認める」という法律の基本ルールを踏まえつつ、スムーズな手続きとトラブルの回避を優先して対応することが大切です。チェックリストを参考にしながら、社内フローの見直しやマニュアル整備を進めておくことで、突然の退職にも冷静に対処できるようになります。
退職代行を利用する従業員がいることに驚く経営者や管理者も多いかもしれません。しかし、法律上、従業員には退職の自由が保障されており、代行サービスを通じた意思表示であっても、基本的には受け入れなければなりません。
ここで重要なのは、「なぜ退職代行を使う必要があったのか?」という背景をしっかりと考えることです。自社の働きやすさやコミュニケーションの課題を見直し、必要に応じて改善していくことが、同じようなケースを減らす鍵となります。また、急な退職による混乱を防ぐためにも、普段から業務の引き継ぎ体制や退職の仕組みを整えておくことで、企業の信頼度アップにもつながります。
【ポイント】
(1)退職代行=「退職の意思表示を代行するサービス」です。従業員の退職の自由は尊重する必要があります。
(2)退職日や引き継ぎ、貸与物の返却などは、法的に問題のない形でスムーズに対応します。
(3)引き留めや過剰な連絡は避け、トラブルの回避を最優先にします。
(4)職場環境や相談体制を改善し、業務マニュアルを整備することで、対応力を高めることができます。
退職代行を利用するケースは今後も増えると考えられます。日頃から従業員と良好なコミュニケーションを取り、退職時にもスムーズに手続きが進められる環境を整えることが、企業にとって大きなプラスになります。