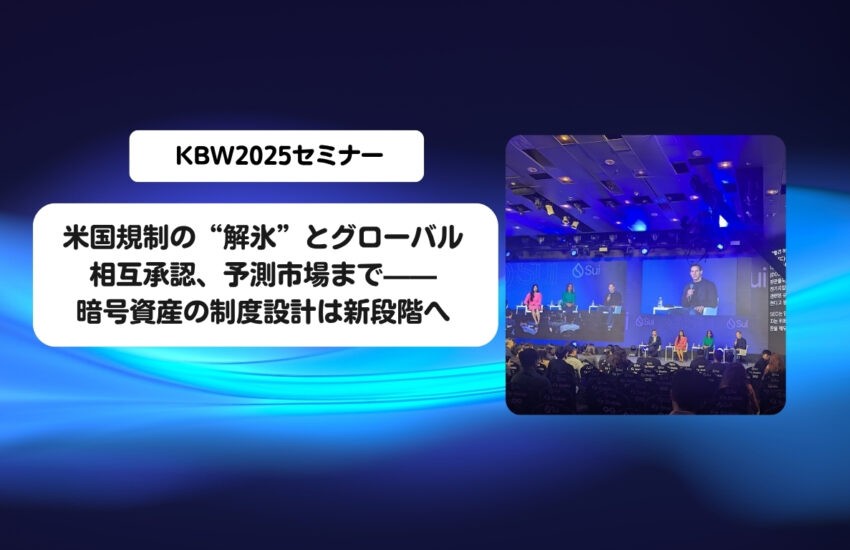Caroline Pham
CFTC代行議長。2022年に米上院の全会一致で承認され、以降、市場アクセス・競争・流動性向上に注力。法律・金融で24年の経験を持ち、Citiでの経営幹部経験も有する。UCLA卒、ジョージ・ワシントン大学ロースクールでJD取得。
Sheila Warren
Project Liberty CSO兼COO、Project Liberty Institute CEO。以前はCrypto Council for Innovation初代CEOを務め、責任ある暗号資産推進をリード。議会証言や主要メディア出演も多く、2023年「ワシントンの最も影響力ある女性」に選出。
Matthew Solomon
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP パートナー。SEC主任訴訟顧問や連邦検察官を歴任し、証券規制、ホワイトカラー犯罪、暗号資産紛争で高い評価を持つ訴訟専門家。2024年Law360 MVP、2023年Litigator of the Weekを受賞。
Leo Schwartz
Fortuneシニア記者。フィンテック、暗号資産、ベンチャー投資、金融規制を取材。VC動向を扱うニュースレター「Term Sheet」を執筆し、ポッドキャスト「Crypto Playbook」の共同ホストも務める。
エンフォースメント依存から「立法→規則→実装」へ

暗号資産を取り巻く米国の規制環境が「過渡期」を抜け、制度としての骨格づくりに本格的に舵を切り始めたことが強調されました。
過去数年、米国では「エンフォースメント・バイ・レギュレーション(執行で規制線を引く)」が実質的な運用基準となり、市場参加者にとって予見可能性の欠如が最大のボトルネックでした。
登壇者は、こうした運用が不公平さをもたらした側面を率直に認めつつ、今後は立法(議会)→規則制定(行政)→実装(監督)という正攻法に回帰していくと述べています。
とりわけ、ステーブルコイン制度を規定する法(Genius Act)と、トークン化や取引所運営の基準を含む市場構造法案(Market Structure Bill)が、米国の復権と国際的な互換性の確保に向けた二枚看板であることが示されました。
さらに、本セッションは予測市場(Prediction Markets)という先進的テーマにも踏み込み、「情報を価格に蒸留する市場」の公共性とブロックチェーンの適性を、金融史の文脈に位置づけています。
いま、何が変わったのか——「不確実性の時代」からの脱出
登壇した法律家や政策担当者は、直近2〜3年で米国の執行姿勢が顕著に変化したと述べました。ここでいう変化とは、単なる厳格化や緩和の振れではなく、「線引き」を執行に委ねる慣行を見直し、明文化されたルールで市場行動をガイドする方向への転換です。
ICOが“無制限”に解禁される時代へ逆戻りするわけではありません。むしろ、一定の開示義務・適格要件・販売制限などを伴う「秩序ある公募・私募」に落ち着くという認識が共有されました。
ただし、米国法には原則5年の時効(事案により長期化の余地あり)が存在します。したがって、過去行為の評価や遡及的リスクを無視できない以上、KYC(本人確認)とディスクロージャー(開示)の徹底は、今後も変わらず必須だという“冷水”も投げかけられました。
この「期待と警鐘」の両立が、本セッションの基調です。イノベーションの前進を支える制度化と遵法リスクの可視化という二正面作戦が、ようやく現実的なラインに乗り始めたと言えます。
立法の現在地:Genius Act と市場構造法案
1. Genius Act(ステーブルコインの制度化)
セッションでは、Genius Actがすでに可決され、財務省による具体的な規則(ルールメイキング)を待つ段階にあると整理されました。
重点は、準備金の安全性・透明性・監督可能性です。なかでも、準備資産の保管先を米金融機関に限定する方向性が示されており、国内回帰(オンショアリング)を促す制度設計がにじみます。
一方で、英国など主要法域との互換性(コンパチビリティ)を意識した対話が進み、越境ユースケースを阻害しない設計が探られています。
規則制定までの時間差(レイテンシ)は避けられませんが、逆に言えばここが産業界が実装可能性をフィードバックする貴重な期間でもあります。
2. 市場構造法案(Market Structure Bill)
トークン化の概念整理、取引所の運営基準、カストディ/清算/相場インフラの責任分担など、資本市場の“配線図”を書き換えるのが市場構造法案です。
上院では複数の案が併走しており、暗号資産の“有価証券性”/“コモディティ性”の線引き、交換所とブローカーの役割、発行体の開示負担などが議論の俎上にあります。
登壇者は、可決への自信を示しながらも、条文の分厚さと複雑性、そして監督当局による実装リソースという現実的ハードルを率直に認めました。
立法→規則→実装の全工程を考えれば、“今から数年単位”のロードマップが見込まれます。重要なのは、可決後の規則設計に産業界が関わり続けることです。
国際調和のカギ:相互承認フレームワークと「帰還」の道
米国は暗号資産においても最大級の需要地であり、基軸通貨ドルを背景とする規制設計は世界基準の参照点にならざるを得ません。セッションでは、商品デリバティブを所管するCFTC(米商品先物取引委員会)の動きが紹介されました。
CFTCは、外国ボード・オブ・トレード(FBOT)登録枠組みの再確認を通じ、越境取引に耐える制度の相互承認を志向しています。これは1990年代から積み上がる制度資産の再活用であり、“米国で上場・清算される取引”と“国外で行われる取引”の整合性を担保する試みです。
これは、かつて規制の不明確さを嫌い欧州・アジアへ拠点を逃がした米系企業に、「帰還(リショアリング)」の実線ルートを提供する意味を持ちます。登壇者の「America is back」という言葉には、雇用・投資・技術の再内生化を促したい意思が明瞭に表れていました。
越境アーキテクチャを標準化できるかどうかは、グローバルTAM(獲得可能市場)の広がりを左右します。英米協調が進めば、欧州・アジアの主要法域も巻き込みやすくなるはずです。
政治の文脈:多国間主義の後退と“デジタル資産例外”の可能性
登壇者の一人は、米国政治における多国間主義の後退(移民、関税、通商など)を指摘しつつ、デジタル資産では例外的に国際協調が維持され得るという見立てを示しました。
たとえば準備金の米国内保管は、内向き(内外差)の色合いを帯びる一方、業界は国際互換性のある実装を望みます。この綱引きは今後も続く見込みです。
ただし、米国は資本市場の深さと機能する法秩序という強みを持ちます。半導体産業での遅れから学び、デジタル資産(特にステーブルコイン)を次世代経済の中核と捉え直すべきだ、という危機感が共有されました。
結局のところ、ドルのデジタル実装(プログラマブル・ドル)をめぐる覇権競争で、先に標準を敷いた国が主導権を握るという現実が、政策選好を規定しているように見えます。
企業の行動変容:オフショアからオンショアへ
法曹実務の現場からは、SECの特定案件への強い執行(たとえばリップル訴追)を契機にオフショア移転した企業が多数あった実情が語られました。和解の過程で米国内プラットフォームを停止・撤退した事例もあったほどです。
近時は、当局による暫定的なスタッフ・ガイダンスや制度設計の見通しが共有されるにつれ、米国回帰(規制当局との協調ルートを選ぶ)動きが目立ち始めています。
それでもなお、州レベルの規制差異や行為時点の評価など、実務的なリスク管理は欠かせません。販売体制・適格投資家の線引き・流通制限といった販売オペレーションの作法を、文書化と証跡まで含めて設計する必要があります。
市場が「制度を信頼できる」と判断する鍵は、予見可能性と執行の一貫性です。可決法の規則化と、規則化後の監督実務の安定が、資本の再流入速度を決めます。
予測市場(Prediction Markets):情報こそ“次代のコモディティ”
本セッションの白眉は、予測市場に関する議論でした。登壇者は、AI・ディープフェイクが普及した時代においては、「真なる情報」こそ最重要の商品(コモディティ)になると断言します。
市場の本質は「分散した知識を価格に集約する機能」にあります。株式市場が日々、経営の質・キャッシュフロー・戦略といった多次元情報を1つの価格に凝縮するのと同じように、イベント駆動の情報も市場で価格化できます。
ブロックチェーンは、広域からの流動性と参加者を集め、改ざん耐性と透明性を付与できる点で、情報市場の基盤として高い適性を持ちます。
予測市場は英国・豪州・カナダなど多くの国で合法的に運用され、米国でも1990年代から小規模に承認されてきました。2008年の概念公表(コンセプト・リリース)では、今なお議論が続く論点まで先取りして検討されています。
米国では現在、選挙・スポーツ・天候などをめぐり、州の賭博規制とCFTCが所管する「イベント契約」の線引きが活発に争われています。CFTCの所掌は公共目的(価格リスク低減・価格発見・価格伝達)に根ざし、農産物先物→気象デリバティブという歴史的系譜を持ちます。
結論として、“情報を価格にする市場”は公共インフラであり、ブロックチェーン時代の制度設計においても、透明性・検証可能性・相互運用性を満たす形で推進すべきだという立場が示されました。
3〜5年の見通し:制度の“不可逆化”が焦点です
Genius Actの施行規則、市場構造法案の成立と規則設計、相互承認の実装という三段階を考えると、3〜5年スパンの工程管理が現実的です。
・短期(〜1年):財務省によるステーブルコイン規則のドラフトが具体化し、準備金の保全・開示・監査の実務が固まります。並行して、市場構造法案の主要論点(資産区分・インフラ責務・投資家保護)が政治的に整理されます。
・中期(〜3年):市場構造法案が可決→規則設計に移り、CFTC/SEC/財務省など横断のテクニカル・ルール(定義・手続・報告)が整備されます。英米協調を核に、他法域との互換性も試されます。
・中長期(〜5年):監督実務が安定し、エンフォースメントの一貫性が担保されます。ここまで進むと、産業の不可逆的定着(ロックイン)が生じ、政権交代リスクの影響は相対的に小さくなります。
制度の不可逆化とは、市場インフラ・監督運用・業界実務が互いに依存し合い、元に戻す方が社会的コストが高くなる状態を指します。セッションでは、そこへ至る「今」が最も重要だと繰り返し強調されました。
実務者への示唆:チェックリストと運用設計の勘所
本セッションの議論を、事業・法務・リスク管理の視点で持ち帰れるよう、要点をチェックリストに整理します。
1. コンプライアンス体制
☐ KYC/AML/制裁スクリーニングを要件定義→オペレーション→記録管理まで一気通貫で設計します。
☐ 開示(ディスクロージャー)は、販売形態(公募/私募/適格投資家限定)ごとにテンプレート化し、更新フローを定着させます。
☐ 州規制の差(マネー・トランスミッター規制等)を地図化し、許認可の進捗ダッシュボードを運用します。
2. ステーブルコイン対応
☐ 準備資産の区分・保管先・破綻隔離を、監査証跡まで組み込んだ運用規程に落とし込みます。
☐ 米金融機関保管の要件を想定しつつ、主要法域での比較表(可否・必要書式・報告頻度)を整備します。
☐ 異常時(清算/償還)手順のスイムレーン図を作り、訓練(ドリル)を定期実施します。
3. 市場構造・トークン化
☐ 資産の性質(証券性/コモディティ性/ユーティリティ)の初期評価メモを常備し、法改正のトリガーがあれば改訂します。
☐ アローワンス設計(譲渡制限・ロックアップ・情報開示のタイミング)を契約・コード双方で整合させます。
☐ 清算・カストディ・ベネフィシャルオーナー把握の境界条件を明文化し、監査対応に耐える記録管理を徹底します。
4. 予測市場・イベント契約
☐ 対象イベントの適法性(州賭博法との関係)を事前照会(ノーアクション/相談)で確認します。
☐ 価格発見の公共目的(リスク低減・伝達)に整合するユースケース記述を用意します。
☐ ブロックチェーン活用は、参加者KYC・不正監視・決済の透明性を強化する方向で設計します。
5. 政策対話
☐ ルールメイキングの意見募集(RFI/RFC)には組織として定期参加し、現場データを添えて建設的に提案します。
☐ 業界団体や学術コミュニティと連携し、国際互換性を意識した“最小公倍数案”をまとめて提示します。
☐ 越境相互承認の論点は、英米→EU→アジアと波及する可能性が高く、多法域同時対応の工程表が有効です。
なぜ「予見可能性」が資本を呼ぶのか
制度はリスクの上限と合規のコストを事前に見積もらせるための“共通言語”です。予見可能性が高まるほど、企業はディスカウント率を下げ、長期投資に資金を振り向けられます。
・投資家は、法的停止や回収不能のテールリスクが限定されると考えれば、資本コスト(WACC)を引き下げられます。
・発行体は、開示項目の固定化と監査の定型化で、一件あたりの法務コストを逓減できます。
・当局は、監督リソースを予防(ルール)と是正(監督)に配分しやすくなり、市場の健全性指標を安定的に改善できます。
この三者の利害一致が起きたとき、制度は不可逆に定着します。セッションAは、まさにその臨界点に近づいていることを示していました。
結語:解氷期に“走り始める”ための現実解
セッションAのメッセージを一言で要約すれば、「米国は制度で戻ってくる(America is back)」です。Genius Actと市場構造法案という二本柱、CFTCによる相互承認の枠組みの再確認、そして予測市場の公共性という前向きな話題が、エンフォースメント依存の時代に終止符を打ちつつあります。
ただし、これはゴールではなく“スタートライン”です。規則設計の遅延や州規制のばらつき、過去行為の時効問題など、実務の不確実性は依然として残ります。
ここで重要になるのは、
1.KYC/開示/記録管理の当たり前の質を引き上げること
2.越境互換性を意識した設計で再工事コストを抑えること
3.政策対話に測定可能なデータで参加し、望ましいルールへと“共創”していくこと
の三点です。
制度の解氷は、規制当局だけでは完遂できません。資本提供者・事業者・ユーザーの三者が、それぞれの位置から予見可能性の高い市場を作っていく必要があります。セッションAは、そのための現実解(プレイブック)を明確に示したと言えるでしょう。