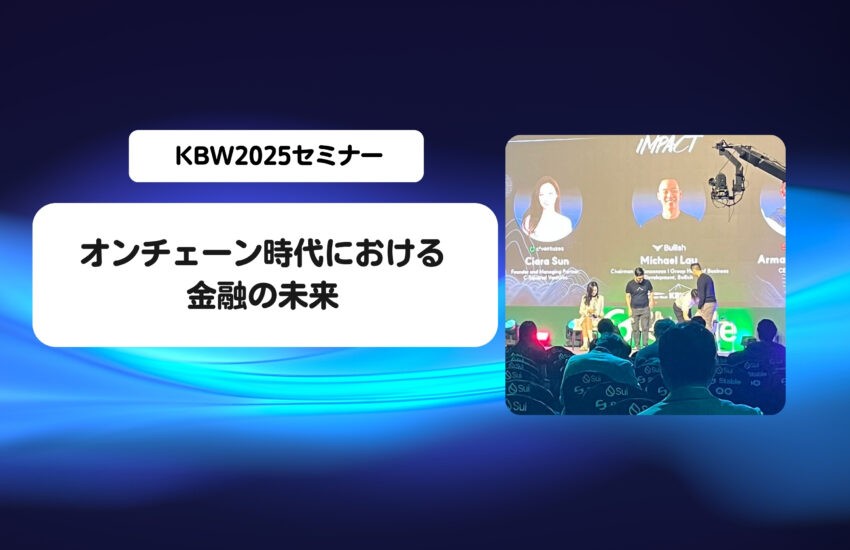Michael Lau
Consensus議長/Bullishグループ事業開発責任者。2025年「Consensus Hong Kong」を成功に導き、世界的な暗号資産イベントを主導。CLSAやJ.P. Morganでの経験を含め、資本市場で10年以上の実績を持つ。
Armani Ferrante
Backpack CEO。ウォレットやNFT「Mad Lads」、取引所を展開するBackpackを創業。Solana向け開発ツール「Anchor」を開発し、Appleでのエンジニア経験も持つ。
Ciara Sun
C² Ventures創業者・マネージングパートナー。Huobi副社長を経て独立し、Web3投資を推進。著書『The Rise of the Metaverse』や女性支援団体「Women Who Crypto」を通じ、業界のリーダーとして国際的に活動。
序章:オンチェーン化がもたらす新たな金融のかたち

2025年、韓国で開催されたKorea Blockchain Week(KBW2025)において、「オンチェーン化の進展と金融の未来」をテーマにしたセッションが行われました。本パネルでは、Bullish社副社長でありConsensusカンファレンスの議長でもあるマイケル・ラウ氏をはじめ、複数の業界関係者が登壇し、オンチェーン化の意義や課題、そしてユーザー体験や機関投資家の参入について議論しました。
オンチェーンという言葉はこれまで「検閲耐性※」を中心に語られてきましたが、現在では「透明性」「検証可能性」が重視されるようになっています。本記事では、パネルで語られた論点を整理し、オンチェーン金融の未来像を描きます。
※「検閲耐性(けんえつたいせい)」とは、単一の存在がデータを制御または改変する力を持たない、つまり取引やデータ交換が不当にブロック、監視、操作されないシステム、特にブロックチェーンや暗号通貨において目指される性質のことです。
第1章:オンチェーンの定義はどのように変化したのか
従来の「オンチェーン」
かつてオンチェーンといえば「検閲耐性」が最大の特徴でした。誰もがノードを運営でき、特定の権威や国家に依存せず、システムが中立的に機能することが理想とされてきました。つまり、規制の枠組みが意味を持たないほどに「自然界のように規制不可能な存在」として捉えられていたのです。
変化するオンチェーンの意味
しかし業界が成熟し、多様な参加者が増える中で「オンチェーン」の定義は大きく変化しました。現在では「完全な検閲耐性」よりも、「透明性」「取引の検証可能性」「不正防止」といった要素が重視されています。つまり、公共ブロックチェーンだけでなく、銀行や証券会社、決済機関といった既存金融機関においてもオンチェーン的な仕組みが求められる時代になっているのです。
第2章:取引所がオンチェーンに移行する二つの方向性
登壇者たちは、中央集権型取引所(CEX)がオンチェーン化する流れについて2つの方向性を提示しました。
1.アクセスのためのオンチェーン化
取引所はユーザーが暗号経済にアクセスする「入り口」です。銀行口座やCEXアカウントから、SolanaやEthereumのようなパブリックチェーン上の資産やサービスに接続できることが重要になります。
2.リスク最小化のためのオンチェーン化
取引や資産管理をオンチェーン上で記録・証明することにより、監査可能性を高め、リスクを減らします。バックパック取引所の事例では、取引履歴を完全に検証可能とし、準備金の証明を毎日ブロックチェーン上に公開する取り組みが紹介されました。
これにより「次世代金融インフラ」が形成され、2008年の金融危機や従来の中央集権的リスクに対抗する仕組みが構築されつつあります。
第3章:機関投資家の参入と教育の必要性
機関投資家へのアプローチ
Bullish社が初期に取った戦略は「伝統金融の言語を話すこと」でした。機関投資家にとって重要なのは、透明性や監査体制、規制当局との連携です。そのため、ブロックチェーンの技術的な革新性よりも、まずは「安心できるフレームワーク」を提示することが優先されました。
馬車から自動車へ:技術導入の比喩
セッションでは、自動車の初期に「馬の形を模した装飾」がつけられていた話が引用されました。新技術を導入する際には、既存の認識や文化に配慮する「移行期の工夫」が必要であり、ブロックチェーンも同様に段階的な教育と導入が不可欠であると語られました。
第4章:ユーザー体験とセルフカストディの進化
ワンタップ体験の実現
オンチェーン体験を普及させるには「ワンタップで使える利便性」が必要です。ユーザーは複雑なウォレット操作を学ぶことを望まず、シームレスな体験を期待しています。
これに対して、2つのアプローチが議論されました。
1.バックエンド型:ユーザーは資産を預け、運営者が裏側で管理・運用する仕組み。銀行やファンドに近い形で、ユーザーは利便性を享受できます。
2.アカウント抽象化型:スマートコントラクトを用いて資産管理を行い、鍵を紛失しても復旧が可能な仕組み。これにより真の意味での「セルフカストディ」が実現可能になります。
セキュリティと利便性のバランス
従来の「秘密鍵喪失=資産消失」という構造は大きな欠陥とされました。アカウント抽象化によって、友人や金融機関を通じた復旧手段が導入されれば、中央集権的リスクと自己管理リスクの双方を軽減できると期待されています。
第5章:資本効率と透明性
ユーザーや機関投資家にとって重要なのは「資本効率」です。オンチェーン化によって、ポジションが相殺されている場合のリスク管理や、資産の透明性が飛躍的に向上します。これにより、資金の滞留を減らし、より効率的な運用が可能になります。
第6章:AMM(自動マーケットメイカー)の可能性
Bullish社が注目したのは、AMMの可能性でした。従来は限られた利用にとどまっていましたが、AMMはコミュニティとの関わりを深める有効な手段として注目されています。
しかし、世界の金融市場規模(約103兆ドル)に比べれば、暗号資産市場はまだ3兆ドル規模にすぎません。今後はさらなる資本流入と、伝統金融と暗号資産の融合が求められると指摘されました。
※自動マーケットメイカー(AMM)は、アルゴリズムとスマートコントラクトを用いて資産の価格を自動的に決定する仕組みのことを指します。
第7章:市場の健全性と今後の展望
セッションの最後に登壇者たちは、市場の浮き沈みは避けられないが、重要なのは「健全な成長を支える基盤を整えること」であると強調しました。
特に、
・規制当局との協調
・技術と文化の橋渡し
・ユーザー体験の改善
・機関投資家の安心感の確保
これらが揃うことで、オンチェーン金融は単なる新興技術ではなく、グローバル金融システムの中心へと進化していくと結論づけられました。
結論:オンチェーン金融の未来は「透明性」と「アクセス」が鍵
議論を通じて浮かび上がったのは、オンチェーン金融の未来像です。かつて「検閲耐性」に象徴されていたオンチェーンは、現在では「透明性」「検証可能性」「アクセスの容易さ」へとシフトしています。
ユーザーは利便性を、機関投資家は安心感を求め、規制当局は透明性を重視します。その三者をつなぐのがオンチェーン技術であり、これが次世代の金融インフラを形作る中心になるといえるでしょう。
KBW2025のセッションは、その未来を垣間見せる場となりました。今後の展開に注目が集まります。