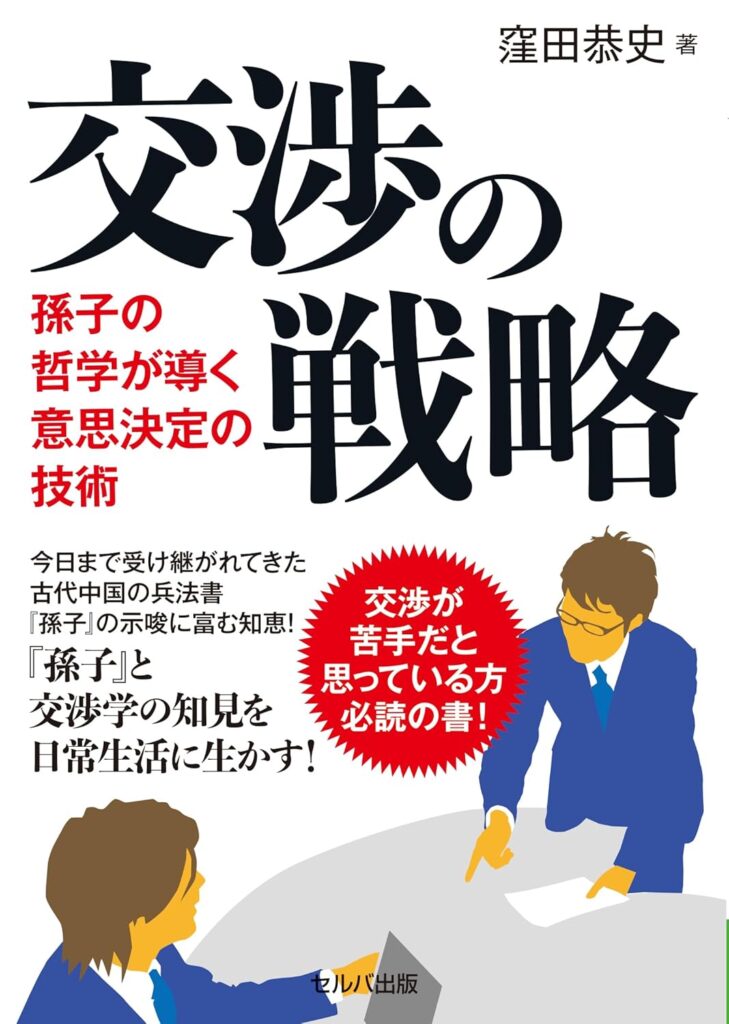「交渉の戦略 孫子の哲学が導く意思決定の技術」を上梓した窪田恭史氏にインタビューしました。本記事では、孫子の思想を現代のビジネスにどう活かすかについて、実践的な交渉戦略とともにお話しいただいています。中小企業の経営者にとっても、すぐに取り入れられるヒントが詰まっています。
1973年、神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)にてコンサルティングおよび研修講師業務を担当。
2000年、ナカノ株式会社に入社。2007年リサイクル部事業企画室長、
2019年取締役副社長を歴任し、2024年に代表取締役社長に就任。
ーーまずはじめに、この本を書こうと思われた背景や経緯についてお聞かせください。
窪田氏(以下敬称略):本書執筆のきっかけは、私が所属する「日本交渉協会」が配信しているポッドキャスト『人をつなぐ、未来をつなぐ。トレードオンの交渉学』でした。この番組の中で、月に1回「孫子で読む交渉学」というテーマでお話しする機会をいただき、その連載内容が今回の書籍のベースとなっています。
ただし、孫子を基に交渉について語るという構想自体は、それ以前から長く温めてきたものでした。私はもともと中国の古典、とりわけ孫子を読むことが好きで、幼少期から親しんでいました。
ご承知のとおり、孫子は約2,500年前の戦争を前提として書かれた兵法書です。そのため、古代の武器や地形といった記述は、現代のビジネスに直結しにくく、読み手にとって距離を感じさせる部分も少なくありません。それでも多くの読者は、自身の経験や現代の事例と照らし合わせながら孫子の内容を理解されているのだと思います。
実際、孫子の知見を現代の課題に応用する書籍はこれまでも多く出版されています。しかし、それらを読むなかで私が強く感じたのは、孫子が13篇からなる体系的な構造を持っており、個別の言葉だけでなく全体のつながりを踏まえてこそ、本来の意図や教訓をより深く捉えることができるという点でした。その問題意識もあり、十数年前、『孫子塾』という講座で1年をかけ、改めて孫子を学びなおしました。
各篇を個別に切り分けてテーマ別に読むのではなく、13篇を貫く一貫した視点から読み進めるほうが、本質的な理解に近づける、そのために何か良い題材はないか?
長年問題意識として持ち続けた結果、「一貫した視点」として適しているのが、私が十数年にわたって学び続けてきた交渉学であるという確信に至りました。交渉という観点を軸にすれば、孫子全体の構造と論理を通して読み解くことが可能であると感じたのです。
こうした経緯を経て、本書の執筆に取り組むこととなりました。
なお、本書は孫子の原文や現代語訳を詳しく解説することを目的としていません。孫子に書かれた主張や要点を抽出し、それらを交渉理論の視点から読み解く構成となっています。その意味で、本書は「孫子の解説書」ではなく、「交渉学の書籍」として捉えていただければと思います。
ーーありがとうございます。ここからは書籍の内容に少し踏み込んでお伺いしたいと思います。孫子の兵法をビジネスに応用する際、特に重要となる原則について、どのようにお考えでしょうか。
窪田:はい。書籍の中でも述べましたが、まず注目すべきは冒頭の3篇に示されている孫子の基本的な思想です。特に重要だと考えているのが、以下の3つの言葉です。
1つ目は「兵は国の大事なり」。これは、戦いというものが国家にとって重大な決断であるという意味です。ビジネスにおいても、交渉は企業の方向性を左右しかねない重要な意思決定である場合があります。しかしそれ以上に、交渉は戦争と違い、積極的に行うべきものであると反語的に捉えています。
2つ目は「敵に勝ちて強を益す」。つまり、相手に勝利することで自らの力も増すという考え方です。適切な交渉を行うことで、価値のパイを増大させていく、つまり、価値創造していくという発想にも通じます。
3つ目は、よく知られている「戦わずして勝つ」という考えです。これは実際の対立を回避しながらも、目的を達成することの重要性を示しています。現代のビジネス交渉でも、衝突を避けつつ合意形成に導く力が求められます。
この3点に加えて、私が特に強調したいのが「兵は詭道なり」という言葉です。直訳すると「戦いは騙し合いである」という意味になりますが、これは単に欺くことの重要性を説いているのではなく、戦いや交渉というものは常に変数が多く、単純な正解が存在しないということを示しています。
交渉学に関心を持つ方からは、「こうすれば必ず勝てる」というような万能の交渉術はあるのか、という質問をよく受けます。しかし、孫子が「詭道」と述べているように、交渉もまた状況や相手によって変わるものです。絶対的な成功法則は存在せず、あくまで柔軟に状況を見極めながら対応していく姿勢が求められます。
この前提を理解せずに、理論やテクニックだけを形式的に学んでしまうと、かえって現実とのズレが生じるリスクもあります。交渉における本質的な力とは、特効薬を求めることではなく、多様な状況に対応するための思考力や判断力を磨くことにあると考えています。
以上の4点が、孫子の思想を現代のビジネス交渉に応用するうえで特に重要な原則だと捉えています。
ーーありがとうございます。ビジネスの現場では、自分が優位な立場にあるというケースはあまり多くないと感じています。特に中小企業の経営者などは、自分よりも立場の強い相手と交渉せざるを得ない状況が多いのではないでしょうか。こうした“劣勢”の状況を逆手に取るような交渉の方法はあるのでしょうか。
窪田:私自身も中小の卸売業に携わっており、上流(川上)と下流(川下)の間に挟まれる立場にあります。そのため、交渉の場においては必ずしも優位とは言えない状況に置かれることも少なくありません。そういった意味で、弱い立場からどう交渉を展開していくかは、私自身の実感としても非常に重要なテーマです。
確かに、交渉では力の強い側が有利になることが多いという現実は否定できません。ただし、弱者が常に不利かというと、必ずしもそうとは限りません。孫子の教えにも通じる部分ですが、交渉という行為自体、そもそも双方に何らかのメリットがあるからこそ成立しています。
その前提に立つと、たとえ立場が弱いと感じていたとしても、相手にとって我々と交渉する理由、つまり無視できない“強み”のようなものが存在する可能性があります。それが特別な技術や商品であれば分かりやすいですが、そうでなくても、他社にはない対応力や関係性、信頼性など、交渉の席に着くに足る要素は探せば見つかることが多いものです。まずは自社の持つ価値を冷静に見極めることが重要です。
加えて、「BATNA(バトナ)」という交渉学の概念も活用できます。これは「Best Alternative to a Negotiated Agreement」の略で、直訳すると「交渉の合意に代わる最善の代替案」という意味です。交渉の場に臨む前に、自分にとってのBATNAを明確にしておくことで、仮に交渉がまとまらなくても、別の手段があるという安心感を持つことができます。
例えば、就職活動において第1志望の企業があった場合、その企業から内定をもらう前に、別の同等レベルの企業から内定を得ていると、それだけで交渉力が増します。その内定が「強いBATNA」になるからです。企業側も、ライバル企業に人材を取られたくないという心理が働くため、こちらに有利な状況をつくり出せるわけです。
また、本書でも触れたように、交渉においては相手にもBATNAがあります。状況によっては、相手のBATNAを相対的に弱める工夫も可能です。たとえば、他の選択肢が現実的に存在しないような状況をつくることも一つの戦略です。
さらに、交渉相手を1対1の関係に限定せず、もう少し広い視野で捉えることも重要です。交渉に影響を与える人物は実際には複数存在する可能性があります。たとえば、自分が相手の上司と関係を築いていて、すでにその上司との間で話がついていれば、直接交渉している担当者の影響力は相対的に弱まります。あるいは、ライバル企業の存在、業界内の他社との連携、法規制、行政の動向、世論など、交渉に関与し得る外部要因も少なくありません。
最近の例で言えば、大手企業による下請け業者への圧力が問題視され、社会的な非難や政府の介入が強まっているケースが挙げられます。かつては絶対的な力を持っていた企業に対しても、世論や法制度の変化によって力のバランスが変わり、下請け企業の立場が相対的に強くなったという事例です。
このように、交渉は単に力関係だけで決まるものではなく、状況の見極め方や、どれだけ多面的に戦略を組み立てられるかが重要です。弱い立場にあるからといって、必ずしも不利であるとは限りません。

ーー交渉においては「情報」が重要な鍵を握るという点が、本書の中でも強調されていたかと思います。具体的には、どのような情報を集めることが有効だとお考えでしょうか。
窪田:交渉の場面は多種多様で、それぞれに必要な情報も異なります。ですので、「これとこれを集めれば十分」という形で一般化するのは難しいのが実際のところです。
ただ、その上で参考になるのが、孫子の有名な言葉「彼を知り己を知れば百戦危うからず」です。ここでの「彼」は相手、「己」は自分を指しますが、この言葉にはさらに別の表現があり、「彼を知り己を知り、天を知り地を知る」という表現が存在します。「天と地」は自分と相手を取り巻く環境と解釈できますので、要するに“相手・自分・環境”の3つについて情報を収集することが、交渉を有利に進める上で重要だということになります。
まず、相手に関する情報としては、誰もが事前に調査するであろう「相手のニーズ」や「交渉担当者の性格」、「組織の中で誰が決定権を持っているのか」といった点が挙げられます。こうした情報は、交渉の準備段階で欠かせません。
一方で、見落とされがちなのが「自分」に関する情報の整理です。たとえば、先ほどの話にも出てきた「BATNA(交渉の合意に代わる最良代替案)」を事前に明確にしておくことは、自身の交渉力を把握するうえで非常に重要です。また、自社の強みや弱みを客観的に分析することも、実際には十分に行われていないケースが多いと感じています。
さらに、「環境」に関する情報も見逃せません。市場の規制状況、法制度の変化、業界の動向、競合他社の動きなど、交渉に間接的な影響を及ぼす要因を把握しておくことも、戦略を立てるうえで大きな意味を持ちます。
まとめると、「相手」「自分」「環境」という3つの視点から情報を集め、事前に整理しておくことが、交渉を成功に導くための基本であると考えています。
ーービジネスの世界における言葉で表現すると、いわゆるSWOT分析をしっかり行うことに通じるのではないでしょうか。
窪田:はい、その通りだと思います。
ーーまた、事前準備の重要性についても触れておられましたが、やはり「自分」「相手」「環境」を事前に調査・整理しておくことが、準備の本質だと捉えてよいでしょうか。
窪田:はい。準備をせずに交渉の場に臨むと、その場その場のアドリブや場当たり的な対応に頼らざるを得なくなります。もちろん、偶然うまくいくこともゼロではありませんが、交渉においてはやはり事前の準備が成否を大きく左右します。
特に重要なのは、先ほど申し上げた情報収集です。加えて、交渉に臨むにあたって「どのような戦略を採るか」「どのような戦術を展開するか」といったシミュレーションを事前に行うことも、非常に有効だと考えています。
私自身、交渉理論を学んだ後は、交渉の現場に向かう前に「交渉シナリオシート」を作成して臨むことを習慣にしていました。シートには、交渉の目的、達成したい目標、想定されるBATNA、交渉戦略、相手の反応の予測などを記入し、頭の中で整理したうえで現場に入るようにしていました。
もちろん、実際の交渉は必ずしもシナリオ通りには進みません。しかし、事前に思考を深め、複数の展開を想定しておくことで、現場での判断に余裕が生まれます。
さらに、長期的な関係性がある取引先であれば、交渉の場面に限らず、日常的にコミュニケーションを取っておくことも重要です。問題が生じたときだけ訪問するのではなく、普段から顔を出し、信頼関係を築いておく。こうした継続的な関わりも、交渉における重要な準備のひとつと考えています。
ーーご自身のご経験にも少し触れていただきましたが、これまでの交渉の中で特に印象に残っている成功例、あるいは失敗例、そしてそこから得られた教訓などがあれば、ぜひお聞かせいただけますか。
窪田:そうですね。具体的な事例については、業務上の守秘もあるため詳細をお話しするのは難しいのですが、少し抽象的な形でお伝えできればと思います。
私の仕事は、祖父の代から3代にわたって90年以上続いているもので、皆さんの不要になった古着を回収し、リサイクルする事業を展開しています。この仕事には、単に「物を再利用する」という以上の価値があると感じています。
交渉という観点から見ると、私たちの事業は常に「ウィンウィンの関係構築」を目指しており、これは交渉学でいう「統合型交渉」にあたります。つまり、相手と自分がそれぞれの利益を最大化しながら、より良い解決策を導き出すことを目指す交渉スタイルです。
古着のリサイクルという行為には、資源の再活用という実利的な意味に加えて、衣類ならではの特別な価値があると感じています。たとえば、ジュースの空き缶や新聞紙などを捨てる際、多少のもったいなさを感じることはあっても、そこに強い感情的なつながりを持つ人は多くありません。
しかし、衣類の場合は事情が異なります。ある服が、亡くなったご家族の思い出の品であったり、学生時代の青春の記憶と結びついていたりすることも多く、非常に個人的な意味を持っています。衣類は、単なるモノではなく「自分の一部」として扱われていることが多いのです。
そのため、我々が衣類を回収・リサイクルする際には、そうした感情的な側面にも配慮しながら、できる限り「その服が新しい場で活躍している様子」を可視化する工夫をしています。 たとえば、回収された衣類がどのように再利用されているかを伝える取り組みを通じて、持ち主の方が「自分の大切な服が再び誰かの役に立っている」と実感できるようにしています。
こうした取り組みによって、衣類を手放すことに伴う心理的なハードルを下げることができれば、リサイクルへの協力も得やすくなり、結果として循環型の仕組みがより機能するようになります。
成功事例というよりも、こうした価値観の共有を通じて社会との信頼関係を築くことが、交渉における成果の一つだと捉えています。私たちの事業の特性そのものが、統合型交渉の実践であり、日々その価値を実感しています。
ーー交渉というのは、単なる1対1のやり取りではなく、交渉相手の背後にいる関係者や組織、あるいは外部の状況なども含めて意識しながら、コミュニケーションを図っていく必要があると感じます。
窪田:まさにその通りです。交渉は必ずしも1対1で完結するものではなく、相手の背景にある組織的な要素や利害関係者、周囲の環境も踏まえて考える必要があります。
一方で、これは失敗というよりも、私自身の交渉スタイルにおける課題だと常々感じていることですが、たとえ「統合型交渉」――すなわち価値の創造を重視するアプローチ――を意識していたとしても、日々の業務に追われる中で、ついスピードを優先してしまうことがあります。
結果として、ある程度の成果が見込めた段階で交渉を打ち切ってしまう。言い換えれば、本来であればもう一段階深い価値創造が可能であったかもしれないにもかかわらず、それを追求しきれないまま終えてしまい、反省するケースがあります。
もちろん、スピード感があるという点では長所とも言えますが、一方で統合型交渉には一定の忍耐力や粘り強さ、そして広い視野を持った取り組みが欠かせません。そこをおろそかにしてしまうと、潜在的な価値を見落としてしまうことになりかねません。
そうした意味で、自身の交渉のスタイルや姿勢を省みると、テクニックやプロセス以前に、その人の性格や価値観、つまり「交渉の主体者としてのあり方」が交渉結果に大きな影響を与えていると強く感じます。
今回の書籍では、その「人としてのあり方」についてはあまり深く触れていませんが、個人的には、交渉における最も大きな学びはこの点にあったと考えています。
ーー現在、交渉力を高めたいというニーズは、特にビジネスの現場で高まっているように感じます。そのような力を身につけるには、日頃からどのようなことを心がけると良いのでしょうか。
窪田:先ほど少し触れた「交渉シナリオシート」も、まさに交渉力を高めるために私が取り組んできた方法のひとつです。これと同様に、自分が日常で経験する交渉について、簡単なメモや日記のような形で記録し、後から振り返って分析するという方法も非常に有効だと思います。
交渉というとビジネスの場面を思い浮かべがちですが、実際には家庭での会話、友人とのやり取り、さらには社内のちょっとしたお願いごとに至るまで、日常には数多くの交渉が存在しています。意識を向けさえすれば、交渉の機会は無数にあるということです。
たとえば、上司にちょっとしたお願いをする場面でも、「どうすれば了承を得られるか」を考えて実行するというプロセスは、まさに交渉の一例です。そうした身近な体験を振り返り、自分がどういうアプローチをとったのか、相手はどう反応したのか、といったことを記録・分析していくことで、自分なりの交渉スタイルや改善点が見えてきます。
加えて、実体験から得られた気づきを「感覚」にとどめず、言語化して整理するためにも、交渉理論の知識をあらかじめ持っておくことは非常に有効です。理論を学んでおくことで、自分の経験をより深く理解し、次に活かしやすくなります。
結局のところ、交渉力を高めるには「知識」と「実践」の両輪を回し続けることが大切だと考えています。知識によって視野が広がり、実践によってそれが深まる。その繰り返しこそが、交渉力を着実に育てていく道ではないでしょうか。
ーーそうした考え方は、個人だけでなく、組織としても重要になりますね。部下の交渉力を高めたいと考えるマネージャーも多いかと思いますが、やはり実践を通じて経験を積むことが鍵になるのでしょうか。
窪田:はい。基本的には、理論と実践の循環――いわば「サイクル」を回していくことが大切だと考えています。
例を挙げるなら、相撲が上達したいのであれば、実際に相撲を取るしかありません。水泳や筋トレも補助にはなるかもしれませんが、やはり本質的には相撲を通じて学ぶ必要があります。交渉もそれと同じで、交渉力を高めたいなら、実際に交渉の場に立ち続けることが不可欠です。
ただし、実践だけを重ねれば良いというものでもありません。江戸時代の剣豪・千葉周作の言葉に「理より入るものは上達早く、業より入るものは上達遅し」というものがあります。これは、「感覚だけでなく理(ことわり)から入る人の方が、上達が早い」という意味です。
この考えは交渉にも当てはまります。ただ経験を積むのではなく、その経験を知識で裏づけし、言語化しながら整理しておくことで、より深く応用できるようになります。交渉力を高めるには、理論と実践の両方を繰り返しながら身につけていく必要があります。
一方で、実践には限界もあります。たとえば、お客様との交渉で無事に契約が成立したとしても、それが本当に最適な合意だったかどうかは、その場では判断できないことが多いものです。結果が後になってから見えてくるケースや、そもそも相手からフィードバックを得られないことも珍しくありません。
また、社内のコミュニケーションにおいても、上司が部下にどう接したか、それが適切だったのかどうかを確認する機会は少ないのが現実です。教育の現場でも、教え方が本当に効果的だったかは、すぐにはわかりません。
こうしたフィードバックの欠如を補う手法として、ロールプレイやシミュレーションが非常に有効です。たとえば、アメリカのビジネススクールなどでは、架空の交渉シナリオを用いたロールプレイがよく行われています。
こうした練習の利点は、交渉が終わった直後に、相手と互いの意図や反応について話し合い、すぐにフィードバックを得られる点にあります。実際の交渉では得がたい振り返りが可能になるため、教育やトレーニングの手段として非常に効果的だと考えています。
補足になりますが、参考までにご紹介させていただきます。私自身、日本交渉協会で「交渉アナリスト」という民間資格の講座を担当しています。この資格は、交渉理論を体系的に学ぶことを目的としたもので、講座は土日を活用して開催しています。
この講座では、全体の約3分の1の時間を理論のインプットに充て、残りの3分の2は徹底的にロールプレイを行います。そして、ロールプレイ後には参加者同士でフィードバックを共有し合いながら、実践力を磨いていく構成となっています。
ーーロールプレイを通じて練習できる場があるというのは、とても貴重ですね。そういった講座を活用しながら実践を積み重ねることで、交渉力を高めていけるというわけですね。ところで、今回出版されたご著書についてですが、読者がどのように活用するとより効果的でしょうか。
窪田:実のところ、活用法については著者である私が一方的に決めるというよりも、むしろ読者の皆さんからのフィードバックをいただきながら、多様な使い方が生まれていくことを期待しています。
本書では、「交渉は外交やビジネス、司法の現場だけでなく、誰にとっても身近な行為である」と繰り返し強調しました。ただ実際には、紹介している事例の多くが外交問題など、スケールの大きい領域に偏っている面があるのも事実です。これは、「交渉理論」や「交渉研究」を扱ったという性質上、避けられなかった部分でもあります。
とはいえ、読者の皆さんには、孫子の思想や交渉理論をベースとしながらも、それを自分の置かれている日常や現場に引き寄せて読み解いていただければと思っています。たとえば、職場でのコミュニケーションや家庭での話し合いなど、より身近な場面に当てはめて考えることで、理論が現実の中で生きた知識として役立つはずです。
また、個人的には、輪読会や読書会のような形で本書を複数人で読み、意見交換をしながら理解を深めるという活用法も有効だと考えています。交渉そのものが対話の中で発展するものである以上、読書もまた他者との対話を通じて価値が深まる面があると思います。
そのため、友人や同僚と本書を一緒に読み、それぞれの解釈や気づきを共有し合うことで、より多くの学びが得られるのではないでしょうか。もし他にも「こんな活用の仕方をしてみた」というお声があれば、ぜひ伺ってみたいですね。
ーーここで少し視点を広げて、国際情勢について伺いたいと思います。昨今の情勢は非常に流動的であり、とりわけトランプ氏の再登場などによって、政治・経済ともに不透明感が一層強まっている印象があります。そのような環境下で、企業や個人が生き残るためには、どのような交渉戦略が鍵になるとお考えでしょうか。
窪田:大きく分けて2つの視点から考えることができると思います。
まず1つ目は、やはり交渉理論を体系的に学んでおくことの重要性です。トランプ氏に代表されるような、いわゆる「パワープレイ型」の交渉スタイルは、感覚的に強く印象に残るものですが、理論をもとに分析することで、相手の出方や意図をより冷静に理解し、対応するための選択肢が広がります。国際政治や経済の不確実性が高まる中では、交渉相手の行動を読み解く力がますます求められるはずです。
もう1つは、やや理想的に聞こえるかもしれませんが、「統合型交渉」の重要性がこれまで以上に高まっているという点です。現代の国際社会においては、単なる分配型交渉――つまり「勝者と敗者」がはっきり分かれるゼロサム的な交渉――だけでは成り立たない場面が増えています。国家間、企業間、そして地域間の相互依存が進んでいる今、短期的な利得だけを追求しても、持続的な関係を築くことは困難です。
日常の商談やビジネスの現場でも、単に価格だけを交渉の材料とするのではなく、複数の価値軸を提示しながら、お互いにとって納得できる合意を目指す――つまり価値を「分け合う」ではなく「創り出す」ことが求められています。この考え方に基づいた交渉こそが、統合型交渉であり、今後の社会においてますます必要とされていくと考えています。
そのためにも、理論と実践を往復しながら、自らの交渉スキルを継続的に高めていく姿勢が重要になります。変化が激しく不確実な時代だからこそ、対立を乗り越え、共に価値を生み出していく交渉のアプローチが、持続的な成長と安定の鍵になるのではないでしょうか。
ーーありがとうございます。実際、窪田さんはさまざまな国の方々と交渉や商取引をされていると思いますが、日本人の交渉スタイルには、どのような特徴や課題があるとお考えでしょうか。良い点も含めてお聞かせいただけますか。
窪田:よく「日本人は交渉が苦手だ」と言われることがありますが、まずその前提として2点お伝えしておきたいことがあります。
第1に、国や文化によって交渉スタイルが異なるというのは事実ですが、それはあくまで「相対的な違い」であるということです。たとえば、日本人は間接的な表現を好むと言われます。中国人はそれよりもやや直接的な傾向がありますが、アメリカ人から見れば、中国人もまだ間接的だと感じられることがあります。逆に、日本人から見れば、アメリカ人は非常に率直に感じられるかもしれませんが、ブラジル人から見ると控えめだという印象を持たれることもあります。
つまり、交渉スタイルの「文化的特徴」は、絶対的なものではなく、比較の中で見えてくる相対的なものであることを理解することが重要です。
第2に、文化だけではなく、職業や性別、そして個人の性格によっても交渉スタイルは大きく変わります。同じ日本人でも、営業職と研究職ではアプローチが異なるように、一般化には注意が必要です。
その上で、あくまで「ステレオタイプ的な傾向」として、日本人の交渉スタイルについて語るとすれば、「対立を避けて調和を重んじる」という点が挙げられます。これは一つの美徳とも言えますが、同時に、自分の立場や意見を十分に主張できず、相手に押し切られてしまう場面が生まれやすい要因にもなっています。
実際、日本交渉協会が2022年に実施したアンケート調査では、日本人男女の6割以上が「交渉が苦手」と回答していました。その理由として多く挙がっていたのが、「論理的に話すのが苦手」「相手にどう思われるかが気になって強く主張できない」「譲歩しすぎてしまう」といったものでした。
つまり、「交渉は論理力や話術が求められる」「強く主張しなければならない」といった固定観念が、日本人の交渉に対する苦手意識を生んでいるとも言えます。
ただし、相手の立場や心情を推し量り、調和を重視する姿勢自体は、決して否定すべきものではありません。むしろ、現代のビジネスや国際社会で求められている「統合型交渉」――双方が満足できる合意を目指す交渉――においては、このような姿勢が大きな強みとなります。
重要なのは、「対立を避けたいから調和を目指す」のではなく、「協力的な関係の中で、より良い結果を生むために調和を大切にする」という発想への転換です。そのうえで、自分の考えや希望をどの程度主張すれば相手に受け入れられるのか、逆に、どのような言い方が相手に抵抗を与えないかといった判断力を、実践と知識の両面から高めていく必要があります。
したがって、まずは交渉に関する理論やスキルを身につけた上で、日常の中で小さな「お願い」や「提案」を実践してみることをお勧めします。たとえば、同僚に何かを頼んでみる、質問をしてみるといった経験を重ねることで、「自分の希望を伝えることは相手に迷惑ではない」「意外と受け入れてもらえる」といった手応えを得られるようになります。
こうした積み重ねを通じて、徐々に「自己主張=悪いこと」という思い込みを手放し、必要なときに自分の意見をしっかりと伝えられるようになっていく。そのプロセスこそが、今後の交渉力向上にとって非常に大切なのではないかと感じています。
ーーありがとうございます。最後の質問になります。トランプ氏の強硬な交渉スタイルは世界的にも注目を集めていますが、ビジネスパーソンが参考にできる点、あるいは避けるべき点があれば、教えていただけますか。
窪田:とても重要なテーマですね。個人的にも印象に残っているのは、以前報道されたトランプ氏とゼレンスキー大統領の会談決裂の場面です。あのような出来事を見ると、交渉スタイルがもたらす影響の大きさを痛感します。
この点について、私自身の意見もありますが、客観的な見解としてご紹介したいのが、2019年にマサチューセッツ工科大学(MIT)のトーマス・コチャン教授が『ネゴシエーション・ジャーナル』に寄稿した論文です。そこでは、ビジネスパーソンが反面教師として学ぶべきトランプ氏の交渉スタイルの特徴として、以下の5つを挙げています。
1️⃣分配型交渉に偏っている
価値を奪い合うゼロサム型の交渉姿勢が強く、統合型交渉への関心が見られない。
2️⃣ 人間関係構築への無関心
交渉を一時的な勝敗と捉え、長期的な関係づくりを重視しない。
3️⃣感情的な満足を優先する傾向
実質的な成果よりも、自らのプライドや感情の充足を優先する場面が見られる。
4️⃣個人攻撃に傾く
相手の人格や立場を攻撃するスタイルがしばしば見られる。
5️⃣倫理的に問題のある相手との交渉をためらわない
交渉の相手や手段に対して倫理面の配慮が希薄。
これらはすべて「ビジネスの現場では避けるべき交渉スタイル」として紹介されています。
一方で、トランプ氏自身がかつて著書の中で語っている「自らの交渉スタイルのポジティブな側面」も無視すべきではありません。私なりに要点を整理すると、以下のようになります。
1️⃣ 高い目標を掲げる
交渉目標を高く設定することで、最終的な成果が向上するという実証結果もあります。
2️⃣リスクを先に見積もり、戦略的に備える
悲観的な視点でシナリオを想定し、リスクマネジメントを徹底している点は参考になります。
3️⃣ 常に複数のBATNA(代替案)を用意しておく
一つの交渉に依存せず、常に選択肢を複数持つ姿勢は、柔軟性のある戦略を可能にします。
4️⃣ 現場感覚や顧客インサイトを重視する
外部に頼るのではなく、自ら市場を観察・体感し、定性的な感覚を重視するアプローチ。
5️⃣ 影響力や優位性を最大限に活用する
交渉におけるポジショニングや心理的な優位を意識的に設計する点は戦略的とも言えます。
6️⃣言葉や見せ方によって価値を最大化する
不動産の価値を上げるために「どう見せるか」「どう語るか」を重視する姿勢は、ブランディングにも通じます。
7️⃣ 反撃を恐れない
自らの正義や立場を守るためには、訴訟なども辞さないという毅然とした態度を取ることもある。
8️⃣理想だけでなく実行力を重視する
ビジョンを描くだけでなく、それを実現するための行動力が必要であるという信念。
9️⃣ 成果だけでなくコスト管理も徹底する
成果至上主義ではなく、コスト削減によってバランスの取れた成果を目指す姿勢。
🔟 プロセスを楽しむ
結果よりも、交渉というプロセスそのものにやりがいと価値を見出している。
このように、トランプ氏の交渉スタイルには、反面教師となる要素と参考になる要素の両面が存在しています。重要なのは、それぞれの要素を「自分にとってどう活用できるか」という視点で冷静に見極めることだと思います。
実は、今回のこのご質問に驚きました。というのも、ちょうどこの「トランプ流交渉の賛否」をテーマに原稿を書いたばかりだったからです。日本交渉協会のホームページにある「交渉アナリストニュースレター」で公開されています。
ーー一般の方でも登録すれば閲覧可能でしょうか?
窪田:はい、公開されましたので、日本交渉協会のホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
(日本交渉協会交渉アナリストニュースレター トランプの交渉スタイル(1))
ーーわかりました。そちらも楽しみに拝見させていただきます。本日はご多忙の中、貴重なお話を本当にありがとうございました。
「交渉の戦略 孫子の哲学が導く意思決定の技術」に関しては以下より購入可能です。是非ともご購入いただければ幸いです。