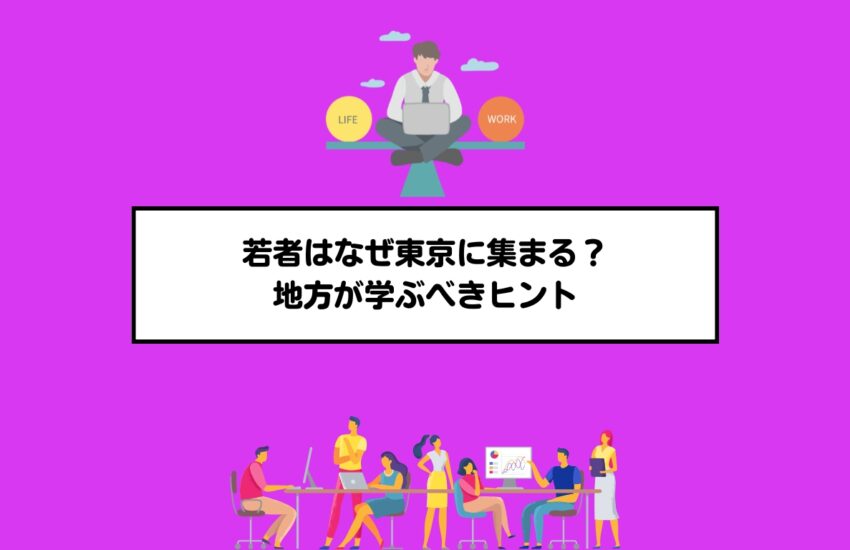「なぜ、若者は地方を選ばないのか。」
この問いの背後には、20年後の日本の姿が隠れています。少子高齢化が進む中にあっても、東京は依然として人口を維持しています。一方で地方では、若者の流出が止まらず、高齢化やインフラの老朽化が進行し、自治体の存続すら危ぶまれる地域が増えています。
都市と地方。この分断を生み出す最大の要因は、「若者の選択」にあります。東京へと向かう若者たちの意思決定を丁寧に読み解くことで、地方がこれからの時代を生き抜くためのヒントが見えてくるはずです。
そのカギとなるのは、経済・生活・文化という三つの要素です。そして、地方に求められるのは「東京の代わり」になることではなく、「地域ならではの価値」を創り出す戦略です。本稿では、若者を惹きつけている福岡や札幌の取り組みを手がかりに、地方が学ぶべき視点と可能性について考察します。
若者が東京に集まる理由(3つの軸)

若者が東京を目指す背景には、単なる憧れだけでなく、明確な経済的・社会的・文化的要因があります。ここでは、その三つの側面から理由をひもといていきます。
経済面:仕事・雇用のチャンスが集中
東京には大企業の本社や最先端のスタートアップが集まり、豊富な就職先とキャリア形成の機会が存在しています。とくに若者にとっては、専門性を活かせる職種や高収入が期待できるポジションが多いことが魅力です。
一方、地方では産業構造の変化や人口減少の影響を受け、就職先が限られている地域も少なくありません。結果として、「地元では将来が描きにくい」と感じる若者が、自然と東京へと流れていく傾向があります。
社会面:生活インフラと利便性の高さ
東京は、交通・医療・教育・娯楽といったあらゆる面で生活の利便性が高く、効率的に暮らせる都市です。電車やバスといった公共交通機関の網羅性や、24時間営業の店舗、最新の医療設備を備えた病院など、生活に必要な要素が身近に揃っています。
これに対し、地方ではインフラやサービスの不足が課題となり、移動手段の乏しさや医療へのアクセスの不便さが、若者の定住意欲を削ぐ要因になっています。
教育・文化面:成長と刺激のある環境
東京には有名大学や専門学校が集中しており、学びの場としても大きな魅力を持っています。また、音楽、ファッション、サブカルチャーなど、常に新しいトレンドが生まれる「文化の発信地」であることも、若者にとって刺激的な環境です。
多くの若者が進学をきっかけに東京へ移り住み、そのまま就職・定住するという流れは、長年にわたり定着しています。これは、学びと働きの双方を一つの都市で完結できるという東京の強みを如実に示しています。
地方が取り組むべき3つの戦略

東京に若者が集まる理由を冷静に見つめ直すと、地方が取りうる対策も浮かび上がってきます。重要なのは「東京に勝つ」ことではなく、「地域ならではの魅力をいかに発揮するか」という視点です。以下、三つの柱で整理してみましょう。
雇用を生む仕組みと都市との接点づくり
地域産業を育成・再編するだけでなく、都市部の仕事を地域に呼び込む仕組みづくりが鍵となります。たとえば、リモートワークの受け皿となるようなコワーキングスペースや、高速通信環境の整備は、地元にいながら都市の仕事に参画できる新しい働き方を可能にします。これは、若者が地元に留まりながらも自己実現できる環境づくりに直結します。
暮らしやすさ向上と住民支援の充実
「日々の暮らし」が充実しているかどうかは、定住の大きな決め手になります。とくに子育て世帯や若年層にとっては、保育所の整備、医療へのアクセス改善、買い物・移動手段の確保といった要素が非常に重要です。地方の強みは、土地や自然といった物理的ゆとりにあります。これらを活かし、安心して暮らせる環境を整えることが、人口流出を防ぐ力となります。
教育・文化の魅力で人を呼び込む
大学や専門学校の誘致が難しい場合でも、地域独自の学びの場や文化活動を創出することは可能です。地元の伝統、自然、産業を活かした教育プログラムや、地域発のアート・音楽・デジタル文化の発信が、若者の「挑戦の場」となり得ます。単に東京を真似るのではなく、地域に根ざした価値観や創造性が問われる時代です。
若者が地域に目を向けるようになるには、「都市の代替」ではなく「地域ならではの選択肢」を用意することが求められます。今こそ、地方が主体的に未来像を描き直すときといえます。
都市の未来をつくる2つの力

地方の未来を考えるうえで重要なのは、「政策」と「生活様式」という二つの視点を併せ持つことです。上からの制度的支援(トップダウン)と、下からの暮らしの選択(ボトムアップ)が両輪となって初めて、持続可能で多様な地域社会が形づくられます。
トップダウン:政策で仕組みを整える
国や自治体が主導する移住支援金、子育て支援策、インバウンド誘致などの政策は、地域の基盤整備に不可欠な役割を果たしています。こうした制度は、人口減少への対応にとどまらず、地域の魅力を高める仕組みとして機能します。
成功事例としては、交通・産業インフラが整備されている福岡市や札幌市が挙げられます。これらの都市では、都市機能と自然環境が共存し、多様なライフスタイルを受け入れる土壌が育まれています。
ボトムアップ:住民の暮らしから変える
一方で、個人のライフスタイルの変化も、地域社会を変える大きな力となっています。コロナ禍を契機に普及したテレワークや二拠点生活は、「どこで働き、どこで暮らすか」を柔軟に選べる新たな潮流を生み出しました。
完全な移住に踏み切ることが難しい人にとっても、「週末は地方で過ごす」「一定期間だけ地域で働く」といった選択肢が広がっており、これが新しい地域との関わり方を生み出しています。
相乗効果が“選ばれる都市”をつくる
政策が環境を整え、個人が自発的に地域を選ぶ――このトップダウンとボトムアップのアプローチが連携することで、地方の未来はより多様で持続可能なものとなっていきます。制度だけでも、個人の意志だけでも限界があるからこそ、この両輪をどう噛み合わせるかが、これからの地域社会の鍵となるでしょう。
福岡・札幌に見る成功のヒント

東京一極集中の中にあっても、地方都市の中で独自の魅力を築き、「若者に選ばれる地域」として存在感を高めているのが、福岡市と札幌市です。これらの都市は、単に人口が多いというだけでなく、都市機能と自然環境のバランス、そして多様なライフスタイルを受け入れる柔軟性を持ち合わせています。
福岡市:アジアとつながるグローバル都市
福岡市は、国内でも特にスタートアップ支援や若者支援に力を入れている都市です。
・交通・アクセス:福岡空港から市中心部まで地下鉄で10分程度という利便性は、国内外問わず高く評価されています。
・スタートアップ支援:官民連携の「スタートアップカフェ」や「グローバル創業・雇用創出特区」といった制度により、若手起業家が集まる土壌を形成しています。
・住みやすさ:家賃や物価が比較的抑えられていること、自然との距離が近く「都市にいながら海や山にアクセスできる」点も魅力です。
このように、経済的な可能性と生活の快適さを同時に満たせる都市として、福岡は若者だけでなく子育て世代からも支持を集めています。
札幌市:都市と自然が共存する暮らし
札幌市もまた、北海道の中心都市として広大な自然と都市機能が調和する「多機能都市」です。
・交通・都市インフラ:碁盤の目のような道路網、発達した地下鉄網により、雪国でありながらも日常の移動に支障が少ない都市設計となっています。
・観光と文化資源:雪まつりをはじめとする地域イベントが都市文化として根づいており、全国・海外からの集客力も高い。
・UIターン施策:北海道外からの移住促進に向けたオンライン相談窓口、企業とのマッチング支援など、実効性の高い支援策が用意されています。
特に注目すべきは、完全移住にこだわらない“季節移住”や“二拠点居住”を歓迎する柔軟なスタンスです。自然と都市生活の両立を望む人々にとって、札幌は現実的な選択肢となっています。
選ばれる都市の条件|コンパクトシティ+生活満足度がカギ
福岡や札幌に共通するのは、「大都市であると同時に、人が暮らしやすいサイズ感」「起業や転職といった人生の選択肢が用意されていること」「文化や自然に触れられる生活環境が整っていること」です。
つまり、ただ人口を呼び込むのではなく、“生活の総合的な満足度”をいかに高めるかが地方都市にとっての本質的課題であるということを、これらの成功例は示しています。
未来を選ぶのは誰か?

東京一極集中という構造は、今後20年を見通しても大きく変わらない可能性があります。しかし、それは地方に未来がないことを意味するわけではありません。むしろ、「なぜ若者が東京を選ぶのか」という問いの先に、地方が選ばれるためのヒントがあるのです。
地域が生き残り、発展していくためには、若者にとっての“選ばれる理由”をいかに築けるかが鍵となります。
・自治体や中小企業にとっては、「魅力ある地域とは何か」「どうすればそこに人が集まるのか」を問い続け、具体的な行動に落とし込む姿勢が問われます。
・生活者にとっては、「どこで暮らすのか」「どんな働き方を選ぶのか」といった、自身の生き方に関わる選択が、これまで以上に重要になっていくでしょう。
未来の日本は、こうした一人ひとりの選択と、地域の取り組みが交差する場所に生まれてきます。
地方創生に関するおすすめ記事
消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事
地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析
- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣
- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)
- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介
- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例
- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵
- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール
- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル
- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力
- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓
- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント
- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実
- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略