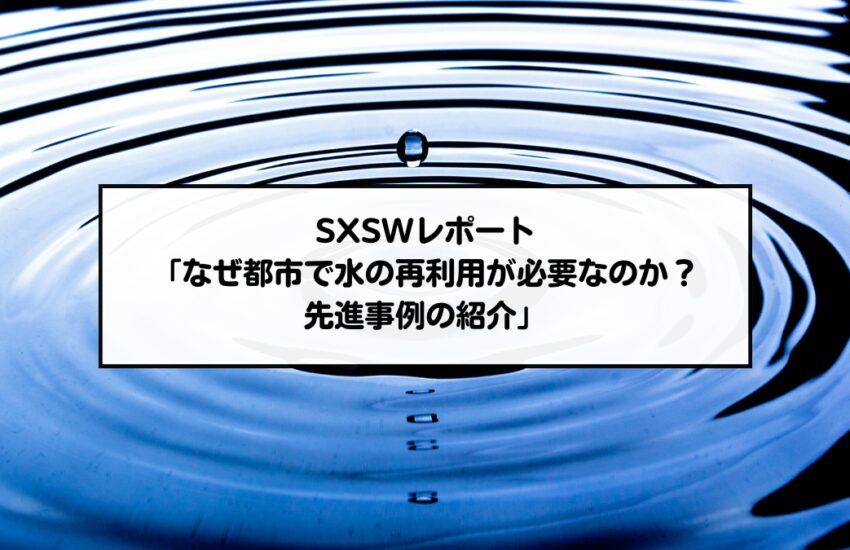本セッションは、 2025年3月12日 11:30am ~ Hilton Austin Downtown Favorite Salon Aで開催。Lawrence Berkeley National LaboratoryのNewsha Ajami氏、Corgan Samantha Flores氏、Austin Water Katherine Jashinski氏、Epic Cleantec Aaron Tartakovsky氏が登壇。
アーロン・タルディコフスキー氏(Aaron Tardikovsky):モデレーター。Epic Clean Techという会社に所属、不動産物件向けに再生水利用システムを導入しています。
キャサリン氏(Catherine):オースティン市水道局(Austin Water)から参加。地域における水政策の第一人者です。
ナッチャ・アジャミ氏(Newsha Ajami):バークレー国立研究所の開発責任者。サステナビリティと水政策の融合に取り組む研究者で、米国の官民連携を推進するリーダーでもあります。
サマンサ・フローレス氏(Samantha Flores):大手建築設計事務所 Gensler(ジェンスラー)の副社長で、フューチャリストチームのディレクター。建築と水利用の革新をつなぐ視点を持っています。
なぜ都市で水の再利用が必要なのか?

サンフランシスコ市は、全米で初めて「すべての新築大型ビルにオンサイトの再利用水システムを義務化した都市」です。
ここで重要な問いが投げかけられました:
「なぜ私たちは、公園の灌漑やオフィスのトイレ洗浄に“飲めるほど綺麗な水”を使っているのか?」
この疑問から、政策・業界・技術者たちが連携し、飲料水の無駄な使用を減らすための都市レベルの仕組みが始まりました。
Epic Clean Techは、民間と連携して安全な再生水活用を可能にする技術を導入しており、サンフランシスコでは「オンサイト再利用」のための10ステップのチェックリストを作成。これは他都市のモデルにもなりました。
オースティン市の挑戦と導入事例
キャサリン氏は、オースティンが新たにこのモデルを取り入れ、一定規模以上の建物に雨水・排水の再利用を義務づける政策を導入したことを紹介。
「新たに建設される中高層ビルは、敷地内で雨水やグレーウォーター(生活排水)を回収し、再利用するシステムを備える必要があります。」
これにより、対象の建物は水道水の50〜75%を削減できる見込みであり、都市全体での水資源圧迫を緩和する大きな効果が期待されています。
なぜ“水の見えない存在”が課題なのか?
アジャミ氏はこう指摘します。
「私たちは水の存在を“感じにくい”ように設計された都市に住んでいます。だからこそ、人々は水のありがたみを感じづらく、それが投資や政策の遅れにもつながっているのです。」
また、再利用水のシステムは一般に認知されにくく、地中にあるインフラは見えないため、日常の中での理解や関心が不足しがちだとも述べました。
サンフランシスコの取り組み:水再利用政策の全国モデルへ
Epic Clean Techのアーロン氏はこう説明します:
「現在、サンフランシスコでは約30棟のビルでオンサイト再利用水システムが稼働しており、さらに40棟が建設中または計画中です。これは、市内の上水供給のうち10%程度を再利用水でまかなえるポテンシャルがあることを意味します。」
さらに、「都市の政策が“実験の場”として機能することが重要だ」と語り、こう続けました:
「技術革新は政策の支援があって初めてスケールします。単に素晴らしい技術があっても、導入する義務やインセンティブがなければ企業も投資をためらう。サンフランシスコでは、それを打破する“仕組み”を作ったんです。」
なぜ建築・開発の現場とつながるのか?
サマンサ・フローレス氏(Gensler)によると、設計現場ではいまだに「水は当たり前に供給されるもの」という前提が根強く残っているといいます。
「私たちは何十年もの間、水を“無限に使える資源”として扱ってきました。でも、今はそうではありません。再利用やリサイクルを前提とした建築設計が必要なのです。」
Genslerでは現在、建物内で排水を循環利用する“ブルーループ”設計や、庭園・中水利用システムなどを組み込んだ「レジリエンス設計」を推進しています。
また、実際の建築開発では「初期コストを誰が負担するのか」が最大の障壁になっていると指摘します。
「建物の設計者や住む人たちは、この取り組みの恩恵を受けるけれど、最初にお金を出すのは開発業者。その構造を変えていかなければ、大きな普及は難しい。」
コストと政策の両輪で実現する都市スケールの再利用
オースティン市のキャサリン氏は、市のプログラムにおける「段階的アプローチ」について説明します。
「まずは任意で参加できるプログラムを導入し、その後、条例を整備して義務化に移行しました。義務化後、事業者は本気で向き合いはじめ、具体的な質問や対応が生まれました。」
加えて、市は建物所有者への経済的負担を軽減するために、次の3つの支援策を導入しています:
(1)コスト低減のための戦略(市側が一部コストを負担)
(2)資金調達の仕組み(競争型補助金制度)
(3)迅速な建築許可手続き(特定条件を満たす案件は優先的に審査)
「たとえば、市が所有する再利用水の配管に接続するプロジェクトであれば、接続手数料の一部を市が負担します。その分、プロジェクト全体のコストが抑えられます。」
このような制度設計により、サステナブルな設計を“現実のプロジェクト”として成立させているのです。
水とエネルギー:再分散型システムに共通する学び
最後に、アーロン氏はエネルギー業界との共通点を指摘します:
「ソーラーや風力のような分散型エネルギーの普及と同じように、水も“大規模集中型”から“分散型・建物スケール”へのシフトが起きつつあります。」
エネルギーの再分散化が15年かけて達成されたように、水の分散利用もまた、政策・技術・設計・教育のすべてが連携することで、ようやく社会実装へと進んでいくのだと語られました。
革新的水インフラを広げるうえでの課題
アーロン氏:
「コストの話は非常に重要です。水分野でのイノベーションは難しい。農業テックの会社が市場に受け入れられるまでに15年かかるという話もある。多くの企業がその途中で潰れてしまう。」
「再生可能エネルギー、特に太陽光や風力の分散型システムと比べても、水は浸透が遅い。その背景には、物理的なインフラのハードル、制度設計の複雑さがある。」
「私たちは、エネルギー業界の進化から多くを学べる。小規模分散型の成功は、水分野にも応用可能です。」
建築業界における“デザイン”の再定義
サマンサ氏(Gensler):
「設計とは、建物の見た目を整えるだけではありません。“水がどのように流れ、使われ、再利用されるか”までを含めた“循環のデザイン”が必要です。」
「私たちは建築家として、不動産開発業者や設計者に『レジリエントで、持続可能な未来を前提とした建物のあり方』を教育する責任があります。」
「実際のところ、建物を使う人(入居者)は、こうした設計の恩恵を受ける立場です。しかし、最初に費用を払うのは開発業者。そのため『これは必要ない』と初期コストで拒否されてしまうことが多い。これが普及を阻む最大の壁です。」
解決のカギは「インセンティブ設計」
サンフランシスコ市の取り組みに話が戻り、次のような制度設計が紹介されました:
(1)段階的な制度導入(最初は任意、後に義務化)
(2)プロジェクトに対する補助金制度
(3)許認可プロセスの簡素化と優先審査
「義務化された後、人々はようやく本気で向き合い始めました。“これはやらなきゃいけない”と分かってから、質問が増え、関心が高まり、実装が進んだのです。」
市民の意識改革とデータの活用
パネリストたちは、住民の「水に対する見えない依存」への意識改革の必要性を強調します。
「私たちは毎日水を使っているのに、その出どころや仕組み、インフラの存在を全く意識していません。」
これに対し、自治体や企業が協力して、水の“見える化”と教育的アプローチを進めるべきだという意見が交わされました。
最後に:ポッドキャストやデジタルメディアと同じく「リーチの戦略」が必要
アーロン氏:
「情報発信の文脈でも、水の分野は遅れている。YouTubeやTikTokのように、人々が情報に触れやすい場で『水の話』を届けていく必要がある。教育や文化として根付かせなければならない。」
「今やZ世代は動画で情報を得る。例えば、私は『Call Her Daddy(人気ポッドキャスト)』を聴いたことはないけど、TikTokでそのコンテンツの一部を見たことで番組を知りました。」
同様に、水に関する取り組みも、柔軟なメディア戦略とマルチチャネル展開で「見える存在」になることが重要だと語られました。
最終メッセージ:これは長期戦。だが、未来は変えられる
最後にパネリスト全員が強調したのは、「水の未来は、短期的なROI(投資回収)で測るべきではない」ということでした。
都市全体が恩恵を受けるインフラは、市民の安全と繁栄に直結している。
政策・テクノロジー・設計・市民の理解の4つが揃って初めて、持続可能な水循環の社会が実現する。
そして、未来の都市や建物は「水をただ消費する場所」ではなく、「水を再生・循環させるシステム」として設計されるべきだと、強く訴えかけてセッションは締めくくられました。
※本記事は、本メディアの記者がSXSW2025のセッション「Cities and Buildings Leading the Water Reuse Revolution(水再利用の革命を牽引する都市と建物たち)」に参加し、内容をまとめたものです。公式の発表とは異なる点がある場合がありますので、ご了承ください。
関連記事: