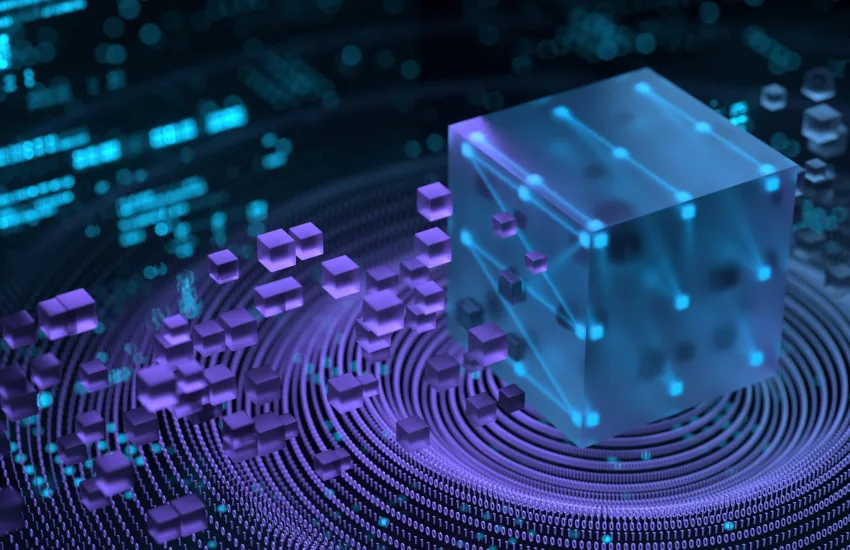ブロックチェーンを理解する上で、重要なのがLayer(レイヤー)と呼ばれる概念です。特にLayer1とLayer2の違いや変化を正しく把握しておけば、仮想通貨やNFT、メタバースなど関連技術の可能性をより深く理解することができます。
この記事では、今知っておきたいLayer1とLayer2の違い、そしてこれからの動向について解説します。
Layer1とは
Layer1は、全てのブロックチェーン関連のサービスにおける軸としての役割を果たす、ベースレイヤーを指します。端的に言えば、Layer1はブロックチェーン技術そのものであると言えるでしょう。
Layerの概念は、全部で5種類存在しますが、それぞれのLayerごとにサービスが存在するというよりも、複数のLayerが必要に応じて重なりながらサービスを支えていると考える方がわかりやすいでしょう。Layer1は、間違いなく全てのブロックチェーン関連サービスの基礎となる存在であり、必要に応じて別のLayerが増えたり減ったりします。
Layer1の成果と課題
Layer1は、ブロックチェーンを使ったあらゆるサービスの登場を後押ししたことから、世界にもたらした衝撃はかつてないものでした。ユーザーごとに分散管理されているノードを、従来のような中央集権的なクライアントサーバーではなく、ユーザー間というP2P取引で実現することを可能にしたからです。
ただ、ブロックチェーンを使ったLayer1単体のサービスのあり方には、問題もあります。広く認知されている問題の一つに、スケーラビリティの問題が挙げられます。
スケーラビリティの問題とは、取引に参与するユーザーの数が増えれば増えるほど、その手続き負担が大きくなってしまう問題です。ブロックチェーンは安全な送金手続きを実現する技術として知られていますが、これは仮想通貨マイナーの処理能力に依存しているのが現状です。マイナーのキャパシティを上回るトランザクションが発生すると、期待しているような適正な取引が行われなくなるケースが見られます。
サービスに関わる人が増え、トランザクションの数が増えていくと、金銭的な条件が良い取引にのみ処理が集中するので、取引を行うためにかかる手数料は高騰します。わずかな手数料と高速な入金処理で、自由な金銭取引ができると期待して導入した仮想通貨取引が、結果的に現金取引よりも高価な手数料と処理遅延をもたらす可能性があるというわけです。
もう一つ押さえておきたいのが、Layer1の抱えるトリレンマの問題です。正常なブロックチェーンシステムは、セキュリティと分散化、そして前述したスケーラビリティという、3つの特質を有している必要があるとされています。しかし、実際にはこれら3つの特質のうち、実際に担保できるのは2つだけであり、そのうちの1つは犠牲になってしまうとされているのです。
そのため、Layer1のブロックチェーン技術のみを使ってサービスを開発する場合、常に妥協やトレードオフをあらかじめ踏まえておき、そのサービスの弱点をはじめから覚悟しなければならないのが問題とされています。
例えばブロックチェーンの分散化を進めるため、ノードを大量に用意する場合、安全性を維持できるようノードの信頼性を高め、取引の手数料を高額にせざるを得ません。ノードごとのコストを抑えて運用することもできますが、そうすると分散化とスケーラビリティは確保できるものの、セキュリティ面での不安が残ることとなります。
このように、Layer1ではあっちを立てればこっちが沈む、こっちを立てればあっちが沈むといった、パラメータのバランスをうまく調節しながら運用しなければなりません。
Layer2とは
このようなスケーラビリティの問題や、さらに向こう側にあるトリレンマの問題を解消すべく誕生したのが、Layer2と呼ばれる概念です。Layer2とは、ブロックチェーンに関与しない、オフチェーンでトランザクションを実行するための仕組みを指します。
Layer1単体の場合、ブロックチェーン取引に関わる全ての処理をブロックチェーン上で実行する必要があります。しかしLayer2では、一度Layer1とは関係のないところで計算処理を実行し、取引が実際に発生する段階でブロックチェーンに関与させ、取引結果をブロックチェーン上に記録します。
Layer1にかかる負荷をLayer2で分散し、トランザクションに必要なリソースを削減し、少ないコストでの取引を実現することができるという仕組みです。
日々の光熱費の支払いやちょっとした買い物で仮想通貨を使用する場合、必然的に取引回数は増加します。そこで、Layer2を噛ませた仮想通貨を利用することで、ブロックチェーンを日常的に利用できる可能性に注目が集まっています。
Layer3以降のプロトコルについて
今回はLayer1とLayer2に絞って解説をしますが、実際にはLayer3以降のプロトコルも存在します。
Layer3
Layer3は発行流通プロトコルと呼ばれ、その名の通り取引のプロセス管理などに用いられるのが特徴です。Layer3を活用することで、複雑なNFTの発行や売買も、高度な技術を持っていない人が簡単に携われるようになります。
Layer4
Layer4は金融化プロトコルと呼ばれる、独自にトークンを発行することができるプロトコルです。例えばNFTに裏付けられたトークンを発行し、独自にトークンを使った取引が行えるようになるなどの機能を実現できます。
仮想通貨やNFTの流動性を高め、より活発な取引を促す上で重要な役割を果たすと期待されるプロトコルです。
Layer5
Layer5は、アグリゲータープロトコルと呼ばれる技術です。これまで紹介したレイヤーごとに、情報処理が細かく行われるわけですが、Layer5でこれらの分散した情報を集約し、管理することができます。
NFTをトークン化して現在の取引状況が複雑になりすぎた場合も、アグリゲータープロトコルを実装すれば、一目で状況を把握可能です。
Layer2の種類
話を戻しますが、Layer2は実のところ複数の種類に分かれています。ここではLayer2の主な種類について、代表的なものを紹介します。
ライトニングネットワーク
ライトニングネットワークは、比較的ポピュラーなLayer2の一種です。Layer1で実行されるブロックチェーン外にペイメントチャネルを設け、そこであらかじめ決められた通貨量の取引を実行します。
ライトニングネットワークは二者間での取引が基本ですが、ノードを数珠繋ぎにして複数経由させれば、三者以上が関与する取引も可能です。ライトニングネットワークは、ビットコインの取引にも使われています。
ライデンネットワーク
ライデンネットワークは、仮想通貨のイーサリアムの取引において採用されているLayer2の一種です。基本的な仕組みはライトニングネットワークと同じで、ブロックチェーン外にペイメントチャネルを設置し、取引に関与するユーザー同士の同意があって初めて、通貨取引が実現します。
Layer1への負荷を最小限に抑え、高速かつ低コストの取引が可能なプロトコルです。
Plasma
Plasmaはライデンネットワークとは別に存在している、イーサリアム上で稼働するLayer2の一種です。ライトニングネットワークやライデンネットワークとは異なり、Plasmaはオンチェーンで取引を実行するのが特徴です。Layer1を親チェーンと考え、Plasmaを通じてLayer1常に子チェーン、孫チェーンを形成し、ブロックチェーンそのものの階層化で負荷の削減を試みます。
イーサリアムが高く評価されている理由として、スマートコントラクトと呼ばれる取引形態を実現していることが挙げられます。スマートコントラクトとは、あらかじめ設定しておいたルールに則り、自動で取引を実行できる仕組みを指しますが、Plasmaを使えば副次的に生成したブロックチェーン全てにスマートコントラクトを実装できます。
Plasmaが実装されたことで、金融取引におけるイーサリアムの価値は短期間で高騰し、一躍ビットコインに並ぶ仮想通貨として評価されるようになったのです。
Layer2の課題
Layer2はLayer1単体のブロックチェーン技術に比べ、飛躍的に利便性を高めることに成功しました。ただ、Layer2には課題も残るため、完全な技術であると評価するには時期尚早と言えます。
Layer2が抱えている問題として、オフチェーン型の場合の取引では不正の可能性が残されている点が挙げられます。オフチェーンのライトニングネットワークやライデンネットワークの取引は、ブロックチェーンから離れたところで計算処理が行われるので、戻された結果が必ずしも正しいとは限りません。
ペイメントチャネルの脆弱性も報告されており、サイバー攻撃を受けた場合、取引が消滅してしまう恐れもあることに注意が必要です。
また、オンチェーン型のPlasmaのようなプロトコルも、課題が残ります。オンチェーンのLayer2はその取引の様子を管理することができないため、暗号資産がサイバー攻撃を受ける可能性を常に抱えています。
ブロックチェーンを全てダウンロードして管理することもできますが、これには多くの負担がかかるため、ブロックチェーン本来の利便性が損なわれてしまうでしょう。
Layer2の今後
この記事では、Layer1が抱える課題をカバーする、Layer2の特徴や種類について解説しました。Layer2の実装により、イーサリアムのような仮想通貨はその価値を高め、NFTの取引の活性化などに貢献しています。
ただ、Layer2にも依然として課題は存在し、サイバー攻撃の脅威などは残り続けています。現在もLayer1やLayer2をはじめとしたプロトコルは改良が続いており、利便性や安全性の向上が見られることから、今よりも低リスクの運用にも期待が集まるところです。